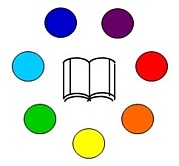今回の読書会は「明日からまた一週間はじまるな」という日曜日の夜に行われましたね、めずらしい。課題本は栗原康著の『サボる哲学』ということで、いかにサボりながら本を読むかという課題にもチャレンジしていたところ、不覚にもパソコンに繋げたマイクの調子が悪くテキストチャットのみでの読書会参加となってしまい、皆さんの発言要旨をメモることができました。やちゃえ、きたろう。
以下、読書会で出た話題。
・サクサク読みやすかった。働きたくない→人間がモノ扱いされてることにたいする抵抗、ひとりでに身体が動くということが生きているということ。人新世の資本論とカブるようなところがあった。
・クダけた口調にびっくり。エッセイ調で気軽だった。資本主義体制下での被圧制を我がこととして振り返ると、働かずして(家事だけして)家にいることに苦しみを感じていたが、それでも自分の価値が損なわれることはないということが分かってきて、ようやく資本主義を外部から眺めることができるようになった。これからもしばらく逃げていこう。
・口語体の書き方で読みやすかった。章立ても区切りが細かくてよみやすかった。海賊の話とかラッダイトの話がおもしろかった。大杉栄の話がたくさんでてきて、こんな人がいたんだということが知れてよかった。
・ヒャッハー体の文章がなぜか懐かしく、自分の大学生の時の会話を思い出した、何かの原点があってそれのパロディで話す感じ。「いきなりステーキ」の話が面白かった。「雇用のジャストインタイム」という話題、言いえて妙。トヨタ形式は下請けにムリさせる、それを雇用にやらせているのがハケン労働の本質、自分が目にしたハケン労働者も、それを生み出した雇用環境ひっくるめて腹が立った。
・正直、自分には合わない本でした。言うこともあまりない。全体的に。読むのが苦痛であった。
・著者に対して反感を抱いてしまうところも確かにあった。8年くらいプーやってて就活して…働き盛りの人間を養ってくれる家族がいるような人が、「逃げろ」「打ちこわし」っていわれても、お前が言うなと思ってしまう。
・この著者は頭でっかちのお坊ちゃんだと思うけど、そのような立場じゃないと言えないことだと思う。大逆事件の当事者たちはどうやってやっていたのだろう。シンパがいた?
・面白い話だったけど、海賊の話には共感できなかった。
・ワンピースがあったから、海賊の話はすんなり入っていけた。
・裕福で余裕がある人じゃないと社会活動はできない…最下層の人たちはそういうことを考えられない、活動家の扇動に乗るだけ。
・労働組合運動でギリギリの生活をしている人がオルグして賛同してストライキをして…かつての労働活動はホントによくやったんだと感心する。そのうえに今の労働環境がある。人権意識の伝播、経済成長があったから→そのバックラッシュで、労働者側がおしかえされている。
土地の私有っておかしいよねって昔腑に落ちないとおもっていたことを思い出した。
・土地は国有がいい?
・単に貧困層向けの住宅政策がないことが目立っているだけ?空き家、「負」動産の話も思い出した。
・建設的な話じゃなかったのが受け付けなかった
・今30代で、今から本書にあるように意識の転換はできないのでモヤっとするが、今後100年後くらいに転換できるように少しずつソフトしていくことを考えながら読んだ。転換期。
・資本主義にかわるドラスティックなものが即座に思いつくわけではないけど、何らかのブレインストーミングが必要かとおもった。少しずつスモールステップで。
・資本主義に問題があるのは分かるが、今ある資本主義を変えていく方向はないのか。この本のおかげで資本主義のことを考えるきっかけになった。エシカル投資などすれば資本主義のダメさが減るのではないか。
・個人株主を増やしている某企業は良いと思います。経済系の雑誌で反資本主義系の書評が取り上げられるのは、そうしないと海外からの投資を呼び込めないからでもある。外国人実習生のこともしかり。
・ショックだったこと―「くたばれオリンピック」あんなに感動もらったのに。
・やるべきでなかったと私は思う。オリンピックもカネの論理。選手がかわいそうというのも分かるけど。
これだけ反対派が多いなか、アスリートに批判を向けた者のことが分からない。怒るならバッハに怒れ。
・著者の言い方が悪いよね。おカネの面だけじゃなく、やらなきゃいけない理由はあったと思う。
・著者の文体は大槻ケンジにそっくりだと思った。
・町田康にも通ずるものがあった。
・最近は、輸送の移動しかしていない
・自分の読書は、徒歩旅行をしていると思っている。生活のなかで、無目的にやることがあると楽しいよね
・何もいない空き家に占有している人がワルい人だったら、いい気がしない。著者はどう思うのか。ワルも受け止めるのか。自分の身が脅かされることを思うと、排除するのも当然分かる。
・本気でアナキズムやろうとすると、暴力にうったえることになるかもしれないと思った。
・アナキズムと聞くとコワい感じがするが、中身を見ると相互扶助とか、そうでもなさそう。
・「やっちゃえ」という言葉の多様がコワかった。
・「自発的に」−ソクインのジョウ?井戸に落ちそうな子供を思わず助けてしまうヤツ、と通じているのかもと思った。
・労働組合の話。搾取と戦うための運動が、一枚岩になると新たな搾取構造になってしまうことについて、あるある感。
・一枚岩になることは大事だけど、一人ひとりが思うことは違うわけで、それは対立してしまうこともあるんだなぁ。
・支配がなくなってもう一度団結するときに、「ルール」はだれが決める?
・新たな権力関係が生まれないように、ボランティア的な動き方はどうか。
・闘いの舞台に乗らずに異質のものを持ち込むこと―センゲンミチコ、アメノウズメ、海賊。
・著者の思考、いい意味でコドモっぽい。いい意味で純粋、アナキズムと繋がっている。
・著者も國分功一郎 も、ルックスがよい。
会のなかで紹介した『ヒューマンカインド』(ルトガー・ブレグマン著、文藝春秋)では、性悪説的でホッブズ的人間理解と性善説的でルソー的人間理解の対を対立させて、世の中一般的には前者こそがありのままの真実であると信じられているけど、本当は後者が人間の真の姿ではないのか、ということを、いろんなエピソードを交えて説いていきます。本書『サボる哲学』に登場する「アナキスト」像は、このルソー的な「自然人」像と相当程度カブってみえます。本書がスケッチする無支配生活の「眉唾さ」はそもそもの「自然人」概念のフィクション性に直接は由来していると思います。このあたりのことは幾万もの研究の蓄積があるので、気になった方は各自あたればいいと思います。
以下、読書会で出た話題。
・サクサク読みやすかった。働きたくない→人間がモノ扱いされてることにたいする抵抗、ひとりでに身体が動くということが生きているということ。人新世の資本論とカブるようなところがあった。
・クダけた口調にびっくり。エッセイ調で気軽だった。資本主義体制下での被圧制を我がこととして振り返ると、働かずして(家事だけして)家にいることに苦しみを感じていたが、それでも自分の価値が損なわれることはないということが分かってきて、ようやく資本主義を外部から眺めることができるようになった。これからもしばらく逃げていこう。
・口語体の書き方で読みやすかった。章立ても区切りが細かくてよみやすかった。海賊の話とかラッダイトの話がおもしろかった。大杉栄の話がたくさんでてきて、こんな人がいたんだということが知れてよかった。
・ヒャッハー体の文章がなぜか懐かしく、自分の大学生の時の会話を思い出した、何かの原点があってそれのパロディで話す感じ。「いきなりステーキ」の話が面白かった。「雇用のジャストインタイム」という話題、言いえて妙。トヨタ形式は下請けにムリさせる、それを雇用にやらせているのがハケン労働の本質、自分が目にしたハケン労働者も、それを生み出した雇用環境ひっくるめて腹が立った。
・正直、自分には合わない本でした。言うこともあまりない。全体的に。読むのが苦痛であった。
・著者に対して反感を抱いてしまうところも確かにあった。8年くらいプーやってて就活して…働き盛りの人間を養ってくれる家族がいるような人が、「逃げろ」「打ちこわし」っていわれても、お前が言うなと思ってしまう。
・この著者は頭でっかちのお坊ちゃんだと思うけど、そのような立場じゃないと言えないことだと思う。大逆事件の当事者たちはどうやってやっていたのだろう。シンパがいた?
・面白い話だったけど、海賊の話には共感できなかった。
・ワンピースがあったから、海賊の話はすんなり入っていけた。
・裕福で余裕がある人じゃないと社会活動はできない…最下層の人たちはそういうことを考えられない、活動家の扇動に乗るだけ。
・労働組合運動でギリギリの生活をしている人がオルグして賛同してストライキをして…かつての労働活動はホントによくやったんだと感心する。そのうえに今の労働環境がある。人権意識の伝播、経済成長があったから→そのバックラッシュで、労働者側がおしかえされている。
土地の私有っておかしいよねって昔腑に落ちないとおもっていたことを思い出した。
・土地は国有がいい?
・単に貧困層向けの住宅政策がないことが目立っているだけ?空き家、「負」動産の話も思い出した。
・建設的な話じゃなかったのが受け付けなかった
・今30代で、今から本書にあるように意識の転換はできないのでモヤっとするが、今後100年後くらいに転換できるように少しずつソフトしていくことを考えながら読んだ。転換期。
・資本主義にかわるドラスティックなものが即座に思いつくわけではないけど、何らかのブレインストーミングが必要かとおもった。少しずつスモールステップで。
・資本主義に問題があるのは分かるが、今ある資本主義を変えていく方向はないのか。この本のおかげで資本主義のことを考えるきっかけになった。エシカル投資などすれば資本主義のダメさが減るのではないか。
・個人株主を増やしている某企業は良いと思います。経済系の雑誌で反資本主義系の書評が取り上げられるのは、そうしないと海外からの投資を呼び込めないからでもある。外国人実習生のこともしかり。
・ショックだったこと―「くたばれオリンピック」あんなに感動もらったのに。
・やるべきでなかったと私は思う。オリンピックもカネの論理。選手がかわいそうというのも分かるけど。
これだけ反対派が多いなか、アスリートに批判を向けた者のことが分からない。怒るならバッハに怒れ。
・著者の言い方が悪いよね。おカネの面だけじゃなく、やらなきゃいけない理由はあったと思う。
・著者の文体は大槻ケンジにそっくりだと思った。
・町田康にも通ずるものがあった。
・最近は、輸送の移動しかしていない
・自分の読書は、徒歩旅行をしていると思っている。生活のなかで、無目的にやることがあると楽しいよね
・何もいない空き家に占有している人がワルい人だったら、いい気がしない。著者はどう思うのか。ワルも受け止めるのか。自分の身が脅かされることを思うと、排除するのも当然分かる。
・本気でアナキズムやろうとすると、暴力にうったえることになるかもしれないと思った。
・アナキズムと聞くとコワい感じがするが、中身を見ると相互扶助とか、そうでもなさそう。
・「やっちゃえ」という言葉の多様がコワかった。
・「自発的に」−ソクインのジョウ?井戸に落ちそうな子供を思わず助けてしまうヤツ、と通じているのかもと思った。
・労働組合の話。搾取と戦うための運動が、一枚岩になると新たな搾取構造になってしまうことについて、あるある感。
・一枚岩になることは大事だけど、一人ひとりが思うことは違うわけで、それは対立してしまうこともあるんだなぁ。
・支配がなくなってもう一度団結するときに、「ルール」はだれが決める?
・新たな権力関係が生まれないように、ボランティア的な動き方はどうか。
・闘いの舞台に乗らずに異質のものを持ち込むこと―センゲンミチコ、アメノウズメ、海賊。
・著者の思考、いい意味でコドモっぽい。いい意味で純粋、アナキズムと繋がっている。
・著者も國分功一郎 も、ルックスがよい。
会のなかで紹介した『ヒューマンカインド』(ルトガー・ブレグマン著、文藝春秋)では、性悪説的でホッブズ的人間理解と性善説的でルソー的人間理解の対を対立させて、世の中一般的には前者こそがありのままの真実であると信じられているけど、本当は後者が人間の真の姿ではないのか、ということを、いろんなエピソードを交えて説いていきます。本書『サボる哲学』に登場する「アナキスト」像は、このルソー的な「自然人」像と相当程度カブってみえます。本書がスケッチする無支配生活の「眉唾さ」はそもそもの「自然人」概念のフィクション性に直接は由来していると思います。このあたりのことは幾万もの研究の蓄積があるので、気になった方は各自あたればいいと思います。
|
|
|
|
|
|
|
|