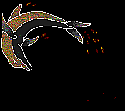平安時代中期に編纂の『延喜式神名帳』に記載されている神社を「式内社」という。
式内社であるだけですでに創建千年以上となり、由緒ある古社と呼ぶにふさわしいことになる。
その一方、もうすでに現存しないか特定ができない場合もある。
さらに「式内論社」というのがあって、こいつは少々やっかいだ。
長い歴史の中では、一旦途絶えても後の時代に復興したり、訳あって遷座をくり返す中で同じ神社が複数残ってしまうことがある。
こちらが正統だと名乗り合い、複数が比定される場合を論社という...
美濃国厚見郡(現在の岐阜市)の式内社は、
比奈守神社
茜部神社
物部神社
の三座である。
ここで不思議に感じる方もいらっしゃると思います。
岐阜の古社といえば伊奈波神社であるはずが、金神社もなければ橿森神社もない。
私も最初は不思議でした。
このうち、社名を同じくする比奈守神社と茜部神社は現存しており、物部神社は残念ながら伊奈波神社に合祀されてしまいました。
確実なのは、当時大和朝廷の荘園にあった茜部神社のみ。
比奈守神社は論社として、厚見郡の手力雄神社とする説も有力です。
この手力雄神社の祭神である天手力男神は、宮中にあった祭神を伊勢神宮から分祀したことによるとされています。
ここで気になるのは、直線距離にして北東に約1.5kmしか離れていない各務郡の手力雄神社。
こちらはもともと磐座を祀った真幣明神で、後に戸隠神社の天手力男神を勧請して各務氏の氏神となった。
比奈は飛騨であり夷のことで、茜部に荘園を持つ大和朝廷の前線基地という意味が隠されています。
どちらも当時の木曽川である境川に面しており、飛騨というより尾張から入る夷に備えたと推測されます...
▼二つの手力雄神社
http://
...
式内社であるだけですでに創建千年以上となり、由緒ある古社と呼ぶにふさわしいことになる。
その一方、もうすでに現存しないか特定ができない場合もある。
さらに「式内論社」というのがあって、こいつは少々やっかいだ。
長い歴史の中では、一旦途絶えても後の時代に復興したり、訳あって遷座をくり返す中で同じ神社が複数残ってしまうことがある。
こちらが正統だと名乗り合い、複数が比定される場合を論社という...
美濃国厚見郡(現在の岐阜市)の式内社は、
比奈守神社
茜部神社
物部神社
の三座である。
ここで不思議に感じる方もいらっしゃると思います。
岐阜の古社といえば伊奈波神社であるはずが、金神社もなければ橿森神社もない。
私も最初は不思議でした。
このうち、社名を同じくする比奈守神社と茜部神社は現存しており、物部神社は残念ながら伊奈波神社に合祀されてしまいました。
確実なのは、当時大和朝廷の荘園にあった茜部神社のみ。
比奈守神社は論社として、厚見郡の手力雄神社とする説も有力です。
この手力雄神社の祭神である天手力男神は、宮中にあった祭神を伊勢神宮から分祀したことによるとされています。
ここで気になるのは、直線距離にして北東に約1.5kmしか離れていない各務郡の手力雄神社。
こちらはもともと磐座を祀った真幣明神で、後に戸隠神社の天手力男神を勧請して各務氏の氏神となった。
比奈は飛騨であり夷のことで、茜部に荘園を持つ大和朝廷の前線基地という意味が隠されています。
どちらも当時の木曽川である境川に面しており、飛騨というより尾張から入る夷に備えたと推測されます...
▼二つの手力雄神社
http://
...
|
|
|
|
コメント(9)
>トピ主さん
式内社設置には間違いなく何らかの政治的意図があったと思います。
設置の主体となって住み着いた部族は、その神社を当然崇敬します。
他方、式内社以前の部族も滅ぼされるか完全服従(奴隷化)しない以上氏神社を崇敬します。ですから、両神社の主要な氏子の特性を研究すればいいのです。
大雑把にいうと、航海系、古山系、新山系の三分類が効果的かもしれません。 ある時期の神社から一神社に山系の姓と海系の姓の氏子があり、当該地域において前者が支配的立場にあるような雰囲気があります。伽耶と日本の「海の民山の民」の二重構造性を念頭に置くと理解しやすくなります。ですから、山系あるいは海系の姓だけの神社はかなり古いと思われるのです。
式内社設置には間違いなく何らかの政治的意図があったと思います。
設置の主体となって住み着いた部族は、その神社を当然崇敬します。
他方、式内社以前の部族も滅ぼされるか完全服従(奴隷化)しない以上氏神社を崇敬します。ですから、両神社の主要な氏子の特性を研究すればいいのです。
大雑把にいうと、航海系、古山系、新山系の三分類が効果的かもしれません。 ある時期の神社から一神社に山系の姓と海系の姓の氏子があり、当該地域において前者が支配的立場にあるような雰囲気があります。伽耶と日本の「海の民山の民」の二重構造性を念頭に置くと理解しやすくなります。ですから、山系あるいは海系の姓だけの神社はかなり古いと思われるのです。
>比奈守神社
まだ検証不足ですが、
祭神が応神天皇と同母の神巧皇后というのは少々疑問も感じます。
手力神社と考えたほうがしっくりきます。
宇佐八幡神社が先住の宇佐氏と渡来の秦氏の合体であることを思えば、
比奈守という固有名詞は、先住の香りがするからです。
飛騨への拠点といっても位置的に?ですから、私説ですが「ひなもり」は比名(奴)森すなわち比自火伽耶族の森(鍛冶場→火祭り)と考えたほうが自然です。飛騨、日田、肥田、斐太、氷川も同族の関係地名だと推測しています。同部族は藤原氏の出自とも言われている(だから百済と混同される)ので、手力雄命を祀る各務氏も百済系と判断されているのではないでしょうか。
まだ検証不足ですが、
祭神が応神天皇と同母の神巧皇后というのは少々疑問も感じます。
手力神社と考えたほうがしっくりきます。
宇佐八幡神社が先住の宇佐氏と渡来の秦氏の合体であることを思えば、
比奈守という固有名詞は、先住の香りがするからです。
飛騨への拠点といっても位置的に?ですから、私説ですが「ひなもり」は比名(奴)森すなわち比自火伽耶族の森(鍛冶場→火祭り)と考えたほうが自然です。飛騨、日田、肥田、斐太、氷川も同族の関係地名だと推測しています。同部族は藤原氏の出自とも言われている(だから百済と混同される)ので、手力雄命を祀る各務氏も百済系と判断されているのではないでしょうか。
ここでもう一度、私なりに美濃と古代の九州との関わりを整理したいと思います。
岐阜市の県庁近くに宇佐の地名がある。
だが、なぜここが筑紫の宇佐なのかよくわからない。
近くには八雲神社と本荘神社と六条神社があり、それぞれ八岐大蛇の頭と胴と尾を現しているので三つで一つとされている。
いずれも祭神はスサノオである。
そこから南の茜部に式内社の美濃国厚見郡茜部神社がある。
茜部荘は710年ころにはじまる東大寺の荘園で、830年ころに宇佐八幡から勧請された。
八幡宮として10番目の分社で、手向山や石清水や鶴岡より古い。
この宇佐と茜部の中間に式内社の美濃国厚見郡比奈守神社があるのも何か意味を感じる。
比奈守(ひなもり)は古事記や魏史倭人伝にもある古代の役職、夷守(ひなもり)とすると、いったいいつだれがどんな敵から守っていたのか。
江戸時代は飛田森神社と称していた。
夷に対する大和朝廷の前線基地だったとすると、その土地柄から見ても飛騨川へ通じる木曽川の交通をここで監視したとも考えられるが。
美濃と尾張を分けた木曽川は境川と呼ばれていた。
まだ勢力を誇っていた尾張と対峙していたのか。
岐阜市は稲葉郡だった。
稲葉は因幡の白兎につながり気になるが。
稲葉山こと金華山から南一帯は厚見郡だった。
厚見(アツミ)は渥美半島の地名由来と同じく、北九州の安曇族から来ている。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=48239782&comm_id=3180326
岐阜市の県庁近くに宇佐の地名がある。
だが、なぜここが筑紫の宇佐なのかよくわからない。
近くには八雲神社と本荘神社と六条神社があり、それぞれ八岐大蛇の頭と胴と尾を現しているので三つで一つとされている。
いずれも祭神はスサノオである。
そこから南の茜部に式内社の美濃国厚見郡茜部神社がある。
茜部荘は710年ころにはじまる東大寺の荘園で、830年ころに宇佐八幡から勧請された。
八幡宮として10番目の分社で、手向山や石清水や鶴岡より古い。
この宇佐と茜部の中間に式内社の美濃国厚見郡比奈守神社があるのも何か意味を感じる。
比奈守(ひなもり)は古事記や魏史倭人伝にもある古代の役職、夷守(ひなもり)とすると、いったいいつだれがどんな敵から守っていたのか。
江戸時代は飛田森神社と称していた。
夷に対する大和朝廷の前線基地だったとすると、その土地柄から見ても飛騨川へ通じる木曽川の交通をここで監視したとも考えられるが。
美濃と尾張を分けた木曽川は境川と呼ばれていた。
まだ勢力を誇っていた尾張と対峙していたのか。
岐阜市は稲葉郡だった。
稲葉は因幡の白兎につながり気になるが。
稲葉山こと金華山から南一帯は厚見郡だった。
厚見(アツミ)は渥美半島の地名由来と同じく、北九州の安曇族から来ている。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=48239782&comm_id=3180326
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170688人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90045人
- 3位
- mixi バスケ部
- 37855人