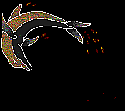木曽川町にある籠守勝手神社(こもりかってじんじゃ)は、地元では「おこもりさん」として親しまれています。
ここは昔の木曽川が流れていていた鎌倉街道沿いにある創建不詳の古社(黒田神社)で、瀬織津姫命と淀姫命(豊玉姫命)という二座の水神が祀られている...
 フォトアルバム
フォトアルバム
籠守勝手神社(一宮市木曽川町黒田)
http://
このおこもりさんではお月見の日(中秋の名月)に年中行事があり、旧暦八月十五日(に近い土曜日)に「御駕籠祭(おかごさい)」、通称「芋名月」が行われます。
この神社に残る億計皇子(オケオウ)と弘計皇子(ヲケオウ)の二皇子の伝承を、後の世まで語り継ぐものとして1500年以上も続けられています。
 フォトアルバム
フォトアルバム
おこもりさんの御駕籠祭
http://
父を殺害された二皇子は、皇位継承の難を逃れるため尾張国一宮の「真清田神社」に向かいました。
途中、黒田松枝郷に鎮座する「黒田明神」の社森に駕籠をとめて一夜を過ごしたことにより、これ以後、黒田明神を「籠守勝手神社」と称するようになったということです。
参考リンク:
http://
http://
...
ここは昔の木曽川が流れていていた鎌倉街道沿いにある創建不詳の古社(黒田神社)で、瀬織津姫命と淀姫命(豊玉姫命)という二座の水神が祀られている...
籠守勝手神社(一宮市木曽川町黒田)
http://
このおこもりさんではお月見の日(中秋の名月)に年中行事があり、旧暦八月十五日(に近い土曜日)に「御駕籠祭(おかごさい)」、通称「芋名月」が行われます。
この神社に残る億計皇子(オケオウ)と弘計皇子(ヲケオウ)の二皇子の伝承を、後の世まで語り継ぐものとして1500年以上も続けられています。
おこもりさんの御駕籠祭
http://
父を殺害された二皇子は、皇位継承の難を逃れるため尾張国一宮の「真清田神社」に向かいました。
途中、黒田松枝郷に鎮座する「黒田明神」の社森に駕籠をとめて一夜を過ごしたことにより、これ以後、黒田明神を「籠守勝手神社」と称するようになったということです。
参考リンク:
http://
http://
...
|
|
|
|
コメント(10)
> k_yairi_dy51_1983さん
謎の継体天皇につながるこの神社はなかなかすごいところですよ。
日本書紀では丹波から播磨へ落ち延びたとなっている億計、弘計の二皇子。
しかし、継体天皇の妃は尾張連の目子媛とある。
ここに正史として初めて尾張氏の名が登場します...
そのすっぽりと抜けてしまっている5世紀前後の歴史が、美濃と尾張の伝承にたくさん残されます。
二皇子が都に戻り皇位につくまでの30年あまり、真清田神社近くで二手にわかれて潜伏していたという神社もあります。
その間、弟の弘計王に生まれたのが後の継体天皇。
雄略の執拗な探索をおそれて美濃の山奥に隠れ住み、根尾の養父母に育てられる。
ここにも養母を祀る神社があり、有名なうすずみ桜も継体天皇が即位のためこの地を去るときの御手植えと伝わってます。
また、牛頭天王を祀る津島神社の有名な天王祭も、継体天皇の起源によるものといわれています...
まだまだありますが、この続きはまた改めてトピを立てますね!
それから、祭神表記が瀬織津姫というのもすごいですね。
この近くで生まれた円空も、長良川や木曽川の本源神に瀬織津姫の姿を見ていたんでしょうね。
さらに、並祭の淀比 (神功皇后の妹)にちなんだ景雲祭が毎年10月20日にあって、三韓出兵で大功を立てられた事によって景雲年間十月二十日に官幣を奉られ、それ以来続くとされる神事です。
といった感じで、何度通っても一筋縄ではいかない神社です。
この辺りに住んでるんですが、宇佐見姓はたしかに多いです...
謎の継体天皇につながるこの神社はなかなかすごいところですよ。
日本書紀では丹波から播磨へ落ち延びたとなっている億計、弘計の二皇子。
しかし、継体天皇の妃は尾張連の目子媛とある。
ここに正史として初めて尾張氏の名が登場します...
そのすっぽりと抜けてしまっている5世紀前後の歴史が、美濃と尾張の伝承にたくさん残されます。
二皇子が都に戻り皇位につくまでの30年あまり、真清田神社近くで二手にわかれて潜伏していたという神社もあります。
その間、弟の弘計王に生まれたのが後の継体天皇。
雄略の執拗な探索をおそれて美濃の山奥に隠れ住み、根尾の養父母に育てられる。
ここにも養母を祀る神社があり、有名なうすずみ桜も継体天皇が即位のためこの地を去るときの御手植えと伝わってます。
また、牛頭天王を祀る津島神社の有名な天王祭も、継体天皇の起源によるものといわれています...
まだまだありますが、この続きはまた改めてトピを立てますね!
それから、祭神表記が瀬織津姫というのもすごいですね。
この近くで生まれた円空も、長良川や木曽川の本源神に瀬織津姫の姿を見ていたんでしょうね。
さらに、並祭の淀比 (神功皇后の妹)にちなんだ景雲祭が毎年10月20日にあって、三韓出兵で大功を立てられた事によって景雲年間十月二十日に官幣を奉られ、それ以来続くとされる神事です。
といった感じで、何度通っても一筋縄ではいかない神社です。
この辺りに住んでるんですが、宇佐見姓はたしかに多いです...
> k_yairi_dy51_1983さん
津島の地名は対馬からきてると思いますが、この地図で見ればそのルートもわかる気がします...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29906309&comm_id=3180326
> 美濃にも宇佐見姓があり
で思い出したのが、筑紫より八幡宮を勧請したという美濃国厚見郡の式内社茜部(あかなべ)神社です。
ここは有名な手向山や鶴岡や石清水より古く、宇佐八幡宮10番目の分社です...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39057868&comm_id=3180326
景雲祭はいつも平日だったりして、まだ見たことないんですよ。
今年の10月にリベンジする予定です^^;
津島の地名は対馬からきてると思いますが、この地図で見ればそのルートもわかる気がします...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29906309&comm_id=3180326
> 美濃にも宇佐見姓があり
で思い出したのが、筑紫より八幡宮を勧請したという美濃国厚見郡の式内社茜部(あかなべ)神社です。
ここは有名な手向山や鶴岡や石清水より古く、宇佐八幡宮10番目の分社です...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39057868&comm_id=3180326
景雲祭はいつも平日だったりして、まだ見たことないんですよ。
今年の10月にリベンジする予定です^^;
>宇佐
でしょ?
実は、親戚がそこに住んでいます。
宇佐が和鍛冶族、八幡が韓鍛冶族ではないでしょうか?
岐阜は、金神社、金華山など製鉄色が濃い土地柄ですね。
これはまったくの私見ですが、長良という地名もインド製鉄部族の神名からきていると思うのです。岐阜市に安良、日置江、曽我屋や物部バリバリの穂積という地名があるのも無視できません。
>比奈守
飛騨封じだとすると、尾張族と関係を考慮する必要性も生まれますが・・・
ともかくも、式内社ではない古社に古代史を解く鍵がありそうです。
ところで、南宮大社は各務原市鵜沼にあった一宮が移されたという説があるのをご存知ですか?事実なら一番の氏神を奪った大社は、先住民封じという意味合いも生じます。
でしょ?
実は、親戚がそこに住んでいます。
宇佐が和鍛冶族、八幡が韓鍛冶族ではないでしょうか?
岐阜は、金神社、金華山など製鉄色が濃い土地柄ですね。
これはまったくの私見ですが、長良という地名もインド製鉄部族の神名からきていると思うのです。岐阜市に安良、日置江、曽我屋や物部バリバリの穂積という地名があるのも無視できません。
>比奈守
飛騨封じだとすると、尾張族と関係を考慮する必要性も生まれますが・・・
ともかくも、式内社ではない古社に古代史を解く鍵がありそうです。
ところで、南宮大社は各務原市鵜沼にあった一宮が移されたという説があるのをご存知ですか?事実なら一番の氏神を奪った大社は、先住民封じという意味合いも生じます。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6473人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19251人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208305人