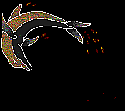羽島市や羽島郡の「羽島」の地名は、羽栗郡の「羽」に中島郡の「島」をつけた地名です。
明治30年(1897)にこの二つの郡が合併して一つの「羽島郡」が生まれました。
そして昭和29年(1954)に羽島郡南部の町村が分離独立して「羽島市」が誕生しました。
天正年間の大洪水で現在の木曽川が生まれましたが、羽島市はこの時に葉栗郡から羽栗郡へと改名され、尾張の国より美濃の国に編入されています。
宝暦年間には、薩摩藩士の御手伝普請による宝暦治水工事の大業が行われて、輪中地帯の真只中にある羽島市は多大にその恩恵を受けました。
羽島の地名を知ろうとすれば、「羽栗(葉栗)」と「中島」の意味を探ることが必要です。
この二つの郡名とも、すでに奈良期の文書にでてくる千年を超える古い地名です...
◆尾張国中嶋(なかしま)郡
古代からの郡名で、愛知県北西部、木曾川中流左岸にあり、濃尾平野のほぼ中央に位置し、国府・国分寺が置かれました。
対岸は岐阜県羽島市(旧美濃国中島郡)で、おおむね現在の稲沢市、尾西市、一宮市(東部および北部の一部を除く)、中島郡の地域です。
平安期の国語辞典でもある『和名抄』では、「奈加之万(なかしま)」と訓じています。
木曽川の流の運び出す土砂がたまって中州ができます。
その中州と中州の間が埋まって中州間(なかすま)となり、中島となったようです。
「ナカ(中)・シマ(周囲を水などで囲まれた地)」の意とする説、天正14(1586)年の大洪水によって木曾川がほぼ現在の流路となる前、鵜沼川の支流が二つに分かれ、下流でまた落ち合い、その間の地を中島といっていたことによるとする説があります。
◆尾張国葉栗(はくり)郡
古代からの郡名で、愛知県北西部、木曾川中流左岸、中島郡の北にあり、おおむね現在の一宮市の北部、江南市の北西部、葉栗(はぐり)郡木曾川(きそがわ)町の地域です。
平安期の『和名抄』は、「波久利(はくり)」と訓じます。
もともとは木曽川の水流で刳(えぐり)とった崖(端)をさす端刳(えぐり)の地からきたようです。
「ハ(端)・クリ(川の蛇行)」の意、「ハグ(剥)・リ(接尾語)」で「浸食されやすい自然堤防」の意、「早生の栗が生える地」、「地味の越えた地」などの説があります。
◆大洪水による尾張国「葉栗」と美濃国「羽栗」
かつて尾張国葉栗郡の郡域は広かったが、安土桃山時代の1586年(天正14年)の木曽川の大洪水により、美濃国との境に流れていた木曽川が葉栗郡内のほぼ中央を流れるようになった。
数年後、豊臣秀吉の命により、新しい木曽川を尾張国と美濃国の境とし、美濃国側を羽栗郡に改称した。
この天正年間の木曽川の大洪水により、尾張国と美濃国の境が変更された地域は多く、尾張国葉栗郡、中島郡、海西郡(現海部郡)にて一部が美濃国羽栗郡(現各務原市南西部、羽島郡、羽島市北部、岐阜市南部)、中島郡(現羽島市南部)、海西郡(後の海津郡、現海津市)に変更された。
岐阜県側の「羽栗」は明治の合併で「羽島」となりすでに消滅。
しかし、愛知県側の「葉栗」はつい最近まで存続していました。
戦後は北方村や浅井町、宮田町、草井村などが属していたが、最後まで残った葉栗郡木曽川町が、2005年4月1日、尾西市と共に一宮市に編入されたため消滅した。
これにて地名としての「はぐり」は過去のものとなってしまいました。
しかし、木曽川をはさんで学校名や地区名、交差点名などに、羽栗と葉栗はその名残りを見せています...
▽猿投神社の尾張古図
http://
▽木曽三川 〜木曽川水系とは
http://
...
明治30年(1897)にこの二つの郡が合併して一つの「羽島郡」が生まれました。
そして昭和29年(1954)に羽島郡南部の町村が分離独立して「羽島市」が誕生しました。
天正年間の大洪水で現在の木曽川が生まれましたが、羽島市はこの時に葉栗郡から羽栗郡へと改名され、尾張の国より美濃の国に編入されています。
宝暦年間には、薩摩藩士の御手伝普請による宝暦治水工事の大業が行われて、輪中地帯の真只中にある羽島市は多大にその恩恵を受けました。
羽島の地名を知ろうとすれば、「羽栗(葉栗)」と「中島」の意味を探ることが必要です。
この二つの郡名とも、すでに奈良期の文書にでてくる千年を超える古い地名です...
◆尾張国中嶋(なかしま)郡
古代からの郡名で、愛知県北西部、木曾川中流左岸にあり、濃尾平野のほぼ中央に位置し、国府・国分寺が置かれました。
対岸は岐阜県羽島市(旧美濃国中島郡)で、おおむね現在の稲沢市、尾西市、一宮市(東部および北部の一部を除く)、中島郡の地域です。
平安期の国語辞典でもある『和名抄』では、「奈加之万(なかしま)」と訓じています。
木曽川の流の運び出す土砂がたまって中州ができます。
その中州と中州の間が埋まって中州間(なかすま)となり、中島となったようです。
「ナカ(中)・シマ(周囲を水などで囲まれた地)」の意とする説、天正14(1586)年の大洪水によって木曾川がほぼ現在の流路となる前、鵜沼川の支流が二つに分かれ、下流でまた落ち合い、その間の地を中島といっていたことによるとする説があります。
◆尾張国葉栗(はくり)郡
古代からの郡名で、愛知県北西部、木曾川中流左岸、中島郡の北にあり、おおむね現在の一宮市の北部、江南市の北西部、葉栗(はぐり)郡木曾川(きそがわ)町の地域です。
平安期の『和名抄』は、「波久利(はくり)」と訓じます。
もともとは木曽川の水流で刳(えぐり)とった崖(端)をさす端刳(えぐり)の地からきたようです。
「ハ(端)・クリ(川の蛇行)」の意、「ハグ(剥)・リ(接尾語)」で「浸食されやすい自然堤防」の意、「早生の栗が生える地」、「地味の越えた地」などの説があります。
◆大洪水による尾張国「葉栗」と美濃国「羽栗」
かつて尾張国葉栗郡の郡域は広かったが、安土桃山時代の1586年(天正14年)の木曽川の大洪水により、美濃国との境に流れていた木曽川が葉栗郡内のほぼ中央を流れるようになった。
数年後、豊臣秀吉の命により、新しい木曽川を尾張国と美濃国の境とし、美濃国側を羽栗郡に改称した。
この天正年間の木曽川の大洪水により、尾張国と美濃国の境が変更された地域は多く、尾張国葉栗郡、中島郡、海西郡(現海部郡)にて一部が美濃国羽栗郡(現各務原市南西部、羽島郡、羽島市北部、岐阜市南部)、中島郡(現羽島市南部)、海西郡(後の海津郡、現海津市)に変更された。
岐阜県側の「羽栗」は明治の合併で「羽島」となりすでに消滅。
しかし、愛知県側の「葉栗」はつい最近まで存続していました。
戦後は北方村や浅井町、宮田町、草井村などが属していたが、最後まで残った葉栗郡木曽川町が、2005年4月1日、尾西市と共に一宮市に編入されたため消滅した。
これにて地名としての「はぐり」は過去のものとなってしまいました。
しかし、木曽川をはさんで学校名や地区名、交差点名などに、羽栗と葉栗はその名残りを見せています...
▽猿投神社の尾張古図
http://
▽木曽三川 〜木曽川水系とは
http://
...
|
|
|
|
コメント(4)
水問題研究所:木曽川物語
http://www5.ocn.ne.jp/~suiken/ksgwmngtr/kiso02.html
洪水のたびに流れを変える木曾川に大々的に人の手を入れたのは秀吉でした。
天正14年(1586年)の洪水で荒れた木曾川に秀吉は文禄元年(1592年)から3年かけて国境を明確にし、戦略上防衛のためと、水害防止のため「文禄の治水」といわれる天端が2米程度の堤防を築いております。
その後家康は、慶長12年(1607年)に義直を清洲城に配すると、慶長13年に東国の防衛と治水のために伊奈忠次に命じて犬山から弥富まで50kmにわたって御囲堤を造りました。この御囲堤は「美濃の堤は、尾張の堤より三尺低かるべきこと。」とされ、美濃側の堤防より尾張側の堤防が高く、天端(馬踏)も8間ほどの堅固なものでした。
その上、慶長14年義直が紀州の浅野幸長の娘、春姫と結婚することになりましたが、家康は「木曽の山を嫁の化粧料にくれてやろう。」と言ったその時、尾張藩の家老の成瀬隼人守正成が「木曽の山川ともご拝領有難く。」と言って山も川も含めてもらってしまったと言われております。〔事蹟録。藩選記録集成〕
しかし、美濃側では、この御囲堤と木曽川によって、慶長年間から宝暦年間の168年間(1596−1763)に110回の洪水に見舞われたと言われております。
明治になって木曽川を測量したら、美濃側が若干高かったようですが、美濃側では子供でも堤防に上がるときは、袂に小石をいれて運ぶように教えられていたとか、徳川幕府が弱体化した頃から、明治の初めにかけていっせいに土盛りをしたとか言われております。
徳川政権が強い時は隠れて堤防の嵩上げをし、弱体化すると公然と土を運んで堤防の嵩上げを行ったと言うこと、両方とも本当だと思います。
一方、尾張側では、この御囲堤の完成で木曽側の氾濫は無くなりましたが、逆に尾張平野はそれまで派川であった五条川、青木川、日光川、三宅川、領内川などの八流が無くなり水不足になるようになりました。
このため、尾張藩では真清田神社の宮大工を用水工法の先進地である播磨や大和に送って杁や水門の技術を学ばせ、木曾川からの取水口と用水路の整備を行ないました。そして、木曽八流は農業用水路に変化して行き、新田開発が進んで莫大な利益を上げていったのです。
美濃側も黙っていたわけではありません。つまり、「幕府が出している行政区画図の決定版である国絵図には国境は木曽川の中央になっていたので、美濃側は木曽川が尾張のものであると言うのはおかしい。」と言うものでした。
幕府は「幕府の国絵図は間違いない。また、権現様が木曽川を尾張にやったと言ったならそれも正しい。」と言ったような判決でした。
しかし、美濃側は何度も訴えており、最終的に、幕府の評定所では「境界、流域所有の如何を問わず河水の及ぶ限り尾張藩の支配とする。」と言う判定をしました。
こうしたことから、美濃の人々は木曽川について尾張藩に対し、よい感情は抱いていませんでした。そして、自分たちの集落を守るために美濃側では輪中が造られていったものと思われます。
さらに、濃尾平野全体で見ると、木曽側の河床が一番高く長良川、揖斐川の順に西に向って低くなっており、下流地域では三川は交わりあっており、洪水になると西側ほど被害が大きくなっていました。このため幕府も美濃の大きな被害に関心があり、地元からの要請もあって三川の改修に乗り出しました。
これは、「宝暦の治水」と言われ、宝暦3年にお手伝い普請として薩摩藩に幕命が降りて、宝暦4年から5年にかけて工事が行なわれました。
工事は油島締め切り工事、大榑川洗堰締め切り工事など4ヶ所で工事が行われましたが、度重なる洪水に出会い難工事となって薩摩藩は藩の石高の2年分にあたる160万石=40万両と多くに生命を失いました。(切腹者54名、死者33人)
徳川幕府が崩壊すると、堅く守られていた木曽の山林は、官林・私有林とも盗伐、乱伐が増加して洪水に見舞われるようになりました。
このため、明治政府は明治6年オランダからデレーケを招いて治水に当たらせることになりました。デレーケは実地調査の結果、木曽川、長良川、揖斐川の三川を完全に分流することになりましたが、三川分流の準備として「治水のもとは治山」と考え、森林監視、禁伐林・制限林の制定、など山林政策を建策しました。
明治政府は植林を行うとともに、明治20年から明治44年までかけて、現在のように完全に三川を分流して洪水対策を行ったのです。
こうして、木曽川は長野県築摩郡木祖村の鉢盛山(2446m)を発し、三重県桑名市で伊勢湾に注ぐ、幹線流路延長229km、流域面積5275k?、の大河川に生まれ変わったのです。
http://www5.ocn.ne.jp/~suiken/ksgwmngtr/kiso02.html
洪水のたびに流れを変える木曾川に大々的に人の手を入れたのは秀吉でした。
天正14年(1586年)の洪水で荒れた木曾川に秀吉は文禄元年(1592年)から3年かけて国境を明確にし、戦略上防衛のためと、水害防止のため「文禄の治水」といわれる天端が2米程度の堤防を築いております。
その後家康は、慶長12年(1607年)に義直を清洲城に配すると、慶長13年に東国の防衛と治水のために伊奈忠次に命じて犬山から弥富まで50kmにわたって御囲堤を造りました。この御囲堤は「美濃の堤は、尾張の堤より三尺低かるべきこと。」とされ、美濃側の堤防より尾張側の堤防が高く、天端(馬踏)も8間ほどの堅固なものでした。
その上、慶長14年義直が紀州の浅野幸長の娘、春姫と結婚することになりましたが、家康は「木曽の山を嫁の化粧料にくれてやろう。」と言ったその時、尾張藩の家老の成瀬隼人守正成が「木曽の山川ともご拝領有難く。」と言って山も川も含めてもらってしまったと言われております。〔事蹟録。藩選記録集成〕
しかし、美濃側では、この御囲堤と木曽川によって、慶長年間から宝暦年間の168年間(1596−1763)に110回の洪水に見舞われたと言われております。
明治になって木曽川を測量したら、美濃側が若干高かったようですが、美濃側では子供でも堤防に上がるときは、袂に小石をいれて運ぶように教えられていたとか、徳川幕府が弱体化した頃から、明治の初めにかけていっせいに土盛りをしたとか言われております。
徳川政権が強い時は隠れて堤防の嵩上げをし、弱体化すると公然と土を運んで堤防の嵩上げを行ったと言うこと、両方とも本当だと思います。
一方、尾張側では、この御囲堤の完成で木曽側の氾濫は無くなりましたが、逆に尾張平野はそれまで派川であった五条川、青木川、日光川、三宅川、領内川などの八流が無くなり水不足になるようになりました。
このため、尾張藩では真清田神社の宮大工を用水工法の先進地である播磨や大和に送って杁や水門の技術を学ばせ、木曾川からの取水口と用水路の整備を行ないました。そして、木曽八流は農業用水路に変化して行き、新田開発が進んで莫大な利益を上げていったのです。
美濃側も黙っていたわけではありません。つまり、「幕府が出している行政区画図の決定版である国絵図には国境は木曽川の中央になっていたので、美濃側は木曽川が尾張のものであると言うのはおかしい。」と言うものでした。
幕府は「幕府の国絵図は間違いない。また、権現様が木曽川を尾張にやったと言ったならそれも正しい。」と言ったような判決でした。
しかし、美濃側は何度も訴えており、最終的に、幕府の評定所では「境界、流域所有の如何を問わず河水の及ぶ限り尾張藩の支配とする。」と言う判定をしました。
こうしたことから、美濃の人々は木曽川について尾張藩に対し、よい感情は抱いていませんでした。そして、自分たちの集落を守るために美濃側では輪中が造られていったものと思われます。
さらに、濃尾平野全体で見ると、木曽側の河床が一番高く長良川、揖斐川の順に西に向って低くなっており、下流地域では三川は交わりあっており、洪水になると西側ほど被害が大きくなっていました。このため幕府も美濃の大きな被害に関心があり、地元からの要請もあって三川の改修に乗り出しました。
これは、「宝暦の治水」と言われ、宝暦3年にお手伝い普請として薩摩藩に幕命が降りて、宝暦4年から5年にかけて工事が行なわれました。
工事は油島締め切り工事、大榑川洗堰締め切り工事など4ヶ所で工事が行われましたが、度重なる洪水に出会い難工事となって薩摩藩は藩の石高の2年分にあたる160万石=40万両と多くに生命を失いました。(切腹者54名、死者33人)
徳川幕府が崩壊すると、堅く守られていた木曽の山林は、官林・私有林とも盗伐、乱伐が増加して洪水に見舞われるようになりました。
このため、明治政府は明治6年オランダからデレーケを招いて治水に当たらせることになりました。デレーケは実地調査の結果、木曽川、長良川、揖斐川の三川を完全に分流することになりましたが、三川分流の準備として「治水のもとは治山」と考え、森林監視、禁伐林・制限林の制定、など山林政策を建策しました。
明治政府は植林を行うとともに、明治20年から明治44年までかけて、現在のように完全に三川を分流して洪水対策を行ったのです。
こうして、木曽川は長野県築摩郡木祖村の鉢盛山(2446m)を発し、三重県桑名市で伊勢湾に注ぐ、幹線流路延長229km、流域面積5275k?、の大河川に生まれ変わったのです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170689人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90046人
- 3位
- mixi バスケ部
- 37855人