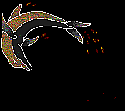酷暑の夏に疫病が流行しないように祈願する、牛頭天王のお祭り。
京都の祇園祭をはじめ、博多の山笠など牛頭天王の祭礼としたお祭りはほとんどこの時期に行われます...
祇園祭とは、約1100年前の平安時代に京で疫病が流行した際、当時の国の数にちなんで66本の鉾を立て、祇園の神を迎えて災厄が取り除かれるよう祈ったことが始まりとされています。
八坂神社の祭神、素戔嗚尊(すさのおのみこと)は、古くは「牛頭天王」(ごずてんのう)と呼ばれていました。
その素戔嗚尊が旅の途中でもてなしてくれた蘇民将来に対し、お礼として「子孫に疫病を免れさせる」と約束し、その印として「茅(ち)の輪」を付けさせました。
茅の輪が変化した「ちまき」も厄除けの役割を担っています。
現在の祇園祭は、八坂神社や京都市内の中心部で1ヶ月間行われます。
7月1日の「吉符入り」で幕を開け、14〜16日の宵山は、山や鉾に提灯の明かりが照らされます。
17日にはクライマックスともいえる山鉾巡行と神幸祭があります。
その後も様々な行事を経て、31日に八坂神社の境内、疫神社の鳥居に大きな芽の輪を付け、輪を潜り抜けて厄除けを祈願する「夏越祭」で、1ヶ月にわたる祇園祭が締めくくられます。
この地方でも、津島牛頭天王社は疫病、災厄除けの神として祀られています。
そして荘厳で華麗な川祭り、津島天王祭が行わます。
この祭りの起源について、京都の神泉苑へ御霊を鎮め送った祭事(御よし流し)が次第に地方へ伝播したなど諸説ありますが、津島神社の祭礼としての始まりは約500年程前の室町時代末期頃といわれています。
しかし、津島の歴史にはやはり何かあったのではといえそうな伝承もたくさん残っています。
須佐之男命が、西の海より津島湊の河口である市江島に着岸した折に、草刈りの童子が遊び戯れているのを見て、稚児の舞、笛の譜を作ったといわれます。
その後、疫病の流行とともに神を慰めるため、この祭りが行われるようになったという説があります。
また、後醍醐天皇の子孫、南朝の良王を守る津島武士(四家七党)が、北朝方の武士を船遊びにことよせて、討ち取ったことからとも伝えられます...
■尾張津島天王祭
津島天王祭りは津島神社と天王川公園で繰り広げられる大祭で、津島川祭りとか津島祭とも呼ばれます。
かつては旧暦六月十四〜十五日に行われていましたが、現在は7月第4土曜日とその翌日に行われています。
祭りは数ヶ月に渡って様々な行事、儀式、神事が行われますが、祭りのクライマックスは「宵祭」と「朝祭」です。
宵祭りは土曜日の夜、津島五車(津島五ヶ村の堤下、米之座、今市場、筏場、下構)の車楽(だんじり)といわれる提灯に彩られた巻藁(まきわら)船5艘が、車河戸と天王川の御旅所を往復します。
車楽の中心には真柱が立てられ、1年の月数12個(閏年は13個)の提灯をつけられます。
屋根には半円山型状に、1年の日数365個の提灯がつけられます。
一方朝祭りは翌朝、夜飾りを撤去し装いを新たにした津島五車に市江村(現在の佐屋町)の「市江車」が先頭に加わわります。
明治5年(1872)までは車楽と呼ばれる山車(船)だけでなく、津島五ヶ村から大山と呼ばれる山車(船)も登場していました。
それぞれ6艘に能人形を飾った車楽船が、古楽を奏でながら中之島付近に進みます。
市江車から布鉾を持った鉾持が、水中に水しぶきをあげながら次々に池に飛び込み、お旅所まで泳ぎ拝礼し、さらに津島神社まで走り拝殿前に奉納します。
また朝祭終了後の深夜には、社殿に奉斎されていた古い神葭を天王川に流す「神葭流し」があります。
新しい神葭は津島神社本殿に納められ、一年間人々の祈願を受けます。
江戸時代に天王川が海に続いていたころは、この神葭が知多半島や三河湾に漂着したという記録も残っています。
漂着した場では御社を建て神葭を奉り、近郷近在の信仰を集めたそうです。
その津島神社の信仰の広まりと共に、周辺には津島天王祭の影響を受けたと思われる祭りが多く分布しています。
その多くが牛頭天王(須佐之男命)を祀る津島神社・(牛頭)天王社・須佐之男社・八坂神社の祭礼です。
犬山市三光寺稲荷、尾西、川島などの木曽川流域でも巻藁船が浮かべられています。
また、天王祭として各地で山車を曳く夏祭りが行われます...
■各地の巻藁提灯を飾る山車のお祭り
・黒岩川祭(一宮市浅井)・・・木曽川の二重輪中の間に位置するため、木曽川に隣接しながら祭船を出せなかったため山車になったといわれます
・ちんとろ祭(半田市上半田)・・・住吉神社の社前に広がる宮池にちんとろ船(巻藁船)が浮かべられます
・こがし祭り(稲沢市北市場)・・・屋根上に提灯を飾る山車も、以前は五条川に浮かべる巻藁型川船だったといわれます
・大森天王祭(名古屋市守山区)・・・以前は夕刻になると山車の屋根を取り外し、巻藁に付け替えて半球に竹笹提灯を飾ったといわれます
他にも出来町天王祭(名古屋市東区)、筒井町天王祭(名古屋市東区)、牛立天王祭(名古屋市中川区)、西枇杷島祭(西枇杷島町)、岩倉天王祭(岩倉市)、玉野町天王祭(春日井市玉野町)などなど...
関連>月夜見 [ツクヨミ] トピック
▽雑節【大祓】
http://
...
京都の祇園祭をはじめ、博多の山笠など牛頭天王の祭礼としたお祭りはほとんどこの時期に行われます...
祇園祭とは、約1100年前の平安時代に京で疫病が流行した際、当時の国の数にちなんで66本の鉾を立て、祇園の神を迎えて災厄が取り除かれるよう祈ったことが始まりとされています。
八坂神社の祭神、素戔嗚尊(すさのおのみこと)は、古くは「牛頭天王」(ごずてんのう)と呼ばれていました。
その素戔嗚尊が旅の途中でもてなしてくれた蘇民将来に対し、お礼として「子孫に疫病を免れさせる」と約束し、その印として「茅(ち)の輪」を付けさせました。
茅の輪が変化した「ちまき」も厄除けの役割を担っています。
現在の祇園祭は、八坂神社や京都市内の中心部で1ヶ月間行われます。
7月1日の「吉符入り」で幕を開け、14〜16日の宵山は、山や鉾に提灯の明かりが照らされます。
17日にはクライマックスともいえる山鉾巡行と神幸祭があります。
その後も様々な行事を経て、31日に八坂神社の境内、疫神社の鳥居に大きな芽の輪を付け、輪を潜り抜けて厄除けを祈願する「夏越祭」で、1ヶ月にわたる祇園祭が締めくくられます。
この地方でも、津島牛頭天王社は疫病、災厄除けの神として祀られています。
そして荘厳で華麗な川祭り、津島天王祭が行わます。
この祭りの起源について、京都の神泉苑へ御霊を鎮め送った祭事(御よし流し)が次第に地方へ伝播したなど諸説ありますが、津島神社の祭礼としての始まりは約500年程前の室町時代末期頃といわれています。
しかし、津島の歴史にはやはり何かあったのではといえそうな伝承もたくさん残っています。
須佐之男命が、西の海より津島湊の河口である市江島に着岸した折に、草刈りの童子が遊び戯れているのを見て、稚児の舞、笛の譜を作ったといわれます。
その後、疫病の流行とともに神を慰めるため、この祭りが行われるようになったという説があります。
また、後醍醐天皇の子孫、南朝の良王を守る津島武士(四家七党)が、北朝方の武士を船遊びにことよせて、討ち取ったことからとも伝えられます...
■尾張津島天王祭
津島天王祭りは津島神社と天王川公園で繰り広げられる大祭で、津島川祭りとか津島祭とも呼ばれます。
かつては旧暦六月十四〜十五日に行われていましたが、現在は7月第4土曜日とその翌日に行われています。
祭りは数ヶ月に渡って様々な行事、儀式、神事が行われますが、祭りのクライマックスは「宵祭」と「朝祭」です。
宵祭りは土曜日の夜、津島五車(津島五ヶ村の堤下、米之座、今市場、筏場、下構)の車楽(だんじり)といわれる提灯に彩られた巻藁(まきわら)船5艘が、車河戸と天王川の御旅所を往復します。
車楽の中心には真柱が立てられ、1年の月数12個(閏年は13個)の提灯をつけられます。
屋根には半円山型状に、1年の日数365個の提灯がつけられます。
一方朝祭りは翌朝、夜飾りを撤去し装いを新たにした津島五車に市江村(現在の佐屋町)の「市江車」が先頭に加わわります。
明治5年(1872)までは車楽と呼ばれる山車(船)だけでなく、津島五ヶ村から大山と呼ばれる山車(船)も登場していました。
それぞれ6艘に能人形を飾った車楽船が、古楽を奏でながら中之島付近に進みます。
市江車から布鉾を持った鉾持が、水中に水しぶきをあげながら次々に池に飛び込み、お旅所まで泳ぎ拝礼し、さらに津島神社まで走り拝殿前に奉納します。
また朝祭終了後の深夜には、社殿に奉斎されていた古い神葭を天王川に流す「神葭流し」があります。
新しい神葭は津島神社本殿に納められ、一年間人々の祈願を受けます。
江戸時代に天王川が海に続いていたころは、この神葭が知多半島や三河湾に漂着したという記録も残っています。
漂着した場では御社を建て神葭を奉り、近郷近在の信仰を集めたそうです。
その津島神社の信仰の広まりと共に、周辺には津島天王祭の影響を受けたと思われる祭りが多く分布しています。
その多くが牛頭天王(須佐之男命)を祀る津島神社・(牛頭)天王社・須佐之男社・八坂神社の祭礼です。
犬山市三光寺稲荷、尾西、川島などの木曽川流域でも巻藁船が浮かべられています。
また、天王祭として各地で山車を曳く夏祭りが行われます...
■各地の巻藁提灯を飾る山車のお祭り
・黒岩川祭(一宮市浅井)・・・木曽川の二重輪中の間に位置するため、木曽川に隣接しながら祭船を出せなかったため山車になったといわれます
・ちんとろ祭(半田市上半田)・・・住吉神社の社前に広がる宮池にちんとろ船(巻藁船)が浮かべられます
・こがし祭り(稲沢市北市場)・・・屋根上に提灯を飾る山車も、以前は五条川に浮かべる巻藁型川船だったといわれます
・大森天王祭(名古屋市守山区)・・・以前は夕刻になると山車の屋根を取り外し、巻藁に付け替えて半球に竹笹提灯を飾ったといわれます
他にも出来町天王祭(名古屋市東区)、筒井町天王祭(名古屋市東区)、牛立天王祭(名古屋市中川区)、西枇杷島祭(西枇杷島町)、岩倉天王祭(岩倉市)、玉野町天王祭(春日井市玉野町)などなど...
関連>月夜見 [ツクヨミ] トピック
▽雑節【大祓】
http://
...
|
|
|
|
コメント(2)
なんでこの地方は舟を山車とする川祭りとなったんだろう?
津島のスサノオ伝説がヒントとなり、当時はかなりの範囲が海や大河に囲まれていた地域だったことも関係してきそう...
伊勢や鳥羽の島々に行くと、玄関先には門符を付けた注連縄が年中飾られていることに気づきます。
伊勢市街の外れに蘇民の杜という神社があり、そこでこの門符を出している。
昔むかし、旅の途中この地を訪れたスサノオが宿を求め歩き、心優しい蘇民将来だけが泊めてくれた。
去り際にスサノオは、これからこの地に疫病を流行らせるが、あなたの一族だけは助けるといった。
そして一族とわかるように全員に門符(護符)を取り付けるようにいわれた。
それ以来、この地では子孫とわかるように蘇民将来と書かれた護符が...
今モバイルなので多少間違ってるかもですが、だいたいこんな感じのスサノオ伝説が残っています。
神代の昔、スサノオが津島まで来たことは十分考えられるし、当時は伊勢から津島(島と名の付く高台の陸地)一帯は海人族の地。
当時は船で移動する方が当たり前で、辺り一面の水辺には無数の船が海と川とを行き来していたはず。
現在の祭りを見ても、以前は川に水量があったりして船を出していたのに、環境が変わって上陸する山車が増えたように、当時は狭い陸地の丘陵地帯で山車なんてやってられず、いっそのこと船に乗っけちゃえとなったのかもしれません...
ってことは、逆もしかり(>_<)
京都の祇園だって、ルーツは船だったかも???
結局そんなこと、私にはわかりゃしません^^;...
津島のスサノオ伝説がヒントとなり、当時はかなりの範囲が海や大河に囲まれていた地域だったことも関係してきそう...
伊勢や鳥羽の島々に行くと、玄関先には門符を付けた注連縄が年中飾られていることに気づきます。
伊勢市街の外れに蘇民の杜という神社があり、そこでこの門符を出している。
昔むかし、旅の途中この地を訪れたスサノオが宿を求め歩き、心優しい蘇民将来だけが泊めてくれた。
去り際にスサノオは、これからこの地に疫病を流行らせるが、あなたの一族だけは助けるといった。
そして一族とわかるように全員に門符(護符)を取り付けるようにいわれた。
それ以来、この地では子孫とわかるように蘇民将来と書かれた護符が...
今モバイルなので多少間違ってるかもですが、だいたいこんな感じのスサノオ伝説が残っています。
神代の昔、スサノオが津島まで来たことは十分考えられるし、当時は伊勢から津島(島と名の付く高台の陸地)一帯は海人族の地。
当時は船で移動する方が当たり前で、辺り一面の水辺には無数の船が海と川とを行き来していたはず。
現在の祭りを見ても、以前は川に水量があったりして船を出していたのに、環境が変わって上陸する山車が増えたように、当時は狭い陸地の丘陵地帯で山車なんてやってられず、いっそのこと船に乗っけちゃえとなったのかもしれません...
ってことは、逆もしかり(>_<)
京都の祇園だって、ルーツは船だったかも???
結局そんなこと、私にはわかりゃしません^^;...
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人