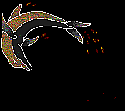日本では古来より、民間信仰のなかに「棚機津女=棚機女(たなばたつめ)」という行事がありました。
人里離れた水辺につくられた棚で乙女が機(はた)を織り、神を迎えて禊(みそぎ)を行う行事でした。
農村では七月七日の夜に、神の嫁となる処女=巫女が神の降臨を待って、人里離れた水辺の小屋で一晩過ごし、翌日に笹竹の飾りを川や海に流して穢れを流してもらいます。
流し雛のように穢れを流すので、「たなばた流し」または「たなばた送り」と呼ばれます。
この乙女=巫女を「棚機(たなばた)つ女(め)」といい、中国から伝わった「織女伝説」と結びついて、今日の七夕の風習ができたのではないかといわれています。
そうして日本語の「たなばた」が、いつしか「七夕」=「たなばた」となったようです。
川にものを流す「鐘楼流し」や「ねぶた祭り」も、棚機女信仰から派生した行事です。
東日本では、身のけがれを流すかわりに人形やロウソクを船にのせて川に流し、自分も水浴びをするという風習がありました。
東北地方各地では「ねむり流し」、栃木県足利地方では「ねぶと流し」といわれます。
農繁期を前に眠気を水に流して追い払う意味があり、夏場に人々を襲う睡魔を「ねむの木」に託し、川に流して送り出すという行事です。
現在でも、東北の夏祭りとして「ねぶた」(青森)、「ねぷた」(弘前)が大変有名です。
そしてちょうど七夕の時期は、キュウリやナス、麦などの収穫を祝う「収穫祭」でもありました。
収穫を控えたこの時期、畑に「たなばた様」という神様が来るという考えがありました。
里芋の葉にたまった水で墨をすって字を書くなど、収穫祝いの意味があります。
この収穫祝いのための祭壇も、「棚旗(たなばた)」とよばれました。
棚旗の「棚」はそなえ物を並べる板のことで、「旗」はこの棚の周りに立てた囲いの木(これが後にササになる)につるした五色の短冊のことです。
このように民間では棚機女(たなばたつめ)信仰が長い間行われており、宮中の七夕行事が入ってきたのはようやく江戸時代に入ってからでした...
詳しくは、月夜見 [ツクヨミ] トピックへ
http://
この地方では一宮や安城で、旧暦の七夕に近い7月末から8月頭に七夕祭りがありますね!
日本の三大七夕祭りは「仙台・平塚・一宮」、または「仙台・平塚・安城」といわれています...
■一宮七夕まつり
毎年7月の最終日曜日をフィナーレとする木曜日からの4日間。
尾張一宮真清田神社の摂社「服織(はとり)神社」の祭礼。
そのご祭神は、天火明命の母神であり機織りの守護神である「萬幡豊秋津師比賣命(ヨロズハタトヨアキツシヒメ)」です。
公式サイト:
http://
■安城七夕まつり
毎年8月の第1金曜日から3日間。
安城神社の末社「七夕神社」の祭礼。
そのご祭神は、猿田彦大神と天宇受売命となります。
公式サイト:
http://
ちなみに七夕神社と名のつく神社は福岡県や宮城県にあり、名古屋市北区には多奈波太神社があります。
■多奈波太神社
愛知県名古屋市北区金城4-13-16
祭神:天之棚機姫命
メモ:8月7日「例大祭」
昭和50年代まで「七夕町」、それ以前は「田端村」と呼ばれていた。
■星神社(星大明神社)
愛知県名古屋市西区上小田井1-172
祭神:大己貴命
メモ:8月7日「七夕祭」
多奈波太神社の対岸にあり、同じく七夕に深い関わりを持つ神社。
*[コメント9] 名古屋の小田井と田幡に伝わる七夕説話
もし他にも、この地域で七夕に関する水辺の伝承があればぜひ教えてください!
...
人里離れた水辺につくられた棚で乙女が機(はた)を織り、神を迎えて禊(みそぎ)を行う行事でした。
農村では七月七日の夜に、神の嫁となる処女=巫女が神の降臨を待って、人里離れた水辺の小屋で一晩過ごし、翌日に笹竹の飾りを川や海に流して穢れを流してもらいます。
流し雛のように穢れを流すので、「たなばた流し」または「たなばた送り」と呼ばれます。
この乙女=巫女を「棚機(たなばた)つ女(め)」といい、中国から伝わった「織女伝説」と結びついて、今日の七夕の風習ができたのではないかといわれています。
そうして日本語の「たなばた」が、いつしか「七夕」=「たなばた」となったようです。
川にものを流す「鐘楼流し」や「ねぶた祭り」も、棚機女信仰から派生した行事です。
東日本では、身のけがれを流すかわりに人形やロウソクを船にのせて川に流し、自分も水浴びをするという風習がありました。
東北地方各地では「ねむり流し」、栃木県足利地方では「ねぶと流し」といわれます。
農繁期を前に眠気を水に流して追い払う意味があり、夏場に人々を襲う睡魔を「ねむの木」に託し、川に流して送り出すという行事です。
現在でも、東北の夏祭りとして「ねぶた」(青森)、「ねぷた」(弘前)が大変有名です。
そしてちょうど七夕の時期は、キュウリやナス、麦などの収穫を祝う「収穫祭」でもありました。
収穫を控えたこの時期、畑に「たなばた様」という神様が来るという考えがありました。
里芋の葉にたまった水で墨をすって字を書くなど、収穫祝いの意味があります。
この収穫祝いのための祭壇も、「棚旗(たなばた)」とよばれました。
棚旗の「棚」はそなえ物を並べる板のことで、「旗」はこの棚の周りに立てた囲いの木(これが後にササになる)につるした五色の短冊のことです。
このように民間では棚機女(たなばたつめ)信仰が長い間行われており、宮中の七夕行事が入ってきたのはようやく江戸時代に入ってからでした...
詳しくは、月夜見 [ツクヨミ] トピックへ
http://
この地方では一宮や安城で、旧暦の七夕に近い7月末から8月頭に七夕祭りがありますね!
日本の三大七夕祭りは「仙台・平塚・一宮」、または「仙台・平塚・安城」といわれています...
■一宮七夕まつり
毎年7月の最終日曜日をフィナーレとする木曜日からの4日間。
尾張一宮真清田神社の摂社「服織(はとり)神社」の祭礼。
そのご祭神は、天火明命の母神であり機織りの守護神である「萬幡豊秋津師比賣命(ヨロズハタトヨアキツシヒメ)」です。
公式サイト:
http://
■安城七夕まつり
毎年8月の第1金曜日から3日間。
安城神社の末社「七夕神社」の祭礼。
そのご祭神は、猿田彦大神と天宇受売命となります。
公式サイト:
http://
ちなみに七夕神社と名のつく神社は福岡県や宮城県にあり、名古屋市北区には多奈波太神社があります。
■多奈波太神社
愛知県名古屋市北区金城4-13-16
祭神:天之棚機姫命
メモ:8月7日「例大祭」
昭和50年代まで「七夕町」、それ以前は「田端村」と呼ばれていた。
■星神社(星大明神社)
愛知県名古屋市西区上小田井1-172
祭神:大己貴命
メモ:8月7日「七夕祭」
多奈波太神社の対岸にあり、同じく七夕に深い関わりを持つ神社。
*[コメント9] 名古屋の小田井と田幡に伝わる七夕説話
もし他にも、この地域で七夕に関する水辺の伝承があればぜひ教えてください!
...
|
|
|
|
コメント(17)
> なりさん
多奈波太神社と服織神社に行かれたなんて驚きですが、どうやらシンクロしてたようですね。
七夕に関係あるという星神社の情報ありがとうございます。
真清田神社はその昔、今で言う木曽川の本流にあたる川が目の前に流れていたそうです。
そこで桃の節句に河原に自生していた桃の枝(流し雛)を流していたんだけど、水辺の機織りにも関係しているのではと思ってます。
各地の七夕神社の由来には、そんな水辺が関係していないか気になるところです。
旧暦の話でいうと、七月十五日がお盆。
お盆にもナスやキュウリを供えますが、お盆のはじまりは十五夜の一週間前、つまり上弦の半月、七夕です。
ちなみに、そのことは月と旧暦のコミュに詳しく書いてあります...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21907452&comm_id=1110372
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21456477&comm_id=1110372
...
多奈波太神社と服織神社に行かれたなんて驚きですが、どうやらシンクロしてたようですね。
七夕に関係あるという星神社の情報ありがとうございます。
真清田神社はその昔、今で言う木曽川の本流にあたる川が目の前に流れていたそうです。
そこで桃の節句に河原に自生していた桃の枝(流し雛)を流していたんだけど、水辺の機織りにも関係しているのではと思ってます。
各地の七夕神社の由来には、そんな水辺が関係していないか気になるところです。
旧暦の話でいうと、七月十五日がお盆。
お盆にもナスやキュウリを供えますが、お盆のはじまりは十五夜の一週間前、つまり上弦の半月、七夕です。
ちなみに、そのことは月と旧暦のコミュに詳しく書いてあります...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21907452&comm_id=1110372
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=21456477&comm_id=1110372
...
> なりさん
コメント[02]が[04]へ移動したので前後したということですが、気にしないでください!
では、この水辺を感じる「真清田(真墨田)」の由来に触れてみます...
木曽川からも離れていて、現在はこの辺りに川が見当たりません。
しかし、昔は木曽川の流れが神社の周囲にあったそうです。
そのころ、そこには桃の木がたくさんあったので、参詣者はその桃の木の枝に自分の厄を託して木曽川に流したと伝えられています。
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/festival/toukasai.html
平安時代の「延喜式」神名帳には「眞墨田神社」として記載されています。
この真清田(ますみだ)という社名の由来は、公式ホームページを見ると、
「もとこの地域は、木曽川の灌漑用水による水田地帯として、清く澄んだ水によって水田を形成していたため、真清田(ますみだ)と名付けられた。」
ということになってます。
http://www.masumida.or.jp/yuisho/index.html
ちなみに、参考としてこんなページがあります。
ポリネシア語で解く日本の地名・日本の古典・日本語の語源
http://www.iris.dti.ne.jp/~muken/
つまり真清田とは「マ・ツ・ミ・タ(MA-TU-MI-TA)」で、「川が・荒々しく・襲ってくる・清らかな(土地、地域)」の意味になるそうです。
http://www.iris.dti.ne.jp/~muken/timei17.htm#%81i%82R%81j%92%86%93%88%81i%82%C8%82%A9%82%B5%82%DC%81j%8CS
灌漑技術で水田地帯へと開拓したことによって、縄文の地名「マツミタ」という土地の荒々しい川を鎮めることで、読んで字の如く「真清田」になったのではないかと思います!
コメント[02]が[04]へ移動したので前後したということですが、気にしないでください!
では、この水辺を感じる「真清田(真墨田)」の由来に触れてみます...
木曽川からも離れていて、現在はこの辺りに川が見当たりません。
しかし、昔は木曽川の流れが神社の周囲にあったそうです。
そのころ、そこには桃の木がたくさんあったので、参詣者はその桃の木の枝に自分の厄を託して木曽川に流したと伝えられています。
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/festival/toukasai.html
平安時代の「延喜式」神名帳には「眞墨田神社」として記載されています。
この真清田(ますみだ)という社名の由来は、公式ホームページを見ると、
「もとこの地域は、木曽川の灌漑用水による水田地帯として、清く澄んだ水によって水田を形成していたため、真清田(ますみだ)と名付けられた。」
ということになってます。
http://www.masumida.or.jp/yuisho/index.html
ちなみに、参考としてこんなページがあります。
ポリネシア語で解く日本の地名・日本の古典・日本語の語源
http://www.iris.dti.ne.jp/~muken/
つまり真清田とは「マ・ツ・ミ・タ(MA-TU-MI-TA)」で、「川が・荒々しく・襲ってくる・清らかな(土地、地域)」の意味になるそうです。
http://www.iris.dti.ne.jp/~muken/timei17.htm#%81i%82R%81j%92%86%93%88%81i%82%C8%82%A9%82%B5%82%DC%81j%8CS
灌漑技術で水田地帯へと開拓したことによって、縄文の地名「マツミタ」という土地の荒々しい川を鎮めることで、読んで字の如く「真清田」になったのではないかと思います!
↑なんと旧暦七夕の8月7日から2日間、なりさんが三河で水と暮らしのワークショップを企画してくれましたので、こちらでも紹介させてもらいますね!
詳しくは「音魂瞑想」コミュのイベントをご覧ください↓
http://mixi.jp/view_event.pl?id=33115834&comm_id=217035
〜以下、転載です
三河*七夕 水と暮らしのワークショップ
開催日時:2008年08月07日(〜8日)
開催場所:愛知県
こんにちは。愛知県でち〜こさんの
ワークショップを行います。タイミングのあうかた
どうぞご参加ください。楽しみにしています!
***
三河*七夕 水と暮らしのワークショップ
たなばた。日本では古来より「棚機女(たなばたつめ)」とよばれる
巫女が、水辺で神の降臨を待つという農村の「禊ぎ(みそぎ)」の行事が
あったそうです。それが中国から伝来した七夕伝説と結びついて
「七夕」=「たなばた」となったといわれています。
旧暦七夕のこの日。小嶋さちほさんのみちひらきで
水や土、天への感謝、大地に根っこ。畑しごとや
ごはんづくりをともに行いましょう。山里で
五感をひらいて、のんびりご一緒に。
7日(木)
お昼ごろ 集合(名古屋)
猿投神社 水を尊ぶうた 小さな滝
おやつタイム
畑(草取りと収穫など)
染(麻布を草木で染めます)
ごはんづくり
(お風呂)波フラ
音魂瞑想ワークショップ
ごはんタイム 七夕の宴
8日(金)
起床 畑
ごはんづくりor蚕霊神社へ山あるき(朝日)
ヨガ 朝ごはん 掃除 シェア
お昼ごろ 解散 (温泉?)
<ナビゲイター> 小嶋さちほ
http://www.songstar-donto.com/family.html
<日時> 2008年8月7日(木)〜8日(金)
<場所> 愛知県豊田市小原(名古屋からは車で1時間ほどです。
個人宅になりますので、場所などは折り返しご案内させていただきます)
<参加費> 17000円(1泊2食、ワーク代すべて含)
(音魂瞑想ワークショップのみ参加の方は 3000円
瞑想後、ごはん&七夕の宴、参加の方 +1000円)
<問> 安達080-3645-2641 adachinari@gmail.com
mixiでのメッセージはコチラ→なりhttp://mixi.jp/show_friend.pl?id=694135
***
...
詳しくは「音魂瞑想」コミュのイベントをご覧ください↓
http://mixi.jp/view_event.pl?id=33115834&comm_id=217035
〜以下、転載です
三河*七夕 水と暮らしのワークショップ
開催日時:2008年08月07日(〜8日)
開催場所:愛知県
こんにちは。愛知県でち〜こさんの
ワークショップを行います。タイミングのあうかた
どうぞご参加ください。楽しみにしています!
***
三河*七夕 水と暮らしのワークショップ
たなばた。日本では古来より「棚機女(たなばたつめ)」とよばれる
巫女が、水辺で神の降臨を待つという農村の「禊ぎ(みそぎ)」の行事が
あったそうです。それが中国から伝来した七夕伝説と結びついて
「七夕」=「たなばた」となったといわれています。
旧暦七夕のこの日。小嶋さちほさんのみちひらきで
水や土、天への感謝、大地に根っこ。畑しごとや
ごはんづくりをともに行いましょう。山里で
五感をひらいて、のんびりご一緒に。
7日(木)
お昼ごろ 集合(名古屋)
猿投神社 水を尊ぶうた 小さな滝
おやつタイム
畑(草取りと収穫など)
染(麻布を草木で染めます)
ごはんづくり
(お風呂)波フラ
音魂瞑想ワークショップ
ごはんタイム 七夕の宴
8日(金)
起床 畑
ごはんづくりor蚕霊神社へ山あるき(朝日)
ヨガ 朝ごはん 掃除 シェア
お昼ごろ 解散 (温泉?)
<ナビゲイター> 小嶋さちほ
http://www.songstar-donto.com/family.html
<日時> 2008年8月7日(木)〜8日(金)
<場所> 愛知県豊田市小原(名古屋からは車で1時間ほどです。
個人宅になりますので、場所などは折り返しご案内させていただきます)
<参加費> 17000円(1泊2食、ワーク代すべて含)
(音魂瞑想ワークショップのみ参加の方は 3000円
瞑想後、ごはん&七夕の宴、参加の方 +1000円)
<問> 安達080-3645-2641 adachinari@gmail.com
mixiでのメッセージはコチラ→なりhttp://mixi.jp/show_friend.pl?id=694135
***
...
昨日からはじまった一宮七夕まつり!
駅前からアーケード街にかけて、派手な吊り下げ飾りに吸い込まれるように浴衣姿が集まりだします...
1枚目:駅前の竹飾りが七夕まつりへと誘います。
2枚目:服織(はとり)神社でお参りしてから短冊に願いごとを書いたら、恒例の火の輪くぐりへ。
燃え盛る火の洗礼を受け、その先にある神水社で霊泉の水を飲み、井戸に顔を写すと身が清められるといいます。
まさに火と水の調和。
この水は、平安時代に白河天皇がご病気の折にこの水を飲んで病気が癒えたと伝えられる霊験あらたかな水。
当時この近くに流れていた木曽川の伏流水が、今でも井戸となって涌いているのでしょう...
3枚目:そして最後はこれ!
このお祭りの裏名物は、なんといってもこのお化け屋敷でしょう(笑)
駅前からアーケード街にかけて、派手な吊り下げ飾りに吸い込まれるように浴衣姿が集まりだします...
1枚目:駅前の竹飾りが七夕まつりへと誘います。
2枚目:服織(はとり)神社でお参りしてから短冊に願いごとを書いたら、恒例の火の輪くぐりへ。
燃え盛る火の洗礼を受け、その先にある神水社で霊泉の水を飲み、井戸に顔を写すと身が清められるといいます。
まさに火と水の調和。
この水は、平安時代に白河天皇がご病気の折にこの水を飲んで病気が癒えたと伝えられる霊験あらたかな水。
当時この近くに流れていた木曽川の伏流水が、今でも井戸となって涌いているのでしょう...
3枚目:そして最後はこれ!
このお祭りの裏名物は、なんといってもこのお化け屋敷でしょう(笑)
名古屋の小田井と田幡に伝わる七夕説話
〜小島勝彦著『東海の民話(改訂版)』より〜
むかしむかし、尾張(おわり)の国の庄内(しょうない)川をはさんで、北には小田井(おたい)の里・南には田幡(たばた)の里二つの村がありました。
南の田幡の里には昼は田畑の仕事・夜になれば機織と働き者の美しい娘がおりました。北の小田井の里には田畑の事なら誰にも負けない元気な若者がおりました。
ある年の盆(旧暦8月15日)の事でありました。小田井の里の若者達が、田幡の里の盆踊りに招かれたので、庄内川の稲生(いのう)の渡しを舟で渡りました。
その年の盆踊りはとてもにぎやかになりました。そしてその盆踊りの時に若者は娘を見るなり好きになってしまったのです。娘の方も若者が忘れられなくなっておりました。さて盆踊りも夜が明ける頃には終わり、小田井の里の若者達は稲生の渡しを渡り帰りました。
盆が過ぎても二人は七日に一度逢っておりました。そして段々逢う日も短くなり三日に一度は逢っておりました。夜には渡しの舟が出ないので、若者は泳いで行きました。娘は岸辺で明かりを持って待っておりました。
秋の祭りの頃になりました。若者は父親に「田幡の里の娘が嫁に欲しい」と言いました。父親はもう分かっておりましたので、笑ってうなづきました。若者はもう、いても立ってもいられなくなりなしたが、4・5日前から大雨が降って、渡し舟は出ていません。
若者は水かさが増し、流れが速くなっている川を泳ぎ始めました。そこに浮き木が流れてきて若者の頭にあたってしまったのです。次の日、小田井の里の者が総出で若者を探しましたが見つかりませんでした。
三日後、若者は遺体で見つかりました。里のでは葬儀をし、野辺送りも終わっり、木枯らしが吹く季節になった頃、田幡の里の娘も命を絶ちました。
里の人達は冬の空に光る二つの星を見て「あの若者と娘が星になったのだな」と語り合ったと言う事です。
※庄内川の田幡の里には祭神/天棚織姫神を祭る多奈波太神社があり、対岸の小田井の里には祭神/牽牛・織女を祭る星大明神社があります。
〜小島勝彦著『東海の民話(改訂版)』より〜
むかしむかし、尾張(おわり)の国の庄内(しょうない)川をはさんで、北には小田井(おたい)の里・南には田幡(たばた)の里二つの村がありました。
南の田幡の里には昼は田畑の仕事・夜になれば機織と働き者の美しい娘がおりました。北の小田井の里には田畑の事なら誰にも負けない元気な若者がおりました。
ある年の盆(旧暦8月15日)の事でありました。小田井の里の若者達が、田幡の里の盆踊りに招かれたので、庄内川の稲生(いのう)の渡しを舟で渡りました。
その年の盆踊りはとてもにぎやかになりました。そしてその盆踊りの時に若者は娘を見るなり好きになってしまったのです。娘の方も若者が忘れられなくなっておりました。さて盆踊りも夜が明ける頃には終わり、小田井の里の若者達は稲生の渡しを渡り帰りました。
盆が過ぎても二人は七日に一度逢っておりました。そして段々逢う日も短くなり三日に一度は逢っておりました。夜には渡しの舟が出ないので、若者は泳いで行きました。娘は岸辺で明かりを持って待っておりました。
秋の祭りの頃になりました。若者は父親に「田幡の里の娘が嫁に欲しい」と言いました。父親はもう分かっておりましたので、笑ってうなづきました。若者はもう、いても立ってもいられなくなりなしたが、4・5日前から大雨が降って、渡し舟は出ていません。
若者は水かさが増し、流れが速くなっている川を泳ぎ始めました。そこに浮き木が流れてきて若者の頭にあたってしまったのです。次の日、小田井の里の者が総出で若者を探しましたが見つかりませんでした。
三日後、若者は遺体で見つかりました。里のでは葬儀をし、野辺送りも終わっり、木枯らしが吹く季節になった頃、田幡の里の娘も命を絶ちました。
里の人達は冬の空に光る二つの星を見て「あの若者と娘が星になったのだな」と語り合ったと言う事です。
※庄内川の田幡の里には祭神/天棚織姫神を祭る多奈波太神社があり、対岸の小田井の里には祭神/牽牛・織女を祭る星大明神社があります。
> えーさん
前の日付とはどこの日付と比較されたのかわかりませんが、コメント1から時系列順に並んでいるはずなので、きっとトピック本文の日付を見られたのですね?
もしそうなら技でも何でもありません。
現在「2009/07/09 12:55」となっているのに、コメントは2008年の昨年あたりからはじまってる。
これはトピ本文に関してコミュの管理人もしくはトピ主だけが編集し直すことができるため、私がその日付で本文に加筆して更新したからです。
最初に書かれた日付が記録されないのでわかりませんが、おそらくトピックを作ったのが2008年の7月ということです。
しかし、日記は編集で何度書き換えてもシステム上日付はそのままです。
だからその感覚でえーさんは戸惑ってらっしゃるのではないかと察します。
実は私もこの件は改善して欲しいと思っていました。
最初に書かれた日付プラス最新の更新日付を同時に表示すれば、いろんな参加者が長い時間をかけ別々に閲覧した場合にもこのような混乱をすることなくとてもわかりやすいと思うのですが...
前の日付とはどこの日付と比較されたのかわかりませんが、コメント1から時系列順に並んでいるはずなので、きっとトピック本文の日付を見られたのですね?
もしそうなら技でも何でもありません。
現在「2009/07/09 12:55」となっているのに、コメントは2008年の昨年あたりからはじまってる。
これはトピ本文に関してコミュの管理人もしくはトピ主だけが編集し直すことができるため、私がその日付で本文に加筆して更新したからです。
最初に書かれた日付が記録されないのでわかりませんが、おそらくトピックを作ったのが2008年の7月ということです。
しかし、日記は編集で何度書き換えてもシステム上日付はそのままです。
だからその感覚でえーさんは戸惑ってらっしゃるのではないかと察します。
実は私もこの件は改善して欲しいと思っていました。
最初に書かれた日付プラス最新の更新日付を同時に表示すれば、いろんな参加者が長い時間をかけ別々に閲覧した場合にもこのような混乱をすることなくとてもわかりやすいと思うのですが...
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82539人
- 2位
- 酒好き
- 170702人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人