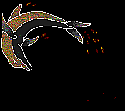那加手力雄神社と長森手力雄神社
岐阜には東山道が通っている。
この道を信州戸隠の修験者が都と信濃を行き来し、情報・文化を伝播したと言われている。
戸隠の九頭竜神が天手力雄の神を迎えて奥社とし、中社には思兼命を祀る。
天手力雄神の身体は籠であり、祈りによって降雨を給うという。
那加手力雄神社は各務郡更木郷の総社である。
各務郡は芥見を含み、東山道の影響を直接受ける地域である。
もともと真幣明神(みてぐらみょうじん)と申し上げて日本でも最も古い形態の神社の一つであるが、早い時代 文安二年(1445年)に手力神社を名乗り、籠の彫刻や民話があるのも戸隠信仰の影響下にあると考えられる。
長森は人皇第95代花園天皇(在位1321〜1330)が皇室領を京都大徳寺に奇進したという。
人皇第96代は後醍醐天皇でこの方も大徳寺を祈願所として尊崇された。足利尊氏や、楠正成の活躍する少し前のことです。
貞視2年(860年)頃美濃の国府は不破にあり、物部氏が勢力をふるっていましたが、各務郡には村国男依がいて、壬申の乱を天武方の勝利に導いた。
やがて村国氏の勢力が衰退すると各務氏が勢力を伸長し、各務の大領各務吉雄・厚見の大領各務吉宗が貞観8年尾張の農民が国司の承認のもと広野川(現在の境川・木曽川の本流)の流路変更の工事をしていたのを700名程で襲撃し、死者を出したと三代実録にあります。
だから、各務郡の氏神の手力雄神社を厚見郡に祀ったのだ、とする考えも出るのですが、厚見郡の中心は茜部・鶉で、荒田川の東から新加納の丘陵部までは湿地が多く、皇室領(屯倉)として一種の空白地帯でした。
各務吉宗が祀ったのは石切神社で、各務氏の祖神石凝姥命を祀っています。
長森の手力雄神社は宮中の祭神を分祀したものと考えられ、伊勢の神宮の手力雄神と同神だと考えられます。
龍神信仰は無いことと、円城寺村の雨乞いは天保3年が始まりであることからも戸隠信仰とは別の神社である。
昭和56年は旱天続きであったが、円城寺の雨乞いの後夕刻から降雨があった。
〜手力雄神社(長森)パンフレットより
この二つの手力雄神社は私の産土であり氏神。
各務原の手力で産まれ、長森の手力で育ったことになる。
今になっていろいろわかってきたのは、この神社が金華山東南麓に流れていた昔の木曽川沿いだったこと。
創建は通説で860年とされているが、かなり遡れるであろうことがわかってきた。
子供のころの遊び場だった琴塚古墳はこの地方の豪族として結びつく。
また今はまったくその存在すら跡形もないが、金華山南麓に在ったとされる物部神社が延喜式や美濃の郷土史には残っている...
参考URL:
手力雄命
http://
火祭りの歴史
http://
琴塚古墳
http://
フォトアルバム:
手力の火祭(春の大祭)
http://
手力雄神社(岐阜市長森)
http://
手力雄神社(各務原市那加)
http://
冨士神社(岐阜県笠松円城寺)
http://
▼東山道 〜古代の陸路あづまのやまつみち
http://
▼式内社美濃国厚見郡三座について
http://
...
岐阜には東山道が通っている。
この道を信州戸隠の修験者が都と信濃を行き来し、情報・文化を伝播したと言われている。
戸隠の九頭竜神が天手力雄の神を迎えて奥社とし、中社には思兼命を祀る。
天手力雄神の身体は籠であり、祈りによって降雨を給うという。
那加手力雄神社は各務郡更木郷の総社である。
各務郡は芥見を含み、東山道の影響を直接受ける地域である。
もともと真幣明神(みてぐらみょうじん)と申し上げて日本でも最も古い形態の神社の一つであるが、早い時代 文安二年(1445年)に手力神社を名乗り、籠の彫刻や民話があるのも戸隠信仰の影響下にあると考えられる。
長森は人皇第95代花園天皇(在位1321〜1330)が皇室領を京都大徳寺に奇進したという。
人皇第96代は後醍醐天皇でこの方も大徳寺を祈願所として尊崇された。足利尊氏や、楠正成の活躍する少し前のことです。
貞視2年(860年)頃美濃の国府は不破にあり、物部氏が勢力をふるっていましたが、各務郡には村国男依がいて、壬申の乱を天武方の勝利に導いた。
やがて村国氏の勢力が衰退すると各務氏が勢力を伸長し、各務の大領各務吉雄・厚見の大領各務吉宗が貞観8年尾張の農民が国司の承認のもと広野川(現在の境川・木曽川の本流)の流路変更の工事をしていたのを700名程で襲撃し、死者を出したと三代実録にあります。
だから、各務郡の氏神の手力雄神社を厚見郡に祀ったのだ、とする考えも出るのですが、厚見郡の中心は茜部・鶉で、荒田川の東から新加納の丘陵部までは湿地が多く、皇室領(屯倉)として一種の空白地帯でした。
各務吉宗が祀ったのは石切神社で、各務氏の祖神石凝姥命を祀っています。
長森の手力雄神社は宮中の祭神を分祀したものと考えられ、伊勢の神宮の手力雄神と同神だと考えられます。
龍神信仰は無いことと、円城寺村の雨乞いは天保3年が始まりであることからも戸隠信仰とは別の神社である。
昭和56年は旱天続きであったが、円城寺の雨乞いの後夕刻から降雨があった。
〜手力雄神社(長森)パンフレットより
この二つの手力雄神社は私の産土であり氏神。
各務原の手力で産まれ、長森の手力で育ったことになる。
今になっていろいろわかってきたのは、この神社が金華山東南麓に流れていた昔の木曽川沿いだったこと。
創建は通説で860年とされているが、かなり遡れるであろうことがわかってきた。
子供のころの遊び場だった琴塚古墳はこの地方の豪族として結びつく。
また今はまったくその存在すら跡形もないが、金華山南麓に在ったとされる物部神社が延喜式や美濃の郷土史には残っている...
参考URL:
手力雄命
http://
火祭りの歴史
http://
琴塚古墳
http://
フォトアルバム:
手力の火祭(春の大祭)
http://
手力雄神社(岐阜市長森)
http://
手力雄神社(各務原市那加)
http://
冨士神社(岐阜県笠松円城寺)
http://
▼東山道 〜古代の陸路あづまのやまつみち
http://
▼式内社美濃国厚見郡三座について
http://
...
|
|
|
|
コメント(3)
平安時代中期に編纂の『延喜式神名帳』記載の美濃国厚見郡「比奈守神社」は、論社として同じ厚見郡の手力雄神社とする説が有力です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39057868&comm_id=3180326
江戸時代の『木曾路名所図会』によると、「比奈守神社・加納より高田・新加納の間、長柄村にあり。今手力雄社といふ。延喜式内なり」としている。
貞観二年(860)の創立と伝えられ、『美濃国神名帳』記載の「従五位下、手力雄明神」にあたります。
祭神である天手力男神は、宮中にあった祭神を伊勢神宮から分祀したことによるとされています。
ここで気になるのは、直線距離にして北東に約1.5kmしか離れていない各務郡の手力雄神社。
天手力男神を主神に、高御産巣日神、神御産巣日神の他六神を配祀する。
しかし、こちらはもともと磐座を祀った真幣明神で、『美濃国神名帳』記載の「従五位下、真幣明神」にあたります。
後に戸隠神社の天手力男神を勧請して各務氏の氏神となった。
あえて言うなら、厚見郡(長森)と各務郡(那加)の手力雄神社は、伊勢神宮と戸隠神社という2つの「タヂカラオ」と言い換えられるかもしれない...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=39057868&comm_id=3180326
江戸時代の『木曾路名所図会』によると、「比奈守神社・加納より高田・新加納の間、長柄村にあり。今手力雄社といふ。延喜式内なり」としている。
貞観二年(860)の創立と伝えられ、『美濃国神名帳』記載の「従五位下、手力雄明神」にあたります。
祭神である天手力男神は、宮中にあった祭神を伊勢神宮から分祀したことによるとされています。
ここで気になるのは、直線距離にして北東に約1.5kmしか離れていない各務郡の手力雄神社。
天手力男神を主神に、高御産巣日神、神御産巣日神の他六神を配祀する。
しかし、こちらはもともと磐座を祀った真幣明神で、『美濃国神名帳』記載の「従五位下、真幣明神」にあたります。
後に戸隠神社の天手力男神を勧請して各務氏の氏神となった。
あえて言うなら、厚見郡(長森)と各務郡(那加)の手力雄神社は、伊勢神宮と戸隠神社という2つの「タヂカラオ」と言い換えられるかもしれない...
■那加手力雄神社の真幣明神(みてぐらみょうじん)について
この真幣明神がいったいどんな神なのかよくわからない。
いくら調べてみても、他で祀られている様子もないのである。
真幣(みてぐら)として調べると、平安時代の大和言葉に「幣」の一文字で「みてぐら」と読むことがわかった。
---引用はじめ---
幣(ぬさ・みてぐら・まひ)
・幣帛(へいはく)
・大幣(おおぬさ)
神に祈るときの捧げ物。
また、祓(はらえ)の料とするもの。
古くは麻・木綿(ゆう)などを用い、のちには織った布や紙を用いた。
旅の道中の安全を祈って道の神に供えるときのものは、布・紙などを小さく切って作る。
その総称をミテグラ(御手座の意)という。
大幣は大きな串につけた幣のこと。
祓えが済むと参列の人々がそれを引き寄せて身の穢れをそれに移し、川に流すことになっていた。
またはひっぱりだこ・気が多いことを意味する。
「大幣の」は「引く」にかかる枕詞。
---引用おわり---
つまり、これは大麻(おおぬさ)を祀っていたということかもしれない!!!
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38821624&comm_id=3180326
...
この真幣明神がいったいどんな神なのかよくわからない。
いくら調べてみても、他で祀られている様子もないのである。
真幣(みてぐら)として調べると、平安時代の大和言葉に「幣」の一文字で「みてぐら」と読むことがわかった。
---引用はじめ---
幣(ぬさ・みてぐら・まひ)
・幣帛(へいはく)
・大幣(おおぬさ)
神に祈るときの捧げ物。
また、祓(はらえ)の料とするもの。
古くは麻・木綿(ゆう)などを用い、のちには織った布や紙を用いた。
旅の道中の安全を祈って道の神に供えるときのものは、布・紙などを小さく切って作る。
その総称をミテグラ(御手座の意)という。
大幣は大きな串につけた幣のこと。
祓えが済むと参列の人々がそれを引き寄せて身の穢れをそれに移し、川に流すことになっていた。
またはひっぱりだこ・気が多いことを意味する。
「大幣の」は「引く」にかかる枕詞。
---引用おわり---
つまり、これは大麻(おおぬさ)を祀っていたということかもしれない!!!
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=38821624&comm_id=3180326
...
火祭り:裸の男衆、勇壮に 岐阜・手力雄神社(毎日新聞 2009年4月11日)
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090412k0000m040095000c.html
岐阜市蔵前の手力雄(てぢからお)神社で11日、みこしを担いだ裸男たちが、火の粉を浴びながら勇壮に練り歩く「火祭り」が行われた。
江戸時代から伝わる岐阜県重要無形民俗文化財。
午後6時50分、神社境内に「バチバチ」と爆竹の音が鳴り響き、13町の御神灯に点火された。
約20メートルのさおの先に取り付けた「滝花火」の火の粉が舞い散る中、裸の男衆が担ぐ8基のみこしが登場。みこしに仕掛けられた花火からは勢いよく火花が噴き上がり、境内は真昼のような明るさとなった。【鈴木敬子】
※写真:男たちが火花の噴き上がるみこしを担ぎ、勇壮に練り歩いた火祭り=岐阜市蔵前で2009年4月11日午後8時、兵藤公治撮影
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090412k0000m040095000c.html
岐阜市蔵前の手力雄(てぢからお)神社で11日、みこしを担いだ裸男たちが、火の粉を浴びながら勇壮に練り歩く「火祭り」が行われた。
江戸時代から伝わる岐阜県重要無形民俗文化財。
午後6時50分、神社境内に「バチバチ」と爆竹の音が鳴り響き、13町の御神灯に点火された。
約20メートルのさおの先に取り付けた「滝花火」の火の粉が舞い散る中、裸の男衆が担ぐ8基のみこしが登場。みこしに仕掛けられた花火からは勢いよく火花が噴き上がり、境内は真昼のような明るさとなった。【鈴木敬子】
※写真:男たちが火花の噴き上がるみこしを担ぎ、勇壮に練り歩いた火祭り=岐阜市蔵前で2009年4月11日午後8時、兵藤公治撮影
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6479人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19255人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208311人