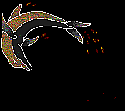猿投神社に伝わる養老元年(717)の尾張古図。
かつて、濃尾平野が海であったことを物語っています。
尾張平野ははるか以前、養老山脈を断崖とする深い谷でした。
約1万年前から海面上昇し、約6000年前にピ−クとなる縄文海進がありました。
海進と海退をくり返しながら、約2000年前には葦原を耕地に変え、国生み神話の時代に入ります。
この地図からは、木曽三川に至る歴史と伝統文化を知る上で、ひとつの道しるべとなるでしょう...
・
・
・
ずいぶん以前の話ですが、木曽三川公園の歴史を紹介する資料の中に、たまたまこの地図が展示されていました。
今でも私は、それを初めて見たときの衝撃を忘れることができません。
その後、再びこの地図と出会ったのは新聞記事の中でした。
当時、この記事を読んだ私はあることを確信しました...
岐阜新聞で連載されていた「ぎふ海紀行」から、1998年2月4日付の記事を全文ご紹介します!
---
ぎふ海紀行 海の記憶
古代の濃尾平野 金色の波寄せた海湾
太古の海水がわき出た本巣郡根尾村の「うすずみ温泉」から、卑弥呼(ひみこ)と争った狗奴国王の古墳ではと注目を集める象鼻山のある養老郡養老町まで根尾川、揖斐川沿いに南下する時、はっと気付いた。
西の伊吹山から南へ養老山塊がどっしり構えるが、そこから南、東に目を転じる時、はるか東に岐阜市の金華山が島のように浮かぶほかは何一つ遮るものはない。まるで大海原のような濃尾平野を見て、一枚の古地図を思い出したのだ。
「世に三河国賀茂郡猿投神社および尾張国葉栗郡玉井神社所蔵の古図と称するものがある。その描くところによると、濃尾地方は一面の海で、中央に中島郡の孤島があり、その南に日置、津島、戸田、長島、枇杷島などの数島が碁石のように点々とし、また長良河口に東、西、中などの六つの島があり、今の金華山の辺に岐阜山と注し、その西に磯島などを描いて、濃尾地方が広漠とした海湾であったことを示している」
「県治水史」は、「濃尾平野の有史的変遷について口碑の伝うるもの2、3に留まらぬが、一つとして学理上信を措くに足るものが無い」とし、その例としてこの一文を挙げている。
猿投神社の図は1830(天保元)年、千年前の古図として世に現れたが、海だったという各所に遺跡が知られて偽作との見方が強い。一方で、伊勢湾台風(1959年)による大水害を体験して、あれは千年前の洪水の図とみる人もいる。真偽はともかく、眼前に広がる風景は、まさにこの「広漠たる海」なのだ。
「縄文海進の海は深くて海面が1、2メートル下がっても海岸線はそう後退しなかった。濃尾平野は木曽三川が運ぶ土砂のたい積で形成されたが、今の姿になったのは近世の海面干拓以降。気候温暖化で小海進があった平安から中世まで、県南部の輪中地帯は海とも陸ともいえぬような所だったと思われる」と、名古屋大名誉教授の井関弘太郎さん。
東征の帰途、熱田から伊吹山に向かったヤマトタケルは舟の上で、多度山に落ちる夕日を見たかもしれない。もうこのころは遠浅の海で金色の波の向こうに伊吹はあまりに近く大きく、田子ノ浦から見る富士、美保湾から見る大山のように聖なる山に見えただろう。
伊吹山の神によって傷つき、養老で「足がたぎたぎしく」(疲れるの意味)なり、鈴鹿の能褒野(のぼの)で「大和し美し」と望郷の歌を詠んで死んだタケルは架空の人物だが、壬申の乱(672年)で挙兵した大海人皇子(後の天武天皇)は、この逆ル−トを進軍したとの見方もある。
古代の養老は、元正天皇の養老改元(717年)や孝子伝説、七堂伽藍(がらん)など全国ニュ−スの発信地。想像以上に海陸交通の要衝だったのだろう。
---
▽木曽三川 〜木曽川水系とは
http://
▽天正の大洪水と木曽川治水史 〜羽島・羽栗(葉栗)という地名について
http://
...
かつて、濃尾平野が海であったことを物語っています。
尾張平野ははるか以前、養老山脈を断崖とする深い谷でした。
約1万年前から海面上昇し、約6000年前にピ−クとなる縄文海進がありました。
海進と海退をくり返しながら、約2000年前には葦原を耕地に変え、国生み神話の時代に入ります。
この地図からは、木曽三川に至る歴史と伝統文化を知る上で、ひとつの道しるべとなるでしょう...
・
・
・
ずいぶん以前の話ですが、木曽三川公園の歴史を紹介する資料の中に、たまたまこの地図が展示されていました。
今でも私は、それを初めて見たときの衝撃を忘れることができません。
その後、再びこの地図と出会ったのは新聞記事の中でした。
当時、この記事を読んだ私はあることを確信しました...
岐阜新聞で連載されていた「ぎふ海紀行」から、1998年2月4日付の記事を全文ご紹介します!
---
ぎふ海紀行 海の記憶
古代の濃尾平野 金色の波寄せた海湾
太古の海水がわき出た本巣郡根尾村の「うすずみ温泉」から、卑弥呼(ひみこ)と争った狗奴国王の古墳ではと注目を集める象鼻山のある養老郡養老町まで根尾川、揖斐川沿いに南下する時、はっと気付いた。
西の伊吹山から南へ養老山塊がどっしり構えるが、そこから南、東に目を転じる時、はるか東に岐阜市の金華山が島のように浮かぶほかは何一つ遮るものはない。まるで大海原のような濃尾平野を見て、一枚の古地図を思い出したのだ。
「世に三河国賀茂郡猿投神社および尾張国葉栗郡玉井神社所蔵の古図と称するものがある。その描くところによると、濃尾地方は一面の海で、中央に中島郡の孤島があり、その南に日置、津島、戸田、長島、枇杷島などの数島が碁石のように点々とし、また長良河口に東、西、中などの六つの島があり、今の金華山の辺に岐阜山と注し、その西に磯島などを描いて、濃尾地方が広漠とした海湾であったことを示している」
「県治水史」は、「濃尾平野の有史的変遷について口碑の伝うるもの2、3に留まらぬが、一つとして学理上信を措くに足るものが無い」とし、その例としてこの一文を挙げている。
猿投神社の図は1830(天保元)年、千年前の古図として世に現れたが、海だったという各所に遺跡が知られて偽作との見方が強い。一方で、伊勢湾台風(1959年)による大水害を体験して、あれは千年前の洪水の図とみる人もいる。真偽はともかく、眼前に広がる風景は、まさにこの「広漠たる海」なのだ。
「縄文海進の海は深くて海面が1、2メートル下がっても海岸線はそう後退しなかった。濃尾平野は木曽三川が運ぶ土砂のたい積で形成されたが、今の姿になったのは近世の海面干拓以降。気候温暖化で小海進があった平安から中世まで、県南部の輪中地帯は海とも陸ともいえぬような所だったと思われる」と、名古屋大名誉教授の井関弘太郎さん。
東征の帰途、熱田から伊吹山に向かったヤマトタケルは舟の上で、多度山に落ちる夕日を見たかもしれない。もうこのころは遠浅の海で金色の波の向こうに伊吹はあまりに近く大きく、田子ノ浦から見る富士、美保湾から見る大山のように聖なる山に見えただろう。
伊吹山の神によって傷つき、養老で「足がたぎたぎしく」(疲れるの意味)なり、鈴鹿の能褒野(のぼの)で「大和し美し」と望郷の歌を詠んで死んだタケルは架空の人物だが、壬申の乱(672年)で挙兵した大海人皇子(後の天武天皇)は、この逆ル−トを進軍したとの見方もある。
古代の養老は、元正天皇の養老改元(717年)や孝子伝説、七堂伽藍(がらん)など全国ニュ−スの発信地。想像以上に海陸交通の要衝だったのだろう。
---
▽木曽三川 〜木曽川水系とは
http://
▽天正の大洪水と木曽川治水史 〜羽島・羽栗(葉栗)という地名について
http://
...
|
|
|
|
コメント(7)
本文中に、岐阜新聞の記事を追記しました。
この記事で注目すべきは以下の地名に関して、
> 中央に中島郡の孤島があり、その南に日置、津島、戸田、長島、枇杷島などの数島が碁石のように点々とし、また長良河口に東、西、中などの六つの島があり、今の金華山の辺に岐阜山と注し、その西に磯島などを描いて、濃尾地方が広漠とした海湾であったことを示している
この地図からは、津島、枇杷島、飛島、沖之島など、「島」のつく地名がかつての川中島だったことが一目瞭然です。
私は最初、岐阜の「羽島」もそうなんだと勝手に思っていましたが、だいぶ後になってからそれは合併による地名だと気づきました...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=34401775&comm_id=3180326
この地図は、伊吹山と本宮山と猿投山の頂上から眺めて描かれたのではないかと想像できます。
地図の信憑性についても、昭和34年の伊勢湾台風時に水没した水際線上に貝塚などの縄文遺跡が分布するため、やはり縄文海進と重なるようです...
この記事で注目すべきは以下の地名に関して、
> 中央に中島郡の孤島があり、その南に日置、津島、戸田、長島、枇杷島などの数島が碁石のように点々とし、また長良河口に東、西、中などの六つの島があり、今の金華山の辺に岐阜山と注し、その西に磯島などを描いて、濃尾地方が広漠とした海湾であったことを示している
この地図からは、津島、枇杷島、飛島、沖之島など、「島」のつく地名がかつての川中島だったことが一目瞭然です。
私は最初、岐阜の「羽島」もそうなんだと勝手に思っていましたが、だいぶ後になってからそれは合併による地名だと気づきました...
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=34401775&comm_id=3180326
この地図は、伊吹山と本宮山と猿投山の頂上から眺めて描かれたのではないかと想像できます。
地図の信憑性についても、昭和34年の伊勢湾台風時に水没した水際線上に貝塚などの縄文遺跡が分布するため、やはり縄文海進と重なるようです...
> もとあきさん
そうなんですよ〜
私も温暖化問題が叫ばれ始めたとき、この地図のことを思い出しました。
これは過去のものではなく、近未来予想図として現代から未来に向かって生き続けていると。
だから現代社会のあらゆる問題のヒントともなり得るし、環境問題を扱っている人たちにとっても必見だと思っています。
といった感じで、この地図1枚からいろんな意味で様々な物語を感じ取ることができます。
今あるものがすべてではなく、過去に何度もこのような海進と海退をくり返しながら、先人たちがこのすばらしい大地を築き上げてきてくれたわけです。
歴史を語る道具としてだけではなく、このコミュではそんなことも含めて進めていけたらと思います!
そうなんですよ〜
私も温暖化問題が叫ばれ始めたとき、この地図のことを思い出しました。
これは過去のものではなく、近未来予想図として現代から未来に向かって生き続けていると。
だから現代社会のあらゆる問題のヒントともなり得るし、環境問題を扱っている人たちにとっても必見だと思っています。
といった感じで、この地図1枚からいろんな意味で様々な物語を感じ取ることができます。
今あるものがすべてではなく、過去に何度もこのような海進と海退をくり返しながら、先人たちがこのすばらしい大地を築き上げてきてくれたわけです。
歴史を語る道具としてだけではなく、このコミュではそんなことも含めて進めていけたらと思います!
冬至祭の行われる岐阜県揖斐川町の朝鳥明神。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37704304&comm_id=3180326
この朝鳥が、大和建国以前から条里制がはじまる美濃国の測量拠点でした。
朝鳥から見て、冬至の太陽が昇るのは遠く瀬戸であると伝わっており、妙に古墳や古い神社が並んでいるラインを見つけました。
そこには尾張一宮の真清田神社から三河一宮の砥鹿神社へいたるラインがしっかりと感じ取れます。
なぜこの場所が神聖視されたのか、あるいは別の重要な聖地から見て何らかの重要なポイントだったと考えつつここ数年見てきました。
それが昨年、尾張氏の拠点である東谷山(山頂には尾張戸神社と古墳があり、麓には白鳥塚古墳がある)から見て、冬至の太陽は猿投山から昇り、夏至の太陽は伊吹山の方へ沈むことに気づきました。
これでやっとすっきりしたのですが、朝鳥と小牧の岩崎山(熊野神社)と東谷山と猿投山は一直線につながることを地図上でしっかり確かめることができました。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1252320323&owner_id=4857509
ということはこの地図が作られた8世紀、測量地点の拠点ともいえるこの猿投山にて尾張国の地図が作られた可能性はますます高くなる。
それゆえの朝鳥であり、どちらがというより相互にレイラインとしての機能をはたしていたんだと思います。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37704304&comm_id=3180326
この朝鳥が、大和建国以前から条里制がはじまる美濃国の測量拠点でした。
朝鳥から見て、冬至の太陽が昇るのは遠く瀬戸であると伝わっており、妙に古墳や古い神社が並んでいるラインを見つけました。
そこには尾張一宮の真清田神社から三河一宮の砥鹿神社へいたるラインがしっかりと感じ取れます。
なぜこの場所が神聖視されたのか、あるいは別の重要な聖地から見て何らかの重要なポイントだったと考えつつここ数年見てきました。
それが昨年、尾張氏の拠点である東谷山(山頂には尾張戸神社と古墳があり、麓には白鳥塚古墳がある)から見て、冬至の太陽は猿投山から昇り、夏至の太陽は伊吹山の方へ沈むことに気づきました。
これでやっとすっきりしたのですが、朝鳥と小牧の岩崎山(熊野神社)と東谷山と猿投山は一直線につながることを地図上でしっかり確かめることができました。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1252320323&owner_id=4857509
ということはこの地図が作られた8世紀、測量地点の拠点ともいえるこの猿投山にて尾張国の地図が作られた可能性はますます高くなる。
それゆえの朝鳥であり、どちらがというより相互にレイラインとしての機能をはたしていたんだと思います。
木曽川沿岸の情報誌として無料配布されている『かわなみ通信』に、岐阜大の教授が地質学調査の上で「旧木曽川の流れは美濃加茂から大きく北上し、長良川を飲み込む形で関市から山県市(高富)まで流れ込んでいた。ある時期の木曽川は、長良川や鳥羽川沿い、場合によっては伊自良川沿いにまで延びていた可能性が考えられる。」といった記事が載っておりました。
この地図は、尾張古図の美濃にある古代の河口域がその後どのように枝分かれして川となっていったのかの大きな手がかりとなりました。
なぜなら、現在の長良川と木曽川の中間域に海岸線の名残りや大河の流れを感じていたからです。
メモとして、以下の書き込みをこちらにも残しておきたいと思います...
コミュ『◆日本の神話と古代史と日本文化』のトピック
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=508139&page=12&id=47035958
コメント[222] 2009年11月21日 14:19
∞音∞ a.k.a. 風*月
>>216 六次元さん
> 出雲氏族は自分たちの祖先の名を変えて、御利益のある神様として全国の神社に祀っています
> 「伊・加賀・色雄(松江市加賀の者=佐太大神)」を、天香具(加賀)山、菊(加賀)利などに変えています
カガ、カグ、カゴから以下、気になるところを書いておきます。
天香香背男(カガセオ)は尾張族の祖先ともいわれ、稲沢市にある国府宮こと尾張大国霊神社の社家は天背男命の子孫を名乗ってます。
宇摩志麻遅命は天香具山命とともに物部の兵を率いて尾張、美濃、越国を平定したとされていますが、尾張氏の初世代(尾張氏の祖)は天火明命=ニギハヤヒの子である天香具山命(天香語山命)=高倉下命であるとしています。
> 天手力男の子孫を称する氏族は存在しません
> 天手力男を佐那神社に祀ったのは、日子坐王(=大田田根子)の孫の曙立王です
以前からご指摘されてる通り、手力雄神社(岐阜市蔵前)から北東方向、清水山の麓にある伊波之西神社(岐阜市岩田)には日子坐命が祀られ、山の中腹には日子坐命の墓がありますね。
> 天手力男も「天・田・力男」であり田神のことですが、これに尊称の「大」「根子」を付ければ、大田根子=大田田根子です
以前からご指摘されてる通り、手力雄神社のある蔵前のすぐ東隣が岐阜市「高田」。
さらに北西方向には、岐阜市「田神」の地名があります。
この田神周辺にはその由来となるような神社も伝承もなく、この地名に関してずっと気になっていたのですが、天手力男=タヂカラオのことだったのかもしれませんね。
そこからすぐ北に金華山があり、その麓である岐阜市長森「岩戸」の地名もやはり天手力男に関係しているのでしょうが、ここにはかつて式内の物部神社がありました。
コメント[223] 2009年11月21日 17:39
六次元
>∞音∞ a.k.a. 風*月 さん
岩戸、田神の地名と、手力雄神社は固まってあります
那加手力雄神社がある那加手力町は、「加賀・み原(各務原)」です
真清田神社は、山県市高木町ー岐阜市高田ー一宮市高田の延長にあります
一宮市高田の南の今伊勢町馬寄には石刀(いわと)神社もあります
山県市高木町から真清田神社ー萩原町高木ー岐阜県海津市平田町高田
の古代ルートがあったのではなかと思います
このラインの高低差はご存じではないでしょうか
(伊勢湾が山県市まで入り込んでいた頃に陸地であったかどうか)
コメント[225] 2009年11月21日 19:06
∞音∞ a.k.a. 風*月
> 六次元さん
なんとその石刀神社の祭神も手力男神なんですよ!
イワトが天の岩戸に結びつくのはわかるんですが、なぜ石に刀の字を当てたのかがまったくの謎なんです。
ちなみに磐座ではなく古墳の上に社殿が建ってます。
山県市から海津市までは古代ルートの可能性が大いにありますね。
濃尾平野はほとんどが海で島々が点在していました。
まずはビジュアル的に一目でわかるので、猿投神社の尾張古図が参考になるかと思います。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29906309&comm_id=3180326
山県市から南進して現在の長良川を越え、金華山東麓の日野へ抜けるとすぐに岐阜市高田に出ます。
日野は谷になっており山の近くで古墳が連続しておりますが、水海道の地名があるようにこのルート上に大河(長良川と木曽川をつなぐような)の流れがあったかもしれません。
手力雄神社の辺りは芋島など島のつく地名が点在しています。
石刀神社や真清田神社まで来ると、中島という大きな陸地となります。
以上
この地図は、尾張古図の美濃にある古代の河口域がその後どのように枝分かれして川となっていったのかの大きな手がかりとなりました。
なぜなら、現在の長良川と木曽川の中間域に海岸線の名残りや大河の流れを感じていたからです。
メモとして、以下の書き込みをこちらにも残しておきたいと思います...
コミュ『◆日本の神話と古代史と日本文化』のトピック
http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=508139&page=12&id=47035958
コメント[222] 2009年11月21日 14:19
∞音∞ a.k.a. 風*月
>>216 六次元さん
> 出雲氏族は自分たちの祖先の名を変えて、御利益のある神様として全国の神社に祀っています
> 「伊・加賀・色雄(松江市加賀の者=佐太大神)」を、天香具(加賀)山、菊(加賀)利などに変えています
カガ、カグ、カゴから以下、気になるところを書いておきます。
天香香背男(カガセオ)は尾張族の祖先ともいわれ、稲沢市にある国府宮こと尾張大国霊神社の社家は天背男命の子孫を名乗ってます。
宇摩志麻遅命は天香具山命とともに物部の兵を率いて尾張、美濃、越国を平定したとされていますが、尾張氏の初世代(尾張氏の祖)は天火明命=ニギハヤヒの子である天香具山命(天香語山命)=高倉下命であるとしています。
> 天手力男の子孫を称する氏族は存在しません
> 天手力男を佐那神社に祀ったのは、日子坐王(=大田田根子)の孫の曙立王です
以前からご指摘されてる通り、手力雄神社(岐阜市蔵前)から北東方向、清水山の麓にある伊波之西神社(岐阜市岩田)には日子坐命が祀られ、山の中腹には日子坐命の墓がありますね。
> 天手力男も「天・田・力男」であり田神のことですが、これに尊称の「大」「根子」を付ければ、大田根子=大田田根子です
以前からご指摘されてる通り、手力雄神社のある蔵前のすぐ東隣が岐阜市「高田」。
さらに北西方向には、岐阜市「田神」の地名があります。
この田神周辺にはその由来となるような神社も伝承もなく、この地名に関してずっと気になっていたのですが、天手力男=タヂカラオのことだったのかもしれませんね。
そこからすぐ北に金華山があり、その麓である岐阜市長森「岩戸」の地名もやはり天手力男に関係しているのでしょうが、ここにはかつて式内の物部神社がありました。
コメント[223] 2009年11月21日 17:39
六次元
>∞音∞ a.k.a. 風*月 さん
岩戸、田神の地名と、手力雄神社は固まってあります
那加手力雄神社がある那加手力町は、「加賀・み原(各務原)」です
真清田神社は、山県市高木町ー岐阜市高田ー一宮市高田の延長にあります
一宮市高田の南の今伊勢町馬寄には石刀(いわと)神社もあります
山県市高木町から真清田神社ー萩原町高木ー岐阜県海津市平田町高田
の古代ルートがあったのではなかと思います
このラインの高低差はご存じではないでしょうか
(伊勢湾が山県市まで入り込んでいた頃に陸地であったかどうか)
コメント[225] 2009年11月21日 19:06
∞音∞ a.k.a. 風*月
> 六次元さん
なんとその石刀神社の祭神も手力男神なんですよ!
イワトが天の岩戸に結びつくのはわかるんですが、なぜ石に刀の字を当てたのかがまったくの謎なんです。
ちなみに磐座ではなく古墳の上に社殿が建ってます。
山県市から海津市までは古代ルートの可能性が大いにありますね。
濃尾平野はほとんどが海で島々が点在していました。
まずはビジュアル的に一目でわかるので、猿投神社の尾張古図が参考になるかと思います。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=29906309&comm_id=3180326
山県市から南進して現在の長良川を越え、金華山東麓の日野へ抜けるとすぐに岐阜市高田に出ます。
日野は谷になっており山の近くで古墳が連続しておりますが、水海道の地名があるようにこのルート上に大河(長良川と木曽川をつなぐような)の流れがあったかもしれません。
手力雄神社の辺りは芋島など島のつく地名が点在しています。
石刀神社や真清田神社まで来ると、中島という大きな陸地となります。
以上
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
飛騨*美濃*尾張∞火と水の調和のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6473人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19251人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人