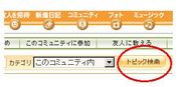ロボット AI ニューラルネットワーク エピソード記憶
----------------------------------------
http://
●前野隆司(まえの たかし、 1962年 - )
慶應義塾大学理工学部機械工学科教授で、専門分野はロボティクス。
<ふゆき氏(http://
受動意識仮説における感覚と評価 2007年02月19日15:35 受動意識仮説とは
前野隆司氏が主張する、受動意識仮説とはどのような仮説であるかについて概略を述べる。
意識とは
意識とは自分が感じることのできる全ての感覚のことである。
脳とは
脳はそれぞれ独立して各々の処理をこなすモジュールから成っている。これをニューラルネットワークと言う。処理内容としては、大きく分けて「知」「情」「意」などがあり、それぞれ自律分散的な処理を行っている。
エピソード記憶とは
エピソード記憶とは、意識がシミュレーションした歴史を記憶すること、またはその記憶自身のことを表す言葉である。さらに、意識はエピソード記憶以外の情報に寄与しない。従って、エピソード記憶が存在しなければ、意識が存在する必要はない。
受動意識仮説とは
受動意識仮説とは、意識を、ニューラルネットワークを制御する大きなシステムとして考えるのではなくて、ニューラルネットワークによって制御される対象であると考える仮説。根拠として、人間の意識が起こす錯覚が、エピソード記憶を行いやすいように加工された結果であるように見えることを挙げている。
受動意識仮説における意識とは
受動意識仮説では、意識はニューラルネットワークによって制御される対象である。従って、自分が感じる全ての感覚は、ニューラルネットワークによってプログラムされた結果である。つまり、意識は意志を持たず、全ての感覚は錯覚であると言える。
受動意識仮説における感覚とは
意識はエピソード記憶以外の情報に寄与しない。受動意識仮説ではこれをさらに拡張して、意識はエピソード記憶の機能を達成するために必要不可欠なものであると考える。さらに、自分が感じる感覚は、自分が物理的に経験した事実に対して評価を与えるための道具であって、エピソード記憶における評価に不可欠なものとする。つまり、ニューラルネットワークがエピソード記憶にタグをつけるために、意識に対して感覚を感じさせているということである。これを正当化する根拠として、エピソード記憶が感覚によるタグをつけないままに記憶し続けていくと、各々の記憶に対して評価ができないだけでなく、どれが重要な情報でどれが重要でない情報か分からないことから、記憶の整理ができなくなって要領オーバーを起こしてしまうであろうということを述べている。
受動意識仮説のまとめ
受動意識仮説では意識をエピソード記憶に記憶させる情報を統合するための装置として再定義した。そして、その統合という操作は、他のニューラルネットワークによって加工された情報を元に行われているにすぎないもので、意識というものは自分を制御できるようなものでなく、逆に制御された情報を受け取り、統合するだけの存在だとした。さらに、その新しく定義された装置としての意識は、自分が感じている感覚としての意識と同値関係で結ばれているとした。つまり、その装置に他のニューラルネットワークが情報を送り、その装置がエピソード記憶にそれを保存する操作と、自分が感覚として感じる意識を同じものであるとしたのである。
考察
受動意識仮説において、感覚(つまり意識)とは、エピソード記憶を評価するものにすぎないことを主張した。これは、僕の感覚と照らし合わせても十分に成立しうることだと思う。明らかに、自分が物事の評価を行いうる情報としてアクセスできる情報は過去の自分が感じたこと以外にない。つまり、感覚というのは、過去の事象を今に生かすことのできる唯一の方法であると考えられる。そして、その感覚というものが自らの意志に反するもの、すなわち、他のニューラルネットワークによって加工された情報にすぎないことも肯定できる。要するに、脳の中の構造として、ニューラルネットワークの全てを把握できるシステムが構成できるはずがないということだ。物理的に不可能であると考えられる。そして、そうのような大きなシステムを考えなかった場合、意識が小さな受動的なシステムで構成されるのは当然である。これは、僕の感覚にも合っている。人間は同時に多くのことを意識して行うことができない。しかし、無意識の動作はあまりに複雑なことを容易に行ってる。その事実から見ても、意識がそんなに大きなシステムでないことは明らかである。ただ、一つだけ納得できないことがある。受動意識仮説では、意識に対して"あたかも自分が意志を持つかのように感じさせる"ことによって、自分の感じる感覚を"エピソード記憶に都合の良いものとしている"と述べている。確かに、自分が主体的にやっていると感じさせた方が、論理が線形になって、分散的なシステムであるニューラルネットワークがそれぞれ別々に判断したことを記憶させるよりコンパクトな情報として時系列データを扱うことができる。しかし、これは「なぜ、それを自分が、今自分が感じているように感じなければならないのか」という疑問に完全に答えられてはいない。つまり、ただ都合の良いように情報を操作して、各ニューラルネットワークが作成した感覚に基づいたタグをつけたものをエピソード記憶に記憶させるだけならば、自分が、この今感じられるような世界を感じる必要性が全く存在しないからだ。それに、結局のところ自分というものが物理的な空間と全く離れた"勘違い空間"にどうやって構成されているのかについて全く答えが出せない。これでは、まだまだ心身二元論を否定するだけの仮説と成り得ないのだ。
物理空間と直交した空間としての意識
ぼくは、物理空間において受動意識仮説を全面的に肯定する。つまり、物理空間における意識はやはりエピソード記憶に記憶させる情報を統合するための装置でしかありえない。あるいは、こう考えている。意識とは、各ニューラルネットワークがエピソード記憶に送る情報が流れる経路の「交点」にすぎない。あるいは、統合する対象としての装置が存在するとすれば、意識とは、その装置の「出力情報」にすぎないと考える。おそらく、装置自身ではない。なぜなら、意識というのは、たぶん何もしないからである。なにかするとおかしい。意識がなにかをするなら、意志があることになってしまう。なにかをしようとしていることになってしまう。そして、それはどうもおかしいと思う。そして同時に、実際にこういう風に見えている世界は、物理的空間にあるなにかがぼくに対して意図して見させることはできないはずである。もしできるとすれば、それはその"対象"というものを延々と考えることになり、なにも解決しない。いや、解決しないのではなくて、納得していないだけなのだと思う。物理的空間における物理的な意識というのは、おそらく単なる点である。そして、物理空間から離れてしまった自分の感覚というのは、物理空間に対して単なる同値関係が存在するだけなのだと思う。そして、それは物理空間と全く異なる空間のはずである。要するに、エピソード記憶に記憶させる情報を送ることと同値関係で結ばれた、物理空間に直交した空間を考えないと、全く解決しないのだと思う。そして、その空間自体が、自分が実際に感じている意識である。もう一つ言いたいのは、この物理空間とは異なった空間は、勝手に作られてしまう性質のものであるはずだということです。エピソード記憶に情報を送ると勝手にこの空間ができてしまうはずです。従って、コペルニクス的な発想の転換は、実はここになぜか存在してしまう仮想空間に対して行われるべきなのではないかと考えます。
以上。
----------------------------------------
http://
●前野隆司(まえの たかし、 1962年 - )
慶應義塾大学理工学部機械工学科教授で、専門分野はロボティクス。
<ふゆき氏(http://
受動意識仮説における感覚と評価 2007年02月19日15:35 受動意識仮説とは
前野隆司氏が主張する、受動意識仮説とはどのような仮説であるかについて概略を述べる。
意識とは
意識とは自分が感じることのできる全ての感覚のことである。
脳とは
脳はそれぞれ独立して各々の処理をこなすモジュールから成っている。これをニューラルネットワークと言う。処理内容としては、大きく分けて「知」「情」「意」などがあり、それぞれ自律分散的な処理を行っている。
エピソード記憶とは
エピソード記憶とは、意識がシミュレーションした歴史を記憶すること、またはその記憶自身のことを表す言葉である。さらに、意識はエピソード記憶以外の情報に寄与しない。従って、エピソード記憶が存在しなければ、意識が存在する必要はない。
受動意識仮説とは
受動意識仮説とは、意識を、ニューラルネットワークを制御する大きなシステムとして考えるのではなくて、ニューラルネットワークによって制御される対象であると考える仮説。根拠として、人間の意識が起こす錯覚が、エピソード記憶を行いやすいように加工された結果であるように見えることを挙げている。
受動意識仮説における意識とは
受動意識仮説では、意識はニューラルネットワークによって制御される対象である。従って、自分が感じる全ての感覚は、ニューラルネットワークによってプログラムされた結果である。つまり、意識は意志を持たず、全ての感覚は錯覚であると言える。
受動意識仮説における感覚とは
意識はエピソード記憶以外の情報に寄与しない。受動意識仮説ではこれをさらに拡張して、意識はエピソード記憶の機能を達成するために必要不可欠なものであると考える。さらに、自分が感じる感覚は、自分が物理的に経験した事実に対して評価を与えるための道具であって、エピソード記憶における評価に不可欠なものとする。つまり、ニューラルネットワークがエピソード記憶にタグをつけるために、意識に対して感覚を感じさせているということである。これを正当化する根拠として、エピソード記憶が感覚によるタグをつけないままに記憶し続けていくと、各々の記憶に対して評価ができないだけでなく、どれが重要な情報でどれが重要でない情報か分からないことから、記憶の整理ができなくなって要領オーバーを起こしてしまうであろうということを述べている。
受動意識仮説のまとめ
受動意識仮説では意識をエピソード記憶に記憶させる情報を統合するための装置として再定義した。そして、その統合という操作は、他のニューラルネットワークによって加工された情報を元に行われているにすぎないもので、意識というものは自分を制御できるようなものでなく、逆に制御された情報を受け取り、統合するだけの存在だとした。さらに、その新しく定義された装置としての意識は、自分が感じている感覚としての意識と同値関係で結ばれているとした。つまり、その装置に他のニューラルネットワークが情報を送り、その装置がエピソード記憶にそれを保存する操作と、自分が感覚として感じる意識を同じものであるとしたのである。
考察
受動意識仮説において、感覚(つまり意識)とは、エピソード記憶を評価するものにすぎないことを主張した。これは、僕の感覚と照らし合わせても十分に成立しうることだと思う。明らかに、自分が物事の評価を行いうる情報としてアクセスできる情報は過去の自分が感じたこと以外にない。つまり、感覚というのは、過去の事象を今に生かすことのできる唯一の方法であると考えられる。そして、その感覚というものが自らの意志に反するもの、すなわち、他のニューラルネットワークによって加工された情報にすぎないことも肯定できる。要するに、脳の中の構造として、ニューラルネットワークの全てを把握できるシステムが構成できるはずがないということだ。物理的に不可能であると考えられる。そして、そうのような大きなシステムを考えなかった場合、意識が小さな受動的なシステムで構成されるのは当然である。これは、僕の感覚にも合っている。人間は同時に多くのことを意識して行うことができない。しかし、無意識の動作はあまりに複雑なことを容易に行ってる。その事実から見ても、意識がそんなに大きなシステムでないことは明らかである。ただ、一つだけ納得できないことがある。受動意識仮説では、意識に対して"あたかも自分が意志を持つかのように感じさせる"ことによって、自分の感じる感覚を"エピソード記憶に都合の良いものとしている"と述べている。確かに、自分が主体的にやっていると感じさせた方が、論理が線形になって、分散的なシステムであるニューラルネットワークがそれぞれ別々に判断したことを記憶させるよりコンパクトな情報として時系列データを扱うことができる。しかし、これは「なぜ、それを自分が、今自分が感じているように感じなければならないのか」という疑問に完全に答えられてはいない。つまり、ただ都合の良いように情報を操作して、各ニューラルネットワークが作成した感覚に基づいたタグをつけたものをエピソード記憶に記憶させるだけならば、自分が、この今感じられるような世界を感じる必要性が全く存在しないからだ。それに、結局のところ自分というものが物理的な空間と全く離れた"勘違い空間"にどうやって構成されているのかについて全く答えが出せない。これでは、まだまだ心身二元論を否定するだけの仮説と成り得ないのだ。
物理空間と直交した空間としての意識
ぼくは、物理空間において受動意識仮説を全面的に肯定する。つまり、物理空間における意識はやはりエピソード記憶に記憶させる情報を統合するための装置でしかありえない。あるいは、こう考えている。意識とは、各ニューラルネットワークがエピソード記憶に送る情報が流れる経路の「交点」にすぎない。あるいは、統合する対象としての装置が存在するとすれば、意識とは、その装置の「出力情報」にすぎないと考える。おそらく、装置自身ではない。なぜなら、意識というのは、たぶん何もしないからである。なにかするとおかしい。意識がなにかをするなら、意志があることになってしまう。なにかをしようとしていることになってしまう。そして、それはどうもおかしいと思う。そして同時に、実際にこういう風に見えている世界は、物理的空間にあるなにかがぼくに対して意図して見させることはできないはずである。もしできるとすれば、それはその"対象"というものを延々と考えることになり、なにも解決しない。いや、解決しないのではなくて、納得していないだけなのだと思う。物理的空間における物理的な意識というのは、おそらく単なる点である。そして、物理空間から離れてしまった自分の感覚というのは、物理空間に対して単なる同値関係が存在するだけなのだと思う。そして、それは物理空間と全く異なる空間のはずである。要するに、エピソード記憶に記憶させる情報を送ることと同値関係で結ばれた、物理空間に直交した空間を考えないと、全く解決しないのだと思う。そして、その空間自体が、自分が実際に感じている意識である。もう一つ言いたいのは、この物理空間とは異なった空間は、勝手に作られてしまう性質のものであるはずだということです。エピソード記憶に情報を送ると勝手にこの空間ができてしまうはずです。従って、コペルニクス的な発想の転換は、実はここになぜか存在してしまう仮想空間に対して行われるべきなのではないかと考えます。
以上。
|
|
|
|
|
|
|
|
トピック検索 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
トピック検索のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90013人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208277人
- 3位
- 暮らしを楽しむ
- 75469人