2009年 1つ目のトピックになります。
前々から考えていたけどやらなかったリレー小説をやってみようと思い、テストということでお試しな感じにやってみたいと思います。
不評だったときにすぐやめられるということもあるのでまずはテストですテスト。都合のいいのが管理人です。視線が痛いけど気にしません。
他にも参加者さんが作ったリレートピックもありますのでそちらも平行してどうぞーー!
************************************
管理人が考えたルールを説明します。
リレー小説とは、コミュニティ参加者全員で文章を繋げて1つの小説を作っていくものです。
キャラクター・舞台・ストーリー 全ては皆さんの力で紡いでいく。結末はどうなるかわからない。あなたも参加してみませんか?
■投稿はコミュ参加者なら誰でもいつでも可能です。
■トピックのコメントへ続きを書くようにお願いします
■こちらのトピックはストーリーだけで進行させて頂きます
■投稿時の字数制限は設けませんが最低1行。最大で1000文字程度に収めていただけると、次の人が書き易いと思いますので、そのぐらいを目安にして下さい。
■連投は不可とします。一度投稿されたかたは、間に必ず1人入れて書き込みを行って下さい。
■管理人も含め、文章構成の上手さには人により大幅に違いがあると思います。素人もいれば、実践的に使用してるような方もいるかもしれません。そのあたりを考慮しつつ、できるだけ全員が楽しめるようにやっていきたいと思います。不満等を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが何卒ご協力をお願いします。
それでは僭越ながらトップバッターを勤めさせて頂きます。文才はないです。ひどいです。管理人がこれ以降、カキコミするかは不明です それでもまったりいきましょう。
管理人は長文きついので最初の部分しか書きませんが気にしないで進めて下さい(
キャラクターや舞台設定。雑談・ご意見などは下記URLでお願いします(参加する方は一読を)
http://
*************************************
12月
雪の降るこの街に私、「詩野 千早(しの ちはや)」は帰ってきた。
長時間電車に揺られ、目的地である駅。雪見町のホームへと降り立つ。
「んーーーっ・・・・・・・はぁ、寒い」
大きな伸びをひとつ。そして白い息をみながら一言。
電車から降りた千早はまっすぐ改札口へと向かい駅の外へと出た。
深々と降り続ける雪をよそに、昔とはまったく違うネオンに彩られた光景に目を向けながら街中へと歩き出す。
「えーと。こっちでいいのかな」
これから向かう先は決まっていた。兄からもらったメモを取り出す。
「・・・・・・・」
メモを見た瞬間、千早の足が止まり頭を抱える。
兄に頼った自分がバカだったと後悔する。次に会った時は仕返ししてやろうと強く胸に誓う千早だった。
一抹の不安を抱えながらも、かろうじて読み取れるその地図らしきものをみながら再び歩き出す。
そして
迷った。
「うそぉーーーーーー!」
寒空の下、千早の声だけが響くのであった。
前々から考えていたけどやらなかったリレー小説をやってみようと思い、テストということでお試しな感じにやってみたいと思います。
不評だったときにすぐやめられるということもあるのでまずはテストですテスト。都合のいいのが管理人です。視線が痛いけど気にしません。
他にも参加者さんが作ったリレートピックもありますのでそちらも平行してどうぞーー!
************************************
管理人が考えたルールを説明します。
リレー小説とは、コミュニティ参加者全員で文章を繋げて1つの小説を作っていくものです。
キャラクター・舞台・ストーリー 全ては皆さんの力で紡いでいく。結末はどうなるかわからない。あなたも参加してみませんか?
■投稿はコミュ参加者なら誰でもいつでも可能です。
■トピックのコメントへ続きを書くようにお願いします
■こちらのトピックはストーリーだけで進行させて頂きます
■投稿時の字数制限は設けませんが最低1行。最大で1000文字程度に収めていただけると、次の人が書き易いと思いますので、そのぐらいを目安にして下さい。
■連投は不可とします。一度投稿されたかたは、間に必ず1人入れて書き込みを行って下さい。
■管理人も含め、文章構成の上手さには人により大幅に違いがあると思います。素人もいれば、実践的に使用してるような方もいるかもしれません。そのあたりを考慮しつつ、できるだけ全員が楽しめるようにやっていきたいと思います。不満等を持つ方もいらっしゃるかもしれませんが何卒ご協力をお願いします。
それでは僭越ながらトップバッターを勤めさせて頂きます。文才はないです。ひどいです。管理人がこれ以降、カキコミするかは不明です それでもまったりいきましょう。
管理人は長文きついので最初の部分しか書きませんが気にしないで進めて下さい(
キャラクターや舞台設定。雑談・ご意見などは下記URLでお願いします(参加する方は一読を)
http://
*************************************
12月
雪の降るこの街に私、「詩野 千早(しの ちはや)」は帰ってきた。
長時間電車に揺られ、目的地である駅。雪見町のホームへと降り立つ。
「んーーーっ・・・・・・・はぁ、寒い」
大きな伸びをひとつ。そして白い息をみながら一言。
電車から降りた千早はまっすぐ改札口へと向かい駅の外へと出た。
深々と降り続ける雪をよそに、昔とはまったく違うネオンに彩られた光景に目を向けながら街中へと歩き出す。
「えーと。こっちでいいのかな」
これから向かう先は決まっていた。兄からもらったメモを取り出す。
「・・・・・・・」
メモを見た瞬間、千早の足が止まり頭を抱える。
兄に頼った自分がバカだったと後悔する。次に会った時は仕返ししてやろうと強く胸に誓う千早だった。
一抹の不安を抱えながらも、かろうじて読み取れるその地図らしきものをみながら再び歩き出す。
そして
迷った。
「うそぉーーーーーー!」
寒空の下、千早の声だけが響くのであった。
|
|
|
|
コメント(22)
続きは、コメントにかいていくのですか?
ということで、リレー小説大賛成なので、続き書きます
-------
しかし、叫んでいても始まらない。
(足跡が残っているわけだから、ある程度は戻れるはずだ!!!)
ソウ考えて、きびすを返しもと来た道を戻り始めた。
が、しかし、5分もしないうちに、千早は足元を見て後悔し始めた、
(雪で、足跡が消えている・・・・・)
そう、しんしんと降る雪が、自分の足跡をきれいに消し去っていたのだ。
そして、気がついて周りを見渡すと見知らぬ路地裏の小さな空き地にたどり着いていた。
(ここはどこだ?)
しかも、そこは行き止まりで、電柱にある、小さな電灯が1つついているだけで、後は雪が降り積もって
いるだけだった
携帯電話のGPS機能を確認しようと携帯のディスプレイを見たが、電波の届かないところにいるせいか、GPS機能が使えないことがディスプレイに表示されていた。
「んーーーーーーーーーー、どうしたらいいんだろう?」
誰に聞かせるわけも無く、今の自分の心境を声を出して言ってみた。
「・・・・・・・」
(誰も返事なんてするわけないか・・・)
そんなことを考えて途方にくれていると、いつの間にか、電柱の下の電灯に照らされた場所に
人が立っていた。
(あれっ? いつの間に人が?)
千早の場所からでは、顔は確認できないが、長い黒髪を腰の辺りまで伸ばしているのは、わかった。
--enD--
ということで、リレー小説大賛成なので、続き書きます
-------
しかし、叫んでいても始まらない。
(足跡が残っているわけだから、ある程度は戻れるはずだ!!!)
ソウ考えて、きびすを返しもと来た道を戻り始めた。
が、しかし、5分もしないうちに、千早は足元を見て後悔し始めた、
(雪で、足跡が消えている・・・・・)
そう、しんしんと降る雪が、自分の足跡をきれいに消し去っていたのだ。
そして、気がついて周りを見渡すと見知らぬ路地裏の小さな空き地にたどり着いていた。
(ここはどこだ?)
しかも、そこは行き止まりで、電柱にある、小さな電灯が1つついているだけで、後は雪が降り積もって
いるだけだった
携帯電話のGPS機能を確認しようと携帯のディスプレイを見たが、電波の届かないところにいるせいか、GPS機能が使えないことがディスプレイに表示されていた。
「んーーーーーーーーーー、どうしたらいいんだろう?」
誰に聞かせるわけも無く、今の自分の心境を声を出して言ってみた。
「・・・・・・・」
(誰も返事なんてするわけないか・・・)
そんなことを考えて途方にくれていると、いつの間にか、電柱の下の電灯に照らされた場所に
人が立っていた。
(あれっ? いつの間に人が?)
千早の場所からでは、顔は確認できないが、長い黒髪を腰の辺りまで伸ばしているのは、わかった。
--enD--
勢い良く声をかけた千早。
しかし相手はまったく気がついていないようだった。
致し方なくさらに近くへと近寄っていくと・・・
その髪の長い女性の足元にはおびただしいほどの真っ赤な血が・・・・
「ええッ!!?・・・血ッ!?」
雪の上に広がるソレをみた千早は思わず大きな声を上げた。その声に反応して相手の女性も驚きの声を上げる
「きゃあッ!!血?血どこですかーーーッ!?血ッ ちーーーーー!」
ドサドサッ
半分パニック状態の様な驚きで手に持っていた荷物が地面へと散らばる。
そこで彼女の落としたものをみた千早は自分の間違いに気付く。
「ああ!画材道具・・・・なーんだ絵の具かぁ」
一人で勘違いをして相手を驚かせ自己解決で納得して頷いてる千早。
一報、急に後ろから血などと叫ばれ画材道具を落としパニックに陥いっている女性。
なんともシュールなこの二人の光景に、寒さはより一層増すのであった。
彼女の住んでいる部屋はそこから5分とかからないところにあった。
表札には“Asano”の文字が見えたような気がした。
「どうぞ上がってください。ちょっとちらかってますけど……」
一足先に入った彼女は、画材を持ったまま暖房のスイッチを入れてお湯を沸かす準備をしながらそう言った。
(荷物おろせばいいのに……)
ふとそんなことを思ったが、なんだかタイミングを失った千早はその言葉に甘えて部屋の中に入った。
見渡せばいわゆるワンルーム。壁はすべて本棚で隠され、窓際にはイーゼルやら絵具やら彼女の職業を思わせるものが整然と置かれていた。
「画家さん、なんですか?」
「えっ? あぁ・・・・・・まぁ、そんなところです」
千早の質問に、彼女は驚いたように、それでも少しはにかんで笑った。
しばらくしてやかん片手にやってきた彼女は、ようやく荷物を下ろすと「コーヒーしかないんですけど……」と言ってインスタントのコーヒーを入れ始めた。
「お名前、聞いてもいいですか?」
「あぁ・・・・・・みはるです。浅野美悠。えーと・・・・・」
「あたしは千早。詩野千早って言います」
とりあえず自己紹介をして、入れてもらったコーヒーを受け取り・・・・・・そこから会話が途切れてしまった。
雪が降っている時は静かだ、というが、その部屋にはまさに静寂だけが支配していた。
「えーと……」「あの……」
お互い静寂に耐えられなくなったのか、ほぼ同時に声を発した。
「ごめんなさい・・・・先にどうぞ」
「あ、じゃあ……あの地図、目的地はどこなんですか?」
行き先が分かれば案内もできると思うんですけど・・・・・・
言われて、あっと気づく。
確かに訳の分からないメモを見せるよりも、そちらを知らせた方が分かる可能性が高いはずなのに。
「そうですよね・・・・・・すみません、気が回らなくて」
苦笑いでそういうと、あたしは行き先を話し始めた。
表札には“Asano”の文字が見えたような気がした。
「どうぞ上がってください。ちょっとちらかってますけど……」
一足先に入った彼女は、画材を持ったまま暖房のスイッチを入れてお湯を沸かす準備をしながらそう言った。
(荷物おろせばいいのに……)
ふとそんなことを思ったが、なんだかタイミングを失った千早はその言葉に甘えて部屋の中に入った。
見渡せばいわゆるワンルーム。壁はすべて本棚で隠され、窓際にはイーゼルやら絵具やら彼女の職業を思わせるものが整然と置かれていた。
「画家さん、なんですか?」
「えっ? あぁ・・・・・・まぁ、そんなところです」
千早の質問に、彼女は驚いたように、それでも少しはにかんで笑った。
しばらくしてやかん片手にやってきた彼女は、ようやく荷物を下ろすと「コーヒーしかないんですけど……」と言ってインスタントのコーヒーを入れ始めた。
「お名前、聞いてもいいですか?」
「あぁ・・・・・・みはるです。浅野美悠。えーと・・・・・」
「あたしは千早。詩野千早って言います」
とりあえず自己紹介をして、入れてもらったコーヒーを受け取り・・・・・・そこから会話が途切れてしまった。
雪が降っている時は静かだ、というが、その部屋にはまさに静寂だけが支配していた。
「えーと……」「あの……」
お互い静寂に耐えられなくなったのか、ほぼ同時に声を発した。
「ごめんなさい・・・・先にどうぞ」
「あ、じゃあ……あの地図、目的地はどこなんですか?」
行き先が分かれば案内もできると思うんですけど・・・・・・
言われて、あっと気づく。
確かに訳の分からないメモを見せるよりも、そちらを知らせた方が分かる可能性が高いはずなのに。
「そうですよね・・・・・・すみません、気が回らなくて」
苦笑いでそういうと、あたしは行き先を話し始めた。
「実は、おばあちゃ・・・いえ、祖母が以前住んでいた家を探しているんです。昔、一緒に住んでいたことがあったんですが・・・」
千早のぎこちない敬語を聞いた美悠はクスっと笑う
「変に敬語を使わなくてもいいですよ。それでその祖母さんの住所はわからないんですよね」
「あう。そう言ってもらえると助かります・・・」
普段から敬語を使い慣れていない千早にとって、美悠の気遣いは非常に助かる申し出だった。
照れ隠しにコーヒーを飲もうとカップを口に運ぶ。
「あちっ!」
しかし、まだ入れたばかりのコーヒーは熱く、千早は自分が猫舌なのを忘れていた。
「大丈夫ですか!?」
慌てて近寄る美悠。
「はは・・・大丈夫です。大丈夫。それより話を続きをっ」
自分の行動の恥ずかしさにいたたまれなくなった千早は話を進めることにした。
「えと、それで今度こっちに引越しをすることになったんです。おばあちゃんも今は病院に入院しちゃって、誰も住んでないから」
「そうですか。何か、家の近くに目印になるようなものはあったりしますか?」
千早の言葉を聞いた美悠は、千早の家庭環境が少し特殊なのではないかと直感的に感じていた。
「うーん。あたしもずいぶん昔のことなのでよく覚えてないんですよね・・・」
二人でどうしたものかと思案を巡らせて悩む。
いい案が浮かばず、行き詰っていたところで千早の携帯が鳴る。
手に取った千早の携帯のディスプレイに表示される名前と番号は千早の兄からだった。
千早のぎこちない敬語を聞いた美悠はクスっと笑う
「変に敬語を使わなくてもいいですよ。それでその祖母さんの住所はわからないんですよね」
「あう。そう言ってもらえると助かります・・・」
普段から敬語を使い慣れていない千早にとって、美悠の気遣いは非常に助かる申し出だった。
照れ隠しにコーヒーを飲もうとカップを口に運ぶ。
「あちっ!」
しかし、まだ入れたばかりのコーヒーは熱く、千早は自分が猫舌なのを忘れていた。
「大丈夫ですか!?」
慌てて近寄る美悠。
「はは・・・大丈夫です。大丈夫。それより話を続きをっ」
自分の行動の恥ずかしさにいたたまれなくなった千早は話を進めることにした。
「えと、それで今度こっちに引越しをすることになったんです。おばあちゃんも今は病院に入院しちゃって、誰も住んでないから」
「そうですか。何か、家の近くに目印になるようなものはあったりしますか?」
千早の言葉を聞いた美悠は、千早の家庭環境が少し特殊なのではないかと直感的に感じていた。
「うーん。あたしもずいぶん昔のことなのでよく覚えてないんですよね・・・」
二人でどうしたものかと思案を巡らせて悩む。
いい案が浮かばず、行き詰っていたところで千早の携帯が鳴る。
手に取った千早の携帯のディスプレイに表示される名前と番号は千早の兄からだった。
半ば反射的に通話ボタンを押してしまい、美悠の顔を伺う。
彼女は微笑みながらどうぞと口を動かす。
そんな美悠の気遣いに尊敬の念を抱きながら、兄からですと千早も口だけを動かして携帯を耳にあてる。
「いまどこにいる?」
お気楽な声が聞こえてくる。外にいるのだろう、アナウンスの声がかすかに聞こえる。
「いまどこにいる?もしかしてもう着いた?」
なぜか安心したような声で話す兄に千早は苛立ちを覚えながら答える。
「そんなわけないじゃん!あんな『考えるな、感じろ』って書いてあるだけの紙に何の価値があるのよ!」
「片方だけじゃダメだったか・・・」
「何よ片方って?メモは一枚しか無かったよ?」
そう言いつつ千早は持ってきた荷物に目をやる。
「あん?メモは一枚でいいんよ。だってあれは『地図はお前の頭ん中にある』って伝えたかっただけ。片方ってのは地図の話な。」
「『考えるな、感じろ』ってそういう意味なのか・・・あれ?でも片方の地図が千早の頭の中ってことはひょっとして・・・」
携帯の受話音量が大きいせいか、千早の兄の話し声がかすかではあるが聞こえたのだろう、美悠が独り言のように呟いた。
千早は会話を聞かれた恥ずかしさと、美悠の『ひょっとして・・・』の先が知りたくて黙り込む。しかしその答えはすぐそばからやってきた。
「まぁ、オレもあんまり覚えてないんだけどな。」
そう、うれしそうに呟く兄に対し千早は言葉がでない。そして兄は続ける。
「だからオレも来ちゃった。何か思い出せそうな気がして。」
千早は不安な表情で美悠を見つめる。美悠は笑顔でそれに応える。
雪だけがその表情をかえることなく、静かに降り続けている。
彼女は微笑みながらどうぞと口を動かす。
そんな美悠の気遣いに尊敬の念を抱きながら、兄からですと千早も口だけを動かして携帯を耳にあてる。
「いまどこにいる?」
お気楽な声が聞こえてくる。外にいるのだろう、アナウンスの声がかすかに聞こえる。
「いまどこにいる?もしかしてもう着いた?」
なぜか安心したような声で話す兄に千早は苛立ちを覚えながら答える。
「そんなわけないじゃん!あんな『考えるな、感じろ』って書いてあるだけの紙に何の価値があるのよ!」
「片方だけじゃダメだったか・・・」
「何よ片方って?メモは一枚しか無かったよ?」
そう言いつつ千早は持ってきた荷物に目をやる。
「あん?メモは一枚でいいんよ。だってあれは『地図はお前の頭ん中にある』って伝えたかっただけ。片方ってのは地図の話な。」
「『考えるな、感じろ』ってそういう意味なのか・・・あれ?でも片方の地図が千早の頭の中ってことはひょっとして・・・」
携帯の受話音量が大きいせいか、千早の兄の話し声がかすかではあるが聞こえたのだろう、美悠が独り言のように呟いた。
千早は会話を聞かれた恥ずかしさと、美悠の『ひょっとして・・・』の先が知りたくて黙り込む。しかしその答えはすぐそばからやってきた。
「まぁ、オレもあんまり覚えてないんだけどな。」
そう、うれしそうに呟く兄に対し千早は言葉がでない。そして兄は続ける。
「だからオレも来ちゃった。何か思い出せそうな気がして。」
千早は不安な表情で美悠を見つめる。美悠は笑顔でそれに応える。
雪だけがその表情をかえることなく、静かに降り続けている。
それからどのくらい時間が経ったのだろうか。
少なくとも美悠の注いでくれた2杯目のコーヒーが冷めるくらい兄との会話が続いていた。
「あ、やべえ。千早! 携帯の電池切れるわっ まぁお前はお前でなんとかなるだろ。じゃあな」
「え、ちょっとっ! 肝心の話が全然できてないじゃない!まっ・・・プツッ」
「切れた・・・・」
千早の制止も空しく、勝手に電話を切られる。
「これからあたしどうしよう。。」
兄からの着信履歴を眺めながら、途方に暮れる千早だった。
「ま、なんとかなるか。あれ?そういえば美悠さんはどこにいったんだろう」
立ち直りも早かった!
「美悠さーん?」
声を出しても返事は返ってこない。
「おかしいなー。さっきまでここに居たはずなのに」
不審に思った千早は、家の中を探し始めた。
と、言ってもワンルームなので探す場所は少ない。すぐに全てを探し終わってしまう。
「どこいっちゃったんだろ」
千早は、さきほどまで座っていたところに戻ると、冷めたコーヒーを口にして考えるが電話に夢中で心当たりがない。
そんな千早を他所に『ガチャ』というドアの開く音と共に美悠が帰ってきた。
「あら・・・千早さん お電話の方は終わったんですか?」
「美悠さん!どこ行ってたんですか!探しましたよーー!」
そう言ってまだ会って間もない美悠に抱きつく。
「ああうう!ごめんなさい。ちょっとアトリエまで行ってました」
「アトリエ?」
あまり聞いたことのない言葉に思わず聞き返す。
「ええ。アトリエというほど大層なものじゃないんですけど、ここの大家さんが善意で貸してくれた物置が今の私の仕事場なんです。こっちでも描くには描くんですが、やっぱり自室だとあまり引き締まらないので。千早さんも行ってみますか?」
「なるほどー。美悠さんの仕事場ですか!あたしも見てみたいです。是非是非お願いします!」
「それでは行きましょうか」
嬉しいような恥ずかしいような顔をした美悠は千早をアトリエへと招待するのであった。
少なくとも美悠の注いでくれた2杯目のコーヒーが冷めるくらい兄との会話が続いていた。
「あ、やべえ。千早! 携帯の電池切れるわっ まぁお前はお前でなんとかなるだろ。じゃあな」
「え、ちょっとっ! 肝心の話が全然できてないじゃない!まっ・・・プツッ」
「切れた・・・・」
千早の制止も空しく、勝手に電話を切られる。
「これからあたしどうしよう。。」
兄からの着信履歴を眺めながら、途方に暮れる千早だった。
「ま、なんとかなるか。あれ?そういえば美悠さんはどこにいったんだろう」
立ち直りも早かった!
「美悠さーん?」
声を出しても返事は返ってこない。
「おかしいなー。さっきまでここに居たはずなのに」
不審に思った千早は、家の中を探し始めた。
と、言ってもワンルームなので探す場所は少ない。すぐに全てを探し終わってしまう。
「どこいっちゃったんだろ」
千早は、さきほどまで座っていたところに戻ると、冷めたコーヒーを口にして考えるが電話に夢中で心当たりがない。
そんな千早を他所に『ガチャ』というドアの開く音と共に美悠が帰ってきた。
「あら・・・千早さん お電話の方は終わったんですか?」
「美悠さん!どこ行ってたんですか!探しましたよーー!」
そう言ってまだ会って間もない美悠に抱きつく。
「ああうう!ごめんなさい。ちょっとアトリエまで行ってました」
「アトリエ?」
あまり聞いたことのない言葉に思わず聞き返す。
「ええ。アトリエというほど大層なものじゃないんですけど、ここの大家さんが善意で貸してくれた物置が今の私の仕事場なんです。こっちでも描くには描くんですが、やっぱり自室だとあまり引き締まらないので。千早さんも行ってみますか?」
「なるほどー。美悠さんの仕事場ですか!あたしも見てみたいです。是非是非お願いします!」
「それでは行きましょうか」
嬉しいような恥ずかしいような顔をした美悠は千早をアトリエへと招待するのであった。
「美悠さんって、普段は何をしているの?」
喉の奥まで出掛かったその疑問を、千早は自制した。モデル足るもの唇ですら安易に動かすことは慎むべきだと、木炭を握った瞬間から一言も喋らない美悠の姿を見て感じていた。またその言葉が、勉強中の画家の生活を支える経済的な事情を暗に聞き出す意図をも含んでしまっていることにも気付いていた。そんなことは自分得意の想像力に委ねておけば良い。千早はそう思い込むことにした。
「美悠さんって、いくつ?」
「絵を描き始めてどれくらい?」
「出身は何処?」
しかし、片膝を抱えながら千早は、選んだ言葉全てが喉の奥にあるダムサイトのような建造物に引っ掛かって、外に流れ出していかない状態をもどかしく思った。慎重に選び抜いたどの言葉も、無自覚の内に相手の不信感を買うきっかけを孕んでいやしまいかと疑心暗鬼になっていた。恐らくは口にしないであろう言葉達の為に、こんなに頭を悩ませたのは初めての経験だった。
同時に、ダムサイトが放水するかの如く、その言葉達が文字通り堰を切り、一斉に外へ流れ出すことが恐ろしかった。
その言葉を耳にした時、美悠は案外にもすんなりと答えてくれるかも知れない。しかし、そうでなければ?
彼女は怪訝な顔をするだろうか。
彼女は蔑んだ目であたしを一瞥するだろうか。
―嗚呼、何故あたしはこんなに緊張しているのだろうか?
答えはキャンバスの向こう側にあった。これが「気迫」というやつか、と千早は思った。
キャンパスに向きあう黒髪の画家が、上段に真剣を構えた武士に見えた。元来割とおしゃべりな方の千早ですら、美悠が木炭を手にした瞬間からは金縛りにでもあったかのように静かで、唇は一ミリも動かず静止していた。そして妙な想像を頭の中で駆け巡らせ、1人で被害妄想に陥っていた。永遠とも思える20分間は、本当に永遠と続くような気がして、熱い汗が額から滲み出た。
「あの・・・」
その永遠なる沈黙を破ったのは、意外にも上段構えの武士―もとい美悠だった。
「千早さんって、普段何をしているの?」
喉の奥まで出掛かったその疑問を、千早は自制した。モデル足るもの唇ですら安易に動かすことは慎むべきだと、木炭を握った瞬間から一言も喋らない美悠の姿を見て感じていた。またその言葉が、勉強中の画家の生活を支える経済的な事情を暗に聞き出す意図をも含んでしまっていることにも気付いていた。そんなことは自分得意の想像力に委ねておけば良い。千早はそう思い込むことにした。
「美悠さんって、いくつ?」
「絵を描き始めてどれくらい?」
「出身は何処?」
しかし、片膝を抱えながら千早は、選んだ言葉全てが喉の奥にあるダムサイトのような建造物に引っ掛かって、外に流れ出していかない状態をもどかしく思った。慎重に選び抜いたどの言葉も、無自覚の内に相手の不信感を買うきっかけを孕んでいやしまいかと疑心暗鬼になっていた。恐らくは口にしないであろう言葉達の為に、こんなに頭を悩ませたのは初めての経験だった。
同時に、ダムサイトが放水するかの如く、その言葉達が文字通り堰を切り、一斉に外へ流れ出すことが恐ろしかった。
その言葉を耳にした時、美悠は案外にもすんなりと答えてくれるかも知れない。しかし、そうでなければ?
彼女は怪訝な顔をするだろうか。
彼女は蔑んだ目であたしを一瞥するだろうか。
―嗚呼、何故あたしはこんなに緊張しているのだろうか?
答えはキャンバスの向こう側にあった。これが「気迫」というやつか、と千早は思った。
キャンパスに向きあう黒髪の画家が、上段に真剣を構えた武士に見えた。元来割とおしゃべりな方の千早ですら、美悠が木炭を手にした瞬間からは金縛りにでもあったかのように静かで、唇は一ミリも動かず静止していた。そして妙な想像を頭の中で駆け巡らせ、1人で被害妄想に陥っていた。永遠とも思える20分間は、本当に永遠と続くような気がして、熱い汗が額から滲み出た。
「あの・・・」
その永遠なる沈黙を破ったのは、意外にも上段構えの武士―もとい美悠だった。
「千早さんって、普段何をしているの?」
「なんだじゃないわよ、そっちこそなによ!」
どうしてここがわかったのお前こそなんでここにいるんだ私が訊いてるのおれの質問に答えろようるさいわねだいたいあんたのせいで。
「あ、あのっ」
顔を合わせたとたんに怒涛のごとく文句の応酬を始めた二人の間でおろおろと立ち尽くしていた美悠がついに声を上げた。千早と兄はびくりとして同時に口を閉じる。一瞬でアトリエにはきんと耳が痛くなるほどの静けさが戻ってきた。
「あの、あなたが千早さんのお兄さん……ですか?」
恐る恐るといったふうに美悠が兄に尋ねた。
「あー、はいそうです」
見ず知らずの他人にみっともないところを見せてしまったと反省しているのか兄の態度は幾分しおらしい。
「うちの妹がお世話になったみたいで、申し訳ありません」
「いいえ、こちらこそ……」
千早そっちのけで平身低頭の二人を眉をひそめて眺めやる。兄が頭を下げれば美悠も下げ、それにまた兄が応えて頭を下げ美悠も略。
二人してへこへこしちゃって。
「ほら千早、お前もちゃんとお礼言えよ」
ひとしきり謝罪のしあいは終わったようで兄が目を吊り上げて千早を呼んだ。「ふざけんじゃないよ、なんで私が」と言いかけた千早の頭を兄の大きな手ががしりとつかむ。そのまま力強く下に向かって押された。
「そんな……っ、頭上げてくださいお二人とも」
美悠は千早と兄の二人から頭を下げられて恐縮してしまっている様子だった。
「私のほうこそお急ぎの千早さんにモデルなんか頼んでしまったばっかりに」
「モデルっ?」
突然兄がひっくり返った声を上げた。兄の声に美悠が顔をこわばらせる。兄は千早と美悠を見比べて「も、モデルってヌードか……?」相変わらずの上ずった声でどちらにともなく尋ねた。どこまでも思考回路の同じ兄には頭が下がる。というか兄と考えていることが同じなんて。勘弁してくれ。
「まさかっ、普通に座ってもらってただけですっ」
「……だよな、こんな貧相な……」
「おい」
千早を哀れむように見下ろしてきた兄を剣呑な視線で刺してやった。貧相とは失礼な。否定はできないけど。
千早の殺気を感じたのか小さく悲鳴を上げて体を縮める兄に、美悠がくすっと笑った。「やっぱりご兄弟なんですね」それはどういう意味だ。
「ここは寒いですので、うちに戻りましょうか」
美悠のありがたい申し出に千早と兄は同時にうなずいた。
どうしてここがわかったのお前こそなんでここにいるんだ私が訊いてるのおれの質問に答えろようるさいわねだいたいあんたのせいで。
「あ、あのっ」
顔を合わせたとたんに怒涛のごとく文句の応酬を始めた二人の間でおろおろと立ち尽くしていた美悠がついに声を上げた。千早と兄はびくりとして同時に口を閉じる。一瞬でアトリエにはきんと耳が痛くなるほどの静けさが戻ってきた。
「あの、あなたが千早さんのお兄さん……ですか?」
恐る恐るといったふうに美悠が兄に尋ねた。
「あー、はいそうです」
見ず知らずの他人にみっともないところを見せてしまったと反省しているのか兄の態度は幾分しおらしい。
「うちの妹がお世話になったみたいで、申し訳ありません」
「いいえ、こちらこそ……」
千早そっちのけで平身低頭の二人を眉をひそめて眺めやる。兄が頭を下げれば美悠も下げ、それにまた兄が応えて頭を下げ美悠も略。
二人してへこへこしちゃって。
「ほら千早、お前もちゃんとお礼言えよ」
ひとしきり謝罪のしあいは終わったようで兄が目を吊り上げて千早を呼んだ。「ふざけんじゃないよ、なんで私が」と言いかけた千早の頭を兄の大きな手ががしりとつかむ。そのまま力強く下に向かって押された。
「そんな……っ、頭上げてくださいお二人とも」
美悠は千早と兄の二人から頭を下げられて恐縮してしまっている様子だった。
「私のほうこそお急ぎの千早さんにモデルなんか頼んでしまったばっかりに」
「モデルっ?」
突然兄がひっくり返った声を上げた。兄の声に美悠が顔をこわばらせる。兄は千早と美悠を見比べて「も、モデルってヌードか……?」相変わらずの上ずった声でどちらにともなく尋ねた。どこまでも思考回路の同じ兄には頭が下がる。というか兄と考えていることが同じなんて。勘弁してくれ。
「まさかっ、普通に座ってもらってただけですっ」
「……だよな、こんな貧相な……」
「おい」
千早を哀れむように見下ろしてきた兄を剣呑な視線で刺してやった。貧相とは失礼な。否定はできないけど。
千早の殺気を感じたのか小さく悲鳴を上げて体を縮める兄に、美悠がくすっと笑った。「やっぱりご兄弟なんですね」それはどういう意味だ。
「ここは寒いですので、うちに戻りましょうか」
美悠のありがたい申し出に千早と兄は同時にうなずいた。
雪は降り続いていた。
深々と。むしろ、ここに来る前より強くなっている気がする。
この雪だけは変わらないんだろうな。
随分霞んでしまった雪解け水のような記憶を掻き集めながら、千早は再び椅子の上で膝を抱えた。
先刻と違うのは、この兄の存在。
「うちの妹で役に立ちますか?」
美悠に淹れてもらったコーヒーで指先と喉を温めながら、アトリエの隅で二人の様子を眺めている。
失礼な、とは思いつつ、自分でも少し不安が残るので言い返すのはやめておいた。代わりに美悠が微笑む。
「勿体ないくらいですよ」
目元をふわりと綻ばせ、カンバスと千早を見比べながら木炭を走らせる。
その動作は無駄がなかった。手元は見えないけれど、描き加えて消しての繰り返しさえまるで決められた型のように流れていく。
「きらきらして、可愛らしくて。大人しいのかしらと思った次の瞬間には笑顔を輝かせたり。まるで、春の太陽みたいに」
お世辞だとは分かっていても、顔が熱くなるのが分かる。褒められ慣れていないのだ。
それにしても、勿体ないって。きらきらって。太陽って!
やっぱり画家だけあって感性が違うのだろうかと、照れ隠しでどうでもいいことに思いを馳せる。
すると同じことを考えたのか、兄がにやにやとした笑みを浮かべた。
「太陽ねぇ…同じ太陽なら、真夏のカンカン照りって感じだけどな」
「否定はしない。けど冬の枯れススキみたいな兄貴は黙って」
これにはさすがに口を挟む。
「ススキはないだろ」
「なによ。雪かぶって今にも倒れそうだったくせに。それとも、もやし?」
「お前、もやしを馬鹿にすんなよ。美味いんだぞもやし。それに安い、使い勝手もいい。月末の救世主だ」
「ああ、じゃあもやしに失礼ね」
いつの間にかまた漫才のようなやり取りに発展する二人。
そして押し殺した美悠の笑い声に気がついて、また居心地の悪い思いをするのだった。
「よし。出来ました」
それから幾分もせずに、魔法のようだった美悠の手が止まった。満足そうにカンバスを見渡す。
そしてちょっと照れくさそうに、出来たばかりのそれを千早に向ける。
「完成と言っても、まだ下絵ですけどね」
千早は兄と共にその未完成の完成品を見つめた。
そこに居たのは、少し澄ました瞳をした自分。繊細に明と暗だけで描かれたひとりの少女。
「へぇ」
だから、兄の言葉につられて溜め息を漏らした。
「まるで千早じゃないみたいだ」
深々と。むしろ、ここに来る前より強くなっている気がする。
この雪だけは変わらないんだろうな。
随分霞んでしまった雪解け水のような記憶を掻き集めながら、千早は再び椅子の上で膝を抱えた。
先刻と違うのは、この兄の存在。
「うちの妹で役に立ちますか?」
美悠に淹れてもらったコーヒーで指先と喉を温めながら、アトリエの隅で二人の様子を眺めている。
失礼な、とは思いつつ、自分でも少し不安が残るので言い返すのはやめておいた。代わりに美悠が微笑む。
「勿体ないくらいですよ」
目元をふわりと綻ばせ、カンバスと千早を見比べながら木炭を走らせる。
その動作は無駄がなかった。手元は見えないけれど、描き加えて消しての繰り返しさえまるで決められた型のように流れていく。
「きらきらして、可愛らしくて。大人しいのかしらと思った次の瞬間には笑顔を輝かせたり。まるで、春の太陽みたいに」
お世辞だとは分かっていても、顔が熱くなるのが分かる。褒められ慣れていないのだ。
それにしても、勿体ないって。きらきらって。太陽って!
やっぱり画家だけあって感性が違うのだろうかと、照れ隠しでどうでもいいことに思いを馳せる。
すると同じことを考えたのか、兄がにやにやとした笑みを浮かべた。
「太陽ねぇ…同じ太陽なら、真夏のカンカン照りって感じだけどな」
「否定はしない。けど冬の枯れススキみたいな兄貴は黙って」
これにはさすがに口を挟む。
「ススキはないだろ」
「なによ。雪かぶって今にも倒れそうだったくせに。それとも、もやし?」
「お前、もやしを馬鹿にすんなよ。美味いんだぞもやし。それに安い、使い勝手もいい。月末の救世主だ」
「ああ、じゃあもやしに失礼ね」
いつの間にかまた漫才のようなやり取りに発展する二人。
そして押し殺した美悠の笑い声に気がついて、また居心地の悪い思いをするのだった。
「よし。出来ました」
それから幾分もせずに、魔法のようだった美悠の手が止まった。満足そうにカンバスを見渡す。
そしてちょっと照れくさそうに、出来たばかりのそれを千早に向ける。
「完成と言っても、まだ下絵ですけどね」
千早は兄と共にその未完成の完成品を見つめた。
そこに居たのは、少し澄ました瞳をした自分。繊細に明と暗だけで描かれたひとりの少女。
「へぇ」
だから、兄の言葉につられて溜め息を漏らした。
「まるで千早じゃないみたいだ」
「いいえ、千早さんは本当に透明な方です」
いままでの気弱そうな言葉よりも少し強めに美悠は言い切った。その目に浮かぶ自信はこの細っこい体のどこから湧いてくるのだろうと不思議に思う。
透明といわれて意味もわからずとりあえず褒められているのだろうと解釈した千早は顔を赤くしてうつむいた。どうだまいったかといわんばかりにちらりと隣の兄を窺う。
「……?」
兄は千早じゃないみたいだ、のあと黙ったままだった。眉根を寄せてにらむようにキャンバス上の千早に見入っている。
「兄ィ?」
「へ?」
千早の訝しげな視線に気づいた兄が間抜けな声を上げて千早を振返った。さっきまでの別人のような引き締まった顔はどこへやら、いつものだらしない顔だった。
「なにしてんのよぼうっとしちゃって。私に惚れちゃった?」
そんなわけあるか。そう返ってくることを予想して嘲笑混じりに言ってやると、意外にも兄は再び表情を曇らせてキャンバスに目を戻した。なんだか様子がおかしい。千早は美悠と顔を見合わせた。
「似てる」
え、とつぶやくのが美悠と同時だった。誰が誰に似てるって?
「この辺に住んでた頃によく遊んでくれた人に」
初耳だ。
「そんな人いたの」
千早が詰問すると少々たじろいだ様子で両手を顔の前で振って「別に好きな人とかじゃないんだ、あと二人、男の人もいたし」早口で弁明するところをみると恐らく言ってる事は本当だろう。けれどこの辺りに住んでいたのは祖母と暮らしていたほんの数年のことだし、もう十年近い昔のことだ。千早が幼稚園に入る前に引っ越しているのだから、その頃兄は幼稚園を卒業するかどうかという年齢だったはずだ。
「おれさ、引っ込み思案で友達いなくて、」
ぽつりぽつりと話し始めた兄の回想の内容はこうだ。
どうやって知り合ったのかいつから一緒だったのかははっきりと覚えていない。けれど気がついたときにはいつも男二人女一人の彼らがいた。人と触れ合うことが苦手だった兄も、彼らとは自然に話す事ができた。走り回ったり近くの竹やぶで、本当はいけないのにタケノコを採ってみたり。内緒だよ、といって藪に踏み入っていく彼らの後姿がひどく輝いていたことは覚えているらしい。
名前も住んでいるところも知らない。母親は明らかに怪しいその三人に付いてまわる兄に不審を抱くどころか、一緒に遊べる相手が見つかったことがうれしかったらしく、何も言わなかった。
ところがある日突然、ぷつりと糸は切れた。もともと不確かなつながりであったし、だいたい名前すら知らない相手は探しようがない。それから彼らには一度も逢っていない。
「今思うと、あの人たちと遊んでた日は夢だったのかもしれない。あんまりリアルだから現実と区別がつかんだけで」
でも一つだけ残ってるんだといいながら兄がジーンズのポケットから携帯電話を取り出す。無愛想な黒い筐体に一つだけ寂しくぶら下がったサルのマスコットがぷらんと揺れた。
昔は尻尾を引くとかわいらしくもなんともない不気味な声を発していたように思うが、けっこう前からもう音もしなくなっている。本来鳴いてなんぼのすっかり汚れて黒ずんでしまったサルを、物持ちの悪いこの兄が未だに大切に持っていた。そういえば昔からあるなあとぼんやりサルを見上げる。
「これをもらったんだ、あの人らに。使い方とかいろいろ教えてくれた。あのころはやっててさ、おれすっごい欲しかったんだ。これだけが、あの人らが夢の人じゃなかったってことの証明みたいだろ」
肩をすくめながらサルと電話をポケットに突っ込んで兄は表情を緩めた。「気の強そうな顔だったと思うんだな、おまえに似て」
「なにおう」
馬鹿にしたように千早を見下ろしてくる兄を思い切りにらみ上げ、
「あれ、どうしたの美悠さん?」
ふと視界に入った美悠の顔から血の気が引いているのが見えて視線を兄から美悠へ移す。
「まさか……」
震えた声で美悠が言い、兄を見つめた。
「千春……くん?」
いままでの気弱そうな言葉よりも少し強めに美悠は言い切った。その目に浮かぶ自信はこの細っこい体のどこから湧いてくるのだろうと不思議に思う。
透明といわれて意味もわからずとりあえず褒められているのだろうと解釈した千早は顔を赤くしてうつむいた。どうだまいったかといわんばかりにちらりと隣の兄を窺う。
「……?」
兄は千早じゃないみたいだ、のあと黙ったままだった。眉根を寄せてにらむようにキャンバス上の千早に見入っている。
「兄ィ?」
「へ?」
千早の訝しげな視線に気づいた兄が間抜けな声を上げて千早を振返った。さっきまでの別人のような引き締まった顔はどこへやら、いつものだらしない顔だった。
「なにしてんのよぼうっとしちゃって。私に惚れちゃった?」
そんなわけあるか。そう返ってくることを予想して嘲笑混じりに言ってやると、意外にも兄は再び表情を曇らせてキャンバスに目を戻した。なんだか様子がおかしい。千早は美悠と顔を見合わせた。
「似てる」
え、とつぶやくのが美悠と同時だった。誰が誰に似てるって?
「この辺に住んでた頃によく遊んでくれた人に」
初耳だ。
「そんな人いたの」
千早が詰問すると少々たじろいだ様子で両手を顔の前で振って「別に好きな人とかじゃないんだ、あと二人、男の人もいたし」早口で弁明するところをみると恐らく言ってる事は本当だろう。けれどこの辺りに住んでいたのは祖母と暮らしていたほんの数年のことだし、もう十年近い昔のことだ。千早が幼稚園に入る前に引っ越しているのだから、その頃兄は幼稚園を卒業するかどうかという年齢だったはずだ。
「おれさ、引っ込み思案で友達いなくて、」
ぽつりぽつりと話し始めた兄の回想の内容はこうだ。
どうやって知り合ったのかいつから一緒だったのかははっきりと覚えていない。けれど気がついたときにはいつも男二人女一人の彼らがいた。人と触れ合うことが苦手だった兄も、彼らとは自然に話す事ができた。走り回ったり近くの竹やぶで、本当はいけないのにタケノコを採ってみたり。内緒だよ、といって藪に踏み入っていく彼らの後姿がひどく輝いていたことは覚えているらしい。
名前も住んでいるところも知らない。母親は明らかに怪しいその三人に付いてまわる兄に不審を抱くどころか、一緒に遊べる相手が見つかったことがうれしかったらしく、何も言わなかった。
ところがある日突然、ぷつりと糸は切れた。もともと不確かなつながりであったし、だいたい名前すら知らない相手は探しようがない。それから彼らには一度も逢っていない。
「今思うと、あの人たちと遊んでた日は夢だったのかもしれない。あんまりリアルだから現実と区別がつかんだけで」
でも一つだけ残ってるんだといいながら兄がジーンズのポケットから携帯電話を取り出す。無愛想な黒い筐体に一つだけ寂しくぶら下がったサルのマスコットがぷらんと揺れた。
昔は尻尾を引くとかわいらしくもなんともない不気味な声を発していたように思うが、けっこう前からもう音もしなくなっている。本来鳴いてなんぼのすっかり汚れて黒ずんでしまったサルを、物持ちの悪いこの兄が未だに大切に持っていた。そういえば昔からあるなあとぼんやりサルを見上げる。
「これをもらったんだ、あの人らに。使い方とかいろいろ教えてくれた。あのころはやっててさ、おれすっごい欲しかったんだ。これだけが、あの人らが夢の人じゃなかったってことの証明みたいだろ」
肩をすくめながらサルと電話をポケットに突っ込んで兄は表情を緩めた。「気の強そうな顔だったと思うんだな、おまえに似て」
「なにおう」
馬鹿にしたように千早を見下ろしてくる兄を思い切りにらみ上げ、
「あれ、どうしたの美悠さん?」
ふと視界に入った美悠の顔から血の気が引いているのが見えて視線を兄から美悠へ移す。
「まさか……」
震えた声で美悠が言い、兄を見つめた。
「千春……くん?」
名前を呼ぶ、聞きなれない声に視線を移す。
妹より身長のある相手を確認する為に、目線を上げて。
でも、自分の真正面よりは、少し下げて。
濡れ羽色の艶やかな前髪の隙間から覗ける、長い睫毛は小刻みに揺れていた。
白い陶器のような肌、本来なら血色の透ける頬も、今は赤みを失っていて。
「「なんで」」
千春の声と、美悠の声が重なる。
一人、仲間外れにされた千早は眉根を寄せ、首を軽く傾けながら、
上目遣いで二人を見遣る。
「俺の名前知ってるんだ?」
「ここにいるの?」
方向性の違う疑問は再び同時発生する。
2方向、いや、置いてけぼりの千早の疑問も含めると、3方向か。
「え、なに、二人は、」
軌道修正し、2方向の疑問の先に、頂点を見つけようと紡いだ言葉は、
美悠によって更なる軌道修正を要求された。
「だって、・・・千春くんは、・・あのとき・・・・・きゃあああっ」
何らかの成分を、脳内と体外へ多量に放出した美悠は意識を遠のかせた。
千早は、置いてけぼりの仲間外れではなくなった。
美悠を抱きとめる兄も、置いてけぼりの表情そのものだった。
妹より身長のある相手を確認する為に、目線を上げて。
でも、自分の真正面よりは、少し下げて。
濡れ羽色の艶やかな前髪の隙間から覗ける、長い睫毛は小刻みに揺れていた。
白い陶器のような肌、本来なら血色の透ける頬も、今は赤みを失っていて。
「「なんで」」
千春の声と、美悠の声が重なる。
一人、仲間外れにされた千早は眉根を寄せ、首を軽く傾けながら、
上目遣いで二人を見遣る。
「俺の名前知ってるんだ?」
「ここにいるの?」
方向性の違う疑問は再び同時発生する。
2方向、いや、置いてけぼりの千早の疑問も含めると、3方向か。
「え、なに、二人は、」
軌道修正し、2方向の疑問の先に、頂点を見つけようと紡いだ言葉は、
美悠によって更なる軌道修正を要求された。
「だって、・・・千春くんは、・・あのとき・・・・・きゃあああっ」
何らかの成分を、脳内と体外へ多量に放出した美悠は意識を遠のかせた。
千早は、置いてけぼりの仲間外れではなくなった。
美悠を抱きとめる兄も、置いてけぼりの表情そのものだった。
つまり、
「兄ィと美悠さんはほんとに面識ないの?」
「だからおれは覚えてないんだって。こんな美人、いっかい見たら忘れない」
セクハラ、と呟いてソファ横に座り込んだ兄の背中を蹴っ飛ばす。「なんだよう」兄が不満げにこちらを見上げてくるが、それどころではない。
椅子の背を抱きかかえるようにして逆さに座った千早が、背に顎をのっけて美悠に視線を向ける。美悠は、ソファの上でかすかに寝息を立てていた。突然倒れたあと兄がここまで運んだのだ(こういうときだけ体が大きいのが役に立つ)。白い頬に長い髪が一筋、墨のように流れていた。
「だいじょうぶそうだね」
「うん」
兄の視線は美悠の少し上あたりをふわふわとしている。なにか考えごとをしているとき兄はいつもこういう顔をする。
「昔さ、」
「なに」
「あの人らといたときだったと思うけど、崖から落ちたことがあるんだよ」
「はあ」
兄は少し首を傾けて続ける。
「崖っていっても大したものじゃあないんだけど、子どもからしたらでかいもんでさ。出された手つかみ損なってずずずって」
「落ちたわけか」
「落ちたわけだ」
ふうむと頷いて千早は首をひねる。「それが何?」
「いや、美悠さんの言ってたのがそのことなのかと思って」
自信なげにこちらを振り向いて兄が首をすくめた。ふたりしてうーんと唸ったり首をひねったりしていると、
「……あ……」
ソファの上で美悠が身じろぎした。
「兄ィと美悠さんはほんとに面識ないの?」
「だからおれは覚えてないんだって。こんな美人、いっかい見たら忘れない」
セクハラ、と呟いてソファ横に座り込んだ兄の背中を蹴っ飛ばす。「なんだよう」兄が不満げにこちらを見上げてくるが、それどころではない。
椅子の背を抱きかかえるようにして逆さに座った千早が、背に顎をのっけて美悠に視線を向ける。美悠は、ソファの上でかすかに寝息を立てていた。突然倒れたあと兄がここまで運んだのだ(こういうときだけ体が大きいのが役に立つ)。白い頬に長い髪が一筋、墨のように流れていた。
「だいじょうぶそうだね」
「うん」
兄の視線は美悠の少し上あたりをふわふわとしている。なにか考えごとをしているとき兄はいつもこういう顔をする。
「昔さ、」
「なに」
「あの人らといたときだったと思うけど、崖から落ちたことがあるんだよ」
「はあ」
兄は少し首を傾けて続ける。
「崖っていっても大したものじゃあないんだけど、子どもからしたらでかいもんでさ。出された手つかみ損なってずずずって」
「落ちたわけか」
「落ちたわけだ」
ふうむと頷いて千早は首をひねる。「それが何?」
「いや、美悠さんの言ってたのがそのことなのかと思って」
自信なげにこちらを振り向いて兄が首をすくめた。ふたりしてうーんと唸ったり首をひねったりしていると、
「……あ……」
ソファの上で美悠が身じろぎした。
「・・・ええ、と」
目を覚ます。なんで私、ソファに横になっていたんだろうか。
「起きました?美悠さん」
首だけを横に動かし、声の主を見る。心配そうに見つめる女の子とほっ、としている顔をした男の人。
「あぁ・・・」
そうでした。千早さんと千春くんと話をしていて、そしたら急に立ちくらみがしたんでした。
「すいません・・・。ご心配おかけしました」
私は起き上がり、右手で頭を押さえながら謝罪した。
「大丈夫ですか?美悠さん。何処か痛いところでも?」
「それはないだろう。俺が優しく抱きとめ・・」
「兄ィは黙ってて」
千早さんは千春くんを睨みつけて言った。
「大丈夫です。なんともありません」
「よかったぁ・・・」
ほっとしたように、千早さんは安堵した表情を見せた。
私は、それを笑顔で受け止める。
ふと、千春くんを見ると複雑そうな顔で私を見つめていた。
「・・・千早」
と、千春くんが無表情で言う。
「なに?兄ィ」
「そろそろ、帰ろうか」
「はい?帰るって、家に?」
「違う。駅前にホテルがあったから、そこに泊まろう。ここに長く居すぎた。美悠さんにも迷惑だろう」
そう言うと、千春くんは立ち上がった。
「そんな。迷惑ではありませんよ。もう少し居てくださっても・・・・」
「・・・いえ、今日は帰ります」
私の顔を見ずに、千春くんは一人で玄関に向かい、出て行った。
「ちょっ、兄ィ!・・すいません、美悠さん。とりあえず帰ります」
「え、えぇ・・。また、きてください」
「はいっ!また来ます!」
千早さんは嬉しそうな顔で出て行った。
兄ィを追うと、街灯の下に佇んでいた。
「ちょっと。兄ィ。急にどうしたのよ」
「・・・別に」
兄ィは、夜空を見上げながら吸い慣れないと言っていた煙草を取り出していた。
「なぁ、千早」
「なによ」
私は不満そうに兄ィを見る。
「・・・明日、この町を出る。家に、帰る。ばぁちゃん家は、また今度、だ」
思いも寄らないことを、兄ィは言い始めた。
目を覚ます。なんで私、ソファに横になっていたんだろうか。
「起きました?美悠さん」
首だけを横に動かし、声の主を見る。心配そうに見つめる女の子とほっ、としている顔をした男の人。
「あぁ・・・」
そうでした。千早さんと千春くんと話をしていて、そしたら急に立ちくらみがしたんでした。
「すいません・・・。ご心配おかけしました」
私は起き上がり、右手で頭を押さえながら謝罪した。
「大丈夫ですか?美悠さん。何処か痛いところでも?」
「それはないだろう。俺が優しく抱きとめ・・」
「兄ィは黙ってて」
千早さんは千春くんを睨みつけて言った。
「大丈夫です。なんともありません」
「よかったぁ・・・」
ほっとしたように、千早さんは安堵した表情を見せた。
私は、それを笑顔で受け止める。
ふと、千春くんを見ると複雑そうな顔で私を見つめていた。
「・・・千早」
と、千春くんが無表情で言う。
「なに?兄ィ」
「そろそろ、帰ろうか」
「はい?帰るって、家に?」
「違う。駅前にホテルがあったから、そこに泊まろう。ここに長く居すぎた。美悠さんにも迷惑だろう」
そう言うと、千春くんは立ち上がった。
「そんな。迷惑ではありませんよ。もう少し居てくださっても・・・・」
「・・・いえ、今日は帰ります」
私の顔を見ずに、千春くんは一人で玄関に向かい、出て行った。
「ちょっ、兄ィ!・・すいません、美悠さん。とりあえず帰ります」
「え、えぇ・・。また、きてください」
「はいっ!また来ます!」
千早さんは嬉しそうな顔で出て行った。
兄ィを追うと、街灯の下に佇んでいた。
「ちょっと。兄ィ。急にどうしたのよ」
「・・・別に」
兄ィは、夜空を見上げながら吸い慣れないと言っていた煙草を取り出していた。
「なぁ、千早」
「なによ」
私は不満そうに兄ィを見る。
「・・・明日、この町を出る。家に、帰る。ばぁちゃん家は、また今度、だ」
思いも寄らないことを、兄ィは言い始めた。
私は夏が好きだ。
その言葉を口にすることはないし、そもそも体があまり強くないから夏の強い日差しは私には合わない。
それでも好きな季節は夏である。
「美悠大丈夫か?肩かすよ。」
そう語りかける冬嗣に私は、はにかんだ笑顔を隠すようにうなずく。
夏の暑い日差しとは別の熱が私の体をかける。
私たち3人は幼馴染である。
「今日から新しい仲間になる、千春だ。」
幼い仲間は私たちに馴染むのには時間がかかった。
そんな千春を案じてか、冬嗣がタケノコを採りに行こうと私たちを誘う。
夏間近であり私の体は当然のごとく、また禁止されてるタケノコ採りのせいで心拍数は自然と高くなる。
禁止されてるとはいえ、山に入るのに障害はない。
「大丈夫か?」
冬嗣のやさしい声に元気をもらう。
大丈夫、そう言おうと顔を上げると冬嗣の視線は私の後方を見ている。
背丈に似合わない程の歩幅でかけて来る千春。
冬嗣はその場で千春を迎え、額の汗を拭い水筒の中身をわけている。
何だろう、この気持ち悪い感情は…
そして私は彼の…
フラッシュバックした断片的な記憶。
美悠は再び気持ち悪い感情を抱くことになる、罪悪感と言うおまけまでついて・・・
全てを思い出したわけではなかった。
だが出て行った千春を見て不安が増す。
耐え切れなくなり、彼のアドレスを探す。
その言葉を口にすることはないし、そもそも体があまり強くないから夏の強い日差しは私には合わない。
それでも好きな季節は夏である。
「美悠大丈夫か?肩かすよ。」
そう語りかける冬嗣に私は、はにかんだ笑顔を隠すようにうなずく。
夏の暑い日差しとは別の熱が私の体をかける。
私たち3人は幼馴染である。
「今日から新しい仲間になる、千春だ。」
幼い仲間は私たちに馴染むのには時間がかかった。
そんな千春を案じてか、冬嗣がタケノコを採りに行こうと私たちを誘う。
夏間近であり私の体は当然のごとく、また禁止されてるタケノコ採りのせいで心拍数は自然と高くなる。
禁止されてるとはいえ、山に入るのに障害はない。
「大丈夫か?」
冬嗣のやさしい声に元気をもらう。
大丈夫、そう言おうと顔を上げると冬嗣の視線は私の後方を見ている。
背丈に似合わない程の歩幅でかけて来る千春。
冬嗣はその場で千春を迎え、額の汗を拭い水筒の中身をわけている。
何だろう、この気持ち悪い感情は…
そして私は彼の…
フラッシュバックした断片的な記憶。
美悠は再び気持ち悪い感情を抱くことになる、罪悪感と言うおまけまでついて・・・
全てを思い出したわけではなかった。
だが出て行った千春を見て不安が増す。
耐え切れなくなり、彼のアドレスを探す。
夜に向かって煙を吐き出す。ゆらゆらと空に上っていく煙を見送りぼんやり空を仰ぐ。無意識に昔のことを思い出していた。
背の高い男の人と、髪の短い女の人、それから小柄で少し怖い顔をした男の人。今思えば、あれほど同世代と馴染めなかった自分が、どうして見ず知らずの年上の人とつるんでいたのだろう。あのころ同い年の友だちと遊んだ記憶はほとんどないが、あの三人と走り回った雑木林の景色はいまでもはっきり覚えている。
「兄ィ、ねえってば」
「え」
斜め下から呼ぶ声がしてふと我に返る。直後、ごんっと鈍い音がした。少し遅れて額にじわじわと鈍痛が広がる。「痛ぅー……」ぶつけた額を押さえて顔を上げると、背の高い電柱がこちらを見下ろしていた。
「なにやってんの、あぶないよって言ったじゃん」
妹の呆れた声が下から飛んできて軽く頭を振る。口の端に引っ掛けた煙草の先から灰がこぼれて中に舞った。じーんとしびれる額を手の甲でごしごし擦って、「考え事してて……」腰に手を当てて眉をひそめている妹を見下ろし我ながら情けない顔でつぶやく。
「なに、美悠さんがあんまり美人でまだぼうっとしてるわけ」
「そういうわけじゃ」
「じゃあどういうわけ?」
「……おれ、まじで美悠さんに覚えないんだけど」
右手でがしがし髪をかき回してうーんと首をひねる。さっきのキャンバスに描かれた妹の肖像画(というにはあまりにもよくできすぎていたが)は確かに記憶の中の三人組の一人によく似ていたが、それを描いた美悠本人に見覚えはなかった。……むこうはこっちのこと知ってたっぽいけど。
ふと顎の辺りにちくちくした視線を感じて顔をそちらに向ける。
「ふうん」
千早は全く信じてない顔で例の恐ろしい目をいっそう細めてこちらを睨み上げていた。
「あっ、おまえ信じてないだろっ」
「だあって兄ィがそんなマジな顔してるなんてありえないもん」
「おれがマジな顔したらいけないってのか」
「だれもそんなこと言ってないじゃん、ばーか」
「あ、てめっ、兄貴に向かってこの口っ」
二人してだんだん声が高くなり、妹の一言にかちんときて小さいくせに口ばっかり達者な妹の頬をひねり上げた。「いはいっ、はなへこのやろーっ」ところが妹は全力で反撃してきたので「わっ、DV反対っ」こちらが降参してすぐに手を放した。
最後にこちらの脛を思いっきり蹴っ飛ばしておいて、千早は踵を返し早足に歩き始めた。千春もまだ長い煙草を足元に落として踏み消し(千早が見ていたらまた殴られる。あれで案外律儀なやつなのだ)、大股で妹の背中を追う。
あの三人の記憶は、ある日を境にすっぱり途切れていた。テレビのチャンネルを変えたときのようになんの余韻も残さず、そこから先はまったく別の新しい思い出が上書きされている。年を重ねるごとに三人と過ごした記憶は新しい情報に埋もれてどんどん遠ざかる。その記憶をいまごろ掘り出すことになるとは思わなかった。
途切れた記憶の端、いちばん最後の部分。伸ばされた手と、頭上に広がる木々の隙間から覗く空の色。そして誰かが叫ぶように呼んだ千春の名前。けれど何かが頭の片隅で引っかかっていた。
そうだ、忘れてた。この記憶は、引っ張り出しちゃいけなかったんだ。
せっかく歩き出した足を再び止めた。少しむこうで千早が振り返って怪訝そうな視線を投げてくる。その千早の目を見るともなくただ前を見つめて、千春はつぶやいた。
「おれ、落ちたんじゃない……落とされたんだ」
背の高い男の人と、髪の短い女の人、それから小柄で少し怖い顔をした男の人。今思えば、あれほど同世代と馴染めなかった自分が、どうして見ず知らずの年上の人とつるんでいたのだろう。あのころ同い年の友だちと遊んだ記憶はほとんどないが、あの三人と走り回った雑木林の景色はいまでもはっきり覚えている。
「兄ィ、ねえってば」
「え」
斜め下から呼ぶ声がしてふと我に返る。直後、ごんっと鈍い音がした。少し遅れて額にじわじわと鈍痛が広がる。「痛ぅー……」ぶつけた額を押さえて顔を上げると、背の高い電柱がこちらを見下ろしていた。
「なにやってんの、あぶないよって言ったじゃん」
妹の呆れた声が下から飛んできて軽く頭を振る。口の端に引っ掛けた煙草の先から灰がこぼれて中に舞った。じーんとしびれる額を手の甲でごしごし擦って、「考え事してて……」腰に手を当てて眉をひそめている妹を見下ろし我ながら情けない顔でつぶやく。
「なに、美悠さんがあんまり美人でまだぼうっとしてるわけ」
「そういうわけじゃ」
「じゃあどういうわけ?」
「……おれ、まじで美悠さんに覚えないんだけど」
右手でがしがし髪をかき回してうーんと首をひねる。さっきのキャンバスに描かれた妹の肖像画(というにはあまりにもよくできすぎていたが)は確かに記憶の中の三人組の一人によく似ていたが、それを描いた美悠本人に見覚えはなかった。……むこうはこっちのこと知ってたっぽいけど。
ふと顎の辺りにちくちくした視線を感じて顔をそちらに向ける。
「ふうん」
千早は全く信じてない顔で例の恐ろしい目をいっそう細めてこちらを睨み上げていた。
「あっ、おまえ信じてないだろっ」
「だあって兄ィがそんなマジな顔してるなんてありえないもん」
「おれがマジな顔したらいけないってのか」
「だれもそんなこと言ってないじゃん、ばーか」
「あ、てめっ、兄貴に向かってこの口っ」
二人してだんだん声が高くなり、妹の一言にかちんときて小さいくせに口ばっかり達者な妹の頬をひねり上げた。「いはいっ、はなへこのやろーっ」ところが妹は全力で反撃してきたので「わっ、DV反対っ」こちらが降参してすぐに手を放した。
最後にこちらの脛を思いっきり蹴っ飛ばしておいて、千早は踵を返し早足に歩き始めた。千春もまだ長い煙草を足元に落として踏み消し(千早が見ていたらまた殴られる。あれで案外律儀なやつなのだ)、大股で妹の背中を追う。
あの三人の記憶は、ある日を境にすっぱり途切れていた。テレビのチャンネルを変えたときのようになんの余韻も残さず、そこから先はまったく別の新しい思い出が上書きされている。年を重ねるごとに三人と過ごした記憶は新しい情報に埋もれてどんどん遠ざかる。その記憶をいまごろ掘り出すことになるとは思わなかった。
途切れた記憶の端、いちばん最後の部分。伸ばされた手と、頭上に広がる木々の隙間から覗く空の色。そして誰かが叫ぶように呼んだ千春の名前。けれど何かが頭の片隅で引っかかっていた。
そうだ、忘れてた。この記憶は、引っ張り出しちゃいけなかったんだ。
せっかく歩き出した足を再び止めた。少しむこうで千早が振り返って怪訝そうな視線を投げてくる。その千早の目を見るともなくただ前を見つめて、千春はつぶやいた。
「おれ、落ちたんじゃない……落とされたんだ」
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
創作小説 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
創作小説のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8433人
- 2位
- 音楽が無いと生きていけない
- 195994人
- 3位
- マイミク募集はここで。
- 89504人
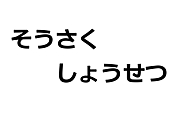












![[dir]小説・文学・作家](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/7/27/220727_135s.jpg)










