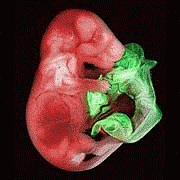開催終了日本分子生物学会2006フォーラム
詳細
2006年10月27日 11:01 更新
日本分子生物学会2006フォーラム 分子生物学の未来 〜コンファレンス&サイエンスティフィック・エキジビション〜
日本分子生物学会は、例年年会が行われる12月に、本年は「日本分子生物学2006フォーラム(分子生物学の未来)」を開催します。ここでは、基礎生物学としての分子生物学の成果・展望のみでなく、成果の社会への還元についても議論できるような場とします。
発表および参加は日本分子生物学会会員に限定しませんので、多数の皆様のご参加をお願いいたします。
開催日:
2006年12月6日(水)〜8日(金)
会場:
名古屋国際会議場
組織委員 代表:
町田 泰則
(名古屋大学大学院理学研究科)
プレナリーレクチャー
Prof. Victor R. Ambros (Dartmouth Medical School, NH, USA)
「MicroRNAs in Animal Development」
上田 建仁 氏(トヨタ自動車 東富士研究所 常務役員)
「自動車技術の課題とバイオテクノロジーへの期待」
○シンポジウム
組織委員会・プログラム委員会にて、全50テーマのシンポジウムを企画しました。シンポジウムは同時に10会場で、3日間の会期中全日程で行います。
Sa1B 神経変性疾患研究の新展開:病態解明から治療まで
世話人:祖父江 元(名大・院医)、高橋 良輔(京大・院医)
パーキンソン病、アルツハイマー病、運動ニューロン疾患などの神経変性疾患の多くは、その病態が全く不明であった。しかしここ十数年の分子生物学的研究の進歩により、多くの神経変性疾患で異常蛋白質の凝集・蓄積が神経変性に共通するメカニズムであるらしいことがわかってきた。さらに最近は異常蛋白質の生成や分解、神経細胞に対する毒性発現のメカニズムが、個々の疾患について分子レベルで明らかになってきており、その知見に基づいた有望な治療法が提唱される新しい展開を迎えている。さまざまな方法論を駆使し、神経変性疾患の病態解明と治療法開発に迫ろうとする研究の最前線を、国内のトップ研究者が紹介する。
Sa1C 光環境と植物の適応戦略
世話人:井澤 毅(農業生物資源研究所)、和田 正三(基生研)
植物は、光合成により、光エネルギーを変換することで、栄養源を獲得、生存している。この一見、単純な生活環をおくっているかに見える植物であるが、発芽し、根を張った大地の自然環境、特に、その土地での日周変化・四季の変化といった刻々と変化する光環境に適応するために、フィトクロム・クリプトクロム・フォトトロピンといった植物光受容体を介した信号伝達系を駆使し、様々な生理反応を起こすことで、効率的に子孫を残すという、実は、かなり、したたかな生存戦略を身につけている。本シンポジウムでは、その植物がもつ光環境に対する適応戦略のいくつかを取り上げ、その分子メカニズムに迫りたいと考えてる。今回取り上げるのは、光を受けた直後に、「動き」として現れる、静的なイメージの強い植物からは、想像しにくい生理現象から、「青色光による気孔の光開口」と、葉の細胞が適量な光を受けるために、葉緑体が細胞内を移動する「葉緑体光定位運動」を取り上げる予定である。また、光環境の日周変動への適応に必須な「概日時計」、そして、日長変化 を認識することで、季節変化を予期し、適切な時期に開花をし、効率的に種子を残す戦略としての、「光周性花芽形成」を取り上げる。
Sa1D 生体応答システムと老化・寿命の分子メカニズム― 基礎老化研究から抗老化研究へ
世話人:鍋島 陽一(京大・院医)、石井 直明(東海大・医)
近年の寿命や老化に関わるモデル動物を使った研究から、老化の分子メカニズムが明らかになりつつある。その中でもエネルギー代謝とその副産物である酸化ストレスが注目されている。酸化ストレスは細胞に傷害を起こして老化を促進と同時に、生体防御因子として老化を抑制する役割も持つために、酸化ストレスの制御が老化の重要な鍵となる。一方、生体恒常性の維持が老化にともなう生理機能の減退に大きく関わっていることから、酸化ストレスの制御とともに、生体の応答システムが寿命や老化速度の決定に重要であることが明らかになりつつある。この生体応答システムはヒトにも存在することから、エネルギー代謝・酸化ストレスの制御や恒常性維持の老化への関わりを議論することにより、ヒトの老化のメカニズム解明と同時に抗老化へ展望できると考える。
Sa1E バイオイメージングでとらえる生命現象
世話人:上野 直人(基生研・形態形成)、野中 茂紀(基生研・バイオイメージング研究室(仮称))
分子生物学は、遺伝子工学を軸として大成功を納める一方、その分子が働く時間と空間については空間分解能・感度などの点で十分な解析手段を持ち得なかった。しかし今やようやく字義通りの「分子生物学」、すなわち実際の分子の挙動から生物学を理解するための方法論が揃いつつある。本シンポジウムでは、観察対象となる分子を標識するプローブ技術、それを実時間でとらえる顕微鏡技術という観点から、興味深い研究を行っている5人に発表していただく。今後の分子生物学の進むべき方向を考えたい。
Sa1F 細胞内のタンパク質社会と品質管理
世話人:遠藤 斗志也(名大・院理)、吉田 秀郎(京大・院理)
生命現象を担うのは、細胞内のタンパク質がつくる「タンパク質社会」である。そして細胞には、タンパク質社会が正しく働くよう、その状態を監視し、維持する「品質管理」システムが存在する。品質管理システムは異常タンパク質を検知すると、翻訳を抑えて負荷を減らし、異常タンパク質の修復や無毒化を図り、修復が成功しなければ分解にまわし、それでもダメなら細胞死を誘導する。品質管理を免れた異常タンパク質は、プリオン線維やアミロイドのような「秩序ある凝集体」を形成することがある。これらの凝集体はタンパク質社会全体にとって脅威であるが、一方で凝集形成は多くのタンパク質に共通する性質らしいことが分かってきた。本シンポジウムでは、こうしたタンパク質社会と品質管理に関する様々な話題を、最前線で活躍されている研究者の方々に紹介いただき、いままさに急速に展開しつつある分野の熱気を実感できるようなシンポジウムとしたい。
Sa1G 一分子生理学・バイオ分子操作
世話人:岩根 敦子(阪大・院生命機能)、吉村 成弘(京大・院生命科学)
細胞には、染色体、情報伝達物質、分子モーター、転写複合体に代表される様々なナノサイズの分子機械が存在し、細胞膜から核への細胞情報ネットワークが形成されている。これらの分子機械は、熱ゆらぎの中で絶えず相互に干渉したり、強調したり、時にはフィードバックを掛け合いながら働いている。このような分子間相互作用を時空間的に理解するには、従来の分子生物学的、細胞生物学的手法に加え、1分子イメージング、1分子ナノ操作という生物物理学的手法が有用である。ここでは、これらの1分子観察・計測の最新技術を紹介すると共に、これらの技術が生体反応の分子メカニズムを理解する上でどのように利用されているかを、最近のトピックスをまじえながら分かり易く紹介する。
Sa1H 蛋白質ネットワークによるエピジェネティクな遺伝子制御とその破綻
世話人:五十嵐 和彦(東北大・院医)、中尾 光善(熊本大・発生医学研究センター)
エピジェネティクスを支えるDNAやクロマチン因子などの化学修飾は安定ではあるが、可逆的に変化し得ることが示唆されている。化学基を導入する修飾システム、化学基を取り除く脱修飾システム、これらシステムの発動を指令する制御システムなどの実体が明らかになりつつある。本シンポジウムでは、遺伝子発現を調節するエピジェネティクス関連蛋白質システムに焦点を当てて、システム間の協調や拮抗作用、そしてその脱制御と癌化の関連について報告していただき、次の一手を探る機会としたい。
Sa1I 染色体・核のダイナミックな機能と構造
世話人:仁木 宏典(国立遺伝研・系統生物研究センター)、原口 徳子(情報通信研究機構・未来ICT研究センター)
ゲノム継承の仕組みを分子レベルで理解することは、生命科学の重要な問題である。ゲノムプロジェクトやプロテオミクスによる解析により、DNA複製過程 や分裂期での染色体分配に関与する因子が次々と発見されるなど、近年、急速 に分子レベルでの知見が蓄積されつつある。しかし、染色体は、いつでも・どこでも一定不変というものではなく、状況により場所により、時々刻々変化するものであることから、染色体の構造と機能を真に理解するためには、これらの分子機構を細胞核という空間で統合的かつ動的に理解することが重要であると考えられる。生命システムの統合的な理解を目指して、細胞核機能の時間的・空間的な制御機構の解明を、独自な視点で行っている研究を紹介する。
Sa1J 細胞骨格のダイナミクス
世話人:稲垣 昌樹(愛知県がんセンター研究所)、竹縄 忠臣(東大・医科研)
細胞骨格という研究分野は骨格筋や平滑筋収縮研究に始まった1950年代から続く息の長い研究分野である。細胞骨格の主要繊維としてアクチンフィラメント、微小管そして中間径フィラメントが同定されている。最近では蛋白質リン酸化シグナルや低分子量G蛋白質シグナルがこの構築制御系として同定されたことと、制御分子の可視化技術や部位特異的抗リン酸化ペプチド抗体の活用によって新展開をみせている。本シンポジウムではこの分野の最近のトピックスを紹介したい。
Sa1K 形態形成を制御する細胞外環境−その未知なるもの
世話人:西脇 清二(理研・細胞移動研究チーム)、瀬原 淳子(京大・再生研)
動物の発生過程における組織や器官の形態形成は細胞の増殖、分化、接着、移動などの細胞の活動によって成し遂げられる。しかしながら形態形成の過程では細胞のみならず「細胞の外」が重要な役割を果たすことが明らかになってきた。細胞はその外部に細胞外マトリックスを形成し、そこに種々のシグナル分子を分泌・配備することにより形態形成に必要な「環境」を作り出す。このような「細胞外環境」は、細胞が分泌あるいはその表面に提示するプロテアーゼによって分解・再編され、新たな機能を獲得する、きわめて動的なもののようだ。形態形成過程で多数の細胞が統制のとれた挙動を行うためには細胞外環境の構造と機能の正確な時空間的制御が必須であるが、そのメカニズムの理解はまだまだ不十分である。本シンポジウムでは形態形成における細胞外環境の役割解明に向けた最近の研究に焦点をあて、この新しい生命科学領域の近未来像を探る。
Sp1B 重複受精研究の進展〜新発見が続く植物生殖研究の最前線〜
世話人:木下 哲(国立遺伝研・育種遺伝研)、東山 哲也(東大・院理)
被子植物の受精は、花器官の奥深くでおこるため、これまで容易には解析できなかった。また、多くの生物種に見られる一つの卵子と一つの精子との融合とは違い、いわゆる「重複受精」と呼ばれる被子植物特有のシステマティックなプロセスでおこなわれる。近年、これまで謎の多かった被子植物の受精のプロセスが次々と明らかにされつつある。花粉の自己非自己の認識や、花粉管がめしべの中を卵細胞に向かう機構、原生動物までにも普遍性を示す精細胞膜タンパク質による受精の制御、アレル間の遺伝子発現のエピジェネティックな制御、生殖隔離機構など、世界レベルの発見が次々と日本の研究グループから報告されている。本シンポジウムでは、このように大きな進展を見せる生殖研究の最前線を紹介し、議論したい。
Sp1C クロマチンと高次生命現象の接点を探る
世話人:田上 英明(名市大・院システム自然科学)、中山 潤一(理研・CBD)
「ヒストンコード」に代表されるクロマチン上の情報は、遺伝子発現調節のような一過的な機能を持つだけでなく、細胞分裂や個体の発生・分化を通じて維持されることにより、同じ遺伝情報を持つ細胞間の異なった表現型(エピジェネシス)を規定する大きな要因の一つとなっている。本シンポジウムでは、クロマチンのダイナミックな構造変換とそれを維持する分子機構が、どのように発生や分化といった高次生命現象の理解へつながるのか、異なる視点からアプローチしている国内外の若手研究者を中心とした研究からその接点を探ることを目的とする。クロマチン制御の分子メカニズムの追求と、クロマチン構造制御を介した複雑な生命現象の理解を目指す研究を繋ぐことで、古くて新しいクロマチン機能研究の将来を模索する場となることを期待する。
Sp1D 免疫系・血液系細胞の生体内での移動・定着とその時間空間的制御
世話人:長澤 丘司(京大・再生研)、福井 宣規(九大・生医研)
哺乳動物は、複雑な三次元構造を持つ組織で構成され、組織内部や、異なる組織間における細胞の移動や定着は、その高次機能を遂行するために重要である。中でも免疫系・血液系の細胞は、生体で最も運動性に富んだ細胞系列のひとつで、その形成過程や免疫反応などの機能発現においてダイナミックあるいは精緻に移動・定着を行い、近年の研究により、その時間空間的制御の分子機構の理解が大きく進展している。本シンポジウムでは、その中から、分子・細胞・個体レベルにわたる最前線の研究のいくつかを紹介する。
Sp1E Integrative approaches for evolutionary developmental biology.
世話人:田村 宏治(東北大・院生命科学)、倉谷 滋(理研・CDB)
Evolutionary developmental biology (Evo. Devo.), which addresses many issues on evolution and diversity of organisms from morphogenetic mechanisms during development, is one of the oldest but most prosperous fields in biology. This field is characterized by its integrative nature, which does not only focus on embryology and developmental biology from a comparative evolutionary perspective, but also utilizes other discipline and approaches, including molecular evolution, system/theoretical biology, paleontology, and molecular biology. This session will focus on some current topics in Evo. Devo., and we will discuss molecular aspects of framework of diversification in animals.
Sp1F プロテインキナーゼが制御するシグナル伝達経路
世話人:松本 邦弘(名大・院理)、辻 順(North Carolina State Univ.)
細胞内シグナル伝達経路は、外界からの情報に対して細胞が適切な応答を行い、発生分化の方向の決定や生体の恒常性の維持において必須の役割を果たしている。この細胞応答には、遺伝子発現パターンの変更や細胞死の誘導が含まれる。この細胞内シグナルはネットワークを形成し、複数の分子がそれぞれの刺激に応じて異なる役割を果たしている。近年の研究では、この細胞内シグナルネットワークが、どのようにつながり、どのように制御されているのかを解明することが重要な課題となっている。本シンポジウムでは、細胞内シグナルネットワークの重要な因子であるプロテインキナーゼに注目して、ネットワーク全体における役割と制御機構を議論する。
Sp1G 生命科学の革新的ナノバイオロジー
世話人:野地 博行(阪大・産研)、竹内 昌治(東大・生産技術研究所)
本シンポジウムでは、ATP合成酵素やべん毛モーターなど回転分子モーターのナノバイオ研究を紹介する。特に、自ら新しい方法論を開発することで分子メカニズムの本質に迫る研究を行っている若手研究者に最新の成果を発表してもらう。紹介する革新的技術は、マイクロデバイスを用いた新しい1分子計測技術、タンパク質の局所的構造変化を検出する1分子計測技術、タンパク質の構造変化の分子シミュレーション技術などである。また、立体構造解析から明らかになったATP合成酵素とべん毛モーターの意外な共通性に関しても発表する。
Sp1H 統合失調症と気分障害の病態生理研究の動向
世話人:尾崎 紀夫(名大・院医)、橋本 亮太(阪大・院医付属子どものこころの分子統御機構研究センター)
統失調症と気分障害は、ともに発症頻度が高く、自殺、休務など大きな社会的問題を引きおこすが、現在の治療法では十分に対応できない難治・再発例が多い。したがって、その病態を解明して、病態に基づく治療法・予防法を見いだすことが強く望まれている。近年、分子生物学、ゲノム医学、脳科学、神経画像など諸科学の進展により、統合失調症と気分障害の病態研究は徐々に進展しつつある。本シンポジウムでは、多様な手法で統合失調症と気分障害の病態にアプローチしている研究を紹介することとした。なお、本学会の会員の多くが臨床医でないことを想定して、疾患概念を概説した上で、研究動向を触れることにする。本シンポジウムを切っ掛けとして、分子生物学を主たる方法論としている研究者の方々にこの分野への関心を一層深めていただき、新たな研究方向性が創出され、臨床に還元できる日が来ることを期待している。
Sp1I 動く遺伝子:ゲノム多様化と新規機能獲得へのインパクト
世話人:古賀 章彦(名大・院理)、大坪 久子(東大・分生研)
レトロトランスポゾンに代表される動く遺伝子は、ゲノム再編をもたらすことで進化に貢献している“はず”、との推測は、従来からなされていた。その貢献の実態が最近次々に明らかにされており、目を見張る成果が多い。そのような成果のうちから、幅広い分野の研究者の興味の対象となるものを選び、講演と討論を行う。取り上げる話題は、哺乳類における胎盤形成能の獲得、哺乳類細胞の多分化能維持、昆虫のテロメアの形成や維持、ゲノムの安定性の制御に関与する因子を予定している。また、動く遺伝子の応用では、従来の遺伝子導入や突然変異誘発に加え、系統分類に確実な情報をもたらすツールとしての利用が注目されている。その最新の成果の紹介も予定している。
Sp1J メンブレントラフィックの奔流−分子から高次機能へ−
世話人:中野 明彦(東大・院理)、中山 和久(京大・院薬)
細胞が正常に機能するため、ひいては生体が正常に機能するためには、タンパク質や脂質が機能すべき適切な部位(オルガネラや細胞膜)に運ばれたり、細胞外に分泌されたり、不必要な時には分解されたりしなければならない。本シンポジウムでは、これらの細胞機能を調節するための基盤となるタンパク質や脂質のメンブレントラフィックに関して、第一線で活躍する研究者に分子レベルから個体レベルに至るまでの最新の知見を紹介していただき、今後の展望についての討論を行なう。
Sp1K 細胞極性のしくみ
世話人:貝淵 弘三(名大・院医)、松崎 文雄(理研・CDB)
細胞は極性を持つことで、非対称に分裂したり、ニューロンや上皮細胞にみられるように、機能的な形態を獲得し、また、決まった方向への細胞移動が可能になる。このように、細胞極性はそれぞれの細胞の振る舞いや形態を制御することにより、また、細胞間の相互作用を統制することによって、細胞集団の機能的な構築やダイナミクスに重要な役割を果たしている。本シンポジウムでは、先端的な研究を行っている若手研究者を中心に、細胞が極性を形成するしくみとその役割について議論する。
Sp2B 高等動物細胞に特異的な細胞周期制御機構
世話人:中西 真(名市大・院医)、北川 雅敏(浜松医大・生化学1)
自己複製は生命にとり必須の属性であり、真核細胞の増殖は細胞周期制御機構により調節されている。細胞周期制御機構は基本的にサイクリン依存性キナーゼの時期特異的活性化によりその進行が制御される点で、酵母からヒトに至るまでよく保存されている。しかしながら、最近の研究から高等動物細胞独自の周期進行制御、あるいはチェックポイント制御機構の存在が示され、これらの特異的な機構の破綻が多細胞生物体に見られる癌・老化等の様々な増殖異常疾患群の基盤となっていることが明らかとなりつつある。本シンポジウムでは哺乳動物細胞独自の細胞周期調節機構に焦点をあてて紹介し、疾患との関連について議論していきたい。
Sp2C 神経シナプスにおけるシグナル伝達機構
世話人:深田 正紀(国立長寿医療センター研究所)、尾藤 晴彦(東大・院医)
神経シナプスにおけるシグナル伝達機構は、シナプス蛋白質の局在や機能を制御して、シナプス形態やシナプス伝達効率を変化させる。シナプスにおけるシグナル伝達機構の解明は記憶や学習だけでなくシナプス機能が変化する精神神経疾患、認知症、てんかん等の病態を理解する上でも極めて重要である。近年のゲノム解析、質量分析法を用いた生化学的解析、および神経細胞生物学的解析によりシナプス構成蛋白質の同定および性状解析が次々と進んでいる。本シンポジウムでは新進気鋭の神経科学者らにより、シナプス形成、維持およびシナプス可塑性を制御する分子メカニズムについて、蛋白質相互作用、翻訳後修飾、遺伝学および生理学などの観点から最新の話題を提供したい。
Sp2D 生殖細胞を規定する機構
世話人:相賀 裕美子(国立遺伝研・発生工学研究室)、小林 悟(基生研・統合バイオサイエンスセンター)
生殖細胞は唯一次世代に受け継がれる細胞で発生の初期に体細胞系列と分かれて分化し、体細胞に囲まれて発生しながらもその特質を維持し、生殖細胞に特異的な性質を確立する。発生遺伝学的解析の進んでいるショウジョウバエとマウスにおいては、最初の生殖細胞確立機構としては、異なったストラテジーをとりながらも、進化過程を通じて維持されてきた共通の機構をも有することが明らかになってきた。今回は特に生殖細胞の初期分化機構の解析を精力的に進めている若手研究者を中心に、最近の研究成果について発表してもらう。
Sp2E 器官形成を支える細胞のふるまい
世話人:高橋 淑子(奈良先端大・バイオサイエンス)、西井 一郎(理研・FRS)
多細胞体制を支える基本単位は細胞である。個体発生が進行する際、細胞はある場所にとどまって細胞増殖や遺伝子発現を制御するのみならず、体の中をダイナミックに動きまわってさまざまな器官形成にあずかる。個々の細胞の移動や運動のメカニズムについては、これまで主に2次元的培養細胞を用いて研究がおこなわれ、多くの新規分子が同定された。一方で、細胞をとりまく環境は、培養条件内(2次元)と体内(3次元)では著しく異なることもわかり始めてきた。本シンポジウムでは、1)個体発生中の器官や組織形成の過程において、どのような細胞がどのようにふるまうのか、2)それらの細胞のふるまいがその後の器官形成にどのような役割をもつのか、3)それらの細胞のふるまいは、3次元環境の中でどのような制御を受けるのか、などについて、オリジナルな研究の最新の成果にふれ、それらをもとにディスカッションしたい。
Sp2F ホルモンと低分子RNAによる植物発生制御
世話人:上野 宜久(名大・院理)、深城 英弘(神大・理)、長谷部 光泰(基生研・生物進化研究部門/総合研究大学院大・生命科学研究/ERATO分化全能性進化プロジェクト)
植物の発生は、細胞の増殖と分化の制御の上に成り立っている。植物ホルモンが細胞の増殖や分化を制御できることは半世紀ほど前から知られていたが、個体発生におけるこの増殖・分化の制御の実体は、現在でもまだ十分には理解されていない。近年のシロイヌナズナを中心とした発生遺伝学的解析などから、転写因子のネットワークだけではなく、実際にオーキシンなどの植物ホルモンや、これに加えて低分子RNAがこの制御の重要な鍵分子として浮上してきている。また、比較ゲノム解析からこれらの制御機構は植物進化の過程でダイナミックに変化してきたことが明らかになってきた。本シンポジウムでは、異なった局面からこの問題に迫る演者の先生方に、最新の成果を紹介していただく。
Sp2G オルガネラDNAの片親遺伝の様式と分子機構
世話人:杉山 康雄(名大・遺伝子実験施設)、林 純一(筑波大・生命環境)
ミトコンドリアと葉緑体は、それらのゲノムDNAと共に、すべての動植物で非メンデル型遺伝する。一部の二枚貝を除き、現在までに調べられたほとんどすべての動物ミトコンドリア(mt)DNAは母性遺伝し、精子mtDNAは受精卵において選択的に排除される。また母性遺伝する植物の葉緑体(プラスチド)DNAは花粉が成熟する過程で精細胞から排除される。一方、花粉の精細胞におけるmtDNAの選択的分解については疑問があり、また、受精卵でのmtDNAの様子は良く分かっていない。さらに植物では父性遺伝する種も知られていて話は複雑である。このシンポジウムでは、片親遺伝する動物と植物についての研究の現状を紹介し、互いの共通点と相違点を整理する。そしてモデル生物(マウス、メダカ)の母性遺伝の解析に利用された高感度DNA検出技術、ホモプラスミックなオルガネラDNAでは本来不要な組換えの存在について紹介し、今後の分子機構の解明に向けて動物と植物の研究者が同じ土俵で議論する。
Sp2H DNAの修復と再編成−安定性と多様性とのトレードオフ
世話人:武田 俊一(京大・院医)、井倉 毅(東北大・院医)
クロマチンタンパクの修飾(リン酸化、ユビキチン化など)は遺伝子発現制御に重要な役割をもつ。この修飾は、DNAの修復や再編成もコントロールしていることが解明されつつある。複雑な転写制御機構と異なり、修復や再編成は、必ずDNA損傷発生によって開始される。そのため、人工的に誘導された損傷で開始され修復や再編成に至るまでの、クロマチンタンパクの修飾・ダイナミックスを様々なミュータントで経時的に解析できる。すなわちクロマチンレベルのダイナミックスやその生物学的意義が研究している上で、DNA修復と再編成は優れたモデルである。これまでDNAに直接に働きかける分子だけを解析してきた研究から、クロマチンレベルの分子機構解析にも展開しつつあるDNA修復と再編成の先端的研究を紹介する。
Sp2I 構造プロテオミクスの分子生物学への寄与−転写・翻訳のメカニズム−
世話人:田中 勲(北大・院理)、横山 茂之(理研・ゲノム科学総合研究センター)、西村 善文(横浜市立・院国際総合科学)
構造生物学の手法(タンパク質調製、X線結晶構造解析、NMR解析等)の進歩はめざましく、多くのタンパク質や核酸などからなる複雑なシステムの理解をめざした研究(構造プロテオミクス)が進められている。我が国でも平成14年度から本年度まで、「タンパク3000」プロジェクトが行われ、重要なタンパク質について従来は考えられなかったほど多数の構造解析がなされている。本シンポジウムでは、「タンパク3000」プロジェクトの分子生物学への寄与について紹介する。特に、転写・翻訳のメカニズムに焦点を当てる。転写では、RNAポリメラーゼ、様々な転写因子、真核生物の染色体構造の制御因子などについての構造解析が進められ、基本的分子機構から制御のメカニズムまで解明が進み、疾患との関係などもわかってきた。翻訳では、tRNA関連酵素、翻訳因子、リボソームなどの構造解析が進められ、翻訳の基本的メカニズムが次々と解明されている。
Sp2J 再生医療の最前線
世話人:山中 伸弥(京大・再生研)、出澤 真理(京大・院医)
幹細胞生物学や組織医工学などからなる再生医学研究は日進月歩で進んでおり、皮膚、骨や軟骨、角膜などにおいて臨床応用が実現している。また神経組織、骨格筋、心筋、膵臓β細胞などに関する研究も進んでおり、これらの再生医療も近い将来に実現される可能性がある。脊髄損傷、パーキンソン病、筋ジストロフィー、心不全、若年型糖尿病など多くの疾患への応用が期待される。本シンポジウムにおいては、再生医療を実現するためにどのような研究が行われているのかに関して、その現状と展望を紹介する。
Sp2K ゲノムネットワーク解析に基づく新しい創薬、診断、治療戦略
世話人:柳川 弘志(慶大・院理工)、宮本 悦子(慶大・院理工)
ポストゲノム時代に入り、ゲノム機能解析を生命現象の理解や疾患メカニズムの解明へ具体的に結びつけることを加速させる技術が所望されている。タンパク質相互作用解析やタンパク質機能解析技術の紹介と、それらの方法で得られたデータを用いたバイオインフォマティクスによるネットワーク解析、創薬、診断、治療への応用とその戦略として、内因性機能ペプチドの予測やモチーフと相互作用する低分子化合物の予測、"Omics"を用いた病理病態からの癌の診断と治療の展望などを議論する。
Sa3B 植物高次生命現象を司るオルガネラ機能
世話人:吉岡 泰(名大・院理)、明賀 史純(理研・植物科学研究センター)
ゲノム解読や様々なオーム解析によりゲノム関連情報が急速に蓄積されつつある。しかし、それによって直ちに代謝・生理・発生・行動・環境応答といった高次生命現象の分子基盤が理解できるわけではない。高次生命現象の分子基盤を理解するためにはオルガネラ、細胞、組織、器官、個体といった高次のレベルにおいて生体分子が形成するダイナミックなネットワークを解明する必要がある。本ワークショップでは植物オルガネラの機能に関して先端的な研究を行なっている研究者を演者とし、代謝・生理・発生・環境応答などの高次生命現象を支える植物オルガネラの機能に焦点をあて、高次生命現象の分子基盤をになうオルガネラ機能について議論する。
Sa3C 細胞膜のセンサーの作動原理
世話人:川岸 郁朗(名大・院理)、富永 真琴(岡崎統合バイオサイエンスセンター)
さまざまな感覚・環境応答系において、刺激の受容と細胞内への情報伝達を司るのは膜貫通型受容体である。膜貫通型受容体は、出力制御様式によって大まかにイオンチャネル共役型、Gタンパク質共役型、酵素共役型の3タイプに分けられる。いずれのタイプについてもさまざまな系において精力的に研究が進められており、多くの知見が得られている。しかしながら、それらの作動原理、すなわち膜の外から内への情報伝達のメカニズムについては依然として謎も多い。本シンポジウムでは、動物・植物・細菌におけるさまざまな膜貫通型受容体の作動原理についての最先端の知見を紹介し、それらを比較することによって普遍性や多様性について考察出来る場を提供したい。
Sa3D 細胞死の多様な調節機構と生理機能
世話人:三浦 正幸(東大・院薬)、後藤 由希子(東大・分生研)
細胞死の分子メカニズムが詳しく研究され、アポトーシス機構の詳しい理解に加え、非アポトーシスによる細胞死の調節機構も少しずつ明らかにされてきている。細胞死調節因子の生理機能を発生や疾患といった個体レベルで調べる研究が行われた結果、これら因子の多彩な機能が浮き彫りにされてきた。本シンポジウムでは、多彩な細胞死調節機構とそれぞれの因子の新たな生理機能を追求している先端の研究を若手研究者から紹介していただき細胞死研究の新たな展開を議論したい。
Sa3E 組換え、修復によって維持されるゲノムの恒常性
世話人:小林 武彦(基生研・ゲノム動態)、益谷 央豪(阪大・院生命機能)
ゲノムの恒常性(安定性)を維持することは、生物にとって最も重要な作用の1つである。近年加速するオゾン層破壊による有害放射線の増加、人類の生産活動に伴う変異物質、発癌物質の蔓延は、このまま続けば将来的にゲノムを危機的状況へ追いやると予想され、そのリスクを低減することは人類にとって環境、医学両面での緊急課題である。ゲノムの損傷は外的要因と、それに起因するDNA複製障害等の内的要因によって主に引き起こされる。本シンポジウムでは、ゲノムの恒常性を維持する主要な手段であるDNA組換え及び修復研究を精力的に行っている研究者に、膨大で脆弱な遺伝情報が如何に日々維持されているのか、その機構について最近の知見を中心に発表願う。
Sa3F 比較ゲノム研究による生命システム解明への挑戦
世話人:小原 雄治(国立遺伝研)、藤山 秋佐夫(国立情報学研究所)
「生命の歴史は染色体に記されてある」とは60年前の木原均博士の言葉である。現在、ゲノムシーケンシングの技術の進展により様々な生物のゲノム配列が明らかとなり、この言葉が具体化しつつある。例えば、進化上様々な位置にある生物のゲノム配列の比較から祖先ゲノムの解明などゲノム進化の詳細が明らかになりつつあるし、遺伝子組成の比較から、生物のシステムとしての進化についても解明の努力がなされている。さらに、種内の多様なゲノム比較からは、疾患遺伝子を始め、体質など様々な形質の遺伝的基盤の解明が進行中である。いわば自然が与えてくれた「システムの変異体」の比較解析アプローチといえよう。ここでは、このようなアプローチに関する最新の研究成果を紹介いただき、その先にあるべき生命システムの解明に向けた研究の方向について議論したい。
Sa3G 植物の細胞増殖制御と発生・分化のクロストーク
世話人:伊藤 正樹(名大・院生命農学)、佐藤 豊(名大・院生命農学)
細胞増殖制御に関する多くの知見は、酵母や培養細胞などの単細胞の系を用いた細胞周期研究によりもたらされてきた。一方で多細胞体構築の過程における細胞増殖は、細胞間相互作用などを介した複雑な発生的制御を受けていると考えられる。一般に植物の器官が形成される過程では、初期において盛んであった細胞増殖が、発生が進むにつれてその程度が低下し、やがて停止する。このような増殖の発生的な変化はどのようにもたらされるのか。また、植物の器官や個体はおおよそ一定の大きさや形になるように遺伝的に決定されているが、細胞増殖制御はこれにどのように関連しているのか。多くの場合、増殖の停止と細胞の分化が平行して起きるが、これらはどのような関係にあるのかなど、植物の発生を理解する上で本質的な問題が多く残されている。このような問題に関連する最新の研究例をご紹介いただき、今後の方向性について展望したい。
Sa3H 構造生物学の新しい可能性
世話人:前田 雄一郎(名大・理)、甲斐荘 正恒(名大・理)
今後の生命科学の進歩のためには、構造生物学は蛋白質の結晶構造を決めるだけでは不十分である。蛋白質の機能発現のメカニズムを理解するためには、蛋白質分子の動き(揺動)を深く知る必要がある。また、細胞内での各蛋白質分子の配置やその離合集散を俯瞰的に把握して、細胞生物学との橋渡しも必要である。これらの問題を解くための手法も開発されてきている。本シンポジウムでは、その一端として、大きな複合体の構造解明(クライオ電子顕微法)、遺伝病の原因変異を使っての構造・機能連関の解析、従来の分子量限界を超える新しいNMR法、複数の測定手法を組み合わせてメカニズムの解明へ接近している研究の具体例などを取り上げ、新しい研究戦略を議論したい。なお、特に意図したわけではないが、具体例は細胞運動、細胞骨格の分野が中心となっている。
Sa3I ニューロンの誕生と移動
世話人:宮田 卓樹(名大・院医)、星野 幹雄(京大・院医)
1906年のノーベル賞は、「神経系が,ニューロンという基本素子の、非融合的相互接触による集合体として構成されている」との概念を提示したカハールと、その証明技術を先立って提供していたゴルジに対して与えられた.それからちょうど100年。いま、我々は、さまざまな分子/細胞/発生生物学的手法を用いることによって、ニューロンがいかにして生まれ、個性を持ち、適切な場所に配され、成熟し、成体における脳機能の発揮に至るのかという問題を解きほぐそうと努力を続けている。本シンポジウムでは、ニューロンの誕生とその前後の主要な出来事、すなわち神経前駆細胞集団としての「神経上皮」の「領域化」から、ニューロンを作り出すための前駆細胞による「細胞周期」の進行と「(対称または非対称な)細胞分裂」、そして、娘ニューロンの「(法線方向または接線方向への)移動」と「配置」までに焦点をあて、数人の演者によるthought-provokingな発表を予定する。
Sa3J 幹細胞研究の展開
世話人:岡野 栄之(慶大・医)、阿形 清和(京大・院理)
病気や怪我などで傷付いたり、失われた人体の様々な細胞・組織を元通りに修復する医療の開発を目指し、生物学の古典的な研究テーマである「再生」が、大きくクローズアップされてきている。「再生」とは生体の失われた細胞・組織が、幹細胞の増殖・分化や分化した細胞の分化転換によって補われることと定義される。今、哺乳動物を対象とし、発生過程を一部再現させることにより臓器再生を目指そうという新しい学問潮流が生まれつつあり、まさにこれに立脚した治療哲学である「再生医学」(その実践が「再生医療」)が21世紀の医学の進むべき一つの方向であると期待されている。再生を誘導するためには、色々な臓器を作るもとになる細胞である「幹細胞」が重要である。幹細胞には、各々の臓器に固有の臓器幹細胞(造血幹細胞、神経幹細胞など)の他に、初期胚由来の多能性幹細胞であるES細胞(胚性幹細胞)が含まれる。現在、これらの幹細胞を用いた再生医療に熱い注目が集められている。本講講演では、幹細胞を用いた再生医療の現状と展望について述べてみたいと考える。
Sa3K ゲノム情報発現制御因子としてのNoncoding RNA <Noncoding RNAs as regulators of gene expression>
世話人:廣瀬 哲郎(産総研・生物情報解析研究センター)、塩見 春彦(徳島大・ゲノム機能研究センター)
最近のエピジェネティックスにおけるnoncoding RNA (ncRNA)の役割やmicroRNA等の小分子ncRNAの発生・分化、細胞増殖、そして細胞系譜、さらには幹細胞の増殖とその維持における役割が明らかになるにつれて、急速に、ゲノムのnoncoding領域に重要な‘遺伝学的活性’があり、 それがncRNAというカタチで情報を発信していることが見えてきた。したがって、従来のセントラルドグマに加え、ncRNAが情報発現ネットワークにおける重要な制御分子として機能することで、極めて多様で複雑な高性能システムの創造を可能にしているのではというコンセプトが提唱されるに至っている。本シンポジウムでは、大腸菌からヒトまで様々な分野のncRNA研究者を結集し、できる限り多くの視点からncRNAの機能を考えることで、「生命活動を支えるRNAプログラム」を議論する。
Sp3B 生物リズムの制御メカニズム−刻々と変化する生命現象−
世話人:程 肇(三菱生命研)、八木田 和弘(名大・理)
生物リズムは、遺伝子発現やタンパク質修飾および安定性などの状態を刻々と変化させ、しかもまたある一定時間後に初期状態に戻るという振動現象を制御する非常に動的な生命システムである。ここから派生する生理現象は多岐にわたり、生物にとってかなり根源的なものであると考えられる。最近、生物リズム研究において、概念の転換をもたらす発見が相次いでおり、パラダイムの再構築に向けた活発な研究が内外で進んでいる。同調や安定性といった性質も包含した「振動」の仕組みについて議論し、generalな生命現象としての生物リズムの捉え方と方向性を考える。
Sp3C 膜タンパク質の挙動/構造変化を追う
世話人:小嶋 誠司(名大・院理)、森 博幸(京大・ウイルス研)
ここ数年の膜タンパク質の研究の進展は目覚ましく、ゲノム情報の蓄積や界面活性剤の改良、精製・結晶化の簡便化に伴い、最近では高解像度の結晶構造が次々に報告されるようになった。その結果、タンパク質の構造をもとに変異導入解析の結果を解釈できるようになり、ようやく膜タンパク質においても機能発現メカニズムを原子レベルで説明できる時代になりつつある。次の課題は膜タンパク質のダイナミックな動きと機能発現との相関を明らかにして行くことである。そこで、本シンポジウムでは、様々な手法を用いてこの問題に取り組まれている若手の先生方に最新の研究成果を御紹介いただく予定である。議論の中で新たなメソッド開発のヒントが得られればと考えている。
Sp3D シグナリングシステムの時空間的制御による位置情報の設定と形態形成
世話人:多羽田 哲也(東大・分生研)、濱田 博司(阪大・院生命機能)
細胞外シグナル因子が生体をデザインする仕組みは形態形成の中心課題として今なお詳細な解析が続いている。ヘッジホッグ、Wnt、BMPのように長距離に働く因子群から、Notchのように隣接した細胞に働きかける因子群まで、比較的少数の因子群とその信号伝達系により、きわめて多様な機能と形を持った組織が形成される。これらの研究は発生の体軸の形成という巨視的な文脈での解析に始まり、現在では個々の細胞の3次元の位置を視野に入れた、より精密な構造も対象となりつつあり、複数のシグナリングシステムの時空間的な制御および相互作用の様式が解析の焦点となっている。本シンポジウムでは協調して機能する複数のシグナリングシステムによる位置情報の設定機構を中心に、体構造を構築するメカニズム解明の最先端を紹介する。
Sp3E 新たな発がん研究を目指して−がん幹細胞からモデル動物まで
世話人:高橋 雅英(名大・院医)、佐谷 秀行(熊本大・院医学薬学)
過去20年間のがん遺伝子、がん抑制遺伝子の研究により、発がんの分子メカニズムの理解が急速に進んできた。最近さらに、新たな視点により、さまざまな興味ある発がん研究が各分野で展開されつつある。本シンポジウムでは5人のシンポジストにより、1) 乳がんおよびグリオーマ細胞株に内在するがん幹細胞様細胞の解析、2)H. pyloriによる胃粘膜前駆細胞のDNAメチル化異常と発がん、3)がん細胞の分裂異常におけるAurora-Aの役割、4)Aktシグナルとがん細胞の運動、浸潤能の制御機構、5)消化器がん発生におけるWntシグナルとプロスタングランジン合成酵素Cox-2の相互作用とその個体レベルでの解析について最新の知見を紹介してもらう。
Sp3F 翻訳とmRNA安定性制御
世話人:稲田 利文(名大・院理)、星野 真一 (名市大・院薬)
翻訳とmRNA分解は遺伝子発現の重要な制御段階である。特に最近miRNAによる標的mRNAの発現抑制や、mRNA品質管理機構において必須な役割を果たすことが明らかになり、その分子機構の解析が進んでいる。本シンポジウムでは、様々な細胞種におけるmRNA分解と翻訳制御に関する最近の知見を紹介する。真核生物におけるポリ(A)短鎖化の分子機構、生殖細胞形成機構におけるmiRNAによるポリ(A)短鎖化の役割、生殖質形成における母性mRNAの局在と翻訳制御機構について紹介する。またmRNA品質管理機構について、NMD(ナンセンス依存分解系)の分子機構、ノンストップmRNAの発現抑制における翻訳抑制の役割などの最新の知見を紹介する。さらにNGD(翻訳伸長阻害によるmRNA分解)の代表例として、植物における新生ポリペプチド鎖に依存した翻訳停滞とmRNA分解について紹介する。
Sp3G 生物進化の遺伝メカニズム−生物環境適応と重複遺伝子の分子進化−
世話人:渡邉 正勝(東工大・院生命理工)、郷 康広(総合研究大・先導科学研究)
生物の多様性獲得には、ゲノム上の様々な変異や再編などが大きな役割を果たす。オオノが今から35年以上前に指摘したように、中でも重複遺伝子が進化の原動力として果たす役割は特に大きい。例えば、免疫関連遺伝子群や感覚感受性遺伝子群などに代表される重複遺伝子群においては、生物が環境に適応する過程で多種多様な選択圧にさらされ変異・機能分化し、様々な多様性を獲得してきた。本シンポジウムでは、生物多様性の中でも環境への適応や個体間の相互認識といった種の形成に直接関わることが示唆される現象に着目し、これらに関係ある遺伝子群の進化と表現形の進化との関係性を論じる。
Sp3H 脳のはたらきの統合的解析:遺伝子〜神経回路〜行動
世話人:木村 幸太郎(国立遺伝研・構造遺伝学研究センター)、小田 洋一(名大・院理)
動物の脳は、外界や動物内部からの情報を処理し、行動するため制御信号を出力します。このような脳のはたらきをになう神経回路の構造と機能については、今日さまざまの研究手法により神経回路の構成、回路を形成するニューロンの性質やその分子基盤、さらにその分子をコードする遺伝子まで精力的に調べられるようになりました。ことに最近の遺伝子工学的手法はそれぞれのキィファクターに迫る強力な手法として注目されます。しかし、個々の局面を断片的に調べるだけでは脳のはたらきの理解には到底結びつきません。遺伝子〜神経回路〜行動といった異なる階層を密接に関連づけた統合的な解析が今こそ求められています。本シンポジウムでは、第一線で活躍する研究者の「脳のはたらきを統合的に解析」しようとするチャレンジと、線虫から哺乳類に至るさまざまのモデル動物を用いた成果を、分野外の研究者にも分かり易く説明していただき、議論する予定です。
Sp3I プロジェクト型研究時代の生命科学の課題
世話人:大久保 公策(国立遺伝研・生命情報・DDBJ研究センター)、高木 利久(東大・院新領域)
ゲノム研究以降の大型プロジェクトは目論見どおりの知的基盤としての役割を果たせているか。大型の測定プロジェクトと知的な生産性の関係について分析し、プロジェクト研究の成果を知的生産性に繋げる方策について考える。
Sp3J 人類生存に役に立つ植物研究とは?
世話人:松岡 信(名大・生物機能開発利用研究センター)、西澤 直子(東大・農)
植物は光合成を行い、太陽エネルギーを化学エネルギーに変換できる一次生産者であり、地球環境の維持及び食糧供給など、我々人類の生存にとって必須の生物である。現在、地球レベルでの人口の増加や環境の悪化などの問題が深刻化することが懸念されており、これらの諸問題を解決する有効な手段として、植物の持っている形質のさらなる改良・利用が期待されている。最近、イネやシロイヌナズナのゲノム情報が開示されたことにより、これまでその複雑さ故に不可能だった農業的有用形質の分子レベルの解析が可能となり、理論に基づく作物育種が展開できるようになった。本シンポジウムでは、このような植物科学における基盤技術の革新が、現在人類に突きつけられている課題にどのように答えようとしているのか、また今後どのように答えていくのか、を具体的な取り組みを紹介することにより明らかにしたい。
Sp3K 染色体複製開始サイクルの分子機構と制御スイッチ
世話人:片山 勉(九大・薬)、西谷 秀男(九大・医)
染色体の複製開始においては、複製開始装置と複製伸長装置とのダイナミックな連係が行われている。さらに、複製開始装置を形成・制御する因子には、細胞周期シグナルや複製プロセスからのフィードバックシグナルとの連係を受け持つキーファクターも含まれている。このようにネットワーク連鎖の要(かなめ)となっている複製開始系においては、タンパク質機能の制御動態やDNA-タンパク質相互作用動態の多様性が一望できる。さらに最近はそれらが見事に集約統御されている様させ垣間見えるようになってきた。すなわち、この系は、タンパク質の低分子化合物結合による機能変化と分解、タンパク質高次複合体の形成と解離、DNA-タンパク質複合体の構造形成と変化など、多様な翻訳後制御原理を遺伝子発現制御原理とともに駆使して組み立てられているシステム統合体といえそうである。また、数種の生物を対象とした解析により、この系の構成における進化的保存性の特性にもより広い光条が届き始めた。このような背景のもとで、本シンポジウムでは実際に実験現場に立つ研究者の発表によって最先端研究を展望し制御原理への考察を深めたい。
日本分子生物学会は、例年年会が行われる12月に、本年は「日本分子生物学2006フォーラム(分子生物学の未来)」を開催します。ここでは、基礎生物学としての分子生物学の成果・展望のみでなく、成果の社会への還元についても議論できるような場とします。
発表および参加は日本分子生物学会会員に限定しませんので、多数の皆様のご参加をお願いいたします。
開催日:
2006年12月6日(水)〜8日(金)
会場:
名古屋国際会議場
組織委員 代表:
町田 泰則
(名古屋大学大学院理学研究科)
プレナリーレクチャー
Prof. Victor R. Ambros (Dartmouth Medical School, NH, USA)
「MicroRNAs in Animal Development」
上田 建仁 氏(トヨタ自動車 東富士研究所 常務役員)
「自動車技術の課題とバイオテクノロジーへの期待」
○シンポジウム
組織委員会・プログラム委員会にて、全50テーマのシンポジウムを企画しました。シンポジウムは同時に10会場で、3日間の会期中全日程で行います。
Sa1B 神経変性疾患研究の新展開:病態解明から治療まで
世話人:祖父江 元(名大・院医)、高橋 良輔(京大・院医)
パーキンソン病、アルツハイマー病、運動ニューロン疾患などの神経変性疾患の多くは、その病態が全く不明であった。しかしここ十数年の分子生物学的研究の進歩により、多くの神経変性疾患で異常蛋白質の凝集・蓄積が神経変性に共通するメカニズムであるらしいことがわかってきた。さらに最近は異常蛋白質の生成や分解、神経細胞に対する毒性発現のメカニズムが、個々の疾患について分子レベルで明らかになってきており、その知見に基づいた有望な治療法が提唱される新しい展開を迎えている。さまざまな方法論を駆使し、神経変性疾患の病態解明と治療法開発に迫ろうとする研究の最前線を、国内のトップ研究者が紹介する。
Sa1C 光環境と植物の適応戦略
世話人:井澤 毅(農業生物資源研究所)、和田 正三(基生研)
植物は、光合成により、光エネルギーを変換することで、栄養源を獲得、生存している。この一見、単純な生活環をおくっているかに見える植物であるが、発芽し、根を張った大地の自然環境、特に、その土地での日周変化・四季の変化といった刻々と変化する光環境に適応するために、フィトクロム・クリプトクロム・フォトトロピンといった植物光受容体を介した信号伝達系を駆使し、様々な生理反応を起こすことで、効率的に子孫を残すという、実は、かなり、したたかな生存戦略を身につけている。本シンポジウムでは、その植物がもつ光環境に対する適応戦略のいくつかを取り上げ、その分子メカニズムに迫りたいと考えてる。今回取り上げるのは、光を受けた直後に、「動き」として現れる、静的なイメージの強い植物からは、想像しにくい生理現象から、「青色光による気孔の光開口」と、葉の細胞が適量な光を受けるために、葉緑体が細胞内を移動する「葉緑体光定位運動」を取り上げる予定である。また、光環境の日周変動への適応に必須な「概日時計」、そして、日長変化 を認識することで、季節変化を予期し、適切な時期に開花をし、効率的に種子を残す戦略としての、「光周性花芽形成」を取り上げる。
Sa1D 生体応答システムと老化・寿命の分子メカニズム― 基礎老化研究から抗老化研究へ
世話人:鍋島 陽一(京大・院医)、石井 直明(東海大・医)
近年の寿命や老化に関わるモデル動物を使った研究から、老化の分子メカニズムが明らかになりつつある。その中でもエネルギー代謝とその副産物である酸化ストレスが注目されている。酸化ストレスは細胞に傷害を起こして老化を促進と同時に、生体防御因子として老化を抑制する役割も持つために、酸化ストレスの制御が老化の重要な鍵となる。一方、生体恒常性の維持が老化にともなう生理機能の減退に大きく関わっていることから、酸化ストレスの制御とともに、生体の応答システムが寿命や老化速度の決定に重要であることが明らかになりつつある。この生体応答システムはヒトにも存在することから、エネルギー代謝・酸化ストレスの制御や恒常性維持の老化への関わりを議論することにより、ヒトの老化のメカニズム解明と同時に抗老化へ展望できると考える。
Sa1E バイオイメージングでとらえる生命現象
世話人:上野 直人(基生研・形態形成)、野中 茂紀(基生研・バイオイメージング研究室(仮称))
分子生物学は、遺伝子工学を軸として大成功を納める一方、その分子が働く時間と空間については空間分解能・感度などの点で十分な解析手段を持ち得なかった。しかし今やようやく字義通りの「分子生物学」、すなわち実際の分子の挙動から生物学を理解するための方法論が揃いつつある。本シンポジウムでは、観察対象となる分子を標識するプローブ技術、それを実時間でとらえる顕微鏡技術という観点から、興味深い研究を行っている5人に発表していただく。今後の分子生物学の進むべき方向を考えたい。
Sa1F 細胞内のタンパク質社会と品質管理
世話人:遠藤 斗志也(名大・院理)、吉田 秀郎(京大・院理)
生命現象を担うのは、細胞内のタンパク質がつくる「タンパク質社会」である。そして細胞には、タンパク質社会が正しく働くよう、その状態を監視し、維持する「品質管理」システムが存在する。品質管理システムは異常タンパク質を検知すると、翻訳を抑えて負荷を減らし、異常タンパク質の修復や無毒化を図り、修復が成功しなければ分解にまわし、それでもダメなら細胞死を誘導する。品質管理を免れた異常タンパク質は、プリオン線維やアミロイドのような「秩序ある凝集体」を形成することがある。これらの凝集体はタンパク質社会全体にとって脅威であるが、一方で凝集形成は多くのタンパク質に共通する性質らしいことが分かってきた。本シンポジウムでは、こうしたタンパク質社会と品質管理に関する様々な話題を、最前線で活躍されている研究者の方々に紹介いただき、いままさに急速に展開しつつある分野の熱気を実感できるようなシンポジウムとしたい。
Sa1G 一分子生理学・バイオ分子操作
世話人:岩根 敦子(阪大・院生命機能)、吉村 成弘(京大・院生命科学)
細胞には、染色体、情報伝達物質、分子モーター、転写複合体に代表される様々なナノサイズの分子機械が存在し、細胞膜から核への細胞情報ネットワークが形成されている。これらの分子機械は、熱ゆらぎの中で絶えず相互に干渉したり、強調したり、時にはフィードバックを掛け合いながら働いている。このような分子間相互作用を時空間的に理解するには、従来の分子生物学的、細胞生物学的手法に加え、1分子イメージング、1分子ナノ操作という生物物理学的手法が有用である。ここでは、これらの1分子観察・計測の最新技術を紹介すると共に、これらの技術が生体反応の分子メカニズムを理解する上でどのように利用されているかを、最近のトピックスをまじえながら分かり易く紹介する。
Sa1H 蛋白質ネットワークによるエピジェネティクな遺伝子制御とその破綻
世話人:五十嵐 和彦(東北大・院医)、中尾 光善(熊本大・発生医学研究センター)
エピジェネティクスを支えるDNAやクロマチン因子などの化学修飾は安定ではあるが、可逆的に変化し得ることが示唆されている。化学基を導入する修飾システム、化学基を取り除く脱修飾システム、これらシステムの発動を指令する制御システムなどの実体が明らかになりつつある。本シンポジウムでは、遺伝子発現を調節するエピジェネティクス関連蛋白質システムに焦点を当てて、システム間の協調や拮抗作用、そしてその脱制御と癌化の関連について報告していただき、次の一手を探る機会としたい。
Sa1I 染色体・核のダイナミックな機能と構造
世話人:仁木 宏典(国立遺伝研・系統生物研究センター)、原口 徳子(情報通信研究機構・未来ICT研究センター)
ゲノム継承の仕組みを分子レベルで理解することは、生命科学の重要な問題である。ゲノムプロジェクトやプロテオミクスによる解析により、DNA複製過程 や分裂期での染色体分配に関与する因子が次々と発見されるなど、近年、急速 に分子レベルでの知見が蓄積されつつある。しかし、染色体は、いつでも・どこでも一定不変というものではなく、状況により場所により、時々刻々変化するものであることから、染色体の構造と機能を真に理解するためには、これらの分子機構を細胞核という空間で統合的かつ動的に理解することが重要であると考えられる。生命システムの統合的な理解を目指して、細胞核機能の時間的・空間的な制御機構の解明を、独自な視点で行っている研究を紹介する。
Sa1J 細胞骨格のダイナミクス
世話人:稲垣 昌樹(愛知県がんセンター研究所)、竹縄 忠臣(東大・医科研)
細胞骨格という研究分野は骨格筋や平滑筋収縮研究に始まった1950年代から続く息の長い研究分野である。細胞骨格の主要繊維としてアクチンフィラメント、微小管そして中間径フィラメントが同定されている。最近では蛋白質リン酸化シグナルや低分子量G蛋白質シグナルがこの構築制御系として同定されたことと、制御分子の可視化技術や部位特異的抗リン酸化ペプチド抗体の活用によって新展開をみせている。本シンポジウムではこの分野の最近のトピックスを紹介したい。
Sa1K 形態形成を制御する細胞外環境−その未知なるもの
世話人:西脇 清二(理研・細胞移動研究チーム)、瀬原 淳子(京大・再生研)
動物の発生過程における組織や器官の形態形成は細胞の増殖、分化、接着、移動などの細胞の活動によって成し遂げられる。しかしながら形態形成の過程では細胞のみならず「細胞の外」が重要な役割を果たすことが明らかになってきた。細胞はその外部に細胞外マトリックスを形成し、そこに種々のシグナル分子を分泌・配備することにより形態形成に必要な「環境」を作り出す。このような「細胞外環境」は、細胞が分泌あるいはその表面に提示するプロテアーゼによって分解・再編され、新たな機能を獲得する、きわめて動的なもののようだ。形態形成過程で多数の細胞が統制のとれた挙動を行うためには細胞外環境の構造と機能の正確な時空間的制御が必須であるが、そのメカニズムの理解はまだまだ不十分である。本シンポジウムでは形態形成における細胞外環境の役割解明に向けた最近の研究に焦点をあて、この新しい生命科学領域の近未来像を探る。
Sp1B 重複受精研究の進展〜新発見が続く植物生殖研究の最前線〜
世話人:木下 哲(国立遺伝研・育種遺伝研)、東山 哲也(東大・院理)
被子植物の受精は、花器官の奥深くでおこるため、これまで容易には解析できなかった。また、多くの生物種に見られる一つの卵子と一つの精子との融合とは違い、いわゆる「重複受精」と呼ばれる被子植物特有のシステマティックなプロセスでおこなわれる。近年、これまで謎の多かった被子植物の受精のプロセスが次々と明らかにされつつある。花粉の自己非自己の認識や、花粉管がめしべの中を卵細胞に向かう機構、原生動物までにも普遍性を示す精細胞膜タンパク質による受精の制御、アレル間の遺伝子発現のエピジェネティックな制御、生殖隔離機構など、世界レベルの発見が次々と日本の研究グループから報告されている。本シンポジウムでは、このように大きな進展を見せる生殖研究の最前線を紹介し、議論したい。
Sp1C クロマチンと高次生命現象の接点を探る
世話人:田上 英明(名市大・院システム自然科学)、中山 潤一(理研・CBD)
「ヒストンコード」に代表されるクロマチン上の情報は、遺伝子発現調節のような一過的な機能を持つだけでなく、細胞分裂や個体の発生・分化を通じて維持されることにより、同じ遺伝情報を持つ細胞間の異なった表現型(エピジェネシス)を規定する大きな要因の一つとなっている。本シンポジウムでは、クロマチンのダイナミックな構造変換とそれを維持する分子機構が、どのように発生や分化といった高次生命現象の理解へつながるのか、異なる視点からアプローチしている国内外の若手研究者を中心とした研究からその接点を探ることを目的とする。クロマチン制御の分子メカニズムの追求と、クロマチン構造制御を介した複雑な生命現象の理解を目指す研究を繋ぐことで、古くて新しいクロマチン機能研究の将来を模索する場となることを期待する。
Sp1D 免疫系・血液系細胞の生体内での移動・定着とその時間空間的制御
世話人:長澤 丘司(京大・再生研)、福井 宣規(九大・生医研)
哺乳動物は、複雑な三次元構造を持つ組織で構成され、組織内部や、異なる組織間における細胞の移動や定着は、その高次機能を遂行するために重要である。中でも免疫系・血液系の細胞は、生体で最も運動性に富んだ細胞系列のひとつで、その形成過程や免疫反応などの機能発現においてダイナミックあるいは精緻に移動・定着を行い、近年の研究により、その時間空間的制御の分子機構の理解が大きく進展している。本シンポジウムでは、その中から、分子・細胞・個体レベルにわたる最前線の研究のいくつかを紹介する。
Sp1E Integrative approaches for evolutionary developmental biology.
世話人:田村 宏治(東北大・院生命科学)、倉谷 滋(理研・CDB)
Evolutionary developmental biology (Evo. Devo.), which addresses many issues on evolution and diversity of organisms from morphogenetic mechanisms during development, is one of the oldest but most prosperous fields in biology. This field is characterized by its integrative nature, which does not only focus on embryology and developmental biology from a comparative evolutionary perspective, but also utilizes other discipline and approaches, including molecular evolution, system/theoretical biology, paleontology, and molecular biology. This session will focus on some current topics in Evo. Devo., and we will discuss molecular aspects of framework of diversification in animals.
Sp1F プロテインキナーゼが制御するシグナル伝達経路
世話人:松本 邦弘(名大・院理)、辻 順(North Carolina State Univ.)
細胞内シグナル伝達経路は、外界からの情報に対して細胞が適切な応答を行い、発生分化の方向の決定や生体の恒常性の維持において必須の役割を果たしている。この細胞応答には、遺伝子発現パターンの変更や細胞死の誘導が含まれる。この細胞内シグナルはネットワークを形成し、複数の分子がそれぞれの刺激に応じて異なる役割を果たしている。近年の研究では、この細胞内シグナルネットワークが、どのようにつながり、どのように制御されているのかを解明することが重要な課題となっている。本シンポジウムでは、細胞内シグナルネットワークの重要な因子であるプロテインキナーゼに注目して、ネットワーク全体における役割と制御機構を議論する。
Sp1G 生命科学の革新的ナノバイオロジー
世話人:野地 博行(阪大・産研)、竹内 昌治(東大・生産技術研究所)
本シンポジウムでは、ATP合成酵素やべん毛モーターなど回転分子モーターのナノバイオ研究を紹介する。特に、自ら新しい方法論を開発することで分子メカニズムの本質に迫る研究を行っている若手研究者に最新の成果を発表してもらう。紹介する革新的技術は、マイクロデバイスを用いた新しい1分子計測技術、タンパク質の局所的構造変化を検出する1分子計測技術、タンパク質の構造変化の分子シミュレーション技術などである。また、立体構造解析から明らかになったATP合成酵素とべん毛モーターの意外な共通性に関しても発表する。
Sp1H 統合失調症と気分障害の病態生理研究の動向
世話人:尾崎 紀夫(名大・院医)、橋本 亮太(阪大・院医付属子どものこころの分子統御機構研究センター)
統失調症と気分障害は、ともに発症頻度が高く、自殺、休務など大きな社会的問題を引きおこすが、現在の治療法では十分に対応できない難治・再発例が多い。したがって、その病態を解明して、病態に基づく治療法・予防法を見いだすことが強く望まれている。近年、分子生物学、ゲノム医学、脳科学、神経画像など諸科学の進展により、統合失調症と気分障害の病態研究は徐々に進展しつつある。本シンポジウムでは、多様な手法で統合失調症と気分障害の病態にアプローチしている研究を紹介することとした。なお、本学会の会員の多くが臨床医でないことを想定して、疾患概念を概説した上で、研究動向を触れることにする。本シンポジウムを切っ掛けとして、分子生物学を主たる方法論としている研究者の方々にこの分野への関心を一層深めていただき、新たな研究方向性が創出され、臨床に還元できる日が来ることを期待している。
Sp1I 動く遺伝子:ゲノム多様化と新規機能獲得へのインパクト
世話人:古賀 章彦(名大・院理)、大坪 久子(東大・分生研)
レトロトランスポゾンに代表される動く遺伝子は、ゲノム再編をもたらすことで進化に貢献している“はず”、との推測は、従来からなされていた。その貢献の実態が最近次々に明らかにされており、目を見張る成果が多い。そのような成果のうちから、幅広い分野の研究者の興味の対象となるものを選び、講演と討論を行う。取り上げる話題は、哺乳類における胎盤形成能の獲得、哺乳類細胞の多分化能維持、昆虫のテロメアの形成や維持、ゲノムの安定性の制御に関与する因子を予定している。また、動く遺伝子の応用では、従来の遺伝子導入や突然変異誘発に加え、系統分類に確実な情報をもたらすツールとしての利用が注目されている。その最新の成果の紹介も予定している。
Sp1J メンブレントラフィックの奔流−分子から高次機能へ−
世話人:中野 明彦(東大・院理)、中山 和久(京大・院薬)
細胞が正常に機能するため、ひいては生体が正常に機能するためには、タンパク質や脂質が機能すべき適切な部位(オルガネラや細胞膜)に運ばれたり、細胞外に分泌されたり、不必要な時には分解されたりしなければならない。本シンポジウムでは、これらの細胞機能を調節するための基盤となるタンパク質や脂質のメンブレントラフィックに関して、第一線で活躍する研究者に分子レベルから個体レベルに至るまでの最新の知見を紹介していただき、今後の展望についての討論を行なう。
Sp1K 細胞極性のしくみ
世話人:貝淵 弘三(名大・院医)、松崎 文雄(理研・CDB)
細胞は極性を持つことで、非対称に分裂したり、ニューロンや上皮細胞にみられるように、機能的な形態を獲得し、また、決まった方向への細胞移動が可能になる。このように、細胞極性はそれぞれの細胞の振る舞いや形態を制御することにより、また、細胞間の相互作用を統制することによって、細胞集団の機能的な構築やダイナミクスに重要な役割を果たしている。本シンポジウムでは、先端的な研究を行っている若手研究者を中心に、細胞が極性を形成するしくみとその役割について議論する。
Sp2B 高等動物細胞に特異的な細胞周期制御機構
世話人:中西 真(名市大・院医)、北川 雅敏(浜松医大・生化学1)
自己複製は生命にとり必須の属性であり、真核細胞の増殖は細胞周期制御機構により調節されている。細胞周期制御機構は基本的にサイクリン依存性キナーゼの時期特異的活性化によりその進行が制御される点で、酵母からヒトに至るまでよく保存されている。しかしながら、最近の研究から高等動物細胞独自の周期進行制御、あるいはチェックポイント制御機構の存在が示され、これらの特異的な機構の破綻が多細胞生物体に見られる癌・老化等の様々な増殖異常疾患群の基盤となっていることが明らかとなりつつある。本シンポジウムでは哺乳動物細胞独自の細胞周期調節機構に焦点をあてて紹介し、疾患との関連について議論していきたい。
Sp2C 神経シナプスにおけるシグナル伝達機構
世話人:深田 正紀(国立長寿医療センター研究所)、尾藤 晴彦(東大・院医)
神経シナプスにおけるシグナル伝達機構は、シナプス蛋白質の局在や機能を制御して、シナプス形態やシナプス伝達効率を変化させる。シナプスにおけるシグナル伝達機構の解明は記憶や学習だけでなくシナプス機能が変化する精神神経疾患、認知症、てんかん等の病態を理解する上でも極めて重要である。近年のゲノム解析、質量分析法を用いた生化学的解析、および神経細胞生物学的解析によりシナプス構成蛋白質の同定および性状解析が次々と進んでいる。本シンポジウムでは新進気鋭の神経科学者らにより、シナプス形成、維持およびシナプス可塑性を制御する分子メカニズムについて、蛋白質相互作用、翻訳後修飾、遺伝学および生理学などの観点から最新の話題を提供したい。
Sp2D 生殖細胞を規定する機構
世話人:相賀 裕美子(国立遺伝研・発生工学研究室)、小林 悟(基生研・統合バイオサイエンスセンター)
生殖細胞は唯一次世代に受け継がれる細胞で発生の初期に体細胞系列と分かれて分化し、体細胞に囲まれて発生しながらもその特質を維持し、生殖細胞に特異的な性質を確立する。発生遺伝学的解析の進んでいるショウジョウバエとマウスにおいては、最初の生殖細胞確立機構としては、異なったストラテジーをとりながらも、進化過程を通じて維持されてきた共通の機構をも有することが明らかになってきた。今回は特に生殖細胞の初期分化機構の解析を精力的に進めている若手研究者を中心に、最近の研究成果について発表してもらう。
Sp2E 器官形成を支える細胞のふるまい
世話人:高橋 淑子(奈良先端大・バイオサイエンス)、西井 一郎(理研・FRS)
多細胞体制を支える基本単位は細胞である。個体発生が進行する際、細胞はある場所にとどまって細胞増殖や遺伝子発現を制御するのみならず、体の中をダイナミックに動きまわってさまざまな器官形成にあずかる。個々の細胞の移動や運動のメカニズムについては、これまで主に2次元的培養細胞を用いて研究がおこなわれ、多くの新規分子が同定された。一方で、細胞をとりまく環境は、培養条件内(2次元)と体内(3次元)では著しく異なることもわかり始めてきた。本シンポジウムでは、1)個体発生中の器官や組織形成の過程において、どのような細胞がどのようにふるまうのか、2)それらの細胞のふるまいがその後の器官形成にどのような役割をもつのか、3)それらの細胞のふるまいは、3次元環境の中でどのような制御を受けるのか、などについて、オリジナルな研究の最新の成果にふれ、それらをもとにディスカッションしたい。
Sp2F ホルモンと低分子RNAによる植物発生制御
世話人:上野 宜久(名大・院理)、深城 英弘(神大・理)、長谷部 光泰(基生研・生物進化研究部門/総合研究大学院大・生命科学研究/ERATO分化全能性進化プロジェクト)
植物の発生は、細胞の増殖と分化の制御の上に成り立っている。植物ホルモンが細胞の増殖や分化を制御できることは半世紀ほど前から知られていたが、個体発生におけるこの増殖・分化の制御の実体は、現在でもまだ十分には理解されていない。近年のシロイヌナズナを中心とした発生遺伝学的解析などから、転写因子のネットワークだけではなく、実際にオーキシンなどの植物ホルモンや、これに加えて低分子RNAがこの制御の重要な鍵分子として浮上してきている。また、比較ゲノム解析からこれらの制御機構は植物進化の過程でダイナミックに変化してきたことが明らかになってきた。本シンポジウムでは、異なった局面からこの問題に迫る演者の先生方に、最新の成果を紹介していただく。
Sp2G オルガネラDNAの片親遺伝の様式と分子機構
世話人:杉山 康雄(名大・遺伝子実験施設)、林 純一(筑波大・生命環境)
ミトコンドリアと葉緑体は、それらのゲノムDNAと共に、すべての動植物で非メンデル型遺伝する。一部の二枚貝を除き、現在までに調べられたほとんどすべての動物ミトコンドリア(mt)DNAは母性遺伝し、精子mtDNAは受精卵において選択的に排除される。また母性遺伝する植物の葉緑体(プラスチド)DNAは花粉が成熟する過程で精細胞から排除される。一方、花粉の精細胞におけるmtDNAの選択的分解については疑問があり、また、受精卵でのmtDNAの様子は良く分かっていない。さらに植物では父性遺伝する種も知られていて話は複雑である。このシンポジウムでは、片親遺伝する動物と植物についての研究の現状を紹介し、互いの共通点と相違点を整理する。そしてモデル生物(マウス、メダカ)の母性遺伝の解析に利用された高感度DNA検出技術、ホモプラスミックなオルガネラDNAでは本来不要な組換えの存在について紹介し、今後の分子機構の解明に向けて動物と植物の研究者が同じ土俵で議論する。
Sp2H DNAの修復と再編成−安定性と多様性とのトレードオフ
世話人:武田 俊一(京大・院医)、井倉 毅(東北大・院医)
クロマチンタンパクの修飾(リン酸化、ユビキチン化など)は遺伝子発現制御に重要な役割をもつ。この修飾は、DNAの修復や再編成もコントロールしていることが解明されつつある。複雑な転写制御機構と異なり、修復や再編成は、必ずDNA損傷発生によって開始される。そのため、人工的に誘導された損傷で開始され修復や再編成に至るまでの、クロマチンタンパクの修飾・ダイナミックスを様々なミュータントで経時的に解析できる。すなわちクロマチンレベルのダイナミックスやその生物学的意義が研究している上で、DNA修復と再編成は優れたモデルである。これまでDNAに直接に働きかける分子だけを解析してきた研究から、クロマチンレベルの分子機構解析にも展開しつつあるDNA修復と再編成の先端的研究を紹介する。
Sp2I 構造プロテオミクスの分子生物学への寄与−転写・翻訳のメカニズム−
世話人:田中 勲(北大・院理)、横山 茂之(理研・ゲノム科学総合研究センター)、西村 善文(横浜市立・院国際総合科学)
構造生物学の手法(タンパク質調製、X線結晶構造解析、NMR解析等)の進歩はめざましく、多くのタンパク質や核酸などからなる複雑なシステムの理解をめざした研究(構造プロテオミクス)が進められている。我が国でも平成14年度から本年度まで、「タンパク3000」プロジェクトが行われ、重要なタンパク質について従来は考えられなかったほど多数の構造解析がなされている。本シンポジウムでは、「タンパク3000」プロジェクトの分子生物学への寄与について紹介する。特に、転写・翻訳のメカニズムに焦点を当てる。転写では、RNAポリメラーゼ、様々な転写因子、真核生物の染色体構造の制御因子などについての構造解析が進められ、基本的分子機構から制御のメカニズムまで解明が進み、疾患との関係などもわかってきた。翻訳では、tRNA関連酵素、翻訳因子、リボソームなどの構造解析が進められ、翻訳の基本的メカニズムが次々と解明されている。
Sp2J 再生医療の最前線
世話人:山中 伸弥(京大・再生研)、出澤 真理(京大・院医)
幹細胞生物学や組織医工学などからなる再生医学研究は日進月歩で進んでおり、皮膚、骨や軟骨、角膜などにおいて臨床応用が実現している。また神経組織、骨格筋、心筋、膵臓β細胞などに関する研究も進んでおり、これらの再生医療も近い将来に実現される可能性がある。脊髄損傷、パーキンソン病、筋ジストロフィー、心不全、若年型糖尿病など多くの疾患への応用が期待される。本シンポジウムにおいては、再生医療を実現するためにどのような研究が行われているのかに関して、その現状と展望を紹介する。
Sp2K ゲノムネットワーク解析に基づく新しい創薬、診断、治療戦略
世話人:柳川 弘志(慶大・院理工)、宮本 悦子(慶大・院理工)
ポストゲノム時代に入り、ゲノム機能解析を生命現象の理解や疾患メカニズムの解明へ具体的に結びつけることを加速させる技術が所望されている。タンパク質相互作用解析やタンパク質機能解析技術の紹介と、それらの方法で得られたデータを用いたバイオインフォマティクスによるネットワーク解析、創薬、診断、治療への応用とその戦略として、内因性機能ペプチドの予測やモチーフと相互作用する低分子化合物の予測、"Omics"を用いた病理病態からの癌の診断と治療の展望などを議論する。
Sa3B 植物高次生命現象を司るオルガネラ機能
世話人:吉岡 泰(名大・院理)、明賀 史純(理研・植物科学研究センター)
ゲノム解読や様々なオーム解析によりゲノム関連情報が急速に蓄積されつつある。しかし、それによって直ちに代謝・生理・発生・行動・環境応答といった高次生命現象の分子基盤が理解できるわけではない。高次生命現象の分子基盤を理解するためにはオルガネラ、細胞、組織、器官、個体といった高次のレベルにおいて生体分子が形成するダイナミックなネットワークを解明する必要がある。本ワークショップでは植物オルガネラの機能に関して先端的な研究を行なっている研究者を演者とし、代謝・生理・発生・環境応答などの高次生命現象を支える植物オルガネラの機能に焦点をあて、高次生命現象の分子基盤をになうオルガネラ機能について議論する。
Sa3C 細胞膜のセンサーの作動原理
世話人:川岸 郁朗(名大・院理)、富永 真琴(岡崎統合バイオサイエンスセンター)
さまざまな感覚・環境応答系において、刺激の受容と細胞内への情報伝達を司るのは膜貫通型受容体である。膜貫通型受容体は、出力制御様式によって大まかにイオンチャネル共役型、Gタンパク質共役型、酵素共役型の3タイプに分けられる。いずれのタイプについてもさまざまな系において精力的に研究が進められており、多くの知見が得られている。しかしながら、それらの作動原理、すなわち膜の外から内への情報伝達のメカニズムについては依然として謎も多い。本シンポジウムでは、動物・植物・細菌におけるさまざまな膜貫通型受容体の作動原理についての最先端の知見を紹介し、それらを比較することによって普遍性や多様性について考察出来る場を提供したい。
Sa3D 細胞死の多様な調節機構と生理機能
世話人:三浦 正幸(東大・院薬)、後藤 由希子(東大・分生研)
細胞死の分子メカニズムが詳しく研究され、アポトーシス機構の詳しい理解に加え、非アポトーシスによる細胞死の調節機構も少しずつ明らかにされてきている。細胞死調節因子の生理機能を発生や疾患といった個体レベルで調べる研究が行われた結果、これら因子の多彩な機能が浮き彫りにされてきた。本シンポジウムでは、多彩な細胞死調節機構とそれぞれの因子の新たな生理機能を追求している先端の研究を若手研究者から紹介していただき細胞死研究の新たな展開を議論したい。
Sa3E 組換え、修復によって維持されるゲノムの恒常性
世話人:小林 武彦(基生研・ゲノム動態)、益谷 央豪(阪大・院生命機能)
ゲノムの恒常性(安定性)を維持することは、生物にとって最も重要な作用の1つである。近年加速するオゾン層破壊による有害放射線の増加、人類の生産活動に伴う変異物質、発癌物質の蔓延は、このまま続けば将来的にゲノムを危機的状況へ追いやると予想され、そのリスクを低減することは人類にとって環境、医学両面での緊急課題である。ゲノムの損傷は外的要因と、それに起因するDNA複製障害等の内的要因によって主に引き起こされる。本シンポジウムでは、ゲノムの恒常性を維持する主要な手段であるDNA組換え及び修復研究を精力的に行っている研究者に、膨大で脆弱な遺伝情報が如何に日々維持されているのか、その機構について最近の知見を中心に発表願う。
Sa3F 比較ゲノム研究による生命システム解明への挑戦
世話人:小原 雄治(国立遺伝研)、藤山 秋佐夫(国立情報学研究所)
「生命の歴史は染色体に記されてある」とは60年前の木原均博士の言葉である。現在、ゲノムシーケンシングの技術の進展により様々な生物のゲノム配列が明らかとなり、この言葉が具体化しつつある。例えば、進化上様々な位置にある生物のゲノム配列の比較から祖先ゲノムの解明などゲノム進化の詳細が明らかになりつつあるし、遺伝子組成の比較から、生物のシステムとしての進化についても解明の努力がなされている。さらに、種内の多様なゲノム比較からは、疾患遺伝子を始め、体質など様々な形質の遺伝的基盤の解明が進行中である。いわば自然が与えてくれた「システムの変異体」の比較解析アプローチといえよう。ここでは、このようなアプローチに関する最新の研究成果を紹介いただき、その先にあるべき生命システムの解明に向けた研究の方向について議論したい。
Sa3G 植物の細胞増殖制御と発生・分化のクロストーク
世話人:伊藤 正樹(名大・院生命農学)、佐藤 豊(名大・院生命農学)
細胞増殖制御に関する多くの知見は、酵母や培養細胞などの単細胞の系を用いた細胞周期研究によりもたらされてきた。一方で多細胞体構築の過程における細胞増殖は、細胞間相互作用などを介した複雑な発生的制御を受けていると考えられる。一般に植物の器官が形成される過程では、初期において盛んであった細胞増殖が、発生が進むにつれてその程度が低下し、やがて停止する。このような増殖の発生的な変化はどのようにもたらされるのか。また、植物の器官や個体はおおよそ一定の大きさや形になるように遺伝的に決定されているが、細胞増殖制御はこれにどのように関連しているのか。多くの場合、増殖の停止と細胞の分化が平行して起きるが、これらはどのような関係にあるのかなど、植物の発生を理解する上で本質的な問題が多く残されている。このような問題に関連する最新の研究例をご紹介いただき、今後の方向性について展望したい。
Sa3H 構造生物学の新しい可能性
世話人:前田 雄一郎(名大・理)、甲斐荘 正恒(名大・理)
今後の生命科学の進歩のためには、構造生物学は蛋白質の結晶構造を決めるだけでは不十分である。蛋白質の機能発現のメカニズムを理解するためには、蛋白質分子の動き(揺動)を深く知る必要がある。また、細胞内での各蛋白質分子の配置やその離合集散を俯瞰的に把握して、細胞生物学との橋渡しも必要である。これらの問題を解くための手法も開発されてきている。本シンポジウムでは、その一端として、大きな複合体の構造解明(クライオ電子顕微法)、遺伝病の原因変異を使っての構造・機能連関の解析、従来の分子量限界を超える新しいNMR法、複数の測定手法を組み合わせてメカニズムの解明へ接近している研究の具体例などを取り上げ、新しい研究戦略を議論したい。なお、特に意図したわけではないが、具体例は細胞運動、細胞骨格の分野が中心となっている。
Sa3I ニューロンの誕生と移動
世話人:宮田 卓樹(名大・院医)、星野 幹雄(京大・院医)
1906年のノーベル賞は、「神経系が,ニューロンという基本素子の、非融合的相互接触による集合体として構成されている」との概念を提示したカハールと、その証明技術を先立って提供していたゴルジに対して与えられた.それからちょうど100年。いま、我々は、さまざまな分子/細胞/発生生物学的手法を用いることによって、ニューロンがいかにして生まれ、個性を持ち、適切な場所に配され、成熟し、成体における脳機能の発揮に至るのかという問題を解きほぐそうと努力を続けている。本シンポジウムでは、ニューロンの誕生とその前後の主要な出来事、すなわち神経前駆細胞集団としての「神経上皮」の「領域化」から、ニューロンを作り出すための前駆細胞による「細胞周期」の進行と「(対称または非対称な)細胞分裂」、そして、娘ニューロンの「(法線方向または接線方向への)移動」と「配置」までに焦点をあて、数人の演者によるthought-provokingな発表を予定する。
Sa3J 幹細胞研究の展開
世話人:岡野 栄之(慶大・医)、阿形 清和(京大・院理)
病気や怪我などで傷付いたり、失われた人体の様々な細胞・組織を元通りに修復する医療の開発を目指し、生物学の古典的な研究テーマである「再生」が、大きくクローズアップされてきている。「再生」とは生体の失われた細胞・組織が、幹細胞の増殖・分化や分化した細胞の分化転換によって補われることと定義される。今、哺乳動物を対象とし、発生過程を一部再現させることにより臓器再生を目指そうという新しい学問潮流が生まれつつあり、まさにこれに立脚した治療哲学である「再生医学」(その実践が「再生医療」)が21世紀の医学の進むべき一つの方向であると期待されている。再生を誘導するためには、色々な臓器を作るもとになる細胞である「幹細胞」が重要である。幹細胞には、各々の臓器に固有の臓器幹細胞(造血幹細胞、神経幹細胞など)の他に、初期胚由来の多能性幹細胞であるES細胞(胚性幹細胞)が含まれる。現在、これらの幹細胞を用いた再生医療に熱い注目が集められている。本講講演では、幹細胞を用いた再生医療の現状と展望について述べてみたいと考える。
Sa3K ゲノム情報発現制御因子としてのNoncoding RNA <Noncoding RNAs as regulators of gene expression>
世話人:廣瀬 哲郎(産総研・生物情報解析研究センター)、塩見 春彦(徳島大・ゲノム機能研究センター)
最近のエピジェネティックスにおけるnoncoding RNA (ncRNA)の役割やmicroRNA等の小分子ncRNAの発生・分化、細胞増殖、そして細胞系譜、さらには幹細胞の増殖とその維持における役割が明らかになるにつれて、急速に、ゲノムのnoncoding領域に重要な‘遺伝学的活性’があり、 それがncRNAというカタチで情報を発信していることが見えてきた。したがって、従来のセントラルドグマに加え、ncRNAが情報発現ネットワークにおける重要な制御分子として機能することで、極めて多様で複雑な高性能システムの創造を可能にしているのではというコンセプトが提唱されるに至っている。本シンポジウムでは、大腸菌からヒトまで様々な分野のncRNA研究者を結集し、できる限り多くの視点からncRNAの機能を考えることで、「生命活動を支えるRNAプログラム」を議論する。
Sp3B 生物リズムの制御メカニズム−刻々と変化する生命現象−
世話人:程 肇(三菱生命研)、八木田 和弘(名大・理)
生物リズムは、遺伝子発現やタンパク質修飾および安定性などの状態を刻々と変化させ、しかもまたある一定時間後に初期状態に戻るという振動現象を制御する非常に動的な生命システムである。ここから派生する生理現象は多岐にわたり、生物にとってかなり根源的なものであると考えられる。最近、生物リズム研究において、概念の転換をもたらす発見が相次いでおり、パラダイムの再構築に向けた活発な研究が内外で進んでいる。同調や安定性といった性質も包含した「振動」の仕組みについて議論し、generalな生命現象としての生物リズムの捉え方と方向性を考える。
Sp3C 膜タンパク質の挙動/構造変化を追う
世話人:小嶋 誠司(名大・院理)、森 博幸(京大・ウイルス研)
ここ数年の膜タンパク質の研究の進展は目覚ましく、ゲノム情報の蓄積や界面活性剤の改良、精製・結晶化の簡便化に伴い、最近では高解像度の結晶構造が次々に報告されるようになった。その結果、タンパク質の構造をもとに変異導入解析の結果を解釈できるようになり、ようやく膜タンパク質においても機能発現メカニズムを原子レベルで説明できる時代になりつつある。次の課題は膜タンパク質のダイナミックな動きと機能発現との相関を明らかにして行くことである。そこで、本シンポジウムでは、様々な手法を用いてこの問題に取り組まれている若手の先生方に最新の研究成果を御紹介いただく予定である。議論の中で新たなメソッド開発のヒントが得られればと考えている。
Sp3D シグナリングシステムの時空間的制御による位置情報の設定と形態形成
世話人:多羽田 哲也(東大・分生研)、濱田 博司(阪大・院生命機能)
細胞外シグナル因子が生体をデザインする仕組みは形態形成の中心課題として今なお詳細な解析が続いている。ヘッジホッグ、Wnt、BMPのように長距離に働く因子群から、Notchのように隣接した細胞に働きかける因子群まで、比較的少数の因子群とその信号伝達系により、きわめて多様な機能と形を持った組織が形成される。これらの研究は発生の体軸の形成という巨視的な文脈での解析に始まり、現在では個々の細胞の3次元の位置を視野に入れた、より精密な構造も対象となりつつあり、複数のシグナリングシステムの時空間的な制御および相互作用の様式が解析の焦点となっている。本シンポジウムでは協調して機能する複数のシグナリングシステムによる位置情報の設定機構を中心に、体構造を構築するメカニズム解明の最先端を紹介する。
Sp3E 新たな発がん研究を目指して−がん幹細胞からモデル動物まで
世話人:高橋 雅英(名大・院医)、佐谷 秀行(熊本大・院医学薬学)
過去20年間のがん遺伝子、がん抑制遺伝子の研究により、発がんの分子メカニズムの理解が急速に進んできた。最近さらに、新たな視点により、さまざまな興味ある発がん研究が各分野で展開されつつある。本シンポジウムでは5人のシンポジストにより、1) 乳がんおよびグリオーマ細胞株に内在するがん幹細胞様細胞の解析、2)H. pyloriによる胃粘膜前駆細胞のDNAメチル化異常と発がん、3)がん細胞の分裂異常におけるAurora-Aの役割、4)Aktシグナルとがん細胞の運動、浸潤能の制御機構、5)消化器がん発生におけるWntシグナルとプロスタングランジン合成酵素Cox-2の相互作用とその個体レベルでの解析について最新の知見を紹介してもらう。
Sp3F 翻訳とmRNA安定性制御
世話人:稲田 利文(名大・院理)、星野 真一 (名市大・院薬)
翻訳とmRNA分解は遺伝子発現の重要な制御段階である。特に最近miRNAによる標的mRNAの発現抑制や、mRNA品質管理機構において必須な役割を果たすことが明らかになり、その分子機構の解析が進んでいる。本シンポジウムでは、様々な細胞種におけるmRNA分解と翻訳制御に関する最近の知見を紹介する。真核生物におけるポリ(A)短鎖化の分子機構、生殖細胞形成機構におけるmiRNAによるポリ(A)短鎖化の役割、生殖質形成における母性mRNAの局在と翻訳制御機構について紹介する。またmRNA品質管理機構について、NMD(ナンセンス依存分解系)の分子機構、ノンストップmRNAの発現抑制における翻訳抑制の役割などの最新の知見を紹介する。さらにNGD(翻訳伸長阻害によるmRNA分解)の代表例として、植物における新生ポリペプチド鎖に依存した翻訳停滞とmRNA分解について紹介する。
Sp3G 生物進化の遺伝メカニズム−生物環境適応と重複遺伝子の分子進化−
世話人:渡邉 正勝(東工大・院生命理工)、郷 康広(総合研究大・先導科学研究)
生物の多様性獲得には、ゲノム上の様々な変異や再編などが大きな役割を果たす。オオノが今から35年以上前に指摘したように、中でも重複遺伝子が進化の原動力として果たす役割は特に大きい。例えば、免疫関連遺伝子群や感覚感受性遺伝子群などに代表される重複遺伝子群においては、生物が環境に適応する過程で多種多様な選択圧にさらされ変異・機能分化し、様々な多様性を獲得してきた。本シンポジウムでは、生物多様性の中でも環境への適応や個体間の相互認識といった種の形成に直接関わることが示唆される現象に着目し、これらに関係ある遺伝子群の進化と表現形の進化との関係性を論じる。
Sp3H 脳のはたらきの統合的解析:遺伝子〜神経回路〜行動
世話人:木村 幸太郎(国立遺伝研・構造遺伝学研究センター)、小田 洋一(名大・院理)
動物の脳は、外界や動物内部からの情報を処理し、行動するため制御信号を出力します。このような脳のはたらきをになう神経回路の構造と機能については、今日さまざまの研究手法により神経回路の構成、回路を形成するニューロンの性質やその分子基盤、さらにその分子をコードする遺伝子まで精力的に調べられるようになりました。ことに最近の遺伝子工学的手法はそれぞれのキィファクターに迫る強力な手法として注目されます。しかし、個々の局面を断片的に調べるだけでは脳のはたらきの理解には到底結びつきません。遺伝子〜神経回路〜行動といった異なる階層を密接に関連づけた統合的な解析が今こそ求められています。本シンポジウムでは、第一線で活躍する研究者の「脳のはたらきを統合的に解析」しようとするチャレンジと、線虫から哺乳類に至るさまざまのモデル動物を用いた成果を、分野外の研究者にも分かり易く説明していただき、議論する予定です。
Sp3I プロジェクト型研究時代の生命科学の課題
世話人:大久保 公策(国立遺伝研・生命情報・DDBJ研究センター)、高木 利久(東大・院新領域)
ゲノム研究以降の大型プロジェクトは目論見どおりの知的基盤としての役割を果たせているか。大型の測定プロジェクトと知的な生産性の関係について分析し、プロジェクト研究の成果を知的生産性に繋げる方策について考える。
Sp3J 人類生存に役に立つ植物研究とは?
世話人:松岡 信(名大・生物機能開発利用研究センター)、西澤 直子(東大・農)
植物は光合成を行い、太陽エネルギーを化学エネルギーに変換できる一次生産者であり、地球環境の維持及び食糧供給など、我々人類の生存にとって必須の生物である。現在、地球レベルでの人口の増加や環境の悪化などの問題が深刻化することが懸念されており、これらの諸問題を解決する有効な手段として、植物の持っている形質のさらなる改良・利用が期待されている。最近、イネやシロイヌナズナのゲノム情報が開示されたことにより、これまでその複雑さ故に不可能だった農業的有用形質の分子レベルの解析が可能となり、理論に基づく作物育種が展開できるようになった。本シンポジウムでは、このような植物科学における基盤技術の革新が、現在人類に突きつけられている課題にどのように答えようとしているのか、また今後どのように答えていくのか、を具体的な取り組みを紹介することにより明らかにしたい。
Sp3K 染色体複製開始サイクルの分子機構と制御スイッチ
世話人:片山 勉(九大・薬)、西谷 秀男(九大・医)
染色体の複製開始においては、複製開始装置と複製伸長装置とのダイナミックな連係が行われている。さらに、複製開始装置を形成・制御する因子には、細胞周期シグナルや複製プロセスからのフィードバックシグナルとの連係を受け持つキーファクターも含まれている。このようにネットワーク連鎖の要(かなめ)となっている複製開始系においては、タンパク質機能の制御動態やDNA-タンパク質相互作用動態の多様性が一望できる。さらに最近はそれらが見事に集約統御されている様させ垣間見えるようになってきた。すなわち、この系は、タンパク質の低分子化合物結合による機能変化と分解、タンパク質高次複合体の形成と解離、DNA-タンパク質複合体の構造形成と変化など、多様な翻訳後制御原理を遺伝子発現制御原理とともに駆使して組み立てられているシステム統合体といえそうである。また、数種の生物を対象とした解析により、この系の構成における進化的保存性の特性にもより広い光条が届き始めた。このような背景のもとで、本シンポジウムでは実際に実験現場に立つ研究者の発表によって最先端研究を展望し制御原理への考察を深めたい。
困ったときには