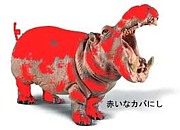開催終了多様化する家族-幸せのカタチはひゃくまん通り!?-
詳細
2016年08月19日 00:04 更新
と き 6月21日(火)19:00〜
場 所 月ヶ瀬公民館2F 研修室
参加費 100円
報告者 藤田美佳 さん (奈良教育大学 特任准教授)
今月12日、野党4党は選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を衆議院に提出した。今、多くの女性が改姓による不利益を避けるために、事実婚を選んだり旧姓の通称使用をしたりしているという。また昨年11月から東京都渋谷区と世田谷区では、同性カップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ証明書」等の発行を始めた。同性カップルと分かると賃貸物件の入居を拒否されたり、愛する人を病院に見舞えなかったりするため、不動産業者や病院に同性カップルを家族とみなすよう促すのが狙いだそうだ。
また、1999年にヒットしたドラマをきっかけに『週末婚』という週末(休日)のみ会う、週末のみ生活をともにする夫婦・結婚スタイルが広く認知されるようになった。今では、入籍をしたあとも同じ家には住まない「別居婚」夫婦も増えている。そして、夫による妻の介護という現状も見落とすことはできない。
このように、「家族」「夫婦」と言っても一昔と異なり超多様化している現代。ご自身も通称使用&別居婚というスタイルを貫き奈良で多文化共生の研究を続けている藤田美佳さんをお招きし、多様な家族の姿とそれぞれの幸せのカタチについて考えてみたい。
場 所 月ヶ瀬公民館2F 研修室
参加費 100円
報告者 藤田美佳 さん (奈良教育大学 特任准教授)
今月12日、野党4党は選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を衆議院に提出した。今、多くの女性が改姓による不利益を避けるために、事実婚を選んだり旧姓の通称使用をしたりしているという。また昨年11月から東京都渋谷区と世田谷区では、同性カップルを結婚に相当する関係と認める「パートナーシップ証明書」等の発行を始めた。同性カップルと分かると賃貸物件の入居を拒否されたり、愛する人を病院に見舞えなかったりするため、不動産業者や病院に同性カップルを家族とみなすよう促すのが狙いだそうだ。
また、1999年にヒットしたドラマをきっかけに『週末婚』という週末(休日)のみ会う、週末のみ生活をともにする夫婦・結婚スタイルが広く認知されるようになった。今では、入籍をしたあとも同じ家には住まない「別居婚」夫婦も増えている。そして、夫による妻の介護という現状も見落とすことはできない。
このように、「家族」「夫婦」と言っても一昔と異なり超多様化している現代。ご自身も通称使用&別居婚というスタイルを貫き奈良で多文化共生の研究を続けている藤田美佳さんをお招きし、多様な家族の姿とそれぞれの幸せのカタチについて考えてみたい。
コメント(1)
2016年08月19日 00:04
第49回学習会報告
報告者は、奈良教育大学特任准教授の藤田美佳さん。秋田県出身、飲食店を営む両親の元に生まれた彼女は、小学生時代より「地元を離れて勉学に努めたい」と考えており、東京の大学に進学、卒業後は関東で総合職の仕事に就いた。その後、知人からの相談で引き受けた地元の公民館での日本語教室のボランティアをきっかけに、仕事上すべての人と平等に接する両親の姿から学んだことを改めて考え、外国人などの少数者に対する地域の教育、多文化共生の研究を進めていくこととなる。40代で移住女性の言語習得について体験的に研究するために韓国に短期留学し、自分自身の体で語学習得の難しさも体験した。また、結婚から9年後に奈良での仕事を得たことにより、「別居婚」というかたちをとってお互いの仕事を優先させて別居生活を続けている。そんな彼女の研究は、言語習得と社会参加、そして家族や人間関係の多様性という社会的に最も原始的な内容を取り扱っている。
学習会ではまず、パウロ・フレイレというブラジルの教育者について教えてくれた。1960年代にフレイレが提唱した教育は、権力から搾取される人々を解放するため、識字率を高め、投票する力を身につけさせるものであった。文字を読み、世界を知る、自分の暮らしを良くし、社会を良くする。そんな明白な理由が、人々に考える力を身につけさせ、生活水準の向上に大きく貢献した。
日本は、識字率が高いがコミュニケーション能力が低いと言われている。特に家庭内でコミュニケーションが取れず、「身近な他者」である家族と建設的な会話をすることが難しいと考えられているそうだ。それは日本の教育プログラムが、一方向的な「知識注入型」で進められていることが大きく関わっていると彼女は考える。文字を読めても、その背景や文脈を理解する「批判的識字」の能力がない。特に、東日本大震災以降、メディア・政府が提示する情報を多面的に読まなければならない日本の状況を考えると、そのような能力はますます必須となってくる。地域の課題に対して耳を傾け、同じ視線で一緒に考えるような「課題提起型教育」の必要性を彼女は説いている。キング牧師がアメリカで行った公民権運動の一連の流れからも、60年代の黒人、70年代の女性、80年代の性的少数者の解放には、教育の改革が欠かせない材料であったことを教えてくれた。
次に幾つかのVTRを見せてもらった。ひとつは定年後に各々がやりたいことに集中するため別居する「卒婚」、もうひとつは妻の認知症をきっかけに介護をする男性の姿。両方のVTRからパートナーを支える様々な形が紹介された。「会って話すだけが対話ではない」「つらい時は、周りとのコミュニケーションが大切」、そんな言葉が参加者の心をつかんで離さない映像だった。続いて性的少数者についての世界での動きを、VTRを交えて紹介いただいた。ディズニーランドで挙式をしたレズビアンのカップル、東京都渋谷区で進められているパートナーシップ証明書、『夫夫円満』の著者であるパトリック・リネハンとエマーソン・カネグスケ夫夫、「Tokyo Rainbow Week」。すべての映像には、胸を張って自分たちを笑顔で紹介する姿が映っており、とても和やかな雰囲気が伝わってきたが、その活動どれもが困難の連続で、様々な方面で理解を得て運動を起こしていく苦悩と努力があることを忘れてはいけないと感じさせた。
最後に、性的少数者の自殺などの問題を背景に制作された「It gets better(より良い未来がある)」というブロードウェイのアーティストたちによる楽曲を鑑賞。音楽を参加者みんなで聴いていると、自然と笑顔が溢れる。「つらい時は、呼吸だけでいいから、呼吸だけしていて(自ら命を絶たないで)!あなたの家族・友人、そして自分自身の心と体の声に耳を傾けてほしい」という言葉を添えて、藤田さんは講演を終了した。
日々、誰もが問題を抱えて暮らしている。幸せとは何か、答えを出すことは難しい。しかし、「耳を傾ける」という小さな行動を重ねていくことが大切だとヒントをくれた今回の講義は、どんな授業よりも人間として本質的なものを学ぶ機会となった。 (大樋真彦)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには