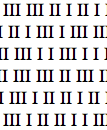開催終了☆11/30 松井茂/福永信/水無田気流 セッション形式のレクチャー
詳細
2008年09月13日 13:50 更新
Yotsuya Art Studium:批評(創造)の現在シリーズ +シンポジウム
各回3人のゲスト講師によるセッション形式のレクチャーシリーズ「批評(創造)の現在」(全4回)が10月より開講されます。現在を組織しつつある、もっとも切れ味のある若手批評家、創作者が登場します。
批評(創造)の現在シリーズ
批評・創造の切れ味は、見通しのきかぬ任意の点にあえて立ち止り、なおその地点が含まれるはずの時空の全体を見通し(構築し)、あるいは見通した上でそこに道を開く、つまりは現在という時空を切り裂く鮮やかさにこそ示される。偏見と誹られようと、批評家(創作家と同様に)はこうしたリスクを引き受け率先して、その偏向を代行する。なぜならば批評はいつも、こうした突発性としてしか遂行されえない、一つの事件であるからである。
■日時/講師
第1回…………
10月21日(火)18:30−21:30
講師=伊藤亜紗/上崎千/柳澤田実
第2回…………
11月4日(火)18:30−21:30
講師=池田剛介/黒瀬陽平/沢山遼
第3回…………
11月18日(火)18:30−21:30
講師=千葉雅也/平倉圭/福嶋亮大
第4回…………
11月30日(日)17:00−20:00
講師=福永信/松井茂/水無田気流
http://
http://
■会場:四谷アート・ステュディウム講義室
http://
■受講料
−レクチャー4回+シンポジウム2回セット:10,000円
−レクチャー:各回2,000円(特別価格)
−シンポジウム:各回1,500円
■問い合わせ/申し込み先
近畿大学国際人文科学研究所 東京コミュニティカレッジ
四谷アート・ステュディウム事務室
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-5 2F
tel. 03-3351-0591(9:30−17:00、日曜・祭日 休)
fax. 03-3353-7300
各回3人のゲスト講師によるセッション形式のレクチャーシリーズ「批評(創造)の現在」(全4回)が10月より開講されます。現在を組織しつつある、もっとも切れ味のある若手批評家、創作者が登場します。
批評(創造)の現在シリーズ
批評・創造の切れ味は、見通しのきかぬ任意の点にあえて立ち止り、なおその地点が含まれるはずの時空の全体を見通し(構築し)、あるいは見通した上でそこに道を開く、つまりは現在という時空を切り裂く鮮やかさにこそ示される。偏見と誹られようと、批評家(創作家と同様に)はこうしたリスクを引き受け率先して、その偏向を代行する。なぜならば批評はいつも、こうした突発性としてしか遂行されえない、一つの事件であるからである。
■日時/講師
第1回…………
10月21日(火)18:30−21:30
講師=伊藤亜紗/上崎千/柳澤田実
第2回…………
11月4日(火)18:30−21:30
講師=池田剛介/黒瀬陽平/沢山遼
第3回…………
11月18日(火)18:30−21:30
講師=千葉雅也/平倉圭/福嶋亮大
第4回…………
11月30日(日)17:00−20:00
講師=福永信/松井茂/水無田気流
http://
http://
■会場:四谷アート・ステュディウム講義室
http://
■受講料
−レクチャー4回+シンポジウム2回セット:10,000円
−レクチャー:各回2,000円(特別価格)
−シンポジウム:各回1,500円
■問い合わせ/申し込み先
近畿大学国際人文科学研究所 東京コミュニティカレッジ
四谷アート・ステュディウム事務室
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-5 2F
tel. 03-3351-0591(9:30−17:00、日曜・祭日 休)
fax. 03-3353-7300
コメント(2)
2008年12月01日 05:01
3人でのセッション形式ということで勝手に鼎談を想像していたんですが、そうではなく
「社会・アイデンティティ・批評」という同一のテーマでの各人のレクチャーでした。
松井茂さんは二人目として登場。
普段行わない話のテーマということで、まずは松井さんの中にある
「社会」「アイデンティティ」「批評」への「考え」や「ひっかかり」を
とりあえず並べながら考えながら話すという感じ。
「社会」:木原善彦さんの「UFOとポストモダン」を参照。
「現実」に対比される言葉を手掛かりとした時代区分として、
「理想」の時代(1945~1972)連合赤軍
「虚構」の時代(1972-1995)サリン事件のあとの95年以降の現在は
「諸現実」の時代
「アイデンティティ」:オクタビオ・パスの詩のタイトルからと言う小見出し
「アイデンティティは『二つの声によるソロ』」が印象的でした。
それから
「複数のアイデンティティを持つことは、たんに可能だということだけでなく、望んでしかるべきものなのだ。複数の異なった文化に属しているという意識は、ひたすら自分をゆたかにしてくれる」(バレンボイム/サイード 「音楽と社会」)
「批評」:批評については、レクチャーの最初に示された「象徴交換と死」からの引用
「詩的実践それは言葉の固有の法則に対する、言語そのものによる武装蜂起だ」、
そして「つまり詩を書くことは批評である」という松井さんの解説が全てを語っているように思いますが、
いくつか「批評」の項目でわざわざあげられたタームを並べると、
「モデル化」「アルゴリズム」「自律的」「アニマシー」「多手法による描法」「日常的」「科学的」「同時並列」「インスタレーション」「劣化しないコピー」「コンピュータの普及」「筆者のための詩」
普段あまり語ったことのない事柄を語ることで見えてきたのは、
私にとっては松井さんの一貫した興味でした。
松井茂は「システム(それも自律する、再生産する、アノニマスな)に興味がある」
松井茂は「並べる(批評性と非批評性がそこにはあるように思う)に興味がある」
そして今回特に感じたのは「現実」にとても興味がある、ということでした。
アイデンティティの項目で「ある応答的なことが成立する時にアメニズム的に感じる」と言い、
批評の項目で「短歌と言う『57577』の形式が生命体のように感じる」と言っていること、
の二つはだからこそ松井さんが「方法詩」を書いている理由そのものに思えました。
(57577の中で素晴らしい短歌を詠むより、57577に変わる形式を作ることに松井茂は興味がある)
(※立花ハジメがむかし「アプリケーション」という作品を作ったのを思い出しました。すごいCGを作るのと、フォトショップを作るのと、どっちがすごい?)
(それから形式とリンクして、「素」としての同時並列回路の「■」「□」や、カムフラージュの「/」「\」)
松井さんのレジュメは3つの項目に関する覚え書きと、
過去に松井さんが書いた文章の再録でできていて、
まず「社会」「アイデンティティ」「批評」について並べる、ということだったんですが、40分というレクチャー時間ではそれだけでほぼ終ってしまいました。
文章の方はもっぱら「現実」との対応のことが書かれているように思いました。
そしてそれは「詩」と「権力」との関係についての意識が書かれているように思います。
レクチャー終了後の岡崎乾二郎さんからの質問から話は始まったのですが、
松井さんが詩を書き始めるきっかけとしてあげているのが湾岸戦争期の体験で、
そこで未来派と藤井貞和さんが並んだことが松井さんにとっては大きかったそうです。
詩(あるいは詩を書くこと)=反戦
ということが決定事項であった湾岸戦争当時、
藤井さんは「詩は戦争を賛美することもできる」と書き(藤井さんがそうというわけでなく)、それを見せてくれたのが未来派だった。
そして「戦争を賛美することができる詩」だからこそ、「戦争を批判することもできる」詩というものに可能性を感じ、詩を選んだそうです。
そして「しかし詩は長く、権力の側のものだった。」
という問題意識のもとに立つ松井さんの方法詩を思うとき、
「詩的実践それは言葉の固有の法則に対する、言語そのものによる武装蜂起だ」
という松井さんがレクチャー冒頭に引用したボードレールの言葉を私は思い出しました。
追伸)
岡崎乾二郎さんの未来派を引合いに出した指摘から、
松井さんの詩は「抽象度が高い」からこそ「運用」の問題も出て来て、
statementも朗読も自注も「運用」の問題に関わる、
という話題は今日は突っ込んだ話にならなかったですが興味深かったです。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには