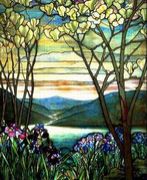開催終了「華麗なるアール・ヌーヴォー アール・デコの世界」〜エミール・ガレとドーム兄弟、ルネ・ラリック〜
詳細
2007年07月22日 19:20 更新
●概要●
1889年のパリ万国博覧会を契機に西欧諸国では、植物的モティーフによる曲線の装飾価値を強調するアール・ヌーヴォーが一世を風靡しました。この芸術表現の中心的な存在として、ガラス工芸の分野でエミール・ガレとドーム兄弟が活躍します。
第一次大戦後、それまでの曲線や植物的装飾の趣味は一転して、直線・即物的な装飾を好むようになり、時代の変化に素早く反応したのがルネ・ラリックでした。
1920年を境に勃発したアール・ヌーヴォーからアール・デコへの劇的な変化を、この時代を通して開花した彼ら三大作家のガラス作品120余点から概観します。近代工芸界に多大な影響を与えたガラス工芸の精華をご堪能ください。
●出展品●
【エミール・ガレ】
エミール・ガレは、19世紀後半フランスのナンシーを拠点に、ガラス、陶器、家具などの幅広い分野に創造力を発揮した工芸作家でした。
文学や哲学、修辞学、音楽、植物学、鉱物学などに通じ、当代一流の文化人とも交流を持ったガレは、造形のなかにジャポニスムや象徴主義、自然主義、博物学などの要素を盛りこんで、幻想的なイメージを絡み合わせた独自の世界をくりひろげました。ガレは1846年5月4日、フランス東部の古都ナンシーで生まれました。
ガラス器・陶器の発行者兼卸売業者であった父シャルル・ガレのもと、デザインと製造管理の修練を積み、1877年、31歳で会社の経営を引き継ぎます。デザインに独創的な手腕を発揮して、翌年のパリ万国博覧会、1884年の装飾美術中央連盟展で受賞を重ね、若き天才の存在を世の中に知らしめました。
1886年、家具製造部門の工場を創設、高級家具の製造にも着手します。1889年のパリ万国博覧会では、ガラス部門でグランプリ、陶器部門で金賞、家具部門で銀賞を獲得し、名声を決定的なものにしました。事業の拡大とともに彼の工場では100人以上の職人が働くようになり、少数限定の最高級品から大量生産による廉価品まで、加工技術の相違によるコストダウンを実現して、数々の名作を量産しました。傑出した表現者、総合的アートディレクター、企業家であったエミール・ガレは1904年9月23日に白血病で死去します。没後は親族が会社を継承し、世界恐慌の影響で1931年に工場を閉鎖するまで、ガレの名前(ブランド)を冠した製品を世の中に送り出しました。
【ドーム(兄弟)】
ナンシーでガラス工場を経営していたジャン・ドームの息子、オーギュスト・ドーム(1853〜1909)と弟のアントナン・ドーム(1864〜1930)が共同経営したガラスメーカーは「ドーム(兄弟)」のブランドで知られています。兄はパリ大学で法律を学び、弟はエコール・サントラルで技師の資格を得ました。兄は1878年に、弟は87年に、父の工場のガラス製造事業に参画しました。
当初、彼らの工場では実用的なガラス食器などを製造していましたが、1889年のパリ万国博覧会におけるエミール・ガレの成功に触発され、1891年には美術工芸品としてのガラス生産を開始しました。
彼らはガラス工芸家や美術家など優秀なスタッフを採用し、水準の高いガラス製品を市場に送り出しました。ドーム社では、ヴィトリフィカシオンと呼ばれる粉末色ガラスを素地に付着させる方法や、透明ガラスの層の間に色ガラスを挟み込み彫刻を施すアンテルカルテールのような独創的な技術を開発しました。
1900年のパリ万国博覧会ではガラス部門でグランプリを獲得します。ドーム社は、同じナンシーに拠点を置くガレ社と並んで、アール・ヌーヴォーを代表する工房のひとつとなっていきました。なかでもエナメル彩とエッチング技法によって製造された作品群は、秀逸な職人芸からくりだされる細密描写と仕上げの丁寧さにおいて群を抜いており、ドーム社ならではの繊細な魅力を放っています。
ドーム社は、アール・ヌーヴォーからアール・デコ、そして現代へと時代の流行の変化に対応しつつ、つねにフランスを代表するガラスメーカーの座を守り続けています。
【ルネ・ラリック】
20世紀前半に活躍したフランスのガラス工芸家ルネ・ラリックは、1910年頃からガラス工芸の制作に携わり、アー ル・デコの時代と呼ばれる1920〜30年代に、当時を代表するガラス・メーカーの経営者として世界的な名声を確立しました。
ガラス製造に着手する以前のラリックは、草木や昆虫といったモティーフを駆使して、新奇で魅力的な宝飾品を生み出すデザイナーとして名を馳せていました。そのジュエリーは、貴金属に宝石をあしらうだけではなく、時には美しく磨き上げられた透明ガラスや色ガラスの小片も用いられていました。
宝石の希少価値よりもデザインを重視したラリックの仕事は、アール・ヌーヴォーが流行する時代において、他の追随を許さないひときわ抜きん出た存在でした。
彼がガラスに傾倒していったのは、香水商コティの香水瓶デザインの依頼を受けてからで、1908年以降ガラス工場を借り受け、最新鋭の機械を投入し、次第にガラス製造を工業化していきます。第一次大戦終結後には、花瓶や香水瓶の製造はもとより、外洋を航海する豪華客船や旅客列車の内装デザインを受注して、随所に装飾ガラスを使い、清楚で洗練された室内空間の演出によって高い評価を得ました。
1925年、パリで開催された「装飾美術産業美術国際博覧会」(通称アール・デコ展)では、ガラスを多用した大規模な展示館や噴水を製作して会場を沸かせました。意識的に色彩の使用を制限し、造形の彫刻的な表情を重んじた透明ガラスがかもし出す、繊細で幻想的な世界は、スピード感や機能性という新しい時代の美意識をも感じさせるものでした。
●開催期間●
2007年6月9日(土)〜8月11日(土)
●休館日●
毎週木曜日(祝日は開館)
●開館時間●
9:30〜16:30(入館は16:00まで)
●開催場所●
MOA美術館
電話 0557-84-2511
FAX 0557-84-2570
〒413-8511 静岡県熱海市桃山町26番2号
http://
●アクセス●
※電車
JR東海道線・JR新幹線熱海駅下車
※バス(伊豆東海バス)
熱海駅乗車→MOA美術館下車
・4番バスのりばより「MOA美術館」行き
・0番バスのりばより「湯〜遊〜バス」
※タクシー(熱海駅より)
3階入口(乗用車駐車場)まで:約8分
エスカレーター入口まで:約5分
※自動車
関西方面から東名沼津I.Cから:約1時間
東京方面から東名厚木I.Cから:約1時間30分
●観覧料●
大人1600円
高大生800円
中学生以下無料
満65才以上1200円
●サイト●
MOA美術館
http://
毎日新聞社
http://
凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹
上記の情報は開催場所のホームページ等をもとにしています。情報の変更等がある場合がありますので、お出掛けの際は、事前に確認をしてください。
また、観に行かれた方は感想などを宜しくお願いします。
1889年のパリ万国博覧会を契機に西欧諸国では、植物的モティーフによる曲線の装飾価値を強調するアール・ヌーヴォーが一世を風靡しました。この芸術表現の中心的な存在として、ガラス工芸の分野でエミール・ガレとドーム兄弟が活躍します。
第一次大戦後、それまでの曲線や植物的装飾の趣味は一転して、直線・即物的な装飾を好むようになり、時代の変化に素早く反応したのがルネ・ラリックでした。
1920年を境に勃発したアール・ヌーヴォーからアール・デコへの劇的な変化を、この時代を通して開花した彼ら三大作家のガラス作品120余点から概観します。近代工芸界に多大な影響を与えたガラス工芸の精華をご堪能ください。
●出展品●
【エミール・ガレ】
エミール・ガレは、19世紀後半フランスのナンシーを拠点に、ガラス、陶器、家具などの幅広い分野に創造力を発揮した工芸作家でした。
文学や哲学、修辞学、音楽、植物学、鉱物学などに通じ、当代一流の文化人とも交流を持ったガレは、造形のなかにジャポニスムや象徴主義、自然主義、博物学などの要素を盛りこんで、幻想的なイメージを絡み合わせた独自の世界をくりひろげました。ガレは1846年5月4日、フランス東部の古都ナンシーで生まれました。
ガラス器・陶器の発行者兼卸売業者であった父シャルル・ガレのもと、デザインと製造管理の修練を積み、1877年、31歳で会社の経営を引き継ぎます。デザインに独創的な手腕を発揮して、翌年のパリ万国博覧会、1884年の装飾美術中央連盟展で受賞を重ね、若き天才の存在を世の中に知らしめました。
1886年、家具製造部門の工場を創設、高級家具の製造にも着手します。1889年のパリ万国博覧会では、ガラス部門でグランプリ、陶器部門で金賞、家具部門で銀賞を獲得し、名声を決定的なものにしました。事業の拡大とともに彼の工場では100人以上の職人が働くようになり、少数限定の最高級品から大量生産による廉価品まで、加工技術の相違によるコストダウンを実現して、数々の名作を量産しました。傑出した表現者、総合的アートディレクター、企業家であったエミール・ガレは1904年9月23日に白血病で死去します。没後は親族が会社を継承し、世界恐慌の影響で1931年に工場を閉鎖するまで、ガレの名前(ブランド)を冠した製品を世の中に送り出しました。
【ドーム(兄弟)】
ナンシーでガラス工場を経営していたジャン・ドームの息子、オーギュスト・ドーム(1853〜1909)と弟のアントナン・ドーム(1864〜1930)が共同経営したガラスメーカーは「ドーム(兄弟)」のブランドで知られています。兄はパリ大学で法律を学び、弟はエコール・サントラルで技師の資格を得ました。兄は1878年に、弟は87年に、父の工場のガラス製造事業に参画しました。
当初、彼らの工場では実用的なガラス食器などを製造していましたが、1889年のパリ万国博覧会におけるエミール・ガレの成功に触発され、1891年には美術工芸品としてのガラス生産を開始しました。
彼らはガラス工芸家や美術家など優秀なスタッフを採用し、水準の高いガラス製品を市場に送り出しました。ドーム社では、ヴィトリフィカシオンと呼ばれる粉末色ガラスを素地に付着させる方法や、透明ガラスの層の間に色ガラスを挟み込み彫刻を施すアンテルカルテールのような独創的な技術を開発しました。
1900年のパリ万国博覧会ではガラス部門でグランプリを獲得します。ドーム社は、同じナンシーに拠点を置くガレ社と並んで、アール・ヌーヴォーを代表する工房のひとつとなっていきました。なかでもエナメル彩とエッチング技法によって製造された作品群は、秀逸な職人芸からくりだされる細密描写と仕上げの丁寧さにおいて群を抜いており、ドーム社ならではの繊細な魅力を放っています。
ドーム社は、アール・ヌーヴォーからアール・デコ、そして現代へと時代の流行の変化に対応しつつ、つねにフランスを代表するガラスメーカーの座を守り続けています。
【ルネ・ラリック】
20世紀前半に活躍したフランスのガラス工芸家ルネ・ラリックは、1910年頃からガラス工芸の制作に携わり、アー ル・デコの時代と呼ばれる1920〜30年代に、当時を代表するガラス・メーカーの経営者として世界的な名声を確立しました。
ガラス製造に着手する以前のラリックは、草木や昆虫といったモティーフを駆使して、新奇で魅力的な宝飾品を生み出すデザイナーとして名を馳せていました。そのジュエリーは、貴金属に宝石をあしらうだけではなく、時には美しく磨き上げられた透明ガラスや色ガラスの小片も用いられていました。
宝石の希少価値よりもデザインを重視したラリックの仕事は、アール・ヌーヴォーが流行する時代において、他の追随を許さないひときわ抜きん出た存在でした。
彼がガラスに傾倒していったのは、香水商コティの香水瓶デザインの依頼を受けてからで、1908年以降ガラス工場を借り受け、最新鋭の機械を投入し、次第にガラス製造を工業化していきます。第一次大戦終結後には、花瓶や香水瓶の製造はもとより、外洋を航海する豪華客船や旅客列車の内装デザインを受注して、随所に装飾ガラスを使い、清楚で洗練された室内空間の演出によって高い評価を得ました。
1925年、パリで開催された「装飾美術産業美術国際博覧会」(通称アール・デコ展)では、ガラスを多用した大規模な展示館や噴水を製作して会場を沸かせました。意識的に色彩の使用を制限し、造形の彫刻的な表情を重んじた透明ガラスがかもし出す、繊細で幻想的な世界は、スピード感や機能性という新しい時代の美意識をも感じさせるものでした。
●開催期間●
2007年6月9日(土)〜8月11日(土)
●休館日●
毎週木曜日(祝日は開館)
●開館時間●
9:30〜16:30(入館は16:00まで)
●開催場所●
MOA美術館
電話 0557-84-2511
FAX 0557-84-2570
〒413-8511 静岡県熱海市桃山町26番2号
http://
●アクセス●
※電車
JR東海道線・JR新幹線熱海駅下車
※バス(伊豆東海バス)
熱海駅乗車→MOA美術館下車
・4番バスのりばより「MOA美術館」行き
・0番バスのりばより「湯〜遊〜バス」
※タクシー(熱海駅より)
3階入口(乗用車駐車場)まで:約8分
エスカレーター入口まで:約5分
※自動車
関西方面から東名沼津I.Cから:約1時間
東京方面から東名厚木I.Cから:約1時間30分
●観覧料●
大人1600円
高大生800円
中学生以下無料
満65才以上1200円
●サイト●
MOA美術館
http://
毎日新聞社
http://
凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹凹
上記の情報は開催場所のホームページ等をもとにしています。情報の変更等がある場合がありますので、お出掛けの際は、事前に確認をしてください。
また、観に行かれた方は感想などを宜しくお願いします。
コメント(1)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
困ったときには