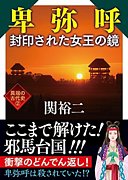開催終了伊藤塾48回目講座
詳細
2015年06月23日 00:31 更新
伊藤塾48回目講座 「豊前の国・歴史散歩」〜日田のルーツを訪ねて〜
今回の伊藤塾は、豊前国の古代史をテーマに行う。今回の特色は、なんと言っても田川の香春を組み入れたことである。その理由は、古代「豊の国」には、田川を始祖として英彦山を中心とした古代国家があり、田川も京都(みやこ)も宇佐も日田も「豊=トヨ」という名の「秦氏」と「鷹」でつながっているからだ。
今回の企画は当初、宇佐と京都郡までだった。その企画提出の翌日、伊藤塾長が香春を入れろと電話があった。え・・なんで?と思いながら・・・。しかしその理由は深かった。何故なら『日本書紀』、『古事記』には、田川に新羅の神が舞い降りてきたという異様な伝承があったからだ。そして「延喜式神名帳」には、香春神社が、宇佐より、奈良の大神神社、石上神宮より15年前に正一位の位をもらっていた誰も知らない歴史があるからである。
そう、これまで伊藤塾長が講座のたびに朝鮮半島とのつながりを説明してきた理由がここにあるからである。そして調べると田川と日田が神話や伝承でつながっていた可能性が高まってきた。
例えば、豊後国志では、西から飛んできた鷹が日田の湖を決壊し日田を創世した鷹が、なんと日田から田川へ飛んで帰ったという記述や、豊西記には、日田は昔「鷹羽郡」と呼ばれていたという。実は、田川も昔は「鷹羽郡」と呼ばれていた事からも、この鷹神話の謎が深まるばかりである。
また、歴史研究家の大和岩雄氏(大和出版社長)は、「秦氏の研究」で、英彦山を創建した日田の藤原恒雄が実は、日本人を名乗っているが、実は渡来系で香春の神であると著書で紹介する事は、日田の神が香春に祀られるという異様さだ。そして、大和氏は、新羅=鷹=鍛冶=秦氏という。
鷹の伝承は、ここでは、割愛するが、宇佐や英彦山にも多くの鷹伝承があり、日田も古代日鷹と呼ばれていた事も忘れてはいけない。
最終的には、新羅の勢力は田川から奥の院日田へ権力が移動し、筑紫や熊襲に睨みをきかせていて、その遺跡が日本最古の豪族居館跡「小迫辻原遺跡」ではないだろうかと想像できる。
徳川も豊臣も最終的に日田を直轄地として九州に睨みをきかせていたという歴史は古代の歴史を繰り返したのかもしれない。そして次に宇佐からみた奥の院日田を紹介する
宇佐の古代史
江上波夫は戦後日本国家の成立を朝鮮半島、中国大陸のみならずアジア一帯に目を向け、半農半牧の騎馬民族国家扶余に求め、南下した扶余が高句麗、百済を造り伽耶を経て、大和朝廷を興したという「騎馬民族征服王朝説」をとなえた。朝鮮の歴史学者金錫亨は五千年前の古朝鮮を開いた檀君の流れをくむ高句麗、百済、新羅、伽耶諸国が日本列島に進出し、在地の諸国と連合して成立したのが大和朝廷であるとした。いわゆる「朝鮮による日本分国論」である。
日田もその流れの中にある。中津の京都郡(みやこぐん)の古文書にはすべての人が朝鮮からの渡来人であると記され、宇佐神宮の成り立ちは三世紀頃より御毛沼命の子宇佐氏と八幡神大神氏と辛島氏などの数多くの渡来人によって興された。
先ごろ亡くなられた児玉先生説によれば宇佐で製鉄技術を買われた渡来人の大蔵氏は磐井の君の敗北した528年ごろ有田に入り平安、南北朝、室町、安土桃山の初期までの約600年日田を治めた豪族であった。古い日田在住の人たちの大半は大蔵氏子孫の流れをくむ子孫である。
今回の散歩は古い渡来人たちの来た道をたどる私たちの先祖探しの小旅行です。テキストに児玉先生著の「鬼の足音」を使いますがお持ちでない方には本を進呈します。
日時 7月2日(木) 参加費3500円(昼食・入場料込)時間 7:45〜17:30
参加者 先着25名
集合場所 大原神社前駐車場 申し込み先 電話 24−3232 伊藤電気
困ったときには