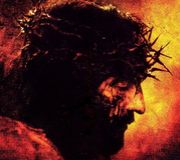開催終了上村静 聖書講座1
詳細
2008年03月09日 23:28 更新
こんにちは。クリスチャンコミュでも紹介致しましたが、こちらでも告知させて頂きます。
毎月第3土曜日の午後3時から5時、
東京・中野の日本キリスト教団中野桃園教会にて、
聖書学者の上村静氏(聖心女子大・東大講師)による聖書講座
宗教の倒錯〜「歴史」を問う〜
を通年で全10回開催致します。
第1回目のテーマは「原初史に見る人間と神」です。
※このイベントは宗教活動ではありません。
【講師プロフィール】
上村 静(うえむら・しずか)
1966年茨城県水戸生まれ。
2000年東京大学大学院博士課程修了。
2005年ヘブライ大学にてPh.D取得。ユダヤ学・聖書学専攻。
関東神学ゼミナール、農村伝道神学校、東海大学、東京大学、聖心女子大学講師。
著作 『キリスト教信仰の成立──ユダヤ教からの分離とその諸問題──』『イエス──人と神と──』
■受講料はお一人様500円/回。
■聖書ご持参ください。旧新約両方ある方がいいです。何語・何訳でも可。会場でも借りられます。
■受講申し込みは不要です。当日、直接会場までお越し下さい。
■中野桃園教会へのアクセス:中野駅北口からサンロード商店街を抜け、早稲田通りを右に約500m進み、中野リサイクルセンターの角を右折、約50m直進した左手。
上村静コミュはこちらです→http://
上村氏は、その著書「イエス──人と神と──」(関東神学ゼミナール)のあとがきに、以下のように記されています。
「私がイエス研究を始めた動機は、キリスト教への憎悪であった。それゆえ私の関心はイエスに集中し、そのためにユダヤ史を学んだのであるが、キリスト教は批判の対象でしかなかった。
(中略)
本書を両親に捧げることをお許し頂きたい。父は保守的な教派の牧師ではあるが、批判的な聖書研究に理解があり、私がこの世界に入ることを勧めてくれた。故母は熱心なキリスト者であり、若き日には牧師を志していたが、教派上の理由でその願いは叶わなかった。しかし、自らの体験から子どもの人権を守る会を立ち上げ、生涯その活動に携わった。また、自ら病を負った身でありながら、死期の近づいた知り合いを頻繁に訪ね、癒しと励ましのために多くの時間を費やしていた。母は、牧師の肩書きを得ることはできなかったが、その生き様において、最も理想的な牧師であったように思う。それは、今にして思えば、小さな<いのち>のために捧げられた生涯であったのだ(享年67歳)。先に述べた憎悪の呪縛からの解放は、私にとって両親のキリスト教信仰との和解でもあったように思う。」
文中に登場するお父様は茨城キリスト教学園大学の元学長、シャロンキリストの教会の上村昌次牧師を指します。
聖書学者は、たいていヨーロッパ(ドイツなど)かアメリカに留学するらしいんですが、上村氏は、長らくイスラエルに留学なさいました。ユダヤ教の観点からキリスト教を見るという、1980代ごろから始まった、比較的新しい聖書学の研究者です。日本基督教団の認可校・農村伝道神学校では7年にわたり教鞭をとって来られました(新約聖書概論および釈義など)。
主催者としては、聖書に親しみ、キリスト教についてより深く理解することによって、 本講座が平和への第一歩、そのきっかけになればと願っております。
他教派との、ユダヤ教との、他宗教との橋渡しに。
「クリスチャンなのに、なぜ争いが起きるの?」
「クリスチャンだから、争いが起きるの」
そのカラクリが、ここに。
イエス・キリストコミュの皆様のお越しをお待ち申し上げます。
++++++
聖書講座
宗教の倒錯〜「歴史」を問う〜
【講義スケジュール】全10回
第1回 原初史に見る人間と神 ── 2008年3月15日
第2回 ユダヤ教の根幹(アブラハム契約とシナイ契約)── 4月19日
第3回 王と預言者 ── 5月17日
第4回 バビロン捕囚とユダヤ教の成立 ── 6月21日
第5回 ヘレニズムとユダイズムの邂逅 ── 7月19日
第6回 セクト運動の展開とローマ支配 ── 10月18日
第7回 イエスの活動と思想 ── 11月15日
第8回 キリスト神話の成立 ── 12月20日
第9回 教会内の多様な立場 ── 2009年1月17日
第10回 キリスト教のユダヤ教からの分離 ── 2月21日
【講義の概要】
宗教は人を幸せにするためにあると言える。宗教は、様々な困難を抱える人を支え、力づけることができるし、何よりも人間について、〈いのち〉について深い洞察を有している。しかしながら、同時にまた、宗教の名のもとに多くの争いが生じている。宗教戦争は歴史年表を埋め尽くしているし、今日なお宗教間対立は払拭されたとは言えない。それは異宗教間の対立のみならず、同一宗教内部でも対立と分裂が繰り返されているし、さらにはある宗教に帰依したことが却ってその人を不幸にしてしまうという現実もある。信仰熱心に見える人が必ずしも本当に宗教的生を生きているとは限らないし、既成宗教とは無関係な人のなかに本当に他者のために生きている人がいるということも稀ではない。
「宗教」と呼ばれる人間の営みには、その内実としての宗教的なるものと、それを容れるための組織や教義、典礼といった器がある。器はその中味を盛って初めて有意味なものとなるはずであるが、宗教はしばしばその中味を見失い、器の色・形にばかり拘ってしまう。中味を見失った宗教は、それを隠蔽するためさらにその器に執着し、エゴイズムと呼ばれるべき暴力を剥き出しにし、他者の〈いのち〉を損なってしまう。これを宗教の倒錯と呼ぶことができよう。
ユダヤ教およびキリスト教は聖書を聖典とする宗教である。聖書は「歴史」にかかわっている。聖書に描かれているのは、歴史に介入する神の物語である。天地創造物語も、アブラハムの召命物語も、出エジプトもバビロン捕囚も、そしてキリストの啓示も神が「歴史」に介入したことを物語る。両宗教はこの「歴史」を史実として、それゆえ真実なるものとして受容することを要請する。確かに「歴史」は過去の出来事にかかわってはいるが、しかし、「歴史」とは史実の集積ではない。「歴史」は記憶されなければ知られないが、過去に起こったすべての事柄を記憶し記述することはできない。「歴史」とは、ある出来事が有意味なものであると認識され、その意味に即して記憶・記述されて初めて「歴史」となるのである。ある出来事が有意味なものとされるのは、その出来事が起こった後に、その出来事が意味づけられたということ、すなわち、その出来事の解釈に基づくということである。その意味は、当然ながらそれを意味づけている歴史家の現在にとっての意味である。歴史家は自分の現在を過去の出来事との連関の中で意味づけるために、過去の出来事を意味づける。そうして今度は時間軸に即して、しかし自分にとって意味のある「歴史」を物語るのである。すなわち、「歴史」とは歴史家によって意味づけられた物語なのである。聖書に記されている「歴史」もまた後から意味づけられた物語なのであって、その史実性に基づいて真理性を主張することはできない。むしろ聖書になんらかの真理性があるとするならば、そこで与えられている「意味」の真理性そのものを問わねばならない。
本講義では、聖書に物語られている「歴史」とそれを物語る者の「歴史」を読み解きつつ、キリスト教信仰の内実とその器としての表象を問う。それによって、人を幸せにするための宗教がなにゆえ人を不幸にしてしまうのか──それはキリスト教にも当てはまる──という宗教の倒錯について考える。
毎月第3土曜日の午後3時から5時、
東京・中野の日本キリスト教団中野桃園教会にて、
聖書学者の上村静氏(聖心女子大・東大講師)による聖書講座
宗教の倒錯〜「歴史」を問う〜
を通年で全10回開催致します。
第1回目のテーマは「原初史に見る人間と神」です。
※このイベントは宗教活動ではありません。
【講師プロフィール】
上村 静(うえむら・しずか)
1966年茨城県水戸生まれ。
2000年東京大学大学院博士課程修了。
2005年ヘブライ大学にてPh.D取得。ユダヤ学・聖書学専攻。
関東神学ゼミナール、農村伝道神学校、東海大学、東京大学、聖心女子大学講師。
著作 『キリスト教信仰の成立──ユダヤ教からの分離とその諸問題──』『イエス──人と神と──』
■受講料はお一人様500円/回。
■聖書ご持参ください。旧新約両方ある方がいいです。何語・何訳でも可。会場でも借りられます。
■受講申し込みは不要です。当日、直接会場までお越し下さい。
■中野桃園教会へのアクセス:中野駅北口からサンロード商店街を抜け、早稲田通りを右に約500m進み、中野リサイクルセンターの角を右折、約50m直進した左手。
上村静コミュはこちらです→http://
上村氏は、その著書「イエス──人と神と──」(関東神学ゼミナール)のあとがきに、以下のように記されています。
「私がイエス研究を始めた動機は、キリスト教への憎悪であった。それゆえ私の関心はイエスに集中し、そのためにユダヤ史を学んだのであるが、キリスト教は批判の対象でしかなかった。
(中略)
本書を両親に捧げることをお許し頂きたい。父は保守的な教派の牧師ではあるが、批判的な聖書研究に理解があり、私がこの世界に入ることを勧めてくれた。故母は熱心なキリスト者であり、若き日には牧師を志していたが、教派上の理由でその願いは叶わなかった。しかし、自らの体験から子どもの人権を守る会を立ち上げ、生涯その活動に携わった。また、自ら病を負った身でありながら、死期の近づいた知り合いを頻繁に訪ね、癒しと励ましのために多くの時間を費やしていた。母は、牧師の肩書きを得ることはできなかったが、その生き様において、最も理想的な牧師であったように思う。それは、今にして思えば、小さな<いのち>のために捧げられた生涯であったのだ(享年67歳)。先に述べた憎悪の呪縛からの解放は、私にとって両親のキリスト教信仰との和解でもあったように思う。」
文中に登場するお父様は茨城キリスト教学園大学の元学長、シャロンキリストの教会の上村昌次牧師を指します。
聖書学者は、たいていヨーロッパ(ドイツなど)かアメリカに留学するらしいんですが、上村氏は、長らくイスラエルに留学なさいました。ユダヤ教の観点からキリスト教を見るという、1980代ごろから始まった、比較的新しい聖書学の研究者です。日本基督教団の認可校・農村伝道神学校では7年にわたり教鞭をとって来られました(新約聖書概論および釈義など)。
主催者としては、聖書に親しみ、キリスト教についてより深く理解することによって、 本講座が平和への第一歩、そのきっかけになればと願っております。
他教派との、ユダヤ教との、他宗教との橋渡しに。
「クリスチャンなのに、なぜ争いが起きるの?」
「クリスチャンだから、争いが起きるの」
そのカラクリが、ここに。
イエス・キリストコミュの皆様のお越しをお待ち申し上げます。
++++++
聖書講座
宗教の倒錯〜「歴史」を問う〜
【講義スケジュール】全10回
第1回 原初史に見る人間と神 ── 2008年3月15日
第2回 ユダヤ教の根幹(アブラハム契約とシナイ契約)── 4月19日
第3回 王と預言者 ── 5月17日
第4回 バビロン捕囚とユダヤ教の成立 ── 6月21日
第5回 ヘレニズムとユダイズムの邂逅 ── 7月19日
第6回 セクト運動の展開とローマ支配 ── 10月18日
第7回 イエスの活動と思想 ── 11月15日
第8回 キリスト神話の成立 ── 12月20日
第9回 教会内の多様な立場 ── 2009年1月17日
第10回 キリスト教のユダヤ教からの分離 ── 2月21日
【講義の概要】
宗教は人を幸せにするためにあると言える。宗教は、様々な困難を抱える人を支え、力づけることができるし、何よりも人間について、〈いのち〉について深い洞察を有している。しかしながら、同時にまた、宗教の名のもとに多くの争いが生じている。宗教戦争は歴史年表を埋め尽くしているし、今日なお宗教間対立は払拭されたとは言えない。それは異宗教間の対立のみならず、同一宗教内部でも対立と分裂が繰り返されているし、さらにはある宗教に帰依したことが却ってその人を不幸にしてしまうという現実もある。信仰熱心に見える人が必ずしも本当に宗教的生を生きているとは限らないし、既成宗教とは無関係な人のなかに本当に他者のために生きている人がいるということも稀ではない。
「宗教」と呼ばれる人間の営みには、その内実としての宗教的なるものと、それを容れるための組織や教義、典礼といった器がある。器はその中味を盛って初めて有意味なものとなるはずであるが、宗教はしばしばその中味を見失い、器の色・形にばかり拘ってしまう。中味を見失った宗教は、それを隠蔽するためさらにその器に執着し、エゴイズムと呼ばれるべき暴力を剥き出しにし、他者の〈いのち〉を損なってしまう。これを宗教の倒錯と呼ぶことができよう。
ユダヤ教およびキリスト教は聖書を聖典とする宗教である。聖書は「歴史」にかかわっている。聖書に描かれているのは、歴史に介入する神の物語である。天地創造物語も、アブラハムの召命物語も、出エジプトもバビロン捕囚も、そしてキリストの啓示も神が「歴史」に介入したことを物語る。両宗教はこの「歴史」を史実として、それゆえ真実なるものとして受容することを要請する。確かに「歴史」は過去の出来事にかかわってはいるが、しかし、「歴史」とは史実の集積ではない。「歴史」は記憶されなければ知られないが、過去に起こったすべての事柄を記憶し記述することはできない。「歴史」とは、ある出来事が有意味なものであると認識され、その意味に即して記憶・記述されて初めて「歴史」となるのである。ある出来事が有意味なものとされるのは、その出来事が起こった後に、その出来事が意味づけられたということ、すなわち、その出来事の解釈に基づくということである。その意味は、当然ながらそれを意味づけている歴史家の現在にとっての意味である。歴史家は自分の現在を過去の出来事との連関の中で意味づけるために、過去の出来事を意味づける。そうして今度は時間軸に即して、しかし自分にとって意味のある「歴史」を物語るのである。すなわち、「歴史」とは歴史家によって意味づけられた物語なのである。聖書に記されている「歴史」もまた後から意味づけられた物語なのであって、その史実性に基づいて真理性を主張することはできない。むしろ聖書になんらかの真理性があるとするならば、そこで与えられている「意味」の真理性そのものを問わねばならない。
本講義では、聖書に物語られている「歴史」とそれを物語る者の「歴史」を読み解きつつ、キリスト教信仰の内実とその器としての表象を問う。それによって、人を幸せにするための宗教がなにゆえ人を不幸にしてしまうのか──それはキリスト教にも当てはまる──という宗教の倒錯について考える。
困ったときには