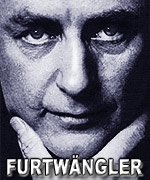オットー・クレンペラー(Otto Klemperer。1885〜1973年。独)
微動だにしない遅めのテンポが大きなスケールで迫り、クールななかにも燃焼度の高い演奏は、重厚かつ純粋です。
戦後ヨーロッパに復帰(一時ナチスに追われて渡米)してブダペスト国立歌劇場、ロンドンPOなどを歴任後、フィルハーモニアPOの首席指揮者としてEMIに膨大な録音を残しました。壮健だった若い頃は現代音楽に深い関心を示していましが、身体の不調があった1960年頃(75歳前後)より古典派やロマン派で彼の芸術的個性が開花したようで、大器晩成の巨人とよばれています。
EMIの録音ではハイドン交響曲(8曲)、ベートーヴェン交響曲・ミサソレ、メンデルスゾーン交響曲(3・4番)・真夏の夜の夢、シューマン・ブラームス・フランク・ブルックナー・マーラーの交響曲などがどれも有名です。
コミュはhttp://
あなたのお好きなクレンペラーの名演・名盤をお教え下さい。
微動だにしない遅めのテンポが大きなスケールで迫り、クールななかにも燃焼度の高い演奏は、重厚かつ純粋です。
戦後ヨーロッパに復帰(一時ナチスに追われて渡米)してブダペスト国立歌劇場、ロンドンPOなどを歴任後、フィルハーモニアPOの首席指揮者としてEMIに膨大な録音を残しました。壮健だった若い頃は現代音楽に深い関心を示していましが、身体の不調があった1960年頃(75歳前後)より古典派やロマン派で彼の芸術的個性が開花したようで、大器晩成の巨人とよばれています。
EMIの録音ではハイドン交響曲(8曲)、ベートーヴェン交響曲・ミサソレ、メンデルスゾーン交響曲(3・4番)・真夏の夜の夢、シューマン・ブラームス・フランク・ブルックナー・マーラーの交響曲などがどれも有名です。
コミュはhttp://
あなたのお好きなクレンペラーの名演・名盤をお教え下さい。
|
|
|
|
コメント(52)
はじめまして。
クレンペラーのCDはあまり持っていないのですが、私のベスト3は、
マーラー4番:ベルリン放送交響楽団
この演奏は凄いですね。1楽章はチェロが何と美しく訴えてくることか。トランペットの音が拾えていないくらいですがこんなに歌わせる演奏は珍しいですね。バーンスタイン盤はこの演奏に比べると影が薄いです。
メンデルスゾーン3番:フィルハーモニア管弦楽団
言わずと知れた名盤ですが、4楽章のコーダ部分を書き換えたバイエルン放送響盤もあるくらいこの曲が好きだったことが分かります。でもやっぱり原曲に忠実なこの盤を選びます。あまりのめり込み過ぎずに冷静でそれでいて哀愁が漂っています。ミュンシュ盤と両極ですね。
ベートーベン8番:フィルハーモニア管弦楽団
例によってテンポは遅いめですが、この曲にはちょうど心地よい曲運びでフルトベングラーのように重過ぎず、それでいて十分に歌えています。遊びもあり愉しいですね。
クレンペラーのCDはあまり持っていないのですが、私のベスト3は、
マーラー4番:ベルリン放送交響楽団
この演奏は凄いですね。1楽章はチェロが何と美しく訴えてくることか。トランペットの音が拾えていないくらいですがこんなに歌わせる演奏は珍しいですね。バーンスタイン盤はこの演奏に比べると影が薄いです。
メンデルスゾーン3番:フィルハーモニア管弦楽団
言わずと知れた名盤ですが、4楽章のコーダ部分を書き換えたバイエルン放送響盤もあるくらいこの曲が好きだったことが分かります。でもやっぱり原曲に忠実なこの盤を選びます。あまりのめり込み過ぎずに冷静でそれでいて哀愁が漂っています。ミュンシュ盤と両極ですね。
ベートーベン8番:フィルハーモニア管弦楽団
例によってテンポは遅いめですが、この曲にはちょうど心地よい曲運びでフルトベングラーのように重過ぎず、それでいて十分に歌えています。遊びもあり愉しいですね。
そのニコリともしない風貌のままの、冷徹で微動だにしない芸風は、決してとっつきやすいものではないが、一度その魅力がわかれば、これほど高みにいたった芸術もないことがよくわかる。
とはいえ、ここまでに至るに1960年代まで待たなくてならなかったというのは、まことに驚くべきことであり、それも、半身不随で車椅子生活となり、言語も不明瞭になってからだというのだから、更に驚いてしまう。
EMIに多く残された60年代以降の演奏を聴くと、とてもそんな不自由な体で指揮した人間が出している音楽とは到底思えないほどに重厚で桁はずれなスケールを持ち、何をやっているのかが全部見えてくるようなスローテンポは、他に比較のしようのないスタイルだ。
こういう、あまりに堅固なスタイルであるため、曲による向き不向きがはっきり出てしまうが、その芸風と曲想が合致した時の演奏は、超名演である。
メンデルスゾーン「スコットランド」「真夏の夜の夢」、ハイドン「軍隊」、モーツァルト『フィガロの結婚』、ベートーヴェン『ミサ・ソレムニス』、ベルリオーズ「幻想交響曲」、ドヴォルザーク「新世界から」は、いずれもクレンペラーとしかいいようのない名演であり、不滅の遺産であろう。
クレンペラーは、大器晩成の典型である。
とはいえ、ここまでに至るに1960年代まで待たなくてならなかったというのは、まことに驚くべきことであり、それも、半身不随で車椅子生活となり、言語も不明瞭になってからだというのだから、更に驚いてしまう。
EMIに多く残された60年代以降の演奏を聴くと、とてもそんな不自由な体で指揮した人間が出している音楽とは到底思えないほどに重厚で桁はずれなスケールを持ち、何をやっているのかが全部見えてくるようなスローテンポは、他に比較のしようのないスタイルだ。
こういう、あまりに堅固なスタイルであるため、曲による向き不向きがはっきり出てしまうが、その芸風と曲想が合致した時の演奏は、超名演である。
メンデルスゾーン「スコットランド」「真夏の夜の夢」、ハイドン「軍隊」、モーツァルト『フィガロの結婚』、ベートーヴェン『ミサ・ソレムニス』、ベルリオーズ「幻想交響曲」、ドヴォルザーク「新世界から」は、いずれもクレンペラーとしかいいようのない名演であり、不滅の遺産であろう。
クレンペラーは、大器晩成の典型である。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
巨匠指揮者讃 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
巨匠指揮者讃のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90050人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人