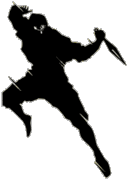マラソン選手のひふく筋(gastrocnemius)では、赤筋すなわち遅筋繊維が94%〜98%、短距離ランナーのひふく筋(gastrocnemius)では、赤筋すなわち遅筋繊維が25%程度で、75%が白筋すなわち遅筋繊維だそうです。
赤筋すなわち遅筋繊維には高い酸化能力があり、白筋すなわち速筋繊維には高い解糖能力があるそうです。持続的な有酸素運動によって発達する筋繊維と、瞬発的な運動によって発達する筋繊維では、必要とする化学的物質に差異があるということであって、運動前に適切な補給をすれば、効率的に筋肉を発達させることが出来るのではないか?という気がします。
筋肉というものは鍛えることによって、筋繊維の構成を変化させやすい部位らしい、という推測がなりたちます。確かに、筋肉というものは、筋トレをするとすぐに発達します。
筋肉を構成するフィラメント(ミオシンとアクシン)は、アミノ酸からなるたんぱく質によって、筋繊維(=筋細胞)の中で製造され、製造をするときに、筋細胞の核内の染色体によって制御されるらしいのですが、逆にストレッチなどの運動が遺伝子の発現に影響を与えるという説もあるようです。
フィラメントの製造が筋細胞の核内の染色体によって制御されるというのは、因果関係が分かり易いのですが、しかし、逆に、ストレッチなどの運動が遺伝子の発現に影響を与えるというのは、因果関係が分かりにくい。
効率良く筋肉を鍛える運動方法の開発、身体というハードウェアを効率的に利用する技術、染色体との因果関係の明確化、この辺りに貢献することこそ、21世紀の忍者の人体実験的テーマかも?
赤筋すなわち遅筋繊維には高い酸化能力があり、白筋すなわち速筋繊維には高い解糖能力があるそうです。持続的な有酸素運動によって発達する筋繊維と、瞬発的な運動によって発達する筋繊維では、必要とする化学的物質に差異があるということであって、運動前に適切な補給をすれば、効率的に筋肉を発達させることが出来るのではないか?という気がします。
筋肉というものは鍛えることによって、筋繊維の構成を変化させやすい部位らしい、という推測がなりたちます。確かに、筋肉というものは、筋トレをするとすぐに発達します。
筋肉を構成するフィラメント(ミオシンとアクシン)は、アミノ酸からなるたんぱく質によって、筋繊維(=筋細胞)の中で製造され、製造をするときに、筋細胞の核内の染色体によって制御されるらしいのですが、逆にストレッチなどの運動が遺伝子の発現に影響を与えるという説もあるようです。
フィラメントの製造が筋細胞の核内の染色体によって制御されるというのは、因果関係が分かり易いのですが、しかし、逆に、ストレッチなどの運動が遺伝子の発現に影響を与えるというのは、因果関係が分かりにくい。
効率良く筋肉を鍛える運動方法の開発、身体というハードウェアを効率的に利用する技術、染色体との因果関係の明確化、この辺りに貢献することこそ、21世紀の忍者の人体実験的テーマかも?
|
|
|
|
コメント(12)
さいきん、男女各一名づつ、びっくりするくらい股関節の柔らかい人を見かけました。偉い人のおぼしめしと考えてまじまじと観察させていただいたわけですが、正直、何らかの”機密/秘密”が紛れこんでいるような印象を受けました。
男性のほうには特に脅威は感じませんでしたが、女性のほうには男性の首に足をひっかけて絞め殺せるくらいの身体能力を感じたので、ちょっとした警戒感を(本能的に)感じた気がしました。気の回し過ぎというか気のせいかもしれませんが。
身体の柔らかい人には(何と言うか)瞬発力を感じないのですが、根拠は不明です。
猫は起床直後にストレッチをするらしいのですが、そんなことはさておいて、筋肉の伸長の仕組みはモデル化が曖昧で、因果関係が理論的に不明瞭であるという印象が否めないのですが如何ですか。
カエルか鳥のモモ肉を使って、とある実験をしてみたいこの頃です。
男性のほうには特に脅威は感じませんでしたが、女性のほうには男性の首に足をひっかけて絞め殺せるくらいの身体能力を感じたので、ちょっとした警戒感を(本能的に)感じた気がしました。気の回し過ぎというか気のせいかもしれませんが。
身体の柔らかい人には(何と言うか)瞬発力を感じないのですが、根拠は不明です。
猫は起床直後にストレッチをするらしいのですが、そんなことはさておいて、筋肉の伸長の仕組みはモデル化が曖昧で、因果関係が理論的に不明瞭であるという印象が否めないのですが如何ですか。
カエルか鳥のモモ肉を使って、とある実験をしてみたいこの頃です。
技さん
コメントをありがとうございます。
>と、習いました。
左様でございますか。では別の角度から質問をさせてください。
(1)屈筋が伸筋が互いに引っ張り合っているような(あたかも弓のような)状態で関節を駆動している場合と、(2)屈筋が伸筋が相互に力を影響させあわずに関節を駆動している場合、この両現象の差異を説明している教科書や文献を御存知でしょうか>
>筋肉自体がエネルギーを使って緩むことはあっても、伸びることはないんじゃ?
筋肉自体がエネルギーを使って伸びることはないでしょうが、別の筋肉にひっぱられて伸びることはありえるのではないでしょうか。
また、筋肉自体がエネルギーを放出して伸張する現象が”絶対にありえない”と言い切る根拠は知りません。
服部
コメントをありがとうございます。
>と、習いました。
左様でございますか。では別の角度から質問をさせてください。
(1)屈筋が伸筋が互いに引っ張り合っているような(あたかも弓のような)状態で関節を駆動している場合と、(2)屈筋が伸筋が相互に力を影響させあわずに関節を駆動している場合、この両現象の差異を説明している教科書や文献を御存知でしょうか>
>筋肉自体がエネルギーを使って緩むことはあっても、伸びることはないんじゃ?
筋肉自体がエネルギーを使って伸びることはないでしょうが、別の筋肉にひっぱられて伸びることはありえるのではないでしょうか。
また、筋肉自体がエネルギーを放出して伸張する現象が”絶対にありえない”と言い切る根拠は知りません。
服部
TaddyHattyさん
自分が知ってるなりに答えますと
(1)の現象は、屈筋と伸筋が同等の力で引っ張り合ってれば動かない状態ですよね。屈筋が勝っていれば曲がっていきます。
(2)の現象は、回旋(捻る)動作の時に屈筋だけ補助(主動は回旋筋)として使われ、同時にその関節が伸びる状態にあれば伸筋は使われます。しかし、この場合でも屈筋と伸筋がお互いに影響しないのは無理だと思います。
(2)の状態が分からないので文献を紹介できません。ごめんなさい。
>別の筋肉にひっぱられて伸びることはありえるのではないでしょうか。
あります。遠心性収縮というものですね。ベンチプレスで重量を上げられずに落ちていく時に大胸筋は力を出しているにも関わらず、伸びていきます。筋肉は縮もうとしているのに、無理矢理引き伸されている状態です。
>筋肉自体がエネルギーを放出して伸張する現象が”絶対にありえない”と言い切る根拠は知りません。
医歯薬出版株式会社さんの『基礎運動学』という本の、「骨格筋の微細構造と筋収縮機序」という項目に書いてあります。
絶対的根拠と言われると、自分の目で見た物さえ疑う事もあるので、何も信用できなくなってしまいます。
自分が知ってるなりに答えますと
(1)の現象は、屈筋と伸筋が同等の力で引っ張り合ってれば動かない状態ですよね。屈筋が勝っていれば曲がっていきます。
(2)の現象は、回旋(捻る)動作の時に屈筋だけ補助(主動は回旋筋)として使われ、同時にその関節が伸びる状態にあれば伸筋は使われます。しかし、この場合でも屈筋と伸筋がお互いに影響しないのは無理だと思います。
(2)の状態が分からないので文献を紹介できません。ごめんなさい。
>別の筋肉にひっぱられて伸びることはありえるのではないでしょうか。
あります。遠心性収縮というものですね。ベンチプレスで重量を上げられずに落ちていく時に大胸筋は力を出しているにも関わらず、伸びていきます。筋肉は縮もうとしているのに、無理矢理引き伸されている状態です。
>筋肉自体がエネルギーを放出して伸張する現象が”絶対にありえない”と言い切る根拠は知りません。
医歯薬出版株式会社さんの『基礎運動学』という本の、「骨格筋の微細構造と筋収縮機序」という項目に書いてあります。
絶対的根拠と言われると、自分の目で見た物さえ疑う事もあるので、何も信用できなくなってしまいます。
技さん
コメントをありがとうございます。
>(1)の現象は、屈筋と伸筋が同等の力で引っ張り合ってれば動かない状態ですよね。
>屈筋が勝っていれば曲がっていきます。
ある筋(A筋)とある筋(B筋)が、同等の力で引っ張り合っている状態を三種類くらいに分けて考えてみては如何かと思います。
a)A筋は収縮しようとしており、更にB筋も収縮しようとして 力学的に釣り合っている場合
b)A筋は収縮しようとしており、更にB筋が伸張された状態から元に戻ろうとして、力学的に釣り合っている場合
c)A筋は収縮しようとしており、更にB筋は伸張されているが元に戻ろうという力は働いていおらず、力学的に釣り合っている場合
a)の場合とb)の場合とc)の場合とで、B筋の内部の化学反応に差異があるのではないかと推測します。更に、B筋が白筋であるか赤筋であるかによって差異が生じると予想します。
教科書を参照してみると、a)の場合、B筋が白筋であれば糖分を分解しながらATPを分解してアクチンとミオシンのスライドを誘発し、B筋が赤筋であれば酸素を消費しながらATPを分解してアクチンとミオシンのスライドを誘発する、という説明くらいしか思いつきませんが、やや因果関係が不明瞭であるという印象が拭えません。
B筋が伸張された状態から元に戻ろうとするとき、通常の収縮のようにATPを分解する場合と、そうでない場合があるえるのではないか?と考えるのです。
>(2)の現象は、回旋(捻る)動作の時に屈筋だけ補助(主動は回旋筋)として使われ、
>同時にその関節が伸びる状態にあれば伸筋は使われます。しかし、この場合でも屈筋と
>伸筋がお互いに影響しないのは無理だと思います。
>(2)の状態が分からないので文献を紹介できません。ごめんなさい。
『屈筋と伸筋がお互いに影響しない状態』を、伸筋の側の化学反応(例えば、酸素を消費しているか、糖分を分解しているか)の状態を調べて、もっと厳密に定義することは可能ではないかと考えますが、如何でしょうか。
>別の筋肉にひっぱられて伸びることはありえるのではないでしょうか。
>あります。遠心性収縮というものですね。ベンチプレスで重量を上げられずに落ちていく時に
>大胸筋は力を出しているにも関わらず、伸びていきます。筋肉は縮もうとしているのに、
>無理矢理引き伸されている状態です。
屈筋と伸筋という分類は、現象の見た目の結果でしかないとおっしゃるのでございましたら、筋肉内部の化学反応の状態に準じて、屈筋と伸筋とは別の用語を用いた方がいいのかもしれません。
>筋肉自体がエネルギーを放出して伸張する現象が”絶対にありえない”と言い切る根拠は
>知りません。
>医歯薬出版株式会社さんの『基礎運動学』という本の、「骨格筋の微細構造と筋収縮機序」という
>項目に書いてあります。
ありがとうございます。
調べてみます。
今わたくしが参考にしている文献は医歯薬出版株式会社さんの『筋力』という本ですが、この文献によると『筋細胞中のCa^2+の濃度を上げる手段を処するならば筋収縮と筋弛緩の能力を向上させることが出来る』という風にも読みとることが出来ます。
服部
コメントをありがとうございます。
>(1)の現象は、屈筋と伸筋が同等の力で引っ張り合ってれば動かない状態ですよね。
>屈筋が勝っていれば曲がっていきます。
ある筋(A筋)とある筋(B筋)が、同等の力で引っ張り合っている状態を三種類くらいに分けて考えてみては如何かと思います。
a)A筋は収縮しようとしており、更にB筋も収縮しようとして 力学的に釣り合っている場合
b)A筋は収縮しようとしており、更にB筋が伸張された状態から元に戻ろうとして、力学的に釣り合っている場合
c)A筋は収縮しようとしており、更にB筋は伸張されているが元に戻ろうという力は働いていおらず、力学的に釣り合っている場合
a)の場合とb)の場合とc)の場合とで、B筋の内部の化学反応に差異があるのではないかと推測します。更に、B筋が白筋であるか赤筋であるかによって差異が生じると予想します。
教科書を参照してみると、a)の場合、B筋が白筋であれば糖分を分解しながらATPを分解してアクチンとミオシンのスライドを誘発し、B筋が赤筋であれば酸素を消費しながらATPを分解してアクチンとミオシンのスライドを誘発する、という説明くらいしか思いつきませんが、やや因果関係が不明瞭であるという印象が拭えません。
B筋が伸張された状態から元に戻ろうとするとき、通常の収縮のようにATPを分解する場合と、そうでない場合があるえるのではないか?と考えるのです。
>(2)の現象は、回旋(捻る)動作の時に屈筋だけ補助(主動は回旋筋)として使われ、
>同時にその関節が伸びる状態にあれば伸筋は使われます。しかし、この場合でも屈筋と
>伸筋がお互いに影響しないのは無理だと思います。
>(2)の状態が分からないので文献を紹介できません。ごめんなさい。
『屈筋と伸筋がお互いに影響しない状態』を、伸筋の側の化学反応(例えば、酸素を消費しているか、糖分を分解しているか)の状態を調べて、もっと厳密に定義することは可能ではないかと考えますが、如何でしょうか。
>別の筋肉にひっぱられて伸びることはありえるのではないでしょうか。
>あります。遠心性収縮というものですね。ベンチプレスで重量を上げられずに落ちていく時に
>大胸筋は力を出しているにも関わらず、伸びていきます。筋肉は縮もうとしているのに、
>無理矢理引き伸されている状態です。
屈筋と伸筋という分類は、現象の見た目の結果でしかないとおっしゃるのでございましたら、筋肉内部の化学反応の状態に準じて、屈筋と伸筋とは別の用語を用いた方がいいのかもしれません。
>筋肉自体がエネルギーを放出して伸張する現象が”絶対にありえない”と言い切る根拠は
>知りません。
>医歯薬出版株式会社さんの『基礎運動学』という本の、「骨格筋の微細構造と筋収縮機序」という
>項目に書いてあります。
ありがとうございます。
調べてみます。
今わたくしが参考にしている文献は医歯薬出版株式会社さんの『筋力』という本ですが、この文献によると『筋細胞中のCa^2+の濃度を上げる手段を処するならば筋収縮と筋弛緩の能力を向上させることが出来る』という風にも読みとることが出来ます。
服部
いわゆるダイエットでは、筋トレをして脂肪を分解させるわけですが、白筋の鍛錬(速い動作による筋トレ)をするのと、赤筋の鍛錬(重い物を持ち上げるような遅い動作による筋トレ)をするのでは、前者の方が脂肪減の速度が速いと考えています。(求ム 関連スル参考文献)
昔、バイト先のある女性が「男はスポーツをするとすぐに体重が落ちるけど、女は容易に体重が落ちない」とボヤいてました。
それは白筋の鍛錬(速い動作による筋トレ)をしていないからではないかと推測しています。
いくら長時間の運動をしても、赤筋の鍛錬(重い物を持ち上げるような遅い動作による筋トレ)では、脂肪が容易に落ちないのではないかと思うのです。
つまり男女差ではなくて、運動の質の好みの差ではないかと考えるのです。
同じスポーツで同じ身体動作であっても、まろやかに動作するのと、バネや弓のように動作するのでは、後者のほうが脂肪燃焼の効率が良いのではないかということです。
服部
昔、バイト先のある女性が「男はスポーツをするとすぐに体重が落ちるけど、女は容易に体重が落ちない」とボヤいてました。
それは白筋の鍛錬(速い動作による筋トレ)をしていないからではないかと推測しています。
いくら長時間の運動をしても、赤筋の鍛錬(重い物を持ち上げるような遅い動作による筋トレ)では、脂肪が容易に落ちないのではないかと思うのです。
つまり男女差ではなくて、運動の質の好みの差ではないかと考えるのです。
同じスポーツで同じ身体動作であっても、まろやかに動作するのと、バネや弓のように動作するのでは、後者のほうが脂肪燃焼の効率が良いのではないかということです。
服部
>昔、バイト先のある女性が「男はスポーツをするとすぐに体重が落ちるけど、女は容易に体重が
>落ちない」とボヤいてました。
>
>それは白筋の鍛錬(速い動作による筋トレ)をしていないからではないかと推測しています。
>いくら長時間の運動をしても、赤筋の鍛錬(重い物を持ち上げるような遅い動作による筋トレ)では、
>脂肪が容易に落ちないのではないかと思うのです。
>
>つまり男女差ではなくて、運動の質の好みの差ではないかと考えるのです。
>同じスポーツで同じ身体動作であっても、まろやかに動作するのと、バネや弓のように動作するの
>では、後者のほうが脂肪燃焼の効率が良いのではないかということです。
・週3日、数百メートルも泳いでいるのに、お腹の贅肉が落ちないし体重も減らないとか、
・週3日、2時間もエクササイズしているのに、お尻の贅肉が落ちないし体重も減らないとか、
そういうことでお悩みの女性は、身体動作をするときに、手足を出来るだけ速く・機敏に動かすように心がけると、脂肪が減って体重が落ち始めるのではないかと推測します。
たとえラジオ体操の振り付けであろうと、出来るだけ速く・機敏に手足を動かすように心がけた場合とそうでない場合では、前者では白筋鍛錬となり、後者では赤筋鍛錬となるのではないかと考えるのです。
そもそも筋細胞の生産システムに男女差があるとは思えません。
同じスポーツで同じ身体動作であっても、女性はまったり動作することを好む者が多く、男性はバネや弓のように動作することを好む者が多いに過ぎないと推測します。
市営プールで定期的に水泳をしている女性を観察して気付いたのですが、機敏な動作で泳ぐ女性は身体が締まっている傾向が強く、まったりとした動作で泳ぐ女性は(たとえ長距離を泳ごうとも)まったく体重が落ちない(贅肉が減らない)傾向が強いのです。
スパイ育成では、人材とミッションを鑑みて、どこの部位の赤筋鍛錬をして、どこの部位の白筋鍛錬をするか、人の目を欺くことまで配慮してトレーニングメニューを設計することになると思われます。
服部
>落ちない」とボヤいてました。
>
>それは白筋の鍛錬(速い動作による筋トレ)をしていないからではないかと推測しています。
>いくら長時間の運動をしても、赤筋の鍛錬(重い物を持ち上げるような遅い動作による筋トレ)では、
>脂肪が容易に落ちないのではないかと思うのです。
>
>つまり男女差ではなくて、運動の質の好みの差ではないかと考えるのです。
>同じスポーツで同じ身体動作であっても、まろやかに動作するのと、バネや弓のように動作するの
>では、後者のほうが脂肪燃焼の効率が良いのではないかということです。
・週3日、数百メートルも泳いでいるのに、お腹の贅肉が落ちないし体重も減らないとか、
・週3日、2時間もエクササイズしているのに、お尻の贅肉が落ちないし体重も減らないとか、
そういうことでお悩みの女性は、身体動作をするときに、手足を出来るだけ速く・機敏に動かすように心がけると、脂肪が減って体重が落ち始めるのではないかと推測します。
たとえラジオ体操の振り付けであろうと、出来るだけ速く・機敏に手足を動かすように心がけた場合とそうでない場合では、前者では白筋鍛錬となり、後者では赤筋鍛錬となるのではないかと考えるのです。
そもそも筋細胞の生産システムに男女差があるとは思えません。
同じスポーツで同じ身体動作であっても、女性はまったり動作することを好む者が多く、男性はバネや弓のように動作することを好む者が多いに過ぎないと推測します。
市営プールで定期的に水泳をしている女性を観察して気付いたのですが、機敏な動作で泳ぐ女性は身体が締まっている傾向が強く、まったりとした動作で泳ぐ女性は(たとえ長距離を泳ごうとも)まったく体重が落ちない(贅肉が減らない)傾向が強いのです。
スパイ育成では、人材とミッションを鑑みて、どこの部位の赤筋鍛錬をして、どこの部位の白筋鍛錬をするか、人の目を欺くことまで配慮してトレーニングメニューを設計することになると思われます。
服部
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
忍者 更新情報
忍者のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90016人
- 2位
- 酒好き
- 170665人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人