|
|
|
|
コメント(8)
Maestosoの部分のテンポの指定は、Breitkopfでも[四分音符]=60で、Bärenreiterと同じです。
従来の慣習では、ここを6つ振りにすることが多く、実質的に[四分音符]=30のテンポにしていたのですが、最近の原典回帰の指向で、「楽譜に指定通り」のテンポで振ろうとするようです。
実際、Bärenreiterを編纂したJonathan Del Marは、ベートーベンの草稿や各種写譜の相違点などを網羅した詳細なCritical Commentaryも出版しているのですが、Maestosoのテンポに関する記述は一切ありません。
(テンポに関しては解決済みの問題ということか?)
むしろ、彼の疑問点は、そのあと920小節目から始まるPrestissimoのテンポ[全音符]=88で、テンポに疑問符が付けてあり、「Critical Commentaryを参照せよ」と注記がされています。
(彼はベートーベンの会話帳まで調べて、Prestissimoのテンポを推定しています。)
もちろん、Jonathan Del Marの仕事は楽譜の校訂にあるので、それをどう解釈しどう表現するかという実際の演奏とは別の次元の話なのですが、参考のため、ご紹介しておきます。
従来の慣習では、ここを6つ振りにすることが多く、実質的に[四分音符]=30のテンポにしていたのですが、最近の原典回帰の指向で、「楽譜に指定通り」のテンポで振ろうとするようです。
実際、Bärenreiterを編纂したJonathan Del Marは、ベートーベンの草稿や各種写譜の相違点などを網羅した詳細なCritical Commentaryも出版しているのですが、Maestosoのテンポに関する記述は一切ありません。
(テンポに関しては解決済みの問題ということか?)
むしろ、彼の疑問点は、そのあと920小節目から始まるPrestissimoのテンポ[全音符]=88で、テンポに疑問符が付けてあり、「Critical Commentaryを参照せよ」と注記がされています。
(彼はベートーベンの会話帳まで調べて、Prestissimoのテンポを推定しています。)
もちろん、Jonathan Del Marの仕事は楽譜の校訂にあるので、それをどう解釈しどう表現するかという実際の演奏とは別の次元の話なのですが、参考のため、ご紹介しておきます。
くわしいご解説ありがとうございます。
Mar氏の校訂の話は知らなかったので勉強になりました。
アバドやラトルの物凄く速いMaestosoはベーレンライター最新版による新解釈ではないんですね。この点を確認したかったんです。一つ疑問が解決できました。
私が若い頃に買ったスコアも何年か前から使ってるカルムス版のパート譜もMaestosoは四分音符=60になってるので、なぜ従来ゆっくり振ってたのかというのが疑問でした。
920小節のPrestissimoのテンポは851小節に付点二分音符=132に戻るという解釈が自然なようで、そうするとフルトヴェングラーらの凄く速い指揮は独自の解釈ということで、その後の指揮者たちはこれに追随したのだろうと推測されます。
920小節のPrestissimoのテンポ[全音符]=88は私のスコア、パート譜にはありませんが、Mar氏はさらに疑問符をつけてるんですね。この点も詳しくご教示いただければ有り難いです。
Mar氏の校訂の話は知らなかったので勉強になりました。
アバドやラトルの物凄く速いMaestosoはベーレンライター最新版による新解釈ではないんですね。この点を確認したかったんです。一つ疑問が解決できました。
私が若い頃に買ったスコアも何年か前から使ってるカルムス版のパート譜もMaestosoは四分音符=60になってるので、なぜ従来ゆっくり振ってたのかというのが疑問でした。
920小節のPrestissimoのテンポは851小節に付点二分音符=132に戻るという解釈が自然なようで、そうするとフルトヴェングラーらの凄く速い指揮は独自の解釈ということで、その後の指揮者たちはこれに追随したのだろうと推測されます。
920小節のPrestissimoのテンポ[全音符]=88は私のスコア、パート譜にはありませんが、Mar氏はさらに疑問符をつけてるんですね。この点も詳しくご教示いただければ有り難いです。
Jonathan Del Marの場合、ベートーベンの楽譜草稿だけでなく、会話帳まで調べているので、ベートーベンがテンポの指定について、あれこれ悩んでメモしていたことについてまで読み込んでしまい、結果的には、深読みしすぎてしまったのかもしれません。
(あくまでも私見ですが。)
たしかに、「920小節のPrestissimoのテンポは851小節のテンポに戻る」という解釈なら、整合性があります。
Jonathan Del Marの深読みとは、「ベートーベンならfinaleをテンポを上げて劇的に盛り上げるはずだ」という「先入観」が働いてしまったのではないかということです。
ですから、彼としては、ベートーベンの草稿だけではなく、会話帳に「88」という数字があるのを発見してしまったら、それを無視するわけにはいかなかったのだろうと思います。
しかし、彼も研究者なら研究者としての良心として、自分の主観を押しつけることも出来ず、自分が編纂した校訂版だというのに、「Critical Commentaryを参照せよ」とコメントを付けるしかなかったのでしょう。
(「批判的校訂」をしたはずなのに、なおも「批判的コメンタリーを読め」というのは、ちょっと不自然なんですけどね。)
もちろん、ベートーベンの時代には、メトロノームによる速度指定と、表情指定による速度指定とでは、必ずしも首尾一貫して一致していないという事情も考慮に入れる必要があるかと思います。
***
と言いつつ、私的は、フルトヴェングラー(振ると面食らう)の「第九」(とくに「バイロイト音楽祭」)のは、大好きです。
ベートーベンが作曲した意図は、おそらくは譜面どおりだろうという憶測は、たしかにそうなのでしょうが、各時代のマエストロが試みてきたように、Maestosoでギリギリ緊張感を溜めて、次のPrestissimoで一気に爆発という演奏方式が、個人的には好みなのです。
(あくまでも私見ですが。)
たしかに、「920小節のPrestissimoのテンポは851小節のテンポに戻る」という解釈なら、整合性があります。
Jonathan Del Marの深読みとは、「ベートーベンならfinaleをテンポを上げて劇的に盛り上げるはずだ」という「先入観」が働いてしまったのではないかということです。
ですから、彼としては、ベートーベンの草稿だけではなく、会話帳に「88」という数字があるのを発見してしまったら、それを無視するわけにはいかなかったのだろうと思います。
しかし、彼も研究者なら研究者としての良心として、自分の主観を押しつけることも出来ず、自分が編纂した校訂版だというのに、「Critical Commentaryを参照せよ」とコメントを付けるしかなかったのでしょう。
(「批判的校訂」をしたはずなのに、なおも「批判的コメンタリーを読め」というのは、ちょっと不自然なんですけどね。)
もちろん、ベートーベンの時代には、メトロノームによる速度指定と、表情指定による速度指定とでは、必ずしも首尾一貫して一致していないという事情も考慮に入れる必要があるかと思います。
***
と言いつつ、私的は、フルトヴェングラー(振ると面食らう)の「第九」(とくに「バイロイト音楽祭」)のは、大好きです。
ベートーベンが作曲した意図は、おそらくは譜面どおりだろうという憶測は、たしかにそうなのでしょうが、各時代のマエストロが試みてきたように、Maestosoでギリギリ緊張感を溜めて、次のPrestissimoで一気に爆発という演奏方式が、個人的には好みなのです。
皆さんいろいろなコメントありがとうございます。
だるびっしゅさん、トスカニーニ改めて聴くと確かに速くて楽譜の速度記号に近いですね。ただその後の有名な指揮者の演奏の多くはフルトヴェングラーに近い感じだったので疑問に思っていたわけです。ベーレンライター最新版による変更ではないことがわかりましたので、従来トスカニーニのような速度で振る方がもっといても良かったはずなんですね(探せばいろいろあるかもしれませんが)。
いろいろな疑問が解決できました。ありがとうございます。
では本題にもどってベーレンライター最新版による改訂の主たるところって何なのでしょう。詳しくご存知の方いらっしゃいますか?
だるびっしゅさん、トスカニーニ改めて聴くと確かに速くて楽譜の速度記号に近いですね。ただその後の有名な指揮者の演奏の多くはフルトヴェングラーに近い感じだったので疑問に思っていたわけです。ベーレンライター最新版による変更ではないことがわかりましたので、従来トスカニーニのような速度で振る方がもっといても良かったはずなんですね(探せばいろいろあるかもしれませんが)。
いろいろな疑問が解決できました。ありがとうございます。
では本題にもどってベーレンライター最新版による改訂の主たるところって何なのでしょう。詳しくご存知の方いらっしゃいますか?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
心に響く『第九』 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
心に響く『第九』のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82539人
- 2位
- 酒好き
- 170702人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人
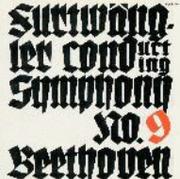














![Grande Messe[ミサ曲コミュ]](https://logo-imagecluster.img.mixi.jp/photo/comm/86/11/308611_96s.jpg)








