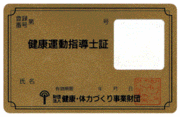スクールトレーナー制度
----------------------
一部で検討されている。
理学療法士等が、学校現場に入り、学校医や養護教諭と連携して、学童の
運動器の健康推進のための様々な活動を行う資格が検討されている。
運動器検診では、学校医の補佐や健診結果の整理分析の支援等を行う。
目的:
運動器医療の高度な学術的知識と臨床技法を有する専門家を育成し、学校長、
学校医・養護教諭及び地区の医師会等と緊密な連携の下に、学校保健の現場に
参画し、支援・協力することにより、児童生徒の運動器の健康増進と健全な心
身の成長・発達と生涯にわたる健康づくりに寄与する。
想定されるスクールトレーナーの活動内容:
1) 小・中学校・高等学校等での総合的な学習の時間、保健体育等の授業、
特別授業及び学校保健委員会での講演等の形式での運動器疾患・障害
に関わる指導・教育の支援。
2) 保健室での学校医・養護教育による児童生徒に対する運動器の健康に関
わる保健指導、健康教育の支援・助言
3)保護者、教職員に対する運動器と運動器疾患・障害に関わる講話・実技指
導等の形式での教育
4)定期健康診断における保健調査表の運動器疾患・障害に関わる事項の整理・
分析の支援、学校医による運動器検診の補佐、検診結果の整理分析の支援等
5)健康診断後の運動器機能不全(いわゆるからだの固い子)及びスポーツ障
害や側わん症等の運動器疾患・障害を有する児童生徒の事後処置・健康教育の
支援
6)その他、学校医・養護教諭と連携した児童生徒の運動器健康に関わる支援
・教育活動
一般財団法人 運動器の10 年・日本協会
http://
4B.日本医師会学校保健委員会、日本学校保健会等に対し、「運動器に係る教
育研修活動」として本事業の趣旨を説明し、協力を求めるとともに、25 年度
作成した「スクールトレーナー活動の概要(認定制度創設構想素案)」をもと
にしたポンチ絵を添えた「スクールトレーナー認定制度創設要望書」を作成し、
文部科学省に提示する。
一般財団法人 運動器の10 年・日本協会
http://
大腿骨近位部2次骨折予防ワーキンググループの活動
事業の概要
また、学会認定の骨粗鬆症専属のナースを養成するする考えもあり、骨粗鬆症
学会に協力していく方針。
4/24 (NHK総合[クローズアップ現代])
異変をどう見つけるか・学校現場の模索
http://
検診を行っているのは宮崎大学医学部・帖佐悦男教授。90人の検査に割り当
てられた時間は1時間。学校医の多くは内科医や小児科医で運動器の詳しい知
識はない。正確な検査実施となると戸惑いもある。学校医(小児科医)・小野
武己は「小児科医にはできない。整形など専門的なものはできない」とコメン
ト。整形外科医以外でも運動器検診が行えるように基礎知識をもってサポート
をする健康スポーツナースの育成に取り組んでいる。
院内認定『宮大健康スポーツナース』
http://
『宮大健康スポーツナース』は、1)地域における運動器検診やスポーツイベン
ト、レクレーション等において、医師や理学療法士等と協働し、地域住民の健
康維持・向上のための活動を行う2)運動器についての知識を習得し、運動器の
構造や役割、および障害とその対処法を理解し、ロコモティブシンドロームの
予防や転倒予防について教育、指導を行うことを目的としています。
認定までの流れ
看護部現任教育「救急看護」の研修を修了
養成研修全てを受講
学校運動器検診への参加(見学と一次検診の実施)
本人の申請
認定試験の実施
認定委員会の審査
認定証授与
養成研修は、整形外科医師、理学療法士を講師として、約60分〜90分の講義と
演習を年間5回実施しています。運動器についての理解や応急処置の基本を学
んでいます。『宮大健康スポーツナース』は、こんな役割を担っています。
運動器疾患における知識を活用し、春と秋に行われる学校運動器検診に協力す
る地域で行われるスポーツイベントには、帯同看護師として負傷者の救護活動
を行う養成研修のアシスタントとして、『宮大健康スポーツナース』を目指す
看護師を支援する院内の患者さんの転倒予防に関する活動を行うロコモティブ
シンドローム予防に対する啓発活動を行う
健康スポーツナース」で地域住民の健康を守る
帖佐悦男(宮崎大学教授・整形外科学)
https:/
宮崎大学では,スポーツ選手・スポーツ愛好家・地域住民を医学の面から支え
る「スポーツメディカルサポートシステム」(図)を展開している。現在,主
に医師や理学療法士などがスポーツ現場での支援に当たっている。さまざまな
分野をサポートするには,医師,トレーナー,看護師,栄養士などの各専門分
野の連携が必要であるが,マンパワー不足という問題を抱えているのが実状だ。
そこでわれわれは,「発育・発達」を意図した運動機能評価,「健康づくり」
としての運動指導,「健康回復」への看護介入やスポーツイベントへの同行・
支援を行うことを目的に,2010年10月に「健康スポーツナース」制度を創設し
た。その体制作りのため,宮崎大医学部看護学科,同附属病院看護部,宮崎県
看護協会が中心となり,健康スポーツナースの認定・普及などに当たる「日本
健康運動看護学会:日本健康スポーツ学会」を2010年2月に設立。第1回の学会・
講習会を10月10日に開催した。
看護師に着目したのは,看護師自身運動・スポーツに関心のある人が多く,
これまでもスポーツ現場に派遣されている実績があり,さらに地域に最も密着
した専門職であるからである。健康スポーツナースの役割については,下記の
4点を軸に考えている。
(1)「運動器検診」への参加
学校や地域における運動器検診に参加し,子どもから高齢者までの運動機能
評価や相談を実施する。
(2)運動機能の維持・改善に向けた指導
病院・施設・健康教室などにおいて,健康づくり・回復の一環として,転倒
防止対策などロコモティブシンドロームやメタボリックシンドローム予防など
の方法を指導する。
(3)スポーツクラブでの健康相談
地域におけるスポーツクラブなどで,選手や愛好家の健康管理について,看
護の立場から運動療法士などと相談し,指導する。
(4)スポーツイベントでの救護
青島太平洋マラソンなど,イベントにおいて救護に当たる。
より専門的知識を修得した健康スポーツナースが運動やスポーツの現場にか
かわることで,スポーツ外傷・障害,ロコモティブシンドローム,生活習慣病
などの予防に貢献し,健康寿命の延伸(元気に老いる!)につながることを期
待したい。
健康運動指導士とは
http://
1. 健康運動指導士とは
個々人の心身の状態に応じた、安全で効果的な運動を実施するための運動プロ
グラムの作成及び指導を行う者
健康運動指導士とは、保健医療関係者と連携しつつ安全で効果的な運動を実施
するための運動プログラム作成及び実践指導計画の調整等を行う役割を担う者
をいいます。この健康運動指導士の養成事業は、昭和63年から厚生大臣の認定
事業として、生涯を通じた国民の健康づくりに寄与する目的で創設され、生活
習慣病を予防し、健康水準を保持・増進する観点から大きく貢献してまいりま
した。平成18年度からは、公益財団法人健康・体力づくり事業財団独自の事業
として継続して実施しております。今般の医療制度改革においては、生活習慣
病予防が生涯を通じた個人の健康づくりだけでなく、中長期的な医療費適正化
対策の柱の一つとして位置づけられており、今後展開される本格的な生活習慣
病対策においては、一次予防に留まらず二次予防も含めた健康づくりのための
運動を指導する専門家の必要性が増しており、とくに平成20年度から実施の特
定健診・特定保健指導において運動・身体活動支援を担うことについて、健康
運動指導士への期待がますます高まっているところです。公益財団法人健康・
体力づくり事業財団としては、平成19年度に健康運動指導士の養成カリキュラ
ム、資格取得方法等に至るまで大幅な見直しを行なったことを踏まえ、ハイリ
スク者も対象にした安全で効果的な運動指導を行なうことのできる専門家を目
指す上で健康運動指導士をまず取得すべき標準的な資格であると位置付け、質
の高い人材の養成、確保を積極的に図っているところです。
----------------------
一部で検討されている。
理学療法士等が、学校現場に入り、学校医や養護教諭と連携して、学童の
運動器の健康推進のための様々な活動を行う資格が検討されている。
運動器検診では、学校医の補佐や健診結果の整理分析の支援等を行う。
目的:
運動器医療の高度な学術的知識と臨床技法を有する専門家を育成し、学校長、
学校医・養護教諭及び地区の医師会等と緊密な連携の下に、学校保健の現場に
参画し、支援・協力することにより、児童生徒の運動器の健康増進と健全な心
身の成長・発達と生涯にわたる健康づくりに寄与する。
想定されるスクールトレーナーの活動内容:
1) 小・中学校・高等学校等での総合的な学習の時間、保健体育等の授業、
特別授業及び学校保健委員会での講演等の形式での運動器疾患・障害
に関わる指導・教育の支援。
2) 保健室での学校医・養護教育による児童生徒に対する運動器の健康に関
わる保健指導、健康教育の支援・助言
3)保護者、教職員に対する運動器と運動器疾患・障害に関わる講話・実技指
導等の形式での教育
4)定期健康診断における保健調査表の運動器疾患・障害に関わる事項の整理・
分析の支援、学校医による運動器検診の補佐、検診結果の整理分析の支援等
5)健康診断後の運動器機能不全(いわゆるからだの固い子)及びスポーツ障
害や側わん症等の運動器疾患・障害を有する児童生徒の事後処置・健康教育の
支援
6)その他、学校医・養護教諭と連携した児童生徒の運動器健康に関わる支援
・教育活動
一般財団法人 運動器の10 年・日本協会
http://
4B.日本医師会学校保健委員会、日本学校保健会等に対し、「運動器に係る教
育研修活動」として本事業の趣旨を説明し、協力を求めるとともに、25 年度
作成した「スクールトレーナー活動の概要(認定制度創設構想素案)」をもと
にしたポンチ絵を添えた「スクールトレーナー認定制度創設要望書」を作成し、
文部科学省に提示する。
一般財団法人 運動器の10 年・日本協会
http://
大腿骨近位部2次骨折予防ワーキンググループの活動
事業の概要
また、学会認定の骨粗鬆症専属のナースを養成するする考えもあり、骨粗鬆症
学会に協力していく方針。
4/24 (NHK総合[クローズアップ現代])
異変をどう見つけるか・学校現場の模索
http://
検診を行っているのは宮崎大学医学部・帖佐悦男教授。90人の検査に割り当
てられた時間は1時間。学校医の多くは内科医や小児科医で運動器の詳しい知
識はない。正確な検査実施となると戸惑いもある。学校医(小児科医)・小野
武己は「小児科医にはできない。整形など専門的なものはできない」とコメン
ト。整形外科医以外でも運動器検診が行えるように基礎知識をもってサポート
をする健康スポーツナースの育成に取り組んでいる。
院内認定『宮大健康スポーツナース』
http://
『宮大健康スポーツナース』は、1)地域における運動器検診やスポーツイベン
ト、レクレーション等において、医師や理学療法士等と協働し、地域住民の健
康維持・向上のための活動を行う2)運動器についての知識を習得し、運動器の
構造や役割、および障害とその対処法を理解し、ロコモティブシンドロームの
予防や転倒予防について教育、指導を行うことを目的としています。
認定までの流れ
看護部現任教育「救急看護」の研修を修了
養成研修全てを受講
学校運動器検診への参加(見学と一次検診の実施)
本人の申請
認定試験の実施
認定委員会の審査
認定証授与
養成研修は、整形外科医師、理学療法士を講師として、約60分〜90分の講義と
演習を年間5回実施しています。運動器についての理解や応急処置の基本を学
んでいます。『宮大健康スポーツナース』は、こんな役割を担っています。
運動器疾患における知識を活用し、春と秋に行われる学校運動器検診に協力す
る地域で行われるスポーツイベントには、帯同看護師として負傷者の救護活動
を行う養成研修のアシスタントとして、『宮大健康スポーツナース』を目指す
看護師を支援する院内の患者さんの転倒予防に関する活動を行うロコモティブ
シンドローム予防に対する啓発活動を行う
健康スポーツナース」で地域住民の健康を守る
帖佐悦男(宮崎大学教授・整形外科学)
https:/
宮崎大学では,スポーツ選手・スポーツ愛好家・地域住民を医学の面から支え
る「スポーツメディカルサポートシステム」(図)を展開している。現在,主
に医師や理学療法士などがスポーツ現場での支援に当たっている。さまざまな
分野をサポートするには,医師,トレーナー,看護師,栄養士などの各専門分
野の連携が必要であるが,マンパワー不足という問題を抱えているのが実状だ。
そこでわれわれは,「発育・発達」を意図した運動機能評価,「健康づくり」
としての運動指導,「健康回復」への看護介入やスポーツイベントへの同行・
支援を行うことを目的に,2010年10月に「健康スポーツナース」制度を創設し
た。その体制作りのため,宮崎大医学部看護学科,同附属病院看護部,宮崎県
看護協会が中心となり,健康スポーツナースの認定・普及などに当たる「日本
健康運動看護学会:日本健康スポーツ学会」を2010年2月に設立。第1回の学会・
講習会を10月10日に開催した。
看護師に着目したのは,看護師自身運動・スポーツに関心のある人が多く,
これまでもスポーツ現場に派遣されている実績があり,さらに地域に最も密着
した専門職であるからである。健康スポーツナースの役割については,下記の
4点を軸に考えている。
(1)「運動器検診」への参加
学校や地域における運動器検診に参加し,子どもから高齢者までの運動機能
評価や相談を実施する。
(2)運動機能の維持・改善に向けた指導
病院・施設・健康教室などにおいて,健康づくり・回復の一環として,転倒
防止対策などロコモティブシンドロームやメタボリックシンドローム予防など
の方法を指導する。
(3)スポーツクラブでの健康相談
地域におけるスポーツクラブなどで,選手や愛好家の健康管理について,看
護の立場から運動療法士などと相談し,指導する。
(4)スポーツイベントでの救護
青島太平洋マラソンなど,イベントにおいて救護に当たる。
より専門的知識を修得した健康スポーツナースが運動やスポーツの現場にか
かわることで,スポーツ外傷・障害,ロコモティブシンドローム,生活習慣病
などの予防に貢献し,健康寿命の延伸(元気に老いる!)につながることを期
待したい。
健康運動指導士とは
http://
1. 健康運動指導士とは
個々人の心身の状態に応じた、安全で効果的な運動を実施するための運動プロ
グラムの作成及び指導を行う者
健康運動指導士とは、保健医療関係者と連携しつつ安全で効果的な運動を実施
するための運動プログラム作成及び実践指導計画の調整等を行う役割を担う者
をいいます。この健康運動指導士の養成事業は、昭和63年から厚生大臣の認定
事業として、生涯を通じた国民の健康づくりに寄与する目的で創設され、生活
習慣病を予防し、健康水準を保持・増進する観点から大きく貢献してまいりま
した。平成18年度からは、公益財団法人健康・体力づくり事業財団独自の事業
として継続して実施しております。今般の医療制度改革においては、生活習慣
病予防が生涯を通じた個人の健康づくりだけでなく、中長期的な医療費適正化
対策の柱の一つとして位置づけられており、今後展開される本格的な生活習慣
病対策においては、一次予防に留まらず二次予防も含めた健康づくりのための
運動を指導する専門家の必要性が増しており、とくに平成20年度から実施の特
定健診・特定保健指導において運動・身体活動支援を担うことについて、健康
運動指導士への期待がますます高まっているところです。公益財団法人健康・
体力づくり事業財団としては、平成19年度に健康運動指導士の養成カリキュラ
ム、資格取得方法等に至るまで大幅な見直しを行なったことを踏まえ、ハイリ
スク者も対象にした安全で効果的な運動指導を行なうことのできる専門家を目
指す上で健康運動指導士をまず取得すべき標準的な資格であると位置付け、質
の高い人材の養成、確保を積極的に図っているところです。
|
|
|
|
|
|
|
|
健康運動指導士 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
健康運動指導士のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90044人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6426人
- 3位
- 独り言
- 9046人