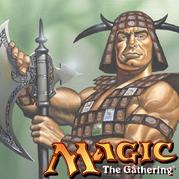公式情報を主に発信していくトピックです!
読み物から新製品情報、イベントカバレージなど最新の情報を更新していきます!
以下、現在連載中の記事のバックナンバーのリンクです。
お知らせ
http://
デイリーデッキ (岩SHOW編)
http://
Making Magic -マジック開発秘話-
http://
Magic Story -未踏世界の物語-
http://
Latest Developments -デベロップ最先端-
http://
Beyond the Basics -上級者への道-
http://
読み物から新製品情報、イベントカバレージなど最新の情報を更新していきます!
以下、現在連載中の記事のバックナンバーのリンクです。
お知らせ
http://
デイリーデッキ (岩SHOW編)
http://
Making Magic -マジック開発秘話-
http://
Magic Story -未踏世界の物語-
http://
Latest Developments -デベロップ最先端-
http://
Beyond the Basics -上級者への道-
http://
|
|
|
|
コメント(926)
食物連鎖(レガシー)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030710/
レガシーをやっていると最も出くわす光景が「1ターン目《死儀礼のシャーマン》」であることは疑いようもない。
最強1マナ圏として、彼は今日も世界のどこかしこで1ターン目から対処を迫っている。すぐ処理できなかったら2ターン目から好きなように動かれてしまう。これまで1マナのマナ・クリーチャーは緑の特権だったのに、それが黒にももたらされたことでマジックの常識は大きく変わってしまった。まあ、今日ではもはやそれが常識か。
では、死儀礼を繰り出してくるデッキは環境にどのくらいあるのだろうか? まず現レガシーの最大勢力「グリクシス・デルバー」、次いで多い「4色コントロール」、それから伝統の「エルフ」。あとは緑と黒が絡んだクリーチャーが採用されているデッキの大半……つまりむっちゃ多いってことだ。死儀礼だけを見て「おっ、○○か」と相手のデッキを断定してプレイするのは危ないってことだね。
他にヒントになるものは土地だが、《Underground Sea》から唱えられても選択肢は多数ある。まあ「グリクシス・デルバー」か「4色コントロール」だろうと高を括ると、その正体はこんなデッキだったりするかもしれない……。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030710/
レガシーをやっていると最も出くわす光景が「1ターン目《死儀礼のシャーマン》」であることは疑いようもない。
最強1マナ圏として、彼は今日も世界のどこかしこで1ターン目から対処を迫っている。すぐ処理できなかったら2ターン目から好きなように動かれてしまう。これまで1マナのマナ・クリーチャーは緑の特権だったのに、それが黒にももたらされたことでマジックの常識は大きく変わってしまった。まあ、今日ではもはやそれが常識か。
では、死儀礼を繰り出してくるデッキは環境にどのくらいあるのだろうか? まず現レガシーの最大勢力「グリクシス・デルバー」、次いで多い「4色コントロール」、それから伝統の「エルフ」。あとは緑と黒が絡んだクリーチャーが採用されているデッキの大半……つまりむっちゃ多いってことだ。死儀礼だけを見て「おっ、○○か」と相手のデッキを断定してプレイするのは危ないってことだね。
他にヒントになるものは土地だが、《Underground Sea》から唱えられても選択肢は多数ある。まあ「グリクシス・デルバー」か「4色コントロール」だろうと高を括ると、その正体はこんなデッキだったりするかもしれない……。
ファートリ・トークン(ブロール)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030713/
ブロール/Brawl、してますか? 大喧嘩してるかってとんでもない質問だが、今年から始まった例の新しい統率者戦のことね。スタンダードのカードのみを用いて統率者デッキを構築して戦うブロール、Twitterなんかを見ているとあちこちで密かな盛り上がりを見せているようで、多人数戦フォーマット好きとしては嬉しい限りだ。
このブロール、以前紹介した時とはルールなどにおいて大きな変更が加わった。まず、禁止カードはスタンダード通りではなく、ブロール独自のものに変更。《密輸人の回転翼機》《魔術遠眼鏡》《遵法長、バラル》が禁止となり、それ以外のカードはすべて使用可能だ。久しぶりに《霊気池の驚異》を起動できたりしちゃうわけだ。夢があるね。
禁止になっているカードは、まあしょうがないかな。特に《魔術遠眼鏡》は、プレインズウォーカーを統率者として用いることができるブロールの面白さを半減させていた。《ウルザの後継、カーン》デッキを使っていた時に何度か2ターン目にこれを出されて「そんなんひどいわ〜!」と叫んだものである(笑)。
というわけで、プレインズウォーカーを主役にしたデッキを作りたかった皆さんにはこれは朗報かと。現スタンダードには魅力的なプレインズウォーカーが複数いるが、テーマを持ったデッキを作れるという点では彼女なんて最高じゃないかな? 《光輝の勇者、ファートリ》が本領発揮だッッ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030713/
ブロール/Brawl、してますか? 大喧嘩してるかってとんでもない質問だが、今年から始まった例の新しい統率者戦のことね。スタンダードのカードのみを用いて統率者デッキを構築して戦うブロール、Twitterなんかを見ているとあちこちで密かな盛り上がりを見せているようで、多人数戦フォーマット好きとしては嬉しい限りだ。
このブロール、以前紹介した時とはルールなどにおいて大きな変更が加わった。まず、禁止カードはスタンダード通りではなく、ブロール独自のものに変更。《密輸人の回転翼機》《魔術遠眼鏡》《遵法長、バラル》が禁止となり、それ以外のカードはすべて使用可能だ。久しぶりに《霊気池の驚異》を起動できたりしちゃうわけだ。夢があるね。
禁止になっているカードは、まあしょうがないかな。特に《魔術遠眼鏡》は、プレインズウォーカーを統率者として用いることができるブロールの面白さを半減させていた。《ウルザの後継、カーン》デッキを使っていた時に何度か2ターン目にこれを出されて「そんなんひどいわ〜!」と叫んだものである(笑)。
というわけで、プレインズウォーカーを主役にしたデッキを作りたかった皆さんにはこれは朗報かと。現スタンダードには魅力的なプレインズウォーカーが複数いるが、テーマを持ったデッキを作れるという点では彼女なんて最高じゃないかな? 《光輝の勇者、ファートリ》が本領発揮だッッ!
掘葬アブザン(モダン)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030715/
ここしばらくは「MTG Arena」でベータテスターとしてスタンダードをプレイし、Magic Onlineではモダンをプレイするというマジックにおいてとても充実したオンライン活動を行えている。ストレートに言おう、最高だ。どんどんとマジックを遊ぶ人にとって、良い環境が作られていくことを心から願うね!
で、本題。先日モダンのデッキを調整していた時のこと。対戦相手は《花盛りの湿地》から《コジレックの審問》を唱えてきた。
あらら1ターン目からハンデスなんて嫌ですわ、とか思いつつも相手のデッキは3つに絞れるなと考えた。「ジャンド」「アブザン」「黒緑」である。《血編み髪のエルフ》解禁によりパワーアップした「ジャンド」は使用者もこの3つの中では最も多い……ようなのだが、どういうわけか僕自身は全く当たらない。なのでこの時も「アブザン」か「黒緑」だろうと思い込んでいた。
で、案の定相手は続いて白黒の土地を置いてきた。やっぱり「アブザン」だなと。《流刑への道》を持っているのがちょっとうっとうしいな、なんて思いながらプレイしていると……相手はこちらのターン終了時に思いがけないカードをプレイしてきた。《忌まわしい回収》!
おいおい、『ラヴニカへの回帰』期のスタンダードを思い出すじゃないか。そのまま《未練ある魂》や《掘葬の儀式》が墓地に落ちた。あの時代のまんまじゃないか! その後、《包囲サイ》が出てきて、それを《修復の天使》で出し入れするという、割と好き放題やられてしまったのである。
以前に紹介した「掘葬の儀式」デッキを思い出したが、あれよりも大型クリーチャーは少なく、天使とサイに絞り込んで色もアブザン(白黒緑)カラーにまとめているようだった。
う〜む、好みじゃないか……ストライクど真ん中な動きをするデッキに魅せられてしまった。そこで各種デッキ掲載サイトを漁っていると……それらしいリストを見つけた。おそらく、これに近いデッキのはずだ。「掘葬アブザン」の登場だ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030715/
ここしばらくは「MTG Arena」でベータテスターとしてスタンダードをプレイし、Magic Onlineではモダンをプレイするというマジックにおいてとても充実したオンライン活動を行えている。ストレートに言おう、最高だ。どんどんとマジックを遊ぶ人にとって、良い環境が作られていくことを心から願うね!
で、本題。先日モダンのデッキを調整していた時のこと。対戦相手は《花盛りの湿地》から《コジレックの審問》を唱えてきた。
あらら1ターン目からハンデスなんて嫌ですわ、とか思いつつも相手のデッキは3つに絞れるなと考えた。「ジャンド」「アブザン」「黒緑」である。《血編み髪のエルフ》解禁によりパワーアップした「ジャンド」は使用者もこの3つの中では最も多い……ようなのだが、どういうわけか僕自身は全く当たらない。なのでこの時も「アブザン」か「黒緑」だろうと思い込んでいた。
で、案の定相手は続いて白黒の土地を置いてきた。やっぱり「アブザン」だなと。《流刑への道》を持っているのがちょっとうっとうしいな、なんて思いながらプレイしていると……相手はこちらのターン終了時に思いがけないカードをプレイしてきた。《忌まわしい回収》!
おいおい、『ラヴニカへの回帰』期のスタンダードを思い出すじゃないか。そのまま《未練ある魂》や《掘葬の儀式》が墓地に落ちた。あの時代のまんまじゃないか! その後、《包囲サイ》が出てきて、それを《修復の天使》で出し入れするという、割と好き放題やられてしまったのである。
以前に紹介した「掘葬の儀式」デッキを思い出したが、あれよりも大型クリーチャーは少なく、天使とサイに絞り込んで色もアブザン(白黒緑)カラーにまとめているようだった。
う〜む、好みじゃないか……ストライクど真ん中な動きをするデッキに魅せられてしまった。そこで各種デッキ掲載サイトを漁っていると……それらしいリストを見つけた。おそらく、これに近いデッキのはずだ。「掘葬アブザン」の登場だ!
シングルカード・ストラテジー
https://mtg-jp.com/reading/translated/0030716/
マジックのデッキを組むための方法には、いくつかの基本的な手法がある。
よくあるやり方の1つは、一般的なアーキタイプやテーマに従ってデッキを構築する方法だ。例えば、アグロやコントロールとかだね。アグレッシブ・デッキの目標は明確だ。可能な限り素早く、かつ可能な限り多くのダメージを与えられるようにする。特定のカードに頼るのではなく、それらアーキタイプやテーマの戦略に沿ってデッキを作るというものだ。
それとは対照的な方法が、カードを軸にデッキを構築する手法だ。それは、デッキ全体を使って特定のカードを最大限生かすよう構築する、というものになる。その方法で作るデッキは、コンボデッキであったり、あるいはどのようなデッキでも使えるような汎用性が無い、特殊なカードを生かすためにあつらえたデッキとなったりするんだ。
これらは2つの異なるデッキ構築戦略について説明している。テーマ・ストラテジーとシングルカード・ストラテジーだ。
今日はそれらについて――そしてそれらに絡むいくつかのカードについて話そうと思う。ええと、それらのカードが全部『基本セット2019』のプレビュー・カードだってことは伝えたっけ? 全部レアか神話レアだってことは? いやあ、とっても気になるね。
もたもたしてる場合じゃない。先に進もう!
https://mtg-jp.com/reading/translated/0030716/
マジックのデッキを組むための方法には、いくつかの基本的な手法がある。
よくあるやり方の1つは、一般的なアーキタイプやテーマに従ってデッキを構築する方法だ。例えば、アグロやコントロールとかだね。アグレッシブ・デッキの目標は明確だ。可能な限り素早く、かつ可能な限り多くのダメージを与えられるようにする。特定のカードに頼るのではなく、それらアーキタイプやテーマの戦略に沿ってデッキを作るというものだ。
それとは対照的な方法が、カードを軸にデッキを構築する手法だ。それは、デッキ全体を使って特定のカードを最大限生かすよう構築する、というものになる。その方法で作るデッキは、コンボデッキであったり、あるいはどのようなデッキでも使えるような汎用性が無い、特殊なカードを生かすためにあつらえたデッキとなったりするんだ。
これらは2つの異なるデッキ構築戦略について説明している。テーマ・ストラテジーとシングルカード・ストラテジーだ。
今日はそれらについて――そしてそれらに絡むいくつかのカードについて話そうと思う。ええと、それらのカードが全部『基本セット2019』のプレビュー・カードだってことは伝えたっけ? 全部レアか神話レアだってことは? いやあ、とっても気になるね。
もたもたしてる場合じゃない。先に進もう!
逆説的ストーム(スタンダード)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030718/
モックス/Moxは良いものだ。マジック最古のセットにて、各色のマナを出す0マナアーティファクトとして5つのモックスが登場した。モックスは造語で、その由来はアメリカなどで用いられるスラング「moxie」だと言われている。同名の炭酸飲料があり、それから転じて活気に満ちている・エネルギッシュな様を表す言葉とのこと。各色のエネルギー、すなわちマナの結晶というわけだ。
初代5つのモックスは強すぎたため、現在ではヴィンテージでしか用いることができない。その後のセットで、同様に0マナでマナを生み出すがデメリットを付けることでバランスを取ったリメイク版モックスが登場し続けている。
マジック生誕25周年の今年、『ドミナリア』にはその最新版である《モックス・アンバー》が収録された。
伝説がテーマのセットらしい、自身がコントロールする伝説のクリーチャー or プレインズウォーカーと同じ色マナが出るという制限付きで、これがなかなか扱うのは難しい。早いターンに出してもマナを得ることは困難で、悪用されないように上手く調整されている。
ただ、法の抜け穴が存在するのがマジックの常。このモックスのテキストを一切無視して、0マナの無色マナ加速として用いるデッキがある。その使用者は少なく、トーナメントに出ても当たることはほとんどない。が、世の中に確実に潜むそのデッキを知っておいて損はないだろう。
スタンダードらしからぬクリーチャーでない呪文が主体のコンボデッキ、「逆説的ストーム」だ。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030718/
モックス/Moxは良いものだ。マジック最古のセットにて、各色のマナを出す0マナアーティファクトとして5つのモックスが登場した。モックスは造語で、その由来はアメリカなどで用いられるスラング「moxie」だと言われている。同名の炭酸飲料があり、それから転じて活気に満ちている・エネルギッシュな様を表す言葉とのこと。各色のエネルギー、すなわちマナの結晶というわけだ。
初代5つのモックスは強すぎたため、現在ではヴィンテージでしか用いることができない。その後のセットで、同様に0マナでマナを生み出すがデメリットを付けることでバランスを取ったリメイク版モックスが登場し続けている。
マジック生誕25周年の今年、『ドミナリア』にはその最新版である《モックス・アンバー》が収録された。
伝説がテーマのセットらしい、自身がコントロールする伝説のクリーチャー or プレインズウォーカーと同じ色マナが出るという制限付きで、これがなかなか扱うのは難しい。早いターンに出してもマナを得ることは困難で、悪用されないように上手く調整されている。
ただ、法の抜け穴が存在するのがマジックの常。このモックスのテキストを一切無視して、0マナの無色マナ加速として用いるデッキがある。その使用者は少なく、トーナメントに出ても当たることはほとんどない。が、世の中に確実に潜むそのデッキを知っておいて損はないだろう。
スタンダードらしからぬクリーチャーでない呪文が主体のコンボデッキ、「逆説的ストーム」だ。
KCI(モダン)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030739/
行ってきましたネバダ州。グランプリ・ラスベガス2018、凄かった!
グランプリ本戦の規模的には、実は日本のものとそれほど差はない。グランプリの参加人数では、日本はアメリカにも勝る世界でも最多クラスの国なのだ。ではどういうところで凄さを感じたのかというと……スケールのデカさだね。
会場はとにかくむちゃくちゃ広い。日本のグランプリで使われるような会場がすっぽり2つは入ってしまうサイズだ。なので広いとは言っても通路も広く、どこに何があるか見つけやすいので迷うことは少ない。アメリカということもあってアーティストも集まりやすく、総勢30名ほどのアーティストがサインや物販などでファンを楽しませる。本戦以外のサイドイベントも数えきれないほどで、某ランドじゃないけど体ひとつですべて回りきるのは不可能なレベルだ。とんでもない、とんでもないお祭りだ。こんなもんは1回参加してしまうと癖になる、本戦で良い結果が残せなくとも十分に楽しい。また来年あったら、必ずや遊びに行くことだろう。
さて、今回のベガスはダブル・グランプリ。モダンとリミテッドだ。当コラム的にはやはりモダンの優勝デッキを取り上げようと……思っていたら、その優勝者がこれまたとんでもない。アメリカの強豪、マット・ナス/Matt Nassがグランプリ・ハートフォード2018に次いでモダングランプリ・2大会連続の優勝! 同時に3大会連続トップ4という「モダンマスター」とでも呼ぶべき偉業を成し遂げた。
今、モダンでノリにノっている彼が使用しているデッキは……コイツだ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030739/
行ってきましたネバダ州。グランプリ・ラスベガス2018、凄かった!
グランプリ本戦の規模的には、実は日本のものとそれほど差はない。グランプリの参加人数では、日本はアメリカにも勝る世界でも最多クラスの国なのだ。ではどういうところで凄さを感じたのかというと……スケールのデカさだね。
会場はとにかくむちゃくちゃ広い。日本のグランプリで使われるような会場がすっぽり2つは入ってしまうサイズだ。なので広いとは言っても通路も広く、どこに何があるか見つけやすいので迷うことは少ない。アメリカということもあってアーティストも集まりやすく、総勢30名ほどのアーティストがサインや物販などでファンを楽しませる。本戦以外のサイドイベントも数えきれないほどで、某ランドじゃないけど体ひとつですべて回りきるのは不可能なレベルだ。とんでもない、とんでもないお祭りだ。こんなもんは1回参加してしまうと癖になる、本戦で良い結果が残せなくとも十分に楽しい。また来年あったら、必ずや遊びに行くことだろう。
さて、今回のベガスはダブル・グランプリ。モダンとリミテッドだ。当コラム的にはやはりモダンの優勝デッキを取り上げようと……思っていたら、その優勝者がこれまたとんでもない。アメリカの強豪、マット・ナス/Matt Nassがグランプリ・ハートフォード2018に次いでモダングランプリ・2大会連続の優勝! 同時に3大会連続トップ4という「モダンマスター」とでも呼ぶべき偉業を成し遂げた。
今、モダンでノリにノっている彼が使用しているデッキは……コイツだ!
Troll Disco(Old School)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030744/
ラスベガスを歩けば、街を行き交う人の多くがお祭り騒ぎ状態。とにかくテンションが高い。そりゃあ世界随一の娯楽都市、毎日がお祭り状態になるってなもんで。グランプリ・ラスベガス2018の会場もまさしくそんな感じで、日本では見られないような派手な格好をするプレイヤーがいたり、とにかくそこかしこで楽しそうにマジックをするプレイヤーの姿が見られた。皆、良い顔してるんだよこれが。
中でも、嬉々としてプレイしている人が多いなと思ったのがサイドイベントの「Old School Championship」。このコラムでも過去に触れたことがある、「Old School」なるフォーマットの大型トーナメントだ。Old schoolとは古き良き時代・ものの意。マジックの黎明期を振り返るフォーマットで、マジックが世に出た1993年から1994年の間に発売されたセットのみが使用可能。禁止カードはなく、制限カードや『フォールン・エンパイア』が使用可能か否かは主催者や地域によって異なることも。古いカードのみでプレイするヴインテージ、と考えてもらえれば差し支えない。
このOld School、往年の名カードが飛び交う本当に楽しいフォーマットである。レガシーやヴィンテージでも使用可能だが、最近のカードにパワー負けするような《Juzam Djinn》が大暴れしたり、《Tawnos's Coffin》のような激シブカードに役目が与えられたりと、古いカードによる攻防は目が離せない。
ヴィンテージで制限を受けているようなカードが同じく使用可能ということでぶっ壊れカードパワーによる瞬殺フォーマットに思われがちだが、実は黎明期のカードプールにはこれらをそこまで悪用する手段はなく、ゲーム展開は割と落ち着いたものとなる。
《セラの天使》や《トリスケリオン》が大活躍する古き良きマジック……そんなOld Schoolを遊ぶために、ベガスには約100名のプレイヤーが集まったのだからビックリだ。今日はこのトーナメントで活躍したデッキリストを1つ紹介しよう。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030744/
ラスベガスを歩けば、街を行き交う人の多くがお祭り騒ぎ状態。とにかくテンションが高い。そりゃあ世界随一の娯楽都市、毎日がお祭り状態になるってなもんで。グランプリ・ラスベガス2018の会場もまさしくそんな感じで、日本では見られないような派手な格好をするプレイヤーがいたり、とにかくそこかしこで楽しそうにマジックをするプレイヤーの姿が見られた。皆、良い顔してるんだよこれが。
中でも、嬉々としてプレイしている人が多いなと思ったのがサイドイベントの「Old School Championship」。このコラムでも過去に触れたことがある、「Old School」なるフォーマットの大型トーナメントだ。Old schoolとは古き良き時代・ものの意。マジックの黎明期を振り返るフォーマットで、マジックが世に出た1993年から1994年の間に発売されたセットのみが使用可能。禁止カードはなく、制限カードや『フォールン・エンパイア』が使用可能か否かは主催者や地域によって異なることも。古いカードのみでプレイするヴインテージ、と考えてもらえれば差し支えない。
このOld School、往年の名カードが飛び交う本当に楽しいフォーマットである。レガシーやヴィンテージでも使用可能だが、最近のカードにパワー負けするような《Juzam Djinn》が大暴れしたり、《Tawnos's Coffin》のような激シブカードに役目が与えられたりと、古いカードによる攻防は目が離せない。
ヴィンテージで制限を受けているようなカードが同じく使用可能ということでぶっ壊れカードパワーによる瞬殺フォーマットに思われがちだが、実は黎明期のカードプールにはこれらをそこまで悪用する手段はなく、ゲーム展開は割と落ち着いたものとなる。
《セラの天使》や《トリスケリオン》が大活躍する古き良きマジック……そんなOld Schoolを遊ぶために、ベガスには約100名のプレイヤーが集まったのだからビックリだ。今日はこのトーナメントで活躍したデッキリストを1つ紹介しよう。
Temur Energy Never Die(スタンダード)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030746/
「MTG Arena」のクローズド・ベータ生活、最近は《巻きつき蛇》デッキを回すことにハマっている。このデッキで一番頼りになるのは《光袖会の収集者》だなと。序盤には止められにくい威迫を活かしてスパンスパンッと小気味よいビートを決めて、そうやって得たエネルギーで追加ドローをもたらしてくれる。この1枚と2〜4点がなかったら負けてるな、というゲーム展開が多い。
かつては1ターン目に《霊気との調和》でエネルギー補給しながら土地も得て、もっと強く運用できていたと考えると恐ろしい。その時は《牙長獣の仔》と分厚い2マナ圏を形成してたなぁ……調和→牙長獣の動きと言えば「ティムール・エネルギー」が懐かしいなぁ。あのデッキは本当に鉄板、安定感の化身だった……とか回想しながらゲームをプレイしていた。
なんだか気になったので、最近「ティムール」を使っている猛者はいないものかと調べてみた。いるじゃないか。MOCSという予選ラウンド全8回戦のトーナメントで6勝2敗。十分な成績だ。もしかして、まだまだやれるのか? 青赤緑のエネルギーを軸とした中速デッキは、息を吹き返すか?
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030746/
「MTG Arena」のクローズド・ベータ生活、最近は《巻きつき蛇》デッキを回すことにハマっている。このデッキで一番頼りになるのは《光袖会の収集者》だなと。序盤には止められにくい威迫を活かしてスパンスパンッと小気味よいビートを決めて、そうやって得たエネルギーで追加ドローをもたらしてくれる。この1枚と2〜4点がなかったら負けてるな、というゲーム展開が多い。
かつては1ターン目に《霊気との調和》でエネルギー補給しながら土地も得て、もっと強く運用できていたと考えると恐ろしい。その時は《牙長獣の仔》と分厚い2マナ圏を形成してたなぁ……調和→牙長獣の動きと言えば「ティムール・エネルギー」が懐かしいなぁ。あのデッキは本当に鉄板、安定感の化身だった……とか回想しながらゲームをプレイしていた。
なんだか気になったので、最近「ティムール」を使っている猛者はいないものかと調べてみた。いるじゃないか。MOCSという予選ラウンド全8回戦のトーナメントで6勝2敗。十分な成績だ。もしかして、まだまだやれるのか? 青赤緑のエネルギーを軸とした中速デッキは、息を吹き返すか?
ギトラグの怪物・コントロール(モダン)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030747/
祝・《世界のるつぼ》再録! 個人的にイラストが大好きなカードで、能力も土地が再利用できて最高。フォーマットを問わず活躍してくれた思い入れもある1枚で、これが現行スタンダードに合流してどのような化学変化が起きるのか楽しみなところ。
そんなるつぼと同じ能力を持ったカードは、実はスタンダード環境にはもうあったりもする。《ラムナプの採掘者》だ。
このクリーチャーはスタンダードではあまり姿を見ることがないが、他のフォーマットではポテンシャルを発揮しているようだ。モダンなんかだと、これを軸にした《集合した中隊》デッキまであったりする。
今日紹介するデッキも、このクリーチャーの力で墓地から土地をプレイすることで利を得るデッキで……まあインパクトがすごいので、とりあえずリストを見ていただこうか。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030747/
祝・《世界のるつぼ》再録! 個人的にイラストが大好きなカードで、能力も土地が再利用できて最高。フォーマットを問わず活躍してくれた思い入れもある1枚で、これが現行スタンダードに合流してどのような化学変化が起きるのか楽しみなところ。
そんなるつぼと同じ能力を持ったカードは、実はスタンダード環境にはもうあったりもする。《ラムナプの採掘者》だ。
このクリーチャーはスタンダードではあまり姿を見ることがないが、他のフォーマットではポテンシャルを発揮しているようだ。モダンなんかだと、これを軸にした《集合した中隊》デッキまであったりする。
今日紹介するデッキも、このクリーチャーの力で墓地から土地をプレイすることで利を得るデッキで……まあインパクトがすごいので、とりあえずリストを見ていただこうか。
スタンダードを振り返る:巻きつき蛇
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030749/
MTG Arenaという、新しいマジックのオンライン対戦ゲームのベータテスターをやっている。より良い製品版が出て、マジックをプレイする人がもっと増えるようにという思いでバグなどのレポートをしつつ……楽しく手軽にマジックをプレイさせてもらっている。
現在Arenaではスタンダード環境がプレイできるようになり、現実世界で活躍するデッキがそのままデジタルの世界でも火花を散らしている。そんなわけで、グランプリなどには出なかったがこの環境のプレイ数自体はそこそこなものになった。
個人的な感覚になってしまうが、このスタンダードでプレイしたデッキ/対戦したデッキの感想をいくつか書いてみようと思う。まずは「もし自分がグランプリ・シンガポール2018に参加していたら何のデッキを使っていたか?」という質問への答えである《巻きつき蛇》を用いたデッキから始めよう。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030749/
MTG Arenaという、新しいマジックのオンライン対戦ゲームのベータテスターをやっている。より良い製品版が出て、マジックをプレイする人がもっと増えるようにという思いでバグなどのレポートをしつつ……楽しく手軽にマジックをプレイさせてもらっている。
現在Arenaではスタンダード環境がプレイできるようになり、現実世界で活躍するデッキがそのままデジタルの世界でも火花を散らしている。そんなわけで、グランプリなどには出なかったがこの環境のプレイ数自体はそこそこなものになった。
個人的な感覚になってしまうが、このスタンダードでプレイしたデッキ/対戦したデッキの感想をいくつか書いてみようと思う。まずは「もし自分がグランプリ・シンガポール2018に参加していたら何のデッキを使っていたか?」という質問への答えである《巻きつき蛇》を用いたデッキから始めよう。
スタンダードを振り返る:テフェリーとコントロール
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030753/
『ドミナリア』環境のスタンダードを振り返るシリーズ第2弾、今日はこのセットの登場で大きな戦力を得たコントロールの話だ。コントロールが得た新戦力はいろいろとあるが、最も強大なるカードは誰が何と言おうが《ドミナリアの英雄、テフェリー》だ。
ドミナリア出身のプレインズウォーカーの中ではウルザに次いで有名であろう、我らが英雄。あの《精神を刻む者、ジェイス》に勝るとも劣らないとまで言われるパワーカードとしてスタンダードに降臨。発売前はその強さのほどはいかほどかと、半信半疑のプレイヤーもいたのだが……発売週末には多くのプレイヤーがお試しで使用した青白のコントロールでのこのカードの強さに魅了されることになった。
とにかく、出たターンの[+1]がたまらなく強いんだなぁこれが。1枚ドローして土地を2つアンタップするのでこのカードは実質3マナで運用できる。浮いたマナで《本質の散乱》《否認》《封じ込め》と構えられる呪文の選択肢も十分。
5と高い初期忠誠度も武器で、とりあえず1ターン耐えればそこからは毎ターン手札とマナでアドバンテージを得まくり。土地が起きる能力は、それと相性の良いカードはあっても悪いカードなんかあることもなく、ただただ自身のメインと相手ターンの両方で行動し続けることができ……そうなれば文字通りゲームを支配、コントロールしきることが可能だ。
発売週末にテフェリーの強さを思い知ったプレイヤーたちは、そこから「青白コントロール」のベストな形を目指していく。それまでのコントロールは《副陽の接近》を勝ち手段としたものが多かったが、テフェリーの登場によりこれすらも不要になった。ライブラリーを引き切ってからテフェリーの[-3]能力で自身を対象に取れば、彼がライブラリーの上に戻りライブラリーアウトで負けることはなくなる。これによりデッキを構成するカードにフィニッシャーが不要になり、コントロールするための呪文群とテフェリーと土地だけで構成された生粋のヘビーコントロールが登場するに至った。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030753/
『ドミナリア』環境のスタンダードを振り返るシリーズ第2弾、今日はこのセットの登場で大きな戦力を得たコントロールの話だ。コントロールが得た新戦力はいろいろとあるが、最も強大なるカードは誰が何と言おうが《ドミナリアの英雄、テフェリー》だ。
ドミナリア出身のプレインズウォーカーの中ではウルザに次いで有名であろう、我らが英雄。あの《精神を刻む者、ジェイス》に勝るとも劣らないとまで言われるパワーカードとしてスタンダードに降臨。発売前はその強さのほどはいかほどかと、半信半疑のプレイヤーもいたのだが……発売週末には多くのプレイヤーがお試しで使用した青白のコントロールでのこのカードの強さに魅了されることになった。
とにかく、出たターンの[+1]がたまらなく強いんだなぁこれが。1枚ドローして土地を2つアンタップするのでこのカードは実質3マナで運用できる。浮いたマナで《本質の散乱》《否認》《封じ込め》と構えられる呪文の選択肢も十分。
5と高い初期忠誠度も武器で、とりあえず1ターン耐えればそこからは毎ターン手札とマナでアドバンテージを得まくり。土地が起きる能力は、それと相性の良いカードはあっても悪いカードなんかあることもなく、ただただ自身のメインと相手ターンの両方で行動し続けることができ……そうなれば文字通りゲームを支配、コントロールしきることが可能だ。
発売週末にテフェリーの強さを思い知ったプレイヤーたちは、そこから「青白コントロール」のベストな形を目指していく。それまでのコントロールは《副陽の接近》を勝ち手段としたものが多かったが、テフェリーの登場によりこれすらも不要になった。ライブラリーを引き切ってからテフェリーの[-3]能力で自身を対象に取れば、彼がライブラリーの上に戻りライブラリーアウトで負けることはなくなる。これによりデッキを構成するカードにフィニッシャーが不要になり、コントロールするための呪文群とテフェリーと土地だけで構成された生粋のヘビーコントロールが登場するに至った。
『基本セット2019』プレリリース入門
https://mtg-jp.com/reading/translated/0030754/
物語には始まりがある。
君たちマジック・プレイヤーの中には、プレリリースを長年にわたって楽しんでおり、お気に入りのイベントになっている人がいるだろう。その一方で、初めてのプレリリースに向けて準備をしている人もたくさんいるはずだ――君のプレリリース物語は、ここから始まるんだ。
ようこそ!
『基本セット2019』は、マジックを始める絶好の機会だ。このセットは、新規から古参まであらゆるマジック・プレイヤーに最適なものになるようデザインされた。マジックを始めるきっかけになる?もちろんだ。経験豊富なプレイヤーでも目を見開くような新カードが登場する?賭けてもいいよ。(もう《破滅の龍、ニコル・ボーラス》は見たかな?)
ではそもそも「プレリリース」って何? そこでは何が行われるんだろう?その魅力は?
今日はそれをお伝えしよう!
https://mtg-jp.com/reading/translated/0030754/
物語には始まりがある。
君たちマジック・プレイヤーの中には、プレリリースを長年にわたって楽しんでおり、お気に入りのイベントになっている人がいるだろう。その一方で、初めてのプレリリースに向けて準備をしている人もたくさんいるはずだ――君のプレリリース物語は、ここから始まるんだ。
ようこそ!
『基本セット2019』は、マジックを始める絶好の機会だ。このセットは、新規から古参まであらゆるマジック・プレイヤーに最適なものになるようデザインされた。マジックを始めるきっかけになる?もちろんだ。経験豊富なプレイヤーでも目を見開くような新カードが登場する?賭けてもいいよ。(もう《破滅の龍、ニコル・ボーラス》は見たかな?)
ではそもそも「プレリリース」って何? そこでは何が行われるんだろう?その魅力は?
今日はそれをお伝えしよう!
スタンダードを振り返る:赤いヤツら
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030756/
スタンダードを振り返るシリーズもこれで最後、ラストは『ドミナリア』環境の中心だった赤いデッキの話だ。赤いデッキは強かった……というのは、今さらこんなコラムで語るまでもなく一般常識。なので皆あまり興味はないかもしれないが、後世に残すアーカイブ的な意味合いでも、このデッキに触れないわけにはいかないのでね。
赤いデッキが躍進した理由は、とにかく強いカードに恵まれていることにある。そしてそれが、特定のタイプやマナ域に偏らないという点も大事だ。他の色も十分に強いカードはあるが、赤はこのバランスにとても恵まれている。ゲームに必要なあらゆるカードが揃っており、新セットを得るたびに新しいものを得ていった、それがプロツアー『破滅の刻』からここ1年ほどの赤単、およびそれに類するデッキの歩んできた道だ。
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030756/
スタンダードを振り返るシリーズもこれで最後、ラストは『ドミナリア』環境の中心だった赤いデッキの話だ。赤いデッキは強かった……というのは、今さらこんなコラムで語るまでもなく一般常識。なので皆あまり興味はないかもしれないが、後世に残すアーカイブ的な意味合いでも、このデッキに触れないわけにはいかないのでね。
赤いデッキが躍進した理由は、とにかく強いカードに恵まれていることにある。そしてそれが、特定のタイプやマナ域に偏らないという点も大事だ。他の色も十分に強いカードはあるが、赤はこのバランスにとても恵まれている。ゲームに必要なあらゆるカードが揃っており、新セットを得るたびに新しいものを得ていった、それがプロツアー『破滅の刻』からここ1年ほどの赤単、およびそれに類するデッキの歩んできた道だ。
ランドスティル(レガシー)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030757/
先日、グランプリのラウンド間の待ち時間を友人らと潰していた時の話。そこでとても面白いクイズと出会った。
適当な枚数のカードを用意し、一人がすべて裏面の状態でプレイする。そこにはテキストも何も書いていないのだが……さも、書いてあるかのように一人回し。その挙動を見て、他のメンバーは一体何のデッキがプレイされているのかを当てる。シルエットクイズみたいなもんだね。
カードの姿は見えずとも、特徴的な動きから何のデッキかというのはわかるものだ。例えば1ターン目、裏向きのカードを出してタップ、裏向きのカードをプレイしてエンド宣言。2ターン目アップキープ、ライブラリーの一番上のカードを見て……公開、同時に先のターンに出したカードを裏向きに。もうわかるよね、《秘密を掘り下げる者》をプレイして変身させる、「グリクシス・デルバー」なのでした。
一見しょうもないやりとりだが結構面白く、奥が深い。僕は以下の問題を出題した。
1ターン目:土地を置くような動きをしてエンド
2ターン目:土地を置くような動きから、それら2枚をタップして何やらパーマネントを展開してエンド
3ターン目:土地を置くような動きから、それを1枚タップして1つを指さす。その後、それで攻撃するかのように前に出しながらタップ……
ここで友人皆が「その動き懐かし〜(笑)」「(3ターン目の)アタックの瞬間に全部のカードの絵が見えましたわ(笑)」と良い反応をしてくれた。
これ、正解は「ランドスティル」というかつてレガシーで活躍したデッキ。
2ターン目に《行き詰まり》を設置し、対戦相手が呪文を唱えてきたら3枚ドローできる状態にして、不用意に動けなくしてしまう。このエンチャントで蓋がされている中、こちらは《ミシュラの工廠》を出して起動して殴る。呪文を唱えずに土地で攻め手を確保するわけだ。
たかが2点のダメージでも相手はいつまでもこれを受け続けるわけにもいかず、また自分が勝ちにいくためにも覚悟を決めて呪文を唱えてくる。そこでいただきますと3枚ドローして、引いてきた打ち消しや除去で対処してやる……という、ロングゲームを挑むコントロールデッキである。土地(ランド)と《行き詰まり》(スタンドスティル)で勝つので「ランドスティル」と呼ばれている。
このデッキは、《精神的つまづき》が使えた頃には1ターン目のアクションを弾いて2ターン目から《行き詰まり》でひきこもることができ、アドバンテージ勝負で他のデッキを圧倒する最強デッキのひとつとして君臨していた。その後、つまづきが禁止されたり奇跡呪文などの新カードが続々と出たりして、コントロールの主流からは外れてマイナーデッキとなり、今に至る。
ただなんか、忘れた頃にポッと出てくるデッキでもあるんだよね。「あれ、ランドスティル勝ってるやん」と、不意にその姿を浮上させてマニアを喜ばせては、特に流行ることもなくまたしばらく潜伏……(笑)。でもまあ、レガシーっていろんなカード、デッキにチャンスがあるんだなってことを思い出させてくれる好例である。
ちょうどそんな遊びをしたついでに、ふと調べてみたら、たまたま最近勝ってるじゃないかと。懐かしの青白「ランドスティル」、ご覧あれ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030757/
先日、グランプリのラウンド間の待ち時間を友人らと潰していた時の話。そこでとても面白いクイズと出会った。
適当な枚数のカードを用意し、一人がすべて裏面の状態でプレイする。そこにはテキストも何も書いていないのだが……さも、書いてあるかのように一人回し。その挙動を見て、他のメンバーは一体何のデッキがプレイされているのかを当てる。シルエットクイズみたいなもんだね。
カードの姿は見えずとも、特徴的な動きから何のデッキかというのはわかるものだ。例えば1ターン目、裏向きのカードを出してタップ、裏向きのカードをプレイしてエンド宣言。2ターン目アップキープ、ライブラリーの一番上のカードを見て……公開、同時に先のターンに出したカードを裏向きに。もうわかるよね、《秘密を掘り下げる者》をプレイして変身させる、「グリクシス・デルバー」なのでした。
一見しょうもないやりとりだが結構面白く、奥が深い。僕は以下の問題を出題した。
1ターン目:土地を置くような動きをしてエンド
2ターン目:土地を置くような動きから、それら2枚をタップして何やらパーマネントを展開してエンド
3ターン目:土地を置くような動きから、それを1枚タップして1つを指さす。その後、それで攻撃するかのように前に出しながらタップ……
ここで友人皆が「その動き懐かし〜(笑)」「(3ターン目の)アタックの瞬間に全部のカードの絵が見えましたわ(笑)」と良い反応をしてくれた。
これ、正解は「ランドスティル」というかつてレガシーで活躍したデッキ。
2ターン目に《行き詰まり》を設置し、対戦相手が呪文を唱えてきたら3枚ドローできる状態にして、不用意に動けなくしてしまう。このエンチャントで蓋がされている中、こちらは《ミシュラの工廠》を出して起動して殴る。呪文を唱えずに土地で攻め手を確保するわけだ。
たかが2点のダメージでも相手はいつまでもこれを受け続けるわけにもいかず、また自分が勝ちにいくためにも覚悟を決めて呪文を唱えてくる。そこでいただきますと3枚ドローして、引いてきた打ち消しや除去で対処してやる……という、ロングゲームを挑むコントロールデッキである。土地(ランド)と《行き詰まり》(スタンドスティル)で勝つので「ランドスティル」と呼ばれている。
このデッキは、《精神的つまづき》が使えた頃には1ターン目のアクションを弾いて2ターン目から《行き詰まり》でひきこもることができ、アドバンテージ勝負で他のデッキを圧倒する最強デッキのひとつとして君臨していた。その後、つまづきが禁止されたり奇跡呪文などの新カードが続々と出たりして、コントロールの主流からは外れてマイナーデッキとなり、今に至る。
ただなんか、忘れた頃にポッと出てくるデッキでもあるんだよね。「あれ、ランドスティル勝ってるやん」と、不意にその姿を浮上させてマニアを喜ばせては、特に流行ることもなくまたしばらく潜伏……(笑)。でもまあ、レガシーっていろんなカード、デッキにチャンスがあるんだなってことを思い出させてくれる好例である。
ちょうどそんな遊びをしたついでに、ふと調べてみたら、たまたま最近勝ってるじゃないかと。懐かしの青白「ランドスティル」、ご覧あれ!
Terra Nova(ヴィンテージ)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030758/
マジックの魅力なんてあげていけばキリがないが、今日はそんな山ほどある要素のひとつ、「デッキ名」に触れてみたい。
あなたがマジックを始めた時、そこにはどんなデッキが存在していただろうか? 僕の時には「nWo」というそれはそれはかっこいい名前のデッキがありまして……名前だけ聞くと「え、何をするの?」とわからないんだけれども、デッキを見ればなるほど納得したり、由来を聞いても「だからなぜこの名前なんだよ!」と逆に疑問が加速したり。
最近では「○○アグロ」や「△△ミッドレンジ」というデッキ名が一般的となって、デッキの色や方向性が一発で把握できるのは良いことだけれども、変なデッキ名好きにはやや物足りない(という話をこのコラムでは定期的にしているように思うね)。
今日はそんな、印象的な名前のデッキをひとつ紹介しよう。その名は「Terra Nova」。Novaと言っても《新星追い》が入ってるとかそういうわけじゃない。デッキ内容を見てもこの名前の意味はピンとこない。Terra Novaで検索してみると、同名のSFドラマと登山具メーカーがあることがわかった。つまり何もわからなかったのと同じだ。ただ、テラノヴァという響きのかっこよさにはそそられるものがある。「今日何使うん?」「Terra Nova」カッコイイ会話やなオイ。
というわけで、そんなごっつい名前のデッキの姿を見てもらおう!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030758/
マジックの魅力なんてあげていけばキリがないが、今日はそんな山ほどある要素のひとつ、「デッキ名」に触れてみたい。
あなたがマジックを始めた時、そこにはどんなデッキが存在していただろうか? 僕の時には「nWo」というそれはそれはかっこいい名前のデッキがありまして……名前だけ聞くと「え、何をするの?」とわからないんだけれども、デッキを見ればなるほど納得したり、由来を聞いても「だからなぜこの名前なんだよ!」と逆に疑問が加速したり。
最近では「○○アグロ」や「△△ミッドレンジ」というデッキ名が一般的となって、デッキの色や方向性が一発で把握できるのは良いことだけれども、変なデッキ名好きにはやや物足りない(という話をこのコラムでは定期的にしているように思うね)。
今日はそんな、印象的な名前のデッキをひとつ紹介しよう。その名は「Terra Nova」。Novaと言っても《新星追い》が入ってるとかそういうわけじゃない。デッキ内容を見てもこの名前の意味はピンとこない。Terra Novaで検索してみると、同名のSFドラマと登山具メーカーがあることがわかった。つまり何もわからなかったのと同じだ。ただ、テラノヴァという響きのかっこよさにはそそられるものがある。「今日何使うん?」「Terra Nova」カッコイイ会話やなオイ。
というわけで、そんなごっつい名前のデッキの姿を見てもらおう!
スゥルタイ・アドベンチャー(スタンダード)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030761/
先週はスタンダード環境の主要デッキを振り返ったりした。もう今週金曜(7月13日)に『基本セット2019』が発売なんて信じられない! そんなわけで、『ドミナリア』環境のスタンダードの話をするのも今日がほんとに最後の最後。ラストは、この最終盤に出会ったお気に入りデッキの話をさせてほしい。
それはいつものように、MTG Arenaのプレイ配信をしている時だった。赤単のさまざまなバリエーションを用意して、《ケルドの炎》型の前のめりっぷりを楽しんだり、《屑鉄場のたかり屋》《再燃するフェニックス》で粘り強く戦うタイプをプレイしたり……そんな時、この環境まだ隠されていたコンボを被弾した。
まだこんな引き出しが眠っていたのか、まさしく黄金郷だったのか!と内心テンションが上がり、配信終了後すぐに目コピーでそのデッキを再現してみた。一体どんなコンボなのかって? まあ地味ではあるけど、シブいよ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030761/
先週はスタンダード環境の主要デッキを振り返ったりした。もう今週金曜(7月13日)に『基本セット2019』が発売なんて信じられない! そんなわけで、『ドミナリア』環境のスタンダードの話をするのも今日がほんとに最後の最後。ラストは、この最終盤に出会ったお気に入りデッキの話をさせてほしい。
それはいつものように、MTG Arenaのプレイ配信をしている時だった。赤単のさまざまなバリエーションを用意して、《ケルドの炎》型の前のめりっぷりを楽しんだり、《屑鉄場のたかり屋》《再燃するフェニックス》で粘り強く戦うタイプをプレイしたり……そんな時、この環境まだ隠されていたコンボを被弾した。
まだこんな引き出しが眠っていたのか、まさしく黄金郷だったのか!と内心テンションが上がり、配信終了後すぐに目コピーでそのデッキを再現してみた。一体どんなコンボなのかって? まあ地味ではあるけど、シブいよ!
鱗親和(モダン)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030763/
先週紹介した「巻きつき蛇」、入稿後に瀧村和幸選手にお話を伺ったところ「蛇デッキのデッキパワーは赤系に並ぶスタンダード2強と言えるレベルににまで達している、最近の成績は32勝7敗(勝率82%!)とノリにのっている」と語ってくれた。《巻きつき蛇》、可能性の塊で秋の『ラヴニカのギルド』が出るまでの間、どこまでやるかが楽しみだ。
そういえば『霊気紛争』発売直後、この蛇を用いたモダンのデッキもあったよなとふと思い出した。クリーチャーに置かれる+1/+1カウンターの数が増えることを活かして、《電結の荒廃者》などのパワーを引き出してやろうというデッキだ。蛇4枚と、すでにモダン環境に存在した《硬化した鱗》を併せてエンジン8枚体制で組まれたアーティファクト中心のデッキで、「蛇親和」「鱗親和」「Snake Scale」などの呼び名があった。このデッキのブン回った時の爆発力は、ちょうどこの時期にビアガーデンで飲むキンキンに冷えたビールくらいの爽快感であった(未成年の皆、お酒苦手な方々、ゴメンネ)。
こんなことを考えていたら、ちょうどグランプリ・バルセロナ2018で《硬化した鱗》デッキが第9位にランクインしていた。おそらく、単体では2/3に過ぎない《巻きつき蛇》はややパワー不足でデッキから抜けてしまったのだろう。アーティファクト主体=無色デッキなのにキーカードが黒緑の2色なのもやや痛かった。鱗のみであれば、その分マナベースに自由ができ、アーティファクト・クリーチャー化する土地なども無理なく採用できる。そして『ドミナリア』からもしっかりと新カードを得ていた……ここで取り上げるにはおあつらえ向きな、「鱗親和」を紹介しよう!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030763/
先週紹介した「巻きつき蛇」、入稿後に瀧村和幸選手にお話を伺ったところ「蛇デッキのデッキパワーは赤系に並ぶスタンダード2強と言えるレベルににまで達している、最近の成績は32勝7敗(勝率82%!)とノリにのっている」と語ってくれた。《巻きつき蛇》、可能性の塊で秋の『ラヴニカのギルド』が出るまでの間、どこまでやるかが楽しみだ。
そういえば『霊気紛争』発売直後、この蛇を用いたモダンのデッキもあったよなとふと思い出した。クリーチャーに置かれる+1/+1カウンターの数が増えることを活かして、《電結の荒廃者》などのパワーを引き出してやろうというデッキだ。蛇4枚と、すでにモダン環境に存在した《硬化した鱗》を併せてエンジン8枚体制で組まれたアーティファクト中心のデッキで、「蛇親和」「鱗親和」「Snake Scale」などの呼び名があった。このデッキのブン回った時の爆発力は、ちょうどこの時期にビアガーデンで飲むキンキンに冷えたビールくらいの爽快感であった(未成年の皆、お酒苦手な方々、ゴメンネ)。
こんなことを考えていたら、ちょうどグランプリ・バルセロナ2018で《硬化した鱗》デッキが第9位にランクインしていた。おそらく、単体では2/3に過ぎない《巻きつき蛇》はややパワー不足でデッキから抜けてしまったのだろう。アーティファクト主体=無色デッキなのにキーカードが黒緑の2色なのもやや痛かった。鱗のみであれば、その分マナベースに自由ができ、アーティファクト・クリーチャー化する土地なども無理なく採用できる。そして『ドミナリア』からもしっかりと新カードを得ていた……ここで取り上げるにはおあつらえ向きな、「鱗親和」を紹介しよう!
黒赤リアニメイト(レガシー)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030764/
7月6日(Magic Onlineでは5日)、《死儀礼のシャーマン》がレガシーにおいて禁止カードとなった。長きに渡って、お疲れさまでしたと言ってやりたい。で、これにマナ基盤などを頼っていたデッキは弱体化どころか退場とまでなってしまうわけで……レガシー環境勢力図は大きく塗り替わることに。
コンボデッキ側もまた、究極の安全確認《ギタクシア派の調査》を同じく禁止で失った。これで『新たなるファイレクシア』以前の、読み合いが重要なレガシーの妙味が蘇ることになった。これまでのように相手の手札は自分にとって都合がいいか悪いかを把握した上で、安全圏なタイミングでゴリゴリ押し付けるという戦術がとれなくなったので……手札破壊なり打ち消しなりのバックアップが前環境以上に必要になってくる。
今回のコラムは禁止改定が実行される直前に書いているので、実際にこの環境がどうなるかはわからないが……《ギタクシア派の調査》にそもそも頼っておらず、《死儀礼のシャーマン》が消えたことで多少楽になる、でもそれで、かえってサイド後にはしっかり用意された対策カードとの戦いが避けられなくなった……そんなコンボデッキを紹介したいと思う。黒赤のリアニメイト・コンボだ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030764/
7月6日(Magic Onlineでは5日)、《死儀礼のシャーマン》がレガシーにおいて禁止カードとなった。長きに渡って、お疲れさまでしたと言ってやりたい。で、これにマナ基盤などを頼っていたデッキは弱体化どころか退場とまでなってしまうわけで……レガシー環境勢力図は大きく塗り替わることに。
コンボデッキ側もまた、究極の安全確認《ギタクシア派の調査》を同じく禁止で失った。これで『新たなるファイレクシア』以前の、読み合いが重要なレガシーの妙味が蘇ることになった。これまでのように相手の手札は自分にとって都合がいいか悪いかを把握した上で、安全圏なタイミングでゴリゴリ押し付けるという戦術がとれなくなったので……手札破壊なり打ち消しなりのバックアップが前環境以上に必要になってくる。
今回のコラムは禁止改定が実行される直前に書いているので、実際にこの環境がどうなるかはわからないが……《ギタクシア派の調査》にそもそも頼っておらず、《死儀礼のシャーマン》が消えたことで多少楽になる、でもそれで、かえってサイド後にはしっかり用意された対策カードとの戦いが避けられなくなった……そんなコンボデッキを紹介したいと思う。黒赤のリアニメイト・コンボだ!
ブルードラージ(モダン)
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030769/
『基本セット2019』の新カードは、基本セットらしいオーソドックスなものから、これは基本セットの枠を超えているなと思わされる個性的なものまで品揃え豊富だ。
個人的に気になっているカードは《冥府の報い》。アートからもわかる通り、黒が得たエルドラージへの解答だ。
たった1マナのインスタントで、どんなサイズの無色クリーチャーもサクッと追放除去し、そいつのパワー分だけライフが得られる。対象を極限まで絞り込んだことで、とんでもないハイスペックの除去に仕上がっている。
僕はエルドラージやあるいは《ワームとぐろエンジン》といったカードが好きなので、このカードは脅威として受け止めねばならない。以前、グランプリ参戦前に候補としてエルドラージ系のデッキを回してみたが、その時に当たるデッキはどれも苦しいものが多くてちょっと下火かなぁと思っていたところに、この追い打ちである。
ほら、エルドラージそんな目立ってないから大丈夫だよな!……なんて思っていたのだが、バッチリ存在感を放つ新しいタイプのエルドラージ・デッキが出てきちゃったよ……いやむしろこれ使えば良いのか? リストを見てみよう、「ブルードラージ」だ!
https://mtg-jp.com/reading/iwashowdeck/0030769/
『基本セット2019』の新カードは、基本セットらしいオーソドックスなものから、これは基本セットの枠を超えているなと思わされる個性的なものまで品揃え豊富だ。
個人的に気になっているカードは《冥府の報い》。アートからもわかる通り、黒が得たエルドラージへの解答だ。
たった1マナのインスタントで、どんなサイズの無色クリーチャーもサクッと追放除去し、そいつのパワー分だけライフが得られる。対象を極限まで絞り込んだことで、とんでもないハイスペックの除去に仕上がっている。
僕はエルドラージやあるいは《ワームとぐろエンジン》といったカードが好きなので、このカードは脅威として受け止めねばならない。以前、グランプリ参戦前に候補としてエルドラージ系のデッキを回してみたが、その時に当たるデッキはどれも苦しいものが多くてちょっと下火かなぁと思っていたところに、この追い打ちである。
ほら、エルドラージそんな目立ってないから大丈夫だよな!……なんて思っていたのだが、バッチリ存在感を放つ新しいタイプのエルドラージ・デッキが出てきちゃったよ……いやむしろこれ使えば良いのか? リストを見てみよう、「ブルードラージ」だ!
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|