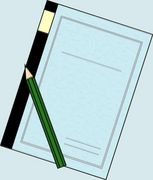33個の項目の詳細を書いていきます。
1.戦略や分析は常に必要
2.まずは、見慣れることから
3.携帯電話でこっそりと
4.問題演習の際は、自分で○、△、×などの評価をする
5.暗記は順序よく行う
6.試験までの日数をカウントダウンする
7.テキストなどに勉強した日付を書き込む
8.計画は細かく立てすぎない
9.時間を計って勉強する
10.Exelの読み上げ機能を活用する
11.ノートはなるべく作らない
12.「短期間で合格するぞ!」と考える
13.勝負は直前期の追い込みで決まる!といっても過言ではない
14.常に、危機感、緊張感もしくは欲をもって勉強する
15.テキストなどは、まず目次、次に全てのページを一読する
16.寝る前に、その日勉強したことを思い出す
17.情報は、なるべく一箇所に集約する
18.インプットよりもアウトプットを意識する
19.蛍光ペンを使用するのなら、色分けをする
20.テキストは何冊も買わない
21.最優先すべきは過去問
22.全ての動きを速くする
23.予備校のパンフレットに付属のハガキを活用する
24.暗記には、繰り返しよりも危機感が効果的
25.試験に出ないことには手を出さない
26.Windows Media Playerの倍速再生を利用する
27.願書を出し忘れない
28.択一の問題は、全ての選択肢を検討する(過去問・予想問題)
29.本を開けないときでも、勉強は出来る
30.問題演習の際は、ペナルティを用意しておく
31.一度で覚えようとしないではなく、一日で覚えようとしない
32.本は出来るだけ離して読む
33.割り切り上手は勉強上手
1.戦略や分析は常に必要
2.まずは、見慣れることから
3.携帯電話でこっそりと
4.問題演習の際は、自分で○、△、×などの評価をする
5.暗記は順序よく行う
6.試験までの日数をカウントダウンする
7.テキストなどに勉強した日付を書き込む
8.計画は細かく立てすぎない
9.時間を計って勉強する
10.Exelの読み上げ機能を活用する
11.ノートはなるべく作らない
12.「短期間で合格するぞ!」と考える
13.勝負は直前期の追い込みで決まる!といっても過言ではない
14.常に、危機感、緊張感もしくは欲をもって勉強する
15.テキストなどは、まず目次、次に全てのページを一読する
16.寝る前に、その日勉強したことを思い出す
17.情報は、なるべく一箇所に集約する
18.インプットよりもアウトプットを意識する
19.蛍光ペンを使用するのなら、色分けをする
20.テキストは何冊も買わない
21.最優先すべきは過去問
22.全ての動きを速くする
23.予備校のパンフレットに付属のハガキを活用する
24.暗記には、繰り返しよりも危機感が効果的
25.試験に出ないことには手を出さない
26.Windows Media Playerの倍速再生を利用する
27.願書を出し忘れない
28.択一の問題は、全ての選択肢を検討する(過去問・予想問題)
29.本を開けないときでも、勉強は出来る
30.問題演習の際は、ペナルティを用意しておく
31.一度で覚えようとしないではなく、一日で覚えようとしない
32.本は出来るだけ離して読む
33.割り切り上手は勉強上手
|
|
|
|
コメント(34)
1、戦略や分析は常に必要
資格試験に限らず、起業、独立、営業、
個人事業であろうが、サラリーマンであろうが、
勝ち抜いていくためには戦略や分析は不可欠です。
「目標を実現させるためには、何をすべきなのか。」
「あれをやってみては、どうだろうか。」
「ここを、こう変えれば上手くいくのではないか。」
「あの人が上手くいっているのは、なぜか。」
「有効な手段には、何があるのか。」
などなど、様々な場面があります。
ときには、ただ闇雲に行動していても、上手くいくことはあるかもしれません。
しかし、それではすぐに限界が訪れます。
なぜ、上手くいったのかが分からないために、成功の再現性がないからです。
常に自分の頭で考え、先を読み計画を立て、実行に移す。
この力の乏しい方では、今後大きく成功することはまず無理です。
戦略と分析の積み重ね。
初めは小さな差であっても、次第に大きな差になっていきます。
常日頃から、心がけるようにしましょう。早ければ早いほど良いです。
資格試験に限らず、起業、独立、営業、
個人事業であろうが、サラリーマンであろうが、
勝ち抜いていくためには戦略や分析は不可欠です。
「目標を実現させるためには、何をすべきなのか。」
「あれをやってみては、どうだろうか。」
「ここを、こう変えれば上手くいくのではないか。」
「あの人が上手くいっているのは、なぜか。」
「有効な手段には、何があるのか。」
などなど、様々な場面があります。
ときには、ただ闇雲に行動していても、上手くいくことはあるかもしれません。
しかし、それではすぐに限界が訪れます。
なぜ、上手くいったのかが分からないために、成功の再現性がないからです。
常に自分の頭で考え、先を読み計画を立て、実行に移す。
この力の乏しい方では、今後大きく成功することはまず無理です。
戦略と分析の積み重ね。
初めは小さな差であっても、次第に大きな差になっていきます。
常日頃から、心がけるようにしましょう。早ければ早いほど良いです。
2.まずは、見慣れることから
「○○○の資格を取ろう!」
そう思って、テキストを開いてみると、
大抵、専門用語の多さに驚いてしまいます。
今まで見たことも聞いたこともない言葉がたくさん。
「こんな言葉、初めて見たよ。」
これらをいきなり覚えようとしていては、
非常に疲れてしまいます・・・
なので、まずは「見慣れる」ことから始めましょう。
「へえー、こういう言葉があるんだ。」
これぐらいの気持ちで、パラパラとページをめくっていって下さい。
そうすれば、段々と専門用語に対する抵抗感がなくなっていきますから。
「抵抗感をなくす」、これは結構大事なことです。
勉強の進み具合に、大きな影響を与えます。
なので、まずは、抵抗感をなくすために見慣れることから始めましょう。
覚えていくのは、そのあとからでも十分です。
「○○○の資格を取ろう!」
そう思って、テキストを開いてみると、
大抵、専門用語の多さに驚いてしまいます。
今まで見たことも聞いたこともない言葉がたくさん。
「こんな言葉、初めて見たよ。」
これらをいきなり覚えようとしていては、
非常に疲れてしまいます・・・
なので、まずは「見慣れる」ことから始めましょう。
「へえー、こういう言葉があるんだ。」
これぐらいの気持ちで、パラパラとページをめくっていって下さい。
そうすれば、段々と専門用語に対する抵抗感がなくなっていきますから。
「抵抗感をなくす」、これは結構大事なことです。
勉強の進み具合に、大きな影響を与えます。
なので、まずは、抵抗感をなくすために見慣れることから始めましょう。
覚えていくのは、そのあとからでも十分です。
3.携帯電話でこっそりと
社会人や大学生であれば、ほとんどの方が持っている携帯電話ですが、
これが便利な勉強ツールになります。
どうやって利用するのか?
簡単です!「ポイント」や「まだ覚えていないこと」を
パソコンで入力し、携帯電話へ送信すればいいだけです。
そうすれば、受信メールを見る感覚で勉強をすることが出来ます。
これが一体どのように役立つのかご説明しましょう。
例えば、
・ぱっと取り出せる。
外出していても、歩きながらメールを見る感覚で勉強できます。
信号待ちや、休憩時間の際にも、ぱっと取り出して勉強できます。
参考書のようなかさばる物を、持ち歩かなくても勉強できるということです。
・狭い場所でも勉強できる
例えば、満員電車のような込み入った場所の場合、
本を開くことは、なかなかできません。
しかし、携帯電話なら!
薄っぺらい上、片手で持てるので、何とか開き画面を見ることが出来ます。
そうすれば、狭い場所でも勉強することは可能ですね。
・人に知られずに勉強することが出来る。
試験勉強をしていることを人に知られたくない人もいるでしょう。
そんなときにも、この方法は役に立ちます。
まさか、携帯電話で勉強しているなんて皆思いません!
だから、メールをチェックするふりをして、こっそり勉強しましょう。
細切れ時間は、有効に使った方が良いので、
この方法を、その1つの手段としておすすめします。
社会人や大学生であれば、ほとんどの方が持っている携帯電話ですが、
これが便利な勉強ツールになります。
どうやって利用するのか?
簡単です!「ポイント」や「まだ覚えていないこと」を
パソコンで入力し、携帯電話へ送信すればいいだけです。
そうすれば、受信メールを見る感覚で勉強をすることが出来ます。
これが一体どのように役立つのかご説明しましょう。
例えば、
・ぱっと取り出せる。
外出していても、歩きながらメールを見る感覚で勉強できます。
信号待ちや、休憩時間の際にも、ぱっと取り出して勉強できます。
参考書のようなかさばる物を、持ち歩かなくても勉強できるということです。
・狭い場所でも勉強できる
例えば、満員電車のような込み入った場所の場合、
本を開くことは、なかなかできません。
しかし、携帯電話なら!
薄っぺらい上、片手で持てるので、何とか開き画面を見ることが出来ます。
そうすれば、狭い場所でも勉強することは可能ですね。
・人に知られずに勉強することが出来る。
試験勉強をしていることを人に知られたくない人もいるでしょう。
そんなときにも、この方法は役に立ちます。
まさか、携帯電話で勉強しているなんて皆思いません!
だから、メールをチェックするふりをして、こっそり勉強しましょう。
細切れ時間は、有効に使った方が良いので、
この方法を、その1つの手段としておすすめします。
4.問題演習の際は、自分で○、△、×などの評価をする
過去問にしろ、予想問題にしろ
演習の際には、自分にとっての難易度の評価をしましょう。
例えば、
○もしくは無印は、完璧!
△は、一応分かるかな、でも心配だから後で復習しよう。
×は、こりゃ駄目だ。今後も気をつけないと。
という感じに、最低限3段階に評価しましょう。
こうしておけば、復習する際の優先順位が一目で分かるようになります。
これは、非常に大事なことです。
勉強というのは、
「分からないことを減らしていくこと」と言われることがあります。
分かることばかり、勉強していても進歩はありません。
分からないことを、分かるようにすることに意味があるのです。
よって、「自分は何が分かり、何が分からないのか」
これをはっきりさせておくことが、効率的な勉強には不可欠です。
過去問にしろ、予想問題にしろ
演習の際には、自分にとっての難易度の評価をしましょう。
例えば、
○もしくは無印は、完璧!
△は、一応分かるかな、でも心配だから後で復習しよう。
×は、こりゃ駄目だ。今後も気をつけないと。
という感じに、最低限3段階に評価しましょう。
こうしておけば、復習する際の優先順位が一目で分かるようになります。
これは、非常に大事なことです。
勉強というのは、
「分からないことを減らしていくこと」と言われることがあります。
分かることばかり、勉強していても進歩はありません。
分からないことを、分かるようにすることに意味があるのです。
よって、「自分は何が分かり、何が分からないのか」
これをはっきりさせておくことが、効率的な勉強には不可欠です。
5.暗記は順序よく行う
いきなり全部を覚えようとしても、人間の記憶力には限界があります。
ごく普通の人には無理です。
そのため、順番に順番に覚えていく必要があります。
では、その順番はどうしたらいいのでしょうか?
1、試験勉強においては、まず赤字、太字です。
「これは、ポイントですよ。」と示してくれているわけですから、
絶対に覚えなくてはなりません。
まずは、それだけを覚えることに集中しましょう。
2、次に赤字、太字を含んだ文章にあるキーワードです。
キーワードというのは、ここでは、「それを覚えていれば、
自分が、その文章の大意を思い出せるようになるもの」のことを指します。
文章を丸々覚えるのは、非常に労力のかかることですから、
要所、要所を押さえて最小限の労力で雰囲気をつかむようにしましょう。
3、「文章全部を覚えなければならない!」という場合は、
文節ごとに区切って、少しずつ覚えていくようにしましょう。
そして、最終的には、区切って覚えたものを頭の中で組み立てていきましょう。
共通のポイントとしては、「少しずつ覚える」ということですね。
いきなり全部を覚えようとしても、人間の記憶力には限界があります。
ごく普通の人には無理です。
そのため、順番に順番に覚えていく必要があります。
では、その順番はどうしたらいいのでしょうか?
1、試験勉強においては、まず赤字、太字です。
「これは、ポイントですよ。」と示してくれているわけですから、
絶対に覚えなくてはなりません。
まずは、それだけを覚えることに集中しましょう。
2、次に赤字、太字を含んだ文章にあるキーワードです。
キーワードというのは、ここでは、「それを覚えていれば、
自分が、その文章の大意を思い出せるようになるもの」のことを指します。
文章を丸々覚えるのは、非常に労力のかかることですから、
要所、要所を押さえて最小限の労力で雰囲気をつかむようにしましょう。
3、「文章全部を覚えなければならない!」という場合は、
文節ごとに区切って、少しずつ覚えていくようにしましょう。
そして、最終的には、区切って覚えたものを頭の中で組み立てていきましょう。
共通のポイントとしては、「少しずつ覚える」ということですね。
8.計画は細かく立てすぎない
これは、計画倒れを防ぐためですね。
いくら完璧な計画を立てたところで、(立てるのは大変です。)
その通りにやっていけるかどうかは分かりません。
軌道修正のための予備の日を用意する、という手もありますが、
それでも計画通りというのは難しいですよね。
「そんなことない。ちゃんと計画通りに進められるよ。」
という方も世の中にはいるでしょうが、
自分を含め、ほとんどの方は、計画通りに出来たためしがないと思います。
それなら、細かい計画を立てても、あまり意味がありませんよね。
計画を立てていた時間は、無駄になってしまいます。
計画を立てる必要はない、とは言いませんが、
時間の無駄は、なるべく減らすべきなので
計画を立てるなら、大まかに立てるようにしましょう。
簡単に出来るもので、
テキストのページ数を、日数で割る方法が良いと思います。
「この本を1ヶ月で読みきろうとしたら、1日にこんなに読まなければいけないのか!」
ということが分かって、勉強のスピードを調節しやすくなります。
また、「今までたくさん勉強してきたつもりが、大したことはなかった!」
なんてことも分かるかもしれませんね。
もう1つ、予備校のパンフレットについている授業の日程表を参考にするのもいいと思います。
予備校のカリキュラムは、考え込まれて作られているわけですから、
それをもとに計画を立てれば、大きく外れるようなことはありません。
いくつか、資料を請求してみましょう。たいてい無料ですから。
これは、計画倒れを防ぐためですね。
いくら完璧な計画を立てたところで、(立てるのは大変です。)
その通りにやっていけるかどうかは分かりません。
軌道修正のための予備の日を用意する、という手もありますが、
それでも計画通りというのは難しいですよね。
「そんなことない。ちゃんと計画通りに進められるよ。」
という方も世の中にはいるでしょうが、
自分を含め、ほとんどの方は、計画通りに出来たためしがないと思います。
それなら、細かい計画を立てても、あまり意味がありませんよね。
計画を立てていた時間は、無駄になってしまいます。
計画を立てる必要はない、とは言いませんが、
時間の無駄は、なるべく減らすべきなので
計画を立てるなら、大まかに立てるようにしましょう。
簡単に出来るもので、
テキストのページ数を、日数で割る方法が良いと思います。
「この本を1ヶ月で読みきろうとしたら、1日にこんなに読まなければいけないのか!」
ということが分かって、勉強のスピードを調節しやすくなります。
また、「今までたくさん勉強してきたつもりが、大したことはなかった!」
なんてことも分かるかもしれませんね。
もう1つ、予備校のパンフレットについている授業の日程表を参考にするのもいいと思います。
予備校のカリキュラムは、考え込まれて作られているわけですから、
それをもとに計画を立てれば、大きく外れるようなことはありません。
いくつか、資料を請求してみましょう。たいてい無料ですから。
10.Exelの読み上げ機能を活用する
Exel2002以降には、
なんと!「音声読み上げ機能」が付いています。
(Adobe Acrobatにもあるようです。)ご存知でしたか?
ツール(T)⇒音声(H)⇒【読み上げ】ツールバーの表示
によって使用できるようになります。
ということは?
ポイントを集めたものを、打ち込んでいけば
自動でそれを読み上げていってくれる便利なツールが出来上がります。
BGM代わりに聞き流す、なんて使い方も出来るでしょう。
ただ、この機能は、さすがに万能ではありません。
読むスピードが少し遅いですからね。
ICレコーダーや、カセットレコーダーに
録音した方が、使い勝手は良いです。
ですが、やはり【パソコンさえあれば、タダで利用できる】
という点は大きいと思われます。
勉強する際に、補助的に利用してみてはいかがでしょう?
Exel2002以降には、
なんと!「音声読み上げ機能」が付いています。
(Adobe Acrobatにもあるようです。)ご存知でしたか?
ツール(T)⇒音声(H)⇒【読み上げ】ツールバーの表示
によって使用できるようになります。
ということは?
ポイントを集めたものを、打ち込んでいけば
自動でそれを読み上げていってくれる便利なツールが出来上がります。
BGM代わりに聞き流す、なんて使い方も出来るでしょう。
ただ、この機能は、さすがに万能ではありません。
読むスピードが少し遅いですからね。
ICレコーダーや、カセットレコーダーに
録音した方が、使い勝手は良いです。
ですが、やはり【パソコンさえあれば、タダで利用できる】
という点は大きいと思われます。
勉強する際に、補助的に利用してみてはいかがでしょう?
11.ノートはなるべく作らない
この場合のノートとは、「単なるまとめノート」のことを指します。
テキストを丁寧にまとめたものです。
このようなまとめノートを作ることは、お薦めしません。
その理由としては、主に以下の事柄が挙げられます。
1、勉強し始めの段階で作成した場合、
・ポイント以外のものまで書いてしまうおそれがある
・最後まで活用できるような完成度の高いものが作れる可能性は低い
・そのため、このようなノートを作る時間はロス
2、勉強が一通り、済んだ段階で作成した場合でも、
作成するのに時間がかかり、貴重な時間をロスしてしまう
ノートを作成していると、すごく勉強しているかのような気分に陥りやすいのですが
実際は、あまり頭に入ってきていないものです。
また、きれいなノートを作成できたことに満足してしまい、
その先の暗記がおろそかになってしまうこともあります。
参考書を買っただけで、勉強した気になるのと同じようなものですね。
テキストのまとめノートが欲しければ、
市販の重要事項を集めた参考書を買った方が良いです。
「でも、お金がかかるじゃないか。」
と思う方がいらしたら、よく考えてみてください。
自分でまとめた場合、お金はかからなくても貴重な時間や手間がかかっているのです。
貴重な時間や手間を、数千円のお金で買えるのだから、買っておいたほうが得なのです。
そして、その分の時間を有効に活用した方が効率的となります。
金額に目をとらわれていては、
本当に大事なものを見失ってしまいますので気をつけましょう。
また、単なるまとめノートではなく、間違いノート、
暗記出来ていないものを集めたノートなどであれば、どんどん作成していきましょう。
復習をする際に、自分の弱点、覚えなければならないことが
一目で分かるようになりますからね。
そして、出来ればノートよりもルーズリーフを使用することをお薦めします。
こちらの方が、取り外しや並べ替えができ、融通が利きますから。
この場合のノートとは、「単なるまとめノート」のことを指します。
テキストを丁寧にまとめたものです。
このようなまとめノートを作ることは、お薦めしません。
その理由としては、主に以下の事柄が挙げられます。
1、勉強し始めの段階で作成した場合、
・ポイント以外のものまで書いてしまうおそれがある
・最後まで活用できるような完成度の高いものが作れる可能性は低い
・そのため、このようなノートを作る時間はロス
2、勉強が一通り、済んだ段階で作成した場合でも、
作成するのに時間がかかり、貴重な時間をロスしてしまう
ノートを作成していると、すごく勉強しているかのような気分に陥りやすいのですが
実際は、あまり頭に入ってきていないものです。
また、きれいなノートを作成できたことに満足してしまい、
その先の暗記がおろそかになってしまうこともあります。
参考書を買っただけで、勉強した気になるのと同じようなものですね。
テキストのまとめノートが欲しければ、
市販の重要事項を集めた参考書を買った方が良いです。
「でも、お金がかかるじゃないか。」
と思う方がいらしたら、よく考えてみてください。
自分でまとめた場合、お金はかからなくても貴重な時間や手間がかかっているのです。
貴重な時間や手間を、数千円のお金で買えるのだから、買っておいたほうが得なのです。
そして、その分の時間を有効に活用した方が効率的となります。
金額に目をとらわれていては、
本当に大事なものを見失ってしまいますので気をつけましょう。
また、単なるまとめノートではなく、間違いノート、
暗記出来ていないものを集めたノートなどであれば、どんどん作成していきましょう。
復習をする際に、自分の弱点、覚えなければならないことが
一目で分かるようになりますからね。
そして、出来ればノートよりもルーズリーフを使用することをお薦めします。
こちらの方が、取り外しや並べ替えができ、融通が利きますから。
12.「短期間で合格するぞ!」と考える
これは、非常に大事なことです。
では、なぜ短期間で合格した方が良いのか?
それは、もちろん、
資格試験の勉強なんかに時間をかけていてはもったいないからです。
資格というのは、取得するまでではなく、取得してからが大事ですからね。
他にも、試験勉強が長期化するとお金がかかります。
テキスト代、過去問題集代、模試代・・・・・
なんといっても、貴重な時間を奪われてしまいます。
「時は金なり」という言葉もあるように、時間というのも大事な財産です。
長期化すればするほど、それがどんどん奪われていってしまいます。
無駄にしないよう、出来るだけ短期間で合格することを考えましょう。
これは、非常に大事なことです。
では、なぜ短期間で合格した方が良いのか?
それは、もちろん、
資格試験の勉強なんかに時間をかけていてはもったいないからです。
資格というのは、取得するまでではなく、取得してからが大事ですからね。
他にも、試験勉強が長期化するとお金がかかります。
テキスト代、過去問題集代、模試代・・・・・
なんといっても、貴重な時間を奪われてしまいます。
「時は金なり」という言葉もあるように、時間というのも大事な財産です。
長期化すればするほど、それがどんどん奪われていってしまいます。
無駄にしないよう、出来るだけ短期間で合格することを考えましょう。
13.勝負は直前期の追い込みで決まる!といっても過言ではない
直前期というのは、最も知識を身につけられる時期です。
というのも、直前期には、
・今まで勉強してきた分、理解しやすくなっているため スムーズに勉強が進みやすくなる
・「もうすぐ試験だから、合格できるようにがんばらないと!」と、
普段よりも勉強に集中しやすくなる、もしくは、集中させられる
・今まで勉強してきたことを一気に復習することにより、
今まであやふやだった知識が、確実なものとなる
ほとんどの受験生は、
今まで怠けていた人たちでも直前期にはものすごく勉強します。
図書館や自習室にこもる人も多くなります。
この時期のがんばりで、不合格ラインから合格ラインへと
変わることだって、十分にありうるわけです。
このように、直前期は、一番理解しやすく、集中しやすく、
知識を確実にしやすく、他の受験生との差に影響する時期です。
是非、有効に活用しましょう。
では、「どうやったら有効に活用できるの?」
という方のために、いくつかの例を挙げておきます。
1、新しい知識には手を出さない。
「多くのあやふやな知識より、少なくても確実な知識を身につけることが大切」
という言葉をどこかで聞いたことがあると思います。
国家試験では、あやふやな知識ではたちうち出来ない問題がほとんどです。
今まで勉強してきた知識がまだあやふやな状態なら、
この言葉の通り、その知識を少しでも確実なものとするようにしましょう。
知識があやふやなら、新しいことを覚えようとしても
混乱するだけで、あまり良いことはありません。
とにかく、今までの復習を最優先で行って下さい。
2、直前期に自分の弱点を克服できるよう、間違いノートを作成しておく。
過去問や模擬試験で、間違った問題というのはたくさんあると思います。
ですが、たとえたくさん間違ったとしても、落ち込むことはありません。
まだ本番ではないのですから。
逆に、試験前に自分の弱点が分かったことに感謝をしましょう。
間違った問題は、一つずつ解けるようにしていけばいいのです。
そのとき、「自分が今まで一体どういう問題を間違えてきたのか」を
まとめた間違いノートがあると非常に便利です。
直前期にそれを一気に復習すれば、確実にレベルアップします。
直前期というのは、最も知識を身につけられる時期です。
というのも、直前期には、
・今まで勉強してきた分、理解しやすくなっているため スムーズに勉強が進みやすくなる
・「もうすぐ試験だから、合格できるようにがんばらないと!」と、
普段よりも勉強に集中しやすくなる、もしくは、集中させられる
・今まで勉強してきたことを一気に復習することにより、
今まであやふやだった知識が、確実なものとなる
ほとんどの受験生は、
今まで怠けていた人たちでも直前期にはものすごく勉強します。
図書館や自習室にこもる人も多くなります。
この時期のがんばりで、不合格ラインから合格ラインへと
変わることだって、十分にありうるわけです。
このように、直前期は、一番理解しやすく、集中しやすく、
知識を確実にしやすく、他の受験生との差に影響する時期です。
是非、有効に活用しましょう。
では、「どうやったら有効に活用できるの?」
という方のために、いくつかの例を挙げておきます。
1、新しい知識には手を出さない。
「多くのあやふやな知識より、少なくても確実な知識を身につけることが大切」
という言葉をどこかで聞いたことがあると思います。
国家試験では、あやふやな知識ではたちうち出来ない問題がほとんどです。
今まで勉強してきた知識がまだあやふやな状態なら、
この言葉の通り、その知識を少しでも確実なものとするようにしましょう。
知識があやふやなら、新しいことを覚えようとしても
混乱するだけで、あまり良いことはありません。
とにかく、今までの復習を最優先で行って下さい。
2、直前期に自分の弱点を克服できるよう、間違いノートを作成しておく。
過去問や模擬試験で、間違った問題というのはたくさんあると思います。
ですが、たとえたくさん間違ったとしても、落ち込むことはありません。
まだ本番ではないのですから。
逆に、試験前に自分の弱点が分かったことに感謝をしましょう。
間違った問題は、一つずつ解けるようにしていけばいいのです。
そのとき、「自分が今まで一体どういう問題を間違えてきたのか」を
まとめた間違いノートがあると非常に便利です。
直前期にそれを一気に復習すれば、確実にレベルアップします。
14.常に、危機感、緊張感もしくは欲をもって勉強する
これは、やはり集中するためにすることですね。
ぼけーっとしながら勉強するよりも、
「勉強しないとまずい!」
「よし!勉強するぞ」
もしくは、
「合格したい!」
「合格して、開業したい!」
「人の役に立ちたい!」
「稼ぎたい!」
といった、強い意志があった方が遥かにはかどりますよね。
勉強するには、集中するのが一番です。
そのために、なるべく強い意志を持つよう心がけましょう。
また、「そんなこと言ったって、強い意志なんて持てないよ。」
という方は、強い意志を持たざるを得ないような状況に自分を追い込みましょう。
すぐに出来ることなら、
友人・知人に「俺、○○の試験を受けるんだ。」と宣言することです。
受けた以上は、合格しないと恥ずかしいですから、がんばらないといけませんね。
ただ、本当のことを言うなら、
強い意志を持てないようなら、試験を受けない方が良いと思います。
何のために受けるのか、つまり、目的がはっきりとしていれば、
その目的を再確認することによって、気持ちが高ぶるはずです。
気持ちが高ぶらないようであれば、
あなたにとって、その目的に大した意味がないということになります。
「別に達成しなくたっていい。」
目的が、その程度でしかないのであれば
初めから受けようと考えない方が、時間を無駄にせずに済むでしょう。
これは、やはり集中するためにすることですね。
ぼけーっとしながら勉強するよりも、
「勉強しないとまずい!」
「よし!勉強するぞ」
もしくは、
「合格したい!」
「合格して、開業したい!」
「人の役に立ちたい!」
「稼ぎたい!」
といった、強い意志があった方が遥かにはかどりますよね。
勉強するには、集中するのが一番です。
そのために、なるべく強い意志を持つよう心がけましょう。
また、「そんなこと言ったって、強い意志なんて持てないよ。」
という方は、強い意志を持たざるを得ないような状況に自分を追い込みましょう。
すぐに出来ることなら、
友人・知人に「俺、○○の試験を受けるんだ。」と宣言することです。
受けた以上は、合格しないと恥ずかしいですから、がんばらないといけませんね。
ただ、本当のことを言うなら、
強い意志を持てないようなら、試験を受けない方が良いと思います。
何のために受けるのか、つまり、目的がはっきりとしていれば、
その目的を再確認することによって、気持ちが高ぶるはずです。
気持ちが高ぶらないようであれば、
あなたにとって、その目的に大した意味がないということになります。
「別に達成しなくたっていい。」
目的が、その程度でしかないのであれば
初めから受けようと考えない方が、時間を無駄にせずに済むでしょう。
15.テキストなどは、まず目次、次に全てのページを一読する
これは、「全体構造を把握するため」です。
予備校でも、第1回目の講義は全体構造編ということが多いですよね。
試験科目の全体を初めに見ることによって、
・これから一体どんなことを勉強していくのか、
・最終的に、どれだけ勉強しなければならないのか、
・試験科目がどのように関連しているのか
ということなどが分かります。
これだけでも、その後の理解のしやすさが随分変わります。
そして、全体を見る際に役立つのが、目次ですね。
目次には、その書籍のエッセンスが詰まっていると言っても過言ではありません。
まずは、目次を読んでみましょう。
そして、次におすすめなのが、全てのページを、さらっと一読することです。
この「さらっと」という点がポイントです。
しっかり読んでいては、時間がかかりますからね。
太文字、赤文字、見出しなどに絞って、読んでみましょう。
これで、目次を読んだときよりさらに、全体を把握しやすくなっています。
つまり、理解もしやすくなっているということです。
全てのページを見たことにより、
「げっ!このページはごちゃごちゃして覚えるのが大変そうだな。」
なんてことも分かり、あらかじめ覚悟して勉強を進めていくこともできるようにもなります。
また、勉強が進んできたときに、ふと目次を見ることも効果的ですね。
「最近勉強していないけど、こういうこともあったな。」
と、思い起こすことによって、覚えたことを忘れにくくなります。
これは、「全体構造を把握するため」です。
予備校でも、第1回目の講義は全体構造編ということが多いですよね。
試験科目の全体を初めに見ることによって、
・これから一体どんなことを勉強していくのか、
・最終的に、どれだけ勉強しなければならないのか、
・試験科目がどのように関連しているのか
ということなどが分かります。
これだけでも、その後の理解のしやすさが随分変わります。
そして、全体を見る際に役立つのが、目次ですね。
目次には、その書籍のエッセンスが詰まっていると言っても過言ではありません。
まずは、目次を読んでみましょう。
そして、次におすすめなのが、全てのページを、さらっと一読することです。
この「さらっと」という点がポイントです。
しっかり読んでいては、時間がかかりますからね。
太文字、赤文字、見出しなどに絞って、読んでみましょう。
これで、目次を読んだときよりさらに、全体を把握しやすくなっています。
つまり、理解もしやすくなっているということです。
全てのページを見たことにより、
「げっ!このページはごちゃごちゃして覚えるのが大変そうだな。」
なんてことも分かり、あらかじめ覚悟して勉強を進めていくこともできるようにもなります。
また、勉強が進んできたときに、ふと目次を見ることも効果的ですね。
「最近勉強していないけど、こういうこともあったな。」
と、思い起こすことによって、覚えたことを忘れにくくなります。
16.寝る前に、その日勉強したことを思い出す
「暗記には、繰り返すことが大切」と、よく言われますよね。
なので、寝る前に思い出すことによって1回繰り返してみましょう。
それだけでも、随分と記憶の定着に効果があります。
しかし、全く思い出せなかったら大問題ですね。
「えーと、今日勉強したことは、というと・・・。何だっけ?」
では、「今朝は、何を食べたっけ?」と同じレベルです。
それでは、「大丈夫ですか?」と心配してしまいます。(汗)
始めのうちは仕方がないかもしれませんが、
少しずつ思い出す練習をしていって、思い出せるようにがんばりましょう。
また、寝る前だけでなく、
次の日の朝思い出してみるというのも効果的だと思われます。
暇があったら、勉強する、もしくは思い出す。
この積み重ねが大切ですね。
「暗記には、繰り返すことが大切」と、よく言われますよね。
なので、寝る前に思い出すことによって1回繰り返してみましょう。
それだけでも、随分と記憶の定着に効果があります。
しかし、全く思い出せなかったら大問題ですね。
「えーと、今日勉強したことは、というと・・・。何だっけ?」
では、「今朝は、何を食べたっけ?」と同じレベルです。
それでは、「大丈夫ですか?」と心配してしまいます。(汗)
始めのうちは仕方がないかもしれませんが、
少しずつ思い出す練習をしていって、思い出せるようにがんばりましょう。
また、寝る前だけでなく、
次の日の朝思い出してみるというのも効果的だと思われます。
暇があったら、勉強する、もしくは思い出す。
この積み重ねが大切ですね。
17.情報は、なるべく一箇所に集約する
試験勉強をしていると、テキスト、過去問題集、予想問題集、模擬試験、などなど
いろいろなものを利用することになると思います。
そうすると、そのうち
「あれ?あのポイントはどこに書いてあったっけ?」
と、困ってしまう可能性があります。
また、復習をする際にも、
「えーと、あれとこれ、あっ!これも読まないといけない!」
なんて面倒なことにだってなります。
このような事態を避けるために、
情報はなるべく一箇所に集約するようにしましょう。
例えば、過去問や予想問題で問われた知識で、
テキストに載っていないことは、テキストに書き込む、
専用のノートに、そのページをコピーして張り付ける
もしくは、書き込むなどすると後々分かりやすくて良いと思います。
勉強には、復習が大切です。
情報が一箇所に集約されていれば、復習がしやすくなります。
つまり、合格しやすくなる!ということです。
是非、心がけるようにしましょう。
試験勉強をしていると、テキスト、過去問題集、予想問題集、模擬試験、などなど
いろいろなものを利用することになると思います。
そうすると、そのうち
「あれ?あのポイントはどこに書いてあったっけ?」
と、困ってしまう可能性があります。
また、復習をする際にも、
「えーと、あれとこれ、あっ!これも読まないといけない!」
なんて面倒なことにだってなります。
このような事態を避けるために、
情報はなるべく一箇所に集約するようにしましょう。
例えば、過去問や予想問題で問われた知識で、
テキストに載っていないことは、テキストに書き込む、
専用のノートに、そのページをコピーして張り付ける
もしくは、書き込むなどすると後々分かりやすくて良いと思います。
勉強には、復習が大切です。
情報が一箇所に集約されていれば、復習がしやすくなります。
つまり、合格しやすくなる!ということです。
是非、心がけるようにしましょう。
18.インプットよりもアウトプットを意識する
インプットとは、「知識を蓄えること」を、
アウトプットとは、「蓄えた知識を、引き出すこと」を指します。
具体的な例としては、インプットは、テキストの読み込みで、
アウトプットは、問題を解くことが挙げられます。
そして、このインプットとアウトプットでは、
アウトプットの方が、より重視すべきものとなります。
というのも、いくら知識を詰め込んだところで、
問題を解く際に瞬時に引き出せなければ、
正解を導くまでに時間がかかってしまい、あまり役に立たないからです。
いつでも、引き出せるようにアウトプットの練習をしておかなければなりません。
その練習として、丁度良いのは過去問題集です。
これは、実際に過去に問われた問題ですから、
単なる知識のアウトプットにとどまらず、
試験の傾向、問題文の注意どころなど多くのことが分かります。
是非、アウトプットの際には、過去問題集を活用しましょう。
インプットとは、「知識を蓄えること」を、
アウトプットとは、「蓄えた知識を、引き出すこと」を指します。
具体的な例としては、インプットは、テキストの読み込みで、
アウトプットは、問題を解くことが挙げられます。
そして、このインプットとアウトプットでは、
アウトプットの方が、より重視すべきものとなります。
というのも、いくら知識を詰め込んだところで、
問題を解く際に瞬時に引き出せなければ、
正解を導くまでに時間がかかってしまい、あまり役に立たないからです。
いつでも、引き出せるようにアウトプットの練習をしておかなければなりません。
その練習として、丁度良いのは過去問題集です。
これは、実際に過去に問われた問題ですから、
単なる知識のアウトプットにとどまらず、
試験の傾向、問題文の注意どころなど多くのことが分かります。
是非、アウトプットの際には、過去問題集を活用しましょう。
19.蛍光ペンを使用するのなら、色分けをする
別にボールペンでもかまわないのですが、
色がたくさんあるペンは、せっかくなので、その色の多さを活用しましょう。
色の違いに意味を持たせれば、一目でどこに、何のために
線が引かれているのかが分かるので時間の節約になります。
例えば、
・専門用語
・用語の定義
・過去問で問われた箇所
・予想問題で問われた箇所
・よく忘れる、間違える箇所
という具合にですね。
蛍光ペンの場合は、太い方と細い方がありますから
それも使い分けるとまた幅が広がります。
例えば、用語は、太い線で、
その定義は、細い下線で、という具合にですね。
蛍光ペンを使用するのなら、どんどん工夫しましょう。
別にボールペンでもかまわないのですが、
色がたくさんあるペンは、せっかくなので、その色の多さを活用しましょう。
色の違いに意味を持たせれば、一目でどこに、何のために
線が引かれているのかが分かるので時間の節約になります。
例えば、
・専門用語
・用語の定義
・過去問で問われた箇所
・予想問題で問われた箇所
・よく忘れる、間違える箇所
という具合にですね。
蛍光ペンの場合は、太い方と細い方がありますから
それも使い分けるとまた幅が広がります。
例えば、用語は、太い線で、
その定義は、細い下線で、という具合にですね。
蛍光ペンを使用するのなら、どんどん工夫しましょう。
20.テキストは何冊も買わない
書店に行くと、資格試験のテキストというのはたくさん売っていますよね。
そうすると、どうしても迷ってしまうのですが、
これだ!と決めたのなら、そのテキストをひたすら繰り返し、
他のテキストのことは考えないようにしましょう。
他のテキストのことを気にしていては、やはり集中力を欠いてしまいますし、
気になりすぎて、書店に何度も足を運んでしまっては、その分時間もロスしてしまいます。
途中でテキストを変えてしまった場合は、一から読み直しです。
いくら前のテキストで読んだものと重なる部分があるとしても、
これも時間のロスとなります。
また、テキストがたくさんあるということは、読むものもたくさんあるということです。
あなたは、そんなに多くの情報を処理できるような器ですか?
(もちろん私は、そんな器ではありません。)
もしも、他のテキストが気になるようであれば、
「今使用しているテキストの情報量をきちんと処理できるだろうか」
ということを自問自答してみて下さい。
「できる!」と自信をもって言えないようであれば、
他のテキストのことは考えないようにしましょう。
さらに、情報量が増えてしまい、処理するのに疲れてしまいますからね。
ただ、どのテキストの評判が良いのか全く分からない状態で
買ってしまい、後から評判を聞いて
「しまった、それにしておけば良かった。」という状況もあると思います。
その場合に買い換えるというのは、やや仕方がない気もしますが
出来れば避けたいことですよね。お金もかかりますし。
そのため、テキストを買う場合は、
インターネットで検索したり、アマゾンなどの売れ筋ランキングを調べておいて
事前に、どのテキストが人気があるのか調べておきましょう。
そして、その評判を下に、
自分の目で確かめて、自分に合ったテキストを選ぶようにしましょう.
書店に行くと、資格試験のテキストというのはたくさん売っていますよね。
そうすると、どうしても迷ってしまうのですが、
これだ!と決めたのなら、そのテキストをひたすら繰り返し、
他のテキストのことは考えないようにしましょう。
他のテキストのことを気にしていては、やはり集中力を欠いてしまいますし、
気になりすぎて、書店に何度も足を運んでしまっては、その分時間もロスしてしまいます。
途中でテキストを変えてしまった場合は、一から読み直しです。
いくら前のテキストで読んだものと重なる部分があるとしても、
これも時間のロスとなります。
また、テキストがたくさんあるということは、読むものもたくさんあるということです。
あなたは、そんなに多くの情報を処理できるような器ですか?
(もちろん私は、そんな器ではありません。)
もしも、他のテキストが気になるようであれば、
「今使用しているテキストの情報量をきちんと処理できるだろうか」
ということを自問自答してみて下さい。
「できる!」と自信をもって言えないようであれば、
他のテキストのことは考えないようにしましょう。
さらに、情報量が増えてしまい、処理するのに疲れてしまいますからね。
ただ、どのテキストの評判が良いのか全く分からない状態で
買ってしまい、後から評判を聞いて
「しまった、それにしておけば良かった。」という状況もあると思います。
その場合に買い換えるというのは、やや仕方がない気もしますが
出来れば避けたいことですよね。お金もかかりますし。
そのため、テキストを買う場合は、
インターネットで検索したり、アマゾンなどの売れ筋ランキングを調べておいて
事前に、どのテキストが人気があるのか調べておきましょう。
そして、その評判を下に、
自分の目で確かめて、自分に合ったテキストを選ぶようにしましょう.
22.全ての動きを速くする
「速読」というのを皆さんご存知だと思います。
そう、字のごとく、速く読むというものです。
なぜ、速く読むのかと言えば、短い時間を有効に活用したいからですよね?
それならば、読むスピードだけでなく、他の全ての動きを速くするように意識してみましょう。
もっともっと、時間を有効に活用できるようになります。
例えば、
・頭の中で思考する速さ
・文字を書く速さ
・歩く速さ
・食事の速さ
・気持ちを切り替える速さ
さらには、
・本のページをめくる速さ
・立ち上がる速さ
・マウスを動かす速さ
・仕事着に着替える速さ
・鞄に荷物を詰め込む速さ
・携帯のメールを打つ速さ
もう、ありとあらゆる日常の動きの速さを上げようと意識して下さい。
そうすれば、以前よりも時間を生み出していくことが出来ます。
ただ、外であまりにも速く動いていると、変な人に見られてしまうので注意しましょう。
「速読」というのを皆さんご存知だと思います。
そう、字のごとく、速く読むというものです。
なぜ、速く読むのかと言えば、短い時間を有効に活用したいからですよね?
それならば、読むスピードだけでなく、他の全ての動きを速くするように意識してみましょう。
もっともっと、時間を有効に活用できるようになります。
例えば、
・頭の中で思考する速さ
・文字を書く速さ
・歩く速さ
・食事の速さ
・気持ちを切り替える速さ
さらには、
・本のページをめくる速さ
・立ち上がる速さ
・マウスを動かす速さ
・仕事着に着替える速さ
・鞄に荷物を詰め込む速さ
・携帯のメールを打つ速さ
もう、ありとあらゆる日常の動きの速さを上げようと意識して下さい。
そうすれば、以前よりも時間を生み出していくことが出来ます。
ただ、外であまりにも速く動いていると、変な人に見られてしまうので注意しましょう。
23.予備校のパンフレットに付属のハガキを活用する
予備校のパンフレットには、たいていハガキが付いています。
そして、そのハガキの中には、
無料講座試聴や合格情報誌などの特典が付いているものがあります。
このような特典が最も多いのが、LECです。
他にはTACにも一部あったように思います。
LECの無料講座試聴は、
アンケートに答えさえすれば返送する必要はないので、非常にお得な制度です。
ホームページでも実施しているので、一度訪問してみてはいかがでしょう。
市販のテキストには載っていない話がある場合もあるので、
是非試聴してみることをおすすめします。
ハガキを出して個人情報を知られたために、
「勧誘の電話や、ダイレクトメールが増えるのではないか。」
と心配されている方がいるかもしれませんが、
現在のところ、勧誘の電話は一切ありませんし、
パンフレットの送付がごくまれにある程度ですので、
心配しなくても大丈夫なように思えます。
また、LECの無料公開講座に行くと、
ほとんどの場合、合格体験記や、合格対策本などを貰うことができます。
(貰えないときもあるので、パンフレットなどで確認しておいて下さい。)
こちらもお得ですので、時間があれば参加することをおすすめします。
予備校のパンフレットには、たいていハガキが付いています。
そして、そのハガキの中には、
無料講座試聴や合格情報誌などの特典が付いているものがあります。
このような特典が最も多いのが、LECです。
他にはTACにも一部あったように思います。
LECの無料講座試聴は、
アンケートに答えさえすれば返送する必要はないので、非常にお得な制度です。
ホームページでも実施しているので、一度訪問してみてはいかがでしょう。
市販のテキストには載っていない話がある場合もあるので、
是非試聴してみることをおすすめします。
ハガキを出して個人情報を知られたために、
「勧誘の電話や、ダイレクトメールが増えるのではないか。」
と心配されている方がいるかもしれませんが、
現在のところ、勧誘の電話は一切ありませんし、
パンフレットの送付がごくまれにある程度ですので、
心配しなくても大丈夫なように思えます。
また、LECの無料公開講座に行くと、
ほとんどの場合、合格体験記や、合格対策本などを貰うことができます。
(貰えないときもあるので、パンフレットなどで確認しておいて下さい。)
こちらもお得ですので、時間があれば参加することをおすすめします。
24.暗記には、繰り返しよりも危機感が効果的
暗記には、繰り返しが大事だとよく言われますね。
確かにそうなのですが、繰り返すこと以上に有効なものがあります。
それが「危機感」です。
私は、中学生のころ小さな町の小さな塾に通っていたのですが、
そこの塾長が本当に恐い人でした。
もうお世話にならなくて済むと思うと、今でもほっとします。
その塾では、ことあるごとにテストをするのですが、
そのほとんどが、
「国の地名と首都を覚えてきなさい。」
「英文を覚えてきなさい。」
「英語の教科書の1単元分を何も見ないで書けるようにしてきなさい。」
といった暗記物で、量も中学生にとってはかなりの多さでした。
覚えておかなければ出来ないテストです。
出来なければ、「だめだ、だめだ!」という空気を作り出され、
非常に、息の詰まる思いをすることになります。
そうなるのは本当に嫌でしたので、
「覚えていかないと怒られる!怒られるのは嫌だ。」
という気持ちが、非常に強くありました。
すると、自然と速く、たくさんのことを覚えることが出来たのですね。
人間の脳というのは、必要なことしか記憶してくれません。
「覚えなくてもいいや。」「これは、自分には必要ない。」「面倒くさい。」
といった感情が少しでもあれば、なかなか記憶することはできません。
逆に、「覚えておかないとひどい目にあう!」
といった危機感があると、非常に脳に刻み込まれやすくなります。
他にも、
「短時間で、たくさんのことを覚えて、皆にいいとこを見せよう。」と考えたり、
嫌いな奴から「こんな量も覚えられないのか?」と言われた状況を想像し、
「余裕で、覚えられるわ!」と気合を入れてみるのも良いですね。
目の前にあるものを覚えることに、
「張り合い」を持たせるようにすることが、記憶には効果的です。
暗記には、繰り返しが大事だとよく言われますね。
確かにそうなのですが、繰り返すこと以上に有効なものがあります。
それが「危機感」です。
私は、中学生のころ小さな町の小さな塾に通っていたのですが、
そこの塾長が本当に恐い人でした。
もうお世話にならなくて済むと思うと、今でもほっとします。
その塾では、ことあるごとにテストをするのですが、
そのほとんどが、
「国の地名と首都を覚えてきなさい。」
「英文を覚えてきなさい。」
「英語の教科書の1単元分を何も見ないで書けるようにしてきなさい。」
といった暗記物で、量も中学生にとってはかなりの多さでした。
覚えておかなければ出来ないテストです。
出来なければ、「だめだ、だめだ!」という空気を作り出され、
非常に、息の詰まる思いをすることになります。
そうなるのは本当に嫌でしたので、
「覚えていかないと怒られる!怒られるのは嫌だ。」
という気持ちが、非常に強くありました。
すると、自然と速く、たくさんのことを覚えることが出来たのですね。
人間の脳というのは、必要なことしか記憶してくれません。
「覚えなくてもいいや。」「これは、自分には必要ない。」「面倒くさい。」
といった感情が少しでもあれば、なかなか記憶することはできません。
逆に、「覚えておかないとひどい目にあう!」
といった危機感があると、非常に脳に刻み込まれやすくなります。
他にも、
「短時間で、たくさんのことを覚えて、皆にいいとこを見せよう。」と考えたり、
嫌いな奴から「こんな量も覚えられないのか?」と言われた状況を想像し、
「余裕で、覚えられるわ!」と気合を入れてみるのも良いですね。
目の前にあるものを覚えることに、
「張り合い」を持たせるようにすることが、記憶には効果的です。
25.試験に出ないことには手を出さない
試験勉強というのは、
試験に出ることを、繰り返し繰り返し勉強するものです。
そうすると、段々あきてきてしまうのですね。
「同じことばかりやっているな。」と。
あきてくると、刺激となる新しい知識を求めるようになります。
例えば、より専門的・実践的な書籍に。
しかし、新しい知識を求める前に、一度踏みとどまって考えてみてください。
「その知識は、試験に出ることなのか」と。
あなたの目的は何でしたか?
試験勉強をしていたのだから、試験に合格することですよね。
試験に出ないことを勉強したところで、合格には近づきません。
むしろ、出ないことに費やした時間のロス、
余計な知識を入れたことによる混乱などの悪影響が出る可能性があります。
試験と関係ない内容であれば、それは、
「試験合格後にとっておくことにしよう!」として、ぐっとこらえましょう。
試験勉強というのは、
試験に出ることを、繰り返し繰り返し勉強するものです。
そうすると、段々あきてきてしまうのですね。
「同じことばかりやっているな。」と。
あきてくると、刺激となる新しい知識を求めるようになります。
例えば、より専門的・実践的な書籍に。
しかし、新しい知識を求める前に、一度踏みとどまって考えてみてください。
「その知識は、試験に出ることなのか」と。
あなたの目的は何でしたか?
試験勉強をしていたのだから、試験に合格することですよね。
試験に出ないことを勉強したところで、合格には近づきません。
むしろ、出ないことに費やした時間のロス、
余計な知識を入れたことによる混乱などの悪影響が出る可能性があります。
試験と関係ない内容であれば、それは、
「試験合格後にとっておくことにしよう!」として、ぐっとこらえましょう。
26.Windows Media Playerの倍速再生を利用する
Windows Media Player をご存知でしょうか?
CDなどを再生する際に利用するPCのプログラムの一つです。
XP以降なら、おそらく付いているものだと思います。
まず、これを使用し、CDの音声を録音します。
そして、録音したファイルを開くと、Windows Media Playerの右下にある、
三角模様のボタンを操作できるようになっています。
そのボタンで何ができるのか?
なんと!スピードを 1.4 、2、 5倍速に変化させることができます。
最近では、解説CDが市販されるケースが増えてきました。
そういうCDを録音し、倍速再生すれば
今まで以上の速さで聞けるようになり、速い分集中力も高まります。
CDの解説のスピードが遅かったり、
一度聞いたものを、二回目も同じ速さで聞くのは嫌な場合は、
雰囲気が随分と変わるので、この方法をお薦めします。
また、もう少し詳しい内容は、
以下のページに書いてあるので、こちらもご覧下さい。
http://osusumesankousyo.fc2web.com/sokudoku.html
Windows Media Player をご存知でしょうか?
CDなどを再生する際に利用するPCのプログラムの一つです。
XP以降なら、おそらく付いているものだと思います。
まず、これを使用し、CDの音声を録音します。
そして、録音したファイルを開くと、Windows Media Playerの右下にある、
三角模様のボタンを操作できるようになっています。
そのボタンで何ができるのか?
なんと!スピードを 1.4 、2、 5倍速に変化させることができます。
最近では、解説CDが市販されるケースが増えてきました。
そういうCDを録音し、倍速再生すれば
今まで以上の速さで聞けるようになり、速い分集中力も高まります。
CDの解説のスピードが遅かったり、
一度聞いたものを、二回目も同じ速さで聞くのは嫌な場合は、
雰囲気が随分と変わるので、この方法をお薦めします。
また、もう少し詳しい内容は、
以下のページに書いてあるので、こちらもご覧下さい。
http://osusumesankousyo.fc2web.com/sokudoku.html
27.願書を出し忘れない
これは、非常に大切なことです。
願書を出さなければ、受験できないのですから。
「そんなの当たり前じゃないか。」と思う方がいるかもしれませんが、
毎年、実際に願書を出し忘れ受験できないケースがあちこちで出ています。
というのも、
・願書は、取り寄せなければいけない(インターネットで申し込める試験もあります)
・「願書取寄せ期間ですよ。」「申込期間ですよ。」
という情報が、あまり入ってこないために忘れやすい
・試験によっては、その期間が結構早かったりする、からです。
「試験を受けよう!」と思った頃には、
既に締め切られていたなんてことが結構あります。
そのため、申込期間などは、真っ先に調べておくようにしましょう。
そして、しっかり申込みをするよう気をつけましょう。
これは、非常に大切なことです。
願書を出さなければ、受験できないのですから。
「そんなの当たり前じゃないか。」と思う方がいるかもしれませんが、
毎年、実際に願書を出し忘れ受験できないケースがあちこちで出ています。
というのも、
・願書は、取り寄せなければいけない(インターネットで申し込める試験もあります)
・「願書取寄せ期間ですよ。」「申込期間ですよ。」
という情報が、あまり入ってこないために忘れやすい
・試験によっては、その期間が結構早かったりする、からです。
「試験を受けよう!」と思った頃には、
既に締め切られていたなんてことが結構あります。
そのため、申込期間などは、真っ先に調べておくようにしましょう。
そして、しっかり申込みをするよう気をつけましょう。
28.択一の問題は、全ての選択肢を検討する(過去問・予想問題)
択一の問題というのは、
「この中から正しいもの(もしくは間違っているもの)を選べ」という、
複数の選択肢の中から、1つの選択肢を選ぶ問題のことです。
そうすると、どうしても正解の選択肢だけに意識がいってしまいがちなのですが、
過去問や予想問題で勉強しているときは、全ての選択肢を検討するようにしましょう。
以前、「過去問の論点は繰り返し問われることがよくある」
という話をしましたが、それは、
「正解の選択肢が繰り返し問われる」ということではありません。
過去には、不正解の選択肢として出題された論点が、
今度は、正解の選択肢として出題された、もしくは、その逆が起こる可能性があります。
予想問題でも同様です。
そのため、どの選択肢から繰り返し出題されても分かるように、
全ての選択肢を検討するように心がけておきましょう。
択一の問題というのは、
「この中から正しいもの(もしくは間違っているもの)を選べ」という、
複数の選択肢の中から、1つの選択肢を選ぶ問題のことです。
そうすると、どうしても正解の選択肢だけに意識がいってしまいがちなのですが、
過去問や予想問題で勉強しているときは、全ての選択肢を検討するようにしましょう。
以前、「過去問の論点は繰り返し問われることがよくある」
という話をしましたが、それは、
「正解の選択肢が繰り返し問われる」ということではありません。
過去には、不正解の選択肢として出題された論点が、
今度は、正解の選択肢として出題された、もしくは、その逆が起こる可能性があります。
予想問題でも同様です。
そのため、どの選択肢から繰り返し出題されても分かるように、
全ての選択肢を検討するように心がけておきましょう。
29.本を開けないときでも、勉強は出来る
「本を開けないとき」というのは、例えば以下のようなときですね。
1、満員電車に乗っているとき
2、歩いているとき
3、自転車をこいでいるとき
4、本を持っていないとき
こういうときでも勉強することは出来ます。
では、どうやって勉強するのでしょうか?
1、以前勉強したことを思い出す
「えーと、昨日は〜〜を勉強したな。」という風にですね。
思い出せるだけ、思い出して下さい。
もし、思い出せなければ、それが自分の弱点となるものです。
後で本を開いて確認すれば、弱点を減らすことができます。
また、知っている「専門用語」を次々と挙げていくのも良いですね。
「こういう単語があったな、それで意味はこういう感じだった。」
これを頻繁に繰り返していけば、
「今の自分には、どれだけの知識が身についているのか?」
ということが分かり、自分の勉強の進み具合を見直すことが出来ます。
2、記憶が不完全な論点を、ひたすら繰り返し頭に刻み込む
あらかじめ「これを覚えよう!」と決めておいて、あとはひたすら繰り返します。
本を開けず、勉強のしづらいときであっても、
記憶をより完全なものとすることが出来、時間を有効に活用できます。
3、テープを聞き流す
あらかじめ、テープレコーダーなどにまだ覚えていないポイントなどを録音しておけば、
本を開けず、両手の自由も利かないときでも、聞き流すことによって勉強することが出来ます。
「本を開けないとき」というのは、例えば以下のようなときですね。
1、満員電車に乗っているとき
2、歩いているとき
3、自転車をこいでいるとき
4、本を持っていないとき
こういうときでも勉強することは出来ます。
では、どうやって勉強するのでしょうか?
1、以前勉強したことを思い出す
「えーと、昨日は〜〜を勉強したな。」という風にですね。
思い出せるだけ、思い出して下さい。
もし、思い出せなければ、それが自分の弱点となるものです。
後で本を開いて確認すれば、弱点を減らすことができます。
また、知っている「専門用語」を次々と挙げていくのも良いですね。
「こういう単語があったな、それで意味はこういう感じだった。」
これを頻繁に繰り返していけば、
「今の自分には、どれだけの知識が身についているのか?」
ということが分かり、自分の勉強の進み具合を見直すことが出来ます。
2、記憶が不完全な論点を、ひたすら繰り返し頭に刻み込む
あらかじめ「これを覚えよう!」と決めておいて、あとはひたすら繰り返します。
本を開けず、勉強のしづらいときであっても、
記憶をより完全なものとすることが出来、時間を有効に活用できます。
3、テープを聞き流す
あらかじめ、テープレコーダーなどにまだ覚えていないポイントなどを録音しておけば、
本を開けず、両手の自由も利かないときでも、聞き流すことによって勉強することが出来ます。
31.一度で覚えようとしないではなく、一日で覚えようとしない
よく、「一度で」全部を覚えようとすることは
負担がかかる上、無理なことが多いので
「繰り返し、繰り返し」やることによって少しずつ覚えていきましょう。
と言われますよね?
ですが、もう少し詳しく言うと、
「一度」ではなく、「一日」で完璧に覚えようとしないことも大事なのです。
記憶というのは、寝ている間に定着するものです。
そのため、寝ることによって、一旦記憶を定着させ、
その記憶が本当にしっかりと定着したかを、復習しながら確認し、
少しずつ確実なものへと変えていく方が効率よく記憶が進みます。
とはいえ、その日のうちの復習が不要と言っているわけではありません。
一日で「無理に」完璧に覚えようとしているのなら、
一旦寝て、記憶を定着させてから復習することによって、
少しずつ確実なものにしていきましょう、ということになります。
よく、「一度で」全部を覚えようとすることは
負担がかかる上、無理なことが多いので
「繰り返し、繰り返し」やることによって少しずつ覚えていきましょう。
と言われますよね?
ですが、もう少し詳しく言うと、
「一度」ではなく、「一日」で完璧に覚えようとしないことも大事なのです。
記憶というのは、寝ている間に定着するものです。
そのため、寝ることによって、一旦記憶を定着させ、
その記憶が本当にしっかりと定着したかを、復習しながら確認し、
少しずつ確実なものへと変えていく方が効率よく記憶が進みます。
とはいえ、その日のうちの復習が不要と言っているわけではありません。
一日で「無理に」完璧に覚えようとしているのなら、
一旦寝て、記憶を定着させてから復習することによって、
少しずつ確実なものにしていきましょう、ということになります。
33.割り切り上手は勉強上手
「まあ、いいか!」と簡単に割り切れる人ほど、
資格試験の勉強には、向いています。
逆に、「何で、こんなことを覚えなきゃいけないんだろう。」
「もっと深く勉強したい!」と学門的専門書にまで手を出すような
こだわり派の性格の人は、向いていません。
というのも、資格試験の勉強というのは、
「試験に出る論点だけを、集中的に勉強する」
という性質の強いものなのです。
「試験に出るから必要、試験にでないから不要」
予備校でも、「ここは試験に出るから、覚えてください。
逆に、ここは試験にあまり出ないから、読み流すだけでかまいません。」と言われます。
出ない論点は自然とテキストなどから削除されていき、
典型的な事例、単調な記述になることが多くなります。
たとえ、興味深い内容があったとしても、
それが試験に出ないことであれば、テキストには載っていません。
合格することに関係のない内容を学ぶことは、労力の無駄であり、
そればかりに気が行くようになると、
「合格」という本来の目的からそれ、合格が遠のいてしまうからです。
逆に、いくらつまらない内容であっても、
試験に出ることなら、覚えなければなりません。
そのため、「試験に出るから、勉強する。試験に出ないから、勉強しない。」
「よく分からないけど、試験によく出る分野だから、丸暗記で済まそう。」
というように、割り切った方がスムーズに勉強できます。
おそらく、勉強をしていく上で、
「何でこんなことを覚えなきゃいけないんだろう。」と思うときがあると思います。
そのときは、「仕方がない、試験に出るんだから。」と、
すぐ割り切るようにしましょう。
こだわっていては、時間を無駄にしてしまいます。
同じように、
テキストなどを読み進めていって、分からない記述があっても
「まあ、いいや。後でじっくり読もう。」
と割り切り、一旦読み飛ばすようにすることも大事です。
後の記述を読めば、理解しやすくなる内容かもしれません。
また、後でもう一度読めば、
前に気づかなかった点に気づき、すぐに理解できるかもしれません。
まずは、分かるところだけを勉強する!
分からないことにはこだわらず、後回しにする!!
このように割り切り、少しでも、
思考が止まる時間を減らすように心がけましょう。
「まあ、いいか!」と簡単に割り切れる人ほど、
資格試験の勉強には、向いています。
逆に、「何で、こんなことを覚えなきゃいけないんだろう。」
「もっと深く勉強したい!」と学門的専門書にまで手を出すような
こだわり派の性格の人は、向いていません。
というのも、資格試験の勉強というのは、
「試験に出る論点だけを、集中的に勉強する」
という性質の強いものなのです。
「試験に出るから必要、試験にでないから不要」
予備校でも、「ここは試験に出るから、覚えてください。
逆に、ここは試験にあまり出ないから、読み流すだけでかまいません。」と言われます。
出ない論点は自然とテキストなどから削除されていき、
典型的な事例、単調な記述になることが多くなります。
たとえ、興味深い内容があったとしても、
それが試験に出ないことであれば、テキストには載っていません。
合格することに関係のない内容を学ぶことは、労力の無駄であり、
そればかりに気が行くようになると、
「合格」という本来の目的からそれ、合格が遠のいてしまうからです。
逆に、いくらつまらない内容であっても、
試験に出ることなら、覚えなければなりません。
そのため、「試験に出るから、勉強する。試験に出ないから、勉強しない。」
「よく分からないけど、試験によく出る分野だから、丸暗記で済まそう。」
というように、割り切った方がスムーズに勉強できます。
おそらく、勉強をしていく上で、
「何でこんなことを覚えなきゃいけないんだろう。」と思うときがあると思います。
そのときは、「仕方がない、試験に出るんだから。」と、
すぐ割り切るようにしましょう。
こだわっていては、時間を無駄にしてしまいます。
同じように、
テキストなどを読み進めていって、分からない記述があっても
「まあ、いいや。後でじっくり読もう。」
と割り切り、一旦読み飛ばすようにすることも大事です。
後の記述を読めば、理解しやすくなる内容かもしれません。
また、後でもう一度読めば、
前に気づかなかった点に気づき、すぐに理解できるかもしれません。
まずは、分かるところだけを勉強する!
分からないことにはこだわらず、後回しにする!!
このように割り切り、少しでも、
思考が止まる時間を減らすように心がけましょう。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
資格試験攻略のコツ! 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
資格試験攻略のコツ!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人