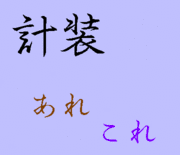|
|
|
|
コメント(14)
フランジ取付やダイアフラムシールの差圧発信器なら、初期設定さえしっかり決めてやれば、特に問題は起きません
(山武のリモートシールだと高/低圧が紛らわしいんだけど、横河のダイアフラムシールはどうだっけ?)
ごく普通の差圧発信器を使い、ドライレグやウェットレグで計測する場合、エア抜き,水抜き,水張りをしっかり行って下さい
ほとんどのトラブルは導圧配管の中に水/エアが残っていたことが原因です
あと、意外によくあるのが、均圧弁を開けられてしまうことです
開放タンクの計測ならば、均圧弁を省略するのも一つのやり方です
ただし、密閉タンクの計測では均圧弁を設けないとメンテの時に死ねます
(ダイアフラムシールでも均圧弁を設けた方がよいです)
(山武のリモートシールだと高/低圧が紛らわしいんだけど、横河のダイアフラムシールはどうだっけ?)
ごく普通の差圧発信器を使い、ドライレグやウェットレグで計測する場合、エア抜き,水抜き,水張りをしっかり行って下さい
ほとんどのトラブルは導圧配管の中に水/エアが残っていたことが原因です
あと、意外によくあるのが、均圧弁を開けられてしまうことです
開放タンクの計測ならば、均圧弁を省略するのも一つのやり方です
ただし、密閉タンクの計測では均圧弁を設けないとメンテの時に死ねます
(ダイアフラムシールでも均圧弁を設けた方がよいです)
補足
#1でKazuさんの書いたやり方が、ドライレグです
#2でぴんぐさんの書いたやり方が、ウェットレグです
ぴんぐさんの書いた、キャピラリー式の差圧発信機と私が書いたダイアフラムシール、リモートシールと同じ物だと思います(メーカによる呼び方の違いでしょう)
横河の型番だとEJX118になるのかな?
私の書いた、フランジ取付はダイアフラムシールの中でも高圧側にだけフランジがついて、低圧側は小さな穴が開いて大気開放されているタイプです
横河の型番だとEJX210になるのだと思います
(すいませんが普段横河の機器を使わないので型番は自信がありません)
具体的な配管方法は
http://www.fic-net.jp/manual/pdf/TN3FFKb.pdf
の9ページ以降に色々のっています
#1でKazuさんの書いたやり方が、ドライレグです
#2でぴんぐさんの書いたやり方が、ウェットレグです
ぴんぐさんの書いた、キャピラリー式の差圧発信機と私が書いたダイアフラムシール、リモートシールと同じ物だと思います(メーカによる呼び方の違いでしょう)
横河の型番だとEJX118になるのかな?
私の書いた、フランジ取付はダイアフラムシールの中でも高圧側にだけフランジがついて、低圧側は小さな穴が開いて大気開放されているタイプです
横河の型番だとEJX210になるのだと思います
(すいませんが普段横河の機器を使わないので型番は自信がありません)
具体的な配管方法は
http://www.fic-net.jp/manual/pdf/TN3FFKb.pdf
の9ページ以降に色々のっています
あ〜、私も屋外の密閉タンクは経験がないです
下手にスチームトレースで凍結防止なんてやると、一発で計測ぐちゃぐちゃになりそうですねぇ
開放タンクで東京くらいの気候なら、よほど配管長引きしなければ凍結の心配はないです
新潟でやった時はフランジ取付使いました
と言うことで、私なら凍結/蒸発の対策考えるよりは、素直にリモートシールに逃げます
>密閉式タンクで差圧で液面計測したことないですが、その場合、タンク底側にH側とL側はタンクに接続する事で内部が水でもなんでも比重換算から差圧換算だけ入れてやれば出来ないでしょうか?
これ、ちょっと意味が分からないのですが
低圧側をタンク上部の気体部分に接続して、特に水を張らないって事でしょうか?
(密閉タンクをドライレグで計るって事?)
であれば、理屈の上では計測可能ですが、現実的には検出配管に水が凝結してたまっていくので、どんどんくるっていきます
なので、条件としてはタンクの内部が十分に乾燥して、検出配管に水が凝結しないような環境が条件になります
それともタンクの中の液体部分に低圧側も接続するって事でしょうか?
これは計測できません
下手にスチームトレースで凍結防止なんてやると、一発で計測ぐちゃぐちゃになりそうですねぇ
開放タンクで東京くらいの気候なら、よほど配管長引きしなければ凍結の心配はないです
新潟でやった時はフランジ取付使いました
と言うことで、私なら凍結/蒸発の対策考えるよりは、素直にリモートシールに逃げます
>密閉式タンクで差圧で液面計測したことないですが、その場合、タンク底側にH側とL側はタンクに接続する事で内部が水でもなんでも比重換算から差圧換算だけ入れてやれば出来ないでしょうか?
これ、ちょっと意味が分からないのですが
低圧側をタンク上部の気体部分に接続して、特に水を張らないって事でしょうか?
(密閉タンクをドライレグで計るって事?)
であれば、理屈の上では計測可能ですが、現実的には検出配管に水が凝結してたまっていくので、どんどんくるっていきます
なので、条件としてはタンクの内部が十分に乾燥して、検出配管に水が凝結しないような環境が条件になります
それともタンクの中の液体部分に低圧側も接続するって事でしょうか?
これは計測できません
>かいぢうぱじゃまさま
>低圧側をタンク上部の気体部分に接続して、特に水を張らないって事でしょうか?
>(密閉タンクをドライレグで計るって事?)
>であれば、理屈の上では計測可能ですが、現実的には検出配管に水が凝結して>たまっていくので、どんどんくるっていきます
>なので、条件としてはタンクの内部が十分に乾燥して、検出配管に水が凝結し>ないような環境が条件になります。
低圧側配管をトレースヒーターで保温でどうですかね?
これなら、水だろうが液体が水以外でも計測できるンじゃないでしょうか?
温度設定は内部圧力と計測液体の凝縮温度以上にしておけばL側には溜らないと思います。取り出しは上部から立ち上げて取る形を取れば完全満水にならない限り密閉タンクでも行けると思うのですが・・・
比重の話は内部が水であれば1mAq=0.1kgf/cm2ですが内部液体が違う場合においては液面として表示する場合に換算が必要ですよというだけです・・・
>それともタンクの中の液体部分に低圧側も接続するって事でしょうか?
>これは計測できません
そりゃ、これは無理ですねw
どっちにもヘッド掛かりますから。
>低圧側をタンク上部の気体部分に接続して、特に水を張らないって事でしょうか?
>(密閉タンクをドライレグで計るって事?)
>であれば、理屈の上では計測可能ですが、現実的には検出配管に水が凝結して>たまっていくので、どんどんくるっていきます
>なので、条件としてはタンクの内部が十分に乾燥して、検出配管に水が凝結し>ないような環境が条件になります。
低圧側配管をトレースヒーターで保温でどうですかね?
これなら、水だろうが液体が水以外でも計測できるンじゃないでしょうか?
温度設定は内部圧力と計測液体の凝縮温度以上にしておけばL側には溜らないと思います。取り出しは上部から立ち上げて取る形を取れば完全満水にならない限り密閉タンクでも行けると思うのですが・・・
比重の話は内部が水であれば1mAq=0.1kgf/cm2ですが内部液体が違う場合においては液面として表示する場合に換算が必要ですよというだけです・・・
>それともタンクの中の液体部分に低圧側も接続するって事でしょうか?
>これは計測できません
そりゃ、これは無理ですねw
どっちにもヘッド掛かりますから。
個人的な見解ですが…
元のプラント条件が判りませんが防爆検定ということから有機溶剤系のタンクかを一時的に測定するものだと推察します。
(圧力容器でしたら耐圧試験ですよね?)
だったらkazu様の方式(高圧側をタンク底面、低圧側をタンク上面)にして測定すればOKかと。
もし恒常的に使用するものだとしても、導圧管をしっかり保温材で巻くか蒸気トレースや電熱式のヒーターつければ問題無いです。
電熱ヒーターも最近は配管凍結防止専用のサーモスタット付でAC100V仕様があったりして便利ですよね。
個人的に防爆仕様でレベル計ならバブリング方式でやらせてもらうかなぁ…
発信器とタンク内液を縁切りできますから。
水屋です。
色々な、水位測定方法を試しましたが、以下が安定しています。
・ポイント型
電極式・・・・・純水・可燃物・不導体・腐食液 除く
フロート式・・・・汚物(絡むもの)・長い物等 除く
フリクト式・・・・・短い物・腐食液・浸食液等 除く (春日電機 TBL含む)
・連続式
超音波・・・・・腐食性薬品の計量等(数値がふらつく)
電波式・・・・・使用経験無し
静電容量・・・高い
フロート式・・・・腐食性薬品の3m以下程度(それ以上は超音波や他)
圧力式・・・・・(差圧含む) テフロンを侵さない(塩酸等)であれば何でもOK
→投げ込み式も含む
水圧の値が目まぐるしく変わるのは、圧力センサー付近に直接落水している場合は避けられ
ませんが、多少の数値のバラつきは、調節計側のダンピング(平均化)で対処して出来ませんかね?
(但し、長すぎると水位の変化に対応出来ないが)
実績上 50cm〜10m程度であれば、圧力式(差圧含む)で対応します。
色々な、水位測定方法を試しましたが、以下が安定しています。
・ポイント型
電極式・・・・・純水・可燃物・不導体・腐食液 除く
フロート式・・・・汚物(絡むもの)・長い物等 除く
フリクト式・・・・・短い物・腐食液・浸食液等 除く (春日電機 TBL含む)
・連続式
超音波・・・・・腐食性薬品の計量等(数値がふらつく)
電波式・・・・・使用経験無し
静電容量・・・高い
フロート式・・・・腐食性薬品の3m以下程度(それ以上は超音波や他)
圧力式・・・・・(差圧含む) テフロンを侵さない(塩酸等)であれば何でもOK
→投げ込み式も含む
水圧の値が目まぐるしく変わるのは、圧力センサー付近に直接落水している場合は避けられ
ませんが、多少の数値のバラつきは、調節計側のダンピング(平均化)で対処して出来ませんかね?
(但し、長すぎると水位の変化に対応出来ないが)
実績上 50cm〜10m程度であれば、圧力式(差圧含む)で対応します。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
計装 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
計装のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 楽天イーグルス
- 31948人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37152人
- 3位
- 一行で笑わせろ!
- 82527人