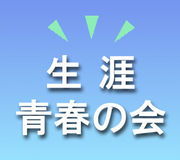NPO法人 生涯青春の会下越支部会報
支部長 西村康太郎
第1号 2010年3月号
会報製作者 石田ふたみ
ブログhttp://
目 次
1、サルエル・ウルマンの詩「青春」
2、脳とお口の体操
3、「生涯青春の会発足の集い」のスピーチの骨子
4、 やさしい人間学 ?1
1、サルエル・ウルマンの詩「青春」
「青春とは人生の或る期間を言うのではなく心の様相をいうのだ
逞ましき意思、優れた創造力、炎ゆる情熱
こういう様相を青春というのだ。
年を重ねただけで人は老いない。
理想を失う時に初めて老いがくる。
人は信念と共に若く、疑惑と共に老ゆる。
人は自信と共に若く、恐怖と共に老ゆる。
希望ある限り若く、失望と共に老い朽ちる。」
2、脳とお口の体操
http://
アナウンサーのトレーミングに使われる資料です。みんなで朗読します。
アメンボ赤いな あ・い・う・え・お 浮きもに、こえびも、泳いでる
柿の木、栗の木、か・き・く・け・こ きつつき、こつこつ、枯れケヤキ
さんまに酢をかけ、さ・し・す・せ・そ その魚、浅瀬で、刺しました
立ちましょラッパで、た・ち・つ・て・と トテトテタッタと飛び立った
なめくじのろのろ、な・に・ぬ・ね・の 納戸にぬめって、なにねばる
はとポッポ、ほろほろ、は・ひ・ふ・へ・ほ 日向のお部屋にゃ、笛を吹く
まいまい、ねじまき、ま・み・む・め・も 梅の実落ちても見もしまい
焼き栗、ゆで栗、や・い・ゆ・え・よ 山田に灯のつく、宵の家
らいちょう寒かろ、ら・り・る・れ・ろ 蓮華が咲いたら、瑠璃の鳥
わいわい、わっしょい、わ・い・う・え・お 植木屋、井戸換え、お祭りだ
歌うたいが、歌うたいにきて、歌うたえと言うが、歌うたいだけ、うたいきれれば、歌うたうけれども、歌うたいほど、歌うたえないから、歌うたわぬ。
ぱら ぴり ぷる ぺれ ぽろ
もずが鳴きます トッキョキョカキョク
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
3、生涯青春の会発足の集いのスピーチの骨子
2005年6月11日 石田双三
本日はお休みのところ、わざわざ生涯青春の会の集いにご参加頂きまして厚くお礼申し上げます。発足の集いに当たり、会の発起人として所感を述べさせていただきます。
最初に会の名称についてお断りいたします。この会のスタート準備時の名称は「80代壮健の会」でありました。80代に自立した生活をするには、若い時代の生き方そのものをチェックして、改めるべきは改めなければならないという趣旨でありました。しかし、80代壮健の会というと80代の人が集まる会であるというように受け止める人が多いのであります。よって、会の名称を生涯青春の会とさせていただきました。生涯青春などはあり得ないと受け止める方もあるかと思います。このことについては、今日のご案内に癒しの森を引用して生涯青春の概念を表示させていただきました。青春とはサルエル・ウルマンが言うように心の様相を言うのであります。心が青春であれば80代は壮健に過ごせるのではないかと思います。
次に言葉の使い方についてお断りします。現在は痴呆症・ボケ老人のことを認知症と呼ぶことになっています。私の話の中では分かりやするために認知症を痴呆症・ボケ老人と発言させていただきますのでよろしくお願い致します。あるいはこれらの社会問題について、適切でない激しい表現を使うかもしれませんが、ボケ老人を出さない運動に対する熱情を持ってのことと、ご理解を頂きたくよろしくお願いいたします。
最初にお話ししたいことは、このような会を作ろうとした動機であります。会報1号の事務局長の挨拶にありますとおり、日本では150万人の痴呆老人がいるのです。10年後には何と250万人に達するのであります。この増える100万人をどこで収容すればよいのでしょう。1年で10万人も増加する認知症(痴呆症)のお年寄りを収容するだけの病院・老人ホームはないのであります。3月末の報道によれば厚生労働省は、お年寄りが共同で暮らすグループホームに入居させようとの方針を立てています。著しい徘徊や混乱症状がある人でも介護保険の規定を改め、グループホームの利用を認めようとしています。それほど収容する場所がないのです。この現実が「呆け老人になるな!」をキャッチフレーズにする生涯青春の会を立ち上げようとした動機であります。
第2の動機はボケ老人を抱える家族の厳しい精神的な負担であります。ボケ老人になるということは、表現はいろいろあろうと思いますが、人間でなくなることを意味します。詳しくは省略しますが、ボケ老人なることは、家族に深刻な負担をかけるのであります。家族がお手上げであれば後は公的な施設に入る。ここであらゆる迷惑と負担をかけて死んで行く、これほど哀れな晩年はないと思います。人生は晩年の5〜10年が最も大切といわれています。この晩年・最終章を「ボケ老人に成らないにしよう」とするのが、会の骨格となる目的であります。
第3の動機はボケ老人が出た時の家計の経済的な負担であります。厚生年金の平均的な受給額は174000円であります。夫婦の一方が痴呆になって施設に入ると、現在の負担額は90000円前後が、まもなく改正されて、130000円余りの負担になるのです。174000円の年金で、130000円の負担が出ると残り44000円ですから、家計は完全に破産するのです。平穏な老夫婦の家庭が一遍に生活弱者になってしまいます。それゆえ「痴呆老人なるな!」と声を大にして叫びたいのであります。
次に第4の動機として、ボケ老人は生活習慣病によるものであるという現実であります。会報1号で専門家の指摘を引用しました。結論として、これら老人性痴呆は、脳を使わないという生活習慣病なのであります。平たく言えば感性の乏しい生き方をしている人は、ほぼ100%ボケ老人になってしまうのです。サルエル・ウルマンが言うように何かに燃える情熱を持っていれば、ボケ老人などは無縁なのであります、この会で呆け老人にならない生活習慣を啓蒙して行きます。ボケ老人にならないテーマと習慣を付ければ、痴呆にならないのであります。
次に「生涯青春の会」の活動の骨子であります。様々な活動を考えていますが、活動の中心は「スピーチの会」であります。1人3分〜5分のスピーチの会を開きます。スピーチの題材は、しばらくの間は、会報に掲載されている短文エッセイを活用していきます。この題材に基づいて、感想と意見などを自由に話していただきます。
たとえば、今日お集まりのご婦人の一人が「よし、毎月会合に会わせて美容院に行き、お気に入りの洋服を着て3分のスピーチをしよう」と決心したとします。この瞬間から「何を話すか」と頭の回転が全く変わってくるのであります。月1回必ずスピーチをするという習慣を付ければ、痴呆症になる危険はゼロになると確信しております。
最初からスピーチとなると負担に感じる人がいるかも知れません。その場合は参考になった場所を拝読していただくだけで結構です。それでも人前で朗読することは、血流まで変わってくるという絶大な効果があるのです。
スピーチの会は、私が講演をするとか、どこから講師を招いて講演をする計画は全くありません。前段に説明しましたように、参加者が主役となっていく会合であります。1回の会合は20〜30名と考えております。参加者が多い場合は会合を分割していく流れになります。(その他のは省略)
次に会報について報告します。会報は1年間通し番号になります。1回の発行は10ページとして、1年で120ページ1冊の会報にまとめる予定であります。皆さんのところに、1号と2号が届いておりますが、この編集方針を説明致します。
1号は80代を元気に過ごすための認識論という位置づけであります。
2号は健康にとって絶対に必要な運動であります。
3号は2号で予告してありますが、食の問題を取り上げています。
4号は人生にとって最も難しいコミュニケーションの特集号としてあります
5号は病気に関する情報を特集します。
6号は会員の意見も伺ってその他のテーマーとする予定であります。
7号から1号のテーマに戻ることにしてあります。
そして順次運動・食・コミュニケーションと反復して行きます。
ここに引用する私の短文エッセイは、1ヵ年で約120篇余りになります。この引用は、スピーチの題材を提供することを目的としています。私のエッセイと異なる意見があっても一向に差し支えないのであります。この会の価値を求める基準は、どれだけ多くの人が意見を発表するかにあります。
最後にサルエル・ウルマンの詩を朗読して終わりたいと思います。
省 略
――――――――――――――――――――――――――――――――――
講座資料?1
やさしい人間学 1
http://
うつ病患者が多い。うつ病や精神障害者で2級に認定されると月額8万円の障害者年金をもらうことが出来る。http://
どれだけのうつ病などの精神疾患の患者がいるのか、私の知る範囲では公表されていない。3年ほど前に書いた情報によると、10年間でうつ病などの精神疾患の患者は50万人も増えたという。詳しくは後記するが、うつ病患者に人間学の勉強をさせると、精神疾患から回復するという。(精神科医の証言)
以前からストレスに強い人は一定レベルの人間学を身に付けていると意識してきた。人間学は学問的には「人間とは何か?」、「人間の本質とは何か」という問いに答えようとする学問である。
難しく言えば人間とは何かを哲学の一部門として、哲学的人間学の名で呼ばれることもある。ここではこんなややこしいことを扱うわけでない。人間学を学んで「ストレスに強い人間」になることを目的に「やさしい人間学」のページを設けることにした。2003年11月23日に次の短文エッセイを書いた。松下幸之助が指摘するように「人間はダイヤモンドの原石」と思うことが人間学の根本であると思う。
1、人間はダイヤモンドの原石
http://
2、アインシュタインの語録
http://
3、歴史に輝く巨人から人間学を学ぶ
http://
4、脳が限りなく活性化するカギは
http://
5、素直であること
http://
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、人間はダイヤモンドの原石
2003年11月23日 癒しの森から
11月18日の日々の映像で暴走族の殺人事件、裁判官の「暴走族は産廃以下」発言に関連して、松下幸之助の人間観を引用した。「人間とは繁栄への能力を秘めたなんと素晴らしい存在であろう。あたかも磨けば光るダイヤモンドの原石のようなものだ」と。人間は繁栄への能力を秘めた素晴らしい存在と認識することが最も大切なことだと思う。
人間は磨けば光る、努力すれば人は変わることが出来る・・そう考えるか、そう信じるか、これが一切のベースなのだろう。これがなければ人は良い方向に変化しないと思う。
磨けば光る、言葉だけでは簡単だが、実際にこれを可能にしていくには、良き指導者に恵まれないと難しい側面を感じる。ただ、この磨けば光るとは、外部から与えられるものでなく、何らかの規範を持って、自分自身の努力によって磨かれていくのではないだろうか。
・人間は 内なる能力 厳然と 磨けば光る ダイヤの如し
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、 アインシュタインの語録
アインシュタインの以下の語録は人間の本質を突いた人間学であると思う。
「常識とは、18歳以前の心に積もりに積もった偏見以上の何物でもない。それから後に出会うどんな新しい考えも、この『常識』の概念と闘わねばならない」2003年の癒しの森を引用します。
・ ・・・・・・・・・・・・・・
人 養老 孟司(たけし)さん
2003年11月16日 癒しの森から
私が解剖学者の養老さんの文章に接したのは、2000年10月のことであった。養老さんが毎日新聞の「時代の風」に登場したのだ。社会を見る視点が独創的であり、文章も分かりやすく軽快であった。この人のコラム(エッセイかもしれない)は、月1回で2002年12月まで続いた。月刊誌潮の12月号で「現代の主役」として養老さんが登場していた。
この人が書いた「バカの壁」がベストセラーになっている。養老さんが言いたいバカの壁とは何か。関心のある人はこの本を読まれたら良いと思う。バカの壁の要点は「現代人は、何だって理解できると勘違いしているのです。つまり自分の考えにこだわって、相手の話しに耳を傾けようとしない。全部でき上がっている世界の中で固まって壁を作り、そこから外を見ようとしないんです」との指摘である。要点中の要点は「自分の考えにこだわって、相手の話に耳を傾けない」ことだろう。
1997年1月27日の日々の映像で、アインシュタインの言葉「常識とは、18歳以前の心に積もりに積もった偏見以上の何物でもない。それから後に出会うどんな新しい考えも、この『常識』の概念と闘わねばならない」を引用して、上記と同じ趣旨のことを書いた。現代人は自分の常識にこだわっている人が余りに多いと思う。
・僅かなる 自分の知識に こだわって 自ら拒否する 新たな概念
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3、歴史に輝く巨人から人間学を学ぶ
中国の魯迅、ナインチン・ゲ−ル、ヘレンケラ−、野口英夫・キュリ−夫人・エジソン・トルストイ・ゲーテ・ユゴー・・・・・歴史に燦然と輝く巨人の伝記を読むことは人間学を学ぶようなものだと思う。このような人たちの伝記を読むと、私の湧き上がる活力が生まれるように思う。ここでは2003年8月23日の癒しの森から「癒しは人との対話で生まれる」を引用します。
・・・・・・・・・・・・・・・
癒しは人との対話で生まれる
2003年08月23日(土) 癒しの森から
心が癒やされ、新たな活力が生まれる方程式があると思う。すべては人とのコミュニケーションの中から生まれると思う。それが過去の人であっても同じように思う。癒しも活力も自分と人(書物を書いた人を含む)、自分と客観世界(音楽・芸術・自然など)の間に生まれると思う。私の湧き上がる活力は、書物を書いた人との間に生まれて来た。伝記の中で最も強い印象が残っているのは、中国の魯迅とナインチン・ゲ−ルである。現在の伝記のベスト5は、ナインチン・ゲ−ル、ヘレンケラ−、野口英夫・キュリ−夫人・エジソンである。
・看護婦の 心の支えの 先駆あり その名轟く ナイチン・ゲール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4、脳が限りなく活性化するカギは
脳が限りなく活性化するカギは単純なのである。「読む」「書く」「話す」
の3点が生活の中に定着することである。ただ「読む」だけの「静」の状態では脳は活発に活動しない。「読む」に加えて「書く」「話す」という「動」が加わると、脳は限りなく活性化していくのである。
NPO法人生涯青春の会の中心イベントは「スピーチの会」である。一人の持ち時間5分間で起承転結がまとまっているスピーチをすることは簡単なものではない。「話す」ために当然「読む」「書く」という準備をしなければならない。リタイヤした中高年が大勢の前でスピーチをする機会はほとんどない。この活動をなぜ行って来たかといえば、ひとえに参加者の脳活性化(記憶力の向上)のためであった。
・・・・・・・・・・・・・・・
記憶力
2004年1月8日 癒しの森」から
今日も昨日と同じく、講演の準備の一つとして2000年12月31日の日々の映像に書いた「記憶力」の大半を引用しておきたい。
・・・私は昔から記憶する能力が乏しいと自覚してきた。この弱さを証明する根拠は、人の名前がなかなか覚えられないという事実である。しかし、書くという行動があると、鈍い私の脳もかなりの情報を記憶する。今日で、1460回目の日々の映像の記述となったが、手を動かすことがいかに重要なことであるかをヒシヒシと感じている。
脳と心の地形図(原書房・リタ・カータ著)という本を読んだ。『脳にある何十億というニューロンは、100兆もの結合を持っていて、その一つずつが記憶の一部になる可能性を秘めている。だから、人間の記憶能力は、正しいやり方で蓄えられれば無限なのである』(同書P259)・・・・
1998年12月31日にも書いたが、情報を得たら先ずメモをする(手を動かす)そして話す(口を動かす)という「動」が加わると、完全に記憶として刻まれるのである。途中で手を動かす行動を省略しても、話すという「動」があればその情報・知識は脳に刻まれる。これらの「動」がいかに重要か、これを深く理解して行動すれば、脳は限りなく活性化していくように思う。ただ聞く、読むだけの「静」の状態では、脳の開発・活性化はありえないのである。
・人間の 脳と呼ばれる 小宇宙 無限に広がる ミクロの世界
・ンチャさんから長文の書き込みがある。
http://
5、素直であること
現役のころ経営者と懇談する機会が多くあった。「社員の求めることは何ですか」という質問に対して「素直であること」と答える人が多くいた記憶がある。
私が20年間取締役であった会社の社長は「社員の条件は素直であること」であった。人間学を語る意味で「素直」という概念ほど重要なことはないと思う。
2003年9月4日のマラソンの指導者である小出義雄監督の言葉を引用した。
「勝者に祝福の声も掛けず嫉妬をしている選手は強くなれない」との指摘だ。以下の通りスポーツの世界も「素直な子」でないと伸びないという。現実の社会も「素直」でないと伸びないことは確かである。
・・・・・・・・・・・・・
人:小出義雄監督
2003年09月04日癒しの森
昨日マラソン「銅」に輝いた千葉真子のことを書いた。千葉は1997年アテネ大会の一万メートルで「銅」であった。再び、世界の舞台に立てたのは小出門下生になったことだろう。
日々の映像でマラソンの指導者小出義雄監督のことは何回も書いた。小出監督の語録は味わい深い。監督は「嫉妬する子は伸びない」という。スポーツの世界は、実力第一の世界である。
伸びていく子は、他の選手が好成績を残した時、素直に「良かったね』と喜ぶという。逆に「勝者に祝福の声も掛けず嫉妬をしている選手は強くなれない」との指摘だ。人間の本質論で理解できる。この語録を踏まえて次の短歌を作る。
・豊かなる 人生開く カギ如何 心に育つか 素直の二文字
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、12月3日入学式でのスピーチの骨子
http://
3、人 佐藤幸子さん
2003年08月24日 癒しの森から
日々の映像を書き出した1977年から4年間余り毎月手書きの日々の映像を佐藤幸子さんに送っていた。佐藤幸子さんは、山形県上山温泉・日本の宿「ホテル古窯」の創業社長である。頭脳明晰、しかも癒しの心とコミュニケーション能力が満ちている素敵な人であった。この人が新潟で講演された内容で、次の短歌を作る。
・目の前に 起こりしことに 学びつつ 我が運命を いかに開かん
・人生は 感動ありて 育むか 話の中に きらめく光
・人生は 一期一会で 良き人と 出会いの中で 生かされゆかん
受講生に対するメッセージ
・6ヵ月 営業講座で 学びつつ 我が運命を いかに開かん
4、人 うつみ宮土理さん(1)
2003年09月29日 癒しの森から
もう6年も前になるが、PHPで「人づきあいの決め手」と題する特集があった。その中のうつみ宮土理さんのエッセイを読む。いまだにそのエッセイの印象が残っている。ここで一部を引用したい。
「『人には機嫌よく接しなさい』という父の言葉は、いつでも私の心に刻み込まれています。思いやりや、心配りのない態度は、相手を疲れさせ、それ以上の深い関係は望めなくなります」と。
「人には機嫌よく接せる」これが人と人とのコミュニケーションが出来る根幹と理解した。宮土理さんは明るく聡明な人である。このエッセイを踏まえて短歌を作る。
・明るさの 振舞いこそが 花となる 心に刻む 父の教えを
『「上機嫌」は、円滑なコミュニケーションのための技!』
齋藤 孝
『上機嫌は、人が社交界にまというる最上の装飾具の一つである』
サッカレー
ウィリアム・サッカレー
英国 の作家 (1811-1863).
Thackeray, William Makepeace
[ イギリス] [作家]
[ウィリアム・サッカレー 人物情報]
イギリスの小説家。1811年東インド会社の収税官の子として、インドのカルカッタに生まれる。1817年にイギリスに帰国。ケンブリッジ大学に入学するが中退。海外旅行に出てワイマールでゲーテと出会った。
父の死や妻の発狂で人生のはかなさを痛感。作品では上・中流階級の生活を詳細かつ風刺的に描いた。
代表作『虚栄の市』『イギリスの俗物たち』など。
支部長 西村康太郎
第1号 2010年3月号
会報製作者 石田ふたみ
ブログhttp://
目 次
1、サルエル・ウルマンの詩「青春」
2、脳とお口の体操
3、「生涯青春の会発足の集い」のスピーチの骨子
4、 やさしい人間学 ?1
1、サルエル・ウルマンの詩「青春」
「青春とは人生の或る期間を言うのではなく心の様相をいうのだ
逞ましき意思、優れた創造力、炎ゆる情熱
こういう様相を青春というのだ。
年を重ねただけで人は老いない。
理想を失う時に初めて老いがくる。
人は信念と共に若く、疑惑と共に老ゆる。
人は自信と共に若く、恐怖と共に老ゆる。
希望ある限り若く、失望と共に老い朽ちる。」
2、脳とお口の体操
http://
アナウンサーのトレーミングに使われる資料です。みんなで朗読します。
アメンボ赤いな あ・い・う・え・お 浮きもに、こえびも、泳いでる
柿の木、栗の木、か・き・く・け・こ きつつき、こつこつ、枯れケヤキ
さんまに酢をかけ、さ・し・す・せ・そ その魚、浅瀬で、刺しました
立ちましょラッパで、た・ち・つ・て・と トテトテタッタと飛び立った
なめくじのろのろ、な・に・ぬ・ね・の 納戸にぬめって、なにねばる
はとポッポ、ほろほろ、は・ひ・ふ・へ・ほ 日向のお部屋にゃ、笛を吹く
まいまい、ねじまき、ま・み・む・め・も 梅の実落ちても見もしまい
焼き栗、ゆで栗、や・い・ゆ・え・よ 山田に灯のつく、宵の家
らいちょう寒かろ、ら・り・る・れ・ろ 蓮華が咲いたら、瑠璃の鳥
わいわい、わっしょい、わ・い・う・え・お 植木屋、井戸換え、お祭りだ
歌うたいが、歌うたいにきて、歌うたえと言うが、歌うたいだけ、うたいきれれば、歌うたうけれども、歌うたいほど、歌うたえないから、歌うたわぬ。
ぱら ぴり ぷる ぺれ ぽろ
もずが鳴きます トッキョキョカキョク
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
3、生涯青春の会発足の集いのスピーチの骨子
2005年6月11日 石田双三
本日はお休みのところ、わざわざ生涯青春の会の集いにご参加頂きまして厚くお礼申し上げます。発足の集いに当たり、会の発起人として所感を述べさせていただきます。
最初に会の名称についてお断りいたします。この会のスタート準備時の名称は「80代壮健の会」でありました。80代に自立した生活をするには、若い時代の生き方そのものをチェックして、改めるべきは改めなければならないという趣旨でありました。しかし、80代壮健の会というと80代の人が集まる会であるというように受け止める人が多いのであります。よって、会の名称を生涯青春の会とさせていただきました。生涯青春などはあり得ないと受け止める方もあるかと思います。このことについては、今日のご案内に癒しの森を引用して生涯青春の概念を表示させていただきました。青春とはサルエル・ウルマンが言うように心の様相を言うのであります。心が青春であれば80代は壮健に過ごせるのではないかと思います。
次に言葉の使い方についてお断りします。現在は痴呆症・ボケ老人のことを認知症と呼ぶことになっています。私の話の中では分かりやするために認知症を痴呆症・ボケ老人と発言させていただきますのでよろしくお願い致します。あるいはこれらの社会問題について、適切でない激しい表現を使うかもしれませんが、ボケ老人を出さない運動に対する熱情を持ってのことと、ご理解を頂きたくよろしくお願いいたします。
最初にお話ししたいことは、このような会を作ろうとした動機であります。会報1号の事務局長の挨拶にありますとおり、日本では150万人の痴呆老人がいるのです。10年後には何と250万人に達するのであります。この増える100万人をどこで収容すればよいのでしょう。1年で10万人も増加する認知症(痴呆症)のお年寄りを収容するだけの病院・老人ホームはないのであります。3月末の報道によれば厚生労働省は、お年寄りが共同で暮らすグループホームに入居させようとの方針を立てています。著しい徘徊や混乱症状がある人でも介護保険の規定を改め、グループホームの利用を認めようとしています。それほど収容する場所がないのです。この現実が「呆け老人になるな!」をキャッチフレーズにする生涯青春の会を立ち上げようとした動機であります。
第2の動機はボケ老人を抱える家族の厳しい精神的な負担であります。ボケ老人になるということは、表現はいろいろあろうと思いますが、人間でなくなることを意味します。詳しくは省略しますが、ボケ老人なることは、家族に深刻な負担をかけるのであります。家族がお手上げであれば後は公的な施設に入る。ここであらゆる迷惑と負担をかけて死んで行く、これほど哀れな晩年はないと思います。人生は晩年の5〜10年が最も大切といわれています。この晩年・最終章を「ボケ老人に成らないにしよう」とするのが、会の骨格となる目的であります。
第3の動機はボケ老人が出た時の家計の経済的な負担であります。厚生年金の平均的な受給額は174000円であります。夫婦の一方が痴呆になって施設に入ると、現在の負担額は90000円前後が、まもなく改正されて、130000円余りの負担になるのです。174000円の年金で、130000円の負担が出ると残り44000円ですから、家計は完全に破産するのです。平穏な老夫婦の家庭が一遍に生活弱者になってしまいます。それゆえ「痴呆老人なるな!」と声を大にして叫びたいのであります。
次に第4の動機として、ボケ老人は生活習慣病によるものであるという現実であります。会報1号で専門家の指摘を引用しました。結論として、これら老人性痴呆は、脳を使わないという生活習慣病なのであります。平たく言えば感性の乏しい生き方をしている人は、ほぼ100%ボケ老人になってしまうのです。サルエル・ウルマンが言うように何かに燃える情熱を持っていれば、ボケ老人などは無縁なのであります、この会で呆け老人にならない生活習慣を啓蒙して行きます。ボケ老人にならないテーマと習慣を付ければ、痴呆にならないのであります。
次に「生涯青春の会」の活動の骨子であります。様々な活動を考えていますが、活動の中心は「スピーチの会」であります。1人3分〜5分のスピーチの会を開きます。スピーチの題材は、しばらくの間は、会報に掲載されている短文エッセイを活用していきます。この題材に基づいて、感想と意見などを自由に話していただきます。
たとえば、今日お集まりのご婦人の一人が「よし、毎月会合に会わせて美容院に行き、お気に入りの洋服を着て3分のスピーチをしよう」と決心したとします。この瞬間から「何を話すか」と頭の回転が全く変わってくるのであります。月1回必ずスピーチをするという習慣を付ければ、痴呆症になる危険はゼロになると確信しております。
最初からスピーチとなると負担に感じる人がいるかも知れません。その場合は参考になった場所を拝読していただくだけで結構です。それでも人前で朗読することは、血流まで変わってくるという絶大な効果があるのです。
スピーチの会は、私が講演をするとか、どこから講師を招いて講演をする計画は全くありません。前段に説明しましたように、参加者が主役となっていく会合であります。1回の会合は20〜30名と考えております。参加者が多い場合は会合を分割していく流れになります。(その他のは省略)
次に会報について報告します。会報は1年間通し番号になります。1回の発行は10ページとして、1年で120ページ1冊の会報にまとめる予定であります。皆さんのところに、1号と2号が届いておりますが、この編集方針を説明致します。
1号は80代を元気に過ごすための認識論という位置づけであります。
2号は健康にとって絶対に必要な運動であります。
3号は2号で予告してありますが、食の問題を取り上げています。
4号は人生にとって最も難しいコミュニケーションの特集号としてあります
5号は病気に関する情報を特集します。
6号は会員の意見も伺ってその他のテーマーとする予定であります。
7号から1号のテーマに戻ることにしてあります。
そして順次運動・食・コミュニケーションと反復して行きます。
ここに引用する私の短文エッセイは、1ヵ年で約120篇余りになります。この引用は、スピーチの題材を提供することを目的としています。私のエッセイと異なる意見があっても一向に差し支えないのであります。この会の価値を求める基準は、どれだけ多くの人が意見を発表するかにあります。
最後にサルエル・ウルマンの詩を朗読して終わりたいと思います。
省 略
――――――――――――――――――――――――――――――――――
講座資料?1
やさしい人間学 1
http://
うつ病患者が多い。うつ病や精神障害者で2級に認定されると月額8万円の障害者年金をもらうことが出来る。http://
どれだけのうつ病などの精神疾患の患者がいるのか、私の知る範囲では公表されていない。3年ほど前に書いた情報によると、10年間でうつ病などの精神疾患の患者は50万人も増えたという。詳しくは後記するが、うつ病患者に人間学の勉強をさせると、精神疾患から回復するという。(精神科医の証言)
以前からストレスに強い人は一定レベルの人間学を身に付けていると意識してきた。人間学は学問的には「人間とは何か?」、「人間の本質とは何か」という問いに答えようとする学問である。
難しく言えば人間とは何かを哲学の一部門として、哲学的人間学の名で呼ばれることもある。ここではこんなややこしいことを扱うわけでない。人間学を学んで「ストレスに強い人間」になることを目的に「やさしい人間学」のページを設けることにした。2003年11月23日に次の短文エッセイを書いた。松下幸之助が指摘するように「人間はダイヤモンドの原石」と思うことが人間学の根本であると思う。
1、人間はダイヤモンドの原石
http://
2、アインシュタインの語録
http://
3、歴史に輝く巨人から人間学を学ぶ
http://
4、脳が限りなく活性化するカギは
http://
5、素直であること
http://
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、人間はダイヤモンドの原石
2003年11月23日 癒しの森から
11月18日の日々の映像で暴走族の殺人事件、裁判官の「暴走族は産廃以下」発言に関連して、松下幸之助の人間観を引用した。「人間とは繁栄への能力を秘めたなんと素晴らしい存在であろう。あたかも磨けば光るダイヤモンドの原石のようなものだ」と。人間は繁栄への能力を秘めた素晴らしい存在と認識することが最も大切なことだと思う。
人間は磨けば光る、努力すれば人は変わることが出来る・・そう考えるか、そう信じるか、これが一切のベースなのだろう。これがなければ人は良い方向に変化しないと思う。
磨けば光る、言葉だけでは簡単だが、実際にこれを可能にしていくには、良き指導者に恵まれないと難しい側面を感じる。ただ、この磨けば光るとは、外部から与えられるものでなく、何らかの規範を持って、自分自身の努力によって磨かれていくのではないだろうか。
・人間は 内なる能力 厳然と 磨けば光る ダイヤの如し
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、 アインシュタインの語録
アインシュタインの以下の語録は人間の本質を突いた人間学であると思う。
「常識とは、18歳以前の心に積もりに積もった偏見以上の何物でもない。それから後に出会うどんな新しい考えも、この『常識』の概念と闘わねばならない」2003年の癒しの森を引用します。
・ ・・・・・・・・・・・・・・
人 養老 孟司(たけし)さん
2003年11月16日 癒しの森から
私が解剖学者の養老さんの文章に接したのは、2000年10月のことであった。養老さんが毎日新聞の「時代の風」に登場したのだ。社会を見る視点が独創的であり、文章も分かりやすく軽快であった。この人のコラム(エッセイかもしれない)は、月1回で2002年12月まで続いた。月刊誌潮の12月号で「現代の主役」として養老さんが登場していた。
この人が書いた「バカの壁」がベストセラーになっている。養老さんが言いたいバカの壁とは何か。関心のある人はこの本を読まれたら良いと思う。バカの壁の要点は「現代人は、何だって理解できると勘違いしているのです。つまり自分の考えにこだわって、相手の話しに耳を傾けようとしない。全部でき上がっている世界の中で固まって壁を作り、そこから外を見ようとしないんです」との指摘である。要点中の要点は「自分の考えにこだわって、相手の話に耳を傾けない」ことだろう。
1997年1月27日の日々の映像で、アインシュタインの言葉「常識とは、18歳以前の心に積もりに積もった偏見以上の何物でもない。それから後に出会うどんな新しい考えも、この『常識』の概念と闘わねばならない」を引用して、上記と同じ趣旨のことを書いた。現代人は自分の常識にこだわっている人が余りに多いと思う。
・僅かなる 自分の知識に こだわって 自ら拒否する 新たな概念
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3、歴史に輝く巨人から人間学を学ぶ
中国の魯迅、ナインチン・ゲ−ル、ヘレンケラ−、野口英夫・キュリ−夫人・エジソン・トルストイ・ゲーテ・ユゴー・・・・・歴史に燦然と輝く巨人の伝記を読むことは人間学を学ぶようなものだと思う。このような人たちの伝記を読むと、私の湧き上がる活力が生まれるように思う。ここでは2003年8月23日の癒しの森から「癒しは人との対話で生まれる」を引用します。
・・・・・・・・・・・・・・・
癒しは人との対話で生まれる
2003年08月23日(土) 癒しの森から
心が癒やされ、新たな活力が生まれる方程式があると思う。すべては人とのコミュニケーションの中から生まれると思う。それが過去の人であっても同じように思う。癒しも活力も自分と人(書物を書いた人を含む)、自分と客観世界(音楽・芸術・自然など)の間に生まれると思う。私の湧き上がる活力は、書物を書いた人との間に生まれて来た。伝記の中で最も強い印象が残っているのは、中国の魯迅とナインチン・ゲ−ルである。現在の伝記のベスト5は、ナインチン・ゲ−ル、ヘレンケラ−、野口英夫・キュリ−夫人・エジソンである。
・看護婦の 心の支えの 先駆あり その名轟く ナイチン・ゲール
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4、脳が限りなく活性化するカギは
脳が限りなく活性化するカギは単純なのである。「読む」「書く」「話す」
の3点が生活の中に定着することである。ただ「読む」だけの「静」の状態では脳は活発に活動しない。「読む」に加えて「書く」「話す」という「動」が加わると、脳は限りなく活性化していくのである。
NPO法人生涯青春の会の中心イベントは「スピーチの会」である。一人の持ち時間5分間で起承転結がまとまっているスピーチをすることは簡単なものではない。「話す」ために当然「読む」「書く」という準備をしなければならない。リタイヤした中高年が大勢の前でスピーチをする機会はほとんどない。この活動をなぜ行って来たかといえば、ひとえに参加者の脳活性化(記憶力の向上)のためであった。
・・・・・・・・・・・・・・・
記憶力
2004年1月8日 癒しの森」から
今日も昨日と同じく、講演の準備の一つとして2000年12月31日の日々の映像に書いた「記憶力」の大半を引用しておきたい。
・・・私は昔から記憶する能力が乏しいと自覚してきた。この弱さを証明する根拠は、人の名前がなかなか覚えられないという事実である。しかし、書くという行動があると、鈍い私の脳もかなりの情報を記憶する。今日で、1460回目の日々の映像の記述となったが、手を動かすことがいかに重要なことであるかをヒシヒシと感じている。
脳と心の地形図(原書房・リタ・カータ著)という本を読んだ。『脳にある何十億というニューロンは、100兆もの結合を持っていて、その一つずつが記憶の一部になる可能性を秘めている。だから、人間の記憶能力は、正しいやり方で蓄えられれば無限なのである』(同書P259)・・・・
1998年12月31日にも書いたが、情報を得たら先ずメモをする(手を動かす)そして話す(口を動かす)という「動」が加わると、完全に記憶として刻まれるのである。途中で手を動かす行動を省略しても、話すという「動」があればその情報・知識は脳に刻まれる。これらの「動」がいかに重要か、これを深く理解して行動すれば、脳は限りなく活性化していくように思う。ただ聞く、読むだけの「静」の状態では、脳の開発・活性化はありえないのである。
・人間の 脳と呼ばれる 小宇宙 無限に広がる ミクロの世界
・ンチャさんから長文の書き込みがある。
http://
5、素直であること
現役のころ経営者と懇談する機会が多くあった。「社員の求めることは何ですか」という質問に対して「素直であること」と答える人が多くいた記憶がある。
私が20年間取締役であった会社の社長は「社員の条件は素直であること」であった。人間学を語る意味で「素直」という概念ほど重要なことはないと思う。
2003年9月4日のマラソンの指導者である小出義雄監督の言葉を引用した。
「勝者に祝福の声も掛けず嫉妬をしている選手は強くなれない」との指摘だ。以下の通りスポーツの世界も「素直な子」でないと伸びないという。現実の社会も「素直」でないと伸びないことは確かである。
・・・・・・・・・・・・・
人:小出義雄監督
2003年09月04日癒しの森
昨日マラソン「銅」に輝いた千葉真子のことを書いた。千葉は1997年アテネ大会の一万メートルで「銅」であった。再び、世界の舞台に立てたのは小出門下生になったことだろう。
日々の映像でマラソンの指導者小出義雄監督のことは何回も書いた。小出監督の語録は味わい深い。監督は「嫉妬する子は伸びない」という。スポーツの世界は、実力第一の世界である。
伸びていく子は、他の選手が好成績を残した時、素直に「良かったね』と喜ぶという。逆に「勝者に祝福の声も掛けず嫉妬をしている選手は強くなれない」との指摘だ。人間の本質論で理解できる。この語録を踏まえて次の短歌を作る。
・豊かなる 人生開く カギ如何 心に育つか 素直の二文字
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2、12月3日入学式でのスピーチの骨子
http://
3、人 佐藤幸子さん
2003年08月24日 癒しの森から
日々の映像を書き出した1977年から4年間余り毎月手書きの日々の映像を佐藤幸子さんに送っていた。佐藤幸子さんは、山形県上山温泉・日本の宿「ホテル古窯」の創業社長である。頭脳明晰、しかも癒しの心とコミュニケーション能力が満ちている素敵な人であった。この人が新潟で講演された内容で、次の短歌を作る。
・目の前に 起こりしことに 学びつつ 我が運命を いかに開かん
・人生は 感動ありて 育むか 話の中に きらめく光
・人生は 一期一会で 良き人と 出会いの中で 生かされゆかん
受講生に対するメッセージ
・6ヵ月 営業講座で 学びつつ 我が運命を いかに開かん
4、人 うつみ宮土理さん(1)
2003年09月29日 癒しの森から
もう6年も前になるが、PHPで「人づきあいの決め手」と題する特集があった。その中のうつみ宮土理さんのエッセイを読む。いまだにそのエッセイの印象が残っている。ここで一部を引用したい。
「『人には機嫌よく接しなさい』という父の言葉は、いつでも私の心に刻み込まれています。思いやりや、心配りのない態度は、相手を疲れさせ、それ以上の深い関係は望めなくなります」と。
「人には機嫌よく接せる」これが人と人とのコミュニケーションが出来る根幹と理解した。宮土理さんは明るく聡明な人である。このエッセイを踏まえて短歌を作る。
・明るさの 振舞いこそが 花となる 心に刻む 父の教えを
『「上機嫌」は、円滑なコミュニケーションのための技!』
齋藤 孝
『上機嫌は、人が社交界にまというる最上の装飾具の一つである』
サッカレー
ウィリアム・サッカレー
英国 の作家 (1811-1863).
Thackeray, William Makepeace
[ イギリス] [作家]
[ウィリアム・サッカレー 人物情報]
イギリスの小説家。1811年東インド会社の収税官の子として、インドのカルカッタに生まれる。1817年にイギリスに帰国。ケンブリッジ大学に入学するが中退。海外旅行に出てワイマールでゲーテと出会った。
父の死や妻の発狂で人生のはかなさを痛感。作品では上・中流階級の生活を詳細かつ風刺的に描いた。
代表作『虚栄の市』『イギリスの俗物たち』など。
|
|
|
|
|
|
|
|
NPO法人生涯青春の会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NPO法人生涯青春の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90053人
- 2位
- 酒好き
- 170690人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人