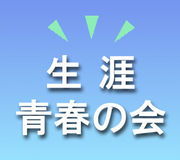1、発起人ご挨拶 2005年6月11日 石田 双三
最初に話が出ましたのは、試料(6)の通り昨年2月「百歳まで生きようじゃないか」の会を作らないかとの提案を受けました。しかし、百歳を超えて自立できているかとなるとこれまた大変なことなのです。2003年9月13日の癒しの森に書きましたが、食事など基本的動作を介助なしで行なえる割合が少ないのです。最も厳しいのは会話が出来ない割合が多いのです。百歳以上の人達で、会話をするなど意思の疎通が出来る割合は、男性が58%女性は35%なのです。意思の疎通が出来なくてただ生きているだけでは意味がないと思います。そのような視点から「百歳まで生きようじゃないか」の会は頓挫いたしましました。その後意見交換が進み昨年11月資料(7)の通り「生涯青春の会」としてスタートしようとの意見が集約され今日に至った次第であります。
2ページ以降に資料が12題引用されておりまが、このことに付いて説明を致します。この文章は、エンピツのサイトを利用して日々の映像としてインターネットに公開しているものです(http://
2、参考資料目次
(1)百歳を過ぎてもまだまだ現役 (2004年2月10日)
(2)人に役立つ意識とパワー (2004年2月11日)
(3)百歳でまだまだこれからの平山直八さん(2004年2月12日)
(4)百歳まで元気でいるには (2004年2月13日)
(5)元気で長生き10ヵ条 ( (2004年2月14日)
(6)百歳まで生きようじゃないか!の会 (2004年2月15日)
(7)生涯青春の会のスタートの機運 (2004年11月24日)
(8)会の基本的な理念 (2005年2月20日)
(9)準備会 (2005年3月17日)
(10)会の方向性 (2005年3月27日)
(11)ボケ老人になる原因 (2005年3月30日)
(12)老人性痴呆は生活習慣病である (2005年4月4日)
(1)百歳を過ぎてもまだまだ現役
(2004年2月10日の癒しの森から)
1998年1月18日の「日々の映像」で「百歳でまだまだこれから」と題するエッセイを書いた。この時登場していただいた人は、弁護士の平山直八(1897年生まれ)氏で、エッセイを書いた時すでに101歳であった。この人の語録を引用したい。「まだまだこれからです。もっと社会にお役に立ちたい」であった。
月刊誌「潮」に脚本家であり、相撲フアンで知られる内館牧子のインタビューシリーズ「今日もがぶりより!」という連載がある。連載27回目の3月号は百歳を過ぎてもまだまだ“現役”を続けている飯田深雪さん(1903年生まれ・料理研究家・アートフラワー創始者)が登場していた。多くを記述するだけの紙幅がないので、人生の根幹と思われる。語録を引用したい。「どんな人にもその人独特の能力とか特徴があると思うのです。それを人のために活かすように考えて行動することです」であった。 詳しくは後日に書きたいが、人のために役立とう(大きく言えば社会貢献)という意識があると、人間としてのパワーが増していくのである。
・100歳で まだまだ現役 意気盛ん 無限のパワーの みなもと如何
(2) 人に役立つ意識とパワー
(2004年2月11日の癒しの森から、以下同)
2月10日「人のために役立とう(大きく家が社会貢献)という意識があると、人間としてのパワーが増していく」と書いた。今日はこのことに付いて1998年1月18日に記述した日々の映像から引用したい。
「今年1月10日のアン安全大会で(財)日本心身医学協会所属の飯田国彦氏(心理学博士)の講演を聞く。講演のテーマは「健康と安全の基本」であった。社会に貢献するという意識が人間としてのパワーを増して行くとの論旨であった。・・・・このような生き方をすると、次のようなパターンになるというのだ。
社会貢献の意識と行動――有効ホルモンの分泌――免疫力の向上――体調良好――能力が顕在化していく。
自分のことしか考えていない生活のパターンでは、免疫力の向上はないし、能力も顕在化して来ないというのである。講演の骨子は、60兆の細胞の活性化も30億のDNA情報の顕在化も、その人の生活のパターンによって決まるというものであった。これと同じ視点、論旨を昨年11月30日(この癒しの森では2月8日)「心の働きと生命の暗号」に書いたので、飯田氏の論旨はよく理解できた」
・行動の 理念がパワーの 母なるか 細胞次元に 意識が届く
(3) 百歳でまだまだこれからの平山直八さん
(2004年2月12日)
平山直八さんのことは2月10日に名前の紹介程度に留めた。しかし、この人のことを書いた1998年1月18日の日々の映像を読んでみると、この人の生きる力の凄さに圧倒される。この癒しの森に引用して、改めて平山直八さんを顕彰したい。
「『潮』2月号に元気な百歳の弁護士平山直八さんのことが出ていた。1897年生まれなので百歳を超えている。小学校の教師をしながら、中央大学の夜間部に通い、33歳の時に司法試験に合格、60歳まで教員生活を続け、その後40年間弁護士として活躍している。百歳になった今でも、離婚・相続などの相談に応じている。このほか東京北区で生涯教育奉仕団を作り、老人ホームを訪問して入居者達を励げましたり、いじめや不登校などの教育問題にも懇談会を開くなど第一線で取り組んでいる。
平山さんの語録がある。『まだまだこれからです。もっと社会のお役に立ちたい』と意気軒昂で、その旺盛な活動は衰えを知らないという」
昨日の飯田国彦氏の論旨に基づくと社会貢献という意識と行動が、有効ホルモンを分泌させ免疫力を向上させ全細胞の活性化が計られているのだ。それゆえ、百歳になられても「まだまだこれからです」という意欲が現われるのだろうと思った。
・人のため 命を燃やして 百歳に 人の鏡か 「まだまだこれから」
(短歌は1998年1月18日の日々の映像から)
(4) 百歳まで元気でいるには (2004年2月13日)
2月10日から百歳に関することを書くのは4回目となった。百歳になって元気でいることが、いかに大変なことかを考えてみよう。2003年9月13日の日々の映像で、百歳以上2万人の実情を書いた。詳しくは省略するが、食事など基本的動作を介助なしで行なえる割合は、男性30・9%対して女性は僅か13・6%しかいないのである。
それゆえ、飯田深雪さんや平山直八さんの存在は、驚嘆すべきことなのである。少なくとも、活力がこんこんと湧き出るような生き方をしないと、百歳になって社会で活躍することは不可能なことだと思う。
アインシュタインが含蓄のある言葉を残している。「人は自分以外のもののために生きられるようになって、初めて生のスタートを切る」と。私は1998年1月18日に日々の映像の結びで次のように書いた「自分以外のもののために生きられるようになる・・これを我が人生の最大の課題にしようと思った。そこに初めて気力が溢れる充実の日々が待っているような気がする」と。
・活力が こんこん湧き出る 生き方は アインシュタインの 示す道かな
(5) 元気で長生き10ヵ条 (2004年2月14日)
長寿に関することをもう一回記述したい。NHK朝8時30分から生活ホットモーニングという番組がある。2月9日は「元気で長生き10か条」のタイトルであった。この10か条は後記のメモの通りであるが、2〜10まではおおよそ理解しているように思う。1番の「血液中のアルブミンの値が高い」ことという条件は、耳なれないことなので少々記述したい。
1、血液中のアルブミンの値
東京都老人総合研究所では、在宅で元気に暮らすためには3.8g/dl以下は要注意、必要と指導しています。血液中のアルブミンが少ないと(低たんぱく状態)、感染症にかかりやすい、ウツ状態になりやすいなど、問題が発生します。
2、血液中のアルブミン値を維持するために
動物性のたんぱく質1(40グラム):植物性のたんぱく質1(40グラム)を摂取しながら、バランスの良い食生活を心がけましょう。(生活ホットモーニングのページから) イメージに薄かったのは4の「自分は健康だ」と思っている人が長生きをするというのだ。これは明らかに「気」が作用している。次に社会参加が活発な人が長寿であることは、補足するまでもないことだ。
・長生きの 秘訣は何かと 尋ねると 気の整えと 食のバランス
メモ、元気で長生き10か条(ホットモーニングから)
1、血液中のアルブミンの値が高い
2、血液中の総コレステロール値は高すぎず低すぎず
3、血圧は高すぎず低すぎず
4、「自分は健康だ」と思っている
5、足が丈夫である
6、短期の記憶力がよい
7、太り方は中くらい
8、タバコを吸わない
9、お酒は飲みすぎない
10、社会参加が活発である
(6) 百歳まで生きようじゃないか!の会 (2004年2月15日)
ここのところ日々の映像の読者と懇談する機会が多くあった。読者の一人から「百歳まで生きようじゃないか!の会」を作らないかとの提案を受ける。この提案者は私が2月10日から以下の通り長寿に関する記述を読んでのことであった。
2月10日 百歳を過ぎてもまだまだ現役
2月11日 人に役立つ意識とパワー
2月12日 百歳でまだまだこれからの平山直八さん
2月13日 百歳まで元気でいるには
2月14日 元気で長生き10か条
ともかく百歳まで元気で生きることは容易なことでない。この会を作るとしたらどのような活動をすればよいのかとの意見交換をする。ここで多少書き出すと次の通りだ。
1、長寿のための食を徹底して学習をする。
2、生きるパワーを増すための学習をする。
3、病気にならないための学習
4、日々の映像・癒しの森を題材とした討論会を開く(会話の機会を作る)
5、百歳まで生きようという「気」のない人はお断り。
6、学習の講師は会のメンバーから輩出していく。(講師は全てボランテァ)
7、会のメンバーは良き友人となって、激励しあっていく。
この会が出来るかどうかは、今日の段階では分からない。趣旨に賛同する人たちと意見交換を積み上げて行きたいと思っている。
(7)生涯青春の会スタートの機運 (2004年11月24日)
今年2月10日から14日まで「百歳を過ぎてもまだまだ現役」など長寿のことを5日間連続して書いた。これを読んだ知人から「百歳までいきようじゃないか!の会」を作らないかとの提案を受ける。ともかく百歳まで元気で生きることは容易なことでない。100歳は余りにハードルが高く現実的ではない。8月3日友人と意見交換したが、「80代壮健の会」(仮称)にしたらどうかとの案となり、以下の項目の意見交換となる。
・会の加入年齢は特に定めない
・長寿のための食の学習をする。
・病気にならないための学習をする。
・日々の映像・癒しの森を題材として会話の機会を作る。
・会のメンバーは良き友人となって、激励し合っていく。
・話し合い 刺激しあって 80代 自分の足で 目指せ壮健
(2004年8月3日の癒しの森から)
(8)生涯青春の会の基本的な理念 (2005年2月20日)
2月17日80代壮健の会に参加したいという60代の婦人三人と懇談した。私の目指すこの会は単なる慰め会・娯楽の会ではないのである。一定の理念を持って、共に行動し励ましあって80代を元気で過ごそうというものである。この会の基本的な理念が一致する人から加入していただこうと考えている。癒しの森で長寿に関して以下の記述を行なったが、この内容が会の基本的な理念になればよいと思っている。理念の骨子は、2004年2月11日に書いた社会貢献の意識と行動、2004年2月13日に書いたアインシュタインの「人は自分以外のもののために生きられるようになって、初めて生のスタートを切る」などである。
・ 2004年02月10日 百歳をすぎてもまだまだ現役
・ 2004年02月11日 人に役立つ意識とパワー
・ 2004年02月12日 百歳でまだまだこれからの平山直八さん
・ 2004年02月13日 百歳まで元気でいるには
・ 2004年02月14日 元気で長生き10か条
・ 2004年02月15日 百歳まで生きようじゃないかの会
・生き方が パワーを生み出す この原理 行動起こして 生へのスタート
(9)生涯青春の会の準備会 (2005年3月17日)
2月17日と2月20日に80代壮健の会のことを書いた。その後この会を作ろうと賛意を示している人たちと時折意見交換をしている。これらの意見を少しずつまとめて、5月頃から月1回の発足準備会を開くことになった。この準備会で様々な意見を交わし、合意点の整理を進め2006年4月ごろ正式に「80代壮健の会」をスタートしたいと思っている。随分とスローでないかとの意見のあるのだが、自分たちが作ろうとする会をあらゆる角度から検討しょうとすることに、かなりの意味があると思っている。
総務省は2月14日、04年10月1日現在の人口推計を、年代別に分析した人口動向を発表した。これによると90歳以上の人口は初めて100万人を突破している。90歳以上の人口は101万6000人(同9.1%増)で、11万9000人だった80年の約10倍になっているのだ。有志で作ろうとしている80代壮健の会は、この80代を自立した生活が出来ることを目標としている。そして、90代まで生きようじゃないかという目標を掲げ、これが可能になるための行き方・食生活他をともに研鑽しょうとするものである。目標が高いので、満1年ぐらいの意見交換の時間が必要なのだ。
・健康に 80代を 乗り越えて 100万人も 90代が
(10)生涯青春の会の準備会の方向性 (2005年3月27日)
2月17日から80代壮健の会のことを書き始めている。この会の方向性が決まったので少々書き留めて置きたい。ここではあまり記述する機会がなかったが、中高年者福祉協会(NPO法人)の理事長・事務局長と交流があった。日々の映像・癒しの森に高い評価を頂きこの度同協会の理事就任の要請があった。これらのことから私が進めようとしている会をNPO法人中高年者福祉協会内で「80代壮健の会」としてスタートさせることになった。これらの協議過程で意見交換した骨子は以下の通りである。
1、キャッチフレーズ 「呆け老人になるな!」
2、活動の骨子
(1)会の基本的な理念の討議(意見交換)
(2)健康のための運動
(3)食の学習
(4)コミュケーションの学習
4のコミュケーションの学習について意外に思う人もあるかもしれない。しかし、高齢者なって家族とのコミュケーションが破壊されている例があまりにも多いのである。よって、謙虚になって、ゼロからコミュケーションの学習をしようとの意見が多いのである。
・晩年の 幸と不幸を 左右する 家族みんなの コミュケーション
(11)痴呆症になる原因 (2005年3月30日)
生涯青春の会の意見交換のテーマを記述したい。NHKの「ためしてガッテン」の協力者である早期痴呆研究所院長の金子満雄先生のリポートを熟読した。同先生は、20年間に渡り2万人以上の痴呆患者と接してきたのである。この経験の上にたってのメッセージを箇条書きで引用させてもらうと次の通りである。
1、ボケになるかならないかはその人の「生き方」によって左右されます。
2、「どういう人がボケやすいのでしょうか?」と質問されたら、私は迷わず「感性の乏しい人」と答えます。
3、脳は体の筋肉などと同じで、使わなければそのぶん確実に衰えていきます。
4、若いころは仕事一辺倒。そんな人は、特に危ないと言わざるをえません。痴呆患者さんの中にも、実はそういう方がたくさんいます。労働の多くは、案外、動物でも持っている脳の中の低い機能しか使わない作業が多い。
5、周囲とのコミュケーションは痴呆予防のためにとても重要です。とくに都会暮らしでは、隣人と交わる機会が少なく、これがボケの大きな原因になっている。
6、痴呆は大まかに、軽度、中度、重度の段階に区分されます。地方では軽〜中度が多く、都会では重度の割合が高いのです。これは、いかにコミュケーションが痴呆予防にとって大切かを示すデータといえるでしょう。
(NHKためしてガッテン 2004秋号から)
このテーマは引き続き記述する機会を持ちたいと思っている。ボケの原因が生き方と感性であるのであれば、ボケ老人に成るか成らないかは、20代・30代に決まるといっても過言でない。
・その人の 乏しいまでの 感性が 因となってか 脳がボケ行く
(12)老人性痴呆は生活習慣病である(2005年4月4日)
ボケ老人になって、家族に深刻な負担をかけ、家族がお手上げであれば後は公的な施設に入る。ここであらゆる迷惑と負担をかけて死んで行く、これほど醜い人生の総決算はないと思う。3月30日に「ボケ老人になる原因」と題して書いた。これら老人性痴呆は生活習慣病なのである。よって、ボケ老人に成るか成らないかの遠因は、20代・30代の「生き方」にあるのだ。ここで記述したいことは老人性痴呆が生活習慣病なので、早く気がつけば進行予防ができるという。3月31日に書いた金子満雄先生のリポートを再度熟読した。痴呆に関する基本的認識の一部を引用したい。
「専門家であるはずの医療機関ですら、アルツハイマー病と老人性痴呆を混同しているケースが多々見られます。両者は重度まで進めば似ていますが、前者は遺伝子異常の病気で、まず治療は困難。それに比べ、後者は生活習慣病で、早く見つければ進行予防も脳機能改善も可能なのです。私が診療した痴呆患者さん2万7000人のうち、アルツハイマー病はわずか90人で、しかもすべて50歳以下の人たちでした。言い換えれば、90人を除くほとんどの人たちが、本来回復の見込みのある痴呆患者なのです」(ガッテン2004秋号から)
痴呆になっても、早期であれば回復するのだから、痴呆老人にならないような生き方をすれば痴呆老人にはならないのである。
・身体は 使わなければ 衰える 生き方次第で ボケなど無縁
最初に話が出ましたのは、試料(6)の通り昨年2月「百歳まで生きようじゃないか」の会を作らないかとの提案を受けました。しかし、百歳を超えて自立できているかとなるとこれまた大変なことなのです。2003年9月13日の癒しの森に書きましたが、食事など基本的動作を介助なしで行なえる割合が少ないのです。最も厳しいのは会話が出来ない割合が多いのです。百歳以上の人達で、会話をするなど意思の疎通が出来る割合は、男性が58%女性は35%なのです。意思の疎通が出来なくてただ生きているだけでは意味がないと思います。そのような視点から「百歳まで生きようじゃないか」の会は頓挫いたしましました。その後意見交換が進み昨年11月資料(7)の通り「生涯青春の会」としてスタートしようとの意見が集約され今日に至った次第であります。
2ページ以降に資料が12題引用されておりまが、このことに付いて説明を致します。この文章は、エンピツのサイトを利用して日々の映像としてインターネットに公開しているものです(http://
2、参考資料目次
(1)百歳を過ぎてもまだまだ現役 (2004年2月10日)
(2)人に役立つ意識とパワー (2004年2月11日)
(3)百歳でまだまだこれからの平山直八さん(2004年2月12日)
(4)百歳まで元気でいるには (2004年2月13日)
(5)元気で長生き10ヵ条 ( (2004年2月14日)
(6)百歳まで生きようじゃないか!の会 (2004年2月15日)
(7)生涯青春の会のスタートの機運 (2004年11月24日)
(8)会の基本的な理念 (2005年2月20日)
(9)準備会 (2005年3月17日)
(10)会の方向性 (2005年3月27日)
(11)ボケ老人になる原因 (2005年3月30日)
(12)老人性痴呆は生活習慣病である (2005年4月4日)
(1)百歳を過ぎてもまだまだ現役
(2004年2月10日の癒しの森から)
1998年1月18日の「日々の映像」で「百歳でまだまだこれから」と題するエッセイを書いた。この時登場していただいた人は、弁護士の平山直八(1897年生まれ)氏で、エッセイを書いた時すでに101歳であった。この人の語録を引用したい。「まだまだこれからです。もっと社会にお役に立ちたい」であった。
月刊誌「潮」に脚本家であり、相撲フアンで知られる内館牧子のインタビューシリーズ「今日もがぶりより!」という連載がある。連載27回目の3月号は百歳を過ぎてもまだまだ“現役”を続けている飯田深雪さん(1903年生まれ・料理研究家・アートフラワー創始者)が登場していた。多くを記述するだけの紙幅がないので、人生の根幹と思われる。語録を引用したい。「どんな人にもその人独特の能力とか特徴があると思うのです。それを人のために活かすように考えて行動することです」であった。 詳しくは後日に書きたいが、人のために役立とう(大きく言えば社会貢献)という意識があると、人間としてのパワーが増していくのである。
・100歳で まだまだ現役 意気盛ん 無限のパワーの みなもと如何
(2) 人に役立つ意識とパワー
(2004年2月11日の癒しの森から、以下同)
2月10日「人のために役立とう(大きく家が社会貢献)という意識があると、人間としてのパワーが増していく」と書いた。今日はこのことに付いて1998年1月18日に記述した日々の映像から引用したい。
「今年1月10日のアン安全大会で(財)日本心身医学協会所属の飯田国彦氏(心理学博士)の講演を聞く。講演のテーマは「健康と安全の基本」であった。社会に貢献するという意識が人間としてのパワーを増して行くとの論旨であった。・・・・このような生き方をすると、次のようなパターンになるというのだ。
社会貢献の意識と行動――有効ホルモンの分泌――免疫力の向上――体調良好――能力が顕在化していく。
自分のことしか考えていない生活のパターンでは、免疫力の向上はないし、能力も顕在化して来ないというのである。講演の骨子は、60兆の細胞の活性化も30億のDNA情報の顕在化も、その人の生活のパターンによって決まるというものであった。これと同じ視点、論旨を昨年11月30日(この癒しの森では2月8日)「心の働きと生命の暗号」に書いたので、飯田氏の論旨はよく理解できた」
・行動の 理念がパワーの 母なるか 細胞次元に 意識が届く
(3) 百歳でまだまだこれからの平山直八さん
(2004年2月12日)
平山直八さんのことは2月10日に名前の紹介程度に留めた。しかし、この人のことを書いた1998年1月18日の日々の映像を読んでみると、この人の生きる力の凄さに圧倒される。この癒しの森に引用して、改めて平山直八さんを顕彰したい。
「『潮』2月号に元気な百歳の弁護士平山直八さんのことが出ていた。1897年生まれなので百歳を超えている。小学校の教師をしながら、中央大学の夜間部に通い、33歳の時に司法試験に合格、60歳まで教員生活を続け、その後40年間弁護士として活躍している。百歳になった今でも、離婚・相続などの相談に応じている。このほか東京北区で生涯教育奉仕団を作り、老人ホームを訪問して入居者達を励げましたり、いじめや不登校などの教育問題にも懇談会を開くなど第一線で取り組んでいる。
平山さんの語録がある。『まだまだこれからです。もっと社会のお役に立ちたい』と意気軒昂で、その旺盛な活動は衰えを知らないという」
昨日の飯田国彦氏の論旨に基づくと社会貢献という意識と行動が、有効ホルモンを分泌させ免疫力を向上させ全細胞の活性化が計られているのだ。それゆえ、百歳になられても「まだまだこれからです」という意欲が現われるのだろうと思った。
・人のため 命を燃やして 百歳に 人の鏡か 「まだまだこれから」
(短歌は1998年1月18日の日々の映像から)
(4) 百歳まで元気でいるには (2004年2月13日)
2月10日から百歳に関することを書くのは4回目となった。百歳になって元気でいることが、いかに大変なことかを考えてみよう。2003年9月13日の日々の映像で、百歳以上2万人の実情を書いた。詳しくは省略するが、食事など基本的動作を介助なしで行なえる割合は、男性30・9%対して女性は僅か13・6%しかいないのである。
それゆえ、飯田深雪さんや平山直八さんの存在は、驚嘆すべきことなのである。少なくとも、活力がこんこんと湧き出るような生き方をしないと、百歳になって社会で活躍することは不可能なことだと思う。
アインシュタインが含蓄のある言葉を残している。「人は自分以外のもののために生きられるようになって、初めて生のスタートを切る」と。私は1998年1月18日に日々の映像の結びで次のように書いた「自分以外のもののために生きられるようになる・・これを我が人生の最大の課題にしようと思った。そこに初めて気力が溢れる充実の日々が待っているような気がする」と。
・活力が こんこん湧き出る 生き方は アインシュタインの 示す道かな
(5) 元気で長生き10ヵ条 (2004年2月14日)
長寿に関することをもう一回記述したい。NHK朝8時30分から生活ホットモーニングという番組がある。2月9日は「元気で長生き10か条」のタイトルであった。この10か条は後記のメモの通りであるが、2〜10まではおおよそ理解しているように思う。1番の「血液中のアルブミンの値が高い」ことという条件は、耳なれないことなので少々記述したい。
1、血液中のアルブミンの値
東京都老人総合研究所では、在宅で元気に暮らすためには3.8g/dl以下は要注意、必要と指導しています。血液中のアルブミンが少ないと(低たんぱく状態)、感染症にかかりやすい、ウツ状態になりやすいなど、問題が発生します。
2、血液中のアルブミン値を維持するために
動物性のたんぱく質1(40グラム):植物性のたんぱく質1(40グラム)を摂取しながら、バランスの良い食生活を心がけましょう。(生活ホットモーニングのページから) イメージに薄かったのは4の「自分は健康だ」と思っている人が長生きをするというのだ。これは明らかに「気」が作用している。次に社会参加が活発な人が長寿であることは、補足するまでもないことだ。
・長生きの 秘訣は何かと 尋ねると 気の整えと 食のバランス
メモ、元気で長生き10か条(ホットモーニングから)
1、血液中のアルブミンの値が高い
2、血液中の総コレステロール値は高すぎず低すぎず
3、血圧は高すぎず低すぎず
4、「自分は健康だ」と思っている
5、足が丈夫である
6、短期の記憶力がよい
7、太り方は中くらい
8、タバコを吸わない
9、お酒は飲みすぎない
10、社会参加が活発である
(6) 百歳まで生きようじゃないか!の会 (2004年2月15日)
ここのところ日々の映像の読者と懇談する機会が多くあった。読者の一人から「百歳まで生きようじゃないか!の会」を作らないかとの提案を受ける。この提案者は私が2月10日から以下の通り長寿に関する記述を読んでのことであった。
2月10日 百歳を過ぎてもまだまだ現役
2月11日 人に役立つ意識とパワー
2月12日 百歳でまだまだこれからの平山直八さん
2月13日 百歳まで元気でいるには
2月14日 元気で長生き10か条
ともかく百歳まで元気で生きることは容易なことでない。この会を作るとしたらどのような活動をすればよいのかとの意見交換をする。ここで多少書き出すと次の通りだ。
1、長寿のための食を徹底して学習をする。
2、生きるパワーを増すための学習をする。
3、病気にならないための学習
4、日々の映像・癒しの森を題材とした討論会を開く(会話の機会を作る)
5、百歳まで生きようという「気」のない人はお断り。
6、学習の講師は会のメンバーから輩出していく。(講師は全てボランテァ)
7、会のメンバーは良き友人となって、激励しあっていく。
この会が出来るかどうかは、今日の段階では分からない。趣旨に賛同する人たちと意見交換を積み上げて行きたいと思っている。
(7)生涯青春の会スタートの機運 (2004年11月24日)
今年2月10日から14日まで「百歳を過ぎてもまだまだ現役」など長寿のことを5日間連続して書いた。これを読んだ知人から「百歳までいきようじゃないか!の会」を作らないかとの提案を受ける。ともかく百歳まで元気で生きることは容易なことでない。100歳は余りにハードルが高く現実的ではない。8月3日友人と意見交換したが、「80代壮健の会」(仮称)にしたらどうかとの案となり、以下の項目の意見交換となる。
・会の加入年齢は特に定めない
・長寿のための食の学習をする。
・病気にならないための学習をする。
・日々の映像・癒しの森を題材として会話の機会を作る。
・会のメンバーは良き友人となって、激励し合っていく。
・話し合い 刺激しあって 80代 自分の足で 目指せ壮健
(2004年8月3日の癒しの森から)
(8)生涯青春の会の基本的な理念 (2005年2月20日)
2月17日80代壮健の会に参加したいという60代の婦人三人と懇談した。私の目指すこの会は単なる慰め会・娯楽の会ではないのである。一定の理念を持って、共に行動し励ましあって80代を元気で過ごそうというものである。この会の基本的な理念が一致する人から加入していただこうと考えている。癒しの森で長寿に関して以下の記述を行なったが、この内容が会の基本的な理念になればよいと思っている。理念の骨子は、2004年2月11日に書いた社会貢献の意識と行動、2004年2月13日に書いたアインシュタインの「人は自分以外のもののために生きられるようになって、初めて生のスタートを切る」などである。
・ 2004年02月10日 百歳をすぎてもまだまだ現役
・ 2004年02月11日 人に役立つ意識とパワー
・ 2004年02月12日 百歳でまだまだこれからの平山直八さん
・ 2004年02月13日 百歳まで元気でいるには
・ 2004年02月14日 元気で長生き10か条
・ 2004年02月15日 百歳まで生きようじゃないかの会
・生き方が パワーを生み出す この原理 行動起こして 生へのスタート
(9)生涯青春の会の準備会 (2005年3月17日)
2月17日と2月20日に80代壮健の会のことを書いた。その後この会を作ろうと賛意を示している人たちと時折意見交換をしている。これらの意見を少しずつまとめて、5月頃から月1回の発足準備会を開くことになった。この準備会で様々な意見を交わし、合意点の整理を進め2006年4月ごろ正式に「80代壮健の会」をスタートしたいと思っている。随分とスローでないかとの意見のあるのだが、自分たちが作ろうとする会をあらゆる角度から検討しょうとすることに、かなりの意味があると思っている。
総務省は2月14日、04年10月1日現在の人口推計を、年代別に分析した人口動向を発表した。これによると90歳以上の人口は初めて100万人を突破している。90歳以上の人口は101万6000人(同9.1%増)で、11万9000人だった80年の約10倍になっているのだ。有志で作ろうとしている80代壮健の会は、この80代を自立した生活が出来ることを目標としている。そして、90代まで生きようじゃないかという目標を掲げ、これが可能になるための行き方・食生活他をともに研鑽しょうとするものである。目標が高いので、満1年ぐらいの意見交換の時間が必要なのだ。
・健康に 80代を 乗り越えて 100万人も 90代が
(10)生涯青春の会の準備会の方向性 (2005年3月27日)
2月17日から80代壮健の会のことを書き始めている。この会の方向性が決まったので少々書き留めて置きたい。ここではあまり記述する機会がなかったが、中高年者福祉協会(NPO法人)の理事長・事務局長と交流があった。日々の映像・癒しの森に高い評価を頂きこの度同協会の理事就任の要請があった。これらのことから私が進めようとしている会をNPO法人中高年者福祉協会内で「80代壮健の会」としてスタートさせることになった。これらの協議過程で意見交換した骨子は以下の通りである。
1、キャッチフレーズ 「呆け老人になるな!」
2、活動の骨子
(1)会の基本的な理念の討議(意見交換)
(2)健康のための運動
(3)食の学習
(4)コミュケーションの学習
4のコミュケーションの学習について意外に思う人もあるかもしれない。しかし、高齢者なって家族とのコミュケーションが破壊されている例があまりにも多いのである。よって、謙虚になって、ゼロからコミュケーションの学習をしようとの意見が多いのである。
・晩年の 幸と不幸を 左右する 家族みんなの コミュケーション
(11)痴呆症になる原因 (2005年3月30日)
生涯青春の会の意見交換のテーマを記述したい。NHKの「ためしてガッテン」の協力者である早期痴呆研究所院長の金子満雄先生のリポートを熟読した。同先生は、20年間に渡り2万人以上の痴呆患者と接してきたのである。この経験の上にたってのメッセージを箇条書きで引用させてもらうと次の通りである。
1、ボケになるかならないかはその人の「生き方」によって左右されます。
2、「どういう人がボケやすいのでしょうか?」と質問されたら、私は迷わず「感性の乏しい人」と答えます。
3、脳は体の筋肉などと同じで、使わなければそのぶん確実に衰えていきます。
4、若いころは仕事一辺倒。そんな人は、特に危ないと言わざるをえません。痴呆患者さんの中にも、実はそういう方がたくさんいます。労働の多くは、案外、動物でも持っている脳の中の低い機能しか使わない作業が多い。
5、周囲とのコミュケーションは痴呆予防のためにとても重要です。とくに都会暮らしでは、隣人と交わる機会が少なく、これがボケの大きな原因になっている。
6、痴呆は大まかに、軽度、中度、重度の段階に区分されます。地方では軽〜中度が多く、都会では重度の割合が高いのです。これは、いかにコミュケーションが痴呆予防にとって大切かを示すデータといえるでしょう。
(NHKためしてガッテン 2004秋号から)
このテーマは引き続き記述する機会を持ちたいと思っている。ボケの原因が生き方と感性であるのであれば、ボケ老人に成るか成らないかは、20代・30代に決まるといっても過言でない。
・その人の 乏しいまでの 感性が 因となってか 脳がボケ行く
(12)老人性痴呆は生活習慣病である(2005年4月4日)
ボケ老人になって、家族に深刻な負担をかけ、家族がお手上げであれば後は公的な施設に入る。ここであらゆる迷惑と負担をかけて死んで行く、これほど醜い人生の総決算はないと思う。3月30日に「ボケ老人になる原因」と題して書いた。これら老人性痴呆は生活習慣病なのである。よって、ボケ老人に成るか成らないかの遠因は、20代・30代の「生き方」にあるのだ。ここで記述したいことは老人性痴呆が生活習慣病なので、早く気がつけば進行予防ができるという。3月31日に書いた金子満雄先生のリポートを再度熟読した。痴呆に関する基本的認識の一部を引用したい。
「専門家であるはずの医療機関ですら、アルツハイマー病と老人性痴呆を混同しているケースが多々見られます。両者は重度まで進めば似ていますが、前者は遺伝子異常の病気で、まず治療は困難。それに比べ、後者は生活習慣病で、早く見つければ進行予防も脳機能改善も可能なのです。私が診療した痴呆患者さん2万7000人のうち、アルツハイマー病はわずか90人で、しかもすべて50歳以下の人たちでした。言い換えれば、90人を除くほとんどの人たちが、本来回復の見込みのある痴呆患者なのです」(ガッテン2004秋号から)
痴呆になっても、早期であれば回復するのだから、痴呆老人にならないような生き方をすれば痴呆老人にはならないのである。
・身体は 使わなければ 衰える 生き方次第で ボケなど無縁
|
|
|
|
|
|
|
|
NPO法人生涯青春の会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
NPO法人生涯青春の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90063人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208309人
- 3位
- 酒好き
- 170692人