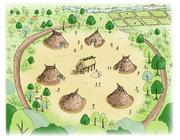|
|
|
|
コメント(27)
管理人としてではなく、一投票者の気持ちでかきますが、
地元をプッシュしたくなる気持ちがやはりあります。
正しく方角、距離を読むと、沖縄にたどり着くのにだれも沖縄説をいわない。これは無意識の差別。。。。などどいうかたも沖縄にはいらっしゃるわけですが、
沖縄はとりあえず可能性低いのです。 3世紀の遺跡が少ないのです。魏志倭人伝にもし誇大広告されても元がしょぼいのでは嘘がばれます。
うーんどうだろう。 魏志倭人伝は「どこが間違ってかかれているか」「どこを正しく伝えたかったか。」「どこを嘘で書かなくてはならなかったか」この3点に気をつけて考える必要があるのでは。
南至邪馬台国女王之所都水行十日陸行一月
沖縄説、距離方角をぼやーっとなんとなーく見ると南・・そうか、沖縄にいきそう。。。ということでよろしいかな?
でもこれは私の一票ではないです。
私の一票はのちほど。
地元をプッシュしたくなる気持ちがやはりあります。
正しく方角、距離を読むと、沖縄にたどり着くのにだれも沖縄説をいわない。これは無意識の差別。。。。などどいうかたも沖縄にはいらっしゃるわけですが、
沖縄はとりあえず可能性低いのです。 3世紀の遺跡が少ないのです。魏志倭人伝にもし誇大広告されても元がしょぼいのでは嘘がばれます。
うーんどうだろう。 魏志倭人伝は「どこが間違ってかかれているか」「どこを正しく伝えたかったか。」「どこを嘘で書かなくてはならなかったか」この3点に気をつけて考える必要があるのでは。
南至邪馬台国女王之所都水行十日陸行一月
沖縄説、距離方角をぼやーっとなんとなーく見ると南・・そうか、沖縄にいきそう。。。ということでよろしいかな?
でもこれは私の一票ではないです。
私の一票はのちほど。
古代史に関しては素人ですが、北九州説に一票、ですかね。
アマテラス=卑弥呼説を軸に、その子孫が神武東征を行った、というのがなんかロマンがあるので(笑)。
伝説と言える期間の天皇の異常な長寿と在位期間を誇張と考え、有史以降の天皇の平均在位期間から伝説期の天皇在位期間を短縮すると、ちょうど神武天皇の数代前くらいが、いわゆる魏志倭人伝の卑弥呼の記述の時期とかなり近いというのも興味深い話です。
また神功皇后(実在しない架空人物という説が有力らしいですが)=卑弥呼ととらえて、その子応神天皇の大和入りも神武東征とかぶるところがある、と言う説も北九州を押したい私です。
あくまで「そっちの方がロマンがあるかな」という程度で根拠は無いんですけど(^^;)。
ちなみに私は中部出身で、一時期岡山にいただけなので、近畿にも北九州にも「地元だから」といた贔屓目はありません。
あと、正史三国志は日本語訳ですがすべてそろえてますので、魏書の記述を素直にたどると南の海にいってしまうのも知ってます(沖縄に着くかどうかは知りませんけど)。
これはよく、北九州説は「単位を間違えている、距離を誇張している」、畿内説は「南と東を間違えている」ととらえてますね。
どちらが正しいのか、それとも沖縄なのか、どうして魏書の記述はああなのかは私には分かりませんが・・・。
ちなみに「どちらが優位か」と言われれば、
今は確か畿内説の方が学者が多いんじゃありませんでしたっけ。
アマテラス=卑弥呼説を軸に、その子孫が神武東征を行った、というのがなんかロマンがあるので(笑)。
伝説と言える期間の天皇の異常な長寿と在位期間を誇張と考え、有史以降の天皇の平均在位期間から伝説期の天皇在位期間を短縮すると、ちょうど神武天皇の数代前くらいが、いわゆる魏志倭人伝の卑弥呼の記述の時期とかなり近いというのも興味深い話です。
また神功皇后(実在しない架空人物という説が有力らしいですが)=卑弥呼ととらえて、その子応神天皇の大和入りも神武東征とかぶるところがある、と言う説も北九州を押したい私です。
あくまで「そっちの方がロマンがあるかな」という程度で根拠は無いんですけど(^^;)。
ちなみに私は中部出身で、一時期岡山にいただけなので、近畿にも北九州にも「地元だから」といた贔屓目はありません。
あと、正史三国志は日本語訳ですがすべてそろえてますので、魏書の記述を素直にたどると南の海にいってしまうのも知ってます(沖縄に着くかどうかは知りませんけど)。
これはよく、北九州説は「単位を間違えている、距離を誇張している」、畿内説は「南と東を間違えている」ととらえてますね。
どちらが正しいのか、それとも沖縄なのか、どうして魏書の記述はああなのかは私には分かりませんが・・・。
ちなみに「どちらが優位か」と言われれば、
今は確か畿内説の方が学者が多いんじゃありませんでしたっけ。
弥生さんに賛成。私ももちろん畿内派です。現在、色々な考古学的発見によって弥生の年代がどんどん遡っており、箸墓も3世紀中頃の築造であって何ら不思議はありません。私は邪馬台国は天理・桜井市にまたがる纒向遺跡周辺であったと考えています。箸墓が発掘できれば、案外「親魏倭王」の金印が出てきそうな気もします。
九州説の人たちは、魏志倭人伝の字句をひねり回して意味のない議論をしていると思いますよ。特に問題となる「南へ水行10日・陸行1月で、女王の都の邪馬台国に至る」という記述ですが、古代から中国人の地理観では日本列島は九州を頭にして南に伸びているというもの。これは元の時代(鎌倉時代)ですらそうです。単純に北九州から瀬戸内(または山陰)の経路で畿内に至る道筋です。
九州説の人たちは、魏志倭人伝の字句をひねり回して意味のない議論をしていると思いますよ。特に問題となる「南へ水行10日・陸行1月で、女王の都の邪馬台国に至る」という記述ですが、古代から中国人の地理観では日本列島は九州を頭にして南に伸びているというもの。これは元の時代(鎌倉時代)ですらそうです。単純に北九州から瀬戸内(または山陰)の経路で畿内に至る道筋です。
モンガ様
中国人の地理観は、「九州を頭にして南に伸びている」という主張の根拠とされる地図は朝鮮のものであり、中国のものではありません。1980年代の研究水準ならともかく、現時点では、その地図を根拠として古代人の地理観を求めるのは誤りです。
http://www.mars.dti.ne.jp/~techno/review/review2.htm
3世紀の中国人がどのような日本列島観を抱いていたかということを明確に示す資料は存在しません。
むしろ、陳寿らがその報告を参考にした魏使は初めて日本列島を調査する立場にあったわけで、先入観に方位感覚をゆがめられることはなかった、と考えるべきでしょう。
したがって、邪馬台国畿内説の根拠に方位観を持ち出すのはかえって説得力を奪うものになりかねません。
魏志倭人伝には邪馬台国の葬制について、「棺あれど槨なし」とあり(古墳の石室はれっきとした「槨」です)、前方後円墳体制以前の地方の状況を示しているものとも読めます。
また、年輪年代測定も現在の日本では、ただ一つの機関のただ一人の研究者が独占している状況で、クロス・チェックがなされているとはいえません。
したがって、3世紀の時点なら、中国と国交を持っていた地域政権が北部九州にあった可能性は十分に残っているものと考えております。
中国人の地理観は、「九州を頭にして南に伸びている」という主張の根拠とされる地図は朝鮮のものであり、中国のものではありません。1980年代の研究水準ならともかく、現時点では、その地図を根拠として古代人の地理観を求めるのは誤りです。
http://www.mars.dti.ne.jp/~techno/review/review2.htm
3世紀の中国人がどのような日本列島観を抱いていたかということを明確に示す資料は存在しません。
むしろ、陳寿らがその報告を参考にした魏使は初めて日本列島を調査する立場にあったわけで、先入観に方位感覚をゆがめられることはなかった、と考えるべきでしょう。
したがって、邪馬台国畿内説の根拠に方位観を持ち出すのはかえって説得力を奪うものになりかねません。
魏志倭人伝には邪馬台国の葬制について、「棺あれど槨なし」とあり(古墳の石室はれっきとした「槨」です)、前方後円墳体制以前の地方の状況を示しているものとも読めます。
また、年輪年代測定も現在の日本では、ただ一つの機関のただ一人の研究者が独占している状況で、クロス・チェックがなされているとはいえません。
したがって、3世紀の時点なら、中国と国交を持っていた地域政権が北部九州にあった可能性は十分に残っているものと考えております。
そもそも古代の中国人が日本列島の形について認識していたかどうかが疑問なのです。「日本」を江南のすぐ東に持っていく地理認識があった、との推定ができますが、その古代中国人のイメージする「日本」の九州や本州の区別があったはずだ、というのは日本列島の形を知っている現代日本人の脳内補完でしかありません。
中国に伝わった明代以前の地図では、日本や倭国の形を明確に描いたものはありません。海上にただ丸を書いてその中に国名を入れたりする程度です。 「日本」「倭国」「扶桑」を海上に並べた地図もあります。
中国には、3世紀・西晋代の地図に基づいて8世紀・唐代に作られたという地図も残っていますが、その範囲は中国大陸に限られており、日本列島は含まれていません。
古地図で、日本列島が九州を頭にして南に伸びている例としては1402年、朝鮮李朝で作られた「混一彊理歴代国都之図 (こんいちきょうりれきだいこくとのず)」があります(京都・龍谷大学蔵)。
この地図については、1988年、弘中芳男氏が、中国で作られた大陸の地図に、当時の日本地図で西を上にして作成されたもの(この時代、日本では地図は必ず北を上にするものとは限られていませんでした)を接合したものであることを考証しています。
弘中氏の著書『古地図と邪馬台国』は現在入手困難ですが、
安本美典氏がその要点をまとめているので参照してください。
http://yamatai.cside.com/tousennsetu/konitu.htm
龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」と同系統の古地図で日本につたわったものはいずれも、日本列島を九州を西、坂東を東として東西に伸びる島として描いています。おそらく龍谷大学蔵の「混一彊理歴代国都之図 」は地図作成の試行錯誤の結果なのでしょう。として作られたものなのでしょう。
龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」は西はアフリカ・ヨーロッパ、東は朝鮮半島、日本列島までを描いた(当時の朝鮮人の世界観による〉世界地図ですが、中央には巨大な中国大陸があり、西のアフリカ大陸、東の朝鮮半島がほぼ同じ大きさに描かれています。この地図の全体を見ると、その巨大な朝鮮半島の東に東西に伸びる島を描きいれる余地はなく、日本列島を朝鮮半島の南で南北に伸びる島として描くしかなかったことがよくわかります。その場合、日本列島各地と朝鮮半島との距離感を表わすには、朝鮮半島南端に近い九州の方を上にするしかなかったでしょう。
http://www.mars.dti.ne.jp/~techno/review/review2.htm
龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」は中国の地図ではないばかりか、朝鮮の地図としても特異なものです。これから70年ほど後に朝鮮李朝で編纂された『海東諸国記』所収の地図でも、日本列島は九州を西にして東西に伸びる形で描かれています。
多くの邪馬台国関係書籍に出てくる「九州を頭にして南に伸びている」地図は、実はこの一点の地図に基づき、孫引きされているものにすぎません。
以上、龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」は15世紀初頭の朝鮮半島という時代・地域の認識を反映したもので、古代人の方位観とはまったく関係ありません。
魏使が「南に行く」と証言している時には、現代人の空想上(それも朝鮮李朝の地図を根拠とした)の地図での「南」ではなく、本当に南に進んだ、と考えるのが妥当でしょう。
邪馬台国畿内説の根拠として持ち出すのはつつしんだ方がよいでしょう。
中国に伝わった明代以前の地図では、日本や倭国の形を明確に描いたものはありません。海上にただ丸を書いてその中に国名を入れたりする程度です。 「日本」「倭国」「扶桑」を海上に並べた地図もあります。
中国には、3世紀・西晋代の地図に基づいて8世紀・唐代に作られたという地図も残っていますが、その範囲は中国大陸に限られており、日本列島は含まれていません。
古地図で、日本列島が九州を頭にして南に伸びている例としては1402年、朝鮮李朝で作られた「混一彊理歴代国都之図 (こんいちきょうりれきだいこくとのず)」があります(京都・龍谷大学蔵)。
この地図については、1988年、弘中芳男氏が、中国で作られた大陸の地図に、当時の日本地図で西を上にして作成されたもの(この時代、日本では地図は必ず北を上にするものとは限られていませんでした)を接合したものであることを考証しています。
弘中氏の著書『古地図と邪馬台国』は現在入手困難ですが、
安本美典氏がその要点をまとめているので参照してください。
http://yamatai.cside.com/tousennsetu/konitu.htm
龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」と同系統の古地図で日本につたわったものはいずれも、日本列島を九州を西、坂東を東として東西に伸びる島として描いています。おそらく龍谷大学蔵の「混一彊理歴代国都之図 」は地図作成の試行錯誤の結果なのでしょう。として作られたものなのでしょう。
龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」は西はアフリカ・ヨーロッパ、東は朝鮮半島、日本列島までを描いた(当時の朝鮮人の世界観による〉世界地図ですが、中央には巨大な中国大陸があり、西のアフリカ大陸、東の朝鮮半島がほぼ同じ大きさに描かれています。この地図の全体を見ると、その巨大な朝鮮半島の東に東西に伸びる島を描きいれる余地はなく、日本列島を朝鮮半島の南で南北に伸びる島として描くしかなかったことがよくわかります。その場合、日本列島各地と朝鮮半島との距離感を表わすには、朝鮮半島南端に近い九州の方を上にするしかなかったでしょう。
http://www.mars.dti.ne.jp/~techno/review/review2.htm
龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」は中国の地図ではないばかりか、朝鮮の地図としても特異なものです。これから70年ほど後に朝鮮李朝で編纂された『海東諸国記』所収の地図でも、日本列島は九州を西にして東西に伸びる形で描かれています。
多くの邪馬台国関係書籍に出てくる「九州を頭にして南に伸びている」地図は、実はこの一点の地図に基づき、孫引きされているものにすぎません。
以上、龍谷大学蔵「混一彊理歴代国都之図 」は15世紀初頭の朝鮮半島という時代・地域の認識を反映したもので、古代人の方位観とはまったく関係ありません。
魏使が「南に行く」と証言している時には、現代人の空想上(それも朝鮮李朝の地図を根拠とした)の地図での「南」ではなく、本当に南に進んだ、と考えるのが妥当でしょう。
邪馬台国畿内説の根拠として持ち出すのはつつしんだ方がよいでしょう。
引き続き私見です。
「倭人伝に南と書いてあるのだから南だ」ということであれば、その後に書いてある「水行10日・陸行1月」という記述も正しいと認めないといけません。そうしたらどうやっても九州の中には納まらなくなりますね。(これは帯方郡からの行程数だとか言わなくてはならなくなります。)明らかに魏志倭人伝の行程記述にはどこか間違いがあるのです。三国史が編まれた時までに、何回か記録の書き写しもあっただろうし、その時写し間違いもあったかもしれません。また、編者の陳寿の校正もあったはずです。
ここで注意すべきは魏史倭人伝の中の以下の記述、「その道里を計るに当に会稽東治(福建省)の東にあるべし」と書いてあります。また、倭国の風俗を記したところで最後に「有無する所、與耳、朱崖(海南島)と同じ」とも書いてあります。明らかに陳寿は倭国を実際の位置より南だと考えていたのです。それが、私が「三国史の編者もそういう認識をもって書いている可能性が高い」と言う理由です。
偽史学博士さん、あなたは年輪年代法のことを、「ただ一つの機関のただ一人の研究者が独占している状況で、クロス・チェックがなされているとはいえません」と書かれていますが、年輪年代法は現時点で最も信頼できる科学的な年代測定法だと私は思います。邪馬台国の所在地論は、近畿の弥生の年代が確定した後、遺跡の発掘成果から分かる3世紀前半の日本列島の人口分布が確定しないと結論は出ないと思います。
「倭人伝に南と書いてあるのだから南だ」ということであれば、その後に書いてある「水行10日・陸行1月」という記述も正しいと認めないといけません。そうしたらどうやっても九州の中には納まらなくなりますね。(これは帯方郡からの行程数だとか言わなくてはならなくなります。)明らかに魏志倭人伝の行程記述にはどこか間違いがあるのです。三国史が編まれた時までに、何回か記録の書き写しもあっただろうし、その時写し間違いもあったかもしれません。また、編者の陳寿の校正もあったはずです。
ここで注意すべきは魏史倭人伝の中の以下の記述、「その道里を計るに当に会稽東治(福建省)の東にあるべし」と書いてあります。また、倭国の風俗を記したところで最後に「有無する所、與耳、朱崖(海南島)と同じ」とも書いてあります。明らかに陳寿は倭国を実際の位置より南だと考えていたのです。それが、私が「三国史の編者もそういう認識をもって書いている可能性が高い」と言う理由です。
偽史学博士さん、あなたは年輪年代法のことを、「ただ一つの機関のただ一人の研究者が独占している状況で、クロス・チェックがなされているとはいえません」と書かれていますが、年輪年代法は現時点で最も信頼できる科学的な年代測定法だと私は思います。邪馬台国の所在地論は、近畿の弥生の年代が確定した後、遺跡の発掘成果から分かる3世紀前半の日本列島の人口分布が確定しないと結論は出ないと思います。
モンガ様> なるほどね!確かにそれは言えますね。物さえでてきてくれれば、同位体やほかの年代方で年代を割り出すことができるのですがね〜。
ずっと気になっているのは見晴台が、九州からはでてきてるけど、近畿では未だ発見されてないですよね(日本に長らく不在だったのでもしかしたら私間違ってるかも・・・)?まぁそんなこともあって私は邪馬台国は思ったより大きな範囲だったのではと思うのですが、仮に卑弥呼の墓がでてきたとしても、邪馬台国の社会性がちゃんと分からない限り、どのぐらいの範囲で広がっていたのか確定するのは難しいですね?
そもそも魏志倭人伝じたい、今残っているのがコピーで、それぞれ違う漢字を使っているみたいなので、その解釈の時点で大きな誤差も生まれてくるはず。そうなると邪馬台国を知る手段は遺跡の発見に後は頼るしかないのでしょうか?
ずっと気になっているのは見晴台が、九州からはでてきてるけど、近畿では未だ発見されてないですよね(日本に長らく不在だったのでもしかしたら私間違ってるかも・・・)?まぁそんなこともあって私は邪馬台国は思ったより大きな範囲だったのではと思うのですが、仮に卑弥呼の墓がでてきたとしても、邪馬台国の社会性がちゃんと分からない限り、どのぐらいの範囲で広がっていたのか確定するのは難しいですね?
そもそも魏志倭人伝じたい、今残っているのがコピーで、それぞれ違う漢字を使っているみたいなので、その解釈の時点で大きな誤差も生まれてくるはず。そうなると邪馬台国を知る手段は遺跡の発見に後は頼るしかないのでしょうか?
モンガ様
今までのは「元の時代の地理観」というものを持ち出されたことに対するレスです。
陳寿が(そして同時代の中国人が)倭国全体を現代人の認識より南とみなしていたということは否定しません。ただしそれは「九州を頭に南に伸びていた」という認識とは必ずしも一致しません。
「会稽東冶」については「その道里を計るに」との判断の根拠が示されています。これは「郡より一万二千余里」と対にして考えるべきものです。行程記事では郡から伊都国までにすでに1万500余里を費やしています。これなら九州島そのものが
「会稽東冶の東」とみなしうるところと認識されていたとしておかしくはないでしょう。
陳寿は魏使の証言を直接聞いたわけではないことは承知しております(陳寿の直接の典拠は『魏略』である可能性が高いでしょう)。しかし倭国にいたった魏使がいた以上、その報告が史料として用いられているとみなすのはむしろ自然ではないでしょうか。
ただ、南北に伸びているとみなすににしろ、東西に伸びているとみなすにしろ、陳寿が倭国を長く伸びた列島として認識していたはず、という認識そのものが現代人の偏見によりものであることを指摘したのです。
: Kobayashi 様
私は年輪年代測定法そのものを否定しているわけではありません。日本における年輪年代測定法の現状について警戒しているだけです。
毎度長くなって申し訳ありません。また、投票形式でという本トピックの趣旨とも外れるので、議論はまた別の場で、ということで如何でしょうか。
今までのは「元の時代の地理観」というものを持ち出されたことに対するレスです。
陳寿が(そして同時代の中国人が)倭国全体を現代人の認識より南とみなしていたということは否定しません。ただしそれは「九州を頭に南に伸びていた」という認識とは必ずしも一致しません。
「会稽東冶」については「その道里を計るに」との判断の根拠が示されています。これは「郡より一万二千余里」と対にして考えるべきものです。行程記事では郡から伊都国までにすでに1万500余里を費やしています。これなら九州島そのものが
「会稽東冶の東」とみなしうるところと認識されていたとしておかしくはないでしょう。
陳寿は魏使の証言を直接聞いたわけではないことは承知しております(陳寿の直接の典拠は『魏略』である可能性が高いでしょう)。しかし倭国にいたった魏使がいた以上、その報告が史料として用いられているとみなすのはむしろ自然ではないでしょうか。
ただ、南北に伸びているとみなすににしろ、東西に伸びているとみなすにしろ、陳寿が倭国を長く伸びた列島として認識していたはず、という認識そのものが現代人の偏見によりものであることを指摘したのです。
: Kobayashi 様
私は年輪年代測定法そのものを否定しているわけではありません。日本における年輪年代測定法の現状について警戒しているだけです。
毎度長くなって申し訳ありません。また、投票形式でという本トピックの趣旨とも外れるので、議論はまた別の場で、ということで如何でしょうか。
Kobayashi様
魏志倭人伝に記された楼閣を思わせる遺跡は佐賀県の吉野ヶ里遺跡にあります。
奈良県の唐子・鍵遺跡からは楼閣を描いた土器が出ていますが、楼閣そのものの跡は見つかっていません。
鳥取県の妻木晩田遺跡から「楼閣」が出たという報道が一時ありましたが、これは間違いでした。
ただし、吉野ヶ里遺跡の「楼閣」も邪馬台国時代よりは前のものですぐに関連付けるわけにはいきません。
今のところは邪馬台国時代を弥生時代終末期におくにしろ、古墳時代の開始期におくにしろ、舶載鏡の大量副葬例や、鉄器、絹製品の出土件数などから、まだ北部九州が優勢が優勢だと考えております。
したがって投票形式でいうなら私は北部九州(筑後平野・菊池平野)に一票です。
しかし邪馬台国が九州にあったにしても、その後の前方後円墳体制形成が畿内主導で進んだことは間違いないものと考えております。
魏志倭人伝に記された楼閣を思わせる遺跡は佐賀県の吉野ヶ里遺跡にあります。
奈良県の唐子・鍵遺跡からは楼閣を描いた土器が出ていますが、楼閣そのものの跡は見つかっていません。
鳥取県の妻木晩田遺跡から「楼閣」が出たという報道が一時ありましたが、これは間違いでした。
ただし、吉野ヶ里遺跡の「楼閣」も邪馬台国時代よりは前のものですぐに関連付けるわけにはいきません。
今のところは邪馬台国時代を弥生時代終末期におくにしろ、古墳時代の開始期におくにしろ、舶載鏡の大量副葬例や、鉄器、絹製品の出土件数などから、まだ北部九州が優勢が優勢だと考えております。
したがって投票形式でいうなら私は北部九州(筑後平野・菊池平野)に一票です。
しかし邪馬台国が九州にあったにしても、その後の前方後円墳体制形成が畿内主導で進んだことは間違いないものと考えております。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
弥生時代を考える 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
弥生時代を考えるのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6475人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19252人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208306人