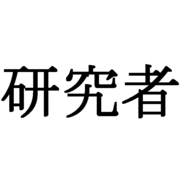はじめまして。
京都で芸術大学に通っております。
専攻(というより研究内容)は、西洋美術史(美学含む)です。
とは言え、学部生ですので[研究者]のコミュにいること自体
図々しいのですが、みなさまのように何かに必死に打ち込めたらと思っています。
院には経済的な理由でいけないので、せめて卒業論文で自分が納得いくようにと研究してます。
私の学科は、二年生と三年生で進級論文を書き
四年生で卒業論文を書きます。
卒論の字数制限は12000〜15600字です。
論文に関しての基本的なルールは踏まえて書いていますが、ちょっとしたニュアンスに困っています。
■世間では出版されていない資料を、草稿段階で知人の学芸員から手に入れた。指導教官は論文内で謝辞を述べるべき、とアドヴァイスをくれましたが、院生でもないのに、なんだかとても恥ずかしいというか、学部生の分際で序論に謝辞など混ぜてもいいのでしょうか?
美術史家はあたりまえのように謝辞を述べますが、自信がありません。
何か柔らかいアドヴァイスをいただけたら嬉しいです。
京都で芸術大学に通っております。
専攻(というより研究内容)は、西洋美術史(美学含む)です。
とは言え、学部生ですので[研究者]のコミュにいること自体
図々しいのですが、みなさまのように何かに必死に打ち込めたらと思っています。
院には経済的な理由でいけないので、せめて卒業論文で自分が納得いくようにと研究してます。
私の学科は、二年生と三年生で進級論文を書き
四年生で卒業論文を書きます。
卒論の字数制限は12000〜15600字です。
論文に関しての基本的なルールは踏まえて書いていますが、ちょっとしたニュアンスに困っています。
■世間では出版されていない資料を、草稿段階で知人の学芸員から手に入れた。指導教官は論文内で謝辞を述べるべき、とアドヴァイスをくれましたが、院生でもないのに、なんだかとても恥ずかしいというか、学部生の分際で序論に謝辞など混ぜてもいいのでしょうか?
美術史家はあたりまえのように謝辞を述べますが、自信がありません。
何か柔らかいアドヴァイスをいただけたら嬉しいです。
|
|
|
|
コメント(15)
■みなさま、ご親切にありがとうございます■
トピ立ち上げ後、その資料を提供してくださった学芸員の方に
連絡をとり、謝辞でお名前をだしてもよろしいですかと伺いました。
非常に謙遜なさって
「出版予定の草稿とはいえ、荒訳だし、文献と言うよりは引用資料として文中で使っていいですよ」
とのことでした。
荒訳だろうと、英語文献からっきしな私が非常に助けられたことは確かなので、みなさまのアドヴァイスどおり謝辞でお礼を述べたいと思います。
今まで、結構、さまざまな文献を読んできましたが
美術系の文献はまえがきのところに付随して謝辞が述べられています。
なので、本文に入る前にまず謝辞を述べて、序論を立てようと思います。
みさなん、本当にご親切にありがとうございました。
トピ立ち上げ後、その資料を提供してくださった学芸員の方に
連絡をとり、謝辞でお名前をだしてもよろしいですかと伺いました。
非常に謙遜なさって
「出版予定の草稿とはいえ、荒訳だし、文献と言うよりは引用資料として文中で使っていいですよ」
とのことでした。
荒訳だろうと、英語文献からっきしな私が非常に助けられたことは確かなので、みなさまのアドヴァイスどおり謝辞でお礼を述べたいと思います。
今まで、結構、さまざまな文献を読んできましたが
美術系の文献はまえがきのところに付随して謝辞が述べられています。
なので、本文に入る前にまず謝辞を述べて、序論を立てようと思います。
みさなん、本当にご親切にありがとうございました。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
研究者 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
研究者のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90065人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208324人
- 3位
- 酒好き
- 170697人