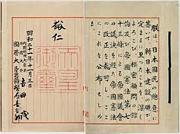|
|
|
|
コメント(13)
前文は、次の一カ所を除き現行前文を踏襲している。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」の最後「信頼して」を「期待して」に変更。
信頼しても野心や悪意のある国を武力行使を止められないからせいぜい「期待して」とすべきであり、信頼にたりないから9条を改正して「自衛軍」を持つべきだという論理である。
それは法学的には間違ってはいまい。
しかし、前文というのは新たな改正憲法の意義を歌う文章でもあるはずだ。これこれの理由で新たに改正憲法を作りましたという宣言がなければ、実用的ではないし、改正への意欲がないと談ぜられる。
つまりは、学者の演習問題というレベルで「たたき台」、これこそあるべき改正案だという気概が感じられない。これでは保守派はもちろんリベラルを辞任する国民にも響くまい。
「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」の最後「信頼して」を「期待して」に変更。
信頼しても野心や悪意のある国を武力行使を止められないからせいぜい「期待して」とすべきであり、信頼にたりないから9条を改正して「自衛軍」を持つべきだという論理である。
それは法学的には間違ってはいまい。
しかし、前文というのは新たな改正憲法の意義を歌う文章でもあるはずだ。これこれの理由で新たに改正憲法を作りましたという宣言がなければ、実用的ではないし、改正への意欲がないと談ぜられる。
つまりは、学者の演習問題というレベルで「たたき台」、これこそあるべき改正案だという気概が感じられない。これでは保守派はもちろんリベラルを辞任する国民にも響くまい。
リベラル派改正案のキモともいえる第九条の小林案は次の通り。
>第九条 日本国民は、第二次世界大戦を反省し、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、他国侵略の手段としては、永久にこれを放棄する。
2 我が国は、自国が他国による侵略の対象とされた場合に備えて、自衛軍を保持する。
3 我が国は、国連安全報償理事会の決議があった場合に限り、国際平和を維持する活動に参加する。ただし、この際には、事前に国会による承認を経なければならない。
関連事項として、第6章「司法」第七六条第二項に「軍法会議」の規定を置く
>第七六条 2 自衛軍のための軍法会議を除き、特別裁判所は設置されない。行政機関は、終審としての裁判を行うことができない。
>第九条 日本国民は、第二次世界大戦を反省し、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、他国侵略の手段としては、永久にこれを放棄する。
2 我が国は、自国が他国による侵略の対象とされた場合に備えて、自衛軍を保持する。
3 我が国は、国連安全報償理事会の決議があった場合に限り、国際平和を維持する活動に参加する。ただし、この際には、事前に国会による承認を経なければならない。
関連事項として、第6章「司法」第七六条第二項に「軍法会議」の規定を置く
>第七六条 2 自衛軍のための軍法会議を除き、特別裁判所は設置されない。行政機関は、終審としての裁判を行うことができない。
一見すると真っ当な感じがするが、小林氏の解説を合わせて読むと、中身は自民党草案よりも恐るべきものである。
ます「侵略戦争」のイメージが第二次世界大戦以前の帝国主義植民地支配においていることが時代錯誤である。
東西冷戦下においてそのような「侵略戦争」は事実上なくなった。冷戦時代の典型的な戦争形態は内戦で、親米、親共の国にするための内戦に大国が「味方する」という形態であった。
さらにソ連崩壊後も今度は政体、民族、宗派対立を原因とする、やはり内戦である。
明確な侵略は、イスラエルにまつわるパレスチナと、フセインイラクによるクェート侵略程度であろう。後は対立する領有権を巡る地域武力衝突である。
小林氏の想定するような、日本全土の占領にいたる戦争は想定の必要を認めがたい。
おととしの「安保法制」における集団自衛権においても、日本の存立を脅かすような事態としているだけで、具体的には周辺有事やシーレーンの途絶である。
もっと恐るべき主張は、小林氏は自衛軍による自衛戦争を、他国軍事基地のみならず首都制圧まで許容しているところである(新書124〜126ページ)。これは自民党草案の想定を遙かに上回り侵略戦争と何ら効果においては変わらない。他国の国土や財産を破壊し、非戦闘員の生命を危機にさらす武力行使が「自衛」であろうはずもない。
第3項は、言葉の選択がそもそも誤っている。
「国連」という略称を憲法に記載することは許されない。きちんと「国際連合(United Nationsの正しい訳語とは思えないが定着しているので不問にしよう)」を用いるべきだ。
なお「安全保障理事会」と限定するのも将来国際連合が、総会決議重視に変わることもあるので、単に「国際連合の決議」とすべきだし、「決議および当事国の要請があった場合」までしぼっておかないと現行のPKO 派遣原則と合致しないだろう。
ます「侵略戦争」のイメージが第二次世界大戦以前の帝国主義植民地支配においていることが時代錯誤である。
東西冷戦下においてそのような「侵略戦争」は事実上なくなった。冷戦時代の典型的な戦争形態は内戦で、親米、親共の国にするための内戦に大国が「味方する」という形態であった。
さらにソ連崩壊後も今度は政体、民族、宗派対立を原因とする、やはり内戦である。
明確な侵略は、イスラエルにまつわるパレスチナと、フセインイラクによるクェート侵略程度であろう。後は対立する領有権を巡る地域武力衝突である。
小林氏の想定するような、日本全土の占領にいたる戦争は想定の必要を認めがたい。
おととしの「安保法制」における集団自衛権においても、日本の存立を脅かすような事態としているだけで、具体的には周辺有事やシーレーンの途絶である。
もっと恐るべき主張は、小林氏は自衛軍による自衛戦争を、他国軍事基地のみならず首都制圧まで許容しているところである(新書124〜126ページ)。これは自民党草案の想定を遙かに上回り侵略戦争と何ら効果においては変わらない。他国の国土や財産を破壊し、非戦闘員の生命を危機にさらす武力行使が「自衛」であろうはずもない。
第3項は、言葉の選択がそもそも誤っている。
「国連」という略称を憲法に記載することは許されない。きちんと「国際連合(United Nationsの正しい訳語とは思えないが定着しているので不問にしよう)」を用いるべきだ。
なお「安全保障理事会」と限定するのも将来国際連合が、総会決議重視に変わることもあるので、単に「国際連合の決議」とすべきだし、「決議および当事国の要請があった場合」までしぼっておかないと現行のPKO 派遣原則と合致しないだろう。
第21条 集会結社や言論表現の自由を定めた重要な条文に、「知る権利」を定めた第3項が加わる。
3 表現の自由の不可欠な前提として、知る権利が保障されている。
まず、実に学者的な文章である。「不可欠な前提として」にそれを見ることができる。
解説によるとこの「知る権利」の内容は、行政権行使に関わる情報公開のことをいうらしい。
ならば、「情報公開請求権」と明記した方がよい。「知る権利」というざっくりしたくくりでは、情報公開請求とイコールではないという解釈も成り立ち、権利の範囲は政府(法律)に委ねられてしまう可能性がある。
幸福追求権や、生活権のように「あるけど実現は保障されない権利」になることだってあり得る。
ここは曖昧さを回避すべきであると考える。
ちなみに亭主の「私案」は、第21条の1以下の条文を付け加えている。
第二十一条の一 (知る権利を明文で追加)
国民は、国及び地方公共団体の保管する情報の公開請求ができる。
2.前項にかかわらず法律により公開を制限することができる。ただし制限期間は30年を超えることができない。
3.前項の制限ができる情報は、最小限でなければならず、相当の理由を明示しなければならない。
第二一条の二
個人に固有の情報は厳重な保護を要する。
2.国または地方公共団体は保有する個人固有の情報によって、個人の権利を侵害してはならない。
第二十一条の三 第二十一条にかかわらず、あらゆる差別に関してそれを煽り、政治目的とする結社、表現はしてはならない。
3 表現の自由の不可欠な前提として、知る権利が保障されている。
まず、実に学者的な文章である。「不可欠な前提として」にそれを見ることができる。
解説によるとこの「知る権利」の内容は、行政権行使に関わる情報公開のことをいうらしい。
ならば、「情報公開請求権」と明記した方がよい。「知る権利」というざっくりしたくくりでは、情報公開請求とイコールではないという解釈も成り立ち、権利の範囲は政府(法律)に委ねられてしまう可能性がある。
幸福追求権や、生活権のように「あるけど実現は保障されない権利」になることだってあり得る。
ここは曖昧さを回避すべきであると考える。
ちなみに亭主の「私案」は、第21条の1以下の条文を付け加えている。
第二十一条の一 (知る権利を明文で追加)
国民は、国及び地方公共団体の保管する情報の公開請求ができる。
2.前項にかかわらず法律により公開を制限することができる。ただし制限期間は30年を超えることができない。
3.前項の制限ができる情報は、最小限でなければならず、相当の理由を明示しなければならない。
第二一条の二
個人に固有の情報は厳重な保護を要する。
2.国または地方公共団体は保有する個人固有の情報によって、個人の権利を侵害してはならない。
第二十一条の三 第二十一条にかかわらず、あらゆる差別に関してそれを煽り、政治目的とする結社、表現はしてはならない。
小林「試案」では、人権として「環境権」を憲法に明記する。
第二十五条の二 すべて国民は、良好な環境の中で暮らす住民としての権利を有する。
「環境権」については改憲反対論者の中でも、「それならよい」と許容する人がいる。
しかし「良好な環境」というものは定義が難しい。
憲法なのだから、人間とりわけ日本人にとって「良好な生活環境」というのが最も狭義なものであろう。
たとえば大都市の住人と農村部では「良好な」は違う。住宅地がほしい都市住民と農地を死守する農村部などは、都市郊外において対立する。
都市の内部でも「保育園の園児の声が閑静な住環境を破壊する」という議論も「良好な環境」が何であるのかが「住民の立場」によって異なることを意味する。
さらに環境が生態系を含むとなれば、猪・鹿・猿・熊といった野生動物の生息環境と人間の居住環境のための「都市化」「宅地化」などの開発事業との優先権も曖昧である。自然環境と住民の利便性(例えば道路整備やトンネル掘削)は明らかに対立する。
都市部の良好な環境のためのゴミ処理場も設置場所の「環境」を破壊すると言うことになる。
このように「環境権」は、対立の多い権利概念であり、憲法上の人権となると双方妥協の余地がないだけに先鋭化する。
環境権は憲法より、個別具体的な状況下での住民間の合意や、訴訟によって解決されるべき問題であろうといえる。
第二十五条の二 すべて国民は、良好な環境の中で暮らす住民としての権利を有する。
「環境権」については改憲反対論者の中でも、「それならよい」と許容する人がいる。
しかし「良好な環境」というものは定義が難しい。
憲法なのだから、人間とりわけ日本人にとって「良好な生活環境」というのが最も狭義なものであろう。
たとえば大都市の住人と農村部では「良好な」は違う。住宅地がほしい都市住民と農地を死守する農村部などは、都市郊外において対立する。
都市の内部でも「保育園の園児の声が閑静な住環境を破壊する」という議論も「良好な環境」が何であるのかが「住民の立場」によって異なることを意味する。
さらに環境が生態系を含むとなれば、猪・鹿・猿・熊といった野生動物の生息環境と人間の居住環境のための「都市化」「宅地化」などの開発事業との優先権も曖昧である。自然環境と住民の利便性(例えば道路整備やトンネル掘削)は明らかに対立する。
都市部の良好な環境のためのゴミ処理場も設置場所の「環境」を破壊すると言うことになる。
このように「環境権」は、対立の多い権利概念であり、憲法上の人権となると双方妥協の余地がないだけに先鋭化する。
環境権は憲法より、個別具体的な状況下での住民間の合意や、訴訟によって解決されるべき問題であろうといえる。
第四章「国会」における改正点は、選挙方法と選曲を法律に委任した第四十七条に、議員定数と都道府県への平等配分を定めた第2項を付け加えるにとどまる。
第四十七条
2 法律で定めた両議員の定数は、比例区を除き、十年ごとの国勢調査の結果により、その半年以内に各都道府県に平等に再配分されなければならない。
自民党草案が「一人1票」の原則をねじ曲げているからというのがその理由である。
「一票の価値格差」をいいたいのだろうが、この第2項は稚拙である。その元は「一人1票の原則」というおかしなものを求めているからである。その原則を「都道府県への平等な再配分」として余計に増幅している。
都道府県の境を超えての調整が必要ならどうするのだろう。
アメリカ上院に人口要件はないことを見てわかるとおり、憲法に定めなければならないほど、重要ではない。
何倍以内は合憲だとか違憲だとかいう議論が無意味である事は、2.1倍と1.9倍の差を考えてみれば良い。
現実問題として、1票の価値格差というのは投票区や議員定数では決して解消されない。
もし解消しようというなら、選ばれた議員の「議決権」あたりで調整するしかない。2倍の格差があれば、議決権を2分の1にするというやり方である。
議決権の調整は格差の完全解消への唯一の方法であるが、国会議員としては決して受け入れられない極論であるので、これも憲法に乗せるべき事ではない。
「法律で定める」でよいのである。
あと一カ所の改正点、現行;
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
に対し、「内閣は20日以内にそれを招集しなければならない」と日限を加えたのは、評価できる。
第四十七条
2 法律で定めた両議員の定数は、比例区を除き、十年ごとの国勢調査の結果により、その半年以内に各都道府県に平等に再配分されなければならない。
自民党草案が「一人1票」の原則をねじ曲げているからというのがその理由である。
「一票の価値格差」をいいたいのだろうが、この第2項は稚拙である。その元は「一人1票の原則」というおかしなものを求めているからである。その原則を「都道府県への平等な再配分」として余計に増幅している。
都道府県の境を超えての調整が必要ならどうするのだろう。
アメリカ上院に人口要件はないことを見てわかるとおり、憲法に定めなければならないほど、重要ではない。
何倍以内は合憲だとか違憲だとかいう議論が無意味である事は、2.1倍と1.9倍の差を考えてみれば良い。
現実問題として、1票の価値格差というのは投票区や議員定数では決して解消されない。
もし解消しようというなら、選ばれた議員の「議決権」あたりで調整するしかない。2倍の格差があれば、議決権を2分の1にするというやり方である。
議決権の調整は格差の完全解消への唯一の方法であるが、国会議員としては決して受け入れられない極論であるので、これも憲法に乗せるべき事ではない。
「法律で定める」でよいのである。
あと一カ所の改正点、現行;
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
に対し、「内閣は20日以内にそれを招集しなければならない」と日限を加えたのは、評価できる。
第五章「内閣」では、内閣の権能を定めた第七十三条中第6号「政令・規則」の制定権に現行「罰則を設けることができない」に替わり「国民の権利を制限しまたは国民に義務を課す規定を設けることができない」とする。
人権派リベラル憲法学者の面目躍如たるところだが、改正案全体を見るときにはここだけでは不十分だろう。
「自衛軍」を認める以上、その運用に対する内閣の責任を明記しないことは、文民統制を確保したいなら通常あり得ない。内閣が自衛軍をコントロールしないのなら、自衛軍の憲法上の権能は、三権とは独立した第四権となりうる。
この点を見逃している「小林案」は明らかに稚拙である。
自民党草案ですら、「国防軍」に内閣は責任を持つことが規定されている。それ故小林「試案」はあきれるほかない。
人権派リベラル憲法学者の面目躍如たるところだが、改正案全体を見るときにはここだけでは不十分だろう。
「自衛軍」を認める以上、その運用に対する内閣の責任を明記しないことは、文民統制を確保したいなら通常あり得ない。内閣が自衛軍をコントロールしないのなら、自衛軍の憲法上の権能は、三権とは独立した第四権となりうる。
この点を見逃している「小林案」は明らかに稚拙である。
自民党草案ですら、「国防軍」に内閣は責任を持つことが規定されている。それ故小林「試案」はあきれるほかない。
第六章「司法」では、第七十六条2項すなわち「特別裁判所の禁止」の例外として「軍法会議」が明記されるにとどまる。
「軍法会議」が開かれる条件に言及がないし、一般訴訟が提起できるという保証もない。これでは、「内閣」の章で問題にしたのと同じく、自衛軍が独立した司法権を持つことになる。まさに三権外の第四権力となってしまう。
また小林「試案」には、現行の最高裁判所による違憲立法審査権が機能不全に陥っていることへの危機感が全くないのもいただけない。
リベラル派にとっては、違憲の疑いのある立法が平然と行われ、一般訴訟との抱き合わせでしか違憲である旨問えないのは、「一票の格差」にせよ他の権利事項や、自衛隊の振る舞いや条約締結にせよ、歯がゆいはず。
「軍法会議」が開かれる条件に言及がないし、一般訴訟が提起できるという保証もない。これでは、「内閣」の章で問題にしたのと同じく、自衛軍が独立した司法権を持つことになる。まさに三権外の第四権力となってしまう。
また小林「試案」には、現行の最高裁判所による違憲立法審査権が機能不全に陥っていることへの危機感が全くないのもいただけない。
リベラル派にとっては、違憲の疑いのある立法が平然と行われ、一般訴訟との抱き合わせでしか違憲である旨問えないのは、「一票の格差」にせよ他の権利事項や、自衛隊の振る舞いや条約締結にせよ、歯がゆいはず。
第七章「財政」では、第八十三条に「財政の健全性は常に確保されなければならない」という第2項が挿入される。
これは自民党草案とほぼ同じである。
しかし両案とも「財政の健全性」とは何かという根本的問題がある。この定義が曖昧な限り、毎年の予算編成や国会審議においていたずらに不毛な政争の具となり、結果として政府与党の恣意に委ねることになって早々に有名無実化されるだろう。
次の改正点は、第八十六条に第2項「予算は、国会の議決を経て、翌年度においても支出することができる」を付け加える。
地方自治法に定めがある「継続費」「繰越明許費」を国家予算についても認めようということで、一定の合理性はあるだろうが、軍備・兵器の開発にかかる予算を繰り越したり、政権交代が起きたときに新政権の予算編成権を縛ることになるので、感心しない。
これは自民党草案とほぼ同じである。
しかし両案とも「財政の健全性」とは何かという根本的問題がある。この定義が曖昧な限り、毎年の予算編成や国会審議においていたずらに不毛な政争の具となり、結果として政府与党の恣意に委ねることになって早々に有名無実化されるだろう。
次の改正点は、第八十六条に第2項「予算は、国会の議決を経て、翌年度においても支出することができる」を付け加える。
地方自治法に定めがある「継続費」「繰越明許費」を国家予算についても認めようということで、一定の合理性はあるだろうが、軍備・兵器の開発にかかる予算を繰り越したり、政権交代が起きたときに新政権の予算編成権を縛ることになるので、感心しない。
第八章「地方自治」第九十二条に( )書きで次の文章が挿入される。
・・地方自治の本旨に基づいて(即ち、各地方に固有の行政需要についてはその地方の住民により組織された自治体が一次的な権限を有するという前提の下で)、法律で定める。
このような解釈文の挿入は、憲法の法文としては全く場違いであろう。小林氏の憲法に対する姿勢を疑わざるを得ない。
第2項を追加して「国は、地方自治体権能に、法的または財政的に不当に干渉してはならない。」とするのが妥当であろう。
さて最後「第十章 最高法規」には変更がないので、第九章の「改正」を残すのみとなった。
「改正」についてはハードルを現行の「国会の発議3分の2」から5分の3に下げる。
特に問題は感じない。
・・地方自治の本旨に基づいて(即ち、各地方に固有の行政需要についてはその地方の住民により組織された自治体が一次的な権限を有するという前提の下で)、法律で定める。
このような解釈文の挿入は、憲法の法文としては全く場違いであろう。小林氏の憲法に対する姿勢を疑わざるを得ない。
第2項を追加して「国は、地方自治体権能に、法的または財政的に不当に干渉してはならない。」とするのが妥当であろう。
さて最後「第十章 最高法規」には変更がないので、第九章の「改正」を残すのみとなった。
「改正」についてはハードルを現行の「国会の発議3分の2」から5分の3に下げる。
特に問題は感じない。
コメント4で第2次世界大戦時のような侵略戦争はない、という認識はロシアによるウクライナ侵略によって覆った。
経済の相互依存が武力衝突をなくすということが幻想で、経済制裁の「返り血」が大きくなるだけということが判明した。
そしてむき出しになったのは、第二次大戦ごすぐの感覚で作られた国際連合・安全保障委員会の陳腐化だ。もはや核兵器を保有する「常任理事国」の身勝手な暴挙を止める手段を持ち合わせないことが明らかになった。
ウクライナはやりたがってるが、武器供与などで後ろ盾となっているNATOは、敵地(ロシア国内)への反撃は危険すぎると断固拒否している。この事実は「敵基地反撃能力保持」を気楽にいう人々にはぜひ考えてもらいたいものだ。
経済の相互依存が武力衝突をなくすということが幻想で、経済制裁の「返り血」が大きくなるだけということが判明した。
そしてむき出しになったのは、第二次大戦ごすぐの感覚で作られた国際連合・安全保障委員会の陳腐化だ。もはや核兵器を保有する「常任理事国」の身勝手な暴挙を止める手段を持ち合わせないことが明らかになった。
ウクライナはやりたがってるが、武器供与などで後ろ盾となっているNATOは、敵地(ロシア国内)への反撃は危険すぎると断固拒否している。この事実は「敵基地反撃能力保持」を気楽にいう人々にはぜひ考えてもらいたいものだ。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
日本国憲法の改正私案 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
日本国憲法の改正私案のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- パニック障害とうつ病
- 8447人
- 2位
- 一行で笑わせろ!
- 82528人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208285人