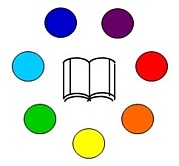すっかり板についてきたzoomでの読書会、やっぱ遠隔の人も参加できるのがいいですね。今回の課題本はアレクシエーヴィチ著『戦争は女の顔をしていない』(三浦みどり訳 岩波現代文庫)でした。厚めの本だったので読めるか心配でしたが、ぐいぐい惹きこまれましたね。あと久しぶりに岩波現代文庫の本を読んだのですが、紙にプラスチック感があって、触ってて気持ちよかったです。
会ではだいたい以下のようなことが話題にのぼりました。
・ノーベル文学賞受賞者の本を課題本にしてもらえてよかった。題名から、戦時中の女性の過酷さを思い浮かべ、日本でいうところの慰安婦問題的なもののイメージで入ったが、本署では最後のほうにあるだけで、むしろ男性のように武器をもって戦地にいくような話が多く、驚いた。
日本においては、特攻の話は多いが、白兵戦の記述はあまりない。新鮮だった。南洋の島々への侵攻では、餓死による死者が多かったので、語られていないのか。
戦国時代の戦は、後方の者はサボってた、というイメージ。本書ではみな愛国心をもって突撃していった。しかし愛国心はどこからくるのか。教育か。
登場人物は、戦中に十代後半から二十代→自分のおばあちゃんと同い年くらいだった。おばあちゃんの戦争体験も聞いてみたい。
・エピソードの一つひとつがヤバいやつばかりで、戦争の酷さうんぬん以前に文学的に目が眩むようだった。一番好きなのは爆撃されて飛び込んだ河から岸へあがるときに、仲間だと思って抱きかかえてたらチョウザメだったやつ。想像で書こうとしても書けない話ばかり。現実ってスゴい。
南洋の島々の話で言うと、大岡正平の『俘虜記』や『野火』との比較はどうか。今度読んでみよう。
・少ない言葉でとても要約などできない戦争というものに対して、同じように要約できない書き方で本書を仕上げることによって、対抗している。
・戦争パロディ?アニメに出てくる銀髪の美少女は、マジで白髪になってしまった若年女性兵士をモデルにしているのか、という驚き。
おばあさんからもらった特別な泥、ウクライナの肥沃な土地に興味。
ほんとうに自分で志願していったのか。集団的な圧力でいったのかもしれない。
証言の語りのなかで、2人称が味方のことを言っているのか敵のことを言っているのかわからない箇所があった。
・証言ゆえ、整理されていないところが多く、ノイズ?が多かった(沈黙を示す「…」など)。ひとの証言をこのまま記したものがこんなに読みづらいとは。
要約することはできないパッチワーク。多面的なカオス。
「序の著者の言葉→あいだに少し著者の言葉」このスタイルでは最後に大々的に著者のまとめがくると思ったが、なかった。証言をききとることの未完成が出ている。
「女性におしつけられた価値観からの解放」的な流れが昨今あるが、むしろ本書では、女性的な価値観が日常を忘れないためのよすがとなっていた。→逆に考えると、男性は大きな物語でしか自分を語れないのか。男性のほうも実は苦しいのではないのか。
・「白兵戦」という言葉の新鮮さ。
「志願して行く」という驚き。洗脳?日本でも同じようなメカニズムあったか。
ロシアの共産主義と、日本の国体護持は分けて考えるべきか。
慰安婦的な人たち→日本の慰安婦以外(他国の慰安婦)は国際的に問題化されていない?
パルチザンの母、人の盾。人が人でなくなってしまうとき。
「戦争は人間の顔をしていない」と言ってもいいのでは。何かしら「人間的なこと」を手元においておかないと戦い抜けないもの、それが戦争。
・村上春樹『アンダーグラウンド』を思い出した。セラピー的に語る(語らせる)ことの効果。
本書の「まとめない」というスタイル→証言者の個を大切にしている。
・著者が証言を記録し始めたのが30代、証言者は主に50代→証言するのに時間がかかったのだ。政治体制の変化。大変な思いをしたのに戦後さらに虐げられること。
白兵戦。日本は本土でも白兵戦になった?独ロは大陸だから白兵戦があった?
女性の兵士採用、共産主義ゆえのある種の男女平等さがあるか?
戦争、大儀、女としての価値観、に対して、個々人で思うことは少しずつ違う。それをそのまま書いているのがいいのだ。
・本書のコミック版を読むこと→美談に回収しがち問題。そっちの方がウケるんだけどね。
・大須・上前津の本屋(オタク系書店)に戦争/ミリタリー系のブースがあって、本書がオススメされていた。
・読んでよかった。多くの人に読んでもらいたい。著者の語り(グレーの囲み文)がよかった。
「思い出すことよりも、思い出さないことのほうが怖いことだからね…」
今までの歴史をみてきて、人間の集団は戦争を起こしてしまうということを自覚しないといけない。どうやったら戦争を起こさないようにしていけるかを考えないといけない。
・アマゾンで本書を買ったが、『アンダーグラウンド』がアマゾンで薦められるようになった。
・『82年生まれ、キム・ジヨン』を以前読書会でやったが、それと手法を比較できないか。様々な声を一つに統合すること/しないこと。
・自ら進んで志願した女の子たち→石垣りんのエピソード(戦地にいく親族に「おめでとうございます」)を思い出した。
自分がきいた戦争体験でよく聞くのが「飛行機が低く飛んでいた」こと。あと、どこに飛び込んで逃げたとか隣のお姉ちゃんがどうしたとか、細かいこと。
・ウチの祖父の話を聞いたことがある。戦後しばらく中国に遊びにいったりしたこともあって、本書における夫たちみたいなタイプかなと思った。
・ドイツ兵に対する親切な扱い→救いを感じた。日本でもそういうことがあったかもしれないし、傷ついた人、飢えた人として個人をみる感じ。勇気のあるエピソード。
・負傷兵を助けにいくことのコストと、中国残留孤児、敵国の子どもたちを育てること。
・「大地」の話がよく出てきた。ロシア人にとって「(肥沃な)大地」って何か意味があるのか。
・本書ではウクライナの「肥沃な(肥沃すぎる)大地」の話が印象的だった。
・大陸の人ゆえの「大地」観か。日本は「山」観。
・ロシアは雪が多いだろうから、雪が溶けて大地が見えることに格別の感じがあるのではないか。
・敵味方のさかいなく助けに行く、その半面、独ソ戦でソ連兵が酷いことをしている話をどっかで聞いた覚えがある。しかし最近、映画『フルメタル・ジャケット』を観たのだが、そこでで描かれるような酷いことを、思いとどまらせる/踏み込ませるきっかけとは何だろうか。
・極限状態における人間の一貫性→思い出さないこと、忘れること。
・全体を通して。ヨーロッパは地続きで、かつて戦争をして領土をとりあっていたが、いまはカタチだけかもしれないが国際協調している。これがすごい。
→その事態はもしかしたら、「ナチスが行った蛮行をドイツは未来永劫反省し続ける」というドイツの戦後処理の仕方と表裏の関係にあるのでは。
・戦後処理について、日本では、天皇という覆してはいけないものがあるので、中途半端になってしまうのか。
・アメリカが統治しやすいように天皇を残した。これが現代日本にも禍根を残しているか。眞子様と小室さんの話。
こんな感じでしょうか。ブレグマン『Humankind』中に紹介のあるノトーリアスな心理学実験・研究のことも話題にのぼったのですが、どの流れか憶えていないのでここに記しておきます。
個人的には最近、本書を読む少し前くらいから、ルポルタージュ/証言録/ノンフィクション、のようなジャンルに目が奪われがちです。まだ読んでいないのですが、日本だと岸政彦さんの仕事がこれからもっともっと注目されてくるでしょうね。
会ではだいたい以下のようなことが話題にのぼりました。
・ノーベル文学賞受賞者の本を課題本にしてもらえてよかった。題名から、戦時中の女性の過酷さを思い浮かべ、日本でいうところの慰安婦問題的なもののイメージで入ったが、本署では最後のほうにあるだけで、むしろ男性のように武器をもって戦地にいくような話が多く、驚いた。
日本においては、特攻の話は多いが、白兵戦の記述はあまりない。新鮮だった。南洋の島々への侵攻では、餓死による死者が多かったので、語られていないのか。
戦国時代の戦は、後方の者はサボってた、というイメージ。本書ではみな愛国心をもって突撃していった。しかし愛国心はどこからくるのか。教育か。
登場人物は、戦中に十代後半から二十代→自分のおばあちゃんと同い年くらいだった。おばあちゃんの戦争体験も聞いてみたい。
・エピソードの一つひとつがヤバいやつばかりで、戦争の酷さうんぬん以前に文学的に目が眩むようだった。一番好きなのは爆撃されて飛び込んだ河から岸へあがるときに、仲間だと思って抱きかかえてたらチョウザメだったやつ。想像で書こうとしても書けない話ばかり。現実ってスゴい。
南洋の島々の話で言うと、大岡正平の『俘虜記』や『野火』との比較はどうか。今度読んでみよう。
・少ない言葉でとても要約などできない戦争というものに対して、同じように要約できない書き方で本書を仕上げることによって、対抗している。
・戦争パロディ?アニメに出てくる銀髪の美少女は、マジで白髪になってしまった若年女性兵士をモデルにしているのか、という驚き。
おばあさんからもらった特別な泥、ウクライナの肥沃な土地に興味。
ほんとうに自分で志願していったのか。集団的な圧力でいったのかもしれない。
証言の語りのなかで、2人称が味方のことを言っているのか敵のことを言っているのかわからない箇所があった。
・証言ゆえ、整理されていないところが多く、ノイズ?が多かった(沈黙を示す「…」など)。ひとの証言をこのまま記したものがこんなに読みづらいとは。
要約することはできないパッチワーク。多面的なカオス。
「序の著者の言葉→あいだに少し著者の言葉」このスタイルでは最後に大々的に著者のまとめがくると思ったが、なかった。証言をききとることの未完成が出ている。
「女性におしつけられた価値観からの解放」的な流れが昨今あるが、むしろ本書では、女性的な価値観が日常を忘れないためのよすがとなっていた。→逆に考えると、男性は大きな物語でしか自分を語れないのか。男性のほうも実は苦しいのではないのか。
・「白兵戦」という言葉の新鮮さ。
「志願して行く」という驚き。洗脳?日本でも同じようなメカニズムあったか。
ロシアの共産主義と、日本の国体護持は分けて考えるべきか。
慰安婦的な人たち→日本の慰安婦以外(他国の慰安婦)は国際的に問題化されていない?
パルチザンの母、人の盾。人が人でなくなってしまうとき。
「戦争は人間の顔をしていない」と言ってもいいのでは。何かしら「人間的なこと」を手元においておかないと戦い抜けないもの、それが戦争。
・村上春樹『アンダーグラウンド』を思い出した。セラピー的に語る(語らせる)ことの効果。
本書の「まとめない」というスタイル→証言者の個を大切にしている。
・著者が証言を記録し始めたのが30代、証言者は主に50代→証言するのに時間がかかったのだ。政治体制の変化。大変な思いをしたのに戦後さらに虐げられること。
白兵戦。日本は本土でも白兵戦になった?独ロは大陸だから白兵戦があった?
女性の兵士採用、共産主義ゆえのある種の男女平等さがあるか?
戦争、大儀、女としての価値観、に対して、個々人で思うことは少しずつ違う。それをそのまま書いているのがいいのだ。
・本書のコミック版を読むこと→美談に回収しがち問題。そっちの方がウケるんだけどね。
・大須・上前津の本屋(オタク系書店)に戦争/ミリタリー系のブースがあって、本書がオススメされていた。
・読んでよかった。多くの人に読んでもらいたい。著者の語り(グレーの囲み文)がよかった。
「思い出すことよりも、思い出さないことのほうが怖いことだからね…」
今までの歴史をみてきて、人間の集団は戦争を起こしてしまうということを自覚しないといけない。どうやったら戦争を起こさないようにしていけるかを考えないといけない。
・アマゾンで本書を買ったが、『アンダーグラウンド』がアマゾンで薦められるようになった。
・『82年生まれ、キム・ジヨン』を以前読書会でやったが、それと手法を比較できないか。様々な声を一つに統合すること/しないこと。
・自ら進んで志願した女の子たち→石垣りんのエピソード(戦地にいく親族に「おめでとうございます」)を思い出した。
自分がきいた戦争体験でよく聞くのが「飛行機が低く飛んでいた」こと。あと、どこに飛び込んで逃げたとか隣のお姉ちゃんがどうしたとか、細かいこと。
・ウチの祖父の話を聞いたことがある。戦後しばらく中国に遊びにいったりしたこともあって、本書における夫たちみたいなタイプかなと思った。
・ドイツ兵に対する親切な扱い→救いを感じた。日本でもそういうことがあったかもしれないし、傷ついた人、飢えた人として個人をみる感じ。勇気のあるエピソード。
・負傷兵を助けにいくことのコストと、中国残留孤児、敵国の子どもたちを育てること。
・「大地」の話がよく出てきた。ロシア人にとって「(肥沃な)大地」って何か意味があるのか。
・本書ではウクライナの「肥沃な(肥沃すぎる)大地」の話が印象的だった。
・大陸の人ゆえの「大地」観か。日本は「山」観。
・ロシアは雪が多いだろうから、雪が溶けて大地が見えることに格別の感じがあるのではないか。
・敵味方のさかいなく助けに行く、その半面、独ソ戦でソ連兵が酷いことをしている話をどっかで聞いた覚えがある。しかし最近、映画『フルメタル・ジャケット』を観たのだが、そこでで描かれるような酷いことを、思いとどまらせる/踏み込ませるきっかけとは何だろうか。
・極限状態における人間の一貫性→思い出さないこと、忘れること。
・全体を通して。ヨーロッパは地続きで、かつて戦争をして領土をとりあっていたが、いまはカタチだけかもしれないが国際協調している。これがすごい。
→その事態はもしかしたら、「ナチスが行った蛮行をドイツは未来永劫反省し続ける」というドイツの戦後処理の仕方と表裏の関係にあるのでは。
・戦後処理について、日本では、天皇という覆してはいけないものがあるので、中途半端になってしまうのか。
・アメリカが統治しやすいように天皇を残した。これが現代日本にも禍根を残しているか。眞子様と小室さんの話。
こんな感じでしょうか。ブレグマン『Humankind』中に紹介のあるノトーリアスな心理学実験・研究のことも話題にのぼったのですが、どの流れか憶えていないのでここに記しておきます。
個人的には最近、本書を読む少し前くらいから、ルポルタージュ/証言録/ノンフィクション、のようなジャンルに目が奪われがちです。まだ読んでいないのですが、日本だと岸政彦さんの仕事がこれからもっともっと注目されてくるでしょうね。
|
|
|
|
コメント(8)
課題本とは関係ない話になりますが、読書会で話題になった事柄について。
読書会の中で従軍慰安婦の話が上がりました。このことについて、自分も含め多くの人がよくわかっていないと思い、この問題について整理してみました。
まず、日本と韓国の間で、従軍慰安婦が問題化したのは80年代であり、戦後からこの年に至るまで、両国の間で問題になっていなかったということ。
事の発端は、吉田清治なる人物が、80年代に出した2冊の著作で、そこで自らの体験として書かれていた内容が「済州島において戦時中、約200人の若い女性を狩り出した」というもの。
のちに問題が大きくなってから、報道関係者、歴史研究家、さらには韓国の研究者まで現地に赴き裏付け調査を行ったが、だれも、何の証拠も、証言も得ることはできなかった。
しかし、1982年、この吉田証言を朝日新聞が記事として取り上げたことで事態は急変する。朝鮮半島における「慰安婦狩り」は事実として韓国で大きく扱われ、対日批判の中心的なイシューとなっていった。
その後朝日新聞は16回に渡って慰安婦に関する記事を掲載。
日本の中学歴史教科書にも記述される。
1990年、韓国の37の女性団体が声明発表。「慰安婦」の強制連行を認めたうえでの公式謝罪、賠償などの6項目を日本に要求。11月、「韓国挺身隊問題対策協議会」設立。
それから、元慰安婦が名乗り出たり、NHKで慰安婦の番組をやったり、アジア女性基金が設立されたり、河野談話があったり、ここでは書き切れないことがたくさんあった後、2014年、朝日新聞はこれまでの「従軍慰安婦」関連報道の検証を公表。32年前の吉田清治証言をはじめ、多くの事実関係の誤りを認めた。
しかし、これはあまりにも遅く、過去の報道が取り消されても、事態が白紙に戻るとは考えにくい。
戦前戦時中は戦意高揚を行い、爆発的に部数を伸ばした大手新聞社が、戦後も解体されず、嘘の報道を行い、問題を深刻化させた罪は重い。
朝日新聞の検証が公表されてからも、従軍慰安婦問題が事実であったといまだに信じている人がたくさんいるように思われる。
メディアと教育の影響力は本当に恐ろしい…。
参考記事
https://www.nippon.com/ja/features/h00074/
読書会の中で従軍慰安婦の話が上がりました。このことについて、自分も含め多くの人がよくわかっていないと思い、この問題について整理してみました。
まず、日本と韓国の間で、従軍慰安婦が問題化したのは80年代であり、戦後からこの年に至るまで、両国の間で問題になっていなかったということ。
事の発端は、吉田清治なる人物が、80年代に出した2冊の著作で、そこで自らの体験として書かれていた内容が「済州島において戦時中、約200人の若い女性を狩り出した」というもの。
のちに問題が大きくなってから、報道関係者、歴史研究家、さらには韓国の研究者まで現地に赴き裏付け調査を行ったが、だれも、何の証拠も、証言も得ることはできなかった。
しかし、1982年、この吉田証言を朝日新聞が記事として取り上げたことで事態は急変する。朝鮮半島における「慰安婦狩り」は事実として韓国で大きく扱われ、対日批判の中心的なイシューとなっていった。
その後朝日新聞は16回に渡って慰安婦に関する記事を掲載。
日本の中学歴史教科書にも記述される。
1990年、韓国の37の女性団体が声明発表。「慰安婦」の強制連行を認めたうえでの公式謝罪、賠償などの6項目を日本に要求。11月、「韓国挺身隊問題対策協議会」設立。
それから、元慰安婦が名乗り出たり、NHKで慰安婦の番組をやったり、アジア女性基金が設立されたり、河野談話があったり、ここでは書き切れないことがたくさんあった後、2014年、朝日新聞はこれまでの「従軍慰安婦」関連報道の検証を公表。32年前の吉田清治証言をはじめ、多くの事実関係の誤りを認めた。
しかし、これはあまりにも遅く、過去の報道が取り消されても、事態が白紙に戻るとは考えにくい。
戦前戦時中は戦意高揚を行い、爆発的に部数を伸ばした大手新聞社が、戦後も解体されず、嘘の報道を行い、問題を深刻化させた罪は重い。
朝日新聞の検証が公表されてからも、従軍慰安婦問題が事実であったといまだに信じている人がたくさんいるように思われる。
メディアと教育の影響力は本当に恐ろしい…。
参考記事
https://www.nippon.com/ja/features/h00074/
>>[1]
リンク先の記事読みましたけど、ひーちんさんのコメントの温度感とは真逆のものを感じました(みんなも安心して読んでみるといいよ! )。
やはり、「朝日新聞の検証が公表されてからも、従軍慰安婦問題が事実であったといまだに信じている人がたくさんいるように思われる。」という記述は書くべきではなかったと思います。って言うか単に「慰安婦のことについてまとめてある記述見つけてから見てみて」ぐらいでよかったと思います。ひーちんさんの書き方だと、諸々細かい微妙な機微(国家間が問題を設定し解決に向かうとはどういうことか、その際何によって事実を認定するのか、認定された事実の裏にどれほどの認定されない事実がありえそうなのか、みたいなこと)に対する想像力が丸々抜け落ちているように感じるからです。そういう意味では、本書はこの機微に迫る一つの方法だったのかもしれませんね。
リンク先の記事読みましたけど、ひーちんさんのコメントの温度感とは真逆のものを感じました(みんなも安心して読んでみるといいよ! )。
やはり、「朝日新聞の検証が公表されてからも、従軍慰安婦問題が事実であったといまだに信じている人がたくさんいるように思われる。」という記述は書くべきではなかったと思います。って言うか単に「慰安婦のことについてまとめてある記述見つけてから見てみて」ぐらいでよかったと思います。ひーちんさんの書き方だと、諸々細かい微妙な機微(国家間が問題を設定し解決に向かうとはどういうことか、その際何によって事実を認定するのか、認定された事実の裏にどれほどの認定されない事実がありえそうなのか、みたいなこと)に対する想像力が丸々抜け落ちているように感じるからです。そういう意味では、本書はこの機微に迫る一つの方法だったのかもしれませんね。
慰安婦の問題について語るには、資料がどれだけあっても足りません(’〜‘)
同じ記事を読んでも、受け取り方は人それぞれですねぇ…。
さて、課題本と大岡昇平の比較の件ですが、お恥ずかしながら『俘虜記』は挫折しましたので、『野火』について考えをお伝えしたいです♪といっても、『野火』もうろ覚え…。
フィクション(野火)とノンフィクション(課題本)って前提があるのと、一兵士の視点と多くの人間の見た世界って大きな違いがあるので、どこまで比較できるかはわかりませんが、共通する部分はいくつかありましたよ。以下の3つ。
1.「語ること」について
2.風景の描き方と凄惨な光景の対比
3.宗教について
1の「語ること」について。小説のラストで判明するのですが、実は『野火』って精神を病んだ復員兵が、精神病棟で回想録として記した日記?を載せているってスタイルなんです。なので、その場で経験した体験を克明に記録する、というより、思い出を装飾して語っているってところが素敵なポイントです。今回の課題本も、戦争体験を思い出し語る=話し手によって編集されているって表現がありましたが、『野火』の主人公田村も、自分の見た(と認めた)世界のことだけ書いているって点では共通していると思います。また田村は、課題本に出てくる男性達のように、大きな戦争の物語を語ることなく、目の前の戦いを自分の内面と対照させて内省しています。
まだ自分の中で咀嚼できていないので上手くいえませんが、自分の読んだ印象では、女性兵士達は自己の辛い体験と向き合うために「語り」ましたが、『野火』田村は、己の本質を隠すために「語(騙る??)」っているように受け取れました。
2.風景と凄惨な光景について。課題本の中でも、戦争の合間にふとあらわれる朝日の眩しさとか、風景の神々しさとか、そういう事柄が語られるシーンがありましたが、『野火』も同じく。戦闘シーンで脳髄が飛び散るみたいな場面や、登場人物たちのドギツイ性根が顕になる場面があると思えば、南洋の生き生きとした植物の緑とか、美しい花、俯瞰で見たときの山々と川の鮮やかさが結構な長尺で説明されたりします。こういう視点は、大岡昇平自身の戦争体験に基づいたものなんじゃないかなと勝手に想像しています。
3.宗教について。女性兵士達の中には、かつては無宗教で、神を信じるなんて皆に笑われてしまうと考えていた方が、戦争体験の中で信仰に目覚めていくというシーンがありましたが、田村もまたジャングル放浪の中で、かつて教養として脇に置いていたはずのキリスト教への信仰心が激しくわきあがります。そして物語終盤で人食を犯した兵士を裁く天使として大活躍?します。彼らの信仰が本物であるかどうかは別問題として、神の存在を意識することで、自己の中にもうひとつの目を獲得したってところが、個人的にはポイントだと思っています。きっと、女性兵士達にとっての宗教や女性性っていうのは、非日常の最中にあって、もうひとつの日常を生きるための錨(第二の視界)のようなものだっただろうし、それは田村に、戦渦にあって生き残るために誰かを押しのけ、利用し貪りつくしたいという餓鬼道に堕ちる欲望を、すんでのところで踏みとどまろうかの逡巡を与えたように思います。(ただ、大岡昇平は意地悪なので、田村のセコさは語りの外でちゃんとバラされます笑 田村はちゃんと餓鬼道の住民です)
宗教は天使として人を裁く名分を与えてしまう毒薬としても表現されています。小説『野火』からは、極限状態において、何か大きな、自分ではない「もの」に判断をゆだねたいと感じる誘惑、「語る(騙る)」ことによって自己を正当化したいと感じるエゴイズムを読み取ることができました♪『戦争は女の顔をしていない』の証言者の中にも、何人か、田村と同じような人がいたかもしれませんね。
長々となりましたが『野火』超名作なので、ぜひお手にとってみてくださいね♪
文章上手すぎてドン引き必至です。
映画『野火』(2015)もまた、賛否両論ありますが、違った解釈で楽しめる?作品ですよ。
(ちなみに、私は否のほうでした笑)
『俘虜記』『レイテ戦記』、また頑張ってみようかなぁ…。
同じ記事を読んでも、受け取り方は人それぞれですねぇ…。
さて、課題本と大岡昇平の比較の件ですが、お恥ずかしながら『俘虜記』は挫折しましたので、『野火』について考えをお伝えしたいです♪といっても、『野火』もうろ覚え…。
フィクション(野火)とノンフィクション(課題本)って前提があるのと、一兵士の視点と多くの人間の見た世界って大きな違いがあるので、どこまで比較できるかはわかりませんが、共通する部分はいくつかありましたよ。以下の3つ。
1.「語ること」について
2.風景の描き方と凄惨な光景の対比
3.宗教について
1の「語ること」について。小説のラストで判明するのですが、実は『野火』って精神を病んだ復員兵が、精神病棟で回想録として記した日記?を載せているってスタイルなんです。なので、その場で経験した体験を克明に記録する、というより、思い出を装飾して語っているってところが素敵なポイントです。今回の課題本も、戦争体験を思い出し語る=話し手によって編集されているって表現がありましたが、『野火』の主人公田村も、自分の見た(と認めた)世界のことだけ書いているって点では共通していると思います。また田村は、課題本に出てくる男性達のように、大きな戦争の物語を語ることなく、目の前の戦いを自分の内面と対照させて内省しています。
まだ自分の中で咀嚼できていないので上手くいえませんが、自分の読んだ印象では、女性兵士達は自己の辛い体験と向き合うために「語り」ましたが、『野火』田村は、己の本質を隠すために「語(騙る??)」っているように受け取れました。
2.風景と凄惨な光景について。課題本の中でも、戦争の合間にふとあらわれる朝日の眩しさとか、風景の神々しさとか、そういう事柄が語られるシーンがありましたが、『野火』も同じく。戦闘シーンで脳髄が飛び散るみたいな場面や、登場人物たちのドギツイ性根が顕になる場面があると思えば、南洋の生き生きとした植物の緑とか、美しい花、俯瞰で見たときの山々と川の鮮やかさが結構な長尺で説明されたりします。こういう視点は、大岡昇平自身の戦争体験に基づいたものなんじゃないかなと勝手に想像しています。
3.宗教について。女性兵士達の中には、かつては無宗教で、神を信じるなんて皆に笑われてしまうと考えていた方が、戦争体験の中で信仰に目覚めていくというシーンがありましたが、田村もまたジャングル放浪の中で、かつて教養として脇に置いていたはずのキリスト教への信仰心が激しくわきあがります。そして物語終盤で人食を犯した兵士を裁く天使として大活躍?します。彼らの信仰が本物であるかどうかは別問題として、神の存在を意識することで、自己の中にもうひとつの目を獲得したってところが、個人的にはポイントだと思っています。きっと、女性兵士達にとっての宗教や女性性っていうのは、非日常の最中にあって、もうひとつの日常を生きるための錨(第二の視界)のようなものだっただろうし、それは田村に、戦渦にあって生き残るために誰かを押しのけ、利用し貪りつくしたいという餓鬼道に堕ちる欲望を、すんでのところで踏みとどまろうかの逡巡を与えたように思います。(ただ、大岡昇平は意地悪なので、田村のセコさは語りの外でちゃんとバラされます笑 田村はちゃんと餓鬼道の住民です)
宗教は天使として人を裁く名分を与えてしまう毒薬としても表現されています。小説『野火』からは、極限状態において、何か大きな、自分ではない「もの」に判断をゆだねたいと感じる誘惑、「語る(騙る)」ことによって自己を正当化したいと感じるエゴイズムを読み取ることができました♪『戦争は女の顔をしていない』の証言者の中にも、何人か、田村と同じような人がいたかもしれませんね。
長々となりましたが『野火』超名作なので、ぜひお手にとってみてくださいね♪
文章上手すぎてドン引き必至です。
映画『野火』(2015)もまた、賛否両論ありますが、違った解釈で楽しめる?作品ですよ。
(ちなみに、私は否のほうでした笑)
『俘虜記』『レイテ戦記』、また頑張ってみようかなぁ…。
従軍慰安婦については、
かつて辺見庸がナヌムの家に居住する元慰安婦の高齢女性たちを長らく取材してきて、
彼女らの痛みについて書いていたのが印象的でした。
「彼」個人の「彼女ら」に対する感受性が表れていて。
人間あるところに(残念ながら)暴力はつきものですが、
究極の暴力である戦争を止めるためには、このような、一人一人の感受性が大事な気がします。
岸政彦よいですね。
「野火」古い方の映画は、まぁまぁでした。ちょっと気合いいるけど。
不凍港、なるほどです。そりゃそうだわなー。
後で思ったのですが、「…」の多さについて。
「語り」特有の、言いよどみなどを文字上に再現したのもあるでしょうが、
言うに言えない、言ってはならない、思い出せない、思い出したくない、うんぬん、の
一つの表現だったこともあるのだろうな、と。
たとえば、
ペレストロイカ以前の戦後ソ連体制の下で、語ってはならないことの縛りはあったでしょうし、
実際、人間味のある語りを自ら覆し、ある種、英雄的?な物言いに
添削して返した登場人物もいましたが。
それ以外にも、たとえば、
戦後に、若い取材者相手に、敵兵や捕虜を救った話はできても、
敵兵を殺した話を赤裸々に話すのはキツいことだと思うのですよ。
加害を加害として語ることができる人というのは、
よほどの人物というか、何か信念がいるでしょう。
かつて辺見庸がナヌムの家に居住する元慰安婦の高齢女性たちを長らく取材してきて、
彼女らの痛みについて書いていたのが印象的でした。
「彼」個人の「彼女ら」に対する感受性が表れていて。
人間あるところに(残念ながら)暴力はつきものですが、
究極の暴力である戦争を止めるためには、このような、一人一人の感受性が大事な気がします。
岸政彦よいですね。
「野火」古い方の映画は、まぁまぁでした。ちょっと気合いいるけど。
不凍港、なるほどです。そりゃそうだわなー。
後で思ったのですが、「…」の多さについて。
「語り」特有の、言いよどみなどを文字上に再現したのもあるでしょうが、
言うに言えない、言ってはならない、思い出せない、思い出したくない、うんぬん、の
一つの表現だったこともあるのだろうな、と。
たとえば、
ペレストロイカ以前の戦後ソ連体制の下で、語ってはならないことの縛りはあったでしょうし、
実際、人間味のある語りを自ら覆し、ある種、英雄的?な物言いに
添削して返した登場人物もいましたが。
それ以外にも、たとえば、
戦後に、若い取材者相手に、敵兵や捕虜を救った話はできても、
敵兵を殺した話を赤裸々に話すのはキツいことだと思うのですよ。
加害を加害として語ることができる人というのは、
よほどの人物というか、何か信念がいるでしょう。
20代のとき、大きな病気をして、あ、やばいかも、となった時に、
病院からの帰り道、急に周囲の景色がクッキリと美しく迫って見えたことがありました。
ガードレールなんかが、なぜか妙に愛おしく懐かしく見えるんですよ。
しばらく経つと、その感じは失せてしまい、
身体も回復し、
また濁った日常に戻ったわけですが。
当時、別の大きな病気をした知人にそれを話すと、
「わかる、わかる、あんた、それ、どれくらい持った?」と聞かれ、
「3ヶ月」と答えたら、
「短いねぇ、私ゃ半年は持ったわよ」と叱られました。
戦争でわやくちゃの中で、過覚醒だったり、ちょっと違った状態になっても、
その中での日常って、案外平凡にあるのかも知れません。
病院からの帰り道、急に周囲の景色がクッキリと美しく迫って見えたことがありました。
ガードレールなんかが、なぜか妙に愛おしく懐かしく見えるんですよ。
しばらく経つと、その感じは失せてしまい、
身体も回復し、
また濁った日常に戻ったわけですが。
当時、別の大きな病気をした知人にそれを話すと、
「わかる、わかる、あんた、それ、どれくらい持った?」と聞かれ、
「3ヶ月」と答えたら、
「短いねぇ、私ゃ半年は持ったわよ」と叱られました。
戦争でわやくちゃの中で、過覚醒だったり、ちょっと違った状態になっても、
その中での日常って、案外平凡にあるのかも知れません。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|