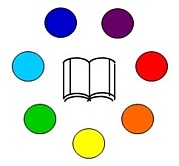いつの間にか日差しも強くなり、夏の気配をすでに感じる連休の後半、第55回目の読書会が行われました。課題本は塚田薫著、長峯信彦監修『増量 日本国憲法を口語訳してみたら』。5月3日の憲法記念日にあわせてこの本が選ばれたわけですが、改憲論議が若干下火になったかと思えばコロナ禍をうけて思わぬ角度から再び話題になったりと、心にとどめ続けるべきテーマでもあります。
今回は当会初の試みとして、オンライン読書会を実施しました。上手くいくか不安でしたが、接続などもスムーズにいき順調に進行したかと思います。なかにはカメラ背景を書斎風に変えてくる参加者もいて、是非自分もやってみたいなと思いまそれどのメニューでやるんですか教えてください。
と思いきや気が緩んでいたのか、せっせとPCに打ち込んでいた皆さんの発言メモを、保存するのを忘れてしまいました泣。やはり新しいことをやるときには注意しなければなりませんね。反省していますごめんなさい。
ということで記憶に残った話題を紹介しようと思います。
・恥ずかしながら、違憲審査制度のことをこの本を読んで初めて知った。ボードゲームに譬えるなら、ルール間で競合した時にゲームマスターに仲裁させるようなものか。
・口語訳がスッと読めた。読めすぎて夜更かしして一気読みした。
・口語訳が面白い。例えば14条3項。「お前が偉いってことじゃなくて」とか「子供とか関係ないからな」とか。分かりやすい行動で言い換えている感じ。
・口語訳と原文を対照形式で載せているのが面白い。原文と即座に比べながら読めることで、口語訳ではどうしても訳し足りない/訳し過ぎな部分が見えてきて、それに気づくことが、原文をよく読もうとすることにつながる。口語訳のみを読んでいるだけではそうはならない。
・本書のスタイルは、単に「口語訳」というわけではなく、「口語訳+通説」と捉えるべき。法を考える際には、それがどのように解されているかの通説を、さらにはその通説がどのような具体的な訴訟や事実関係のもとで形成されていったかの過程を見ることも重要。
・後半のコラムも面白い。個人的には一番最後の社会保障のところが、学生時代の興味関心と重なる部分があってグッときた。
・夫婦別姓を認めたい観点から、24条が気になる。っていうか、別姓を認めてくれないと本当に困る。同性婚の話も24条が関わってきそう。海外でも似たような規定ってあるんだろうか。
・24条と夫婦別姓に関しては、「戸籍」に関する考え方を柔軟にする必要があるかもしれない。しかし振り返れば、昔は領主が領民に対して姓を与えたり、戦中・戦後の混乱で戸籍が不明になって新設したり、結構自由にやってた。意外と自由にやれるものかもしれない。
・憲法改正論議では9条が論点になることが多いが、それ以外の論点もある。例えば目下の新型コロナ騒動を受けて、緊急事態宣言的な文言を憲法に盛り込んではという話もある。
・憲法改正が発議されたとき、それがいきなりだったら困る気がする。いくら国会内で議論を重ねたとしてもその印象は拭えない。本書にも日本国憲法制定時のいきさつが書いてあるが、民間の団体とか出版社が気軽に私案を発表すればいいし、別にこの読書会で私案を発表してもいいのだ。
・自衛隊が違憲かどうか、護憲か改憲か、などについて様々な意見があるだろうが、改憲「派」や護憲「派」のように、無用なカテゴライズはしない方がいい。
・女系天皇、男系女子天皇に関して、性差別の観点から認めるべきだという意見を目にするが、それに関してあまり知られていない点がある。それは、男性皇族が一般女性と結婚した場合、その一般女性は皇族に入るが、逆に女性皇族が一般男性と結婚した場合には、一般男性は皇族に入ることができない、という現行皇室典範の規定。
・日本の天皇(制)に関してはその「万世一系」さが誇りとされているけど、それはつまり「天然記念物」的な珍しさ。それと同様に?、天皇には、少なくとも私たちと同じ意味での人権はない。
・「人権」という言葉はよく見聞きするが、それが自由権と社会権から成ることを改めて確認できた。
・社会権をこの本では「助けてくれと求める権利」と書いているが、社会保障のことも、この基本に立ち返ってここから考えるべき。社会保障制度そのものを批判する言説を見るたび、自分が助けを求める立場になったことを思えばいいのでは、と思う。
・社会保障に関して、いわゆる「自己責任」の旗の下に、それを不要だと主張する人もいるが、そういう人はたいがい、「仕事(=労働)はイヤなもの」とだけ捉えている気がする。目下の営業自粛下での休業補償に関する議論を見ると特にそう思う。
・ベーシックインカムについてはどう思う?やっぱり勤労意欲は削がれるの?その他の社会保障制度(例えば健康保険制度の国民負担割合増加)次第で、逆に本当に困っている人たちがピンチになる可能性はないの?
・Netflixなら、ドラァグ・クイーンに関するドラマだかドキュメンタリーだかが面白いと聞いた。ただし正確な番組名は分からない。
こんなところでしょうか。国の最高法規である憲法が今回のネタでしたが、それでも(だからこそ?)、自らの実生活から接地点をみつけて近づいていくのがよいのかもしれません。しかし逆方向の目線も忘れてはいけないでしょう。すなわち、普段は直接には意識しない法規範が、日常の(ほぼ)隅々まで張り巡らされているという点です。
一つ問いを。憲法は三権を制限すると同時にその根拠でもあります。つまり憲法は、法の法でもある。であるならば、憲法と法(個別法)の関係を、法(個別法)と個人の関係のアナロジーとして捉えることは可能でしょうか。法の下で生きる我々が時折抱く「法が全てではない」という感覚―そしてそれは通常「正義」といわれる―を、憲法との関係でみた個別法も抱きうるのでしょうか。「法的正義」といった際の意味の重層性を聴き取ることで何が見えてくるでしょうか。おそらくそれは、制定以来一度も改正されていない憲法のもと時代々々に応じて個別法が様々に施行され廃止されてきたという非対称性に関係してくると思います。
ではその他、言い足りなかったこととか参加しなかった方のコメントとか、あとNetflixのオススメ番組とか、どうぞ。
今回は当会初の試みとして、オンライン読書会を実施しました。上手くいくか不安でしたが、接続などもスムーズにいき順調に進行したかと思います。なかにはカメラ背景を書斎風に変えてくる参加者もいて、是非自分もやってみたいなと思いまそれどのメニューでやるんですか教えてください。
と思いきや気が緩んでいたのか、せっせとPCに打ち込んでいた皆さんの発言メモを、保存するのを忘れてしまいました泣。やはり新しいことをやるときには注意しなければなりませんね。反省していますごめんなさい。
ということで記憶に残った話題を紹介しようと思います。
・恥ずかしながら、違憲審査制度のことをこの本を読んで初めて知った。ボードゲームに譬えるなら、ルール間で競合した時にゲームマスターに仲裁させるようなものか。
・口語訳がスッと読めた。読めすぎて夜更かしして一気読みした。
・口語訳が面白い。例えば14条3項。「お前が偉いってことじゃなくて」とか「子供とか関係ないからな」とか。分かりやすい行動で言い換えている感じ。
・口語訳と原文を対照形式で載せているのが面白い。原文と即座に比べながら読めることで、口語訳ではどうしても訳し足りない/訳し過ぎな部分が見えてきて、それに気づくことが、原文をよく読もうとすることにつながる。口語訳のみを読んでいるだけではそうはならない。
・本書のスタイルは、単に「口語訳」というわけではなく、「口語訳+通説」と捉えるべき。法を考える際には、それがどのように解されているかの通説を、さらにはその通説がどのような具体的な訴訟や事実関係のもとで形成されていったかの過程を見ることも重要。
・後半のコラムも面白い。個人的には一番最後の社会保障のところが、学生時代の興味関心と重なる部分があってグッときた。
・夫婦別姓を認めたい観点から、24条が気になる。っていうか、別姓を認めてくれないと本当に困る。同性婚の話も24条が関わってきそう。海外でも似たような規定ってあるんだろうか。
・24条と夫婦別姓に関しては、「戸籍」に関する考え方を柔軟にする必要があるかもしれない。しかし振り返れば、昔は領主が領民に対して姓を与えたり、戦中・戦後の混乱で戸籍が不明になって新設したり、結構自由にやってた。意外と自由にやれるものかもしれない。
・憲法改正論議では9条が論点になることが多いが、それ以外の論点もある。例えば目下の新型コロナ騒動を受けて、緊急事態宣言的な文言を憲法に盛り込んではという話もある。
・憲法改正が発議されたとき、それがいきなりだったら困る気がする。いくら国会内で議論を重ねたとしてもその印象は拭えない。本書にも日本国憲法制定時のいきさつが書いてあるが、民間の団体とか出版社が気軽に私案を発表すればいいし、別にこの読書会で私案を発表してもいいのだ。
・自衛隊が違憲かどうか、護憲か改憲か、などについて様々な意見があるだろうが、改憲「派」や護憲「派」のように、無用なカテゴライズはしない方がいい。
・女系天皇、男系女子天皇に関して、性差別の観点から認めるべきだという意見を目にするが、それに関してあまり知られていない点がある。それは、男性皇族が一般女性と結婚した場合、その一般女性は皇族に入るが、逆に女性皇族が一般男性と結婚した場合には、一般男性は皇族に入ることができない、という現行皇室典範の規定。
・日本の天皇(制)に関してはその「万世一系」さが誇りとされているけど、それはつまり「天然記念物」的な珍しさ。それと同様に?、天皇には、少なくとも私たちと同じ意味での人権はない。
・「人権」という言葉はよく見聞きするが、それが自由権と社会権から成ることを改めて確認できた。
・社会権をこの本では「助けてくれと求める権利」と書いているが、社会保障のことも、この基本に立ち返ってここから考えるべき。社会保障制度そのものを批判する言説を見るたび、自分が助けを求める立場になったことを思えばいいのでは、と思う。
・社会保障に関して、いわゆる「自己責任」の旗の下に、それを不要だと主張する人もいるが、そういう人はたいがい、「仕事(=労働)はイヤなもの」とだけ捉えている気がする。目下の営業自粛下での休業補償に関する議論を見ると特にそう思う。
・ベーシックインカムについてはどう思う?やっぱり勤労意欲は削がれるの?その他の社会保障制度(例えば健康保険制度の国民負担割合増加)次第で、逆に本当に困っている人たちがピンチになる可能性はないの?
・Netflixなら、ドラァグ・クイーンに関するドラマだかドキュメンタリーだかが面白いと聞いた。ただし正確な番組名は分からない。
こんなところでしょうか。国の最高法規である憲法が今回のネタでしたが、それでも(だからこそ?)、自らの実生活から接地点をみつけて近づいていくのがよいのかもしれません。しかし逆方向の目線も忘れてはいけないでしょう。すなわち、普段は直接には意識しない法規範が、日常の(ほぼ)隅々まで張り巡らされているという点です。
一つ問いを。憲法は三権を制限すると同時にその根拠でもあります。つまり憲法は、法の法でもある。であるならば、憲法と法(個別法)の関係を、法(個別法)と個人の関係のアナロジーとして捉えることは可能でしょうか。法の下で生きる我々が時折抱く「法が全てではない」という感覚―そしてそれは通常「正義」といわれる―を、憲法との関係でみた個別法も抱きうるのでしょうか。「法的正義」といった際の意味の重層性を聴き取ることで何が見えてくるでしょうか。おそらくそれは、制定以来一度も改正されていない憲法のもと時代々々に応じて個別法が様々に施行され廃止されてきたという非対称性に関係してくると思います。
ではその他、言い足りなかったこととか参加しなかった方のコメントとか、あとNetflixのオススメ番組とか、どうぞ。
|
|
|
|
コメント(9)
ヤトリさん、メモが消えてしまった中、読書会報告作成ありがとうございます!
初めてのオンライン読書会で不安な部分もありましたが、思っていたよりもスムーズにできましたね。家でできるというのは移動しなくてもいいし結構楽かも。
ここからは、読書会で話題になった話も交えながら、司会ということもあり読書会ではあまり言えなかった個人的な思いや考えを述べてみたいと思います。
思い込みについて
この本に載っている5つのコラムの最後に生活保護の話があり、そこでは「イメージが実際とは違っていることがある」という話題になりました。
生活保護には不正受給など悪いイメージがある。けれど、よく調べてみればそんなに単純ことではなく、不正受給にも様々なケースがあったり、本来もらえる人がもらえていなかったり、福祉事務所職員の必要な人数が足りていなかったり。イメージだけで思考停止になってはいけないと、コラムを読んで改めて思うのでした。
偏りのある情報には気を付けないといけない。特にテレビや新聞は偏りが大きいうえ、受け身であるために誘導されやすい。WEBやSNSは偏っている情報もたくさんあるが、一方的ではないため、反論がしっかりとある。そして情報に対して反対意見の情報などを自分で取りにいくこともできる。そこで自分の頭で考えることが大事なんだと思う。
ここで一つ気を付けたいのはわかりやすい情報。複雑な話を単純化しすぎると大事な部分を見落としてしまう。この本はわかりやすくていいのだが、単純化しすぎて見落としている部分もたくさんあるかもしれない。というか、あるだろう。
憲法改正について
現憲法は、「国民主権を決めた憲法なのに国民が読みにくいものだったら意味ないじゃんと言ってわかりやすい口語体で書かれることになった」と、本書でも紹介されているように、国民の誰にでもでもわかりやすいものでなければならないのだと思います。解釈で変えられるような複雑なものではなく明確にしなくてはいけないのです。では、憲法施行から73年たった今、それは維持されているでしょうか?はっきり言ってわかりにくいものになっているし、解釈によって意見が分かれたりしている。そもそも、現憲法は日本が占領されていた当時にGHQの監視のもとにできた憲法であり、当時の社会情勢を反映されて作られたものでもあります。当時と今では全く違う社会になっています。一言でいえば古すぎる。だからこそ、新しい憲法の案がたくさん出てきて、たくさん議論し、より良いものに改正されていくべきだと思います。
戦争について
今から述べることは、受け入れられない人が多いと思うのですが、自分の考えに少しだけお付き合いください。
現在の憲法で日本人の命を守れるのか?憲法を守ることで命が奪われては本末転倒では?という意見に対して(自分が言ったんだけど)、命を守るためにとか言って憲法を変えることに誘導されるのが怖い。それで戦争が起きたりするのではないかという意見がありました。戦争は二度としてはならない。誰もがそう考えていると思います。
ではこう考えてみましょう。今の憲法で戦争を防ぐことができるのか?実際、現在の日本国憲法下で戦争が起きていないといえばうそになるし、これからも安泰であるとはとても言えない状況にあります。北朝鮮の拉致、竹島の不法占拠は他の国からの暴力です。尖閣諸島周辺には、今では毎日のように中国の船が近づき、領空侵犯の恐れのある侵入機に対する自衛隊の緊急発進は年に1000回にも。しかも年々増えている。相手が間違ったことをしてきたときには、許さないぞという抑止力を見せることが必要ではないか。アメリカに守られていることもあり、大きな戦争にこそ至っていないが、このままでは逆に大きな戦争になりかねないのではないかと思うわけです。
さらに言えば、拉致や拿捕といった被害にあわれた当事者でなければ、このまま小さな国際紛争で多少犠牲者がいても、大きな戦争にならなければよい、自分に近いところで事が起きなけれがよいと思っている人もいるかもしれない。けれど拉致だって一歩間違えれば自分や自分の家族だったかもしれない。当事者の身になって少しは考えてみてほしい。拉致された人が幸せに暮らしている可能性だってあると考える人もいるかもしれない。けれど、いきなり拉致され、家族や友人や愛する人と引き裂かれて、あの北朝鮮で幸せだと想像できるだろうか。
まとめると、日本は軍事力の脅威に囲まれた国であり、憲法に交戦権を認め、抑止力を見せつける必要があるということ。自分で自分の国を守れる国にならなければいけないということ。このままでいいという考えは、年々増している周囲の国々の軍事力と挑発行為を無視しているし、アメリカだっていつまでも守ってくれるとは限らないのである。
つづく
初めてのオンライン読書会で不安な部分もありましたが、思っていたよりもスムーズにできましたね。家でできるというのは移動しなくてもいいし結構楽かも。
ここからは、読書会で話題になった話も交えながら、司会ということもあり読書会ではあまり言えなかった個人的な思いや考えを述べてみたいと思います。
思い込みについて
この本に載っている5つのコラムの最後に生活保護の話があり、そこでは「イメージが実際とは違っていることがある」という話題になりました。
生活保護には不正受給など悪いイメージがある。けれど、よく調べてみればそんなに単純ことではなく、不正受給にも様々なケースがあったり、本来もらえる人がもらえていなかったり、福祉事務所職員の必要な人数が足りていなかったり。イメージだけで思考停止になってはいけないと、コラムを読んで改めて思うのでした。
偏りのある情報には気を付けないといけない。特にテレビや新聞は偏りが大きいうえ、受け身であるために誘導されやすい。WEBやSNSは偏っている情報もたくさんあるが、一方的ではないため、反論がしっかりとある。そして情報に対して反対意見の情報などを自分で取りにいくこともできる。そこで自分の頭で考えることが大事なんだと思う。
ここで一つ気を付けたいのはわかりやすい情報。複雑な話を単純化しすぎると大事な部分を見落としてしまう。この本はわかりやすくていいのだが、単純化しすぎて見落としている部分もたくさんあるかもしれない。というか、あるだろう。
憲法改正について
現憲法は、「国民主権を決めた憲法なのに国民が読みにくいものだったら意味ないじゃんと言ってわかりやすい口語体で書かれることになった」と、本書でも紹介されているように、国民の誰にでもでもわかりやすいものでなければならないのだと思います。解釈で変えられるような複雑なものではなく明確にしなくてはいけないのです。では、憲法施行から73年たった今、それは維持されているでしょうか?はっきり言ってわかりにくいものになっているし、解釈によって意見が分かれたりしている。そもそも、現憲法は日本が占領されていた当時にGHQの監視のもとにできた憲法であり、当時の社会情勢を反映されて作られたものでもあります。当時と今では全く違う社会になっています。一言でいえば古すぎる。だからこそ、新しい憲法の案がたくさん出てきて、たくさん議論し、より良いものに改正されていくべきだと思います。
戦争について
今から述べることは、受け入れられない人が多いと思うのですが、自分の考えに少しだけお付き合いください。
現在の憲法で日本人の命を守れるのか?憲法を守ることで命が奪われては本末転倒では?という意見に対して(自分が言ったんだけど)、命を守るためにとか言って憲法を変えることに誘導されるのが怖い。それで戦争が起きたりするのではないかという意見がありました。戦争は二度としてはならない。誰もがそう考えていると思います。
ではこう考えてみましょう。今の憲法で戦争を防ぐことができるのか?実際、現在の日本国憲法下で戦争が起きていないといえばうそになるし、これからも安泰であるとはとても言えない状況にあります。北朝鮮の拉致、竹島の不法占拠は他の国からの暴力です。尖閣諸島周辺には、今では毎日のように中国の船が近づき、領空侵犯の恐れのある侵入機に対する自衛隊の緊急発進は年に1000回にも。しかも年々増えている。相手が間違ったことをしてきたときには、許さないぞという抑止力を見せることが必要ではないか。アメリカに守られていることもあり、大きな戦争にこそ至っていないが、このままでは逆に大きな戦争になりかねないのではないかと思うわけです。
さらに言えば、拉致や拿捕といった被害にあわれた当事者でなければ、このまま小さな国際紛争で多少犠牲者がいても、大きな戦争にならなければよい、自分に近いところで事が起きなけれがよいと思っている人もいるかもしれない。けれど拉致だって一歩間違えれば自分や自分の家族だったかもしれない。当事者の身になって少しは考えてみてほしい。拉致された人が幸せに暮らしている可能性だってあると考える人もいるかもしれない。けれど、いきなり拉致され、家族や友人や愛する人と引き裂かれて、あの北朝鮮で幸せだと想像できるだろうか。
まとめると、日本は軍事力の脅威に囲まれた国であり、憲法に交戦権を認め、抑止力を見せつける必要があるということ。自分で自分の国を守れる国にならなければいけないということ。このままでいいという考えは、年々増している周囲の国々の軍事力と挑発行為を無視しているし、アメリカだっていつまでも守ってくれるとは限らないのである。
つづく
つづき
緊急事態条項について
現憲法では、大規模な災害やテロ、今回のような新型ウイルス感染拡大等の緊急事態に政府ができることが明記されていません。特措法で対処していますが、集会の自由を事実上制限できる法律であるため、憲法違反の疑義もあります。憲法に明記されていなくても個別法で対応できるかもしれませんが、憲法違反の可能性を考えると、政府は緊急事態宣言発令や自粛要請や指示に対して慎重になりすぎ、事態が悪化することが懸念されます。実際今回のコロナウイルスでも、特措法成立や、緊急事態宣言発令に時間がかかり、事態を悪化させたといえるのではないでしょうか。
コロナに乗じて憲法改正を進めるなとの意見もありますが、そこで思考停止にならずにもう一度考えてみる必要があるのだと思います。
天皇について
女系天皇とか女性天皇とかよくわからないという人も多いと思うので、詳しく解説してみたいと思います。
まず、これまでに女系天皇は一人もいませんが女性天皇は何人かいました。
それは男系の女性天皇であり、男系とは父親をたどっていくと初代天皇にたどりつく系統のことを言います。女性でも男性でも、これまでの天皇はすべて男系天皇ということになります。
一方、女性でも男性でも母親が天皇で、父親が初代天皇の系統でない人は女系天皇ということですが、今まで一人もいません。
そもそも天皇というのはイギリス王室とはちがって、ローマ法王と同じように(ローマ法王に就任した女性は一人もいない)伝統宗教のトップ(神道の神主のトップ)であり、男系が伝統であって、そういうものなのです。
2000年も受け継がれてきた世界でも珍しい奇跡的な伝統であり、制度とかいうものでもなく、時の国民が一時の感情や考えで変えていいものではないと思われます。
男性皇族が近い将来いなくなるということで、女系天皇も認めようという話がありますが、実は戦後GHQによって皇籍を離脱された男系男子がたくさんいるので、その人たちを皇族に戻すだけで問題は解決されます。一般人になって長いのでふさわしくないという人もいますが、今でも皇室とかかわりを持っており、それほど問題視することではないと思います。
最後に
「安全保障にかかわることほど、あのときああしておけばよかったと思われることはない。」と言われるそうです。自衛隊について、緊急事態について、しっかりと明記することで未来に何か起きたときに助かることがあるかもしれない。あやふやにしておくのはリスクなのではないでしょうか。日本が戦争に突入してしまったのはなぜか?憲法のせいなのか?二度と戦争を起こさないために思考停止になってはならない。と、思います。
甘いものが食べたいです。
緊急事態条項について
現憲法では、大規模な災害やテロ、今回のような新型ウイルス感染拡大等の緊急事態に政府ができることが明記されていません。特措法で対処していますが、集会の自由を事実上制限できる法律であるため、憲法違反の疑義もあります。憲法に明記されていなくても個別法で対応できるかもしれませんが、憲法違反の可能性を考えると、政府は緊急事態宣言発令や自粛要請や指示に対して慎重になりすぎ、事態が悪化することが懸念されます。実際今回のコロナウイルスでも、特措法成立や、緊急事態宣言発令に時間がかかり、事態を悪化させたといえるのではないでしょうか。
コロナに乗じて憲法改正を進めるなとの意見もありますが、そこで思考停止にならずにもう一度考えてみる必要があるのだと思います。
天皇について
女系天皇とか女性天皇とかよくわからないという人も多いと思うので、詳しく解説してみたいと思います。
まず、これまでに女系天皇は一人もいませんが女性天皇は何人かいました。
それは男系の女性天皇であり、男系とは父親をたどっていくと初代天皇にたどりつく系統のことを言います。女性でも男性でも、これまでの天皇はすべて男系天皇ということになります。
一方、女性でも男性でも母親が天皇で、父親が初代天皇の系統でない人は女系天皇ということですが、今まで一人もいません。
そもそも天皇というのはイギリス王室とはちがって、ローマ法王と同じように(ローマ法王に就任した女性は一人もいない)伝統宗教のトップ(神道の神主のトップ)であり、男系が伝統であって、そういうものなのです。
2000年も受け継がれてきた世界でも珍しい奇跡的な伝統であり、制度とかいうものでもなく、時の国民が一時の感情や考えで変えていいものではないと思われます。
男性皇族が近い将来いなくなるということで、女系天皇も認めようという話がありますが、実は戦後GHQによって皇籍を離脱された男系男子がたくさんいるので、その人たちを皇族に戻すだけで問題は解決されます。一般人になって長いのでふさわしくないという人もいますが、今でも皇室とかかわりを持っており、それほど問題視することではないと思います。
最後に
「安全保障にかかわることほど、あのときああしておけばよかったと思われることはない。」と言われるそうです。自衛隊について、緊急事態について、しっかりと明記することで未来に何か起きたときに助かることがあるかもしれない。あやふやにしておくのはリスクなのではないでしょうか。日本が戦争に突入してしまったのはなぜか?憲法のせいなのか?二度と戦争を起こさないために思考停止になってはならない。と、思います。
甘いものが食べたいです。
ヤトリさんの報告に対するコメントです↓
なかなか有意義な読書会となったようですね。
ここまで話し合えるような環境が各地地域にあれば政治に対する関心も少しは高まるのではないかと思いました。
どの国でもルールは知能をもつ人間が決めているとするならば変えられるのやはり人間であると考えています。人間の本能という性質上、新しい発想や意見・考え方はそれまで築き上げてきた「安心」を脅かす存在になる可能性があり、コ◯ナと同じ目に見えない恐怖に晒されて変えても大丈夫なものが変えられず今日に至るのでないかと思います。おっしゃる通り現行の制度の改善や見直しはやはり必要かと思います。さらに外交に関しては複雑すぎて何が正しい情報なのかよく見極める必要があるかと思います。
それにしてもなかなか濃ゆい会でしたね。(笑)
なかなか有意義な読書会となったようですね。
ここまで話し合えるような環境が各地地域にあれば政治に対する関心も少しは高まるのではないかと思いました。
どの国でもルールは知能をもつ人間が決めているとするならば変えられるのやはり人間であると考えています。人間の本能という性質上、新しい発想や意見・考え方はそれまで築き上げてきた「安心」を脅かす存在になる可能性があり、コ◯ナと同じ目に見えない恐怖に晒されて変えても大丈夫なものが変えられず今日に至るのでないかと思います。おっしゃる通り現行の制度の改善や見直しはやはり必要かと思います。さらに外交に関しては複雑すぎて何が正しい情報なのかよく見極める必要があるかと思います。
それにしてもなかなか濃ゆい会でしたね。(笑)
>>[2]
戦争についてのみ意見を述べてみます。
もっと広〜い視野で物事を見てみると、「戦争はまだ終わっていない」と自分は結論しています。確かに軍事的な意味では大きな戦争は70年以上前に終わったと考えています。
そもそも戦争とは何か?魔物でありサタンであり何より「生きるエネルギーの奪い合い」に他なりません。だとするならば人の悪口、陰口、いじめ、虐待死、コロナ男、メディアの不安を煽る印象操作などが無くならない限り終戦とは自分は認めません。時は「乱世」であり大きなうねりの中を生きているような感覚ではないでしょうか。まだまだ人間の課題は山積みのような気がします。
今年はコロナのおかげで、健康・経済・政治・生活などあらゆる分野で人間が反省する良い機会となったと捉えています。特に経済支援に関しては自治体や政府はあまりアテにならいと学べましたね。キャッシュについて無頓着な経営者もたくさんいたようで…。
ブラック企業も少しは減るといいですけどね!(笑)
戦争についてのみ意見を述べてみます。
もっと広〜い視野で物事を見てみると、「戦争はまだ終わっていない」と自分は結論しています。確かに軍事的な意味では大きな戦争は70年以上前に終わったと考えています。
そもそも戦争とは何か?魔物でありサタンであり何より「生きるエネルギーの奪い合い」に他なりません。だとするならば人の悪口、陰口、いじめ、虐待死、コロナ男、メディアの不安を煽る印象操作などが無くならない限り終戦とは自分は認めません。時は「乱世」であり大きなうねりの中を生きているような感覚ではないでしょうか。まだまだ人間の課題は山積みのような気がします。
今年はコロナのおかげで、健康・経済・政治・生活などあらゆる分野で人間が反省する良い機会となったと捉えています。特に経済支援に関しては自治体や政府はあまりアテにならいと学べましたね。キャッシュについて無頓着な経営者もたくさんいたようで…。
ブラック企業も少しは減るといいですけどね!(笑)
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
読み人倶楽部の読書会 更新情報
読み人倶楽部の読書会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90013人
- 2位
- 酒好き
- 170663人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37150人