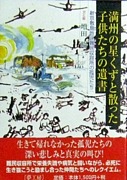|
|
|
|
コメント(15)
増田昭一さんの本と絵本は以下の5冊が書籍化され、販売されているようです。
■満州の星くずと散った子供たちの遺書
■戦場のサブちゃんとゴン
■約束
■ともちゃんのおへそ
■来なかったサンタクロース
もともと手掛けていた夢書房が2023年6月で事業廃止し、現在は神奈川県小田原の老舗書店<積善堂>有限会社平井書店で取り扱っているとのことです。
ネット販売のページは生きているのでURLを記しておきます。
★夢書房サイト(ネット販売)
http://www.yumekoubou-t.com/raiburari/masudasyouitinohonn.html#0010
増田昭一さんの本と絵本を取り扱っている積善堂 平井書店サイトも記します。
★積善堂 平井書店サイト
https://books-hirai.com/
■満州の星くずと散った子供たちの遺書
■戦場のサブちゃんとゴン
■約束
■ともちゃんのおへそ
■来なかったサンタクロース
もともと手掛けていた夢書房が2023年6月で事業廃止し、現在は神奈川県小田原の老舗書店<積善堂>有限会社平井書店で取り扱っているとのことです。
ネット販売のページは生きているのでURLを記しておきます。
★夢書房サイト(ネット販売)
http://www.yumekoubou-t.com/raiburari/masudasyouitinohonn.html#0010
増田昭一さんの本と絵本を取り扱っている積善堂 平井書店サイトも記します。
★積善堂 平井書店サイト
https://books-hirai.com/
終戦が戦争の始まりだった 襲撃と逃避行で家族失った満蒙開拓団 #戦争の記憶
8/9(水) 12:07配信 両丹日日新聞
1945年8月15日、日本の敗戦で終結となった第二次世界大戦。「私たちにとってはこの日が戦争の始まりだった」。そう語るのは国策のもと、満蒙開拓団として送り込まれた旧満州(中国東北部)からの引き揚げ者、京都府福知山市の細谷陽一さん(87)。戦後の混乱の中で失った家族の名が刻まれた墓標を前に、当時を回顧する。
細谷さんは1939年に満州北部の北安省に渡り、愛媛、高知、徳島3県出身者で構成された「予土阿村開拓団」の一員として、両親と姉の4人で入植。師範学校を卒業し、開拓団の子どもたちが通う在満国民学校の教師として渡った父・義夫さんに連れられてのことだった。
武装解除となった敗戦後の9月6日、積年の恨みが募った現地住民数十人の襲撃。当時校長だった義夫さんが隠し持っていた日本刀で応戦したが、銃撃を受け重傷を負い、10日後、帰らぬ人となった。
10月初旬、開拓団の逃避行が始まり、貨車の一種・無蓋(がい)車を乗り継いで南下することに。移動中、飢えと寒さで人が倒れていくなか、入植後に生まれた妹のみのりちゃん(3)、恵ちゃん(1)が亡くなった。
そして12月、弟の拓君(5)も息を引き取った。みんな遺骨を持ち帰ることはできなかった。
予土阿村開拓団の死者数は129人で、ほとんどが学齢以下の子ども。開拓団全体では8万人が寒さや集団自決で亡くなったとされる。「国からの支援はなく、本当に帰れるのか不安だった」
細谷さんと母・さえ子さん、姉・幸さんは46年7月に帰国。しかし数年後、さえ子さんが腸結核で亡くなった。細谷さんは、高校生ぐらいまでは亡くなった5人が夢に出てきて胸が締め付けられたという。「今では夢に出てくることはないが、忘れることはない」。
【記事全文を読む↓】
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e52eb6793ac5ea0f5c39a4ee7fcfe5bce6ec69d
8/9(水) 12:07配信 両丹日日新聞
1945年8月15日、日本の敗戦で終結となった第二次世界大戦。「私たちにとってはこの日が戦争の始まりだった」。そう語るのは国策のもと、満蒙開拓団として送り込まれた旧満州(中国東北部)からの引き揚げ者、京都府福知山市の細谷陽一さん(87)。戦後の混乱の中で失った家族の名が刻まれた墓標を前に、当時を回顧する。
細谷さんは1939年に満州北部の北安省に渡り、愛媛、高知、徳島3県出身者で構成された「予土阿村開拓団」の一員として、両親と姉の4人で入植。師範学校を卒業し、開拓団の子どもたちが通う在満国民学校の教師として渡った父・義夫さんに連れられてのことだった。
武装解除となった敗戦後の9月6日、積年の恨みが募った現地住民数十人の襲撃。当時校長だった義夫さんが隠し持っていた日本刀で応戦したが、銃撃を受け重傷を負い、10日後、帰らぬ人となった。
10月初旬、開拓団の逃避行が始まり、貨車の一種・無蓋(がい)車を乗り継いで南下することに。移動中、飢えと寒さで人が倒れていくなか、入植後に生まれた妹のみのりちゃん(3)、恵ちゃん(1)が亡くなった。
そして12月、弟の拓君(5)も息を引き取った。みんな遺骨を持ち帰ることはできなかった。
予土阿村開拓団の死者数は129人で、ほとんどが学齢以下の子ども。開拓団全体では8万人が寒さや集団自決で亡くなったとされる。「国からの支援はなく、本当に帰れるのか不安だった」
細谷さんと母・さえ子さん、姉・幸さんは46年7月に帰国。しかし数年後、さえ子さんが腸結核で亡くなった。細谷さんは、高校生ぐらいまでは亡くなった5人が夢に出てきて胸が締め付けられたという。「今では夢に出てくることはないが、忘れることはない」。
【記事全文を読む↓】
https://news.yahoo.co.jp/articles/9e52eb6793ac5ea0f5c39a4ee7fcfe5bce6ec69d
8歳で一人異国に残され…母の遺体を運びながら「生きてやる」86歳の戦災孤児が描く絵本 次世代に「家族を、今を大切に」と伝えたい
8/20(日) 16:02配信 FNNプライムオンライン
アジア・太平洋戦争の終戦から78年。終戦の直後、8歳の子供が家族を失って孤児になり、路上生活を強いられた。どうやって生き延びたのか…その過酷な体験を次世代に伝えたいと京都府の86歳男性が描いた絵本がある。
京都府亀岡市の黒田雅夫(くろだ・まさお)さん(86)。この日、初めて自分の絵本を手にした。
戦争のさなか、黒田さんの家族は、今の中国にあった「満州」に移り住んだ。満州を支配していた日本の政府は、開拓団を募集し、約27万人が移住した。
満州に行ってから、お父さんに3回目の召集令状が届いた。
雅夫さん:
お父さんはどこへ行くの?
雅夫さんの母:
兵隊に行くのよ
雅夫さん:
すぐに帰ってくるの?
雅夫さんの質問に母は答えなかった。8歳の雅夫さんと5歳の弟、お母さん、おじいさんが残された。
1945年、戦争が終わる直前に、敵の国が満州に攻めてきた。
雅夫さんの母:
雅夫、逃げるよ!静かに歩くのよ!
人々は、300km以上を歩いて逃げた。食べ物はほとんどなく、たくさんの人が亡くなった。
1カ月後、たどり着いたのは難民の収容所。ここでも食べ物は少ししか配られず、遺体が山のようになっていた。黒田さんのおじいさんもここで亡くなった。
お母さんも寝たきりになり、幼い弟は中国人に預けられた。
ある日、お母さんが起き上がって、ご飯を作ってくれた。
雅夫さんの母:
もっと、もっと食べなさい
次の日の朝、お母さんは冷たくなっていた。32歳だった。やせ細った遺体を運びながら、黒田さんは「生きてやる」と強く思った。
ひとりぼっちになった雅夫さんは、収容所から逃げた。親のいない子供は売られてしまうといわれていたからだ。路上で生活し、毎日寝る場所を変えた。ごみの中から食べ物を探したり、中国人がくれたものを食べたりした。
2カ月ほどたち、キリスト教の教会の人に保護された。そして、一人だけ日本に帰った。
家族を大切に、今を大切に、生きてほしいと願いを込めた絵本。黒田さんの絵本「今を生きる」は、2023年秋から販売する予定だ。
【記事全文を読む↓】
https://news.yahoo.co.jp/articles/fb7caf62074745c17fb7217548f8ba0b74e27811
8/20(日) 16:02配信 FNNプライムオンライン
アジア・太平洋戦争の終戦から78年。終戦の直後、8歳の子供が家族を失って孤児になり、路上生活を強いられた。どうやって生き延びたのか…その過酷な体験を次世代に伝えたいと京都府の86歳男性が描いた絵本がある。
京都府亀岡市の黒田雅夫(くろだ・まさお)さん(86)。この日、初めて自分の絵本を手にした。
戦争のさなか、黒田さんの家族は、今の中国にあった「満州」に移り住んだ。満州を支配していた日本の政府は、開拓団を募集し、約27万人が移住した。
満州に行ってから、お父さんに3回目の召集令状が届いた。
雅夫さん:
お父さんはどこへ行くの?
雅夫さんの母:
兵隊に行くのよ
雅夫さん:
すぐに帰ってくるの?
雅夫さんの質問に母は答えなかった。8歳の雅夫さんと5歳の弟、お母さん、おじいさんが残された。
1945年、戦争が終わる直前に、敵の国が満州に攻めてきた。
雅夫さんの母:
雅夫、逃げるよ!静かに歩くのよ!
人々は、300km以上を歩いて逃げた。食べ物はほとんどなく、たくさんの人が亡くなった。
1カ月後、たどり着いたのは難民の収容所。ここでも食べ物は少ししか配られず、遺体が山のようになっていた。黒田さんのおじいさんもここで亡くなった。
お母さんも寝たきりになり、幼い弟は中国人に預けられた。
ある日、お母さんが起き上がって、ご飯を作ってくれた。
雅夫さんの母:
もっと、もっと食べなさい
次の日の朝、お母さんは冷たくなっていた。32歳だった。やせ細った遺体を運びながら、黒田さんは「生きてやる」と強く思った。
ひとりぼっちになった雅夫さんは、収容所から逃げた。親のいない子供は売られてしまうといわれていたからだ。路上で生活し、毎日寝る場所を変えた。ごみの中から食べ物を探したり、中国人がくれたものを食べたりした。
2カ月ほどたち、キリスト教の教会の人に保護された。そして、一人だけ日本に帰った。
家族を大切に、今を大切に、生きてほしいと願いを込めた絵本。黒田さんの絵本「今を生きる」は、2023年秋から販売する予定だ。
【記事全文を読む↓】
https://news.yahoo.co.jp/articles/fb7caf62074745c17fb7217548f8ba0b74e27811
満州からの過酷な引き揚げ体験、絵本に 黒田雅夫さん
9/2(土) 13:30配信 産経新聞
先の大戦で開拓団として移住した旧満州(現中国東北部)で戦災孤児となり、帰国するまでの体験をまとめた絵本「今を生きる 満州からの引き上げの記録」を出版した。「戦争を知らない若い人に、絵本を残せることがうれしい」と語る。
7歳だった昭和19年6月、父母と弟の4人で京都市で結成された「廟嶺(びょうれい)京都開拓団」に参加し、中国・吉林省へ入植した。ところが20年6月、父の幸次さんに3回目の召集令状(赤紙)が届いた。「すでに2回の召集を受けて兵役を免れていたはずだったが、それほど切羽詰まっていた」と当時の戦況を振り返る。
同年8月には日本敗戦の噂が広がり、同月9日に旧ソ連が旧満州への侵攻を開始。略奪が横行し、治安が悪化する中、近くの別の開拓団と合流し、およそ500人で約300キロ離れた撫順(ぶじゅん)の引き揚げ者収容所を目指すことになった。
慢性的な食糧不足の中、徒歩と鉄道での逃避行は過酷を極め、途中で立ち寄った吉林の劇場跡では金品を狙って侵入した旧ソ連兵が機関銃を乱射。死んだふりをしてやり過ごしたという。
同年9月末ごろに収容所に到着したが、母のしずゑさんは弟を現地の中国人に預けた後、21年1月に亡くなった。母の遺体を安置して収容所に戻ると、衣類や持ち物がなくなっていた。「このままでは売り飛ばされると思い、収容所を飛び出した。キリスト教のシスターに保護され、引き揚げ船に乗ることになりました」。帰国がかなったのは21年7月。入植から2年が経過していた。
生き別れだった父はシベリア抑留を経て22年に帰国。中国残留孤児の弟も平成元年に帰国したが、「『置いて行かれた』というわだかまりがある」と今も戦争が残した傷に苦しんでいる。
15年ほど前から亀岡市内の小中学校に出向き、引き揚げの体験を語り部として伝える一方、当時の体験を約60枚の絵にした。引き揚げの体験のほか、当時の暮らし、収容所を逃げ出してからの路上生活などを朴訥(ぼくとつ)な線で描いている。
ロシアのウクライナ侵略に心を痛める。戦場の悲惨さは、かつての満州での体験と何も変わっていない。「若い人たちに読んでもらいたい。特に親子で一緒に読んでほしい」。絵本を通じて平和の尊さを伝える。(平岡康彦)
くろだ・まさお 昭和12年、旧河原林村(現亀岡市)生まれ、86歳。7歳の時に開拓団として両親とともに旧満州へわたったが、敗戦後に家族を失い、苦難の末に帰国した。クラウドファンディングで資金を調達し、入植から帰国までの2年間を絵本にまとめ、図書館などへの寄付を予定している。
【記事全文を読む↓】
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac3b81daf4ec6026904593cda40f7bd1ac468f61
※「今を生きる 満州からの引き上げの記録」
9/2(土) 13:30配信 産経新聞
先の大戦で開拓団として移住した旧満州(現中国東北部)で戦災孤児となり、帰国するまでの体験をまとめた絵本「今を生きる 満州からの引き上げの記録」を出版した。「戦争を知らない若い人に、絵本を残せることがうれしい」と語る。
7歳だった昭和19年6月、父母と弟の4人で京都市で結成された「廟嶺(びょうれい)京都開拓団」に参加し、中国・吉林省へ入植した。ところが20年6月、父の幸次さんに3回目の召集令状(赤紙)が届いた。「すでに2回の召集を受けて兵役を免れていたはずだったが、それほど切羽詰まっていた」と当時の戦況を振り返る。
同年8月には日本敗戦の噂が広がり、同月9日に旧ソ連が旧満州への侵攻を開始。略奪が横行し、治安が悪化する中、近くの別の開拓団と合流し、およそ500人で約300キロ離れた撫順(ぶじゅん)の引き揚げ者収容所を目指すことになった。
慢性的な食糧不足の中、徒歩と鉄道での逃避行は過酷を極め、途中で立ち寄った吉林の劇場跡では金品を狙って侵入した旧ソ連兵が機関銃を乱射。死んだふりをしてやり過ごしたという。
同年9月末ごろに収容所に到着したが、母のしずゑさんは弟を現地の中国人に預けた後、21年1月に亡くなった。母の遺体を安置して収容所に戻ると、衣類や持ち物がなくなっていた。「このままでは売り飛ばされると思い、収容所を飛び出した。キリスト教のシスターに保護され、引き揚げ船に乗ることになりました」。帰国がかなったのは21年7月。入植から2年が経過していた。
生き別れだった父はシベリア抑留を経て22年に帰国。中国残留孤児の弟も平成元年に帰国したが、「『置いて行かれた』というわだかまりがある」と今も戦争が残した傷に苦しんでいる。
15年ほど前から亀岡市内の小中学校に出向き、引き揚げの体験を語り部として伝える一方、当時の体験を約60枚の絵にした。引き揚げの体験のほか、当時の暮らし、収容所を逃げ出してからの路上生活などを朴訥(ぼくとつ)な線で描いている。
ロシアのウクライナ侵略に心を痛める。戦場の悲惨さは、かつての満州での体験と何も変わっていない。「若い人たちに読んでもらいたい。特に親子で一緒に読んでほしい」。絵本を通じて平和の尊さを伝える。(平岡康彦)
くろだ・まさお 昭和12年、旧河原林村(現亀岡市)生まれ、86歳。7歳の時に開拓団として両親とともに旧満州へわたったが、敗戦後に家族を失い、苦難の末に帰国した。クラウドファンディングで資金を調達し、入植から帰国までの2年間を絵本にまとめ、図書館などへの寄付を予定している。
【記事全文を読む↓】
https://news.yahoo.co.jp/articles/ac3b81daf4ec6026904593cda40f7bd1ac468f61
※「今を生きる 満州からの引き上げの記録」
【戦後76年】終戦後に始まった苦難 旧満州に送り込まれた10代の若者たち
「見捨てられたという一言に尽きる」…逃避行 栄養失調で倒れる仲間
2021年08月11日
京都市に住む92歳の村尾孝さん・・
村尾さんが満州に送り込まれたのは、1945年4月。
16歳で東京農業大学に繰り上げ入学した直後のことでした。
当時、東京農業大学は、ソ連との国境付近に、「報国農場」と呼ばれる農場を開設していました。「報国農場」とは、戦争末期、食料の増産などを目的に満州の開拓団の農場の近くにつくられたもので、全国の府県や農業団体などに、政府公認の農場を割り当てる、というものでした。村尾さんは、1日も授業を受けることのないまま、大学から満州への派遣を告げられたのです。
荒れ果てた大地を耕す日々が4カ月ほど続いた1945年8月9日、事態が動きます。
ソ連軍が国境を超え、侵攻してきたのです。
村尾さんたち学生は、ソ連軍や現地の暴徒に攻撃されながら、山の中をひたすら歩いて逃げ続けるしかありませんでした。逃避行が始まって約1カ月後の9月7日、たまたま出会った関東軍の将校から聞かされたのが終戦の事実。戦争が終わったことも分からず、逃げ続けていたことを知った瞬間でした。
その後、難民収容所へ移ると、さらなる苦難が待っていました。
アワのおかゆが1日2回のみという食事に、劣悪な生活環境。
帰国をともに夢見た同級生たちが、栄養失調で次々と死んでいきました。
同級生の遺体は、穴を掘って投げ込むことしかできませんでした。
【村尾孝さん】
「(隣で寝ていた同級生が)冷たくなったのに気づくのが、今までいっぱいたかっていたシラミが、冷たい死体から温かい方へ行きますから、隣の寝ている人の方へ、それで分かる。死んでると。死んで硬直して、死に化粧もしてやれない。霜がね降りて、白く霜が降りて、それがせめてもの死に化粧なんですかね」
大阪府富田林市に住む藤後博巳さん(92)・・
学校の教師に熱心に勧誘され、自ら志願して、満州の開拓や国境警備を担う「満蒙開拓青少年義勇軍」として14歳で満州に渡りました。満州へ行き、「一旗あげる」思いだったといいます。
終戦を迎えたのは16歳の時。年齢が低く、かろうじてシベリア抑留は免れましたが、たどり着いた難民収容所では、飢えと伝染病が待っていました。「このままでは死んでしまう」と、仕事を求めて中国人のもとを訪ね歩きました。
【藤後博巳さん】
「とにかくあてもなく中国人の家を訪れて、なんでもするから食べさせてくれ、寝かせてくれ、給料はいらないと中国人の家に頼むんですね。たまたま、中華料理店の主人が『子どもには戦争の責任がない』という気持ちで快く引き受けてくれたんですね。私にしたら、命の恩人です。もしそこで、中国人の救助の手が差し伸べられてなかったら、私はその冬に死んでたでしょうね」
その後、藤後さんは、中国共産党の軍隊、「八路軍」に強制的に入隊させられ、衛生兵として、中国国内で国民党と共産党が戦った内戦、国共内戦を戦わざるを得なくなりました。戦場で銃弾が飛び交う中、負傷者を担架に乗せて運ぶこともありました。
帰国できたのは、1955年のこと。
すでに25歳になっていました。
【藤後博巳さん】
「敗戦と同時に多くの人たちが満州に置き去りにされた、当時の棄民政策ですね。そういう、終戦の年に皆さんが日本に帰れたら、こんな大きな犠牲は伴わなかったと私は思います。見捨てられたという一言に尽きますね」
【記事全文を読む↓】
https://www.ktv.jp/news/feature/210811/
カンテレ「報道ランナー」8月11日放送
「見捨てられたという一言に尽きる」…逃避行 栄養失調で倒れる仲間
2021年08月11日
京都市に住む92歳の村尾孝さん・・
村尾さんが満州に送り込まれたのは、1945年4月。
16歳で東京農業大学に繰り上げ入学した直後のことでした。
当時、東京農業大学は、ソ連との国境付近に、「報国農場」と呼ばれる農場を開設していました。「報国農場」とは、戦争末期、食料の増産などを目的に満州の開拓団の農場の近くにつくられたもので、全国の府県や農業団体などに、政府公認の農場を割り当てる、というものでした。村尾さんは、1日も授業を受けることのないまま、大学から満州への派遣を告げられたのです。
荒れ果てた大地を耕す日々が4カ月ほど続いた1945年8月9日、事態が動きます。
ソ連軍が国境を超え、侵攻してきたのです。
村尾さんたち学生は、ソ連軍や現地の暴徒に攻撃されながら、山の中をひたすら歩いて逃げ続けるしかありませんでした。逃避行が始まって約1カ月後の9月7日、たまたま出会った関東軍の将校から聞かされたのが終戦の事実。戦争が終わったことも分からず、逃げ続けていたことを知った瞬間でした。
その後、難民収容所へ移ると、さらなる苦難が待っていました。
アワのおかゆが1日2回のみという食事に、劣悪な生活環境。
帰国をともに夢見た同級生たちが、栄養失調で次々と死んでいきました。
同級生の遺体は、穴を掘って投げ込むことしかできませんでした。
【村尾孝さん】
「(隣で寝ていた同級生が)冷たくなったのに気づくのが、今までいっぱいたかっていたシラミが、冷たい死体から温かい方へ行きますから、隣の寝ている人の方へ、それで分かる。死んでると。死んで硬直して、死に化粧もしてやれない。霜がね降りて、白く霜が降りて、それがせめてもの死に化粧なんですかね」
大阪府富田林市に住む藤後博巳さん(92)・・
学校の教師に熱心に勧誘され、自ら志願して、満州の開拓や国境警備を担う「満蒙開拓青少年義勇軍」として14歳で満州に渡りました。満州へ行き、「一旗あげる」思いだったといいます。
終戦を迎えたのは16歳の時。年齢が低く、かろうじてシベリア抑留は免れましたが、たどり着いた難民収容所では、飢えと伝染病が待っていました。「このままでは死んでしまう」と、仕事を求めて中国人のもとを訪ね歩きました。
【藤後博巳さん】
「とにかくあてもなく中国人の家を訪れて、なんでもするから食べさせてくれ、寝かせてくれ、給料はいらないと中国人の家に頼むんですね。たまたま、中華料理店の主人が『子どもには戦争の責任がない』という気持ちで快く引き受けてくれたんですね。私にしたら、命の恩人です。もしそこで、中国人の救助の手が差し伸べられてなかったら、私はその冬に死んでたでしょうね」
その後、藤後さんは、中国共産党の軍隊、「八路軍」に強制的に入隊させられ、衛生兵として、中国国内で国民党と共産党が戦った内戦、国共内戦を戦わざるを得なくなりました。戦場で銃弾が飛び交う中、負傷者を担架に乗せて運ぶこともありました。
帰国できたのは、1955年のこと。
すでに25歳になっていました。
【藤後博巳さん】
「敗戦と同時に多くの人たちが満州に置き去りにされた、当時の棄民政策ですね。そういう、終戦の年に皆さんが日本に帰れたら、こんな大きな犠牲は伴わなかったと私は思います。見捨てられたという一言に尽きますね」
【記事全文を読む↓】
https://www.ktv.jp/news/feature/210811/
カンテレ「報道ランナー」8月11日放送
「自分の子どもを『1、2の3』と川に捨てた」皆、正気ではなかった
…7歳の少女が目にした戦争の惨劇
テレビユー山形 2023年8月16日
山形県鶴岡市に住む齋藤幸子さん。84歳。
7歳の時、満洲で戦争を経験しました。
太平洋戦争に突入すると、父親が戦死。さらに、生活を一変させる出来事が。
―1945年(昭和20年)8月9日 ソ連軍満洲侵攻
齋藤幸子さん「突然だった。突然『逃げろ』と。『今危ないから逃げなくてはならない』というので」家族5人で2台の馬車に乗って逃げましたが…。
齋藤幸子さん「発砲される。馬に(銃弾が)ドーンと当たって馬車ごと倒れた」
幸子さんと母親、弟の無事は確認できましたが、2人の妹は行方不明に。
齋藤幸子さん「(次の日の朝)日本兵だと思うが、6歳と4歳の女の子。妹を連れてきた。全部傷だらけで、息絶え絶えの妹たちが来て、『誰か親いるのか』と言われて」
その後、妹2人は、逃走中の山中で息を引き取りました。
齋藤幸子さん「我々も人間も動物も全部撃たれているから、全部死体ばかり。死体の上を歩きながら」
食べるものもなく飢餓状態の3人。
母乳が出ない母親、泣きじゃくる8か月の弟。
齋藤幸子さん「子どもが泣く。そうすると泣く音に対して発砲するのがわかるから、誰かが誘導したとみえて『この子どもたちを始末した方がいい』ということで、この川に、滝に(子どもたちを)捨てようということになった」
(Q自分のお子さんを?)
「そうです。自分の子どもを『1、2の3』と川に捨てた」
思い返すと、皆、正気ではなかったと話す幸子さん。
今でも思い残すことは。
齋藤幸子さん「着物が浮いて見えた。(弟の)洋一と名札がついていたので、『洋一だ洋一だ』って。助からないとわかりながらも『洋一だ』って。弟に対して申し訳ない。申し訳ないという気持ちがいまだにもちろんのこと、一生離れない」
家族が次々と命を落とす中、ソ連兵に銃を突きつけられながら収容所への連行、極寒と食糧不足などで生死をさまよいながら、母親と2人、1年余りの逃避行を終え、何とか山形に帰ることができました。
【記事全文を読む↓】
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/664388?display=1
…7歳の少女が目にした戦争の惨劇
テレビユー山形 2023年8月16日
山形県鶴岡市に住む齋藤幸子さん。84歳。
7歳の時、満洲で戦争を経験しました。
太平洋戦争に突入すると、父親が戦死。さらに、生活を一変させる出来事が。
―1945年(昭和20年)8月9日 ソ連軍満洲侵攻
齋藤幸子さん「突然だった。突然『逃げろ』と。『今危ないから逃げなくてはならない』というので」家族5人で2台の馬車に乗って逃げましたが…。
齋藤幸子さん「発砲される。馬に(銃弾が)ドーンと当たって馬車ごと倒れた」
幸子さんと母親、弟の無事は確認できましたが、2人の妹は行方不明に。
齋藤幸子さん「(次の日の朝)日本兵だと思うが、6歳と4歳の女の子。妹を連れてきた。全部傷だらけで、息絶え絶えの妹たちが来て、『誰か親いるのか』と言われて」
その後、妹2人は、逃走中の山中で息を引き取りました。
齋藤幸子さん「我々も人間も動物も全部撃たれているから、全部死体ばかり。死体の上を歩きながら」
食べるものもなく飢餓状態の3人。
母乳が出ない母親、泣きじゃくる8か月の弟。
齋藤幸子さん「子どもが泣く。そうすると泣く音に対して発砲するのがわかるから、誰かが誘導したとみえて『この子どもたちを始末した方がいい』ということで、この川に、滝に(子どもたちを)捨てようということになった」
(Q自分のお子さんを?)
「そうです。自分の子どもを『1、2の3』と川に捨てた」
思い返すと、皆、正気ではなかったと話す幸子さん。
今でも思い残すことは。
齋藤幸子さん「着物が浮いて見えた。(弟の)洋一と名札がついていたので、『洋一だ洋一だ』って。助からないとわかりながらも『洋一だ』って。弟に対して申し訳ない。申し訳ないという気持ちがいまだにもちろんのこと、一生離れない」
家族が次々と命を落とす中、ソ連兵に銃を突きつけられながら収容所への連行、極寒と食糧不足などで生死をさまよいながら、母親と2人、1年余りの逃避行を終え、何とか山形に帰ることができました。
【記事全文を読む↓】
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/664388?display=1
過去の記事より抜粋です・・
-------------------------------------------------------
年の瀬も反戦歌い継ぐ
2023年12月27日 06時52分 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/298374
・・ドラマは旧満州(中国東北部)で終戦を迎えた日本人孤児たちの過酷な生活を描いた「遠い約束〜星になったこどもたち」。旧ソ連軍侵攻後、氷点下30度になる寒さと飢え、病気も加わり、旧満州の日本人犠牲者は軍民合わせて24万5千人とされている。
・・原作者は、2020年に亡くなった小田原市の元教師、増田昭一さん。17歳の時に現地の難民収容所で5カ月間、60人以上の孤児の死をみとった。体験をつづった著書「満州の星くずと散った子供たちの遺書」(夢工房)を含む3冊がドラマ化され、14年にTBS系で放送された。
増田さんによると、中国残留孤児になれたのはごく一部で、多くは誰にも助けられなかった。町で自分の靴下とラーメンを物々交換したさんちゃん、そのラーメンを譲ってもらった親友、「お母さんに会いたかったらおへそをみなさい。きっとお母さんの顔がみえるから」と語った母の遺言を守り続けたともちゃんは、いずれも命を落としたという。生前の取材に「最期まで愛情と思いやり、優しさと分かち合いの心を保ったまま死んだ孤児たちがいたことを知ってほしい」と訴えていた。
-------------------------------------------------------
年の瀬も反戦歌い継ぐ
2023年12月27日 06時52分 東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/298374
・・ドラマは旧満州(中国東北部)で終戦を迎えた日本人孤児たちの過酷な生活を描いた「遠い約束〜星になったこどもたち」。旧ソ連軍侵攻後、氷点下30度になる寒さと飢え、病気も加わり、旧満州の日本人犠牲者は軍民合わせて24万5千人とされている。
・・原作者は、2020年に亡くなった小田原市の元教師、増田昭一さん。17歳の時に現地の難民収容所で5カ月間、60人以上の孤児の死をみとった。体験をつづった著書「満州の星くずと散った子供たちの遺書」(夢工房)を含む3冊がドラマ化され、14年にTBS系で放送された。
増田さんによると、中国残留孤児になれたのはごく一部で、多くは誰にも助けられなかった。町で自分の靴下とラーメンを物々交換したさんちゃん、そのラーメンを譲ってもらった親友、「お母さんに会いたかったらおへそをみなさい。きっとお母さんの顔がみえるから」と語った母の遺言を守り続けたともちゃんは、いずれも命を落としたという。生前の取材に「最期まで愛情と思いやり、優しさと分かち合いの心を保ったまま死んだ孤児たちがいたことを知ってほしい」と訴えていた。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
満州の星くずと散った子供たち 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-