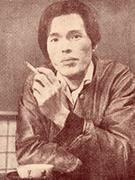28日、千日前のいちびり庵3階でのオダサク倶楽部読書会。図書館副館長の高橋さんが、織田作の直筆俳句、藤沢桓夫、長沖一、秋田実、小野十三郎、庄野英二、石浜恒夫等が参加する浅沢句会のことを、最近発見された句帳にみる俳句を紹介されながら話された。
織田作は、この句会に丈六の俳号で昭和15年から17年頃まで参加しており、その代表作が 「行き暮れてここが思案の善哉かな」で、彼が『夫婦善哉』を発表した翌年の作。
当句は、織田作17回忌を記念して建立された法善寺横町正弁丹吾亭前の句碑に記されているものだ。(昭和39年) しかも、これは画帳「星欄干」に記された織田作の直筆を写し取ったもの。(写真)
読書会では、どれが季語であるかや、この「善哉かな」の読み方や意味についても議論があった。前年発表の『夫婦善哉』にからめて、甘味の善哉を読んだように思われるが。
「木犀の雨をクンパルシータの女行く」の句は、亡き夫人のことを想い詠んだ句(昭和20年10月)だが、字余りはなはだしい。「御堂筋雨雨雨のジープ哉」も前句同様に横文字を用いて当時の俳句としては進取的で大胆だ。
この終戦直後に詠んだリズム感のある「御堂筋雨雨雨のジープ哉」は、焼跡の大阪の哀涙を雨雨雨で表し、進駐軍のジープが敗戦の象徴として配されている時世句であり、高く評価されよう。
織田作のいた三高の寮歌には与謝野鉄幹作「人を恋うる歌」があり、「石を抱きて野にうたう 芭蕉のさびを よろこばず」とあり、このような風土に育った織田作は、戦後を迎えてさらに、伝統的なわびさびの情緒や五七五の型を破る姿勢を表していると私はみる。
なお、芭蕉には「酔うて寝ん撫子咲ける石の上」があり、鉄幹はこの句から先の「芭蕉のさべをよろこばず」の歌を詠んだのかもしれない。
参考に、「おれの俳句は、久保田万太郎や、人事しか、よまん」と言っていた織田作の句会に参加した当時の句をいくつか挙げておこう。
春の宵ローレンスは杜で寝たか
月高く道なき道を往かん哉
鐘霞む丘を下りて初奉公
ろくろ首百足を啖う夜寒かな
轆轤首面やつれけり木犀花
俳句の本流から外れるが、『チャタレー夫人』の作者ローレンスやろくろ首を詠むあたり、異端ぶりがうかがえる。
織田作は、この句会に丈六の俳号で昭和15年から17年頃まで参加しており、その代表作が 「行き暮れてここが思案の善哉かな」で、彼が『夫婦善哉』を発表した翌年の作。
当句は、織田作17回忌を記念して建立された法善寺横町正弁丹吾亭前の句碑に記されているものだ。(昭和39年) しかも、これは画帳「星欄干」に記された織田作の直筆を写し取ったもの。(写真)
読書会では、どれが季語であるかや、この「善哉かな」の読み方や意味についても議論があった。前年発表の『夫婦善哉』にからめて、甘味の善哉を読んだように思われるが。
「木犀の雨をクンパルシータの女行く」の句は、亡き夫人のことを想い詠んだ句(昭和20年10月)だが、字余りはなはだしい。「御堂筋雨雨雨のジープ哉」も前句同様に横文字を用いて当時の俳句としては進取的で大胆だ。
この終戦直後に詠んだリズム感のある「御堂筋雨雨雨のジープ哉」は、焼跡の大阪の哀涙を雨雨雨で表し、進駐軍のジープが敗戦の象徴として配されている時世句であり、高く評価されよう。
織田作のいた三高の寮歌には与謝野鉄幹作「人を恋うる歌」があり、「石を抱きて野にうたう 芭蕉のさびを よろこばず」とあり、このような風土に育った織田作は、戦後を迎えてさらに、伝統的なわびさびの情緒や五七五の型を破る姿勢を表していると私はみる。
なお、芭蕉には「酔うて寝ん撫子咲ける石の上」があり、鉄幹はこの句から先の「芭蕉のさべをよろこばず」の歌を詠んだのかもしれない。
参考に、「おれの俳句は、久保田万太郎や、人事しか、よまん」と言っていた織田作の句会に参加した当時の句をいくつか挙げておこう。
春の宵ローレンスは杜で寝たか
月高く道なき道を往かん哉
鐘霞む丘を下りて初奉公
ろくろ首百足を啖う夜寒かな
轆轤首面やつれけり木犀花
俳句の本流から外れるが、『チャタレー夫人』の作者ローレンスやろくろ首を詠むあたり、異端ぶりがうかがえる。
|
|
|
|
|
|
|
|
織田作之助 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
織田作之助のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人