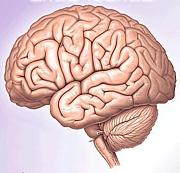●岐阜脳卒中リハビリテーション研究会主催●
●第9回定期勉強会のお知らせ● ※終了いたしました
【テーマ】
高次脳機能と運動療法
【日時】
H23年8月30日(火)
18:30〜20:30(予定)
【内容】
重症脳卒中患者様を目の前にし、一体自分は何に難渋しているのかを、ふと考えます。
そんな時気付かされることは重症麻痺の程度のみならず、高頻度に併発している高次脳機能障害の存在です。
しかし表面だけを観察し、やれ「注意障害」だ、などと決まり決まった、
いわゆる“定義”や“概念”を目の前の患者様に当てはめても、それだけでは根本的治療には結び付きません。
果たして、今自分の目の前で起こっている摩訶不思議な症状、
つまり高次脳機能障害はどんな脳の仕組みで起こっているのか。
今回は前頭前野から頭頂連合野、高次視覚野さらには海馬まで、
高次脳機能障害のそのメカニズムと、運動療法介入について学びます。
【プレゼンテーター】
坪井 祥一 PT
(医療法人社団友愛会 岩砂病院)
【場所】
医療法人社団友愛会 岩砂病院 3Fリハビリテーション室(岐阜市長良福光161-1)
【受講費】
無料
【解説】
?.高次脳機能と運動発現機序
運動発現をもう一度みてみると、高次脳機能との関わりをみることができます。
?まず意識・覚醒が脳幹上行性網様体賦活系から立ち上がり、脳幹・扁桃体・辺縁系・前頭前野眼窩部などにより“動くこと”への意欲・情動が発生されます。
そしてそれを受けた前頭前野は脳全体の覚度の水準(感度)を高めます。
?次に外界からの刺激(体性感覚・視空間感覚・言語聴覚情報等)がレセプターを通じて頭頂葉・後頭葉・側頭葉に入力されますが、
前頭前野背外側部・眼窩部が外部刺激の情報に注意を向け、時に干渉刺激に対しては抑制し、必要な情報であるかどうかを取捨選択します。
?そして、運動に必要な外部感覚刺激、内的欲求や、脳内に蓄積された過去の経験・記憶をもとに総合判断し、
前頭前野はその情報を運動前野・補足運動野に伝達します。
そこで運動の企画・計画が行なわれ、その後一次運動野にて、脊髄全角細胞に向かうインパルスを発射することになるわけです。
?この時、大脳基底核や小脳が運動の時間的・空間的な制御を行なっており、運動の量や質を精密にコントロールしています。
このように一つの運動に対し、脳全体が同時に関わっていることが分かります。
これを高次脳機能の側面から見てみると、どうなるのでしょうか。
(?’〜?’は上記のメカニズム?〜?に対応しています)
?’まず脳幹系・脳全体の問題としてを中心に意識障害や覚醒不良の問題、情動障害、注意の覚度・集中性の障害が生じる可能性があります。
?’頭頂葉・後頭葉・側頭葉の問題として外部から入力される情報自体がエラー、あるいは前頭前野による情報の統合障害が生じる可能性があります。
具体的には身体失認や半側空間無視、失行、構成障害、失語、視覚性失認などがあげれ、さらに注意の持続性や分配性の障害、抑制障害(保続)などが出現します。
?’そして間違った情報は間違った判断を下すため、前頭前野による判断能力が欠如し、遂行機能障害が生じる可能性があります。
また伝達先の補足運動野や運動前野の障害にて両手動作を円滑に使うことが出来なくなったり、運動の系列をうまく行なえなくなったりする可能性があります。
?’大脳基底核や小脳の障害にて、運動制御の障害や失調症などの運動麻痺+αの症状を呈するようになる可能性があります。
つまり一つの運動は脳全体が関わり合っている為、「今、目の前に見えているひとつの運動障害」も脳全体の障害の結果である、すなわち「すべての高次脳機能障害が同時に起こっている」可能性もあると、考えることも出来るのです。
?.高次脳機能の階層性
このように難渋する症例は、多くの高次脳機能障害を併発しています。
臨床においても、一体それらは、どれが最も重要な問題点なのか、迷うことがあるように思います。
その時重要になってくる考え方の一つとして「優先順位を決める」ということです。
つまり高次脳機能の「階層性」を知ると、その仕組みを理解することができます。
高次脳機能の階層性は底面から覚醒・覚度→注意・状況判断・記憶・言語→要素的認知(身体・空間・物体)となっていると考えられます。
つまり、底面にある覚醒、注意や状況判断、記憶などが不良であると、その上位にある要素的認知能力は、より助長されて障害される可能性が高いということです。
高次脳機能を評価する場合には、この階層性が常に関わり合っていることを認識した上で、空間的要素ばかりを評価するのではなく、根本的な基盤となる覚醒や注意、状況判断などを評価し、優先順位を決めて治療にあたる必要があると考えられます。
?.高次脳機能と運動療法
これらを踏まえた上で、具体的にはどのように運動療法を展開すればよいのか、一つの考えを示していきます。
1.身体能力を確保した上で高次脳機能をみる
重度の高次脳機能障害にとらわれるあまり、改善可能な身体機能が獲得できないことが多くあるように思われます。
これは身体的な廃用症候群を招き、その結果、精神面の廃用を招くのは明らかであるように思います。
患者様は次第に能動性を失い、更なる機能低下、高次脳機能障害の重篤化を引き起こしかねない状況に至ります。
よってまずは、積極的な身体能力の改善であり、それはつまり立位・歩行を中心とした抗重力姿勢保持訓練以外、他にはないと考えられます。
その後、身体能力が確保され、患者様自身の能動性や気づきが生まれてから、要素的な高次脳機能障害に目を向けても遅くはないと思われますし、
多くの場合、その時には当初より高次脳機能が改善傾向にある状況も、経験的な範疇で“ある”と感じています。
2.要素的問題点よりも基盤的問題点に目を向ける
高次脳機能の階層性を構成する各機能とその関係性を理解することが重要です。
高次脳機能の階層性は底面から覚醒・覚度→注意・状況判断・記憶・言語→要素的認知(身体・空間・物体)となっていると考えています。
すなわち、底面にある覚醒、注意や状況判断、記憶などが不良であると、その上位にある要素的認知能力は、本来の障害度よりも、さらに助長されて障害される可能性が高いということです。
これが、半側空間無視や、失行などの症状を目に付きやすくし、問題点を複雑化させている原因の一つです。
逆に、覚醒・注意・状況判断が出来ている患者様は空間的認知問題も、ADLの自然な流れの中で対処してしまっている可能性があることからも、この「階層性」理論の考え方は大変重要であるように思います。
まずは表面的な要素的問題よりも、基盤となる問題に着目し、根本的な問題点に対し、アプローチしていく治療プロセスが重要であると考えられます。
3.生きているモダリティを活用した運動療法の構築
◎意識障害・覚度の低下・重度の注意障害がある場合◎
・長下肢装具を用い、とにかく立位・歩行を中心とした抗重力訓練を行なうことを求めます。
・これは足底からの感覚入力(識別性・非識別性)
→小脳・網様体脊髄路の無意識的姿勢制御と意識の賦活化
→視床AN・DMを経由し大脳へ、意識・注意の活性化
→前頭前野・辺縁系の活性化により運動学習される、
このメカニズムからも大変重要であると考えられます。
・なによりも「身体の廃用症候群=脳全体の不活性」が改善されなければ、
高次脳機能障害の改善はありえないと考えられます。
◎右片麻痺の場合◎
欠点(左脳の固有機能)として、
・言語指示を理解し、運動変換するのが苦手(失語)
・言語障害がなくても、言語を介する運動学習が苦手(失行)
・言語障害がなくても、論理的思考能力が低下する
・言語障害がなくても、計算が苦手
と臨床的に感じる場合が多いように思われます。
逆に利点(右脳の固有機能)として、
・状況判断能力に優れている(非言語コミュニケーション)
・空間認識能力・身体図式が保たれていることが多い
・自己認識・病識が保たれていることが多い
つまり利点を生かした運動療法の方略として、
・言語的要素以外のモダリティを入力するよう心がける
・具体的には「見せて真似させる」
「文字に書いて読ませる」
「抑揚・表情や視線、指差し、ジェスチャーで示す」
「ハンドリングを有効に使い体感させる」
が望ましいと考えています。
◎左片麻痺の場合◎
欠点(右脳の固有機能)として、
・空間認識能力・身体図式が大きく崩れていることが多い
・自己認識・病識が崩れていることが多い
・表面的な言語理解は保たれるが裏に含まれる心理状況を読めない
・言語に執着し、物事を非常に細かく捕らえすぎる傾向にある
・理屈っぽくなり、表面的な問題に固執しやすい
と臨床的に感じる場合が多いように思われます。
逆に利点(左脳の固有機能)として、
・言語そのものは保たれ、文章的事項は分かっている
・要素的(言語)記憶が保たれていることが多い
・律儀な性格になりやすい傾向にある
と臨床的に感じる場合が多いように思われます。
つまり利点を生かした運動療法の方略として、
・要素的記憶と言語機能が比較的保たれ、律儀な性格にある傾向を逆手に取り、
患者とセラピスト間でのルールを定め、習慣的な能動性を引き出す
・空間・自己認識能力に劣り、全般的な注意障害を伴うことが多い傾向にあるため、
症例にとって興味のある(情動)、引き付ける視覚的注意要素を模索し、
動作をパターン化させる
ことが望ましいと考えています。
【文責 坪井祥一】
●第9回定期勉強会のお知らせ● ※終了いたしました
【テーマ】
高次脳機能と運動療法
【日時】
H23年8月30日(火)
18:30〜20:30(予定)
【内容】
重症脳卒中患者様を目の前にし、一体自分は何に難渋しているのかを、ふと考えます。
そんな時気付かされることは重症麻痺の程度のみならず、高頻度に併発している高次脳機能障害の存在です。
しかし表面だけを観察し、やれ「注意障害」だ、などと決まり決まった、
いわゆる“定義”や“概念”を目の前の患者様に当てはめても、それだけでは根本的治療には結び付きません。
果たして、今自分の目の前で起こっている摩訶不思議な症状、
つまり高次脳機能障害はどんな脳の仕組みで起こっているのか。
今回は前頭前野から頭頂連合野、高次視覚野さらには海馬まで、
高次脳機能障害のそのメカニズムと、運動療法介入について学びます。
【プレゼンテーター】
坪井 祥一 PT
(医療法人社団友愛会 岩砂病院)
【場所】
医療法人社団友愛会 岩砂病院 3Fリハビリテーション室(岐阜市長良福光161-1)
【受講費】
無料
【解説】
?.高次脳機能と運動発現機序
運動発現をもう一度みてみると、高次脳機能との関わりをみることができます。
?まず意識・覚醒が脳幹上行性網様体賦活系から立ち上がり、脳幹・扁桃体・辺縁系・前頭前野眼窩部などにより“動くこと”への意欲・情動が発生されます。
そしてそれを受けた前頭前野は脳全体の覚度の水準(感度)を高めます。
?次に外界からの刺激(体性感覚・視空間感覚・言語聴覚情報等)がレセプターを通じて頭頂葉・後頭葉・側頭葉に入力されますが、
前頭前野背外側部・眼窩部が外部刺激の情報に注意を向け、時に干渉刺激に対しては抑制し、必要な情報であるかどうかを取捨選択します。
?そして、運動に必要な外部感覚刺激、内的欲求や、脳内に蓄積された過去の経験・記憶をもとに総合判断し、
前頭前野はその情報を運動前野・補足運動野に伝達します。
そこで運動の企画・計画が行なわれ、その後一次運動野にて、脊髄全角細胞に向かうインパルスを発射することになるわけです。
?この時、大脳基底核や小脳が運動の時間的・空間的な制御を行なっており、運動の量や質を精密にコントロールしています。
このように一つの運動に対し、脳全体が同時に関わっていることが分かります。
これを高次脳機能の側面から見てみると、どうなるのでしょうか。
(?’〜?’は上記のメカニズム?〜?に対応しています)
?’まず脳幹系・脳全体の問題としてを中心に意識障害や覚醒不良の問題、情動障害、注意の覚度・集中性の障害が生じる可能性があります。
?’頭頂葉・後頭葉・側頭葉の問題として外部から入力される情報自体がエラー、あるいは前頭前野による情報の統合障害が生じる可能性があります。
具体的には身体失認や半側空間無視、失行、構成障害、失語、視覚性失認などがあげれ、さらに注意の持続性や分配性の障害、抑制障害(保続)などが出現します。
?’そして間違った情報は間違った判断を下すため、前頭前野による判断能力が欠如し、遂行機能障害が生じる可能性があります。
また伝達先の補足運動野や運動前野の障害にて両手動作を円滑に使うことが出来なくなったり、運動の系列をうまく行なえなくなったりする可能性があります。
?’大脳基底核や小脳の障害にて、運動制御の障害や失調症などの運動麻痺+αの症状を呈するようになる可能性があります。
つまり一つの運動は脳全体が関わり合っている為、「今、目の前に見えているひとつの運動障害」も脳全体の障害の結果である、すなわち「すべての高次脳機能障害が同時に起こっている」可能性もあると、考えることも出来るのです。
?.高次脳機能の階層性
このように難渋する症例は、多くの高次脳機能障害を併発しています。
臨床においても、一体それらは、どれが最も重要な問題点なのか、迷うことがあるように思います。
その時重要になってくる考え方の一つとして「優先順位を決める」ということです。
つまり高次脳機能の「階層性」を知ると、その仕組みを理解することができます。
高次脳機能の階層性は底面から覚醒・覚度→注意・状況判断・記憶・言語→要素的認知(身体・空間・物体)となっていると考えられます。
つまり、底面にある覚醒、注意や状況判断、記憶などが不良であると、その上位にある要素的認知能力は、より助長されて障害される可能性が高いということです。
高次脳機能を評価する場合には、この階層性が常に関わり合っていることを認識した上で、空間的要素ばかりを評価するのではなく、根本的な基盤となる覚醒や注意、状況判断などを評価し、優先順位を決めて治療にあたる必要があると考えられます。
?.高次脳機能と運動療法
これらを踏まえた上で、具体的にはどのように運動療法を展開すればよいのか、一つの考えを示していきます。
1.身体能力を確保した上で高次脳機能をみる
重度の高次脳機能障害にとらわれるあまり、改善可能な身体機能が獲得できないことが多くあるように思われます。
これは身体的な廃用症候群を招き、その結果、精神面の廃用を招くのは明らかであるように思います。
患者様は次第に能動性を失い、更なる機能低下、高次脳機能障害の重篤化を引き起こしかねない状況に至ります。
よってまずは、積極的な身体能力の改善であり、それはつまり立位・歩行を中心とした抗重力姿勢保持訓練以外、他にはないと考えられます。
その後、身体能力が確保され、患者様自身の能動性や気づきが生まれてから、要素的な高次脳機能障害に目を向けても遅くはないと思われますし、
多くの場合、その時には当初より高次脳機能が改善傾向にある状況も、経験的な範疇で“ある”と感じています。
2.要素的問題点よりも基盤的問題点に目を向ける
高次脳機能の階層性を構成する各機能とその関係性を理解することが重要です。
高次脳機能の階層性は底面から覚醒・覚度→注意・状況判断・記憶・言語→要素的認知(身体・空間・物体)となっていると考えています。
すなわち、底面にある覚醒、注意や状況判断、記憶などが不良であると、その上位にある要素的認知能力は、本来の障害度よりも、さらに助長されて障害される可能性が高いということです。
これが、半側空間無視や、失行などの症状を目に付きやすくし、問題点を複雑化させている原因の一つです。
逆に、覚醒・注意・状況判断が出来ている患者様は空間的認知問題も、ADLの自然な流れの中で対処してしまっている可能性があることからも、この「階層性」理論の考え方は大変重要であるように思います。
まずは表面的な要素的問題よりも、基盤となる問題に着目し、根本的な問題点に対し、アプローチしていく治療プロセスが重要であると考えられます。
3.生きているモダリティを活用した運動療法の構築
◎意識障害・覚度の低下・重度の注意障害がある場合◎
・長下肢装具を用い、とにかく立位・歩行を中心とした抗重力訓練を行なうことを求めます。
・これは足底からの感覚入力(識別性・非識別性)
→小脳・網様体脊髄路の無意識的姿勢制御と意識の賦活化
→視床AN・DMを経由し大脳へ、意識・注意の活性化
→前頭前野・辺縁系の活性化により運動学習される、
このメカニズムからも大変重要であると考えられます。
・なによりも「身体の廃用症候群=脳全体の不活性」が改善されなければ、
高次脳機能障害の改善はありえないと考えられます。
◎右片麻痺の場合◎
欠点(左脳の固有機能)として、
・言語指示を理解し、運動変換するのが苦手(失語)
・言語障害がなくても、言語を介する運動学習が苦手(失行)
・言語障害がなくても、論理的思考能力が低下する
・言語障害がなくても、計算が苦手
と臨床的に感じる場合が多いように思われます。
逆に利点(右脳の固有機能)として、
・状況判断能力に優れている(非言語コミュニケーション)
・空間認識能力・身体図式が保たれていることが多い
・自己認識・病識が保たれていることが多い
つまり利点を生かした運動療法の方略として、
・言語的要素以外のモダリティを入力するよう心がける
・具体的には「見せて真似させる」
「文字に書いて読ませる」
「抑揚・表情や視線、指差し、ジェスチャーで示す」
「ハンドリングを有効に使い体感させる」
が望ましいと考えています。
◎左片麻痺の場合◎
欠点(右脳の固有機能)として、
・空間認識能力・身体図式が大きく崩れていることが多い
・自己認識・病識が崩れていることが多い
・表面的な言語理解は保たれるが裏に含まれる心理状況を読めない
・言語に執着し、物事を非常に細かく捕らえすぎる傾向にある
・理屈っぽくなり、表面的な問題に固執しやすい
と臨床的に感じる場合が多いように思われます。
逆に利点(左脳の固有機能)として、
・言語そのものは保たれ、文章的事項は分かっている
・要素的(言語)記憶が保たれていることが多い
・律儀な性格になりやすい傾向にある
と臨床的に感じる場合が多いように思われます。
つまり利点を生かした運動療法の方略として、
・要素的記憶と言語機能が比較的保たれ、律儀な性格にある傾向を逆手に取り、
患者とセラピスト間でのルールを定め、習慣的な能動性を引き出す
・空間・自己認識能力に劣り、全般的な注意障害を伴うことが多い傾向にあるため、
症例にとって興味のある(情動)、引き付ける視覚的注意要素を模索し、
動作をパターン化させる
ことが望ましいと考えています。
【文責 坪井祥一】
|
|
|
|
|
|
|
|
岐阜脳卒中リハビリテーション 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
岐阜脳卒中リハビリテーションのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37865人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90064人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208310人