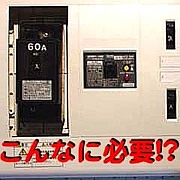個別に問題点、提案など、考えましょう。
資料2 夏期の電力需給対策について(PDF形式:439KB)
http://
1
夏期の電力需給対策について
平成23年5月13日
電力需給緊急対策本部
はじめに
東日本大震災により、東京電力及び東北電力管内の供給力は大幅に減尐し、これによって生じた大きな需給ギャップに対処するため、やむを得ない緊急措置として計画停電が実施された。
国民・産業界の節電への最大限の協力、取組の結果、需給バランスは改善し、懸念された大規模停電は回避され、4月8日には、計画停電は「実施が原則」から「不実施が原則」の状態へ移行した。
しかし、電力の需給バランスは、今後夏に向けて、再び悪化する見込みである。需給両面での抜本的な対策を講じなければ、計画停電の「不実施が原則」の状態を維持することができず、計画停電の弊害から脱却できない。このままでは、国民生活やとりわけ国の活力の源である産業活動が疲弊し、震災からの復興と日本経済の再出発は望めない。
本年4月8日に了解された「夏期の電力需給対策の骨格」(以下「骨格」)に基づき、供給力の積み増しと需要面での対策の具体化を進めてきたところ、以下のとおりその結果を取りまとめる。今後は、官民一体となって、創意工夫を発揮してこの難局から脱するべく、国民各層の理解と叡智を集めてご協力をお願いしたい。
1.今夏の電力需給対策の基本的考え方
(1) 検討に当たっての基本的な視座
電力制約が震災からの復興と日本経済の再出発の妨げとなることのないよう、国民生活及び経済活動への影響の最小化を目指すべきである。
特に、国の活力の源であり、復興の基盤である産業の生産・操業活動への影響を最小限にすることが必要である。この際、具体的対策については、労使で十分に話し合いながら準備を進める必要がある。
東北地方を中心とする被災地に最大限の配慮を行うことが必要である。
2
なお、具体的な対策を講じるに当たっては、単なる今夏の対策に止まらず、我が国のエネルギーの安定的な供給確保と環境負荷の低減に資する再生可能エネルギー・省エネルギー対策等の強化や、ライフスタイルの変革にもつながりうる休業・休暇の分散化・長期化など、中長期視点に立ち、将来につながる施策に取り組むことが必要である。
(2) 需給対策の基本的な枠組み
骨格において示された供給面での積増しを最大限行った上で、なお存在する需給ギャップを解消するために、需要抑制の目標を設定する。
需要抑制に当たっては、使用最大電力(kW)を抑制することを基本とし、予めピーク期間・時間帯の抑制幅を示す。これにより、需要家が、操業時間のシフトや休業・休暇の分散化・長期化などに創意工夫をこらして計画的に取り組むことにより、消費者や、とりわけ国の活力の源であり、また復興の基盤である企業の生産・操業に極力支障の出ないような仕組みとする。
需要面の対策については、大口需要家、小口需要家、家庭の部門別に、それぞれの特性にあった対策を具体化する。
なお、計画停電は、本取りまとめを確実に実施することにより不実施の状態を維持するよう、万全を期しつつ、セーフティネットと位置付け、万が一の緊急時に対応できるよう備えておく。
電力需給に係る制約を早期に解消し、震災からの復興と日本経済の再出発に資するよう、今夏以降の需給対策も併せて進める。
2.今夏の供給力見通しと需要抑制目標
(1) 今夏の供給力の見通し
東京電力及び東北電力管内の供給力については、被災した火力発電所の復旧、長期停止火力発電所の立上げ、ガスタービン等緊急設置電源の導入、自家用発電設備からの電力購入の拡大、揚水発電の活用等の取組に
3
より、積み増しを図ってきた。
これにより、「骨格」で目指すこととされた、東京電力管内で500万kW程度、東北電力管内で50万kW程度の積み増しを超える供給力を確保できる見通しとなった。
さらに、このような供給力をそれぞれ積み上げた上で、被災地を多く抱える東北地方の状況を考慮して、東京電力から東北電力に最大限の電力の融通を行うこととした。
この結果、今夏の供給力の見通しは、東京電力で5,380万kW(7月末)、東北電力で1,370万kW(8月末)となり、最低限必要な需要抑制率は、東京電力で▲10.3%、東北電力で▲7.4%となる。(参考参照)
<最大限の融通を行った場合の需給バランスの比較>
東京電力管内 東北電力管内
想定需要(抑制基準) 6,000万kW 1,480万kW
供給力見通し(融通後) 5,380万kW 1,370万kW
必要な需要抑制率 ▲10.3% ▲7.4%
(注)需要抑制目標は、基準となる想定需要からの抑制比率という形で設定。基準としては、東京電力では6,000万kW、東北電力では1,480万kWという昨年並みのピークを想定した需要を使用。
(2) 需要抑制の目標
需要抑制の目標は、次のようなリスクを踏まえれば、供給力と需要が一致するギリギリのラインではなく、一定の余裕を持ったものとすることが適当である。
・余震等による火力の復旧の遅れ、再被災
・老朽火力の昼夜連続運転、被災火力の緊急復旧等に伴う技術的リスク
・電力融通の不調 等
こうした観点から、東京・東北電力管内全域において目標とする需要抑制率を▲15%とする。
(注)被災者・被災地は需要抑制がより困難であり、東北電力管内全体でより余裕をもった目標とすることが妥当であるため、供給力と需要が一致する抑制率は東京電力に比べて低いが、目標とする抑制率は東京電力と同じとしている。
4
これを達成するための大口需要家・小口需要家・家庭の部門毎の需要抑制の目標については、同じ目標を掲げて国民・産業界が一丸となり、平等に努力してこの夏を乗り切るとの考え方の下、均一に▲15%とする。
(注)ピーク期間・時間帯(7〜9月の平日の9時から20時)における使用最大電力の抑制を原則とする。
(注)需要家には、政府及び地方公共団体を含む。以下同じ。
3.需要面の対策
(1) 大口需要家(契約電力500kW以上の事業者)
?取組の基本的方針
大口需要家は、需要抑制の目標を踏まえ、事業活動のあり方やライフスタイルにも踏み込んだ抜本的な需要抑制の具体的対策について、計画を策定し実施する。その際、震災からの復興や日本経済の再出発に向けて、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えられるよう、労使が十分に話し合いながら取組を進める。
政府は、こうした需要家の自主的な取組を尊重しつつ、需要抑制の実効性及び需要家間の公平性を担保するための補完的措置として、電気事業法第27条を活用できるよう必要な準備を進める。
政府は、需要家の取組を円滑化するため、電力需給対策に関する規制制度の見直しを行う。
東京電力及び東北電力は、需給調整契約のメニューの拡充を図り、その積極的な活用を図ることで、需要家の夏期休業の設定・分散やピークカットを促すとともに、需給逼迫時における需給調整契約の発動余地の拡大を図る。
?需要家の具体的取組
大口需要家は、操業・営業時間の調整・シフトや、休業日・夏期休業の分散化等の取組を関係企業等とも協力しつつ進めることにより、生産量を極力減尐させることなく、経済への影響を最小限に抑えることが可能となる。
5
日本経済団体連合会では、会員企業・団体に対して「電力対策自主行動計画」の策定を呼びかけ、4月末現在、637社 (複数の企業による共同の取組みは1社とカウント)の参加を得ている。また、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会は、需要抑制対策に対して共同して取り組むこととしている。(参考1)
?電気事業法第27条の活用
電気事業法第27条に基づく電気の使用の制限については、以下の骨子に基づき必要な準備を進める。
○対象者
・東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と、直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kW以上)
・対象者は電気事業者との契約単位(事業所単位)で判断
○期間・時間帯
・東京電力:平成23年7月1日〜9月22日(平日)の9時から20時
・東北電力:平成23年7月1日〜9月 9日(平日)の9時から20時
○具体的内容
・原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)」の15%削減した値を使用電力の上限とする
・上記値が分からない場合や契約電力に増減があった場合は所要の補正措置を講ずる。
○共同使用制限スキーム
・複数の大口需要家の事業所が共同して使用最大電力の抑制に取り組むことで、総体として使用最大電力を削減することを可能とするスキームを導入する。
・全体として15%以上の使用削減が実現できる場合には、大口需要家と小口需要家の事業所による共同使用制限スキームの活用を可能とする。
○適用除外・制限緩和
・被災地に対する対応のあり方を含め、適用除外や削減率(15%)の軽減等の制限緩和の具体的内容について、更に検討を深める。
・なお、検討に当たっては、適用除外や制限緩和の対象は、実態を踏まえ最小限度のものとするとともに、その対象であっても、自らできる限りの使用抑制に努め、また、企業・事業体等として削減率(15%)を達成するよう努めることとする。
?電力需給対策に関する規制制度の見直し
大口需要家等が抜本的な需要抑制対策を実施できるよう、一時的な対応も
6
含め、関係する規制制度の見直しを行う必要がある。このため、政府においては、独占禁止法の運用の明確化、自家発電施設の定期事業者検査の弾力化、自家発電設備の活用に係るばい煙排出基準の上乗せ規制に関する考え方についての地方自治体への通知など、既に結論を得た取組(別紙1)を実施するとともに、必要に応じ、電力需給対策本部幹事会を開催する等、引き続き検討を重ね、5月末までに結論を得ることとする。
(2) 小口需要家(契約電力500kW未満の事業者)
?取組の基本的方針
小口需要家は、具体的な抑制目標と、それぞれの事業の形態に適合する形での具体的取組に関する自主的な計画を策定・公表するとともに、実施を図る。その際、労使が十分に話し合いながら取組を進める。
政府は、小口需要家の取組を促すため、「節電行動計画の標準フォーマット」を活用した節電取組の周知等の措置を講ずる。
?需要家の具体的取組
小口需要家は、照明・空調機器等の節電、営業時間の短縮、夏期休業の設定・延長・分散化等の具体的取組を含む自主的な計画(「節電行動計画」)について、自主的に、事業所のわかりやすい場所への掲示や政府が設けるサイトへの掲載といった方法により、公表する。
日本商工会議所等は、これに資するため、「節電行動計画の標準フォーマット」を参考に、小口需要家の需要抑制のためのガイドライン等の策定を検討している。
また、東京中小企業家同友会では、小口需要家が節電行動計画を作成する手引きとして、「中小企業のための節電対策簡易マニュアル」を作成・公表し、中小企業への支援を行うこととしている。
?政府の具体的取組
需要家が自主的計画を策定するに当たって参考とできるよう、電力使用が大きく使用の形態が特徴的な業態について主要な節電アクションを「節電行動計画の標準フォーマット」(参考2)として取りまとめる。その上で、これらを用いて、節電取組の具体例やその効果等について需
7
要家に周知を図る。
関係府省は、個別の需要家による取組に加え、それぞれの需要家の事業の形態に適合する範囲で、同業他社との輪番での休業、建物の所有者とテナントとの共同での節電等、複数の需要家による共同の取組を促す。
需要家の取組の策定を支援するためのサイトを立ち上げ、当該サイトを通じて、需要家が自主的に計画を登録できるようにする。また、国民が広くそれらの取組を一覧し、評価できる仕組みを構築することとし、節電に積極的に取り組む需要家の更なる意識啓発、取組の定着化を図る。
関係府省、業界団体、自治体等を通じて需要家に対する情報提供等の啓発を強力に進める。また、主だった小口需要家に対し、個別訪問等を通じて、節電の必要性、具体的取組方法等についての情報提供や協力依頼を行う。さらに、小口需要家一般を対象に、説明会等を開催し、積極的な取組を呼びかける。
小口需要家による契約電力の引下げは、契約電力を超えないように注意・自制が働くことで、節電意識が喚起され、定着する効用があり、節電の有効な手段である。このため、東京電力及び東北電力に対し、節電を促す料金メニューの工夫を図りつつ、具体的な目標を定めて需要家に対して契約電力引下げの呼びかけを行うよう促すとともに、需要家が契約電力の引下げを具体的に相談・要望する場合には、これに迅速に対応するよう促す。
(3) 家庭
?取組の基本的方針
家庭は、節電対策メニューを活用するなどして意識して節電のための具体的行動に取り組む。
政府は、家庭の節電の取組を促すため、節電対策メニューの周知、節電教育等の措置を講ずる。
?具体的取組
政府は、節電の具体的取組を「家庭の節電対策メニュー」(参考3)として取りまとめ、パンフレット、新聞、テレビ、インターネット等様々
8
な媒体を通じ、節電の必要性と併せ、こうした節電の対策例について、家庭への浸透を図る。
(注)夏期のピーク期間・時間帯における標準的な家庭の使用電力はエアコンが約半分を占め、冷蔵庫、テレビ、照明などがこれに続く。15%の節電を達成するためには、例えば、エアコンの温度設定引上げと照明の消灯を組み合わせるといった取組が求められることとなる。
政府は、小中学校の授業や夏休みの課題で「節電」が取り上げられるよう、各教育委員会等に周知し、小中学校における節電教育の取組を促す。さらに、一部の小学校に対しては省エネ専門家を直接派遣し、節電教育を実施する。節電教育に当たっては、省エネルギーの重要性についても併せて触れる。
政府は、各家庭が自ら参加して節電の目標・取組の内容を宣言し、その達成を図るようなサイト等を設置し、国民一人ひとりが自発的に節電を行うための仕組み作りを行う。また、家庭での節電に向けた機運の盛上げや節電意識の涵養を図るため、広く一般に対し、電力会社が発信する電力需給情報や政府が提供する広報共通コンテンツ等のデータを活用したパソコン・携帯等のアプリケーションの開発・広報等を呼びかける。
家庭による契約アンペアの引下げは、契約アンペアを超えないように注意・自制が働くことで、節電意識が喚起される効用が期待される。このため、政府は、契約アンペアの引下げについて、家庭が具体的に相談・要望する場合には、家庭における利便性を過度に犠牲しないように配慮しつつ、東京電力及び東北電力においてこれに迅速に対応するよう促す。
(4) 国民運動に向けた取組
? 広報・啓発(別紙2)
国民各層及び関係事業者の最大限の理解と協力を得ることが必要不可欠であるところ、政府は、各層に対して積極的な啓発活動を行うこととする。夏のピークに向けて、?まずは節電の必要性、事業者や家庭の取組 といった基本的な事項に重点を置いて周知を図り、?夏が近づくに従い、電力需給の見通しや、個別具体的な節電アクションの実施の呼びかけに重点を置きつつ、節電に取り組む動きを国民運動として盛り上げ
9
ていく。その際、下記の点に留意する。
○参加型の国民運動の喚起
○分かりやすい説明とフィードバック(効果を分かりやすく提示)
○ステップを踏んだ啓発活動(まず電力の特性を踏まえた節電の必要性を理解してもらい、次に具体的アクションを提示)
○経済・社会活動や健康への配慮(経済・社会への負担の軽減や、熱中症等の健康被害発生を避けるよう留意)
○一過性に終わらせずに継続的な省エネ活動へ(長期的なエネルギー需給構造の強化、仕事と生活の調和がとれたライフスタイルの実現)
○自治体との連携
具体的には、新聞、テレビ、インターネット、ポスター、パンフレット等様々な媒体による広範囲な呼びかけを基本にし、節電の必要性等を国民が平易に理解し、常に再確認できるよう、共通ロゴや基本メッセージを準備する。また、節電関係の総合的なポータルサイト(節電.go.jp)の構築、国民から広く節電のアイデアを募るアイデアボックスの立上げ、従来以上に夏期の服装を軽装化することや高機能繊維を用いた衣料の着用への呼びかけ等を実施する。
ホームページ等における電力需給状況及び予想電力需要の「見える化」を図り、国民各層の節電に向けた動機付けの徹底を図ることが有効である。このため、東京電力・東北電力においては、電力需給状況や予想電力需要についての情報発信を自ら行うとともに、民間事業者等(携帯事業者やインターネット事業者等)による幅広い情報提供に積極的に協力することとし、政府はこれを促す。
国民、事業者による様々な節電努力にもかかわらず電力需給が逼迫し、計画停電等のおそれが高まった場合に、政府による「需給逼迫警報」(仮称)として、これを避けるための緊急の節電要請を行うとともに、やむを得ない事態における計画停電の可能性を周知する。
? 大型イベント開催等における配慮
大型イベントの開催については、ピーク期間・時間帯に配慮した開催の可能性検討、イベント開催時の節電取組の実施、イベント参加者への節電呼びかけ等について、イベント主催者に対する協力要請を関係府省から行う。
10
イベントの放送については、関係府省は、放送業界に対し、ピーク期間・時間帯に配慮するよう呼びかける。
?夏季の休業・休暇の分散化/長期化、家庭における外出/旅行の推進
(参考4)
休業・休暇の分散化・長期化は、経済活動への影響を最小限にしつつ、節電の実を上げる有効な手法である。ただし、労働者にとって負担となる労働条件変更につながる可能性もあるため、労使間での十分な話し合いが必要である。
また、旅行等の外出は、行先を問わず、家庭部門に確実な節電効果をもたらす。休業・休暇の分散化・長期化、それによる観光地の混雑緩和等が相まって家族の外出機会が増えれば、節電効果の更なる増大が見込まれる。長期滞在型旅行を始め旅行の促進は、自粛ムードの影響を受ける観光業の活性化を促す。被災地域への旅行は地域経済の復興にも貢献する。これらの取組を、今夏の一時的なものに留めず、仕事と生活の調和がとれたライフスタイルの実現に繋げていくことも期待される。
(5) 政府の節電に係る取組
➢ 政府は、「政府の節電実行基本方針」(別紙3)に基づき、府省毎に節電実行計画を策定し、使用最大電力を15%以上抑制する。また、使用最大電力の抑制にとどまらず、ピーク期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的に取り組むこととする。
➢ また、独立行政法人及び公益法人に対しては、その所管府省が「政府の節電実行基本方針」及び各府省の節電実行計画を参考にしつつ当該法人の節電計画を策定するよう要請する。
(6) セーフティネットとしての計画停電 (別紙4)
計画停電は既に「不実施が原則」の状態へ移行したが、今後、万が一実施せざるを得ない場合には、運用改善を図った上で実施する。具体的には、1日複数回の停電を避けるとともに、1回の停電時間を現行の3時間から2時間程度に短縮する等の措置を講じる。
併せて、国民生活への悪影響を緩和するため、医療機関等について、緊
11
急かつ直接的に人命に関わることを考慮し、変電所の運用改善等によって停電による影響をできる限り緩和するほか、非常用自家発電機のバックアップとしての発電機車の派遣、在宅の人工呼吸器使用患者への小型自家発電機の貸出し、熱中症対策の周知徹底等に取り組む。
4.今夏以降の需給対策
(1) 基本的考え方
電力需給に係る制約から早期に脱却し、震災からの復興と日本経済の再出発に資するよう、今夏以降も引き続き需給両面の対策を講じていく必要がある。
今後の電力需給対策の方向は、今後のエネルギー政策のあり方についての検討状況にもよるが、まずは原子力発電所の安全対策に万全を期すとともに、以下に示す需給両面の対策を講じることにより、今夏よりも需給状況を改善することを目指す。(別紙5)
(注)これらの対策は、今夏の対策としても、できるものは実施することとしている。
(2) 具体的な対応
火力発電所の復旧・立ち上げ、緊急設置電源の新設、自家用発電設備の活用に引き続き取り組むとともに、火力発電所の増設の前倒しを図ることで、火力発電所の供給力を増強する。
既設周波数変換所(FC)について、増容量の早期実現と更なる増強の具現化を図るとともに、FCの更なる大幅な増強を含めた全国大での地域間連系設備等の増強を目指し、電力融通強化を図る。
分散型電源、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱等)の導入に向けて更なる取組み強化を図る。
需要面では、スマートメーターの導入等による需要側におけるエネルギー利用の最適化を図りつつ、節電を促す制度的手法の導入を検討するとともに、節電に資する機器設備の導入促進等省エネルギーの一層の推進、ガスの活用等を図る。
12
おわりに
今回の供給力の積増しは、老朽火力の利用や被災火力の緊急復旧等といった技術的リスクも伴う形で最大限実現したものであり、国民各層の節電への取組が不可欠であることは言うまでもない。今後、国民各層の節電への緊張感が薄れ、結果的に現在「不実施が原則」となっている計画停電を実施せざるを得ない事態に陥ることは、厳に回避しなければならない。
したがって、上記に示した需要抑制の方策について、国民各層の最大限のご理解とご協力をいただくとともに、政府としても最大限の方策を講じていく必要がある。
なお、供給力の状況や需要見通しは、今後も変化することが予想される。したがって、常にこれを把握し、必要に応じて本とりまとめに示された内容を見直していくこととする。
13
(参考)
今夏の供給力見通し
(1) 東京電力・東北電力の供給力見通し
東京電力の供給力見通し
「骨格」の前提と 4月15日時点 5月13日時点
なった見通し の見通し の見通し
7月末 4,650万kW → 5,200万kW → 5,520万kW
8月末 4,460万kW → 5,070万kW → 5,620万kW
東北電力の供給力見通し
「骨格」の前提と 4月15日時点 5月13日時点
なった見通し の見通し の見通し
7月末 1,200万kW → 1,260万kW → 1,280万kW
8月末 1,150万kW → 1,210万kW → 1,230万kW
(2) 東京電力・東北電力の需給バランスの比較
東京電力 東北電力
供給力見通し 5,520万kW 1,230万kW
想定需要(抑制基準) 6,000万kW 1,480万kW
必要な需要抑制率(注) ▲8.0% ▲16.9%
(注)需要抑制目標は、基準となる想定需要からの抑制比率という形で設定。東京電力では6,000万kW、東北電力では1,480万kWという昨年並みのピークを想定した需要を使用。
(3) 最大限の融通を行った場合の需給バランスの比較
東京電力 東北電力
融通量 ▲140万kW +140万kW
融通後供給力 5,380万kW 1,370万kW
必要な需要抑制率 ▲10.3% ▲7.4%
資料2 夏期の電力需給対策について(PDF形式:439KB)
http://
1
夏期の電力需給対策について
平成23年5月13日
電力需給緊急対策本部
はじめに
東日本大震災により、東京電力及び東北電力管内の供給力は大幅に減尐し、これによって生じた大きな需給ギャップに対処するため、やむを得ない緊急措置として計画停電が実施された。
国民・産業界の節電への最大限の協力、取組の結果、需給バランスは改善し、懸念された大規模停電は回避され、4月8日には、計画停電は「実施が原則」から「不実施が原則」の状態へ移行した。
しかし、電力の需給バランスは、今後夏に向けて、再び悪化する見込みである。需給両面での抜本的な対策を講じなければ、計画停電の「不実施が原則」の状態を維持することができず、計画停電の弊害から脱却できない。このままでは、国民生活やとりわけ国の活力の源である産業活動が疲弊し、震災からの復興と日本経済の再出発は望めない。
本年4月8日に了解された「夏期の電力需給対策の骨格」(以下「骨格」)に基づき、供給力の積み増しと需要面での対策の具体化を進めてきたところ、以下のとおりその結果を取りまとめる。今後は、官民一体となって、創意工夫を発揮してこの難局から脱するべく、国民各層の理解と叡智を集めてご協力をお願いしたい。
1.今夏の電力需給対策の基本的考え方
(1) 検討に当たっての基本的な視座
電力制約が震災からの復興と日本経済の再出発の妨げとなることのないよう、国民生活及び経済活動への影響の最小化を目指すべきである。
特に、国の活力の源であり、復興の基盤である産業の生産・操業活動への影響を最小限にすることが必要である。この際、具体的対策については、労使で十分に話し合いながら準備を進める必要がある。
東北地方を中心とする被災地に最大限の配慮を行うことが必要である。
2
なお、具体的な対策を講じるに当たっては、単なる今夏の対策に止まらず、我が国のエネルギーの安定的な供給確保と環境負荷の低減に資する再生可能エネルギー・省エネルギー対策等の強化や、ライフスタイルの変革にもつながりうる休業・休暇の分散化・長期化など、中長期視点に立ち、将来につながる施策に取り組むことが必要である。
(2) 需給対策の基本的な枠組み
骨格において示された供給面での積増しを最大限行った上で、なお存在する需給ギャップを解消するために、需要抑制の目標を設定する。
需要抑制に当たっては、使用最大電力(kW)を抑制することを基本とし、予めピーク期間・時間帯の抑制幅を示す。これにより、需要家が、操業時間のシフトや休業・休暇の分散化・長期化などに創意工夫をこらして計画的に取り組むことにより、消費者や、とりわけ国の活力の源であり、また復興の基盤である企業の生産・操業に極力支障の出ないような仕組みとする。
需要面の対策については、大口需要家、小口需要家、家庭の部門別に、それぞれの特性にあった対策を具体化する。
なお、計画停電は、本取りまとめを確実に実施することにより不実施の状態を維持するよう、万全を期しつつ、セーフティネットと位置付け、万が一の緊急時に対応できるよう備えておく。
電力需給に係る制約を早期に解消し、震災からの復興と日本経済の再出発に資するよう、今夏以降の需給対策も併せて進める。
2.今夏の供給力見通しと需要抑制目標
(1) 今夏の供給力の見通し
東京電力及び東北電力管内の供給力については、被災した火力発電所の復旧、長期停止火力発電所の立上げ、ガスタービン等緊急設置電源の導入、自家用発電設備からの電力購入の拡大、揚水発電の活用等の取組に
3
より、積み増しを図ってきた。
これにより、「骨格」で目指すこととされた、東京電力管内で500万kW程度、東北電力管内で50万kW程度の積み増しを超える供給力を確保できる見通しとなった。
さらに、このような供給力をそれぞれ積み上げた上で、被災地を多く抱える東北地方の状況を考慮して、東京電力から東北電力に最大限の電力の融通を行うこととした。
この結果、今夏の供給力の見通しは、東京電力で5,380万kW(7月末)、東北電力で1,370万kW(8月末)となり、最低限必要な需要抑制率は、東京電力で▲10.3%、東北電力で▲7.4%となる。(参考参照)
<最大限の融通を行った場合の需給バランスの比較>
東京電力管内 東北電力管内
想定需要(抑制基準) 6,000万kW 1,480万kW
供給力見通し(融通後) 5,380万kW 1,370万kW
必要な需要抑制率 ▲10.3% ▲7.4%
(注)需要抑制目標は、基準となる想定需要からの抑制比率という形で設定。基準としては、東京電力では6,000万kW、東北電力では1,480万kWという昨年並みのピークを想定した需要を使用。
(2) 需要抑制の目標
需要抑制の目標は、次のようなリスクを踏まえれば、供給力と需要が一致するギリギリのラインではなく、一定の余裕を持ったものとすることが適当である。
・余震等による火力の復旧の遅れ、再被災
・老朽火力の昼夜連続運転、被災火力の緊急復旧等に伴う技術的リスク
・電力融通の不調 等
こうした観点から、東京・東北電力管内全域において目標とする需要抑制率を▲15%とする。
(注)被災者・被災地は需要抑制がより困難であり、東北電力管内全体でより余裕をもった目標とすることが妥当であるため、供給力と需要が一致する抑制率は東京電力に比べて低いが、目標とする抑制率は東京電力と同じとしている。
4
これを達成するための大口需要家・小口需要家・家庭の部門毎の需要抑制の目標については、同じ目標を掲げて国民・産業界が一丸となり、平等に努力してこの夏を乗り切るとの考え方の下、均一に▲15%とする。
(注)ピーク期間・時間帯(7〜9月の平日の9時から20時)における使用最大電力の抑制を原則とする。
(注)需要家には、政府及び地方公共団体を含む。以下同じ。
3.需要面の対策
(1) 大口需要家(契約電力500kW以上の事業者)
?取組の基本的方針
大口需要家は、需要抑制の目標を踏まえ、事業活動のあり方やライフスタイルにも踏み込んだ抜本的な需要抑制の具体的対策について、計画を策定し実施する。その際、震災からの復興や日本経済の再出発に向けて、国民生活や経済活動への影響を最小限に抑えられるよう、労使が十分に話し合いながら取組を進める。
政府は、こうした需要家の自主的な取組を尊重しつつ、需要抑制の実効性及び需要家間の公平性を担保するための補完的措置として、電気事業法第27条を活用できるよう必要な準備を進める。
政府は、需要家の取組を円滑化するため、電力需給対策に関する規制制度の見直しを行う。
東京電力及び東北電力は、需給調整契約のメニューの拡充を図り、その積極的な活用を図ることで、需要家の夏期休業の設定・分散やピークカットを促すとともに、需給逼迫時における需給調整契約の発動余地の拡大を図る。
?需要家の具体的取組
大口需要家は、操業・営業時間の調整・シフトや、休業日・夏期休業の分散化等の取組を関係企業等とも協力しつつ進めることにより、生産量を極力減尐させることなく、経済への影響を最小限に抑えることが可能となる。
5
日本経済団体連合会では、会員企業・団体に対して「電力対策自主行動計画」の策定を呼びかけ、4月末現在、637社 (複数の企業による共同の取組みは1社とカウント)の参加を得ている。また、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合会は、需要抑制対策に対して共同して取り組むこととしている。(参考1)
?電気事業法第27条の活用
電気事業法第27条に基づく電気の使用の制限については、以下の骨子に基づき必要な準備を進める。
○対象者
・東京電力及び東北電力並びにその供給区域内で供給している特定規模電気事業者と、直接、需給契約を締結している大口需要家(契約電力500kW以上)
・対象者は電気事業者との契約単位(事業所単位)で判断
○期間・時間帯
・東京電力:平成23年7月1日〜9月22日(平日)の9時から20時
・東北電力:平成23年7月1日〜9月 9日(平日)の9時から20時
○具体的内容
・原則、「昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力の値(1時間単位)」の15%削減した値を使用電力の上限とする
・上記値が分からない場合や契約電力に増減があった場合は所要の補正措置を講ずる。
○共同使用制限スキーム
・複数の大口需要家の事業所が共同して使用最大電力の抑制に取り組むことで、総体として使用最大電力を削減することを可能とするスキームを導入する。
・全体として15%以上の使用削減が実現できる場合には、大口需要家と小口需要家の事業所による共同使用制限スキームの活用を可能とする。
○適用除外・制限緩和
・被災地に対する対応のあり方を含め、適用除外や削減率(15%)の軽減等の制限緩和の具体的内容について、更に検討を深める。
・なお、検討に当たっては、適用除外や制限緩和の対象は、実態を踏まえ最小限度のものとするとともに、その対象であっても、自らできる限りの使用抑制に努め、また、企業・事業体等として削減率(15%)を達成するよう努めることとする。
?電力需給対策に関する規制制度の見直し
大口需要家等が抜本的な需要抑制対策を実施できるよう、一時的な対応も
6
含め、関係する規制制度の見直しを行う必要がある。このため、政府においては、独占禁止法の運用の明確化、自家発電施設の定期事業者検査の弾力化、自家発電設備の活用に係るばい煙排出基準の上乗せ規制に関する考え方についての地方自治体への通知など、既に結論を得た取組(別紙1)を実施するとともに、必要に応じ、電力需給対策本部幹事会を開催する等、引き続き検討を重ね、5月末までに結論を得ることとする。
(2) 小口需要家(契約電力500kW未満の事業者)
?取組の基本的方針
小口需要家は、具体的な抑制目標と、それぞれの事業の形態に適合する形での具体的取組に関する自主的な計画を策定・公表するとともに、実施を図る。その際、労使が十分に話し合いながら取組を進める。
政府は、小口需要家の取組を促すため、「節電行動計画の標準フォーマット」を活用した節電取組の周知等の措置を講ずる。
?需要家の具体的取組
小口需要家は、照明・空調機器等の節電、営業時間の短縮、夏期休業の設定・延長・分散化等の具体的取組を含む自主的な計画(「節電行動計画」)について、自主的に、事業所のわかりやすい場所への掲示や政府が設けるサイトへの掲載といった方法により、公表する。
日本商工会議所等は、これに資するため、「節電行動計画の標準フォーマット」を参考に、小口需要家の需要抑制のためのガイドライン等の策定を検討している。
また、東京中小企業家同友会では、小口需要家が節電行動計画を作成する手引きとして、「中小企業のための節電対策簡易マニュアル」を作成・公表し、中小企業への支援を行うこととしている。
?政府の具体的取組
需要家が自主的計画を策定するに当たって参考とできるよう、電力使用が大きく使用の形態が特徴的な業態について主要な節電アクションを「節電行動計画の標準フォーマット」(参考2)として取りまとめる。その上で、これらを用いて、節電取組の具体例やその効果等について需
7
要家に周知を図る。
関係府省は、個別の需要家による取組に加え、それぞれの需要家の事業の形態に適合する範囲で、同業他社との輪番での休業、建物の所有者とテナントとの共同での節電等、複数の需要家による共同の取組を促す。
需要家の取組の策定を支援するためのサイトを立ち上げ、当該サイトを通じて、需要家が自主的に計画を登録できるようにする。また、国民が広くそれらの取組を一覧し、評価できる仕組みを構築することとし、節電に積極的に取り組む需要家の更なる意識啓発、取組の定着化を図る。
関係府省、業界団体、自治体等を通じて需要家に対する情報提供等の啓発を強力に進める。また、主だった小口需要家に対し、個別訪問等を通じて、節電の必要性、具体的取組方法等についての情報提供や協力依頼を行う。さらに、小口需要家一般を対象に、説明会等を開催し、積極的な取組を呼びかける。
小口需要家による契約電力の引下げは、契約電力を超えないように注意・自制が働くことで、節電意識が喚起され、定着する効用があり、節電の有効な手段である。このため、東京電力及び東北電力に対し、節電を促す料金メニューの工夫を図りつつ、具体的な目標を定めて需要家に対して契約電力引下げの呼びかけを行うよう促すとともに、需要家が契約電力の引下げを具体的に相談・要望する場合には、これに迅速に対応するよう促す。
(3) 家庭
?取組の基本的方針
家庭は、節電対策メニューを活用するなどして意識して節電のための具体的行動に取り組む。
政府は、家庭の節電の取組を促すため、節電対策メニューの周知、節電教育等の措置を講ずる。
?具体的取組
政府は、節電の具体的取組を「家庭の節電対策メニュー」(参考3)として取りまとめ、パンフレット、新聞、テレビ、インターネット等様々
8
な媒体を通じ、節電の必要性と併せ、こうした節電の対策例について、家庭への浸透を図る。
(注)夏期のピーク期間・時間帯における標準的な家庭の使用電力はエアコンが約半分を占め、冷蔵庫、テレビ、照明などがこれに続く。15%の節電を達成するためには、例えば、エアコンの温度設定引上げと照明の消灯を組み合わせるといった取組が求められることとなる。
政府は、小中学校の授業や夏休みの課題で「節電」が取り上げられるよう、各教育委員会等に周知し、小中学校における節電教育の取組を促す。さらに、一部の小学校に対しては省エネ専門家を直接派遣し、節電教育を実施する。節電教育に当たっては、省エネルギーの重要性についても併せて触れる。
政府は、各家庭が自ら参加して節電の目標・取組の内容を宣言し、その達成を図るようなサイト等を設置し、国民一人ひとりが自発的に節電を行うための仕組み作りを行う。また、家庭での節電に向けた機運の盛上げや節電意識の涵養を図るため、広く一般に対し、電力会社が発信する電力需給情報や政府が提供する広報共通コンテンツ等のデータを活用したパソコン・携帯等のアプリケーションの開発・広報等を呼びかける。
家庭による契約アンペアの引下げは、契約アンペアを超えないように注意・自制が働くことで、節電意識が喚起される効用が期待される。このため、政府は、契約アンペアの引下げについて、家庭が具体的に相談・要望する場合には、家庭における利便性を過度に犠牲しないように配慮しつつ、東京電力及び東北電力においてこれに迅速に対応するよう促す。
(4) 国民運動に向けた取組
? 広報・啓発(別紙2)
国民各層及び関係事業者の最大限の理解と協力を得ることが必要不可欠であるところ、政府は、各層に対して積極的な啓発活動を行うこととする。夏のピークに向けて、?まずは節電の必要性、事業者や家庭の取組 といった基本的な事項に重点を置いて周知を図り、?夏が近づくに従い、電力需給の見通しや、個別具体的な節電アクションの実施の呼びかけに重点を置きつつ、節電に取り組む動きを国民運動として盛り上げ
9
ていく。その際、下記の点に留意する。
○参加型の国民運動の喚起
○分かりやすい説明とフィードバック(効果を分かりやすく提示)
○ステップを踏んだ啓発活動(まず電力の特性を踏まえた節電の必要性を理解してもらい、次に具体的アクションを提示)
○経済・社会活動や健康への配慮(経済・社会への負担の軽減や、熱中症等の健康被害発生を避けるよう留意)
○一過性に終わらせずに継続的な省エネ活動へ(長期的なエネルギー需給構造の強化、仕事と生活の調和がとれたライフスタイルの実現)
○自治体との連携
具体的には、新聞、テレビ、インターネット、ポスター、パンフレット等様々な媒体による広範囲な呼びかけを基本にし、節電の必要性等を国民が平易に理解し、常に再確認できるよう、共通ロゴや基本メッセージを準備する。また、節電関係の総合的なポータルサイト(節電.go.jp)の構築、国民から広く節電のアイデアを募るアイデアボックスの立上げ、従来以上に夏期の服装を軽装化することや高機能繊維を用いた衣料の着用への呼びかけ等を実施する。
ホームページ等における電力需給状況及び予想電力需要の「見える化」を図り、国民各層の節電に向けた動機付けの徹底を図ることが有効である。このため、東京電力・東北電力においては、電力需給状況や予想電力需要についての情報発信を自ら行うとともに、民間事業者等(携帯事業者やインターネット事業者等)による幅広い情報提供に積極的に協力することとし、政府はこれを促す。
国民、事業者による様々な節電努力にもかかわらず電力需給が逼迫し、計画停電等のおそれが高まった場合に、政府による「需給逼迫警報」(仮称)として、これを避けるための緊急の節電要請を行うとともに、やむを得ない事態における計画停電の可能性を周知する。
? 大型イベント開催等における配慮
大型イベントの開催については、ピーク期間・時間帯に配慮した開催の可能性検討、イベント開催時の節電取組の実施、イベント参加者への節電呼びかけ等について、イベント主催者に対する協力要請を関係府省から行う。
10
イベントの放送については、関係府省は、放送業界に対し、ピーク期間・時間帯に配慮するよう呼びかける。
?夏季の休業・休暇の分散化/長期化、家庭における外出/旅行の推進
(参考4)
休業・休暇の分散化・長期化は、経済活動への影響を最小限にしつつ、節電の実を上げる有効な手法である。ただし、労働者にとって負担となる労働条件変更につながる可能性もあるため、労使間での十分な話し合いが必要である。
また、旅行等の外出は、行先を問わず、家庭部門に確実な節電効果をもたらす。休業・休暇の分散化・長期化、それによる観光地の混雑緩和等が相まって家族の外出機会が増えれば、節電効果の更なる増大が見込まれる。長期滞在型旅行を始め旅行の促進は、自粛ムードの影響を受ける観光業の活性化を促す。被災地域への旅行は地域経済の復興にも貢献する。これらの取組を、今夏の一時的なものに留めず、仕事と生活の調和がとれたライフスタイルの実現に繋げていくことも期待される。
(5) 政府の節電に係る取組
➢ 政府は、「政府の節電実行基本方針」(別紙3)に基づき、府省毎に節電実行計画を策定し、使用最大電力を15%以上抑制する。また、使用最大電力の抑制にとどまらず、ピーク期間・時間帯を通じた使用電力の抑制にも積極的に取り組むこととする。
➢ また、独立行政法人及び公益法人に対しては、その所管府省が「政府の節電実行基本方針」及び各府省の節電実行計画を参考にしつつ当該法人の節電計画を策定するよう要請する。
(6) セーフティネットとしての計画停電 (別紙4)
計画停電は既に「不実施が原則」の状態へ移行したが、今後、万が一実施せざるを得ない場合には、運用改善を図った上で実施する。具体的には、1日複数回の停電を避けるとともに、1回の停電時間を現行の3時間から2時間程度に短縮する等の措置を講じる。
併せて、国民生活への悪影響を緩和するため、医療機関等について、緊
11
急かつ直接的に人命に関わることを考慮し、変電所の運用改善等によって停電による影響をできる限り緩和するほか、非常用自家発電機のバックアップとしての発電機車の派遣、在宅の人工呼吸器使用患者への小型自家発電機の貸出し、熱中症対策の周知徹底等に取り組む。
4.今夏以降の需給対策
(1) 基本的考え方
電力需給に係る制約から早期に脱却し、震災からの復興と日本経済の再出発に資するよう、今夏以降も引き続き需給両面の対策を講じていく必要がある。
今後の電力需給対策の方向は、今後のエネルギー政策のあり方についての検討状況にもよるが、まずは原子力発電所の安全対策に万全を期すとともに、以下に示す需給両面の対策を講じることにより、今夏よりも需給状況を改善することを目指す。(別紙5)
(注)これらの対策は、今夏の対策としても、できるものは実施することとしている。
(2) 具体的な対応
火力発電所の復旧・立ち上げ、緊急設置電源の新設、自家用発電設備の活用に引き続き取り組むとともに、火力発電所の増設の前倒しを図ることで、火力発電所の供給力を増強する。
既設周波数変換所(FC)について、増容量の早期実現と更なる増強の具現化を図るとともに、FCの更なる大幅な増強を含めた全国大での地域間連系設備等の増強を目指し、電力融通強化を図る。
分散型電源、再生可能エネルギー(太陽光、風力、地熱等)の導入に向けて更なる取組み強化を図る。
需要面では、スマートメーターの導入等による需要側におけるエネルギー利用の最適化を図りつつ、節電を促す制度的手法の導入を検討するとともに、節電に資する機器設備の導入促進等省エネルギーの一層の推進、ガスの活用等を図る。
12
おわりに
今回の供給力の積増しは、老朽火力の利用や被災火力の緊急復旧等といった技術的リスクも伴う形で最大限実現したものであり、国民各層の節電への取組が不可欠であることは言うまでもない。今後、国民各層の節電への緊張感が薄れ、結果的に現在「不実施が原則」となっている計画停電を実施せざるを得ない事態に陥ることは、厳に回避しなければならない。
したがって、上記に示した需要抑制の方策について、国民各層の最大限のご理解とご協力をいただくとともに、政府としても最大限の方策を講じていく必要がある。
なお、供給力の状況や需要見通しは、今後も変化することが予想される。したがって、常にこれを把握し、必要に応じて本とりまとめに示された内容を見直していくこととする。
13
(参考)
今夏の供給力見通し
(1) 東京電力・東北電力の供給力見通し
東京電力の供給力見通し
「骨格」の前提と 4月15日時点 5月13日時点
なった見通し の見通し の見通し
7月末 4,650万kW → 5,200万kW → 5,520万kW
8月末 4,460万kW → 5,070万kW → 5,620万kW
東北電力の供給力見通し
「骨格」の前提と 4月15日時点 5月13日時点
なった見通し の見通し の見通し
7月末 1,200万kW → 1,260万kW → 1,280万kW
8月末 1,150万kW → 1,210万kW → 1,230万kW
(2) 東京電力・東北電力の需給バランスの比較
東京電力 東北電力
供給力見通し 5,520万kW 1,230万kW
想定需要(抑制基準) 6,000万kW 1,480万kW
必要な需要抑制率(注) ▲8.0% ▲16.9%
(注)需要抑制目標は、基準となる想定需要からの抑制比率という形で設定。東京電力では6,000万kW、東北電力では1,480万kWという昨年並みのピークを想定した需要を使用。
(3) 最大限の融通を行った場合の需給バランスの比較
東京電力 東北電力
融通量 ▲140万kW +140万kW
融通後供給力 5,380万kW 1,370万kW
必要な需要抑制率 ▲10.3% ▲7.4%
|
|
|
|
|
|
|
|
契約電流制限による計画停電回避 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
契約電流制限による計画停電回避のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55348人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90004人
- 3位
- 酒好き
- 170654人