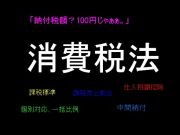|
|
|
|
コメント(30)
>ジャンボさん
ただ、今回の改正は計算には影響しないと考えられます。
なぜなら今回の改正は22年4月1日以後開始する課税期間(だったかな?)に行った調整対象固定資産に係る課税仕入れに対して影響を及ぼします。
そして、今年の本試験の問題は3月決算の問題なら22年4月1日から23年3月31日。
つまり当課税期間に購入したものについては調固に影響を及ぼさないし、今回の改正の対象となる届出書関係にもほとんど関係しません。
まあ、法人税みたいに計算で理論聞いてきてコメント振らせるとか出題されない限り影響及ぼさないでしょう。
私個人的な意見としてはやはり理論での出題が濃厚と思っています。
ただ、今回の改正は計算には影響しないと考えられます。
なぜなら今回の改正は22年4月1日以後開始する課税期間(だったかな?)に行った調整対象固定資産に係る課税仕入れに対して影響を及ぼします。
そして、今年の本試験の問題は3月決算の問題なら22年4月1日から23年3月31日。
つまり当課税期間に購入したものについては調固に影響を及ぼさないし、今回の改正の対象となる届出書関係にもほとんど関係しません。
まあ、法人税みたいに計算で理論聞いてきてコメント振らせるとか出題されない限り影響及ぼさないでしょう。
私個人的な意見としてはやはり理論での出題が濃厚と思っています。
改正論点トピ自体は無いからこの場を借りて議論しちゃってもいいのかな
>豊臣秀吉さん
個人事業者の法人成りした後の法人は3年縛りの影響を受ける可能性もあるということですが、その「可能性もある」というその筆者の表現が、ただ断言することを恐れてそう言っているのか、それとも調整対象固定資産の課税仕入れを行わないと対象にならないという意味で言っているのかよくわかりませんが、法人成りはほぼ間違いなく3年縛りの対象になるでしょうね。
法人成りは承継ではなく譲渡扱いになるので、法人側からすれば譲り受けた、すなわち仕入れ側になります。そしてその譲受は時価による譲受けですから建物なんか所有しちゃっている元個人事業者だったら間違いなく3年縛りの対象になりますね。調整対象固定資産は税抜き100万円以上のものですから、個人事業者でも時価レベルになったら意外と持っていると思うんですよ。するとほとんどの法人成りは3年縛りになるでしょうね。
これは確かに良いんだか悪いんだかって感じですね。法人成り3期目だけで考えると、順調に成長している会社であれば、改正前は3期目免税事業者になれたのに改正後は課税事業者になって納税額が生じる場合であれば、改正前より納付税額丸々損する(という表現は微妙かもしれませんが )ことになりますよね。
)ことになりますよね。
しかし、輸出業者とかで3期目も課税事業者の方が有利だからどちらにしろ課税事業者選択届出書を提出しようとしている会社からしたら手間が省けていいかもしれない。
んーーー、考えれば考えるほど良し悪しな感じですね
>豊臣秀吉さん
個人事業者の法人成りした後の法人は3年縛りの影響を受ける可能性もあるということですが、その「可能性もある」というその筆者の表現が、ただ断言することを恐れてそう言っているのか、それとも調整対象固定資産の課税仕入れを行わないと対象にならないという意味で言っているのかよくわかりませんが、法人成りはほぼ間違いなく3年縛りの対象になるでしょうね。
法人成りは承継ではなく譲渡扱いになるので、法人側からすれば譲り受けた、すなわち仕入れ側になります。そしてその譲受は時価による譲受けですから建物なんか所有しちゃっている元個人事業者だったら間違いなく3年縛りの対象になりますね。調整対象固定資産は税抜き100万円以上のものですから、個人事業者でも時価レベルになったら意外と持っていると思うんですよ。するとほとんどの法人成りは3年縛りになるでしょうね。
これは確かに良いんだか悪いんだかって感じですね。法人成り3期目だけで考えると、順調に成長している会社であれば、改正前は3期目免税事業者になれたのに改正後は課税事業者になって納税額が生じる場合であれば、改正前より納付税額丸々損する(という表現は微妙かもしれませんが
しかし、輸出業者とかで3期目も課税事業者の方が有利だからどちらにしろ課税事業者選択届出書を提出しようとしている会社からしたら手間が省けていいかもしれない。
んーーー、考えれば考えるほど良し悪しな感じですね
皆さま
ありがとうございます。
まさかO原のサイトからDLできるとは☆
本当に助かりました。
今会社で税務通信引っ張り出して勉強してます。
もう少し教えて下さい。改正とは直接関係ないんですが。
従来の自販機スキームの流れとして、あるHPでは、
?個人事業者が平成21年に事業を開始
?平成21年中に課税事業者選択届出書を提出し、平成21年分につき納税義務者となる→還付を受ける
?同じく平成21年中に簡易課税制度選択届出書を提出し、平成22年分につき簡易課税を選択する
?平成22年中に課税事業者選択不適用届出書を提出し、平成23年分につき免税事業者となる
とあります。
この場合、?で簡易課税制度選択届出書を提出したことによる2年継続適用は実際に届出書を提出した課税期間である平成21年から2年なのか?
実際に簡易が始まった平成22年から2年なのか?こんがらがってきました。
理サブだと、「簡易課税制度の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができない。」と書いてあります。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。
まさかO原のサイトからDLできるとは☆
本当に助かりました。
今会社で税務通信引っ張り出して勉強してます。
もう少し教えて下さい。改正とは直接関係ないんですが。
従来の自販機スキームの流れとして、あるHPでは、
?個人事業者が平成21年に事業を開始
?平成21年中に課税事業者選択届出書を提出し、平成21年分につき納税義務者となる→還付を受ける
?同じく平成21年中に簡易課税制度選択届出書を提出し、平成22年分につき簡易課税を選択する
?平成22年中に課税事業者選択不適用届出書を提出し、平成23年分につき免税事業者となる
とあります。
この場合、?で簡易課税制度選択届出書を提出したことによる2年継続適用は実際に届出書を提出した課税期間である平成21年から2年なのか?
実際に簡易が始まった平成22年から2年なのか?こんがらがってきました。
理サブだと、「簡易課税制度の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ不適用届出書を提出することができない。」と書いてあります。
宜しくお願いします。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
消費税法@税理士試験 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
消費税法@税理士試験のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90048人
- 2位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6428人
- 3位
- 独り言
- 9045人