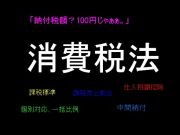|
|
|
|
コメント(17)
5−5−10 事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、その出向した使用人(以下5−5−10において「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者(出向者を出向させている事業者をいう。以下5−5−10において同じ。)が支給することとしているため、出向先事業者(出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5−5−10において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下5−5−10において「給与負担金」という。)を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。
(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。
問題に、経営指導料(給与の甲社負担分相当額)とありますので、給与として取り扱って相当だと思います。
(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。
問題に、経営指導料(給与の甲社負担分相当額)とありますので、給与として取り扱って相当だと思います。
>マコトさん
その?の答えが「雇用関係がないため当然不課税扱い」となっていますが、これだけ結論が逆ですね・・・
さて、実務書に記載の件ですが、雇用関係について明記してありますのでその通りかと思います。出向契約とありますが個々の契約内容により、出向とは名目であって、実は派遣であるということもあるのでしょうね。
ところで、一般的に「出向」といった場合は、労働者は出向元企業と出向先企業の両者との間に雇用関係を持つと思います。もちろん契約内容を見たら実は派遣だったということも有り得ると思います。
私の場合は、試験問題に「出向契約を締結している」旨の記載のみであれば、出向先と労働者に雇用関係があると理解して解答します。
あと、今回の問題は「出向」「経営指導料」「給与負担相当額」のキーワードで5-5-10の通達について聞いていると思います。これを派遣として解答するのは深読みのような気がします。
あくまで私の考えですので、他の方にもご意見を頂いて判断してください。
その?の答えが「雇用関係がないため当然不課税扱い」となっていますが、これだけ結論が逆ですね・・・
さて、実務書に記載の件ですが、雇用関係について明記してありますのでその通りかと思います。出向契約とありますが個々の契約内容により、出向とは名目であって、実は派遣であるということもあるのでしょうね。
ところで、一般的に「出向」といった場合は、労働者は出向元企業と出向先企業の両者との間に雇用関係を持つと思います。もちろん契約内容を見たら実は派遣だったということも有り得ると思います。
私の場合は、試験問題に「出向契約を締結している」旨の記載のみであれば、出向先と労働者に雇用関係があると理解して解答します。
あと、今回の問題は「出向」「経営指導料」「給与負担相当額」のキーワードで5-5-10の通達について聞いていると思います。これを派遣として解答するのは深読みのような気がします。
あくまで私の考えですので、他の方にもご意見を頂いて判断してください。
実務書はほどほどにってことですね。役に立つこともあるだろうけど場合によっては深読みしすぎちゃうことになるわけですね。自分も気をつけたいと思います。
給与負担金についてもいろいろあると思いますが、大原の全統での僕の最大の疑問は、中国の保税区内にある現地法人A社の工場に材料を無償で送って、それを用いて焼付け加工を施した後に、半製品として輸入したやつなんですけど、甲社とは何の関係もないA社の工場宛に無償で輸出した材料がなぜ「自己の使用」のための輸出に該当してみなし輸出になるか調べた方いらっしゃいますか?
自分の周りではあまりにもFOB価格が出てきたから怪しくてみなし輸出にしたっていう人はいましたけど、自分はどう考えても海外の支店でも工場でもない他社の工場だから「自己の使用」にならないだろうと思ってどんなにFOB価格が出てきても断じて計算に関係させないようにしました。
みなさんはどのように判断しましたか?またこれについて調べた方がいらっしゃったらご教示願いたいと思います。
給与負担金についてもいろいろあると思いますが、大原の全統での僕の最大の疑問は、中国の保税区内にある現地法人A社の工場に材料を無償で送って、それを用いて焼付け加工を施した後に、半製品として輸入したやつなんですけど、甲社とは何の関係もないA社の工場宛に無償で輸出した材料がなぜ「自己の使用」のための輸出に該当してみなし輸出になるか調べた方いらっしゃいますか?
自分の周りではあまりにもFOB価格が出てきたから怪しくてみなし輸出にしたっていう人はいましたけど、自分はどう考えても海外の支店でも工場でもない他社の工場だから「自己の使用」にならないだろうと思ってどんなにFOB価格が出てきても断じて計算に関係させないようにしました。
みなさんはどのように判断しましたか?またこれについて調べた方がいらっしゃったらご教示願いたいと思います。
>アンチョビさん
なるほど、確かにそう考えるしかないんですよね。あくまでA社の工場では半製品にしかしておらず、当社が輸入して完成形の商品を完成させて譲渡しているのだから「自己の使用のため」って考えるしかないんですよね。
でもやはりあくまで「A社の工場」で使用してるんですよね。A社の工場で使用していることが自己の使用に該当することがどうしても不思議でしょうがないんですよ。A社との契約で工場の一部を使用させていただいているとかだったらまだわかるんですけどね。でもそうであれば使用料をA社に支払っているはずなのにとか考えちゃうんですよね。
ちなみに通達では自己の使用の例としてはやはり国外に所在する自分の工場で使用するためくらいしか書いてないんです。あと質疑応答事例でも国外移送関係のものはあがってなかったです。
なるほど、確かにそう考えるしかないんですよね。あくまでA社の工場では半製品にしかしておらず、当社が輸入して完成形の商品を完成させて譲渡しているのだから「自己の使用のため」って考えるしかないんですよね。
でもやはりあくまで「A社の工場」で使用してるんですよね。A社の工場で使用していることが自己の使用に該当することがどうしても不思議でしょうがないんですよ。A社との契約で工場の一部を使用させていただいているとかだったらまだわかるんですけどね。でもそうであれば使用料をA社に支払っているはずなのにとか考えちゃうんですよね。
ちなみに通達では自己の使用の例としてはやはり国外に所在する自分の工場で使用するためくらいしか書いてないんです。あと質疑応答事例でも国外移送関係のものはあがってなかったです。
自分の14の記載に若干の修正をしたいと思います。
A社に対してはF9(8)で加工の委託料を支払っていたんですね。その部分を修正します。しかし、これで改めて疑問ですね。A社工場の使用料としてではなく、加工を委託したいわゆる外注加工ってことですよね。そうしたらなおさら「自己の使用」とは言えないと考えちゃいますよね。
>デイチさん
デイチさんの意見を読んで、問題文を読み返したら気づきました。F8(1)?(ロ)が国外移送に該当するのは、F7の下から2行目に(下記(ロ)に係るものを除く。)とあります。そしてF8(1)?(ロ)は「上記(イ)の無償輸出した加工用消耗材料の一部を」とあるので、当初輸出したのは(1)?(イ)と(ロ)の合計(9,500,000円+1,500,000円)だったということです。ということで、A社への輸出をみなし輸出であると百歩譲ったならば、これもみなし輸出にしないといけないことになります。
というわけで、やはり問題はA社に外注加工したことが自己の使用に該当するのかどうかということになりますね。
A社に対してはF9(8)で加工の委託料を支払っていたんですね。その部分を修正します。しかし、これで改めて疑問ですね。A社工場の使用料としてではなく、加工を委託したいわゆる外注加工ってことですよね。そうしたらなおさら「自己の使用」とは言えないと考えちゃいますよね。
>デイチさん
デイチさんの意見を読んで、問題文を読み返したら気づきました。F8(1)?(ロ)が国外移送に該当するのは、F7の下から2行目に(下記(ロ)に係るものを除く。)とあります。そしてF8(1)?(ロ)は「上記(イ)の無償輸出した加工用消耗材料の一部を」とあるので、当初輸出したのは(1)?(イ)と(ロ)の合計(9,500,000円+1,500,000円)だったということです。ということで、A社への輸出をみなし輸出であると百歩譲ったならば、これもみなし輸出にしないといけないことになります。
というわけで、やはり問題はA社に外注加工したことが自己の使用に該当するのかどうかということになりますね。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
消費税法@税理士試験 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
消費税法@税理士試験のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23167人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人