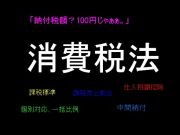またまた皆様のご意見を伺いたいと思いトピック上げをしてみました。
消費税法の試験における時間配分はどのようにされていますか?
自分は最初に計算を見て、計算70分、理論50分くらいで見て理論の柱を考えて書いています。
そして、計算のボリュームがあるときの「切り上げる」の意味がわかりません。
例えば調整対象固定資産の調整で解答用紙をどう見ても変動調整をしなければならなそうなとき、まず70分じゃ終わらないなと思ったとします。
実際だいたいのパターンで個別・一括の比較をしたくらいで65分くらいになってて(まずそこが遅いのでは?という突っ込みも大歓迎です )残り5分で調整対象固定資産に該当するかの判定と調整の要否(変動率・変動差じゃなくて第3年度の課税期間に該当しないとか課のみから非のみへの転用じゃないという意味の調整の要否)位で終わってしまうとしたときに、そこから先何もしないで理論に移るのか、それとも今の状態で取りあえず納付税額を出して理論に移るという意味なのかで悩んでます。
)残り5分で調整対象固定資産に該当するかの判定と調整の要否(変動率・変動差じゃなくて第3年度の課税期間に該当しないとか課のみから非のみへの転用じゃないという意味の調整の要否)位で終わってしまうとしたときに、そこから先何もしないで理論に移るのか、それとも今の状態で取りあえず納付税額を出して理論に移るという意味なのかで悩んでます。
皆さんは時間配分と「切り上げる」の意味はどのようにしていますか?
消費税法の試験における時間配分はどのようにされていますか?
自分は最初に計算を見て、計算70分、理論50分くらいで見て理論の柱を考えて書いています。
そして、計算のボリュームがあるときの「切り上げる」の意味がわかりません。
例えば調整対象固定資産の調整で解答用紙をどう見ても変動調整をしなければならなそうなとき、まず70分じゃ終わらないなと思ったとします。
実際だいたいのパターンで個別・一括の比較をしたくらいで65分くらいになってて(まずそこが遅いのでは?という突っ込みも大歓迎です
皆さんは時間配分と「切り上げる」の意味はどのようにしていますか?
|
|
|
|
コメント(7)
なるほどー
調整対象固定資産は確かに該当するかしないか、あと変動率・変動差のじゃなくて調整の要否を理解してるかの方が確かに重要なんでしょうね
ただ、過去問や最近の上級演習でも全く時間が足りずそこまでたどり着けないんですよね
ある程度分類が合ってれば得点は勝手にあがるんだけど、本試験で受かるってのはそういうことじゃないんですよね。きっと。
最近は計算70分・理論50分を目安にしようと思ってるんですけど、ボリュームが多いやつは納税義務やって、中間やって分類しながら貸倒れ・売返・回収債権やって、さあ仮計から写すぞって時にすでに50分くらい経ってるんですよね
やっぱり遅いんですかね…
調整対象固定資産は確かに該当するかしないか、あと変動率・変動差のじゃなくて調整の要否を理解してるかの方が確かに重要なんでしょうね
ただ、過去問や最近の上級演習でも全く時間が足りずそこまでたどり着けないんですよね
ある程度分類が合ってれば得点は勝手にあがるんだけど、本試験で受かるってのはそういうことじゃないんですよね。きっと。
最近は計算70分・理論50分を目安にしようと思ってるんですけど、ボリュームが多いやつは納税義務やって、中間やって分類しながら貸倒れ・売返・回収債権やって、さあ仮計から写すぞって時にすでに50分くらい経ってるんですよね
やっぱり遅いんですかね…
こんにちは。
僕の場合は理論→計算→理論の順でやってるので計算は調固がある場合は判定と転用だけをやって余裕があれば調整の要否の判定の方法を書いて第2問の理論に移ります。調固の変動は課税売上割合が合わないと無理な上に模試とかだと配点があまりこないのでとばすようにしています。本当に時間ない時は、一括もとばすときもあります。
僕も理論は1分1点と考えているので最低でも50分はかけます。・・・ってかかります
僕の場合は、よく大原の問題とかで「解答範囲に含まれるが時間と用紙を考慮して省く」と言うのがありますが、あの書いていいとこと書いたらアカンところの区別が苦手です 第1問で自分が書ける理論だとうれしくなってその範囲全部書いてしまいそのしわよせが計算や第2問の理論とかにきたりします
第1問で自分が書ける理論だとうれしくなってその範囲全部書いてしまいそのしわよせが計算や第2問の理論とかにきたりします みんなその辺はどうしてるんでしょう・・・もしよかったらお聞かせください
みんなその辺はどうしてるんでしょう・・・もしよかったらお聞かせください
僕の場合は理論→計算→理論の順でやってるので計算は調固がある場合は判定と転用だけをやって余裕があれば調整の要否の判定の方法を書いて第2問の理論に移ります。調固の変動は課税売上割合が合わないと無理な上に模試とかだと配点があまりこないのでとばすようにしています。本当に時間ない時は、一括もとばすときもあります。
僕も理論は1分1点と考えているので最低でも50分はかけます。・・・ってかかります
僕の場合は、よく大原の問題とかで「解答範囲に含まれるが時間と用紙を考慮して省く」と言うのがありますが、あの書いていいとこと書いたらアカンところの区別が苦手です
みなさんいろいろコメントありがとうございます。
レス遅くなって申し訳ございません。
いろいろ自分なりにもできる人に聞いてみたりしていたので遅くなってしまったのですが、やっぱり自分の分類が遅いんだってことに気づきました。
わからなかったら飛ばして分類を終える。そしてその段階で数字を出していく。それで時間が余ったらその分訂正を加えていく。
それで70分が到来したら理論にとりかかる。
これが一番なんだろうなと思いました。
そして今は計算過程を大原の計算パターンどおり(「課税仕入れ等の税額の合計額」は「課税仕入れ等」に省略するとかはしてますけど。)にやっているのですが、もう少し左側の金額欄を埋めていくことを意識してやってこうかなと思ってます。特に調整対象固定資産であれば、通算を出すときにきちんと「前課税期間」とか書いていたんですけど、よく考えればあれで大事なのは「仕入れ等の課税期間」の課税売上割合と通算課税売上割合で変動差・変動率出して判定することですもんね。それだけでもいいんだなと他の人の答案を見せてもらって思いました。
そういうところでスピードアップを図ることも大事だなと思いました。
今度の全統でそういうところを意識しながらやっていこうと思います。
ありがとうございました。
他にもいろいろこうしてるとかあったら教えてください。
レス遅くなって申し訳ございません。
いろいろ自分なりにもできる人に聞いてみたりしていたので遅くなってしまったのですが、やっぱり自分の分類が遅いんだってことに気づきました。
わからなかったら飛ばして分類を終える。そしてその段階で数字を出していく。それで時間が余ったらその分訂正を加えていく。
それで70分が到来したら理論にとりかかる。
これが一番なんだろうなと思いました。
そして今は計算過程を大原の計算パターンどおり(「課税仕入れ等の税額の合計額」は「課税仕入れ等」に省略するとかはしてますけど。)にやっているのですが、もう少し左側の金額欄を埋めていくことを意識してやってこうかなと思ってます。特に調整対象固定資産であれば、通算を出すときにきちんと「前課税期間」とか書いていたんですけど、よく考えればあれで大事なのは「仕入れ等の課税期間」の課税売上割合と通算課税売上割合で変動差・変動率出して判定することですもんね。それだけでもいいんだなと他の人の答案を見せてもらって思いました。
そういうところでスピードアップを図ることも大事だなと思いました。
今度の全統でそういうところを意識しながらやっていこうと思います。
ありがとうございました。
他にもいろいろこうしてるとかあったら教えてください。
>souさん
要するに柱上げの一種になりますよね。
僕は大原の応用理論テキストを使いながら柱上げを中心に今までやってきました。だから柱はあがるけど中身がかけないんですけど
例えば納税義務者関係のところで分割により設立した法人の納税義務の有無の判定について簡記しなさい。(大原生でもってらっしゃるなら44ページ)とあった場合であれば、納税義務と言えば納税義務者→小規模事業者に係る納税義務の免除までは浮かぶと思います。さて、その先の課税事業者選択届出書、相続・合併・分割等・吸収分割の特例(まあこの問題であれば分割等しかないんですけど )、新設法人の特例のどこから書くか、それぞれの関係は?と考えるとそれぞれは並立しているため優先順位はないんですね。そしたら問題文から読み取れることを優先的に書いていくべきと習いました。だから分割等から書いて、新設法人を書いていく(分割により設立した「法人の」とあるので。)。
)、新設法人の特例のどこから書くか、それぞれの関係は?と考えるとそれぞれは並立しているため優先順位はないんですね。そしたら問題文から読み取れることを優先的に書いていくべきと習いました。だから分割等から書いて、新設法人を書いていく(分割により設立した「法人の」とあるので。)。
と考えると、理論体系表を頭に入れておくことによりかなり柱が浮かびやすくなりますし、書いてはいけないところも浮かびやすくなります。
2年目以降の先輩方はやはり書く場所が浮かぶのが早いから書けちゃうんですよね?でもそこで理論体系表やそれぞれの意味を考えてみるとより書く場所の正確性はあがるのではないかと私は思ってます。
要するに柱上げの一種になりますよね。
僕は大原の応用理論テキストを使いながら柱上げを中心に今までやってきました。だから柱はあがるけど中身がかけないんですけど
例えば納税義務者関係のところで分割により設立した法人の納税義務の有無の判定について簡記しなさい。(大原生でもってらっしゃるなら44ページ)とあった場合であれば、納税義務と言えば納税義務者→小規模事業者に係る納税義務の免除までは浮かぶと思います。さて、その先の課税事業者選択届出書、相続・合併・分割等・吸収分割の特例(まあこの問題であれば分割等しかないんですけど
と考えると、理論体系表を頭に入れておくことによりかなり柱が浮かびやすくなりますし、書いてはいけないところも浮かびやすくなります。
2年目以降の先輩方はやはり書く場所が浮かぶのが早いから書けちゃうんですよね?でもそこで理論体系表やそれぞれの意味を考えてみるとより書く場所の正確性はあがるのではないかと私は思ってます。
最近やっと時間配分について自分の中でめどが立ってきました。
計算70分のうち納税義務の判定と中間納付と分類と調整対象固定資産の判定だけを合わせて45分くらいで終われるようにしてやっぱりある程度まともに仮計から写すだけでも20分かかるんですよね。だからそれで65分。で、最後5分で通算を電卓だけで出して変動率・変動差だけ書いて、いければ調整税額まで書いてみる。そしてやはり納付税額を適当に書いておく。
どうでしょう。もっといい概略をお持ちの方いたらよかったら教えてください。
例えば、電卓のみで正確な(もちろん満点という意味ではなく、全プロセスの数字を出してという意味)納付税額を出して、書ける範囲で計算過程を書いていくなんていう人もいるんでしょうか。
計算70分のうち納税義務の判定と中間納付と分類と調整対象固定資産の判定だけを合わせて45分くらいで終われるようにしてやっぱりある程度まともに仮計から写すだけでも20分かかるんですよね。だからそれで65分。で、最後5分で通算を電卓だけで出して変動率・変動差だけ書いて、いければ調整税額まで書いてみる。そしてやはり納付税額を適当に書いておく。
どうでしょう。もっといい概略をお持ちの方いたらよかったら教えてください。
例えば、電卓のみで正確な(もちろん満点という意味ではなく、全プロセスの数字を出してという意味)納付税額を出して、書ける範囲で計算過程を書いていくなんていう人もいるんでしょうか。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
消費税法@税理士試験 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
消費税法@税理士試験のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37846人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人