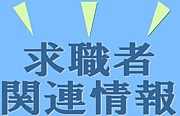改めて指摘するまでもなく、わが国は世界の中でも世代間格差が深刻な国の一つである。
国際的に世代間格差の大きさを見てみると、アメリカ51%、ドイツ92%、イタリア132%、フランス47%、スウェーデン▲22%、ノルウェー63%、カナダ0%、オーストラリア32%、タイ▲88%、アルゼンチン59%などとなっているのに対し、日本は209%である。わが国の世代間格差は、諸外国には例のない異常な水準であり、世界一深刻であることが確認できる。
しかも、先日筆者らが行った研究(「社会保障制度を通じた世代間利害対立の克服−シルバー民主主義を超えて−」NIRAモノグラフシリーズNo.34)によると、将来世代に関しては生涯所得の半分近く、実に48.4%の純負担を負わなければならず、将来世代の生活は生まれる前から実質的に破綻していることが明らかになっている。
結局、わが国において世代間格差が異常に大きいのは、(1)負担に比べて受益が相対的に大きいというアンバランスな社会保障制度における受益負担構造の問題、(2)少子高齢化の進行速度が早いという人口変動の問題、(3)初期時点の政府純債務が大きいという政府債務問題、(4)デフレの継続、(5)若い世代の雇用環境の不安定化、に起因するものと考えられている。
崩れつつある諸制度の前提
要すれば、わが国では、年齢が若いほど人口が多く、年齢が高いほど人口が少ないピラミッド型の年齢構造と高い経済成長がこれまで当然の前提とされ、社会保障制度をはじめとする諸制度が組み立てられてきた。しかし、1990年代後半以降は、少子化、高齢化の進行で逆ピラミッド型の人口構造へと転換するプロセスのまっただ中にあり、過去の前提が大きく崩れつつある。
例えば、実質GDP成長率の推移を見ると、高度成長期には10%近くあった経済成長率は、それ以降低下し、バブルの頃でも5%程度、さらに、90年代は1%程度、2000年代後半にいたっては0.1%とほぼ横ばい、ゼロ成長となっている(図1)。同図からも明らかなように、時が経つに連れて経済成長率は下方に屈折している。
経済の成長と雇用の創出は正比例の関係
総じて見れば、経済の成長(さらには物価上昇率)と雇用の創出との間には正比例の関係があるので、成長率が高いほど求人が多く、成長率が低いほど求人が少なくなる傾向がある。同じ問題意識で言えば、今月23日に厚生労働省の雇用政策を議論する有識者研究会は、一定の前提のもと、現在のゼロ成長が今後も続くとすれば、2030年の就業者数が2010年の6298万人から最大で845万人減少する可能性がある一方、2%成長に転じるなどした場合には就業者数の減少は213万人にとどまるとの推計を公表した。
2012年07月26日(Thu) 島澤 諭 (総合研究開発機構主任研究員)
http://
つまり、残念ながらこれからのわが国では、かつてほど豊富な仕事がすべての世代に供給されるような恵まれた状況にはならない可能性が非常に高い。仕事も少なく、給与も低い状況下で、増大する一方の社会保障関連支出を賄おうとすれば、いずれかの世代がその歪の影響を被ることとなってしまうだろう。
より大きなマイナスの影響を被る新卒世代
それにもかかわらず、社会保障等の分野において、旧来の人口、経済が右肩上がりだった時代に適した制度がそのまま維持されているため、世界でも稀に見る世代間格差が発生している。
実はわが国の雇用慣行も例外ではない。以前と比べれば幾分明るい兆しが見えつつある新卒者の就職戦線の現状であるが、それでもいわゆるリーマン・ショックの直前と比較すると低いままとなっている(図2)。
また、戦後の日本経済史を概観して見ると、日本経済にネガティブなインパクトを与えるイベントが発生した時期には若年者の失業率が高まっていることが確認できる。
例えば、第一次オイルショック時には、全世代の平均失業率が1.9%のときに、新規高卒者を含む15-19歳は3.6%、新規大卒者を含む20-24歳2.9%、第二次オイルショック時には、同じく順に2.2%、5.5%、3.6%、プラザ合意後の円高不況時は、2.8%、7.3%、4.6%、東アジア金融危機・消費税率引き上げ時には4.7%、12.5%、8.4%、ITバブル崩壊時は5.4%、12.8%、9.3%、そしてリーマン・ショック時は5.1%、9.8%、9.1%と、新卒世代の失業率が他の世代よりも大幅に高くなっている。
「景気が悪い時期の就活で運が悪かった」では
すまされない
このように経済が停滞すると、その後数年間失業率が高い期間が継続するが、より大きなマイナスの影響を被るのは、その時期に就職を迎える新卒者である。
しかし、「就職活動の時期がたまたま景気の悪い時期と重なって運が悪かった」という簡単な話ではない。なぜなら、これまでのわが国の場合、新卒で正社員として採用されなかった場合、その後も非正規の仕事しか得られない可能性が非常に高くなる。いわゆる新卒一括採用主義の弊害であるが、この点については、次回詳しく触れる。
アンフェアな若者批判
また、例えば、仕事が見つからず困っている学生に対して、社会、大半は企業や組織でそれなりの地位にあったりすでに退職している世代から「会社の規模や、仕事を選びさえしなければ仕事はたくさんある。最近の若者は仕事の選り好みしているだけだ。」という批判が浴びせられることがある。実際に、世代間格差について取り上げたあるテレビ番組に出演した時に、ある中央省庁の政務三役を務める政治家から発せられた言葉でもある。しかし、こうした発言は実は幾つかの点でフェアとは言えない。
まず、最近の学生は会社や仕事を選り好みするということに対しては、そもそも自分の好みや学歴に見合った就職先を選ぶのは悪いことだろうか。そういう発言をする者だって就職の時点で自分の希望を優先したはずだ。現在のわが国の雇用慣行では、首尾よく正社員として就職できた者は、よっぽどのことがない限り解雇される恐れがないという意味で、安定した「身分」が保証される。
つまり、一旦正社員になりさえすれば、内部はともかく外部との競争にさらされることのない立場である。自らが「選り好んだ」ポストは離さず、他人に選り好みするなというのは傲慢のそしりを免れないであろう。そのような批判をするのであれば、いつでも失職し、就職活動をしなければならなくなる可能性がある同じ土俵に立ってから行うべきだ。イス取りゲームでイスに座ったまま他人にイスを探せというのがルール違反であるのと同じ理屈だ。
「753問題」は最近の傾向ではない
また、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が入社後3年に以内に離職する傾向があることが知られている。いわゆる「753問題」である。
実はこの割合は、長期的にほぼ横ばいで安定しており、現在の若者に限った傾向ではない。ただ最近では、こうした傾向を指して、「最近の若者は堪え性が足りない」と若者を批判するのに使われたり、若者の職業観の欠如と理解しキャリア教育の推進のために使われることもある。しかし、苦労して得た仕事を3年で辞めてしまう者が昔から一定割合でいるのだから、「選り好みするな」という批判は、若者の雇用を取り巻く環境の変化を検討しない限りあまり意味のあるものとはならないだろう。
以上は、終身雇用、解雇規制に起因する問題である。この点についても次回詳しく扱う。
若い世代に押し付けられる経済停滞のツケ
さらに、就職環境の厳しさに関する世代間ギャップの存在も指摘できるだろう。つまり、現在すでに引退し、あるいはある程度の地位にある者が就職活動していた時期は、現在の高校生・大学生が直面する状況よりもはるかに恵まれた状況であった。
図3は世代別の失業率の推移を示したものであるが、この図から明らかなように、最近の若い世代ほどより高い失業率に直面していることが分かる(図3)。失業率は労働市場の厳しさの代理指標といえるから、失業率が低ければ就職がより容易であり、高ければ就職より困難な状況を示している。人は自分の経験を元に物事を判断することがままあるが、先のような発言をする者はまさにそうした罠に陥っている。
一体なぜ経済停滞のツケがその時々の若い世代に押し付けられてしまうのだろうか。筆者は、戦後日本企業や労働界、そして法曹界が営々と築きあげてきた雇用慣行にその原因が求められると考えている。そして、こうした雇用慣行は、たとえ能力が同じであったとしても、生まれた年で、差別的に扱うのに等しく、企業にとっても個人にとっても大きな損失をもたらしている。なによりもそこに合理的な理由は全く見当たらない。
次回は、わが国の雇用慣行の特徴と問題点、その解決策について検討する。
http://
国際的に世代間格差の大きさを見てみると、アメリカ51%、ドイツ92%、イタリア132%、フランス47%、スウェーデン▲22%、ノルウェー63%、カナダ0%、オーストラリア32%、タイ▲88%、アルゼンチン59%などとなっているのに対し、日本は209%である。わが国の世代間格差は、諸外国には例のない異常な水準であり、世界一深刻であることが確認できる。
しかも、先日筆者らが行った研究(「社会保障制度を通じた世代間利害対立の克服−シルバー民主主義を超えて−」NIRAモノグラフシリーズNo.34)によると、将来世代に関しては生涯所得の半分近く、実に48.4%の純負担を負わなければならず、将来世代の生活は生まれる前から実質的に破綻していることが明らかになっている。
結局、わが国において世代間格差が異常に大きいのは、(1)負担に比べて受益が相対的に大きいというアンバランスな社会保障制度における受益負担構造の問題、(2)少子高齢化の進行速度が早いという人口変動の問題、(3)初期時点の政府純債務が大きいという政府債務問題、(4)デフレの継続、(5)若い世代の雇用環境の不安定化、に起因するものと考えられている。
崩れつつある諸制度の前提
要すれば、わが国では、年齢が若いほど人口が多く、年齢が高いほど人口が少ないピラミッド型の年齢構造と高い経済成長がこれまで当然の前提とされ、社会保障制度をはじめとする諸制度が組み立てられてきた。しかし、1990年代後半以降は、少子化、高齢化の進行で逆ピラミッド型の人口構造へと転換するプロセスのまっただ中にあり、過去の前提が大きく崩れつつある。
例えば、実質GDP成長率の推移を見ると、高度成長期には10%近くあった経済成長率は、それ以降低下し、バブルの頃でも5%程度、さらに、90年代は1%程度、2000年代後半にいたっては0.1%とほぼ横ばい、ゼロ成長となっている(図1)。同図からも明らかなように、時が経つに連れて経済成長率は下方に屈折している。
経済の成長と雇用の創出は正比例の関係
総じて見れば、経済の成長(さらには物価上昇率)と雇用の創出との間には正比例の関係があるので、成長率が高いほど求人が多く、成長率が低いほど求人が少なくなる傾向がある。同じ問題意識で言えば、今月23日に厚生労働省の雇用政策を議論する有識者研究会は、一定の前提のもと、現在のゼロ成長が今後も続くとすれば、2030年の就業者数が2010年の6298万人から最大で845万人減少する可能性がある一方、2%成長に転じるなどした場合には就業者数の減少は213万人にとどまるとの推計を公表した。
2012年07月26日(Thu) 島澤 諭 (総合研究開発機構主任研究員)
http://
つまり、残念ながらこれからのわが国では、かつてほど豊富な仕事がすべての世代に供給されるような恵まれた状況にはならない可能性が非常に高い。仕事も少なく、給与も低い状況下で、増大する一方の社会保障関連支出を賄おうとすれば、いずれかの世代がその歪の影響を被ることとなってしまうだろう。
より大きなマイナスの影響を被る新卒世代
それにもかかわらず、社会保障等の分野において、旧来の人口、経済が右肩上がりだった時代に適した制度がそのまま維持されているため、世界でも稀に見る世代間格差が発生している。
実はわが国の雇用慣行も例外ではない。以前と比べれば幾分明るい兆しが見えつつある新卒者の就職戦線の現状であるが、それでもいわゆるリーマン・ショックの直前と比較すると低いままとなっている(図2)。
また、戦後の日本経済史を概観して見ると、日本経済にネガティブなインパクトを与えるイベントが発生した時期には若年者の失業率が高まっていることが確認できる。
例えば、第一次オイルショック時には、全世代の平均失業率が1.9%のときに、新規高卒者を含む15-19歳は3.6%、新規大卒者を含む20-24歳2.9%、第二次オイルショック時には、同じく順に2.2%、5.5%、3.6%、プラザ合意後の円高不況時は、2.8%、7.3%、4.6%、東アジア金融危機・消費税率引き上げ時には4.7%、12.5%、8.4%、ITバブル崩壊時は5.4%、12.8%、9.3%、そしてリーマン・ショック時は5.1%、9.8%、9.1%と、新卒世代の失業率が他の世代よりも大幅に高くなっている。
「景気が悪い時期の就活で運が悪かった」では
すまされない
このように経済が停滞すると、その後数年間失業率が高い期間が継続するが、より大きなマイナスの影響を被るのは、その時期に就職を迎える新卒者である。
しかし、「就職活動の時期がたまたま景気の悪い時期と重なって運が悪かった」という簡単な話ではない。なぜなら、これまでのわが国の場合、新卒で正社員として採用されなかった場合、その後も非正規の仕事しか得られない可能性が非常に高くなる。いわゆる新卒一括採用主義の弊害であるが、この点については、次回詳しく触れる。
アンフェアな若者批判
また、例えば、仕事が見つからず困っている学生に対して、社会、大半は企業や組織でそれなりの地位にあったりすでに退職している世代から「会社の規模や、仕事を選びさえしなければ仕事はたくさんある。最近の若者は仕事の選り好みしているだけだ。」という批判が浴びせられることがある。実際に、世代間格差について取り上げたあるテレビ番組に出演した時に、ある中央省庁の政務三役を務める政治家から発せられた言葉でもある。しかし、こうした発言は実は幾つかの点でフェアとは言えない。
まず、最近の学生は会社や仕事を選り好みするということに対しては、そもそも自分の好みや学歴に見合った就職先を選ぶのは悪いことだろうか。そういう発言をする者だって就職の時点で自分の希望を優先したはずだ。現在のわが国の雇用慣行では、首尾よく正社員として就職できた者は、よっぽどのことがない限り解雇される恐れがないという意味で、安定した「身分」が保証される。
つまり、一旦正社員になりさえすれば、内部はともかく外部との競争にさらされることのない立場である。自らが「選り好んだ」ポストは離さず、他人に選り好みするなというのは傲慢のそしりを免れないであろう。そのような批判をするのであれば、いつでも失職し、就職活動をしなければならなくなる可能性がある同じ土俵に立ってから行うべきだ。イス取りゲームでイスに座ったまま他人にイスを探せというのがルール違反であるのと同じ理屈だ。
「753問題」は最近の傾向ではない
また、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が入社後3年に以内に離職する傾向があることが知られている。いわゆる「753問題」である。
実はこの割合は、長期的にほぼ横ばいで安定しており、現在の若者に限った傾向ではない。ただ最近では、こうした傾向を指して、「最近の若者は堪え性が足りない」と若者を批判するのに使われたり、若者の職業観の欠如と理解しキャリア教育の推進のために使われることもある。しかし、苦労して得た仕事を3年で辞めてしまう者が昔から一定割合でいるのだから、「選り好みするな」という批判は、若者の雇用を取り巻く環境の変化を検討しない限りあまり意味のあるものとはならないだろう。
以上は、終身雇用、解雇規制に起因する問題である。この点についても次回詳しく扱う。
若い世代に押し付けられる経済停滞のツケ
さらに、就職環境の厳しさに関する世代間ギャップの存在も指摘できるだろう。つまり、現在すでに引退し、あるいはある程度の地位にある者が就職活動していた時期は、現在の高校生・大学生が直面する状況よりもはるかに恵まれた状況であった。
図3は世代別の失業率の推移を示したものであるが、この図から明らかなように、最近の若い世代ほどより高い失業率に直面していることが分かる(図3)。失業率は労働市場の厳しさの代理指標といえるから、失業率が低ければ就職がより容易であり、高ければ就職より困難な状況を示している。人は自分の経験を元に物事を判断することがままあるが、先のような発言をする者はまさにそうした罠に陥っている。
一体なぜ経済停滞のツケがその時々の若い世代に押し付けられてしまうのだろうか。筆者は、戦後日本企業や労働界、そして法曹界が営々と築きあげてきた雇用慣行にその原因が求められると考えている。そして、こうした雇用慣行は、たとえ能力が同じであったとしても、生まれた年で、差別的に扱うのに等しく、企業にとっても個人にとっても大きな損失をもたらしている。なによりもそこに合理的な理由は全く見当たらない。
次回は、わが国の雇用慣行の特徴と問題点、その解決策について検討する。
http://
|
|
|
|
|
|
|
|
62、求職者関連情報 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
62、求職者関連情報のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90052人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208284人