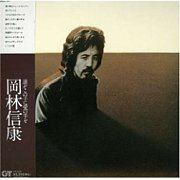検索からたどった或る方のブログの文章です。
私たち同世代に似通った印象があります。
歌詞だけを探していたのですが、参考になるので転載させていただきました。
http://
自由への長い旅/作詞・作曲・歌/岡林信康
♪いつのまにか私が
私でないような
枯葉が風に舞うように
小船が漂うように
私がもういちど
私になるために
育ててくれた世界に
別れを告げて旅立つ
信じたい為に疑いつづける
自由への長い旅をひとり
自由への長い旅を今日も
この歌は1970年、前年蒸発していた岡林信康さんが復帰後リリースしたセカンドアルバム「見る前に跳べ」に収録されています。
初期のフォークを語る人々にとって、岡林信康さんは無視できない存在です。1968年頃受験生ブルースで高石友也さんが注目されていた同時期に岡林さんが彗星のごとく現れます。フォークギター一本で歌う「くそくらえ節」「がいこつの唄」は強烈な社会風刺の曲として、フォーク好きな一部の若者の間に浸透していきます。
その年の秋、山谷ブルース・友よが発売されます。この唄で70年安保闘争を建前とした学生運動家のヒーローに奉られていきます。翌年1969年にリリースされたファーストアルバム「私を断罪せよ」の中には「手紙」や「チューリップのアップリケ」という部落差別を扱った唄もありました。
ボクも「友よ」で岡林さんを知りました。うろ覚えですが、ちょうど岡林さんが自分の作った唄が学生運動家のシンボルになって行く事に耐えられなくなって(多分) 蒸発した頃だと思います。
この時期に、マイク・真木さんから始まった森山良子さん、フォーセインツ、モダンフォークフェローズ、ブロードサイドフォー等、カレッジフォーク系に対し、関西フォークが席捲するようになる。岡林さんのほかに五つの赤い風船、デビュー当時の高田渡さん(後に東京へ)が代表格でした。情報源は深夜ラジオと新譜ジャーナルでした。とにかく新鮮で魅力的な唄が溢れていました。
岡林さんが復活した時フォークギターがエレキに変わっていました。バックバンドは何と皆さんご存知の「はっぴーえんど」です。メンバーは松本隆さん、細野晴臣さん、鈴木茂さん、大瀧詠一さんです。皆さん非凡な才能の持ち主であることは、知っていますね。
牧師の息子として育った岡林さんは同志社大学神学部に入りながら、その年の夏「山谷」にドロップアウトしてしまいます。この時から彼の内省がはじまります。常に自分が作り出す唄に対し、現実とのギャップに苦しみます。特に「友よ」が、左翼デモのテーマ曲やシンボルになってしまう事への重圧に押しつぶされてしまった時期もあったようです。
そういった時期に作った唄が「自由への長い旅」 だと推測します。
♪いつのまにか私が私でないような・・・
この一言に岡林さんの苦悩が表れています。性格的に真面目だからこそ余計苦しんだのでしょうか?そして何に苦しんだのでしょうか?
それは、自分の作った唄に自信が持てなくなったのだと思います。
♪友よ 夜明け前の闇の中で
友よ 闘いの炎を燃やせ
夜明けは近い
夜明けは近い
友よ この闇の向こうには
友よ 輝く明日がある
爆発的な支持を受けて一人歩きして行くこの唄を、ある時から歌わなくなります。
1971年7月28日の日比谷野外音楽堂で「狂い咲きコンサート」がありました。少年はこの日、岡林さんを見に出かけます。どんな風に聴いていたのかは、全く思い出せないのですが、今でも覚えている事がひとつだけあります。
今まで持っていたエレキギターをフォークギターに持ち替えて、静かに歌い始めました。確かナンセンスとかいいながら、「友よ〜夜明けまえの〜・・」と歌い始めました。今までに聴いたことの無い歌い方で、ゆっくりとそしてしっとりと歌ったのです。封印したはずの「友よ」でした。
少年は胸が一杯になりました。。
特に「友よ」に思い入れがあったわけではなかったのですが、岡林さんの苦悩が伝わっていたのかもしれません。
岡林信康さんは、この後すぐにサードアルバム「俺等いちぬけた」をリリースした後、都会を捨て5年間田舎に引き込んでしまう。
そして再び現れた時には、「演歌を歌う岡林信康」に変貌していました。
その頃の少年はすでにフォークを聴かない青年になっていたので、特に気にする事も無く時が過ぎていきました。それから20年近く時が経った頃、岡林信康さんのコンサートがあるというので、観にいきました。
そこには、またしても変貌している岡林さんがいました。エンヤトットのリズムと共に、純粋に音楽を楽しむ素敵な岡林さんがいました。
♪この道がどこを
通るのか知らない
知っているのはたどり着く
ところがあることだけ
そこが何処になるのか
そこで何があるのか
分からないまま一人で
別れを告げて旅立つ
信じたい為に疑い続ける
自由への長い旅をひとり
自由への長い旅を今日も
私たち同世代に似通った印象があります。
歌詞だけを探していたのですが、参考になるので転載させていただきました。
http://
自由への長い旅/作詞・作曲・歌/岡林信康
♪いつのまにか私が
私でないような
枯葉が風に舞うように
小船が漂うように
私がもういちど
私になるために
育ててくれた世界に
別れを告げて旅立つ
信じたい為に疑いつづける
自由への長い旅をひとり
自由への長い旅を今日も
この歌は1970年、前年蒸発していた岡林信康さんが復帰後リリースしたセカンドアルバム「見る前に跳べ」に収録されています。
初期のフォークを語る人々にとって、岡林信康さんは無視できない存在です。1968年頃受験生ブルースで高石友也さんが注目されていた同時期に岡林さんが彗星のごとく現れます。フォークギター一本で歌う「くそくらえ節」「がいこつの唄」は強烈な社会風刺の曲として、フォーク好きな一部の若者の間に浸透していきます。
その年の秋、山谷ブルース・友よが発売されます。この唄で70年安保闘争を建前とした学生運動家のヒーローに奉られていきます。翌年1969年にリリースされたファーストアルバム「私を断罪せよ」の中には「手紙」や「チューリップのアップリケ」という部落差別を扱った唄もありました。
ボクも「友よ」で岡林さんを知りました。うろ覚えですが、ちょうど岡林さんが自分の作った唄が学生運動家のシンボルになって行く事に耐えられなくなって(多分) 蒸発した頃だと思います。
この時期に、マイク・真木さんから始まった森山良子さん、フォーセインツ、モダンフォークフェローズ、ブロードサイドフォー等、カレッジフォーク系に対し、関西フォークが席捲するようになる。岡林さんのほかに五つの赤い風船、デビュー当時の高田渡さん(後に東京へ)が代表格でした。情報源は深夜ラジオと新譜ジャーナルでした。とにかく新鮮で魅力的な唄が溢れていました。
岡林さんが復活した時フォークギターがエレキに変わっていました。バックバンドは何と皆さんご存知の「はっぴーえんど」です。メンバーは松本隆さん、細野晴臣さん、鈴木茂さん、大瀧詠一さんです。皆さん非凡な才能の持ち主であることは、知っていますね。
牧師の息子として育った岡林さんは同志社大学神学部に入りながら、その年の夏「山谷」にドロップアウトしてしまいます。この時から彼の内省がはじまります。常に自分が作り出す唄に対し、現実とのギャップに苦しみます。特に「友よ」が、左翼デモのテーマ曲やシンボルになってしまう事への重圧に押しつぶされてしまった時期もあったようです。
そういった時期に作った唄が「自由への長い旅」 だと推測します。
♪いつのまにか私が私でないような・・・
この一言に岡林さんの苦悩が表れています。性格的に真面目だからこそ余計苦しんだのでしょうか?そして何に苦しんだのでしょうか?
それは、自分の作った唄に自信が持てなくなったのだと思います。
♪友よ 夜明け前の闇の中で
友よ 闘いの炎を燃やせ
夜明けは近い
夜明けは近い
友よ この闇の向こうには
友よ 輝く明日がある
爆発的な支持を受けて一人歩きして行くこの唄を、ある時から歌わなくなります。
1971年7月28日の日比谷野外音楽堂で「狂い咲きコンサート」がありました。少年はこの日、岡林さんを見に出かけます。どんな風に聴いていたのかは、全く思い出せないのですが、今でも覚えている事がひとつだけあります。
今まで持っていたエレキギターをフォークギターに持ち替えて、静かに歌い始めました。確かナンセンスとかいいながら、「友よ〜夜明けまえの〜・・」と歌い始めました。今までに聴いたことの無い歌い方で、ゆっくりとそしてしっとりと歌ったのです。封印したはずの「友よ」でした。
少年は胸が一杯になりました。。
特に「友よ」に思い入れがあったわけではなかったのですが、岡林さんの苦悩が伝わっていたのかもしれません。
岡林信康さんは、この後すぐにサードアルバム「俺等いちぬけた」をリリースした後、都会を捨て5年間田舎に引き込んでしまう。
そして再び現れた時には、「演歌を歌う岡林信康」に変貌していました。
その頃の少年はすでにフォークを聴かない青年になっていたので、特に気にする事も無く時が過ぎていきました。それから20年近く時が経った頃、岡林信康さんのコンサートがあるというので、観にいきました。
そこには、またしても変貌している岡林さんがいました。エンヤトットのリズムと共に、純粋に音楽を楽しむ素敵な岡林さんがいました。
♪この道がどこを
通るのか知らない
知っているのはたどり着く
ところがあることだけ
そこが何処になるのか
そこで何があるのか
分からないまま一人で
別れを告げて旅立つ
信じたい為に疑い続ける
自由への長い旅をひとり
自由への長い旅を今日も
|
|
|
|
コメント(12)
知人の神学生が神父になる為の請願をせずに山谷に移り住んだのは、私が高校生の頃でした。彼を敬愛していた私は、初めて山谷を知りました。そしてボランティアに行き、岡林さんの「山谷ブルース」を知りました。
大学に入り、ニューミュージックや松田聖子さんなど色々な歌を聞く中、岡林さんの事は忘れていきました。
再会は先輩が貸してくれた「岡林信康」ベストアルバムでした。当時私は地方の小学校に数日滞在しては人形劇や影絵を見せてまた次の学校へ行くという部に所属していました。その時岡林さんの歌を聞いていたら「あまりにも暗いからやめて」と後輩に言われ、自分は異質なのかと感じた事を覚えています。
小学校の教員になり、楽しいながらも悩みも多い日常を過ごしていたころ、夜のヒットスタジオに岡林さんが出演すると知り、心踊らせながらその時を迎えました。その時歌われたのが「君に捧げるラブソング」でした。あの歌が突然の病に倒れ、自由に動く事ができなくなった、岡林さんを撮り続けていたカメラマンを思って書かれた歌だと知ったのは、つい最近です。
結婚し育児と家事のみの暮らしの中、ある日主人が買ってきてくれたのが「ペア・ナックルミュージック」。和のリズムを取り入れた曲の中に「山辺に向いて」「嘆きの淵にある時も」などの静かな心にしみいる歌がありました。
今年七月初めてコンサートに行き、岡林さんの歌と、共演されていた様々なジャンルの方の演奏を聞き、強い感動がありました。どの方もそれぞれのジャンルのプロです。技術が高い。でも彼等がきちんと調和している。岡林さんを中心に
岡林さんの感性と表現力は素晴らしい。私は童話「銀河鉄道の夜」を愛読しています。話の中にある言葉が出てきます。岡林さんの歌の底にも同じテ−マを感じる時があります。
岡林さんの歌が好きです。これからは何処でも誰の前でも臆せずそう語る事に決めました。思いのままにだらだら書いてすみません。「でも、私は書きたかった。」(手紙)より
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
mixii岡林信康三宅洋平の会 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
mixii岡林信康三宅洋平の会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90068人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208325人
- 3位
- 酒好き
- 170698人