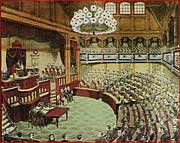会社員の方なら大抵はIDカードと言うものを会社から持たされているだろうが、このIDカードというのは他人が私を私であると識別(identify)するためのものである。しかし、心理学や哲学では、「アイデンティティ」と言う時は自分に対する自己認識を問題にしているらしい。
三省堂辞書サイトによると、
「学術用語としてのアイデンティティーの定義は、哲学分野では、『ものがそれ自身に対して同じであって、一個のものとして存在すること』です。心理学・社会学・人間学などでは、『人が朱鷺や場面を超えて一個の人格として存在し、自己を自己として確信する自我の統一を持っていること』と説明され、『本質的自己規定』をさします。」
となっているが、ここで一つの素朴な疑問がわいてくる。
私には「自己を自己として確信できない」という状態がいかなるものかが想像できないのだ。「私が私でない。」という言い方をする時があるが、それは比喩的な表現であって、まともな表現としてはそもそも文法的に間違っている。
私の体や考え方は毎日変化している。子供の頃の私と現在の私ではまるで別人である。しかし私が私以外であったことはないのである。たとえ記憶をすべて喪失したとしても、正気である限り、いや、もしかしたら正気を失くしたとしても、私は「私は私である。」と言うだろう。どう考えても、私は私以外ではありえないだろうからである。
そんなわけで私は、「アイデンティティの危機」などという言葉を耳にすると、深刻な統合失調症のような印象を受けてしまうし、やたらと「おれの日本人としてのアイデンティティがさぁ‥‥」などと連発する昨今の風潮には少なからず反発を感じる。
心理学のことはよく知らないので、「アイデンティティ」という言葉の意義の有効性について断定的なことは言えないが、この言葉を心理学以外で安易に多用することには抵抗を感じる。
みなさん、アイデンティティってなんだと思いますか?
三省堂辞書サイトによると、
「学術用語としてのアイデンティティーの定義は、哲学分野では、『ものがそれ自身に対して同じであって、一個のものとして存在すること』です。心理学・社会学・人間学などでは、『人が朱鷺や場面を超えて一個の人格として存在し、自己を自己として確信する自我の統一を持っていること』と説明され、『本質的自己規定』をさします。」
となっているが、ここで一つの素朴な疑問がわいてくる。
私には「自己を自己として確信できない」という状態がいかなるものかが想像できないのだ。「私が私でない。」という言い方をする時があるが、それは比喩的な表現であって、まともな表現としてはそもそも文法的に間違っている。
私の体や考え方は毎日変化している。子供の頃の私と現在の私ではまるで別人である。しかし私が私以外であったことはないのである。たとえ記憶をすべて喪失したとしても、正気である限り、いや、もしかしたら正気を失くしたとしても、私は「私は私である。」と言うだろう。どう考えても、私は私以外ではありえないだろうからである。
そんなわけで私は、「アイデンティティの危機」などという言葉を耳にすると、深刻な統合失調症のような印象を受けてしまうし、やたらと「おれの日本人としてのアイデンティティがさぁ‥‥」などと連発する昨今の風潮には少なからず反発を感じる。
心理学のことはよく知らないので、「アイデンティティ」という言葉の意義の有効性について断定的なことは言えないが、この言葉を心理学以外で安易に多用することには抵抗を感じる。
みなさん、アイデンティティってなんだと思いますか?
|
|
|
|
コメント(45)
民族意識の高い青年がいたと仮定しよう。常々日本人であることを誇りに思い、小さいころから朝鮮学校の生徒とはよくいざこざを起こしたりしていた。口癖は「ケッ、チョウセンがっ」である。そんな彼が海外旅行のためのパスポート申請で戸籍謄本を取り寄せたとき、自分の父親が元在日韓国人で日本に帰化していたことが分かってしまった。もともとの姓は「金」で通称が「金本」だったが、帰化の時点で「兼本」とし同時に在日社会とも絶縁していたので、その青年は自分が生粋の日本人であると思い込んでいたのだ。
このような状況の時、その青年は「アイデンティティの危機」に陥るのだろうか?
彼の国籍はもともと日本人だし、日常的に日本語を話し、日本文化の中で育ってきた。そんな彼が「日本人としてアイデンティティの危機」を感じたのだとしたら、もともと彼が持っていた「日本人」の概念に大した意味はなかったのではないかと私は考えてしまう。彼は何も変わっていない、以前と違うのは彼の父親が帰化人だという情報を知ったというだけのことである。彼にとって「日本人」というのは単なる記号以上のものではなかったということではないのだろうか。同時に、こんなものをわざわざ「アイデンティティの危機」などと表現することもないような気がする。
このような状況の時、その青年は「アイデンティティの危機」に陥るのだろうか?
彼の国籍はもともと日本人だし、日常的に日本語を話し、日本文化の中で育ってきた。そんな彼が「日本人としてアイデンティティの危機」を感じたのだとしたら、もともと彼が持っていた「日本人」の概念に大した意味はなかったのではないかと私は考えてしまう。彼は何も変わっていない、以前と違うのは彼の父親が帰化人だという情報を知ったというだけのことである。彼にとって「日本人」というのは単なる記号以上のものではなかったということではないのだろうか。同時に、こんなものをわざわざ「アイデンティティの危機」などと表現することもないような気がする。
そして、大人であっても自尊感情の高い人との対話によって自らが発達し成長しているという体験をし、自尊感情が高まっていきますね。
自尊感情の高い人は、自分の感情をありのままに受け止める力があるので 正直です。
また、他の人を手段だと考えたりしません。考えたとしても そういう自分を 意識する力もあります。
ましてや 苦しんでいる人の苦しみにつけこむような行為は、人としてできないでしょう。
自尊感情の高い人は、自分の行為も 健康的なセルフ・アイデンティティに根ざしているので 良い意味の誇りがあるのではないでしょうか。
矜持です。
行きつ戻りつで 深まっていくようなものなのだろうと思います。自尊感情の高い大人な人の存在は、自分の個性が適応し、喜びを得られるようなばしょへ誘う助けとなります。
有難いです。やっばり 人生には 偶然は ないんじゃないでしょうか。
お恥ずかしいですが、、私自身は、まだまだ、大人になりきれていないところがあると思っていて、、悩みながら少しずつ進んでいます。
でも、思春期の頃よりも悩み方が違ってきました。悩む問題が違ってきました。セルフ・アイデンティティが確立してきたのかもしれません、、。
いろんな方達やいろんなばしょのおかげです。
ありがとうございますp(^^)q
自尊感情の高い人は、自分の感情をありのままに受け止める力があるので 正直です。
また、他の人を手段だと考えたりしません。考えたとしても そういう自分を 意識する力もあります。
ましてや 苦しんでいる人の苦しみにつけこむような行為は、人としてできないでしょう。
自尊感情の高い人は、自分の行為も 健康的なセルフ・アイデンティティに根ざしているので 良い意味の誇りがあるのではないでしょうか。
矜持です。
行きつ戻りつで 深まっていくようなものなのだろうと思います。自尊感情の高い大人な人の存在は、自分の個性が適応し、喜びを得られるようなばしょへ誘う助けとなります。
有難いです。やっばり 人生には 偶然は ないんじゃないでしょうか。
お恥ずかしいですが、、私自身は、まだまだ、大人になりきれていないところがあると思っていて、、悩みながら少しずつ進んでいます。
でも、思春期の頃よりも悩み方が違ってきました。悩む問題が違ってきました。セルフ・アイデンティティが確立してきたのかもしれません、、。
いろんな方達やいろんなばしょのおかげです。
ありがとうございますp(^^)q
>>[18]
コミュニティへの帰属意識というのは私にも理解できます。社会的動物として進化してきた私達の遺伝子には確かにそのような性質が刻み込まれているはずです。家族やふるさとは私たちの心のよりどころです。国家もその延長として考えられるのは自然な感じがします。しかし、私に言わせれば、それは「自然な感じ」がするだけで、近代国家は既に私達には把握できないほど抽象的なものになってしまっているのではないかということです。
「日本人のアイデンティティ」というとき、日本が何であるかということが本当に分かり得るのかという疑問がわたしにはあります。もっと言えば、日本というものが本当にあるのかと私は疑っています。
コミュニティへの帰属意識というのは私にも理解できます。社会的動物として進化してきた私達の遺伝子には確かにそのような性質が刻み込まれているはずです。家族やふるさとは私たちの心のよりどころです。国家もその延長として考えられるのは自然な感じがします。しかし、私に言わせれば、それは「自然な感じ」がするだけで、近代国家は既に私達には把握できないほど抽象的なものになってしまっているのではないかということです。
「日本人のアイデンティティ」というとき、日本が何であるかということが本当に分かり得るのかという疑問がわたしにはあります。もっと言えば、日本というものが本当にあるのかと私は疑っています。
>>[5]
考える糧ゴリーコミュニティへの御参加 ありがとうございました。p(^^)q
初コメントありがとうございます。
また、積極的なご参加に、心から感謝いたします。
トピックの数に対して アクティブメンバーが少ない感じなので申し訳ないのですけど、、、まったりいきたいと思っています。
トピック立ても歓迎いたします。白熱トピックも歓迎いたします♪
★☆★
それから、ご都合の良いときに「 まずは自己紹介からどうぞ」トピックに 短くていいので 自己紹介をお願いいたします♪
★☆★
2016年10月以降にコミュニティに参加してくださったメンバーの皆様、すみませんが、よろしくお願いいたします。
★☆★
「管理人の伝言板トピック(外の方にも)」にも、書いてきます。
トピック主さん、お邪魔いたしました。
考える糧ゴリーコミュニティへの御参加 ありがとうございました。p(^^)q
初コメントありがとうございます。
また、積極的なご参加に、心から感謝いたします。
トピックの数に対して アクティブメンバーが少ない感じなので申し訳ないのですけど、、、まったりいきたいと思っています。
トピック立ても歓迎いたします。白熱トピックも歓迎いたします♪
★☆★
それから、ご都合の良いときに「 まずは自己紹介からどうぞ」トピックに 短くていいので 自己紹介をお願いいたします♪
★☆★
2016年10月以降にコミュニティに参加してくださったメンバーの皆様、すみませんが、よろしくお願いいたします。
★☆★
「管理人の伝言板トピック(外の方にも)」にも、書いてきます。
トピック主さん、お邪魔いたしました。
>>[22]
唯識についてはよくわかりません。私は仏教について語ることが結構ありますが、教理を系統的に学ぶということは全然しておりません。あくまで、自分の体験をもとに我流に考えたもので、もしかしたら「仏教」と言ってはいけないかもしれないと思っています。とことわっておきます。
龍樹の「すべては陽炎と見よ。」という言葉は、私は概念を否定したものと受け止めています。空というのは概念の解体であるというのが私の考えです。その辺のことはブログ記事にしておりますので、興味がおありでしたら読んでみて下さい。
「ゲシュタルト崩壊と空観、それから龍樹へ」
http://blog.goo.ne.jp/gorian21/e/08ffaed9d640ab60d7683841f5c8b637
http://blog.goo.ne.jp/gorian21/e/5d38a9251b195e4672409950fd7b1412
http://blog.goo.ne.jp/gorian21/e/46fffa0c784e9dc2027e949f91f1fd75
そういう観点から、私は「日本」というのも陽炎のようなものではないかと思うのです。家族や友人を守るために戦う、という気持ちは人間の本能に根差した実感であると、私も思います。その延長上に、「国を守るために戦う」ということがある、と人は考えがちですが、実はそれは陽炎のような虚像ではないかと考えるのです。
>私は生まれる時期を間違えた、特攻隊として死にたかった…
「身捨つるほどの祖国」はないと私は思います。
唯識についてはよくわかりません。私は仏教について語ることが結構ありますが、教理を系統的に学ぶということは全然しておりません。あくまで、自分の体験をもとに我流に考えたもので、もしかしたら「仏教」と言ってはいけないかもしれないと思っています。とことわっておきます。
龍樹の「すべては陽炎と見よ。」という言葉は、私は概念を否定したものと受け止めています。空というのは概念の解体であるというのが私の考えです。その辺のことはブログ記事にしておりますので、興味がおありでしたら読んでみて下さい。
「ゲシュタルト崩壊と空観、それから龍樹へ」
http://blog.goo.ne.jp/gorian21/e/08ffaed9d640ab60d7683841f5c8b637
http://blog.goo.ne.jp/gorian21/e/5d38a9251b195e4672409950fd7b1412
http://blog.goo.ne.jp/gorian21/e/46fffa0c784e9dc2027e949f91f1fd75
そういう観点から、私は「日本」というのも陽炎のようなものではないかと思うのです。家族や友人を守るために戦う、という気持ちは人間の本能に根差した実感であると、私も思います。その延長上に、「国を守るために戦う」ということがある、と人は考えがちですが、実はそれは陽炎のような虚像ではないかと考えるのです。
>私は生まれる時期を間違えた、特攻隊として死にたかった…
「身捨つるほどの祖国」はないと私は思います。
>>[35]
アイデンティティーを中心概念として精神発達の理論を建てたのは、エリクソンという人です。フロイトの欲動理論に従って個人の発達における社会との相互作用を考えたものです。これ自体は立派な業績で、大学の心理や教育の学生は必ず教えられました。多分今でもそうでしょう。
重要なのは、理論の内容よりエリクソン先生がアメリカ市民であることでしょう。知的エリートで有産者で、調べてないけれど多分クリスチャン。要するに西欧の自立した個人をベースにして発想してるのは確かです。
ところが、「アイデンティティー」のような概念だけが輸入されると、そこがおかしくなるわけです。
文化的に日本人は個人ではなく共同体をベースに考る傾向が強い。
暗黙にそれを前提にすると、対象への没入や自我の溶解を「アイデンティティー」だと言いかねない(笑
じっさいそういう言説は山ほどあるんですけどね。
アイデンティティーを中心概念として精神発達の理論を建てたのは、エリクソンという人です。フロイトの欲動理論に従って個人の発達における社会との相互作用を考えたものです。これ自体は立派な業績で、大学の心理や教育の学生は必ず教えられました。多分今でもそうでしょう。
重要なのは、理論の内容よりエリクソン先生がアメリカ市民であることでしょう。知的エリートで有産者で、調べてないけれど多分クリスチャン。要するに西欧の自立した個人をベースにして発想してるのは確かです。
ところが、「アイデンティティー」のような概念だけが輸入されると、そこがおかしくなるわけです。
文化的に日本人は個人ではなく共同体をベースに考る傾向が強い。
暗黙にそれを前提にすると、対象への没入や自我の溶解を「アイデンティティー」だと言いかねない(笑
じっさいそういう言説は山ほどあるんですけどね。
■自己もアイデンティティも虚構である。
ある脳科学者は「自分という主体意識は脳が作り出す仮想でしかない」と言う。いまの科学ではそれしか言えない。反論するためには、霊なり魂の存在を証明する必要がある。自己は仮想に過ぎない。科学的にはその通りだ。
最近ますます盛んになっている心理学ブームからはトンデモナイ理論や考え方が次々と登場している。思い通りに生きる方法などあり得ないのだし、たとえそれが実現しても面白くないように思うのだが、そういう本を好んで読む人がいるということにも唖然とさせられる。近年は特には唖然とさせらることが増えてきた。きっとこれは私に限った話ではないだろう。(笑)
昔よく使われたアイデンティティ(自分は何者であり、何をなすべきかという自己の定義。自己同一性。本稿では帰属アイデンティティは除外する。)というのも、自己と同様に虚構であり仮想だ。そこには本質もなければ実体もない。この事実を正しく理解しておかないと、とんでもない罠に落ちる。
■臨床心理学の落とし穴
臨床心理学は科学ではない。心理学者は思い思いの仮説を作って行くが、その仮説が正しいか否かが問われることはない。それでも学問だとされるのは、科学的な証明はできないが臨床では成果を上げていると思われているからだ。
もっとも、これらの考え方や技法は適度に用いるべきであって、深く追求すると泥沼になる。「本当の自分」だとか「自分らしさ」などということは、どんなに考えても答えの出るような問題ではない。単なる時間の無駄ならまだしも、かえって悩みを増やすことになる。
臨床心理学の知見や技法を使うことに問題はないが、期待し過ぎたり、深く追求したりしてはいけない。ヒントやきっかけ、あるいは気休めにはなるかもしれないが、それですべての問題が解決できるような性質のものではない。使用法を間違えれば、薬も毒になる。そういうものだ。
■アイデンティティという虚構
人間とは言葉という過剰を背負った動物である。丸山圭三郎の言葉を使えば、本能レベルの「身分け構造」と、言語レベルの「言分け構造」によって引き裂かれた世界を生きている。生きる意味や、自分の価値を考えずにはいられない。なんとも面倒くさい動物なのだ。
性格や個性ならともかく「アイデンティティ」という言葉はえらそうだ。そして、この概念が登場してから、多くの人が「アイデンティティ」は重要なのだと考えるようになった。しかし、アイデンティティもまた虚構であり、流動的なものなのだから、確固たるアイデンティティを確立するなどという方向性は一長一短だ。
生涯を通じて首尾一貫したアイデンティティを貫く人などいないし、それが正しい生き方でも、素晴らしい生き方でもない。むしろ、状況に応じて虚構としてのアイデンティティを柔軟に変えて行くことの方が重要だろう。
心というのは映像のようなものだ。多くの要素が像を描いているだけで、本質もなければ実体もない。本質があるかのように振る舞うために、アイデンティティという虚構を作る、という解釈すら成り立つだろう。人間には本質とか実体というものを求める性質があるのだから。
■現実と虚構
私たちは現実を生きていると感じている。しかし、現実とは何かを突き詰めると、私たちは現実から得られる虚構を見ているだけであり、決して現実の世界を見ることのできない動物だということになる。
そんな馬鹿な話はないだろう。そうではなく、虚構もまた現実の一形態なのだ。私たちは、虚構あるいは仮想を共有することで社会を形成して生きている。
言い換えると、共有できる虚構が存在するから世界は成立しているのであり、自分自身というものを意識することができる。もっとも、そこには共有できない多くの差異がある。危険なのは一つの現実こそが真実であるという馬鹿げた信念だ。
20世紀哲学の最大の功績は、絶対的な真理など存在しないということを証明したことにある。これからの時代を生きるためには、アイデンティティという虚構を画期的に変化させる必要があるのだろう。それには、世界についての新しい文脈が必要となる。いま、新しい世界観が切実に求められている。
ある脳科学者は「自分という主体意識は脳が作り出す仮想でしかない」と言う。いまの科学ではそれしか言えない。反論するためには、霊なり魂の存在を証明する必要がある。自己は仮想に過ぎない。科学的にはその通りだ。
最近ますます盛んになっている心理学ブームからはトンデモナイ理論や考え方が次々と登場している。思い通りに生きる方法などあり得ないのだし、たとえそれが実現しても面白くないように思うのだが、そういう本を好んで読む人がいるということにも唖然とさせられる。近年は特には唖然とさせらることが増えてきた。きっとこれは私に限った話ではないだろう。(笑)
昔よく使われたアイデンティティ(自分は何者であり、何をなすべきかという自己の定義。自己同一性。本稿では帰属アイデンティティは除外する。)というのも、自己と同様に虚構であり仮想だ。そこには本質もなければ実体もない。この事実を正しく理解しておかないと、とんでもない罠に落ちる。
■臨床心理学の落とし穴
臨床心理学は科学ではない。心理学者は思い思いの仮説を作って行くが、その仮説が正しいか否かが問われることはない。それでも学問だとされるのは、科学的な証明はできないが臨床では成果を上げていると思われているからだ。
もっとも、これらの考え方や技法は適度に用いるべきであって、深く追求すると泥沼になる。「本当の自分」だとか「自分らしさ」などということは、どんなに考えても答えの出るような問題ではない。単なる時間の無駄ならまだしも、かえって悩みを増やすことになる。
臨床心理学の知見や技法を使うことに問題はないが、期待し過ぎたり、深く追求したりしてはいけない。ヒントやきっかけ、あるいは気休めにはなるかもしれないが、それですべての問題が解決できるような性質のものではない。使用法を間違えれば、薬も毒になる。そういうものだ。
■アイデンティティという虚構
人間とは言葉という過剰を背負った動物である。丸山圭三郎の言葉を使えば、本能レベルの「身分け構造」と、言語レベルの「言分け構造」によって引き裂かれた世界を生きている。生きる意味や、自分の価値を考えずにはいられない。なんとも面倒くさい動物なのだ。
性格や個性ならともかく「アイデンティティ」という言葉はえらそうだ。そして、この概念が登場してから、多くの人が「アイデンティティ」は重要なのだと考えるようになった。しかし、アイデンティティもまた虚構であり、流動的なものなのだから、確固たるアイデンティティを確立するなどという方向性は一長一短だ。
生涯を通じて首尾一貫したアイデンティティを貫く人などいないし、それが正しい生き方でも、素晴らしい生き方でもない。むしろ、状況に応じて虚構としてのアイデンティティを柔軟に変えて行くことの方が重要だろう。
心というのは映像のようなものだ。多くの要素が像を描いているだけで、本質もなければ実体もない。本質があるかのように振る舞うために、アイデンティティという虚構を作る、という解釈すら成り立つだろう。人間には本質とか実体というものを求める性質があるのだから。
■現実と虚構
私たちは現実を生きていると感じている。しかし、現実とは何かを突き詰めると、私たちは現実から得られる虚構を見ているだけであり、決して現実の世界を見ることのできない動物だということになる。
そんな馬鹿な話はないだろう。そうではなく、虚構もまた現実の一形態なのだ。私たちは、虚構あるいは仮想を共有することで社会を形成して生きている。
言い換えると、共有できる虚構が存在するから世界は成立しているのであり、自分自身というものを意識することができる。もっとも、そこには共有できない多くの差異がある。危険なのは一つの現実こそが真実であるという馬鹿げた信念だ。
20世紀哲学の最大の功績は、絶対的な真理など存在しないということを証明したことにある。これからの時代を生きるためには、アイデンティティという虚構を画期的に変化させる必要があるのだろう。それには、世界についての新しい文脈が必要となる。いま、新しい世界観が切実に求められている。
「わたし」は脳の中にいるわけではないからねえ。
脳は物体なんだから、そんなところから「わたし」という人間が出て来たらお化けみたいなことになる。
脳が不幸にして病気や外傷で破壊された場合、精神が変容することもあるし、最悪なら意識が消失する。しかしそれは、家の前の電柱にあるケーブルが切れて、固定電話やインターネット接続ができなくなるのと、そう違いが無いのではないか。
脳が意識を「作り出す」というのは、十分な根拠を欠いている。
「意識は脳に<依ってある>」で十分だし、それ以上は空想でしかない。
<依ってある>在り方というのはわれわれにはお馴染みのもので、それは大乗仏教哲学の基本的な構えなんだけどね。近代哲学でも、個物の自立ではなく「関係の先在」を言う立場というのはたくさん例がある。
方向性としてはそっちで正解だと思っています。
脳は物体なんだから、そんなところから「わたし」という人間が出て来たらお化けみたいなことになる。
脳が不幸にして病気や外傷で破壊された場合、精神が変容することもあるし、最悪なら意識が消失する。しかしそれは、家の前の電柱にあるケーブルが切れて、固定電話やインターネット接続ができなくなるのと、そう違いが無いのではないか。
脳が意識を「作り出す」というのは、十分な根拠を欠いている。
「意識は脳に<依ってある>」で十分だし、それ以上は空想でしかない。
<依ってある>在り方というのはわれわれにはお馴染みのもので、それは大乗仏教哲学の基本的な構えなんだけどね。近代哲学でも、個物の自立ではなく「関係の先在」を言う立場というのはたくさん例がある。
方向性としてはそっちで正解だと思っています。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
考える糧ゴリー 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート