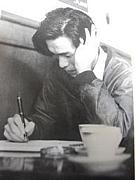織田作や彼の作品を題材にした音楽やコミックを紹介してまいります。
第1回は、
●山川直人のコミック『コーヒーもう一杯』の?巻。
(本巻に織田作之助が取り上げらていると知って、ブックオフで古本400円で入手)
さまざまな場面でコーヒーが登場するストーリーのコミックだが、本巻では作家(織田作)の事実のストーリーが描かれているのは興味深い。
画は人物の顔は目を中心に大きくディフォルメされていて、その方にそれこそ目を取られてしまうきらいがあるが。
織田作の顔は、死の直前に林忠彦が銀座ルパンで撮った写真がベースになっているようで、頬が極端にこけている。
織田作に関しては、「一枝と作之助」の標題のごとく、京都で三高・学生時代にカフェ・リッチモンドに通って、コーヒー何杯もおかわりして粘り、ついに後の夫人、一枝をゲットするエピソードに始まる。
5年後に結婚して芥川賞候補にもなり、新進作家としての道を歩むも、5年後に一枝は子宮ガンで亡くなる。
病床の妻のもとに届いた競馬場への誘いの手紙に嫉妬していた彼は競馬場におもむくという『競馬』の内容がコミックには引用されている。
まもなく、愛人関係となった役者の輪島昭子が織田に尽くし、死を見取ることになるが、死ぬ前にはあれほど好きだったコーヒーをせがまなくなったことに昭子は驚き悲しんだことで、作品は結ばれる。コーヒーに始まりコーヒーに終わるほろ苦いというよりは切ない物語。
大谷晃一の織田作・評伝にもとづき、コーヒー、タバコ、ヒロポンなどの嗜好を調べたうえで、簡潔だがよくまとめられており、これを契機に織田作の小説を読んでくれる若者が増えれば嬉しい。
第1回は、
●山川直人のコミック『コーヒーもう一杯』の?巻。
(本巻に織田作之助が取り上げらていると知って、ブックオフで古本400円で入手)
さまざまな場面でコーヒーが登場するストーリーのコミックだが、本巻では作家(織田作)の事実のストーリーが描かれているのは興味深い。
画は人物の顔は目を中心に大きくディフォルメされていて、その方にそれこそ目を取られてしまうきらいがあるが。
織田作の顔は、死の直前に林忠彦が銀座ルパンで撮った写真がベースになっているようで、頬が極端にこけている。
織田作に関しては、「一枝と作之助」の標題のごとく、京都で三高・学生時代にカフェ・リッチモンドに通って、コーヒー何杯もおかわりして粘り、ついに後の夫人、一枝をゲットするエピソードに始まる。
5年後に結婚して芥川賞候補にもなり、新進作家としての道を歩むも、5年後に一枝は子宮ガンで亡くなる。
病床の妻のもとに届いた競馬場への誘いの手紙に嫉妬していた彼は競馬場におもむくという『競馬』の内容がコミックには引用されている。
まもなく、愛人関係となった役者の輪島昭子が織田に尽くし、死を見取ることになるが、死ぬ前にはあれほど好きだったコーヒーをせがまなくなったことに昭子は驚き悲しんだことで、作品は結ばれる。コーヒーに始まりコーヒーに終わるほろ苦いというよりは切ない物語。
大谷晃一の織田作・評伝にもとづき、コーヒー、タバコ、ヒロポンなどの嗜好を調べたうえで、簡潔だがよくまとめられており、これを契機に織田作の小説を読んでくれる若者が増えれば嬉しい。
|
|
|
|
コメント(13)
織田作トリビア第2回
★今宮高校と織田作の関係深く
第28回(2011年)織田作之助賞を受賞したのが府立今宮高校出身で、芥川賞をすでに受賞しているOL作家の津村記久子さん(34歳)だった。
織田作は旧制高津中学(現・高津高校)の出身だったが、旧制今宮中学(現・今宮高校)の卒業生とは関係が深かった。
文筆や将棋、競馬と公私にわたり兄事した大阪の作家、藤沢桓夫は1922年に今宮中学を卒業している。織田作の『俗臭』が芥川賞候補となった(1939年)あと、雑誌『文学界』(文藝春秋発行)に織田を推挙したのが藤沢であり、短編『放浪』が初めて織田作の商業誌での第一作となった。
彼の小説『東京マダムと大阪夫人』のように織田作の盟友(軽佻浮薄派)であった川島雄三監督による映画化もなされている。
藤沢と今宮中学で同級生だったのが武田麟太郎であり、藤沢同様、三高では織田作の先輩にあたる。また、同人誌『辻馬車』でも同人であった。
しかも、武田は『文藝』(改造社)の第一回推薦作品の審査委員であり、織田作が応募した『夫婦善哉』を、川端康成等の反対を押し切って、「出来上がり唐いえば抜群。眼と才能は現在の文学のレベルを超えている」と強く推挙した。結果、文芸推薦作となり織田作は一躍文壇で脚光を浴びることとなった。
武田は『釜ケ崎』(1934年)のような民衆小説を書いており、織田作に影響を大きな与えた一人である。織田作は武田をモデルにした短編『四月馬鹿』をユーモラスに書いているが、武田が亡くなったとき(1946年)に追悼文を寄せたのが織田作であった。
『きれぎれ』で芥川賞を受賞した町田康も今宮高校出身(1980年)であり、「けつまずき迷走人生」をおくる民衆を饒舌しゃべくり文体で描くなど織田作の影響を受けているようだ。『夫婦茶碗』は題名からみても『夫婦善哉』を想い起こさせる。
町田は『僕と共鳴せえへんか?』という詩を作り(『壊色』1998年)、パンクロックで歌ってもいる(町田町蔵+北澤組『腹ふり』CD)が、この言葉は『夫婦善哉』における柳吉の女を口説く文句にほかならない。
さらに、エッセイ『へらへらぼっちゃん』(1997年)には「無頼のほうへ―織田作之助『世相』『子守歌』『六白金星』」を記し、織田作の底辺の人間を描く作品への共感を表している。
こうみてくると、織田作は旧制今宮中学出身の作家の影響を受け、今宮高校出身の作家に影響を与えるという、親密な関係にある。また、芥川賞との関係も共有するのである。
★今宮高校と織田作の関係深く
第28回(2011年)織田作之助賞を受賞したのが府立今宮高校出身で、芥川賞をすでに受賞しているOL作家の津村記久子さん(34歳)だった。
織田作は旧制高津中学(現・高津高校)の出身だったが、旧制今宮中学(現・今宮高校)の卒業生とは関係が深かった。
文筆や将棋、競馬と公私にわたり兄事した大阪の作家、藤沢桓夫は1922年に今宮中学を卒業している。織田作の『俗臭』が芥川賞候補となった(1939年)あと、雑誌『文学界』(文藝春秋発行)に織田を推挙したのが藤沢であり、短編『放浪』が初めて織田作の商業誌での第一作となった。
彼の小説『東京マダムと大阪夫人』のように織田作の盟友(軽佻浮薄派)であった川島雄三監督による映画化もなされている。
藤沢と今宮中学で同級生だったのが武田麟太郎であり、藤沢同様、三高では織田作の先輩にあたる。また、同人誌『辻馬車』でも同人であった。
しかも、武田は『文藝』(改造社)の第一回推薦作品の審査委員であり、織田作が応募した『夫婦善哉』を、川端康成等の反対を押し切って、「出来上がり唐いえば抜群。眼と才能は現在の文学のレベルを超えている」と強く推挙した。結果、文芸推薦作となり織田作は一躍文壇で脚光を浴びることとなった。
武田は『釜ケ崎』(1934年)のような民衆小説を書いており、織田作に影響を大きな与えた一人である。織田作は武田をモデルにした短編『四月馬鹿』をユーモラスに書いているが、武田が亡くなったとき(1946年)に追悼文を寄せたのが織田作であった。
『きれぎれ』で芥川賞を受賞した町田康も今宮高校出身(1980年)であり、「けつまずき迷走人生」をおくる民衆を饒舌しゃべくり文体で描くなど織田作の影響を受けているようだ。『夫婦茶碗』は題名からみても『夫婦善哉』を想い起こさせる。
町田は『僕と共鳴せえへんか?』という詩を作り(『壊色』1998年)、パンクロックで歌ってもいる(町田町蔵+北澤組『腹ふり』CD)が、この言葉は『夫婦善哉』における柳吉の女を口説く文句にほかならない。
さらに、エッセイ『へらへらぼっちゃん』(1997年)には「無頼のほうへ―織田作之助『世相』『子守歌』『六白金星』」を記し、織田作の底辺の人間を描く作品への共感を表している。
こうみてくると、織田作は旧制今宮中学出身の作家の影響を受け、今宮高校出身の作家に影響を与えるという、親密な関係にある。また、芥川賞との関係も共有するのである。
織田作トリビア第3回
★森見登美彦「夜は短し歩けよ乙女」
京都大学農学部出身の森見さん、こよなく京都の青春を満喫された様子が本書には満載。ああ、京都の青春っていいなあ。その京で京大の教養学部の前身、三高(第三高等学校)で青春や性春を謳歌した、し過ぎて5年で落第し、東京へ去ったのがわが織田作之助である。
『夜は短し歩けよ乙女』に、下鴨古本市の場面で「織田作之助全集」端本を読む和服姿の30代半ば、謎の女性がたびたび登場する。(9ヵ所)
森見の本書を読んで、織田作に興味をもって、織田作の作品を読んだ若い人もおり、2,3人がブログにこのことを書いている。したがって、実際にはかなりの数の人々に織田作を印象づけ、初めて織田作の作品まで読んでいる人がかなりに上る可能性が高い。
本作で下鴨神社糾すの森での古本市に並ぶ本を列挙しており、織田作の影響が作品に現れている。(なお、淀風庵なる70代のおじんも毎年、京の3大古本市を楽しんでいる)
「棚を埋め尽くす無数の文庫本、漫画、こともなげに均一コーナーにならべられた幾多の全集端本、麗々しく飾られた貴重書、文学書、歌集、辞典類、理学書、復刻本、講談本、大判画集に展覧会図録、積み重ねられている古雑誌、大量のB級映画のビデオテープ、標題の読み方も分からない漢籍や古典籍、海を越えて京都へ辿り着いた洋書の数々、(中略)列車時刻表、自費出版とおぼしき正体不明の本まで……紙に印刷された何らかの記憶はすべて古本となる。」
これぞ織田作ワールド。
『夜は短し歩けよ乙女』の内容そのものが、織田作の『猿飛佐助』や『ニコ狆先生』と同じ、忍者、天狗など超能力者を登場させているユーモア性において類似するものがあると思う。
さらに、『宵山万華鏡』に関しては、「織田作之助の『アド・バルーン』という小説の縁日の場面を読んでいたときに、“奥州斎川孫太郎虫”という言葉が出てきて。夜店を順番に列挙していく場面でしたが、その言葉のインパクトにやられました」とも森見は語っており、織田作の影響が大きいことをうかがい知れる。
森見は34歳で活躍中だが、織田作はこの歳にて東京で『土曜夫人』という、戦後まもない京都を舞台とした前半部分の小説を執筆中に客死したのだ。
★森見登美彦「夜は短し歩けよ乙女」
京都大学農学部出身の森見さん、こよなく京都の青春を満喫された様子が本書には満載。ああ、京都の青春っていいなあ。その京で京大の教養学部の前身、三高(第三高等学校)で青春や性春を謳歌した、し過ぎて5年で落第し、東京へ去ったのがわが織田作之助である。
『夜は短し歩けよ乙女』に、下鴨古本市の場面で「織田作之助全集」端本を読む和服姿の30代半ば、謎の女性がたびたび登場する。(9ヵ所)
森見の本書を読んで、織田作に興味をもって、織田作の作品を読んだ若い人もおり、2,3人がブログにこのことを書いている。したがって、実際にはかなりの数の人々に織田作を印象づけ、初めて織田作の作品まで読んでいる人がかなりに上る可能性が高い。
本作で下鴨神社糾すの森での古本市に並ぶ本を列挙しており、織田作の影響が作品に現れている。(なお、淀風庵なる70代のおじんも毎年、京の3大古本市を楽しんでいる)
「棚を埋め尽くす無数の文庫本、漫画、こともなげに均一コーナーにならべられた幾多の全集端本、麗々しく飾られた貴重書、文学書、歌集、辞典類、理学書、復刻本、講談本、大判画集に展覧会図録、積み重ねられている古雑誌、大量のB級映画のビデオテープ、標題の読み方も分からない漢籍や古典籍、海を越えて京都へ辿り着いた洋書の数々、(中略)列車時刻表、自費出版とおぼしき正体不明の本まで……紙に印刷された何らかの記憶はすべて古本となる。」
これぞ織田作ワールド。
『夜は短し歩けよ乙女』の内容そのものが、織田作の『猿飛佐助』や『ニコ狆先生』と同じ、忍者、天狗など超能力者を登場させているユーモア性において類似するものがあると思う。
さらに、『宵山万華鏡』に関しては、「織田作之助の『アド・バルーン』という小説の縁日の場面を読んでいたときに、“奥州斎川孫太郎虫”という言葉が出てきて。夜店を順番に列挙していく場面でしたが、その言葉のインパクトにやられました」とも森見は語っており、織田作の影響が大きいことをうかがい知れる。
森見は34歳で活躍中だが、織田作はこの歳にて東京で『土曜夫人』という、戦後まもない京都を舞台とした前半部分の小説を執筆中に客死したのだ。
織田作トリビア第4回
★寺山修司の織田夫人への追慕
『さかさま文学史黒髪篇』(1978年、角川文庫)において19人の作家の女性が描かれているが、そのうち「女給・一枝、無頼作家織田作之助の孤独の彷徨、『夫婦善哉』無償の愛」と題した1篇を設けている。
その文中で、織田作の小説が寺山に大きな影響を与えたことを明かしている。
「彼の『夫婦善哉』から『六白金星』『世相』『競馬』といった短編、『土曜夫人』といった長編は、私を魅了した。織田は第二次大戦直後、すい星のようにあらわれて消えた作家であったが、私に与えた影響は大きかった。」
「劇作を志し、競馬にあけくれていた青春時代、持病の悩み―ただ一つちがっていたことは、織田が一枝という生涯に、たった一人だけ愛することのできた女をもっていたことである。」
『かもめ 寺山修司メルヘン全集9』
「愛十色」より「織田一枝―織田作之助の小説「競馬」のヒロイン 」の一篇があり、その中で詩が詠まれている。
たしかに
あの人の放浪は
生まれた途端にもう始まって
いたのです。
アドバルーン
アドバルーン
女の過去はわからない
風に吹かれて
ながされて
競馬好きであった寺山は、織田作『競馬』に共感し、夫婦へのオマージュをエッセイや詩で綴り、追悼しているかのようである。
★寺山修司の織田夫人への追慕
『さかさま文学史黒髪篇』(1978年、角川文庫)において19人の作家の女性が描かれているが、そのうち「女給・一枝、無頼作家織田作之助の孤独の彷徨、『夫婦善哉』無償の愛」と題した1篇を設けている。
その文中で、織田作の小説が寺山に大きな影響を与えたことを明かしている。
「彼の『夫婦善哉』から『六白金星』『世相』『競馬』といった短編、『土曜夫人』といった長編は、私を魅了した。織田は第二次大戦直後、すい星のようにあらわれて消えた作家であったが、私に与えた影響は大きかった。」
「劇作を志し、競馬にあけくれていた青春時代、持病の悩み―ただ一つちがっていたことは、織田が一枝という生涯に、たった一人だけ愛することのできた女をもっていたことである。」
『かもめ 寺山修司メルヘン全集9』
「愛十色」より「織田一枝―織田作之助の小説「競馬」のヒロイン 」の一篇があり、その中で詩が詠まれている。
たしかに
あの人の放浪は
生まれた途端にもう始まって
いたのです。
アドバルーン
アドバルーン
女の過去はわからない
風に吹かれて
ながされて
競馬好きであった寺山は、織田作『競馬』に共感し、夫婦へのオマージュをエッセイや詩で綴り、追悼しているかのようである。
織田作文学トリビア第5回
★クミコが歌うアドバルーン
織田作原作『競馬』は亡き一枝を偲んで、競馬場で1の単勝を買い続ける男、すなわち織田作の姿を描いたものだ。それと、詩にあるアドバルーンも織田作の小説のタイトルであるし、「放浪」も昭和15年に発表した作品だ。これらの材料をもとに競馬フアンならではの寺山が語り歌にしたのだ。
『競馬』に題材を得た、寺山修司作詩、クミコによる「織田一枝」のライブの映像も見たが、癌死する妻への嫉妬と哀傷が心に響いた。
『かもめ 寺山修司メルヘン全集9』
「愛十色」より「織田一枝―織田作之助の小説「競馬」のヒロイン 」より。
たしかに
あの人の放浪は
生まれた途端にもう始まって
いたのです。
アドバルーン
アドバルーン
二人の心は揺れている
放浪したいが
紐がある
アドバルーン
アドバルーン
ひとり下宿に残されて
ぼんやり見ている
夏の空
アドバルーン
アドバルーン
女の過去はわからない
風に吹かれて
ながされて
アドバルーン
アドバルーン
やけにふかした煙草には
過ぎしその日の
ためいきが…
アドバルーン
アドバルーン
その身は放浪していても
心はいつも
残ってる
アドバルーン
アドバルーン
★クミコが歌うアドバルーン
織田作原作『競馬』は亡き一枝を偲んで、競馬場で1の単勝を買い続ける男、すなわち織田作の姿を描いたものだ。それと、詩にあるアドバルーンも織田作の小説のタイトルであるし、「放浪」も昭和15年に発表した作品だ。これらの材料をもとに競馬フアンならではの寺山が語り歌にしたのだ。
『競馬』に題材を得た、寺山修司作詩、クミコによる「織田一枝」のライブの映像も見たが、癌死する妻への嫉妬と哀傷が心に響いた。
『かもめ 寺山修司メルヘン全集9』
「愛十色」より「織田一枝―織田作之助の小説「競馬」のヒロイン 」より。
たしかに
あの人の放浪は
生まれた途端にもう始まって
いたのです。
アドバルーン
アドバルーン
二人の心は揺れている
放浪したいが
紐がある
アドバルーン
アドバルーン
ひとり下宿に残されて
ぼんやり見ている
夏の空
アドバルーン
アドバルーン
女の過去はわからない
風に吹かれて
ながされて
アドバルーン
アドバルーン
やけにふかした煙草には
過ぎしその日の
ためいきが…
アドバルーン
アドバルーン
その身は放浪していても
心はいつも
残ってる
アドバルーン
アドバルーン
織田作文学トリビア第6回
★織田作大賞&芥川賞受賞の若手30代作家
大阪ほか関西の出身者で活躍中の30代半ばの作家が多いのに気づいた。それぞれの作品には大阪や京都が舞台となっているものが多い。そして、織田作文学の影響を受けたり、織田作之助を受賞された作家が多い。
30代といえば、織田作は戦後、新進作家として人気を得るなか、東京の宿舎で猛烈に執筆中、1947年1月10日、満33歳で亡くなっているから惜しまれる。ときあたかも、大阪の本戎の日であった。
・柴崎友香 1974年、大阪市出身、市岡高校、大阪府立大、『その街の今は』で織田賞(2006)、芥川賞候補
・西加奈子 1977年生まれ、大阪府立泉陽高等学校、関西大学、『通天閣』で織田作賞(2007)
・津村記久子 1978年生まれ、大阪市出身、今宮高校、大谷大学、『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作賞(2011)、『ポトスライムの舟』で芥川賞(2009)
・川上未映子 1976年、大阪市出身、大阪市立工芸高校、日本大学通信教育部、『乳と卵』芥川賞(2008)、織田作賞候補、関西弁の作品
・森見登美彦 1979年、奈良・生駒市出身、京都大学、京都舞台の作品、織田作の影響も受ける
・万城目学 1976年、大阪市出身、清風南海高校、京都大学、『プリンセス・トヨトミ』なで直木賞候補、大阪や京都を舞台の作品
先日、天神橋筋の書店に立ち寄ったら、これらの作家の新刊本がずらりと棚に並んでいて嬉しかった。
★織田作大賞&芥川賞受賞の若手30代作家
大阪ほか関西の出身者で活躍中の30代半ばの作家が多いのに気づいた。それぞれの作品には大阪や京都が舞台となっているものが多い。そして、織田作文学の影響を受けたり、織田作之助を受賞された作家が多い。
30代といえば、織田作は戦後、新進作家として人気を得るなか、東京の宿舎で猛烈に執筆中、1947年1月10日、満33歳で亡くなっているから惜しまれる。ときあたかも、大阪の本戎の日であった。
・柴崎友香 1974年、大阪市出身、市岡高校、大阪府立大、『その街の今は』で織田賞(2006)、芥川賞候補
・西加奈子 1977年生まれ、大阪府立泉陽高等学校、関西大学、『通天閣』で織田作賞(2007)
・津村記久子 1978年生まれ、大阪市出身、今宮高校、大谷大学、『ワーカーズ・ダイジェスト』で織田作賞(2011)、『ポトスライムの舟』で芥川賞(2009)
・川上未映子 1976年、大阪市出身、大阪市立工芸高校、日本大学通信教育部、『乳と卵』芥川賞(2008)、織田作賞候補、関西弁の作品
・森見登美彦 1979年、奈良・生駒市出身、京都大学、京都舞台の作品、織田作の影響も受ける
・万城目学 1976年、大阪市出身、清風南海高校、京都大学、『プリンセス・トヨトミ』なで直木賞候補、大阪や京都を舞台の作品
先日、天神橋筋の書店に立ち寄ったら、これらの作家の新刊本がずらりと棚に並んでいて嬉しかった。
織田作文学トリビア第7回
★「織田作の小説が親代わりだった」もず唱平
産経新聞「家族を語る」より(2011月11月13日)
「釜ヶ崎人情」(昭和42年)、「花街の母」(同48年)などのヒット曲で知られる作詞家で大阪芸術大学芸術計画学科教授、もず唱平さん(73)=大阪府枚方市。
「12、13歳のころでしょうか。普通だったら多感なときですよね。でも、僕は家族がそんなふうだから(母子家庭)、感情をぶつけたり、考えたりする場が乏しかった。その代わり、当時の僕の心のよりどころになったのが、織田作之助の小説。全部読みましたよ、彼の作品は。
大阪の庶民生活などを描いた作家でね、(一般的に子供が父親らから学ぶ代わりに)彼の作品からたくさん学んだ。家族のことも含め、人の生き方や考え方なんかをね。なかでも、子供ながらに、何に一番引かれたかといえば、あの大阪弁やった。なめらかで、味があって…。とにかく、あの時代を表していたのでしょう。だから、すごく共感できた。
《織田作之助との年齢差は25。庶民の素朴な日々を描きながら、人間とは、社会とは、と語る彼の作品から、ちょうど子が父を見るように、人生や社会の教えを受けたという。また、当時の織田作品への傾倒ぶりはのちの作詞家としての才能も予見させ、実際、18、19歳ごろから大阪で友人と同人誌を作り始める》
もずの「釜ヶ崎人情」は、釜ヶ崎に半年通って、庶民目線でドキュメンタリー・タッチで書いた歌詞で、60万枚のヒット作となった。これぞ、大阪庶民を描いた織田作の視点にほかならない。
「釜ヶ崎人情」(作曲・三山敏、歌・三音英次)
立ちん坊人生 味なもの
通天閣さえ 立ちん坊さ
だれに遠慮が いるじゃなし
じんわり待って 出直そう
ここは天国 ここは天国 釜ヶ崎
身の上話に オチがつき
ここまで落ちたと いうけれど
根性はまる出し まる裸
義理も人情も ドヤもある
ここは天国 ここは天国 釜ヶ崎
★「織田作の小説が親代わりだった」もず唱平
産経新聞「家族を語る」より(2011月11月13日)
「釜ヶ崎人情」(昭和42年)、「花街の母」(同48年)などのヒット曲で知られる作詞家で大阪芸術大学芸術計画学科教授、もず唱平さん(73)=大阪府枚方市。
「12、13歳のころでしょうか。普通だったら多感なときですよね。でも、僕は家族がそんなふうだから(母子家庭)、感情をぶつけたり、考えたりする場が乏しかった。その代わり、当時の僕の心のよりどころになったのが、織田作之助の小説。全部読みましたよ、彼の作品は。
大阪の庶民生活などを描いた作家でね、(一般的に子供が父親らから学ぶ代わりに)彼の作品からたくさん学んだ。家族のことも含め、人の生き方や考え方なんかをね。なかでも、子供ながらに、何に一番引かれたかといえば、あの大阪弁やった。なめらかで、味があって…。とにかく、あの時代を表していたのでしょう。だから、すごく共感できた。
《織田作之助との年齢差は25。庶民の素朴な日々を描きながら、人間とは、社会とは、と語る彼の作品から、ちょうど子が父を見るように、人生や社会の教えを受けたという。また、当時の織田作品への傾倒ぶりはのちの作詞家としての才能も予見させ、実際、18、19歳ごろから大阪で友人と同人誌を作り始める》
もずの「釜ヶ崎人情」は、釜ヶ崎に半年通って、庶民目線でドキュメンタリー・タッチで書いた歌詞で、60万枚のヒット作となった。これぞ、大阪庶民を描いた織田作の視点にほかならない。
「釜ヶ崎人情」(作曲・三山敏、歌・三音英次)
立ちん坊人生 味なもの
通天閣さえ 立ちん坊さ
だれに遠慮が いるじゃなし
じんわり待って 出直そう
ここは天国 ここは天国 釜ヶ崎
身の上話に オチがつき
ここまで落ちたと いうけれど
根性はまる出し まる裸
義理も人情も ドヤもある
ここは天国 ここは天国 釜ヶ崎
織田作文学トリビア第8回
★難波利三の路地・民衆小説
難波利三は1936年、島根県生まれ。関西外国語大学中退。大阪・阿倍野界隈で流しのギター弾きをしたあと、業界紙記者となり、47年『地虫』でオール読売新人賞受賞、59年『てんのじ村』で直木賞受賞。
『新・酒のかたみに』(高山恵太郎監修、たる出版、2004年)の「酒抜きでは語れない織田作之助」で難波利三は次のように述べている。
昭和47年(1972年)に大阪の露店商人の娘を主人公にした『地虫』でオール読売の新人賞を受賞したとき、選考委員の一人から「織田作に似ている」「似ていることはマイナス、損だ」と評された。しかし、似ていることが、むしろ手柄であり、自慢のような気分さえした。
昭和30年代の後半、府下の結核療養所に入院中に織田作の作品に出会い、集中的に読んだ。島根県から大阪へ出てきて数年しか経っておらず、大阪という町の上っ面がどうにか見える程度だったが、織田作の小説は、いわば観光案内的に、大阪がどんな町か、その魅力を存分に教えてくれたような気がする。
地名や場所、店の名前や名物の食べ物、そして値段や金勘定など、濃密な具体性の溢れる文章に、たちまち魅了された。それまでに読んだ名作の類いが綺麗事に過ぎ、途端に色褪せて見えた。こういう小説が書きたい!不遜にも、そんな夢を描いた。
(以上要約)
・黒岩重吾は、『てんのじ村』(文春文庫)解説
「難波利三の本質は民衆作家である。民衆作家とは、日常生活の何気ない事件に怒り喜ぶ庶民の哀感を通して人間の生き様やロマンを描く作家のことだ。
当然民衆作家は庶民の体臭を嗅ぎ、日常行動の一つ一つに鋭い視線を向け、庶民が持つ善良さとエゴを把握しなければならない。そのエゴの中には思わず目をそむけたくなる醜悪さもある筈だ。だがそれ等のものを充分理解した上で庶民の生き様に共鳴するのが民衆作家である。作家は宗教家ではない。どんな作家も人間をずたずたに解剖するメスを手にしている。そういう意味で難波利三は鋭利なメスを持つ作家として庶民を愛しているのである。」
●『わが町』など大阪の路地のおもろて、哀しい人情を描いた織田作、その市井、民衆小説の系譜にある一人が、代表作品『てんのじ村』の難波利三である。さらに、この大阪物を継いでいるのが、増田英『通天閣の下の赤ちゃん』(織田作賞佳作)や西加奈子『通天閣』(織田作賞)なのだ。
★難波利三の路地・民衆小説
難波利三は1936年、島根県生まれ。関西外国語大学中退。大阪・阿倍野界隈で流しのギター弾きをしたあと、業界紙記者となり、47年『地虫』でオール読売新人賞受賞、59年『てんのじ村』で直木賞受賞。
『新・酒のかたみに』(高山恵太郎監修、たる出版、2004年)の「酒抜きでは語れない織田作之助」で難波利三は次のように述べている。
昭和47年(1972年)に大阪の露店商人の娘を主人公にした『地虫』でオール読売の新人賞を受賞したとき、選考委員の一人から「織田作に似ている」「似ていることはマイナス、損だ」と評された。しかし、似ていることが、むしろ手柄であり、自慢のような気分さえした。
昭和30年代の後半、府下の結核療養所に入院中に織田作の作品に出会い、集中的に読んだ。島根県から大阪へ出てきて数年しか経っておらず、大阪という町の上っ面がどうにか見える程度だったが、織田作の小説は、いわば観光案内的に、大阪がどんな町か、その魅力を存分に教えてくれたような気がする。
地名や場所、店の名前や名物の食べ物、そして値段や金勘定など、濃密な具体性の溢れる文章に、たちまち魅了された。それまでに読んだ名作の類いが綺麗事に過ぎ、途端に色褪せて見えた。こういう小説が書きたい!不遜にも、そんな夢を描いた。
(以上要約)
・黒岩重吾は、『てんのじ村』(文春文庫)解説
「難波利三の本質は民衆作家である。民衆作家とは、日常生活の何気ない事件に怒り喜ぶ庶民の哀感を通して人間の生き様やロマンを描く作家のことだ。
当然民衆作家は庶民の体臭を嗅ぎ、日常行動の一つ一つに鋭い視線を向け、庶民が持つ善良さとエゴを把握しなければならない。そのエゴの中には思わず目をそむけたくなる醜悪さもある筈だ。だがそれ等のものを充分理解した上で庶民の生き様に共鳴するのが民衆作家である。作家は宗教家ではない。どんな作家も人間をずたずたに解剖するメスを手にしている。そういう意味で難波利三は鋭利なメスを持つ作家として庶民を愛しているのである。」
●『わが町』など大阪の路地のおもろて、哀しい人情を描いた織田作、その市井、民衆小説の系譜にある一人が、代表作品『てんのじ村』の難波利三である。さらに、この大阪物を継いでいるのが、増田英『通天閣の下の赤ちゃん』(織田作賞佳作)や西加奈子『通天閣』(織田作賞)なのだ。
織田作文学トリビア第9回
★増井英の織田作オマージュ作品
1929年、大阪市出身、国立大阪外事専門学校フランス語科卒業。
『通天閣の下の赤ちゃん』で2002年に織田作賞佳作賞を受賞した洋画家の増田英さん。80歳を越えた増井さんは現在も朝日カルチャーセンターで洋画を教え、宝塚造形芸術大学の名誉教授でもある。
祖父のポンポン飴の商売ぶりを描いた織田作『黒い顔』に触発されて73歳で著した小説がこの受賞作品だ。詩人で織田作賞の選考委員である杉山平一さんは「時代の風俗や習慣、流行など具体的にちりばめ、時代と人間を描いている」と高く評されている。
織田作著『黒い顔』は「銃後の大阪」(1941年5月発行)に発表されたもの。
『通天閣の下の赤ちゃん』は3編からなり、同題の「通天閣の下の赤ちゃん」は筆者自身の子供時代の遊びの世界を活写したもので、生家があった新世界戎通り商店街から新世界一帯が舞台となっている。
筆者は1歳7ヶ月の頃に大阪市主催の赤ちゃんコンクールで1等に輝いたことがあり、小学生になっても赤ちゃんとのニックネームで呼ばれていたそうであり、これが表題の所以である。
3編目の「ポンポン飴屋」は祖父が創業して人気を呼んだ店にまつわる話であり、織田作は新世界を舞台にした『黒い顔』でこの飴屋の丁稚を主人公に書いている。飴は電気仕掛けで回転させて作るもので、店頭での製造実演がハイカラで評判となった。なお、織田作は「デンキ飴」との名称で書いている。
増井さんは、織田作の小説の筋を一通り紹介しながら、新世界にあった遠い昔の祖父の商売と出世物語を回想し、店頭での掛け声など売り捌きの様子を活写している。大阪弁(北摂)、 大阪のわらべ歌、尻取り歌、はやり歌、流行語、俳優や弁士の決り文句、チンドン屋の口上、擬音語、擬声語などが、それこそポンポンと飛び出してテンポが速いのが本小説の特徴である。加えて、銭勘定や風刺、猥雑のくだりが多く出てくる。結果として、その時代の世相、価値観を描いている点において、織田作の文章流儀を継いでいるように思われる。画家らしく、客観的、視覚的、具象的に時代風俗、町の情景、様相を捉えているからこそ、惹き込まれて読んでいってしまう。
増井は織田作より16歳下だが、戦中や終戦直後の共有した時代や土地があったし、学生時代に織田作の作品を好きでよく読んだ増井だから、それらの影響が執筆に現れて当然とも思われる。
『通天閣の下の赤ちゃん』杉山平一の解説より
《画家は一般に文章が拙く、自らを語るのに、絵を見てくれ、という人が多い。ところが、増井さんは文章が巧い。読み易くわかり易く飽かせない。それでいて、文字による文学的描写や表現は使わない。もっぱら、具体事実ものそのものを読者に提供する。「通天閣の下の赤ちゃん」「ポンポン 飴屋」は作者の回想思い出であるが、人物の目鼻立ちや作者の心情よりは、風俗、習慣、流行などものそのものによって時代と人間を描いて行く。それは、画家の本領発揮の壮観である。おそらく時代の資料としても貴重な面白さである。》
文面からみて、増井さんはすごい記憶力であるが、筆者自ら「人生は記憶だ」「記憶が失くなると、その人は滅亡してしまう」と文中で言い切っている。
オダサク倶楽部では2年前に読書会に増井さんをゲストに迎えたことがあるが、氏は司馬さんや俵萌子、石浜恒夫さんとの交流が紹介された。司馬さんのほめ殺しの巧さに乗せられて、小説を書いたようなものだと増井さんの弁。
織田作の弟子を名乗る石浜恒夫氏とは法善寺のカルバスで出会って以来の飲み友達だったそう。石浜さんが倒れたときに、病院の屋上にクルマ椅子で連れてゆき、タバコを吸わせたとのエピソードも紹介。
昭和38年、法善寺の正弁丹吾の前にある織田作の碑の除幕式にも参加しておられた。このときの参加者として、藤沢桓夫、長沖一、前田藤四郎、織田禎子さんらがいたという。
大阪は寄せ場文化だが、このローカル性が文化を生むとのお考えで、織田作を評価され、増井さん自身もそのような小説を書かれたことになるのだ。
織田作が「可能性の文学」を書いた頃は、評価は太宰よりも上であり、ぜひ織田作が再評価されるようにして欲しいとの思いを我々に投げかけられた。
増井さんも織田作と同じ無頼派だと自称されていたが、小説の通天閣のガキ大将に違わぬ奔放な遊びや生き方をされていたようで、その面魂はそのときにもうかがえた。
★増井英の織田作オマージュ作品
1929年、大阪市出身、国立大阪外事専門学校フランス語科卒業。
『通天閣の下の赤ちゃん』で2002年に織田作賞佳作賞を受賞した洋画家の増田英さん。80歳を越えた増井さんは現在も朝日カルチャーセンターで洋画を教え、宝塚造形芸術大学の名誉教授でもある。
祖父のポンポン飴の商売ぶりを描いた織田作『黒い顔』に触発されて73歳で著した小説がこの受賞作品だ。詩人で織田作賞の選考委員である杉山平一さんは「時代の風俗や習慣、流行など具体的にちりばめ、時代と人間を描いている」と高く評されている。
織田作著『黒い顔』は「銃後の大阪」(1941年5月発行)に発表されたもの。
『通天閣の下の赤ちゃん』は3編からなり、同題の「通天閣の下の赤ちゃん」は筆者自身の子供時代の遊びの世界を活写したもので、生家があった新世界戎通り商店街から新世界一帯が舞台となっている。
筆者は1歳7ヶ月の頃に大阪市主催の赤ちゃんコンクールで1等に輝いたことがあり、小学生になっても赤ちゃんとのニックネームで呼ばれていたそうであり、これが表題の所以である。
3編目の「ポンポン飴屋」は祖父が創業して人気を呼んだ店にまつわる話であり、織田作は新世界を舞台にした『黒い顔』でこの飴屋の丁稚を主人公に書いている。飴は電気仕掛けで回転させて作るもので、店頭での製造実演がハイカラで評判となった。なお、織田作は「デンキ飴」との名称で書いている。
増井さんは、織田作の小説の筋を一通り紹介しながら、新世界にあった遠い昔の祖父の商売と出世物語を回想し、店頭での掛け声など売り捌きの様子を活写している。大阪弁(北摂)、 大阪のわらべ歌、尻取り歌、はやり歌、流行語、俳優や弁士の決り文句、チンドン屋の口上、擬音語、擬声語などが、それこそポンポンと飛び出してテンポが速いのが本小説の特徴である。加えて、銭勘定や風刺、猥雑のくだりが多く出てくる。結果として、その時代の世相、価値観を描いている点において、織田作の文章流儀を継いでいるように思われる。画家らしく、客観的、視覚的、具象的に時代風俗、町の情景、様相を捉えているからこそ、惹き込まれて読んでいってしまう。
増井は織田作より16歳下だが、戦中や終戦直後の共有した時代や土地があったし、学生時代に織田作の作品を好きでよく読んだ増井だから、それらの影響が執筆に現れて当然とも思われる。
『通天閣の下の赤ちゃん』杉山平一の解説より
《画家は一般に文章が拙く、自らを語るのに、絵を見てくれ、という人が多い。ところが、増井さんは文章が巧い。読み易くわかり易く飽かせない。それでいて、文字による文学的描写や表現は使わない。もっぱら、具体事実ものそのものを読者に提供する。「通天閣の下の赤ちゃん」「ポンポン 飴屋」は作者の回想思い出であるが、人物の目鼻立ちや作者の心情よりは、風俗、習慣、流行などものそのものによって時代と人間を描いて行く。それは、画家の本領発揮の壮観である。おそらく時代の資料としても貴重な面白さである。》
文面からみて、増井さんはすごい記憶力であるが、筆者自ら「人生は記憶だ」「記憶が失くなると、その人は滅亡してしまう」と文中で言い切っている。
オダサク倶楽部では2年前に読書会に増井さんをゲストに迎えたことがあるが、氏は司馬さんや俵萌子、石浜恒夫さんとの交流が紹介された。司馬さんのほめ殺しの巧さに乗せられて、小説を書いたようなものだと増井さんの弁。
織田作の弟子を名乗る石浜恒夫氏とは法善寺のカルバスで出会って以来の飲み友達だったそう。石浜さんが倒れたときに、病院の屋上にクルマ椅子で連れてゆき、タバコを吸わせたとのエピソードも紹介。
昭和38年、法善寺の正弁丹吾の前にある織田作の碑の除幕式にも参加しておられた。このときの参加者として、藤沢桓夫、長沖一、前田藤四郎、織田禎子さんらがいたという。
大阪は寄せ場文化だが、このローカル性が文化を生むとのお考えで、織田作を評価され、増井さん自身もそのような小説を書かれたことになるのだ。
織田作が「可能性の文学」を書いた頃は、評価は太宰よりも上であり、ぜひ織田作が再評価されるようにして欲しいとの思いを我々に投げかけられた。
増井さんも織田作と同じ無頼派だと自称されていたが、小説の通天閣のガキ大将に違わぬ奔放な遊びや生き方をされていたようで、その面魂はそのときにもうかがえた。
オダサク文学トリビア第10回
★一番弟子・磯田敏夫のユーモア猥雑文(1)
●磯田敏夫の経歴
1917年(大6)、大阪市福島区生れ、小学校卒業後、店員。
作家を志し、1941年(昭16)に堺・北野田の織田作宅を訪問、その後「織田作一番弟子」を名乗る。1943年(昭18)徴兵後、海軍万年上等水兵と自称。
戦後は、1945年(昭20)にキャバレー「歌舞伎」入社。「大劇地下サロン」や「ゆめのくに」のアルバイトサロン支配人&作家として活躍。アルバイトサロン(アルサロ)の名付け親でもあるようだ。
ついには親会社・千土地観光株式会社の代表取締役となるも、千日前デパートの火災で傘下のキャバレーにも多数の犠牲者を出し、その事後処理に苦労。
雑誌「太陽」(太陽社)主催の第一回織田作之助賞(1948年)を『道頓堀左岸』で受賞。http://dogatyaga.blog.so-net.ne.jp/2010-03-05
さらに、現在の大阪文芸振興会主催による第1回織田作之助賞(昭和59年)において『仁輪加 千日前の男前』で佳作を受賞した。そのときの審査委員が富士正晴と藤沢桓夫という織田作ゆかりの作家と矢澤永一(評論家)であった。
著作『ネオン太平記』は今村昌平脚本、磯見忠彦監督、小沢昭一主役(キャバレー支配人役)で映画化されている。(1968年日活)
●作家の道への織田作の影響
《磯田敏夫氏の名を知ったのは、織田作之助が中心になって出していた私どもの雑誌「大阪文学」の誌上においてであった。「あれダレ?面白いね」というと、織田君は「面白いやろ、太宰ばりでね」と大変うれしそうだった。当時、太宰治の、自然主義的な描写を捨てたリズミカルな語りで、ニヒリズムを歌う感性的な文体は、若い世代を魅了していた。》(磯田敏夫『道頓堀左岸』の杉山平一序文)
《彼(磯田)は「文学雑誌」の前身ともいうべき「大阪文学」に織田作之助の紹介で登場した最も古い仲間である。当時あらたに脚光を浴びた太宰治に似た瑞々しい文体で、里見、宇野浩二、織田作之助から野坂昭如、町田康へと続くしゃべくり調を体現していた」と述べている。》(「文学雑誌」磯田敏夫追悼号、平成18年2月における杉山平一の文)
織田作の弟子入りをしたという磯田が、織田作が編集長をしていた「大阪文学」に処女作を発表したのは1942年(昭17)のことである。
《ストックというのではないが、敏夫の小説も二つか三つ、織田作之助のバックと後押しで、出征の前に「日の目をみることもないとあきらめて、碌々読み返しもせず、気分館の織田の机の上においてきたものだ。その小説が不幸にも、不運にも、「大大阪文学」に掲載された頃は、敏夫は内地に居らず、中国の上海、海軍特別陸戦隊の南地区隊に一等水兵として勤務していた。」(「文芸雑誌」第78号、平成14年6月20日号掲載「人情噺九軒高明」より)
●織田作追憶記
戦後は「文学雑誌」に50編の小説を寄せている。その中には織田作について記述した随筆が多い。なかでも、平成8年12月号掲載「大阪府野田丈六」は、師と仰いだ織田作について随所に思い出を綴った追憶の記であり、いかに織田作の影響を受けながら磯田が作家の道に進んだかが分かる。
《ばくは進駐軍キャバレーの人事係をしていて、“海軍ボケ”の後遺症で、南海高野線の最終近くのヤツで、織田作之助に会ったのである。「小説を書けよ」とひどく酔っていた織田がいったのである。それから五十何日で、死亡した。》(「文学雑誌」昭和52年4月号掲載「一番弟子」より)
《「織田さん、わいはまた、小説かけそうになりました」ともうすぐ三回忌の来る作家に向かって、誓うのであった。上質の紙に印刷してあるダンサー志望の用紙の裏に、鉛筆で原稿用紙の桝目のような線を引いて、「道頓堀左岸」の草稿を書いた。(中略)「織田賞はキミかも知れんよ・まだ、極秘の段階やが……と大詩人小野十三郎から、喫茶店「創元」できいた。(中略)小野さんの情報の如く、織田賞を貰った。上等舶来、門外不出、一子相伝、一発必中、笑止千万、本家本元、本邦最初、正真正銘、偽“満州国”の不義ではない。偽ギッチョンギッチョンチョンである。もしも、“偽”と極付けるなら、偽でないのは、芭蕉翁の俳句だけになってしまうぞ! ああ織田や、織田作之助、ああ織田や。(「文学雑誌」平成8年12月号掲載「大阪府野田丈六」より)
★一番弟子・磯田敏夫のユーモア猥雑文(1)
●磯田敏夫の経歴
1917年(大6)、大阪市福島区生れ、小学校卒業後、店員。
作家を志し、1941年(昭16)に堺・北野田の織田作宅を訪問、その後「織田作一番弟子」を名乗る。1943年(昭18)徴兵後、海軍万年上等水兵と自称。
戦後は、1945年(昭20)にキャバレー「歌舞伎」入社。「大劇地下サロン」や「ゆめのくに」のアルバイトサロン支配人&作家として活躍。アルバイトサロン(アルサロ)の名付け親でもあるようだ。
ついには親会社・千土地観光株式会社の代表取締役となるも、千日前デパートの火災で傘下のキャバレーにも多数の犠牲者を出し、その事後処理に苦労。
雑誌「太陽」(太陽社)主催の第一回織田作之助賞(1948年)を『道頓堀左岸』で受賞。http://dogatyaga.blog.so-net.ne.jp/2010-03-05
さらに、現在の大阪文芸振興会主催による第1回織田作之助賞(昭和59年)において『仁輪加 千日前の男前』で佳作を受賞した。そのときの審査委員が富士正晴と藤沢桓夫という織田作ゆかりの作家と矢澤永一(評論家)であった。
著作『ネオン太平記』は今村昌平脚本、磯見忠彦監督、小沢昭一主役(キャバレー支配人役)で映画化されている。(1968年日活)
●作家の道への織田作の影響
《磯田敏夫氏の名を知ったのは、織田作之助が中心になって出していた私どもの雑誌「大阪文学」の誌上においてであった。「あれダレ?面白いね」というと、織田君は「面白いやろ、太宰ばりでね」と大変うれしそうだった。当時、太宰治の、自然主義的な描写を捨てたリズミカルな語りで、ニヒリズムを歌う感性的な文体は、若い世代を魅了していた。》(磯田敏夫『道頓堀左岸』の杉山平一序文)
《彼(磯田)は「文学雑誌」の前身ともいうべき「大阪文学」に織田作之助の紹介で登場した最も古い仲間である。当時あらたに脚光を浴びた太宰治に似た瑞々しい文体で、里見、宇野浩二、織田作之助から野坂昭如、町田康へと続くしゃべくり調を体現していた」と述べている。》(「文学雑誌」磯田敏夫追悼号、平成18年2月における杉山平一の文)
織田作の弟子入りをしたという磯田が、織田作が編集長をしていた「大阪文学」に処女作を発表したのは1942年(昭17)のことである。
《ストックというのではないが、敏夫の小説も二つか三つ、織田作之助のバックと後押しで、出征の前に「日の目をみることもないとあきらめて、碌々読み返しもせず、気分館の織田の机の上においてきたものだ。その小説が不幸にも、不運にも、「大大阪文学」に掲載された頃は、敏夫は内地に居らず、中国の上海、海軍特別陸戦隊の南地区隊に一等水兵として勤務していた。」(「文芸雑誌」第78号、平成14年6月20日号掲載「人情噺九軒高明」より)
●織田作追憶記
戦後は「文学雑誌」に50編の小説を寄せている。その中には織田作について記述した随筆が多い。なかでも、平成8年12月号掲載「大阪府野田丈六」は、師と仰いだ織田作について随所に思い出を綴った追憶の記であり、いかに織田作の影響を受けながら磯田が作家の道に進んだかが分かる。
《ばくは進駐軍キャバレーの人事係をしていて、“海軍ボケ”の後遺症で、南海高野線の最終近くのヤツで、織田作之助に会ったのである。「小説を書けよ」とひどく酔っていた織田がいったのである。それから五十何日で、死亡した。》(「文学雑誌」昭和52年4月号掲載「一番弟子」より)
《「織田さん、わいはまた、小説かけそうになりました」ともうすぐ三回忌の来る作家に向かって、誓うのであった。上質の紙に印刷してあるダンサー志望の用紙の裏に、鉛筆で原稿用紙の桝目のような線を引いて、「道頓堀左岸」の草稿を書いた。(中略)「織田賞はキミかも知れんよ・まだ、極秘の段階やが……と大詩人小野十三郎から、喫茶店「創元」できいた。(中略)小野さんの情報の如く、織田賞を貰った。上等舶来、門外不出、一子相伝、一発必中、笑止千万、本家本元、本邦最初、正真正銘、偽“満州国”の不義ではない。偽ギッチョンギッチョンチョンである。もしも、“偽”と極付けるなら、偽でないのは、芭蕉翁の俳句だけになってしまうぞ! ああ織田や、織田作之助、ああ織田や。(「文学雑誌」平成8年12月号掲載「大阪府野田丈六」より)
オダサク文学トリビア第10回
★一番弟子・磯田敏夫のユーモア猥雑文(2)
●アルサロ支配人のキャッチフレーズ広告
磯田を有名たらしめたのは、アルサロへの彼の客呼び込みのために自らコピーを作成した
大阪的エスプリ精神の溢れたキャッチフレーズ広告(新聞や車内)である。(昭和31〜51年)
「今日はメーデー 晩は酩酊」「金持ちは 麦を食え 貧乏人は 麦酒を飲め」「たった五輪で夜も眠れず」「袋にボーナスが入っている 水着に女体が入っている」「菊人形より生人形 菊の花よりアルサロの花」「蛍の光 窓の雪 酒飲む月日かさねつつ」「逍遥ブラツキ 抱月ダキツク」「酒は一合、女は二号」
大阪の猥雑、アルコールの霧と脂肪の匂いを活写した開高健、野坂昭如、藤本義一らに先駆けた作家であった。(同誌、木津川計記)
“大阪を知り大阪を描いた大阪の作家”であった点で、同じ織田作同門の石浜恒夫と共通している。
●織田作と磯田の文章との共通点
・文体は一文が長い連綿体
例:(『荒唐無稽譚』、「文学雑誌」1993年発表など)
・パロディ、もじり、エスプリ、からかい、ごっちゃ煮、饒舌、猥雑、即物、俗物という感覚が伝わる。
「キャッチフレーズ広告」に表徴されるように、小説においても即物的表現や言葉遊びなどが目立ち大阪的俗臭、猥雑が漂い、次例で分かるように、織田作に比べて、あくの強さ、猥雑さ、エスプリ性では磯田の方が上手をゆく。
《失禁ではなく、もっと重たい奴である。なんというのだろう。大阪には、ババサキといって天王寺区生玉表門筋、歩いて通るのは善男善女で、車で走り去るのは、不倫、情事、不義密通の輩で、ババをサキにして目星しいものを持って帰るのが泥棒であり、ババをその直後にするのは、便秘でなやむ女共である。品位、品格を尊とぶべしとは、織田さんも、藤沢先生も私の場合特にきびしくご注意なされており、馬場町のある課から呼び出しがあるやも知れず、以後ババは禁句とする。》(「文学雑誌」平成8年12月号掲載「大阪府野田丈六」より)
《織田作之助の顔では、太宰治の小説は書けなかっただろうし、逆にいうなら、太宰治の顔では、織田作之助の小説は書けなかったと思う。その点、実物を知らないので、例にひいてはわるいが、梶井基次郎には、少し失望したものだ。あの時代の写真器やフィルムに問題があったと思うが……。寅さんみたいな顔のヤツが、どんな傑作を書こうと、ぼくはよんでやらないことにしている。》(「文学雑誌」昭和52年4月号掲載「一番弟子」より)
★一番弟子・磯田敏夫のユーモア猥雑文(2)
●アルサロ支配人のキャッチフレーズ広告
磯田を有名たらしめたのは、アルサロへの彼の客呼び込みのために自らコピーを作成した
大阪的エスプリ精神の溢れたキャッチフレーズ広告(新聞や車内)である。(昭和31〜51年)
「今日はメーデー 晩は酩酊」「金持ちは 麦を食え 貧乏人は 麦酒を飲め」「たった五輪で夜も眠れず」「袋にボーナスが入っている 水着に女体が入っている」「菊人形より生人形 菊の花よりアルサロの花」「蛍の光 窓の雪 酒飲む月日かさねつつ」「逍遥ブラツキ 抱月ダキツク」「酒は一合、女は二号」
大阪の猥雑、アルコールの霧と脂肪の匂いを活写した開高健、野坂昭如、藤本義一らに先駆けた作家であった。(同誌、木津川計記)
“大阪を知り大阪を描いた大阪の作家”であった点で、同じ織田作同門の石浜恒夫と共通している。
●織田作と磯田の文章との共通点
・文体は一文が長い連綿体
例:(『荒唐無稽譚』、「文学雑誌」1993年発表など)
・パロディ、もじり、エスプリ、からかい、ごっちゃ煮、饒舌、猥雑、即物、俗物という感覚が伝わる。
「キャッチフレーズ広告」に表徴されるように、小説においても即物的表現や言葉遊びなどが目立ち大阪的俗臭、猥雑が漂い、次例で分かるように、織田作に比べて、あくの強さ、猥雑さ、エスプリ性では磯田の方が上手をゆく。
《失禁ではなく、もっと重たい奴である。なんというのだろう。大阪には、ババサキといって天王寺区生玉表門筋、歩いて通るのは善男善女で、車で走り去るのは、不倫、情事、不義密通の輩で、ババをサキにして目星しいものを持って帰るのが泥棒であり、ババをその直後にするのは、便秘でなやむ女共である。品位、品格を尊とぶべしとは、織田さんも、藤沢先生も私の場合特にきびしくご注意なされており、馬場町のある課から呼び出しがあるやも知れず、以後ババは禁句とする。》(「文学雑誌」平成8年12月号掲載「大阪府野田丈六」より)
《織田作之助の顔では、太宰治の小説は書けなかっただろうし、逆にいうなら、太宰治の顔では、織田作之助の小説は書けなかったと思う。その点、実物を知らないので、例にひいてはわるいが、梶井基次郎には、少し失望したものだ。あの時代の写真器やフィルムに問題があったと思うが……。寅さんみたいな顔のヤツが、どんな傑作を書こうと、ぼくはよんでやらないことにしている。》(「文学雑誌」昭和52年4月号掲載「一番弟子」より)
オダサク文学トリビア第11回
★推理作家北村薫と宮部みゆきの織田作短編賛美
北村薫・宮部みゆき編『名短編ほりだしもの』(ちくま文庫)には織田作作品『探し人』『人情噺』『天衣無縫』が収載されている。
北村は織田作フアンであることを、本書での宮部との「解説対談」で明らかにしており、“織田作”という愛称を用いてもいる。(2011.9.28)
以下は対談の内容から北村の織田作作品についての見方を、繋ぎ合わせてまとめたもの。
《織田作之助は大好きな作家なんですが、…そこで、むくむくと対抗心が起こりましてね。ちくま文庫にも岩波文庫にも入っていないものをということで、まず三つを選びました。この三作はそれぞれ織田作らしい。》
《織田作の得意な、長い時間を一気に語っていくというスタイルがある。その語り口が大好きなんです。…いわゆる大河小説になるんじゃなくて、それを短編の中で収めてしまう。凝縮するんですよ。それで端折ったとかそういう感じはしないんですね。》
《織田作が評論のなかで語っているのですが、なぜ半生記を延々と情熱的に語っていくようになったのか、それはもともと劇作家を目指して戯曲を書いていたからだと、劇というのは、昔は、作品の舞台となる「時と場所」を変えられないものだったんです。一幕劇なんかは特にそうですね。だから反動で、長い長い時間のなかで、場所も変っていくものを書きたいという欲求があったと自己分析しています。》
《『天衣無縫』も『夫婦善哉』タイプの作品です。要するに、ダメなヤツ。人がいいんじゃなくて、人が弱いのね。どんどんつけ込まれちゃう。いわゆる「織田作的人物像」といえます。織田作的男と女の関係が非常によく出ている作品です。》
宮部みゆきの作品感想
《私は三つのうちで『天衣無縫』が一番すきです。最後まで奥様の一人語りで「あの人は私だけのものだ」とか、かわいいなあ!》
《『探し人』は凝縮されていて、すごく上手い言い回しでピタッ、ピタッと書いていく。》
《『人情噺』は、大阪弁のイントネーションが効いてますね。『天衣無縫』も語り口勝負ですよね。》
《いやあ、私はすっかりフアンになりました。なんてかわいい小説なんでしょう。どんな人だったのかなあ。意外とむずかしい顔をしてこんな作品を書いていたのだとしたら、それも「かわいい〜」と思ってしまいます。》
北村薫は、淡交社「なごみ」誌の2011年11月号において、“読まずにはいられない”のコラム(見開き)で「わたしの織田作之助―その愛と死」(織田作の愛人で、死を看取った織田昭子の著)を取り上げており、北村の織田作への想いの強さを感じます。
なお、北村の『空飛ぶ馬』(創元推理文庫)を見たかぎり、地の文とは独立した会話文が多く、修飾語も多い特徴があり、文章的に織田作との類似性は見出せない。
北村薫:1949年、埼玉県生まれ、推理作家。1989年、『空飛ぶ馬』でデビュー、1991年に『夜の蝉』で日本推理作家協会賞2009年、『鷺と雪』で第141回直木賞を受賞。
宮部みゆき:1960年江東区生まれ、推理作家。1998年 、『理由』で第120回直木賞受賞。
★推理作家北村薫と宮部みゆきの織田作短編賛美
北村薫・宮部みゆき編『名短編ほりだしもの』(ちくま文庫)には織田作作品『探し人』『人情噺』『天衣無縫』が収載されている。
北村は織田作フアンであることを、本書での宮部との「解説対談」で明らかにしており、“織田作”という愛称を用いてもいる。(2011.9.28)
以下は対談の内容から北村の織田作作品についての見方を、繋ぎ合わせてまとめたもの。
《織田作之助は大好きな作家なんですが、…そこで、むくむくと対抗心が起こりましてね。ちくま文庫にも岩波文庫にも入っていないものをということで、まず三つを選びました。この三作はそれぞれ織田作らしい。》
《織田作の得意な、長い時間を一気に語っていくというスタイルがある。その語り口が大好きなんです。…いわゆる大河小説になるんじゃなくて、それを短編の中で収めてしまう。凝縮するんですよ。それで端折ったとかそういう感じはしないんですね。》
《織田作が評論のなかで語っているのですが、なぜ半生記を延々と情熱的に語っていくようになったのか、それはもともと劇作家を目指して戯曲を書いていたからだと、劇というのは、昔は、作品の舞台となる「時と場所」を変えられないものだったんです。一幕劇なんかは特にそうですね。だから反動で、長い長い時間のなかで、場所も変っていくものを書きたいという欲求があったと自己分析しています。》
《『天衣無縫』も『夫婦善哉』タイプの作品です。要するに、ダメなヤツ。人がいいんじゃなくて、人が弱いのね。どんどんつけ込まれちゃう。いわゆる「織田作的人物像」といえます。織田作的男と女の関係が非常によく出ている作品です。》
宮部みゆきの作品感想
《私は三つのうちで『天衣無縫』が一番すきです。最後まで奥様の一人語りで「あの人は私だけのものだ」とか、かわいいなあ!》
《『探し人』は凝縮されていて、すごく上手い言い回しでピタッ、ピタッと書いていく。》
《『人情噺』は、大阪弁のイントネーションが効いてますね。『天衣無縫』も語り口勝負ですよね。》
《いやあ、私はすっかりフアンになりました。なんてかわいい小説なんでしょう。どんな人だったのかなあ。意外とむずかしい顔をしてこんな作品を書いていたのだとしたら、それも「かわいい〜」と思ってしまいます。》
北村薫は、淡交社「なごみ」誌の2011年11月号において、“読まずにはいられない”のコラム(見開き)で「わたしの織田作之助―その愛と死」(織田作の愛人で、死を看取った織田昭子の著)を取り上げており、北村の織田作への想いの強さを感じます。
なお、北村の『空飛ぶ馬』(創元推理文庫)を見たかぎり、地の文とは独立した会話文が多く、修飾語も多い特徴があり、文章的に織田作との類似性は見出せない。
北村薫:1949年、埼玉県生まれ、推理作家。1989年、『空飛ぶ馬』でデビュー、1991年に『夜の蝉』で日本推理作家協会賞2009年、『鷺と雪』で第141回直木賞を受賞。
宮部みゆき:1960年江東区生まれ、推理作家。1998年 、『理由』で第120回直木賞受賞。
オダサク文学トリビア第12回
★川上未映子『乳と卵』にみる大阪弁長文連綿語り調
本作は芥川賞受賞作である。(下記ページは文芸文庫本による)
川上はミュージシャンが出発で作家へ、そして芥川賞受賞、出身地も大阪で現在は東京住い、町田康と同じパターンだ。
文体的にも、会話が地の文に挿入された長文の連綿語り調で、作品によっては大阪弁が溢れる点においても両作家は共通性がある。
本作品では、豊胸手術や月経という女性特有の感覚、生理を露骨に取り上げつつ、母子家庭の小学生の娘が抱く出生への懐疑や母娘のわだかまりをテーマにしている。これら相克の因って来るすべては、最後に母娘が自ら頭に叩きつける卵まみれの姿に象徴されており、作者の子宮的発想の極致だろうか。
女の生理や肉体、容姿に関しては男性から見ればはっとするほど、即物的に綿密、露骨に表現されているが(75〜76P他)、その観察力はさすが女性ならではである。
この長文連綿語り調は、Youtubeの川上の言葉によれば、樋口一葉の影響だというが、織田作之助から町田康へ、そして川上未映子へと継承されていると感じる。
また、本書における京橋の街のさまざまな店の列挙は(17〜18P)、まさに織田作の商店街や盛り場、夜店の描写と類似の世界である。
長文連綿語りの極みは、37〜44Pの112行にわたる、句点・改行なしの文で、字数にして4,334字に及ぶ。これ原稿用紙にして11枚分に相当するから、織田作や町田もあきれるほどの女性の饒舌ぶりである。
なんか大阪弁には“ん”がつく言葉が多て、柔らかい感じが醸されるんで、どんならん(深刻でどぎつい)争いごとも緩和されて伝わる、そのへんを作者はよう心得て、登場人物が大阪人であるよって駄弁に思われることも辞さんで、ようさん大阪弁を使ってはるんやろな。
★川上未映子『乳と卵』にみる大阪弁長文連綿語り調
本作は芥川賞受賞作である。(下記ページは文芸文庫本による)
川上はミュージシャンが出発で作家へ、そして芥川賞受賞、出身地も大阪で現在は東京住い、町田康と同じパターンだ。
文体的にも、会話が地の文に挿入された長文の連綿語り調で、作品によっては大阪弁が溢れる点においても両作家は共通性がある。
本作品では、豊胸手術や月経という女性特有の感覚、生理を露骨に取り上げつつ、母子家庭の小学生の娘が抱く出生への懐疑や母娘のわだかまりをテーマにしている。これら相克の因って来るすべては、最後に母娘が自ら頭に叩きつける卵まみれの姿に象徴されており、作者の子宮的発想の極致だろうか。
女の生理や肉体、容姿に関しては男性から見ればはっとするほど、即物的に綿密、露骨に表現されているが(75〜76P他)、その観察力はさすが女性ならではである。
この長文連綿語り調は、Youtubeの川上の言葉によれば、樋口一葉の影響だというが、織田作之助から町田康へ、そして川上未映子へと継承されていると感じる。
また、本書における京橋の街のさまざまな店の列挙は(17〜18P)、まさに織田作の商店街や盛り場、夜店の描写と類似の世界である。
長文連綿語りの極みは、37〜44Pの112行にわたる、句点・改行なしの文で、字数にして4,334字に及ぶ。これ原稿用紙にして11枚分に相当するから、織田作や町田もあきれるほどの女性の饒舌ぶりである。
なんか大阪弁には“ん”がつく言葉が多て、柔らかい感じが醸されるんで、どんならん(深刻でどぎつい)争いごとも緩和されて伝わる、そのへんを作者はよう心得て、登場人物が大阪人であるよって駄弁に思われることも辞さんで、ようさん大阪弁を使ってはるんやろな。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
オダサク倶楽部 更新情報
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
オダサク倶楽部のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90069人
- 2位
- 写真を撮るのが好き
- 208326人
- 3位
- 酒好き
- 170699人