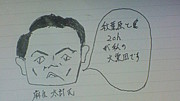一応、「郷土史コミュニティ」と銘打ったので、取り敢えず、郷土史関連のトピックを創りました。
故郷じゃなくても、ちょっと気になる地域に関してでも構いません、また、自分から話すのではなく、ちょっと、あの地方のことに関して色々知りたい、ということでも構いません。
色々、やっちゃってください。
ちなみに、私の場合、家は高安山という小さな山の麓にありますが、この山の山頂近くに高安城跡というのがあります。これは白村江の敗戦(7世紀後半)を受けて、当時の大和朝廷が大陸からの侵入に備えて築いた軍事要塞であるとのことです。
あるいは、近くの墓場の辺りには、畿内における戦国最大の会戦、教興寺の戦いの碑があります。これにより、近畿地方における三好長慶政権の基盤が築かれたとされているようです。
故郷じゃなくても、ちょっと気になる地域に関してでも構いません、また、自分から話すのではなく、ちょっと、あの地方のことに関して色々知りたい、ということでも構いません。
色々、やっちゃってください。
ちなみに、私の場合、家は高安山という小さな山の麓にありますが、この山の山頂近くに高安城跡というのがあります。これは白村江の敗戦(7世紀後半)を受けて、当時の大和朝廷が大陸からの侵入に備えて築いた軍事要塞であるとのことです。
あるいは、近くの墓場の辺りには、畿内における戦国最大の会戦、教興寺の戦いの碑があります。これにより、近畿地方における三好長慶政権の基盤が築かれたとされているようです。
|
|
|
|
コメント(15)
サユさま>
今、私の職場の東北人が
「アテルイ」と「モレ」について
真剣に調べようとしているようです
(もちろん個人的な趣味として)
新聞でもチラッと見ましたが
アテルイについては
東北地方各地で
英雄として見直す動きが出ています
正史「続日本紀」「日本後記」では
この二人は
蝦夷=朝廷への反逆者としてしか
書かれていません
でも、ちょっと考えれば
「聞いたことも無い近畿地方の
ある一家族を『神』としてあがめ、
その政府に稲で税を納めろ」
なんて、当時の東北先住民には
とうてい聞けた話ではなかったはず
鉄や青銅の武器で武装した
何万人もの朝廷軍に
おそらくは数百人レベルで
戦った彼らは英雄として
評価されるべきかも知れません
ひょっとすると白虎隊と同じくらい
勇猛で行動力があった
東北の英雄ですよ
今、私の職場の東北人が
「アテルイ」と「モレ」について
真剣に調べようとしているようです
(もちろん個人的な趣味として)
新聞でもチラッと見ましたが
アテルイについては
東北地方各地で
英雄として見直す動きが出ています
正史「続日本紀」「日本後記」では
この二人は
蝦夷=朝廷への反逆者としてしか
書かれていません
でも、ちょっと考えれば
「聞いたことも無い近畿地方の
ある一家族を『神』としてあがめ、
その政府に稲で税を納めろ」
なんて、当時の東北先住民には
とうてい聞けた話ではなかったはず
鉄や青銅の武器で武装した
何万人もの朝廷軍に
おそらくは数百人レベルで
戦った彼らは英雄として
評価されるべきかも知れません
ひょっとすると白虎隊と同じくらい
勇猛で行動力があった
東北の英雄ですよ
教興寺の戦いは今でこそあまり知名度はありません(三好政権は短期政権だったし、足利将軍を傀儡とするという意味において旧態依然としていたから)が、あの当時においては畿内の政治地図が大きく変わる、衝撃的な事件だったと思います。
それまで、北九州において勢力を涵養し、やがて東上し中原を制するということは古来よりしばしばありましたが、四国から出てきた勢力が中央を掌握するというのは、一時的であれ恐らく三好氏が唯一じゃないでしょうか?
ところで、アテルイですが、ウィキペディアか何かで読んだ覚えがあるのですが、小沢一郎さんのご先祖だそうです。
本当のところは分かりませんが、意外といえば意外ですよね。
アテルイと坂上田村麻呂の対峙に関してですが、確かに戦闘もあったと思いますが、何となく農耕文化の伝播を通しての懐柔政策がメインではなかったかな、なんて思います。
まぁ、飽くまで何の根拠もない推量ですが…。
それまで、北九州において勢力を涵養し、やがて東上し中原を制するということは古来よりしばしばありましたが、四国から出てきた勢力が中央を掌握するというのは、一時的であれ恐らく三好氏が唯一じゃないでしょうか?
ところで、アテルイですが、ウィキペディアか何かで読んだ覚えがあるのですが、小沢一郎さんのご先祖だそうです。
本当のところは分かりませんが、意外といえば意外ですよね。
アテルイと坂上田村麻呂の対峙に関してですが、確かに戦闘もあったと思いますが、何となく農耕文化の伝播を通しての懐柔政策がメインではなかったかな、なんて思います。
まぁ、飽くまで何の根拠もない推量ですが…。
頼朝さま>
>ところで、アテルイですが、ウィキペディアか何かで読んだ覚えがあるのですが、小沢一郎さんのご先祖
>だそうです。
>
> 本当のところは分かりませんが、意外といえば意外ですよね。
>
→ ゲゲッ!それは怪しい!
大体、「日本後記」によれば、紀古佐美を打ち破って
岩手北部で英雄視されていたアテルイとモレを
坂上田村麻呂が「天皇の許しを得て、征東使にするから」と
平安京に捕縛してつれてきたのは、
1200年も昔の延暦21年7月10日ですよ
その1ヵ月後の8月13日(どちらも旧暦)には
アテルイとモレの二人とも斬刑に処されています
そんな昔の蝦夷時代からの「系図」なんて、
小沢家に残っているのかしら…
まさか…、と思いますが、
もし残っているようなら凄いことですよね
> アテルイと坂上田村麻呂の対峙に関してですが、確かに戦闘もあったと思いますが、何となく農耕文>化の伝播を通しての懐柔政策がメインではなかったかな、なんて思います。
→ 田村麻呂は明らかにこの二人に
シンパシーを持っていたようですね
その証拠に、この直後に辞表を提出しています
「アテルイとモレとの信頼関係を反古にされた」
という抗議の意味合いがあったようです
田村麻呂を信じて、
平安京に来たアテルイとモレも
また、自分を信頼してくれた二人を
東北地方平定のリーダーにしようとした
坂上田村麻呂も
武士魂を持った勇者だったんだなあ、
と思います
>ところで、アテルイですが、ウィキペディアか何かで読んだ覚えがあるのですが、小沢一郎さんのご先祖
>だそうです。
>
> 本当のところは分かりませんが、意外といえば意外ですよね。
>
→ ゲゲッ!それは怪しい!
大体、「日本後記」によれば、紀古佐美を打ち破って
岩手北部で英雄視されていたアテルイとモレを
坂上田村麻呂が「天皇の許しを得て、征東使にするから」と
平安京に捕縛してつれてきたのは、
1200年も昔の延暦21年7月10日ですよ
その1ヵ月後の8月13日(どちらも旧暦)には
アテルイとモレの二人とも斬刑に処されています
そんな昔の蝦夷時代からの「系図」なんて、
小沢家に残っているのかしら…
まさか…、と思いますが、
もし残っているようなら凄いことですよね
> アテルイと坂上田村麻呂の対峙に関してですが、確かに戦闘もあったと思いますが、何となく農耕文>化の伝播を通しての懐柔政策がメインではなかったかな、なんて思います。
→ 田村麻呂は明らかにこの二人に
シンパシーを持っていたようですね
その証拠に、この直後に辞表を提出しています
「アテルイとモレとの信頼関係を反古にされた」
という抗議の意味合いがあったようです
田村麻呂を信じて、
平安京に来たアテルイとモレも
また、自分を信頼してくれた二人を
東北地方平定のリーダーにしようとした
坂上田村麻呂も
武士魂を持った勇者だったんだなあ、
と思います
ギョッギョッ
アテルイの話について、様々文献・想像等々お話から小沢さんの話まで。凄い〜と、アタシは聞くしか出来ない〜。
ちなみに、アテルイとの関係は自分は分からない者ですが、
自分の先祖の没後?00年祭に岩手水沢に出掛けた際は、
『和賀の末裔として、アンチ伊達として仙台にいますが、本来ならこちらを選挙区にすべきなのでしょうが小沢大先生が、いらっしゃるので・・・』と挨拶述べました。
アテルイは英雄として捉えられているのが、岩手(東北)の一般的な見方っぽいと思っていました。その血を微かに継いでいると親戚は言うけれど、これも何の根拠もなく。
ただ、伊達百万石の野望の犠牲になった和賀(忠親)とご家来衆(七人)の墓参は自刃した仙台国分尼寺に行き欠かさないようにはしています。
あら、話が逸れまくり〜。すみません。
アテルイの話について、様々文献・想像等々お話から小沢さんの話まで。凄い〜と、アタシは聞くしか出来ない〜。
ちなみに、アテルイとの関係は自分は分からない者ですが、
自分の先祖の没後?00年祭に岩手水沢に出掛けた際は、
『和賀の末裔として、アンチ伊達として仙台にいますが、本来ならこちらを選挙区にすべきなのでしょうが小沢大先生が、いらっしゃるので・・・』と挨拶述べました。
アテルイは英雄として捉えられているのが、岩手(東北)の一般的な見方っぽいと思っていました。その血を微かに継いでいると親戚は言うけれど、これも何の根拠もなく。
ただ、伊達百万石の野望の犠牲になった和賀(忠親)とご家来衆(七人)の墓参は自刃した仙台国分尼寺に行き欠かさないようにはしています。
あら、話が逸れまくり〜。すみません。
サユさま〉
→ そちらでは、政宗は
「撫で斬り&皆殺し」という評判なんですか!!
気の毒なような…
頼朝さま〉
→ 八尾も今東光も、評判とは関係なく
熱烈なファンもいますよ(僕もです)
西武が関西進出の拠点に
八尾を選んだときには
さすがに仰天しましたが…
「鋭どすぎるやろ!!」
と突っ込みたくなりました
浅吉親分も
本人は島之内遊郭で
遊女の逃亡を助けたり
阿漕な高利貸を実力排除したり
結構、カッコいい男ですよねえ
その一方で近所のオバサンの
レンコン掘りを自ら手伝ったりして
ひょうきんなところも
あったらしいし…
八尾中学校の近くの
あの激ウマすし屋は
まだあるのかしら?
→ そちらでは、政宗は
「撫で斬り&皆殺し」という評判なんですか!!
気の毒なような…
頼朝さま〉
→ 八尾も今東光も、評判とは関係なく
熱烈なファンもいますよ(僕もです)
西武が関西進出の拠点に
八尾を選んだときには
さすがに仰天しましたが…
「鋭どすぎるやろ!!」
と突っ込みたくなりました
浅吉親分も
本人は島之内遊郭で
遊女の逃亡を助けたり
阿漕な高利貸を実力排除したり
結構、カッコいい男ですよねえ
その一方で近所のオバサンの
レンコン掘りを自ら手伝ったりして
ひょうきんなところも
あったらしいし…
八尾中学校の近くの
あの激ウマすし屋は
まだあるのかしら?
話は全く替わりますが、以前からちょっと山口県って気になってたんですよね…。
実は日本の歴史を考えるうえでとても大切な土地じゃないかと思うんです。
別に長州が維新の頃にどうしたとか言うんじゃなくて、地政学的に重要じゃないかなと思うんです。
例えば、九州ってのは地方の勢力が力を養うにはもってこいの場所だと思うんです。あるいは、中央で敗れた勢力が都落ちするにはもってこいだと思うんです。だからかどうかは分からないけれども、平家は九州を目指して都落ちしたと思いますし、あるいは彼らが壇ノ浦で滅びても、鎌倉幕府はなかなか九州まで手を広げることが出来なかった…。
足利尊氏だってそうだと思うんです。後醍醐天皇との政争に敗れて、やっぱり一時的に九州に避難して、暫くしてから再度東上し、湊川で楠木正成を破っている…。
幕末においても、薩摩なんて九州の南の端から倒幕勢力が生まれています…。
けれども、足利尊氏と薩摩の場合を見ていて思うんですけれども、どちらも関門海峡を握っていたから中央に殴り込みを掛けられたと思うんです。
つまり、足利尊氏の場合は周防の大内氏を味方につけた、薩摩の場合は勿論薩長同盟…。
恐らく九州だけでも、それこそ今流行の地方主権じゃないけれども、勝手にやることが出来るだけの力はあると思うんです。しかし、防長や関門海峡を把握することで中央へと殴り込みを掛けることが出来ると思うんですね。
そう言えば、秀吉の九州征伐ってのは薩摩の島津氏が九州の制覇を目前にして行われたと思うのですが、あれも、秀吉側から見ると、九州に統一勢力が出来て関門海峡を脅かされるととんでもないことになりかねない、と考えたのかもしれませんね…。
その癖、山口だけで能動的なアクションをしたという話は余り聞きません。
かと思えば、岸信介さんみたいなとんでもない、それこそ「妖怪」との渾名が相応しい人物が出てくることもある。
あそこの人々とか土地ってのは、一体何なのでしょうかね?
実は日本の歴史を考えるうえでとても大切な土地じゃないかと思うんです。
別に長州が維新の頃にどうしたとか言うんじゃなくて、地政学的に重要じゃないかなと思うんです。
例えば、九州ってのは地方の勢力が力を養うにはもってこいの場所だと思うんです。あるいは、中央で敗れた勢力が都落ちするにはもってこいだと思うんです。だからかどうかは分からないけれども、平家は九州を目指して都落ちしたと思いますし、あるいは彼らが壇ノ浦で滅びても、鎌倉幕府はなかなか九州まで手を広げることが出来なかった…。
足利尊氏だってそうだと思うんです。後醍醐天皇との政争に敗れて、やっぱり一時的に九州に避難して、暫くしてから再度東上し、湊川で楠木正成を破っている…。
幕末においても、薩摩なんて九州の南の端から倒幕勢力が生まれています…。
けれども、足利尊氏と薩摩の場合を見ていて思うんですけれども、どちらも関門海峡を握っていたから中央に殴り込みを掛けられたと思うんです。
つまり、足利尊氏の場合は周防の大内氏を味方につけた、薩摩の場合は勿論薩長同盟…。
恐らく九州だけでも、それこそ今流行の地方主権じゃないけれども、勝手にやることが出来るだけの力はあると思うんです。しかし、防長や関門海峡を把握することで中央へと殴り込みを掛けることが出来ると思うんですね。
そう言えば、秀吉の九州征伐ってのは薩摩の島津氏が九州の制覇を目前にして行われたと思うのですが、あれも、秀吉側から見ると、九州に統一勢力が出来て関門海峡を脅かされるととんでもないことになりかねない、と考えたのかもしれませんね…。
その癖、山口だけで能動的なアクションをしたという話は余り聞きません。
かと思えば、岸信介さんみたいなとんでもない、それこそ「妖怪」との渾名が相応しい人物が出てくることもある。
あそこの人々とか土地ってのは、一体何なのでしょうかね?
やっぱり博多が大きいでしょう。平安時代末、恐らく院政期から港湾インフラとして整備されていますから…。
逆に言うと、島津の弱味は、関門海峡を押さえるか、あるいは博多を掌握するかが出来れば、九州に割拠できたけれども、それが出来なかったことにあると思います。
かつてのイギリスがスエズ運河に拘り続けたり、アメリカがパナマ運河に拘るのと同じような事実が背景にあると思います、島津側から見ての話ですが…。
つまり、首都圏(畿内)が瀬戸内の向こうにあり、これが大陸(それこそ北海道も含んで)と首都圏を結ぶ幹線道路である以上、ここを押さえることの軍事・経済・政治における意味は私達の想像以上のものだったと思います。
それこそ地中海とインド洋を結ぶスエズ運河、大西洋と太平洋の結節点たるパナマ運河みたいなものだったでしょう。
源平争乱に関しては、源氏が関門海峡を完全に掌握していたかどうかは議論の余地があると思います。というのも、鎌倉幕府初期、それこそ元寇の折まで、鎌倉幕府の支配力は余り及んでいなかったという事実があるからです。
話は替わりますが、1年ちょっと前から、関門海峡に関してちょっと考えていることがあるんです。
それはね…、
例えば、浦島太郎の亀みたいなのを語り部にして、磐井の乱から薩長同盟までの関門海峡を舞台にしたドラマを描写するという話です。
どうでしょうかねぇ?
逆に言うと、島津の弱味は、関門海峡を押さえるか、あるいは博多を掌握するかが出来れば、九州に割拠できたけれども、それが出来なかったことにあると思います。
かつてのイギリスがスエズ運河に拘り続けたり、アメリカがパナマ運河に拘るのと同じような事実が背景にあると思います、島津側から見ての話ですが…。
つまり、首都圏(畿内)が瀬戸内の向こうにあり、これが大陸(それこそ北海道も含んで)と首都圏を結ぶ幹線道路である以上、ここを押さえることの軍事・経済・政治における意味は私達の想像以上のものだったと思います。
それこそ地中海とインド洋を結ぶスエズ運河、大西洋と太平洋の結節点たるパナマ運河みたいなものだったでしょう。
源平争乱に関しては、源氏が関門海峡を完全に掌握していたかどうかは議論の余地があると思います。というのも、鎌倉幕府初期、それこそ元寇の折まで、鎌倉幕府の支配力は余り及んでいなかったという事実があるからです。
話は替わりますが、1年ちょっと前から、関門海峡に関してちょっと考えていることがあるんです。
それはね…、
例えば、浦島太郎の亀みたいなのを語り部にして、磐井の乱から薩長同盟までの関門海峡を舞台にしたドラマを描写するという話です。
どうでしょうかねぇ?
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
郷土史コミュニティ 更新情報
-
最新のトピック
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
郷土史コミュニティのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90054人
- 2位
- 酒好き
- 170690人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208287人