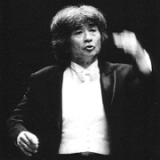かつて、「ごーふるたうん」という短歌のサイトで、マエストロ小澤のモーツァルト演奏の是非について、公開討論をしたことがあります。
相手は、ものすごい博識な方で、知識的には、まったく、かないませんでした。
音楽評論家の方々も、マエストロのモーツァルトに関しては、否定的な意見がけっこうあるようです。
しかしながら、私は、小澤の「フィガロ」と「ドン・ジョバンニ」に感動したのですが……。
ま、身銭を切って聴きに行くのだから、自分が感動すれば、それでいいじゃないか…という世界なのですが、どなたか、同じ舞台を、お聴きになられた方、いらっしゃいませんか?
[68896]風さんにお尋ねします!
2005/09/21(Wed) 15:49:24
風さんは、
前回のウィーン国立歌劇場の来日公演を、
本当に良かったと思われたのでしょうか?
どこを良いと思われたのか、
特に指揮者について、
お聞かせいただきたいと思います。
私は、
あの時初めて、
モーツァルトも汚く演奏され得る、
ということを知ったのですが……。
七代目石井庄七
?65
[68897]七代目石井庄七さまへ質問です
2005/09/21(Wed) 17:11:47
う〜ん、公開質問状ですね。
文学についての論争は受けたことがありますが、音楽については、はじめてです。(^^;)
小澤征爾のモーツァルト演奏は、賛否両論というか、音楽評論家からは、大体、批判的な言質が多いですね。
特に、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任してからの批評を読むと、ほとんど、毎回、貶されていますね。
平板な演奏。
面白味のない解釈。
没個性的でなんの魅力もない。
なんていうふうな批判が、音楽誌を見ていると、満ち満ちています。
わたしは、音楽は専門ではなく、ただ、好き嫌いだけで聴いているので、正直、楽理については、まったく分かりません。
正当な解釈というのも、分かりません。
だから、逆に、ずーっと、疑問だったんですよ。
なぜ、小澤のモーツァルトが、あんなに貶されるのか…ということが。
小澤オタクの風は、「フィガロの結婚」「ドン・ジョバンニ」を2回ずつ、聴きに上京しました。
後半の演奏の方が、飛躍的に良くなっているような気がして、単純に感動して、帰ってきました。
七代目石井庄七さまは、
「あの時初めて、
モーツァルトも汚く演奏され得る、
ということを知ったのですが……。」
とお書きになっているので、多分、音楽評論家の方々と同じようなことをお感じになったと思います。
その「汚い」というのは、どういう部分なのでしょうか?
教えていただければ、ありがたく存じます。
風
[68947]風さんへ
2005/09/23(Fri) 10:36:15
好き嫌いの問題なんですね!
そうなると、
なにやら無粋な質問をしてしまったように思います。
御容赦ください。
しかし風さんが列挙された批評家の発言は、
どれも納得できるものだと思いますよ。
昨年のモーツァルト二作品を
「汚い」と感じた理由も、
そんな欠点にあったと言えるでしょう。
付け加えれば、
ウィーン・フィルの母体である
あの歌劇場のオーケストラが、
ソロの部分はしばしば美しいのに、
いざトゥッティになると
耳を疑うほどに音が濁って汚くなっていたのが、
大いに気になりました。
これはオーケストラの問題ではなく、
指揮者の問題だと思われます。
オーケストラが全く弾まず、
モーツァルトの音楽の愉悦を
引き出せていなかったのも問題ですし、
あまりにも柔軟性に欠けたテンポ設定のため、
しばしば歌唱とオーケストラの間に
かなり大きなずれが生じていたのも、
聞き苦しく感じましたね。
要するにあの指揮者は
モーツァルトに不向きだということで、
ウィーン国立歌劇場が
モーツァルトの主要作品の指揮を
定評のあるリッカルド・ムーティに
任せるようになったというのは、
正当な処置だと思います。
風さんが大好きなあの日本人指揮者が
優れた音楽家であるということは、
もちろん間違いありませんが、
何十回と彼が指揮するオペラを聴いてきた
経験から言えば、
彼はオペラ向きの指揮者ではないのだと思います。
なお、風さんが、
ウィーン国立歌劇場の次回の来日公演で
Die Meistersinger を指揮するのを
残念そうに書いていらっしゃる
クリスティアン・ティーレマンですが、
彼のオペラの指揮は
実に見事なものです。
もちろん実際の舞台を聴いた経験で言うのですが、
少なくとも
ヴァーグナーとR.シュトラウスに関しては、
現代屈指の名指揮者だと言えるでしょう。
好き嫌いで聴くのも悪くはないでしょうが、
いろいろな指揮者の指揮するオペラを聴き比べ、
オペラとはどういうものか見極めることの方が、
一層楽しい、
しかも意義のあることだと思います。
七代目石井庄七
?66
[68953]七代目石井庄七さまへ
2005/09/23(Fri) 12:49:59
[68947]風さんへ の文章、非常に、興味深く拝読いたしました。
新聞や音楽時評では、石井さんのように、具体的な指摘がなされていないので、よく意図が分からなかったのですが、ご意見うかがい、なるほど、こういうことだったのか…という気がしました。
素人の私なりの感想を申し上げますと、
ウィーン・フィルの母体である
あの歌劇場のオーケストラが、
ソロの部分はしばしば美しいのに、
いざトゥッティになると
耳を疑うほどに音が濁って汚くなっていたのが、
大いに気になりました。
という部分ですが、他のオーケストラでも同じだと思うのですが、ウィーンフィルは、特に、初日と楽日の出来の差が激しいオケだと思います。
これは、以前、小澤が、大阪でブラームスのシンフォニーを振ったとき、第1番と第4番が、日本初日だったのですが、最初に演奏した4番の音が、「これが、ウィーンフィル?」というような荒削りの響きでした。
ところが、翌日の最後の曲、第2番は、ウィーンフィル独特のつややかでまろやかな音色でした。
同じことは、昨年、大阪と九州で聴いたゲルギエフの指揮のチャイコフスキーでも感じました。
来日初演の第4番(福岡シンフォニーホール)は、いまひとつ、生硬な感じで、ほどほどの出来だと感じたのですが、後日、NHKで放送されたサントリーホールでの第4番は、見違えるような演奏でした。
石井さんがお聴きになった小澤のモーツァルトが、楽日ならば、上記のことは該当しないと思うのですが、わたしも、前半と後半で、オケの響きが、まったく違って聞こえたので、もし、前半の方の公演をお聴きになったのならば、ご指摘のことは、当たっているかも知れないと思いました。
また、
オーケストラが全く弾まず、
モーツァルトの音楽の愉悦を
引き出せていなかったのも問題ですし、
あまりにも柔軟性に欠けたテンポ設定のため、
しばしば歌唱とオーケストラの間に
かなり大きなずれが生じていたのも、
聞き苦しく感じましたね。
というのは、よくも悪くも、小澤征爾という指揮者の特質をご指摘されているように思いました。
基本的に、小澤は、テンポを揺り動かさず、細部の彫琢に意を尽くす指揮をするので、録音などで聴くと、あまり、面白く感じられないことが、私もあります。
いわば、日本の工芸品の細密な美しさを、西洋音楽で表現しているわけで、細やかなフレーズの音色の微妙な変化とか、スコアの中に、埋没している音を、すくい上げてくるとか、そういう感覚・解釈の音楽なので、「いわゆるモーツァルト」という印象からは、ずれて聞こえるのではないでしょうか。
ただ、これは、オペラではありませんが、茨城県まで、水戸室内管弦楽団のモーツァルト・プログラムを3回ほど聴きに行った経験では、非常に透明感のある細密な演奏で、リンツなど、素晴らしかったように感じました。
小澤は、モーツァルトとか、ワーグナーとか、いわゆる伝統が確立しているクラシックオペラの指揮の評判は悪いのに、なぜか、シェーンベルクとか、アルバン・ベルクとか、20世紀のオペラを振ると、評価が高いですね。
これは、もしかしたら、小澤という指揮者が、カラヤンやバーンスタインに学びながらも、根本的に、伝統的な西洋音楽と断絶した「日本人としての感覚」から、脱却できていないことの証かもしれないと思っています。
つまり、現代音楽という、まだ西洋でも、伝統的演奏法・伝統的解釈が確立されていない曲では、清新に聞こえるにもかかわらず、既に、確固とした伝統が確立されてしまっている曲では、いわゆる「通」の人には、違和感を与えてしまうのではないでしょうか。
「素人」は喜んで聴いているが、「プロ」は顔をしかめて聴いているという断絶感は、どうも、そういうところに由来しているのではないか…という気がしています。
サイトウキネンのブラームスでも、ヨーロッパでは、いささか、違和感をもって、批評された部分もあったようですね。
しかしながら、表現というものに、果たして、「正統な解釈」「絶対的な伝統」というものが、存在するのか……ということになると、議論は果てしなく続いてしまいますね。
かのワーグナーとブラームスの音楽のどちらを認めるかということで、侃々諤々の議論が、同時代のヨーロッパで起こったように、「日本人的なモーツァルト」「日本人的なクラシック解釈」というのが存在して、それに、素朴に感動する人間がいてもいいのではないかという気が、自分はしております。
そういう意味では、小澤が、自分自身で言っているように、彼は、「東洋人がクラシック音楽に受け入れられるかどうかの試金石」のような存在ですね。
あと、石井さんのお話をうかがい、クリスティアン・ティーレマンのワーグナーは、是非とも、聴いてみたくなりました。
3年先に向けて、貯金をしなくては……。
こちらは、経済的にカツカツ状態で、聴きに行っているので、次から次へというわけにはいかないのですが、いろいろなオペラの聞き比べをやってみたくなりました。
興味深いお話、ありがとうございました。
風
[69078]風さんへ
2005/09/27(Tue) 18:06:16
メータのヴァーグナーは、いかがでしたか?
「インド人的」ヴァーグナーではなかったでしょ?
ウィーンフィル(およびウィーン国立歌劇場のオーケストラ)が
しばしば指揮者を見て手を抜いた演奏をする、
という話は、
たしかによく聞きますよね。
カルロス・クライバーの代役で振ったシノーポリは
気の毒だったと思いますが、
まあ、オーケストラに馬鹿にされるかされないかも、
指揮者の力量ということでしょう。
風さん御贔屓のあの指揮者の、
カーテンコールにおける米搗き飛蝗のような
卑屈極まりない態度は、
少なくとも尊敬を集めそうではないと思いますが、
いかがでしょう?
20世紀の音楽についてのくだりは、
私の文章が舌足らずで、
誤解を招いてしまったと後悔しています。
当然のことながらどの時代の音楽でも、
それをきちんと、あるいは見事に演奏するのは
やはり並大抵のことではないでしょう。
ただ、同時代の音楽の方が、
感性が近いので、とでも言いましょうか、
より演奏しやすいはずだと想像しただけのことで、
技術的な問題なども考慮すれば、
あまり説得力のある意見ではなかったかしれませんね。
ただ、たとえば印象派の絵画にしても、
それが現在どれほど高く評価されているのか判りませんが、
発表当時から認めた人は存在したわけで、
同時代的評価は難しい、というのは、
逃げ口上に過ぎないと考えます。
《ごーふる・たうん》に立ち寄るほどの人間なら、
きちんと同時代の芸術を評価すべく
努力しなければならないのではないでしょうか?
風さん御贔屓の指揮者が現代音楽に強い、
というのは、
もちろん認めざるを得ないことでしょう。
メシアン唯一のオペラの初演を
作曲者自身に任されたという事実ひとつだけで、
日本人であることなどまったく抜きにして、
大いに、
かつ永遠に称賛されるべきだと思います。
風さんが
あの指揮者が振った Wozzeck について書いておられることは、
私は松本まで行ってはいませんが、
ほかの彼の現代音楽の演奏から類推して、
理解できることです。
要するにどの音も美しく、聴きやすくなっている、
ということですよね。
余談ですが、
ジェームズ・レヴァインの場合も同じで、
彼が MET で振るベルクやブリテンは、
とても美しく解りやすい。
モーツァルトなどよりもさらにずっと
綺麗で耳に心地よいと感じられるほどです。
それはとても優れた特色ですが、
しかし物足りなく思われもするわけですよね。
おそらく風さん御贔屓の指揮者のベルクやブリテンも、
そういった特色を持っているのだと言えるのでしょう。
私は、
モーツァルトを汚く演奏することは許されないが、
20世紀の音楽は美しいだけでは困る場合がある、
と考えます。
たとえば
Wozzeck の第三幕第三場で演奏される舞台上のピアノは、
スコアには Ein verstimmtes Pianino
すなわち「調子の狂ったアップライトピアノ」と
わざわざ指定してありますよね。
つまりあのピアノは
美しい和音を奏でてはいけない、
そこに発生する不協和音は美しくあってはならない
ということなのだと愚考します。
一瞬も美しく、一瞬一瞬の集積としての全体も美しい、
というのがモーツァルトのオペラだとしたら、
現代のオペラは、
一瞬一瞬は必ずしも美しくはないかも知れないが、
全体を聴けばある圧倒的な美を感じることができるものだ、
ということでしょうか?
風さん御贔屓の指揮者の20世紀オペラに
いささかの不満を感じざるを得ないのは、
そういった観点からなのです。
なお、
風さんは「マイナーな20世紀オペラ」とおしゃいますが、
松本の音楽祭で取り上げられているオペラは、
いずれもマイナーとは呼べない作品だと思います。
Wozzeck をレペルトワールに持たない一流オペラハウスは、
世界中探したって見つからないと思いますよ!
七代目石井庄七
?67
[69092]七代目石井庄七さまへ♪
2005/09/28(Wed) 00:54:39
バイエルン国立歌劇場、メータのワーグナー、素晴らしかったです。
オペラ経験の乏しき風は、『タンホイザー』も『ニュルンベルグのマイスタージンガー』も、始めての経験でした。
『マイスタージンガー』など、休憩を挟んで、5時間半などという代物。
途中、寝てしまったら、どうしようなどと心配しておりましたが、杞憂でした。
旋律のすみずみまで、メータ特有の幅のある豊麗な音楽になっていました。
「『インド人的』ヴァーグナーではなかったでしょ?」
は、確かに、お言葉通り。
『インド人的』どころか、まさに、『独逸の伝統精神』そのものを表現した素晴らしいワーグナーでした。
トーマス・ラングホフの演出が、舞台設定を現代の時代に置き換えていました。
メータの音楽と違和感はなかったので、最初、何も思わず、そのまま、聴き進んでいたのですが、終盤近くになって、ようやく、ラングホフの演出意図が分かりました。
主人公の靴屋の親方ザックスが、「マイスタージンガーを侮らないで」の独逸精神を讃え歌った後、人々は、ザックスを讃え、「ドイツのマイスタージンガーたちを尊敬せよ」の大合唱で、フィナーレとなる。
これは、ベルリンの壁が崩壊して以降、経済格差のあった東西のドイツが統合されたため、経済上、混乱が生じ、国際的な地位が下落してしまった「現在のドイツ」をテーマにした舞台だったのですね。
ワーグナー以前からの、音楽の伝統を継承・確認・体験することにより、凋落傾向にある国家国民の誇りを回復し、賞揚しようとする国威発揚の熱い思い。
愛国心。
演出家と指揮者とオケと歌手のエネルギーが一体となり、舞台から、溢れ出てきて、聴いていて身体が熱くなりました。
さて、今まで、何回かやりとりさせて頂いた公開討論も、そろそろ、大詰めを迎えたと言えるのでしょうか。
(風のカキコが長すぎて、鬱陶しいと思われた方、ごめんなさいね。文章の性質上、長くなってしまいました)
ウィーンフィルが指揮者を選ぶという問題に関し、石井さんのご発言、
「まあ、オーケストラに馬鹿にされるかされないかも、
指揮者の力量ということでしょう。
風さん御贔屓のあの指揮者の、カーテンコールにおける米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度は、少なくとも尊敬を集めそうではないと思いますが、いかがでしょう?」
には、爆笑させていただきました。
なかなか、ユーモアのセンスをお持ちですね。
小澤征爾は、確かに、カーテンコールの時、舞台の上から、身をかがめつつ、両手を拡げ、オケピのメンバーの労をねぎらっていました。
風は、あの小澤の姿を、オーケストラのメンバーとともに、聴衆の拍手を共有している謙虚な人間性の表れとして、見ていました。
ところが、それを、石井さんは、「米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度」だと受け留められたわけですね。
なるほど……こういう形容もあるんですね。
そういえば、かの幻のピアニスト、ミケランジェリが来日し、チェリビダッケとシューマンの協奏曲を演奏したコンサートは、今でも、鮮明に覚えています。
ミケランジェリが舞台に登場した瞬間、異様な緊張感が、ホールに張りつめました。
風は、最前列、かぶりつきの席だったのですが、あのミケランジェリの風貌は、一生、忘れることができません。
ピアノに軽く片手をかけ、うなずくように、首をかすかに前に曲げること3回。
口ひげをたくわえ、神経質そうなミケランジェリの表情からは、聴衆の拍手さえ峻拒し、自分の音楽に没頭しようとする芸術至上主義的な孤高の矜持がオーラのように漂っていました。
これだけ厳しい風貌をした表現者に出会うことは、もう、一生ないだろうと感じました。
演奏は、ミケランジェリとしては、不調だったのか、ピアノの鳴りが、少し悪かったようです。
演奏終了後も、聴衆の大喝采に、弾く前と同じ軽い会釈をするのみ。
にこりともしませんでした。
一切の妥協を許さず、音楽と自分以外の存在を認めまいとするミケランジェリの思いが、風姿から、せつせつと伝わってきて、感動しました。
「表現者としての絶対的孤独」
としかいいようのない品格が、オーラになって、放射されていました。
やっぱり、不調だったのでしょうか。
ミケランジェリは、翌日からのコンサートを、全部、キャンセルして、帰国してしまいました。
なるほど、そのようなミケランジェリの姿に比べると、小澤のあの態度は、石井さんの目には、「米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度」と写るのかも知れませんね。
ただ、私は、石井さんのレトリックの巧みさに感心しつつ、これは、どこかで、読んだことがあるような表現だ……という思いがしました。
何だったんだろう……と、実は、夕刻、石井さんの書き込みを拝読してから考えていたのですが、先ほど、思い出しました。
頬骨が出て、唇が厚くて、眼が三角で、名人三五郎の彫った根付の様な顔をして
魂をぬかれた様にぽかんとして
自分を知らない、こせこせした
命のやすい
見栄坊な
小さく固まって、納まり返った
猿の様な、狐の様な、ももんがあの様な、だぼはぜの様な、麦魚(めだか)の様な、鬼瓦の様な、茶碗のかけらの様な日本人
言わずと知れた、高村光太郎の「根付の国」。
日本人というものが、いかに醜く、能力が低く、くだらない存在であるかというコンプレックスを、高村光太郎自身が、西洋人の眼差しに成り代わって描いた、有名な作品ですね。
「米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度」
という比喩表現には、高村光太郎の「根付の国」に共通している心理があるような気がいたします。
あえて、「小澤征爾」という名前を文中で使用されず、「風さん御贔屓のあの指揮者」とのみ称されているところからも、同様のことを感じました。
「アンチ・カラヤン」というのは、もう30年以上前になりますでしょうか(風は、子供でした)、日本にも、多数存在していましたが、「アンチ・小澤」という方も、現在、たくさん、いらっしゃるわけですね。
日本人の「小澤征爾嫌い」という現象には、現在の日本における「文化人の心理」「音楽評論家の心理」が象徴されているのでは、ないでしょうか。
長年の風の疑問に対する回答を、石井さんより、与えていただいたような気がいたしました。
感謝しております。
そのことは、さておき、とにかく、石井さんの御啓蒙によって、風がいかに、「クラシック」についての知識が不足しているか、学ばせて頂くことができました。
特に、オペラについては、もっともっと、いろいろな舞台を体験して、自分の感性を鍛えておかなければ……と反省いたしました。
相手は、ものすごい博識な方で、知識的には、まったく、かないませんでした。
音楽評論家の方々も、マエストロのモーツァルトに関しては、否定的な意見がけっこうあるようです。
しかしながら、私は、小澤の「フィガロ」と「ドン・ジョバンニ」に感動したのですが……。
ま、身銭を切って聴きに行くのだから、自分が感動すれば、それでいいじゃないか…という世界なのですが、どなたか、同じ舞台を、お聴きになられた方、いらっしゃいませんか?
[68896]風さんにお尋ねします!
2005/09/21(Wed) 15:49:24
風さんは、
前回のウィーン国立歌劇場の来日公演を、
本当に良かったと思われたのでしょうか?
どこを良いと思われたのか、
特に指揮者について、
お聞かせいただきたいと思います。
私は、
あの時初めて、
モーツァルトも汚く演奏され得る、
ということを知ったのですが……。
七代目石井庄七
?65
[68897]七代目石井庄七さまへ質問です
2005/09/21(Wed) 17:11:47
う〜ん、公開質問状ですね。
文学についての論争は受けたことがありますが、音楽については、はじめてです。(^^;)
小澤征爾のモーツァルト演奏は、賛否両論というか、音楽評論家からは、大体、批判的な言質が多いですね。
特に、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に就任してからの批評を読むと、ほとんど、毎回、貶されていますね。
平板な演奏。
面白味のない解釈。
没個性的でなんの魅力もない。
なんていうふうな批判が、音楽誌を見ていると、満ち満ちています。
わたしは、音楽は専門ではなく、ただ、好き嫌いだけで聴いているので、正直、楽理については、まったく分かりません。
正当な解釈というのも、分かりません。
だから、逆に、ずーっと、疑問だったんですよ。
なぜ、小澤のモーツァルトが、あんなに貶されるのか…ということが。
小澤オタクの風は、「フィガロの結婚」「ドン・ジョバンニ」を2回ずつ、聴きに上京しました。
後半の演奏の方が、飛躍的に良くなっているような気がして、単純に感動して、帰ってきました。
七代目石井庄七さまは、
「あの時初めて、
モーツァルトも汚く演奏され得る、
ということを知ったのですが……。」
とお書きになっているので、多分、音楽評論家の方々と同じようなことをお感じになったと思います。
その「汚い」というのは、どういう部分なのでしょうか?
教えていただければ、ありがたく存じます。
風
[68947]風さんへ
2005/09/23(Fri) 10:36:15
好き嫌いの問題なんですね!
そうなると、
なにやら無粋な質問をしてしまったように思います。
御容赦ください。
しかし風さんが列挙された批評家の発言は、
どれも納得できるものだと思いますよ。
昨年のモーツァルト二作品を
「汚い」と感じた理由も、
そんな欠点にあったと言えるでしょう。
付け加えれば、
ウィーン・フィルの母体である
あの歌劇場のオーケストラが、
ソロの部分はしばしば美しいのに、
いざトゥッティになると
耳を疑うほどに音が濁って汚くなっていたのが、
大いに気になりました。
これはオーケストラの問題ではなく、
指揮者の問題だと思われます。
オーケストラが全く弾まず、
モーツァルトの音楽の愉悦を
引き出せていなかったのも問題ですし、
あまりにも柔軟性に欠けたテンポ設定のため、
しばしば歌唱とオーケストラの間に
かなり大きなずれが生じていたのも、
聞き苦しく感じましたね。
要するにあの指揮者は
モーツァルトに不向きだということで、
ウィーン国立歌劇場が
モーツァルトの主要作品の指揮を
定評のあるリッカルド・ムーティに
任せるようになったというのは、
正当な処置だと思います。
風さんが大好きなあの日本人指揮者が
優れた音楽家であるということは、
もちろん間違いありませんが、
何十回と彼が指揮するオペラを聴いてきた
経験から言えば、
彼はオペラ向きの指揮者ではないのだと思います。
なお、風さんが、
ウィーン国立歌劇場の次回の来日公演で
Die Meistersinger を指揮するのを
残念そうに書いていらっしゃる
クリスティアン・ティーレマンですが、
彼のオペラの指揮は
実に見事なものです。
もちろん実際の舞台を聴いた経験で言うのですが、
少なくとも
ヴァーグナーとR.シュトラウスに関しては、
現代屈指の名指揮者だと言えるでしょう。
好き嫌いで聴くのも悪くはないでしょうが、
いろいろな指揮者の指揮するオペラを聴き比べ、
オペラとはどういうものか見極めることの方が、
一層楽しい、
しかも意義のあることだと思います。
七代目石井庄七
?66
[68953]七代目石井庄七さまへ
2005/09/23(Fri) 12:49:59
[68947]風さんへ の文章、非常に、興味深く拝読いたしました。
新聞や音楽時評では、石井さんのように、具体的な指摘がなされていないので、よく意図が分からなかったのですが、ご意見うかがい、なるほど、こういうことだったのか…という気がしました。
素人の私なりの感想を申し上げますと、
ウィーン・フィルの母体である
あの歌劇場のオーケストラが、
ソロの部分はしばしば美しいのに、
いざトゥッティになると
耳を疑うほどに音が濁って汚くなっていたのが、
大いに気になりました。
という部分ですが、他のオーケストラでも同じだと思うのですが、ウィーンフィルは、特に、初日と楽日の出来の差が激しいオケだと思います。
これは、以前、小澤が、大阪でブラームスのシンフォニーを振ったとき、第1番と第4番が、日本初日だったのですが、最初に演奏した4番の音が、「これが、ウィーンフィル?」というような荒削りの響きでした。
ところが、翌日の最後の曲、第2番は、ウィーンフィル独特のつややかでまろやかな音色でした。
同じことは、昨年、大阪と九州で聴いたゲルギエフの指揮のチャイコフスキーでも感じました。
来日初演の第4番(福岡シンフォニーホール)は、いまひとつ、生硬な感じで、ほどほどの出来だと感じたのですが、後日、NHKで放送されたサントリーホールでの第4番は、見違えるような演奏でした。
石井さんがお聴きになった小澤のモーツァルトが、楽日ならば、上記のことは該当しないと思うのですが、わたしも、前半と後半で、オケの響きが、まったく違って聞こえたので、もし、前半の方の公演をお聴きになったのならば、ご指摘のことは、当たっているかも知れないと思いました。
また、
オーケストラが全く弾まず、
モーツァルトの音楽の愉悦を
引き出せていなかったのも問題ですし、
あまりにも柔軟性に欠けたテンポ設定のため、
しばしば歌唱とオーケストラの間に
かなり大きなずれが生じていたのも、
聞き苦しく感じましたね。
というのは、よくも悪くも、小澤征爾という指揮者の特質をご指摘されているように思いました。
基本的に、小澤は、テンポを揺り動かさず、細部の彫琢に意を尽くす指揮をするので、録音などで聴くと、あまり、面白く感じられないことが、私もあります。
いわば、日本の工芸品の細密な美しさを、西洋音楽で表現しているわけで、細やかなフレーズの音色の微妙な変化とか、スコアの中に、埋没している音を、すくい上げてくるとか、そういう感覚・解釈の音楽なので、「いわゆるモーツァルト」という印象からは、ずれて聞こえるのではないでしょうか。
ただ、これは、オペラではありませんが、茨城県まで、水戸室内管弦楽団のモーツァルト・プログラムを3回ほど聴きに行った経験では、非常に透明感のある細密な演奏で、リンツなど、素晴らしかったように感じました。
小澤は、モーツァルトとか、ワーグナーとか、いわゆる伝統が確立しているクラシックオペラの指揮の評判は悪いのに、なぜか、シェーンベルクとか、アルバン・ベルクとか、20世紀のオペラを振ると、評価が高いですね。
これは、もしかしたら、小澤という指揮者が、カラヤンやバーンスタインに学びながらも、根本的に、伝統的な西洋音楽と断絶した「日本人としての感覚」から、脱却できていないことの証かもしれないと思っています。
つまり、現代音楽という、まだ西洋でも、伝統的演奏法・伝統的解釈が確立されていない曲では、清新に聞こえるにもかかわらず、既に、確固とした伝統が確立されてしまっている曲では、いわゆる「通」の人には、違和感を与えてしまうのではないでしょうか。
「素人」は喜んで聴いているが、「プロ」は顔をしかめて聴いているという断絶感は、どうも、そういうところに由来しているのではないか…という気がしています。
サイトウキネンのブラームスでも、ヨーロッパでは、いささか、違和感をもって、批評された部分もあったようですね。
しかしながら、表現というものに、果たして、「正統な解釈」「絶対的な伝統」というものが、存在するのか……ということになると、議論は果てしなく続いてしまいますね。
かのワーグナーとブラームスの音楽のどちらを認めるかということで、侃々諤々の議論が、同時代のヨーロッパで起こったように、「日本人的なモーツァルト」「日本人的なクラシック解釈」というのが存在して、それに、素朴に感動する人間がいてもいいのではないかという気が、自分はしております。
そういう意味では、小澤が、自分自身で言っているように、彼は、「東洋人がクラシック音楽に受け入れられるかどうかの試金石」のような存在ですね。
あと、石井さんのお話をうかがい、クリスティアン・ティーレマンのワーグナーは、是非とも、聴いてみたくなりました。
3年先に向けて、貯金をしなくては……。
こちらは、経済的にカツカツ状態で、聴きに行っているので、次から次へというわけにはいかないのですが、いろいろなオペラの聞き比べをやってみたくなりました。
興味深いお話、ありがとうございました。
風
[69078]風さんへ
2005/09/27(Tue) 18:06:16
メータのヴァーグナーは、いかがでしたか?
「インド人的」ヴァーグナーではなかったでしょ?
ウィーンフィル(およびウィーン国立歌劇場のオーケストラ)が
しばしば指揮者を見て手を抜いた演奏をする、
という話は、
たしかによく聞きますよね。
カルロス・クライバーの代役で振ったシノーポリは
気の毒だったと思いますが、
まあ、オーケストラに馬鹿にされるかされないかも、
指揮者の力量ということでしょう。
風さん御贔屓のあの指揮者の、
カーテンコールにおける米搗き飛蝗のような
卑屈極まりない態度は、
少なくとも尊敬を集めそうではないと思いますが、
いかがでしょう?
20世紀の音楽についてのくだりは、
私の文章が舌足らずで、
誤解を招いてしまったと後悔しています。
当然のことながらどの時代の音楽でも、
それをきちんと、あるいは見事に演奏するのは
やはり並大抵のことではないでしょう。
ただ、同時代の音楽の方が、
感性が近いので、とでも言いましょうか、
より演奏しやすいはずだと想像しただけのことで、
技術的な問題なども考慮すれば、
あまり説得力のある意見ではなかったかしれませんね。
ただ、たとえば印象派の絵画にしても、
それが現在どれほど高く評価されているのか判りませんが、
発表当時から認めた人は存在したわけで、
同時代的評価は難しい、というのは、
逃げ口上に過ぎないと考えます。
《ごーふる・たうん》に立ち寄るほどの人間なら、
きちんと同時代の芸術を評価すべく
努力しなければならないのではないでしょうか?
風さん御贔屓の指揮者が現代音楽に強い、
というのは、
もちろん認めざるを得ないことでしょう。
メシアン唯一のオペラの初演を
作曲者自身に任されたという事実ひとつだけで、
日本人であることなどまったく抜きにして、
大いに、
かつ永遠に称賛されるべきだと思います。
風さんが
あの指揮者が振った Wozzeck について書いておられることは、
私は松本まで行ってはいませんが、
ほかの彼の現代音楽の演奏から類推して、
理解できることです。
要するにどの音も美しく、聴きやすくなっている、
ということですよね。
余談ですが、
ジェームズ・レヴァインの場合も同じで、
彼が MET で振るベルクやブリテンは、
とても美しく解りやすい。
モーツァルトなどよりもさらにずっと
綺麗で耳に心地よいと感じられるほどです。
それはとても優れた特色ですが、
しかし物足りなく思われもするわけですよね。
おそらく風さん御贔屓の指揮者のベルクやブリテンも、
そういった特色を持っているのだと言えるのでしょう。
私は、
モーツァルトを汚く演奏することは許されないが、
20世紀の音楽は美しいだけでは困る場合がある、
と考えます。
たとえば
Wozzeck の第三幕第三場で演奏される舞台上のピアノは、
スコアには Ein verstimmtes Pianino
すなわち「調子の狂ったアップライトピアノ」と
わざわざ指定してありますよね。
つまりあのピアノは
美しい和音を奏でてはいけない、
そこに発生する不協和音は美しくあってはならない
ということなのだと愚考します。
一瞬も美しく、一瞬一瞬の集積としての全体も美しい、
というのがモーツァルトのオペラだとしたら、
現代のオペラは、
一瞬一瞬は必ずしも美しくはないかも知れないが、
全体を聴けばある圧倒的な美を感じることができるものだ、
ということでしょうか?
風さん御贔屓の指揮者の20世紀オペラに
いささかの不満を感じざるを得ないのは、
そういった観点からなのです。
なお、
風さんは「マイナーな20世紀オペラ」とおしゃいますが、
松本の音楽祭で取り上げられているオペラは、
いずれもマイナーとは呼べない作品だと思います。
Wozzeck をレペルトワールに持たない一流オペラハウスは、
世界中探したって見つからないと思いますよ!
七代目石井庄七
?67
[69092]七代目石井庄七さまへ♪
2005/09/28(Wed) 00:54:39
バイエルン国立歌劇場、メータのワーグナー、素晴らしかったです。
オペラ経験の乏しき風は、『タンホイザー』も『ニュルンベルグのマイスタージンガー』も、始めての経験でした。
『マイスタージンガー』など、休憩を挟んで、5時間半などという代物。
途中、寝てしまったら、どうしようなどと心配しておりましたが、杞憂でした。
旋律のすみずみまで、メータ特有の幅のある豊麗な音楽になっていました。
「『インド人的』ヴァーグナーではなかったでしょ?」
は、確かに、お言葉通り。
『インド人的』どころか、まさに、『独逸の伝統精神』そのものを表現した素晴らしいワーグナーでした。
トーマス・ラングホフの演出が、舞台設定を現代の時代に置き換えていました。
メータの音楽と違和感はなかったので、最初、何も思わず、そのまま、聴き進んでいたのですが、終盤近くになって、ようやく、ラングホフの演出意図が分かりました。
主人公の靴屋の親方ザックスが、「マイスタージンガーを侮らないで」の独逸精神を讃え歌った後、人々は、ザックスを讃え、「ドイツのマイスタージンガーたちを尊敬せよ」の大合唱で、フィナーレとなる。
これは、ベルリンの壁が崩壊して以降、経済格差のあった東西のドイツが統合されたため、経済上、混乱が生じ、国際的な地位が下落してしまった「現在のドイツ」をテーマにした舞台だったのですね。
ワーグナー以前からの、音楽の伝統を継承・確認・体験することにより、凋落傾向にある国家国民の誇りを回復し、賞揚しようとする国威発揚の熱い思い。
愛国心。
演出家と指揮者とオケと歌手のエネルギーが一体となり、舞台から、溢れ出てきて、聴いていて身体が熱くなりました。
さて、今まで、何回かやりとりさせて頂いた公開討論も、そろそろ、大詰めを迎えたと言えるのでしょうか。
(風のカキコが長すぎて、鬱陶しいと思われた方、ごめんなさいね。文章の性質上、長くなってしまいました)
ウィーンフィルが指揮者を選ぶという問題に関し、石井さんのご発言、
「まあ、オーケストラに馬鹿にされるかされないかも、
指揮者の力量ということでしょう。
風さん御贔屓のあの指揮者の、カーテンコールにおける米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度は、少なくとも尊敬を集めそうではないと思いますが、いかがでしょう?」
には、爆笑させていただきました。
なかなか、ユーモアのセンスをお持ちですね。
小澤征爾は、確かに、カーテンコールの時、舞台の上から、身をかがめつつ、両手を拡げ、オケピのメンバーの労をねぎらっていました。
風は、あの小澤の姿を、オーケストラのメンバーとともに、聴衆の拍手を共有している謙虚な人間性の表れとして、見ていました。
ところが、それを、石井さんは、「米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度」だと受け留められたわけですね。
なるほど……こういう形容もあるんですね。
そういえば、かの幻のピアニスト、ミケランジェリが来日し、チェリビダッケとシューマンの協奏曲を演奏したコンサートは、今でも、鮮明に覚えています。
ミケランジェリが舞台に登場した瞬間、異様な緊張感が、ホールに張りつめました。
風は、最前列、かぶりつきの席だったのですが、あのミケランジェリの風貌は、一生、忘れることができません。
ピアノに軽く片手をかけ、うなずくように、首をかすかに前に曲げること3回。
口ひげをたくわえ、神経質そうなミケランジェリの表情からは、聴衆の拍手さえ峻拒し、自分の音楽に没頭しようとする芸術至上主義的な孤高の矜持がオーラのように漂っていました。
これだけ厳しい風貌をした表現者に出会うことは、もう、一生ないだろうと感じました。
演奏は、ミケランジェリとしては、不調だったのか、ピアノの鳴りが、少し悪かったようです。
演奏終了後も、聴衆の大喝采に、弾く前と同じ軽い会釈をするのみ。
にこりともしませんでした。
一切の妥協を許さず、音楽と自分以外の存在を認めまいとするミケランジェリの思いが、風姿から、せつせつと伝わってきて、感動しました。
「表現者としての絶対的孤独」
としかいいようのない品格が、オーラになって、放射されていました。
やっぱり、不調だったのでしょうか。
ミケランジェリは、翌日からのコンサートを、全部、キャンセルして、帰国してしまいました。
なるほど、そのようなミケランジェリの姿に比べると、小澤のあの態度は、石井さんの目には、「米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度」と写るのかも知れませんね。
ただ、私は、石井さんのレトリックの巧みさに感心しつつ、これは、どこかで、読んだことがあるような表現だ……という思いがしました。
何だったんだろう……と、実は、夕刻、石井さんの書き込みを拝読してから考えていたのですが、先ほど、思い出しました。
頬骨が出て、唇が厚くて、眼が三角で、名人三五郎の彫った根付の様な顔をして
魂をぬかれた様にぽかんとして
自分を知らない、こせこせした
命のやすい
見栄坊な
小さく固まって、納まり返った
猿の様な、狐の様な、ももんがあの様な、だぼはぜの様な、麦魚(めだか)の様な、鬼瓦の様な、茶碗のかけらの様な日本人
言わずと知れた、高村光太郎の「根付の国」。
日本人というものが、いかに醜く、能力が低く、くだらない存在であるかというコンプレックスを、高村光太郎自身が、西洋人の眼差しに成り代わって描いた、有名な作品ですね。
「米搗き飛蝗のような卑屈極まりない態度」
という比喩表現には、高村光太郎の「根付の国」に共通している心理があるような気がいたします。
あえて、「小澤征爾」という名前を文中で使用されず、「風さん御贔屓のあの指揮者」とのみ称されているところからも、同様のことを感じました。
「アンチ・カラヤン」というのは、もう30年以上前になりますでしょうか(風は、子供でした)、日本にも、多数存在していましたが、「アンチ・小澤」という方も、現在、たくさん、いらっしゃるわけですね。
日本人の「小澤征爾嫌い」という現象には、現在の日本における「文化人の心理」「音楽評論家の心理」が象徴されているのでは、ないでしょうか。
長年の風の疑問に対する回答を、石井さんより、与えていただいたような気がいたしました。
感謝しております。
そのことは、さておき、とにかく、石井さんの御啓蒙によって、風がいかに、「クラシック」についての知識が不足しているか、学ばせて頂くことができました。
特に、オペラについては、もっともっと、いろいろな舞台を体験して、自分の感性を鍛えておかなければ……と反省いたしました。
|
|
|
|
コメント(4)
おお!
長いので、実はまだ、全文を読まずにコメント書いているので恐縮ですが・・・
私は、映像制作の仕事をしていますが、たまに社長なんかと、「私が見ている色と、君が見ている色が同じと言う保証はない!」てな話になります。
結局、人間の視覚から入ってくるイメージは、自分本位な「脳」で処理されるので、極端言えばあるのに見えない事もある。。。と言うような事ですね。
目に見えるものだってそんな具合ですから、音と言う物はもっと曖昧なのではないかと。だって、どんどん消えてゆきますからね(笑
そう考えると、同じ物(演奏)でも、楽しめちゃった者が得と、言う事でしょうか!
僕も、去年の10月の上野のオペラでしか、小澤さんのパフォーマンスを生で見た事が無いのですが、ちょうど横の高い位置の席だったので、ずーーーっと、舞台より、小澤さんが棒振る様を見ていて、たいそう楽しかったです。
ともすれば、演奏なんかどうでもよくて(笑 あこがれの人のパフォーマンスを生で見ている事が重要だったみたいですね。
そんなことで、いろんな楽しみ方、味わい方があって、一つの物にも多様な価値があって。。。人生って面白いですね。
まあ、僕ら、オペラだの、生オーケストラの演奏なんか観に行けて、本当にラッキー!! 恵まれた人生です。ありがたいです。
といいつつ、やっぱりまた、小澤さんのライブに行きたいっす。
長いので、実はまだ、全文を読まずにコメント書いているので恐縮ですが・・・
私は、映像制作の仕事をしていますが、たまに社長なんかと、「私が見ている色と、君が見ている色が同じと言う保証はない!」てな話になります。
結局、人間の視覚から入ってくるイメージは、自分本位な「脳」で処理されるので、極端言えばあるのに見えない事もある。。。と言うような事ですね。
目に見えるものだってそんな具合ですから、音と言う物はもっと曖昧なのではないかと。だって、どんどん消えてゆきますからね(笑
そう考えると、同じ物(演奏)でも、楽しめちゃった者が得と、言う事でしょうか!
僕も、去年の10月の上野のオペラでしか、小澤さんのパフォーマンスを生で見た事が無いのですが、ちょうど横の高い位置の席だったので、ずーーーっと、舞台より、小澤さんが棒振る様を見ていて、たいそう楽しかったです。
ともすれば、演奏なんかどうでもよくて(笑 あこがれの人のパフォーマンスを生で見ている事が重要だったみたいですね。
そんなことで、いろんな楽しみ方、味わい方があって、一つの物にも多様な価値があって。。。人生って面白いですね。
まあ、僕ら、オペラだの、生オーケストラの演奏なんか観に行けて、本当にラッキー!! 恵まれた人生です。ありがたいです。
といいつつ、やっぱりまた、小澤さんのライブに行きたいっす。
原田さま、早速のコメントありがとうございました。
マエストロ小澤の音楽は、ライブで聴かないと、絶対にその真価が分からない!というのが、20年間聴き続けた結論です。
特に、サイトウキネンオーケストラと、水戸室内管弦楽団の演奏の透明感は、比類がありません。
マエストロのモーツァルトのシンフォニーを聴くため、風は、兵庫県から茨城県水戸市まで、いくどとなく足を運びました。
小澤の師匠のカラヤンにも、反対派(アンチ・カラヤン派)が多くいたように、アンチ・小澤派もたくさんいるようです。
現在の指揮者で、カラヤン的な格好良さをもっとも引き継いでいるのは小澤だと思うので、「絶対、小澤だけは認めない!」という方がいるのは、ある意味では、当然かもしれませんが…。
マエストロ小澤の音楽は、ライブで聴かないと、絶対にその真価が分からない!というのが、20年間聴き続けた結論です。
特に、サイトウキネンオーケストラと、水戸室内管弦楽団の演奏の透明感は、比類がありません。
マエストロのモーツァルトのシンフォニーを聴くため、風は、兵庫県から茨城県水戸市まで、いくどとなく足を運びました。
小澤の師匠のカラヤンにも、反対派(アンチ・カラヤン派)が多くいたように、アンチ・小澤派もたくさんいるようです。
現在の指揮者で、カラヤン的な格好良さをもっとも引き継いでいるのは小澤だと思うので、「絶対、小澤だけは認めない!」という方がいるのは、ある意味では、当然かもしれませんが…。
なるほど〜。やはり生がいいのですねえ。
私の小澤さんとの出会いは、高校受験の折ぐらいに、父にもらった小澤征爾さんのドキュメンタリフィルムのVTRを見たのが最初。
ドキュメンタリーとして心を打たれたのですが、それをきっかけに、マーラー2番「復活」が、好きになったのです。
で、しばらくして、NHKで日曜の夜当たりに「N響アワー」と言うような番組があり、新聞で「復活」が演目だと見て、いさんでその番組を見たのですが。。。。
「これ、復活と違う曲だぞ!」と、思ったのです。
どういう事だったかと言うと、「映画が、同じ台本でも、監督が違うと全く異なる作品になってしまうのと同じくらいに、音楽と言うのも指揮者で全く異なる印象のものになるのだ」と、言う事が、この時初めて解ったのです。
そこで、それから高校時代は「OZAWA」のCDを探しまわって(当時は今ほど手に入りやすくなかった)。。。で、たまに他の人の演奏も聴くと、やっぱり、小澤さんのじゃないとだめだ〜と言う事を繰り返し。。。そのうち、小澤さんの以外は聞かなくていいや! と、言う人生にしてしまったのです。
とかいって、そんなにたくさん聞いている訳でもないのですが。。。レスピーギの「ローマの松」のCDなんかは、高校生の時からずっと聞いているディスクですね。
映像制作を生業にしていたので、もっぱら音楽はそのBGMとして日々触覚をはりめぐらせている・・・という感が強かったかもしれません。小澤さんの音楽は、画が湧くのです。
でも、いくつか、小澤解釈が自分の肌に合わない曲もありました。ラヴェルのボレロなんかは、残念ながら別の方指揮の曲の方が、ああ、ボレロだなと思うのです。そういうのもありますよね。
作曲者の価値観と、指揮者の価値観と、聞く者の価値観と。。。時空を超えてそういうのがピタッと合うことが、あるのでしょうか。
今年は、7月に小澤さんのマーラー2番が聞けるはずだったので、是非チケットを取ろうと思っていたのですが。。。
なんか、勝手に書いてますが。風さんのコメントを受けて・・・。
私の小澤さんとの出会いは、高校受験の折ぐらいに、父にもらった小澤征爾さんのドキュメンタリフィルムのVTRを見たのが最初。
ドキュメンタリーとして心を打たれたのですが、それをきっかけに、マーラー2番「復活」が、好きになったのです。
で、しばらくして、NHKで日曜の夜当たりに「N響アワー」と言うような番組があり、新聞で「復活」が演目だと見て、いさんでその番組を見たのですが。。。。
「これ、復活と違う曲だぞ!」と、思ったのです。
どういう事だったかと言うと、「映画が、同じ台本でも、監督が違うと全く異なる作品になってしまうのと同じくらいに、音楽と言うのも指揮者で全く異なる印象のものになるのだ」と、言う事が、この時初めて解ったのです。
そこで、それから高校時代は「OZAWA」のCDを探しまわって(当時は今ほど手に入りやすくなかった)。。。で、たまに他の人の演奏も聴くと、やっぱり、小澤さんのじゃないとだめだ〜と言う事を繰り返し。。。そのうち、小澤さんの以外は聞かなくていいや! と、言う人生にしてしまったのです。
とかいって、そんなにたくさん聞いている訳でもないのですが。。。レスピーギの「ローマの松」のCDなんかは、高校生の時からずっと聞いているディスクですね。
映像制作を生業にしていたので、もっぱら音楽はそのBGMとして日々触覚をはりめぐらせている・・・という感が強かったかもしれません。小澤さんの音楽は、画が湧くのです。
でも、いくつか、小澤解釈が自分の肌に合わない曲もありました。ラヴェルのボレロなんかは、残念ながら別の方指揮の曲の方が、ああ、ボレロだなと思うのです。そういうのもありますよね。
作曲者の価値観と、指揮者の価値観と、聞く者の価値観と。。。時空を超えてそういうのがピタッと合うことが、あるのでしょうか。
今年は、7月に小澤さんのマーラー2番が聞けるはずだったので、是非チケットを取ろうと思っていたのですが。。。
なんか、勝手に書いてますが。風さんのコメントを受けて・・・。
いえいえ、熱いコメント嬉しいです。
マエストロ小澤のマーラー2番は、いいですよ。
ものすごくいいです。
以前、サイトウキネンを聴きに、年末、松本まで行きました。
ものすごく、繊細かつ掘り下げが深くて、こんな細かい部分にまで、魂が宿っているのかと驚かされるような演奏でした。
ノーマルな演奏を記憶しているほど、そのセンシティブで、一音一音の細部を、鋭く射抜くような譜読みの凄さが感じられます。
たとえば、弦パートのピチカートをデクレッシェンドしていくような部分。
背筋が寒くなりました。
楽章の間の沈黙が、限りなく長く感じられました。
あんな表現が、可能などとは、考えたこともありませんでした。
しかし、あれだけの演奏は、サイトウキネンじゃないと、技術的に無理なのだと思います。
要は、そのように、細かな部分、音色の微妙な変化というところに、マエストロ小澤の真価があるのであって、たとえば、ロリン・マゼルのように、テンポを恣意的に動かして、奇をてらうような演奏とは、根本的に、音楽的アプローチが異なるわけです。
そういう細やかな耳を持たない方々には、マエストロの演奏は、単調に聞こえるわけですね。
ダイナミックにして、かつ、センシティブ。
復活した小澤征爾の演奏を、聴きたいです!
マエストロのご回復を、心から、祈っております。
マエストロ小澤のマーラー2番は、いいですよ。
ものすごくいいです。
以前、サイトウキネンを聴きに、年末、松本まで行きました。
ものすごく、繊細かつ掘り下げが深くて、こんな細かい部分にまで、魂が宿っているのかと驚かされるような演奏でした。
ノーマルな演奏を記憶しているほど、そのセンシティブで、一音一音の細部を、鋭く射抜くような譜読みの凄さが感じられます。
たとえば、弦パートのピチカートをデクレッシェンドしていくような部分。
背筋が寒くなりました。
楽章の間の沈黙が、限りなく長く感じられました。
あんな表現が、可能などとは、考えたこともありませんでした。
しかし、あれだけの演奏は、サイトウキネンじゃないと、技術的に無理なのだと思います。
要は、そのように、細かな部分、音色の微妙な変化というところに、マエストロ小澤の真価があるのであって、たとえば、ロリン・マゼルのように、テンポを恣意的に動かして、奇をてらうような演奏とは、根本的に、音楽的アプローチが異なるわけです。
そういう細やかな耳を持たない方々には、マエストロの演奏は、単調に聞こえるわけですね。
ダイナミックにして、かつ、センシティブ。
復活した小澤征爾の演奏を、聴きたいです!
マエストロのご回復を、心から、祈っております。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
小澤征爾様 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
小澤征爾様のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90056人
- 2位
- 酒好き
- 170692人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208288人