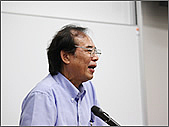このコミュニティーは、2月20日の白石先生喜寿お祝い会用に立ち上げましたが、
その後、有効活用されておらず、管理人としては、今後も盛り上げていくには、
どうすればいいか考えた結果、まずはマーケティングに関する話題を掲載していこうと
思いました。今後、随時、皆様にとって有益となるような事柄を掲載しようと思います。
「世代論」で語る消費分析のワナ
宇南山卓・神戸大学准教授に消費データの正しい見方を聞く(日経ビジネスより抜粋)
宇南山 卓(うなやま・たかし)氏
神戸大学大学院経済学研究科准教授。1997年東京大学経済学部卒、99年同大学大学院修士課程修了、2004年同大学博士(経済学)。慶應義塾大学、京都大学講師を経て現職。専門は、日本経済論。現在、日本経済研究センター特別研究員・経済産業研究所ファカルティーフェローとして、少子化と女性労働について研究している。日本経済研究センターでは「若手研究者による政策提言プロジェクト」に参加、経済産業研究所では吉川洋東京大学教授の研究プロジェクト 「少子高齢化と日本経済」のサブリーダー。
―― 現代の若者はお金を使わない、消費に魅力を感じていないと最近、よく言われます。確かに自動車は以前のように若者の憧れではなくなりましたし、服装もファストファッション化しています。
宇:若者の消費に関するデータを見る場合には、実は色々と気をつけなければならない点が
あります。例えば、総務省統計局が公表している「家計調査」を使って若者の消費を調べようとすれば、年齢階級別のデータを使います。年齢階級は、世帯主の年齢で見ます。
そのため25歳の若者の消費を見ようとすれば、25歳が世帯主となっている世帯の消費を
見るのです。昔は25歳なら、多くの人が結婚していましたから、25歳が世帯主の世帯の消費
を見れば、その年齢階級の若者がどんなものを買っているかが分かりました。
ところが今は、25歳ですと独身で、親元に住んでいたり一人暮らしをしている人が多いでしょう。親は恐らく50歳ぐらいです。親と同居していれば、25歳の消費でも、50歳の消費としてカウントされてしまうのです。
経済学者は、世帯全体の消費から若者の消費だけを抜き出そうと頑張るのですが、若者の消費の現状はこうだと断定するのは、かなり難しいのが実情です。
さらに、家計調査では基本的に「2人以上の世帯」の数値が注目されます。単身世帯も調査していますが、一人暮らしの若者は調査が困難であり、若者のサンプルの質は十分とはいえません。その意味で、結婚をしてないと、そもそも統計から漏れている可能性が高いのです。
◆昔の25歳は世帯主だった
また、消費の実態についても、昔は20代後半〜30代前半なら、大体子供がいました。若い人とはそういう人たちが中心だったのです。現在の結婚をしていない25歳と、昔の結婚をしていた25歳では、消費の仕方が違います。さらに、独身者だけを比較するとしても、高学歴の人ほど結婚が遅くなっている傾向がありますから、昔の独身者と今の独身者では学歴構成は大きく違います。つまり、昔と今の若者の消費行動の違いを、単純に平均によってとらえるのは適ではありません。
―― 社会の変化を多面的に念頭に置か なければ、たとえデータを基にしたとしてもおかしな分析になってしまうのですね。
宇:そもそも「若者は消費をしない」と言う時、それが具体的に何を意味しているのかが重要です。平均としては(バブル期ごろに比べて)自動車を買わないとか、お酒を飲まないという点は確かにあります。しかし、もう1つのキーワードとして「一点豪華主義」に注目すると、より大きな社会の変化と関係づけることができます。その変化とは、消費の多様化です。
「現在の若者は普段金を使わないくせに、一点豪華主義でブランド物を買う」という言い方がされたりします。これは一見もっともらしいですが、暗黙のうちに消費「すべき」モノを想定しています。一点豪華主義という感覚は、昔はみんなが欲しがるもの、買わなければいけないものは大体同じだったことの裏返しだと思います。
例えば都市部では、そこそこの給料をもらえる年齢になったら200〜300万円の自動車を買うという考え方が、暗黙の決まりみたいなものでした。でも、本当に20代後半ぐらいの人全般にとって自動車が、200万円という大金を出す価値があったかというと、恐らくあまりなかったでしょう。かなりの贅沢品ですよね。でも昔はみんなが買うものだったから、一点豪華と言われなかった。でも今、若者がプリウスを買えば、同世代からは一点豪華主義的な消費と見なされてしまうでしょうね。
スカイラインは常識で、シャネルは贅沢?
―― なるほど。
宇:みんなと同じものを買わないと目立って見えるだけで、どこかにお金を集中的に使うのは昔の人も今の人も一緒です。ただ、消費 が多様化した社会では、集中的に使うものが他の人と一致しない可能性が高いのです。他人とたまたま一致しているか、一致してないかで与える印象が違いま す。
昔は若者が日産のスカイラインを買っても、分不相応だと怒る大人はいなくて、「それくらいの年になれば誰でも車は欲しいよね」と言われたでしょう。それが今、自動車なんていらないと言うと、「最近の若者は消費に興味がない、困ったものだ」と論評される。しかし一方で「私、(車は買わないけど) シャネルのバッグ買いました」と言うと、若者のくせに分不相応だと批判する。
車や海外旅行などの“おじさんにも分かりやすいモノ”を買わないからといって、若者はみな消費意欲が落ちているという言い方で結論付けるのは、少々安易ではないでしょうか。
―― 数字や消費の実体を、世代が持つ 価値観という“色眼鏡”を通して見てしまっているのですね。
宇:全く同じことが高齢者にも言えます。1980年前後ですと、大ざっぱに定年は55歳が40%、60歳が40%ぐらいで構成されていました。60歳にして隠居という人は少なくなかったのです。しかしいまや65歳で現役も珍しくない。
◆消費の多様化とは「不必要なマス消費」の消失
そうすると、80年代の55歳から65歳ぐらいの人を今の同じ年齢層と比べて、消費パターンが同じとは到底思えないわけです。昔の高齢者が買っていたものを今の50代が買ってない、それは当たり前でしょう。
ここで指摘したいのは、年齢別のデータは、社会構造、世帯構造が変わっていく流れの中では変化するのは当たり前であり、安易に世代の問題にしてはいけないということです。さらに、消費が多様化しているので、個別の品目だけを見て全体を評価するのは、極めて誤解を招きやすいという2つの点です。
―― ある世代が若いころの単なる流行を、現在でも常識として無意識に引きずっているのかもしれません。
宇:バブルぐらいまでは、世代全体が同じ関心を持っていました。同じ商品をみんなが買うことが、ある意味ハッピーだったんでしょう。
昔だったら必ず買っていたけど、今はあまり買わないものの代表に、嫁入り道具があります。実は必要ないけれど無駄に豪華で高価なものです。必要、不必要という価値観ではなく、買わないと恥ずかしいなど、別の理由で買っていました。それから結婚式ですね。お義理でやっていた人は結婚式をしなくなって きていると考えられます。
―― しかし、結婚情報誌によれば、結婚式の費用がどんどん上がっているようですが。
宇:それは、まさに統計のマジックで、「結婚式をした」という条件付きにして統計をとるから、平均的な費用が高くなるのです。たとえばホテルで挙式する人といわゆる「結婚式場」で挙式する人が、1組ずついたとします。費用はホテルが300万円、結婚式場が100万円とすれば、平均費用の統計を取れば 200万円となります。しかし、消費の多様化によって、自分の価値観に基づき選択をするようになれば、お義理で結婚式をしていた人はいっそ式はやらないと選択をし、ホテルで結婚式をするような「こだわりの人」は変わらず結婚式をするでしょう。すると、結婚式の件数は減りますが、ホテルでの結婚式だけになりますので「平均費用」は300万円になります。
このように、過去においてはそれほど意識せずにしていた消費に対し、今の若い人たちはより主体的に判断するようになったということではないでしょ うか。
―― 画一的な価値観が崩壊したのですね。
宇:それが消費の多様化だと思います。逆に、企業の側から言うと売れ筋を見るのは本当に難しくなったと思います。
大量生産でみんなの需要を賄うようなタイプの商売はかなり難しくなってきていると思います。価格が安い、あるいはプリウスのようにエコなどの付加 価値が高いものは支持される。「環境」というのは、みんなが一致できる数少ない問題意識ですからね。
―― だから社会的起業のようなものが 若い世代から支持されるのかもしれませんね。教育、医療、介護、環境など、全員が問題意識を感じているテーマですね。多様化しているからこそ、本当に大事だと言われる、共通のキーワードに集まる。
宇:でも、そういうキーワードで語られるものって企業が大量生産できないものなんです。例えば売れ筋は「介護」と分かっても、それは大量生産できる財ではありません。最終的には人間と人間の関係で提供されるサービスですから、一人のヘルパーが何万人ものお年寄りをいっぺんに介護す るというわけにはいきません。昔は大勢の関心が一致するものが、大量生産できる財だったので非常にうまくいっていた。現在は、みんなの関心が集中するよう なことがまれになってきた上に、一致できるのは大量生産のできないような財ばかりなのです。
携帯電話は消費を圧迫するのか
―― ところで、昔と大きく変わった点 として、携帯電話などの通信料金がかさんで、ほかの消費に回すお金がなくなったという話もあります。
宇:携帯電話にお金をかけているというのは間違いないですね。家計調査では10大費目といって、すべての消費を10個のカテゴリーに分けています。その中で特に減っているのが「食料」と「被服及び履物」です。一方で、最も増えているのが「交通・通信」で、まさしく携帯電話のところが増えています。
「移動電話通信料」の調査が始まった2000年で月2382円だったのが、今は月7675円まで上がっています。平均額は誰も携帯電話を持ってな い世帯も含めてですから、携帯電話を家族全員で持っていればもっと大きな負担となっています。
しかし、携帯電話以外の消費がすべて減っているかといえば、そうではありません。10大費目でみれば「その他の消費支出」も増加しています。ここにはハンドバッグ、理容、美容などが分類されますし、冠婚葬祭も入ります。バッグ、理容、美容、身の回り用品、そうしたものが全般に増えており、家計調査が想定しているような主要な支出のカテゴリーでは押さえきれないところが増えているといえます。その意味で、携帯電話に対する支出が他の消費を圧迫しているというより、単純に消費のパターンが変化してきただけといえます。
また、消費行動の変化という意味で興味深いのは、女性のストッキングの変遷です。バブル期の1988年に登場した「ジェンティルドンナ」という1 万2000円の高級パンストのブランドがあります。ご存知ですか。
―― 知りません…。
宇:バブル期の数年間でストッキングは急激に高級化しました。家計調査によれば、平均な消費者が買う商品の価格である「購入単 価」は、150円から250円ぐらいに上がりました。今では290円ぐらい。実は、ストッキングだけでなく、婦人服もハンドバッグもバブル期に平均価格がものすごく上がっています。言い換えれば、購入単価で見ると、バブル期に女性関係の消費は大きく構造変化をしているのです。
婦人服、大ざっぱに言うと女性用スーツのことですが、このスーツの平均価格を見ると、70年代には1万円強で婦人用のスーツが買えました。それがバブルのころに2万円程度に、バブルの最盛期には2万5000円程度にまで上がりました。その後も2万円程度の水準を維持しています。
このように婦人服については購入単価が上昇し高級化をしてきましたが、支出金額そのものはバブル後に減少してきています。これは、女性が買うスーツの点数の減少によってもたらされています。
1970年代ごろは、女性のスーツの購入数量が平均して年2着ぐらいでした。それが今、0.5着ぐらい。多様な世代・属性を平均した数字ですので 数字自体の解釈は難しいですが、大ざっぱに言って昔に比べると4分の1着、昔4着買っていた人も1着しか買わなくなっている感じです。購入単価は上がった けれども、購入数量が減少したために、支出金額は減ったのです。
スーツを買わなくなったのはなぜか。昔は、女性が社会に出て働く場合はスーツを着なければいけないと思う人が多かったのでしょう。でも今は、女性 が会社に着ていく洋服は、必ずしもスーツではなくてもいい。ジャケットとパンツで構わないわけです。
実際、ジャケットやパンツ(婦人用スラックス)に対しては支出金額も購入数量も上昇しています。スカートよりもパンツのほうが単価は安く、ジャ ケットとパンツの足し算では「婦人服」より安くなります。要するに、働く女性のトータルコーディネートの値段は昔に比べると下がっているのです。
ここから読み取れるのは、スーツが必要なら今もバブル期と同じ価格帯のスーツを買う、スカートもパンツも価格帯が下がったわけではない。単に、普段着るのはスーツではなく、シャツとパンツの方が多くなったという消費行動です。衣料品にお金をかけなくなったのは消費意欲が低下したからではなく、服装 が全般にカジュアル化したからなのです。
ストッキングと男性用ジャケットの価格の推移を見ると…
―― 確かに周囲を見回しても、かちっ としたスーツを着ている女性ばかりではないですね。男性に比べるとカジュアルです。
宇:それに対し、男性のスーツの購入単価を調べると、バブル期にとても上がるのは女性と一緒ですが、バブル期以降、相当下がる。 いかにもバブルなデータが出ています(笑)。バブルを反省しろと言っている人の多くはたぶん男性でしょう。こういうデータを見ると、それも仕方がないな、 男はバブル期、本当に分不相応なことをしていたからな、と思いますね。
こう考えてみると、女性はバブルの時、「ああ、なるほど、本当にいいものってこういうものなのね」と学習した。その後も本当にいいもの、自分にとって必要なものならそれなりのお金を払って買っている。不況になれば、質の低いものを買うのではなく、コーディネートを変えて対応しているのです。一 方、男性はというと、バブル期だけぜいたくをして、バブルが弾けたら、すっかり元に戻ってしまったということでしょうか。
下のグラフをごらん下さい。男性のジャケットと女性のストッキングの価格の推移です。男性ジャケットの価格はバブル期だけ山のようにぼーんと上がって、あとは元に戻っているでしょう。一方、先ほど述べた、ストッキングの価格は上がったままになっていますね。
―― なるほど。映画「バブルへ GO!!〜タイムマシンはドラム式〜」でもありましたね、1万円札を何枚もひらひらさせて、男性たちがタクシーを止めるシーン。当時についてはあんなイメージですか。
宇:バブルというと、女性が扇子を持って「ディスコ」で躍る写真がよく出てきますが、このグラフを見ると、バブルに躍らされていたのは男性でしょうね。一般に男性の消費というのは、極めて景気の影響を受けやすいのです。男性用のシャツの購入単価を見ても、バブルのときは上がって、その後下がり、1997年にかけてまた少し上がるんですが、その後の景気の悪化が深刻化するとものすごく下がる。
―― 男性の肩を持つとすれば、家族がいると、奥さんにお小遣いを減らされたり、自分の被服費を削って奥さんや家族のために使ったんだ、という見方もできますね…。
◆バブルに踊らされる男性、バブルでリテラシー磨いた女性
宇:でも、家族のことを本当に考えているというのなら、バブル期だけやたらと自分のスーツ代が上がる、ということにはならないのではないでしょうか。
―― 確かに、増えた余剰分をスーツな ど自己投資に過剰に使い、家族にはそれほど分配しなかったと言う見方はできるかもしれませんね。
宇:そういうことです。あと男性の方がフォーマルファッションが画一化されているので、コーディネートでの対応というのが難しい側面もあります。景気が悪いというのに、取引先に派手な格好で行くのはまずい、といった事情もあるでしょう。
さらに男性を弁護するなら、AOKIや紳士服のコナカといった紳士服チェーンが登場した影響は大きかったと思います。これらのチェーンは、昔のテーラー物と比べてもさほど質は悪くないはずです。男性のファッションが画一的であることから、流通革命、技術革新による大量生産・大量販売で、同じ品質のものが安く入手できるようになっただけという見方もできます。いずれにしても、男性の消費行動は経済状況に左右されやすいのだと思います。
◆ファッションの消費パターンの変化には盲点が
それから、もう一つ、ファッション関係の消費パターンの変化には大きな盲点があります。先ほども述べましたが、「被服及び履物」が消費全体に占めるシェアは大きく低下しています。1970年代には約10%でしたが、今は約5%まで落ちています。その落ち込みの大きな部分は、実は和服なんです。
―― なるほど。確かに、1970年代 に祖母が毎日着ていた記憶が残っています。10%がこの40年で5%に落ちたところで、高い和服の分がなくなっただけということですね。
宇:1970年頃だと、「被服及び履物」のうち約10%が和服でした。今は2.5%程度で、振り袖など高価なものをたまに買っているか、喪服程度と考えられます。衣料品のカテゴリーに和服が入っているというのは忘れがちですよね。そのため、携帯電話のせいで服を買わなくなったとい う短絡的なストーリーが作られてしまうのだと思います。こういった思い込みをなくすためにも、客観的なデータ観察が重要なのです。
消費のデータを虚心坦懐に見れば、現在の消費を理解するポイントが分かります。それは、若者や高齢者といった世代論や、携帯電話が諸悪の根源だといった議論ではなく、消費の多様化こそが大きな潮流であるとわかります。
―― 今のお話を聞いていて、この春に 同僚とインタビューした仏ロレアルのジャン=ポール・アゴンCEOの言葉を思い出しました。「今の日本ではチャンスだ」と言うのです。日本の消費者の中間層が崩壊し、下と上になっている、ブランド力のあるロレアルは日本で勝負できるからであると。
宇:消費が多様化した社会では、ほとんどの消費者が消費するような定番商品はきわめて稀になります。かといって、消費者がお金を使わなくなったわけではないのです。特定の商品だけに注目すると、買う人、買わない人の大きな差が出ます。化粧品についても、お金を使いたい人と、使いた くない人がはっきり分かれてきたのではないでしょうか。
ただし、消費の多様化を格差問題として理解するのは誤りです。特定の財についての消費を属人的に言ってしまうと、急にすべてが格差の話になってしまうんです。化粧品に関して言えば、例えば10万円のクリームが出たら、たぶん10万円の価値を見極めた人が買うでしょう。それは、お金持ちだから買うの ではなく、その価値が分かる人が買うのです。言い換えれば、化粧品の市場では、消費者が自分の価値観に基づき選択をしているのではないでしょうか。
商品の価値を自分で判断できるということを「消費が成熟している」と定義してもよいと思います。ちゃんと使ってみて、使い心地をきちんと批判する人が化粧品市場での上流であり、消費が多様化した社会で化粧品メーカーがターゲットとすべき消費者なのです。
これは、例えば、エルメスのバッグを買う人にも言えることです。エルメスのバッグを買う人全員が大金持ちかといえば、そうではないでしょう。エルメスのバッグの価値が分かる人が買うのです。高価な化粧品でもブランド品でも、その価値が分かる人は買うし、分からない人やそもそも興味のない人は買わないのです。
◆「成熟した消費者」に向けた商品が必要
―― つまり、日本人の消費のリテラ シーが上がったというか、モノを見極める目が洗練されてきたという側面で捉えることもできる。
宇:ロレアルのCEOが言うのは、化粧品については、日本の市場は消費のリテラシーが育っているから、比較的高額の化粧品でもある程度勝負ができるということでしょうね。
―― 消費者のリテラシーは企業戦略においても重要ですね。その商品に強い関心を持つ「成熟した消費者」に評価されなければ、モノも売れなくなる。ということは、自社のブランドを若者向けなど にレベルダウンして廉価版を出すという発想は、最終的には企業にとってはプラスにはならないということですか。
宇:高級ブランドのセカンドラインのような例ですね。廉価版を出している企業は、そもそも価値の分かる「成熟した消費者」の市場では競合相手に勝てないことを自覚しているか、そもそも「成熟した消費者」が何を求めているのかが分かってないか、だと思います。自社の商品の本当の理解者、すなわち自分がターゲットにしている人たちが何を求めているかが分からないから、何となく廉価版に飛びつく。
―― たとえば今、消費者の価格に対する目が厳しくて、しかも世の中でファストファッションが人気だから、うちのブランドもその路線でいくか、といったような発想ですね。
宇:深く自覚せずに価格帯が下の商品に手を出してしまうわけです。一方でエルメスのような企業は、本当に最先端のファッションリーダー層が何を欲しがっているかが分かっているし、だからこそ自社に強みがあると分かっているからそういうことはしません。この点を見失うと、もはや 「ブランド」ではない。単に、値札の高いものを売っているだけの企業です。
2009年は高級ブランド品の売り上げが米国をはじめ世界全体で落ち込んだそうです。でもエルメスは連結ベースで前年比で4.1%、売り上げを伸ばしている。しかも2009年第4四半期の売り上げは、前年同期比11%増です。
トヨタ自動車のような「何百万台」というような量の展開はできないけれど、十分採算が取れるビジネスをしているわけです。
―― 日本企業は今、大量生産が利くアジアなどの新興国における中間層を狙おうと意気込んでいる状態ですが、大量生産モデルの戦略としては、新興国に向かうのは間違いではないですよね。
宇:最後まで「マス」を対象として生きていこうとするならば、間違いではないでしょうね。ところで、これまで言ってきたことは、マスメディアについても言えます。
マスメディアは、国内で勝負し続けなければいけませんよね。今後、知識層をうならせるコンテンツ作りが出来るかどうか。情報市場における「最上の層」がどのような思考をするのか理解し、その目線での批判に耐えなければなりません。
iPad(アイパッド)やkindle(キンドル)などが出て来て、紙の「本離れ」は進んでいますが、「活字離れ」はしていないと思いますよ。本が売れなくなったといっても、売れなくなった本の中には「デートマニュアル」といった、ネットで代替できるような内容の薄いものも1冊としてカウントされてきたわけですから、それが減るのは当たり前です。「成熟した情報化社会」では、本当に質の高い本やメディアの意義がますます問われるようになると思います。
その後、有効活用されておらず、管理人としては、今後も盛り上げていくには、
どうすればいいか考えた結果、まずはマーケティングに関する話題を掲載していこうと
思いました。今後、随時、皆様にとって有益となるような事柄を掲載しようと思います。
「世代論」で語る消費分析のワナ
宇南山卓・神戸大学准教授に消費データの正しい見方を聞く(日経ビジネスより抜粋)
宇南山 卓(うなやま・たかし)氏
神戸大学大学院経済学研究科准教授。1997年東京大学経済学部卒、99年同大学大学院修士課程修了、2004年同大学博士(経済学)。慶應義塾大学、京都大学講師を経て現職。専門は、日本経済論。現在、日本経済研究センター特別研究員・経済産業研究所ファカルティーフェローとして、少子化と女性労働について研究している。日本経済研究センターでは「若手研究者による政策提言プロジェクト」に参加、経済産業研究所では吉川洋東京大学教授の研究プロジェクト 「少子高齢化と日本経済」のサブリーダー。
―― 現代の若者はお金を使わない、消費に魅力を感じていないと最近、よく言われます。確かに自動車は以前のように若者の憧れではなくなりましたし、服装もファストファッション化しています。
宇:若者の消費に関するデータを見る場合には、実は色々と気をつけなければならない点が
あります。例えば、総務省統計局が公表している「家計調査」を使って若者の消費を調べようとすれば、年齢階級別のデータを使います。年齢階級は、世帯主の年齢で見ます。
そのため25歳の若者の消費を見ようとすれば、25歳が世帯主となっている世帯の消費を
見るのです。昔は25歳なら、多くの人が結婚していましたから、25歳が世帯主の世帯の消費
を見れば、その年齢階級の若者がどんなものを買っているかが分かりました。
ところが今は、25歳ですと独身で、親元に住んでいたり一人暮らしをしている人が多いでしょう。親は恐らく50歳ぐらいです。親と同居していれば、25歳の消費でも、50歳の消費としてカウントされてしまうのです。
経済学者は、世帯全体の消費から若者の消費だけを抜き出そうと頑張るのですが、若者の消費の現状はこうだと断定するのは、かなり難しいのが実情です。
さらに、家計調査では基本的に「2人以上の世帯」の数値が注目されます。単身世帯も調査していますが、一人暮らしの若者は調査が困難であり、若者のサンプルの質は十分とはいえません。その意味で、結婚をしてないと、そもそも統計から漏れている可能性が高いのです。
◆昔の25歳は世帯主だった
また、消費の実態についても、昔は20代後半〜30代前半なら、大体子供がいました。若い人とはそういう人たちが中心だったのです。現在の結婚をしていない25歳と、昔の結婚をしていた25歳では、消費の仕方が違います。さらに、独身者だけを比較するとしても、高学歴の人ほど結婚が遅くなっている傾向がありますから、昔の独身者と今の独身者では学歴構成は大きく違います。つまり、昔と今の若者の消費行動の違いを、単純に平均によってとらえるのは適ではありません。
―― 社会の変化を多面的に念頭に置か なければ、たとえデータを基にしたとしてもおかしな分析になってしまうのですね。
宇:そもそも「若者は消費をしない」と言う時、それが具体的に何を意味しているのかが重要です。平均としては(バブル期ごろに比べて)自動車を買わないとか、お酒を飲まないという点は確かにあります。しかし、もう1つのキーワードとして「一点豪華主義」に注目すると、より大きな社会の変化と関係づけることができます。その変化とは、消費の多様化です。
「現在の若者は普段金を使わないくせに、一点豪華主義でブランド物を買う」という言い方がされたりします。これは一見もっともらしいですが、暗黙のうちに消費「すべき」モノを想定しています。一点豪華主義という感覚は、昔はみんなが欲しがるもの、買わなければいけないものは大体同じだったことの裏返しだと思います。
例えば都市部では、そこそこの給料をもらえる年齢になったら200〜300万円の自動車を買うという考え方が、暗黙の決まりみたいなものでした。でも、本当に20代後半ぐらいの人全般にとって自動車が、200万円という大金を出す価値があったかというと、恐らくあまりなかったでしょう。かなりの贅沢品ですよね。でも昔はみんなが買うものだったから、一点豪華と言われなかった。でも今、若者がプリウスを買えば、同世代からは一点豪華主義的な消費と見なされてしまうでしょうね。
スカイラインは常識で、シャネルは贅沢?
―― なるほど。
宇:みんなと同じものを買わないと目立って見えるだけで、どこかにお金を集中的に使うのは昔の人も今の人も一緒です。ただ、消費 が多様化した社会では、集中的に使うものが他の人と一致しない可能性が高いのです。他人とたまたま一致しているか、一致してないかで与える印象が違いま す。
昔は若者が日産のスカイラインを買っても、分不相応だと怒る大人はいなくて、「それくらいの年になれば誰でも車は欲しいよね」と言われたでしょう。それが今、自動車なんていらないと言うと、「最近の若者は消費に興味がない、困ったものだ」と論評される。しかし一方で「私、(車は買わないけど) シャネルのバッグ買いました」と言うと、若者のくせに分不相応だと批判する。
車や海外旅行などの“おじさんにも分かりやすいモノ”を買わないからといって、若者はみな消費意欲が落ちているという言い方で結論付けるのは、少々安易ではないでしょうか。
―― 数字や消費の実体を、世代が持つ 価値観という“色眼鏡”を通して見てしまっているのですね。
宇:全く同じことが高齢者にも言えます。1980年前後ですと、大ざっぱに定年は55歳が40%、60歳が40%ぐらいで構成されていました。60歳にして隠居という人は少なくなかったのです。しかしいまや65歳で現役も珍しくない。
◆消費の多様化とは「不必要なマス消費」の消失
そうすると、80年代の55歳から65歳ぐらいの人を今の同じ年齢層と比べて、消費パターンが同じとは到底思えないわけです。昔の高齢者が買っていたものを今の50代が買ってない、それは当たり前でしょう。
ここで指摘したいのは、年齢別のデータは、社会構造、世帯構造が変わっていく流れの中では変化するのは当たり前であり、安易に世代の問題にしてはいけないということです。さらに、消費が多様化しているので、個別の品目だけを見て全体を評価するのは、極めて誤解を招きやすいという2つの点です。
―― ある世代が若いころの単なる流行を、現在でも常識として無意識に引きずっているのかもしれません。
宇:バブルぐらいまでは、世代全体が同じ関心を持っていました。同じ商品をみんなが買うことが、ある意味ハッピーだったんでしょう。
昔だったら必ず買っていたけど、今はあまり買わないものの代表に、嫁入り道具があります。実は必要ないけれど無駄に豪華で高価なものです。必要、不必要という価値観ではなく、買わないと恥ずかしいなど、別の理由で買っていました。それから結婚式ですね。お義理でやっていた人は結婚式をしなくなって きていると考えられます。
―― しかし、結婚情報誌によれば、結婚式の費用がどんどん上がっているようですが。
宇:それは、まさに統計のマジックで、「結婚式をした」という条件付きにして統計をとるから、平均的な費用が高くなるのです。たとえばホテルで挙式する人といわゆる「結婚式場」で挙式する人が、1組ずついたとします。費用はホテルが300万円、結婚式場が100万円とすれば、平均費用の統計を取れば 200万円となります。しかし、消費の多様化によって、自分の価値観に基づき選択をするようになれば、お義理で結婚式をしていた人はいっそ式はやらないと選択をし、ホテルで結婚式をするような「こだわりの人」は変わらず結婚式をするでしょう。すると、結婚式の件数は減りますが、ホテルでの結婚式だけになりますので「平均費用」は300万円になります。
このように、過去においてはそれほど意識せずにしていた消費に対し、今の若い人たちはより主体的に判断するようになったということではないでしょ うか。
―― 画一的な価値観が崩壊したのですね。
宇:それが消費の多様化だと思います。逆に、企業の側から言うと売れ筋を見るのは本当に難しくなったと思います。
大量生産でみんなの需要を賄うようなタイプの商売はかなり難しくなってきていると思います。価格が安い、あるいはプリウスのようにエコなどの付加 価値が高いものは支持される。「環境」というのは、みんなが一致できる数少ない問題意識ですからね。
―― だから社会的起業のようなものが 若い世代から支持されるのかもしれませんね。教育、医療、介護、環境など、全員が問題意識を感じているテーマですね。多様化しているからこそ、本当に大事だと言われる、共通のキーワードに集まる。
宇:でも、そういうキーワードで語られるものって企業が大量生産できないものなんです。例えば売れ筋は「介護」と分かっても、それは大量生産できる財ではありません。最終的には人間と人間の関係で提供されるサービスですから、一人のヘルパーが何万人ものお年寄りをいっぺんに介護す るというわけにはいきません。昔は大勢の関心が一致するものが、大量生産できる財だったので非常にうまくいっていた。現在は、みんなの関心が集中するよう なことがまれになってきた上に、一致できるのは大量生産のできないような財ばかりなのです。
携帯電話は消費を圧迫するのか
―― ところで、昔と大きく変わった点 として、携帯電話などの通信料金がかさんで、ほかの消費に回すお金がなくなったという話もあります。
宇:携帯電話にお金をかけているというのは間違いないですね。家計調査では10大費目といって、すべての消費を10個のカテゴリーに分けています。その中で特に減っているのが「食料」と「被服及び履物」です。一方で、最も増えているのが「交通・通信」で、まさしく携帯電話のところが増えています。
「移動電話通信料」の調査が始まった2000年で月2382円だったのが、今は月7675円まで上がっています。平均額は誰も携帯電話を持ってな い世帯も含めてですから、携帯電話を家族全員で持っていればもっと大きな負担となっています。
しかし、携帯電話以外の消費がすべて減っているかといえば、そうではありません。10大費目でみれば「その他の消費支出」も増加しています。ここにはハンドバッグ、理容、美容などが分類されますし、冠婚葬祭も入ります。バッグ、理容、美容、身の回り用品、そうしたものが全般に増えており、家計調査が想定しているような主要な支出のカテゴリーでは押さえきれないところが増えているといえます。その意味で、携帯電話に対する支出が他の消費を圧迫しているというより、単純に消費のパターンが変化してきただけといえます。
また、消費行動の変化という意味で興味深いのは、女性のストッキングの変遷です。バブル期の1988年に登場した「ジェンティルドンナ」という1 万2000円の高級パンストのブランドがあります。ご存知ですか。
―― 知りません…。
宇:バブル期の数年間でストッキングは急激に高級化しました。家計調査によれば、平均な消費者が買う商品の価格である「購入単 価」は、150円から250円ぐらいに上がりました。今では290円ぐらい。実は、ストッキングだけでなく、婦人服もハンドバッグもバブル期に平均価格がものすごく上がっています。言い換えれば、購入単価で見ると、バブル期に女性関係の消費は大きく構造変化をしているのです。
婦人服、大ざっぱに言うと女性用スーツのことですが、このスーツの平均価格を見ると、70年代には1万円強で婦人用のスーツが買えました。それがバブルのころに2万円程度に、バブルの最盛期には2万5000円程度にまで上がりました。その後も2万円程度の水準を維持しています。
このように婦人服については購入単価が上昇し高級化をしてきましたが、支出金額そのものはバブル後に減少してきています。これは、女性が買うスーツの点数の減少によってもたらされています。
1970年代ごろは、女性のスーツの購入数量が平均して年2着ぐらいでした。それが今、0.5着ぐらい。多様な世代・属性を平均した数字ですので 数字自体の解釈は難しいですが、大ざっぱに言って昔に比べると4分の1着、昔4着買っていた人も1着しか買わなくなっている感じです。購入単価は上がった けれども、購入数量が減少したために、支出金額は減ったのです。
スーツを買わなくなったのはなぜか。昔は、女性が社会に出て働く場合はスーツを着なければいけないと思う人が多かったのでしょう。でも今は、女性 が会社に着ていく洋服は、必ずしもスーツではなくてもいい。ジャケットとパンツで構わないわけです。
実際、ジャケットやパンツ(婦人用スラックス)に対しては支出金額も購入数量も上昇しています。スカートよりもパンツのほうが単価は安く、ジャ ケットとパンツの足し算では「婦人服」より安くなります。要するに、働く女性のトータルコーディネートの値段は昔に比べると下がっているのです。
ここから読み取れるのは、スーツが必要なら今もバブル期と同じ価格帯のスーツを買う、スカートもパンツも価格帯が下がったわけではない。単に、普段着るのはスーツではなく、シャツとパンツの方が多くなったという消費行動です。衣料品にお金をかけなくなったのは消費意欲が低下したからではなく、服装 が全般にカジュアル化したからなのです。
ストッキングと男性用ジャケットの価格の推移を見ると…
―― 確かに周囲を見回しても、かちっ としたスーツを着ている女性ばかりではないですね。男性に比べるとカジュアルです。
宇:それに対し、男性のスーツの購入単価を調べると、バブル期にとても上がるのは女性と一緒ですが、バブル期以降、相当下がる。 いかにもバブルなデータが出ています(笑)。バブルを反省しろと言っている人の多くはたぶん男性でしょう。こういうデータを見ると、それも仕方がないな、 男はバブル期、本当に分不相応なことをしていたからな、と思いますね。
こう考えてみると、女性はバブルの時、「ああ、なるほど、本当にいいものってこういうものなのね」と学習した。その後も本当にいいもの、自分にとって必要なものならそれなりのお金を払って買っている。不況になれば、質の低いものを買うのではなく、コーディネートを変えて対応しているのです。一 方、男性はというと、バブル期だけぜいたくをして、バブルが弾けたら、すっかり元に戻ってしまったということでしょうか。
下のグラフをごらん下さい。男性のジャケットと女性のストッキングの価格の推移です。男性ジャケットの価格はバブル期だけ山のようにぼーんと上がって、あとは元に戻っているでしょう。一方、先ほど述べた、ストッキングの価格は上がったままになっていますね。
―― なるほど。映画「バブルへ GO!!〜タイムマシンはドラム式〜」でもありましたね、1万円札を何枚もひらひらさせて、男性たちがタクシーを止めるシーン。当時についてはあんなイメージですか。
宇:バブルというと、女性が扇子を持って「ディスコ」で躍る写真がよく出てきますが、このグラフを見ると、バブルに躍らされていたのは男性でしょうね。一般に男性の消費というのは、極めて景気の影響を受けやすいのです。男性用のシャツの購入単価を見ても、バブルのときは上がって、その後下がり、1997年にかけてまた少し上がるんですが、その後の景気の悪化が深刻化するとものすごく下がる。
―― 男性の肩を持つとすれば、家族がいると、奥さんにお小遣いを減らされたり、自分の被服費を削って奥さんや家族のために使ったんだ、という見方もできますね…。
◆バブルに踊らされる男性、バブルでリテラシー磨いた女性
宇:でも、家族のことを本当に考えているというのなら、バブル期だけやたらと自分のスーツ代が上がる、ということにはならないのではないでしょうか。
―― 確かに、増えた余剰分をスーツな ど自己投資に過剰に使い、家族にはそれほど分配しなかったと言う見方はできるかもしれませんね。
宇:そういうことです。あと男性の方がフォーマルファッションが画一化されているので、コーディネートでの対応というのが難しい側面もあります。景気が悪いというのに、取引先に派手な格好で行くのはまずい、といった事情もあるでしょう。
さらに男性を弁護するなら、AOKIや紳士服のコナカといった紳士服チェーンが登場した影響は大きかったと思います。これらのチェーンは、昔のテーラー物と比べてもさほど質は悪くないはずです。男性のファッションが画一的であることから、流通革命、技術革新による大量生産・大量販売で、同じ品質のものが安く入手できるようになっただけという見方もできます。いずれにしても、男性の消費行動は経済状況に左右されやすいのだと思います。
◆ファッションの消費パターンの変化には盲点が
それから、もう一つ、ファッション関係の消費パターンの変化には大きな盲点があります。先ほども述べましたが、「被服及び履物」が消費全体に占めるシェアは大きく低下しています。1970年代には約10%でしたが、今は約5%まで落ちています。その落ち込みの大きな部分は、実は和服なんです。
―― なるほど。確かに、1970年代 に祖母が毎日着ていた記憶が残っています。10%がこの40年で5%に落ちたところで、高い和服の分がなくなっただけということですね。
宇:1970年頃だと、「被服及び履物」のうち約10%が和服でした。今は2.5%程度で、振り袖など高価なものをたまに買っているか、喪服程度と考えられます。衣料品のカテゴリーに和服が入っているというのは忘れがちですよね。そのため、携帯電話のせいで服を買わなくなったとい う短絡的なストーリーが作られてしまうのだと思います。こういった思い込みをなくすためにも、客観的なデータ観察が重要なのです。
消費のデータを虚心坦懐に見れば、現在の消費を理解するポイントが分かります。それは、若者や高齢者といった世代論や、携帯電話が諸悪の根源だといった議論ではなく、消費の多様化こそが大きな潮流であるとわかります。
―― 今のお話を聞いていて、この春に 同僚とインタビューした仏ロレアルのジャン=ポール・アゴンCEOの言葉を思い出しました。「今の日本ではチャンスだ」と言うのです。日本の消費者の中間層が崩壊し、下と上になっている、ブランド力のあるロレアルは日本で勝負できるからであると。
宇:消費が多様化した社会では、ほとんどの消費者が消費するような定番商品はきわめて稀になります。かといって、消費者がお金を使わなくなったわけではないのです。特定の商品だけに注目すると、買う人、買わない人の大きな差が出ます。化粧品についても、お金を使いたい人と、使いた くない人がはっきり分かれてきたのではないでしょうか。
ただし、消費の多様化を格差問題として理解するのは誤りです。特定の財についての消費を属人的に言ってしまうと、急にすべてが格差の話になってしまうんです。化粧品に関して言えば、例えば10万円のクリームが出たら、たぶん10万円の価値を見極めた人が買うでしょう。それは、お金持ちだから買うの ではなく、その価値が分かる人が買うのです。言い換えれば、化粧品の市場では、消費者が自分の価値観に基づき選択をしているのではないでしょうか。
商品の価値を自分で判断できるということを「消費が成熟している」と定義してもよいと思います。ちゃんと使ってみて、使い心地をきちんと批判する人が化粧品市場での上流であり、消費が多様化した社会で化粧品メーカーがターゲットとすべき消費者なのです。
これは、例えば、エルメスのバッグを買う人にも言えることです。エルメスのバッグを買う人全員が大金持ちかといえば、そうではないでしょう。エルメスのバッグの価値が分かる人が買うのです。高価な化粧品でもブランド品でも、その価値が分かる人は買うし、分からない人やそもそも興味のない人は買わないのです。
◆「成熟した消費者」に向けた商品が必要
―― つまり、日本人の消費のリテラ シーが上がったというか、モノを見極める目が洗練されてきたという側面で捉えることもできる。
宇:ロレアルのCEOが言うのは、化粧品については、日本の市場は消費のリテラシーが育っているから、比較的高額の化粧品でもある程度勝負ができるということでしょうね。
―― 消費者のリテラシーは企業戦略においても重要ですね。その商品に強い関心を持つ「成熟した消費者」に評価されなければ、モノも売れなくなる。ということは、自社のブランドを若者向けなど にレベルダウンして廉価版を出すという発想は、最終的には企業にとってはプラスにはならないということですか。
宇:高級ブランドのセカンドラインのような例ですね。廉価版を出している企業は、そもそも価値の分かる「成熟した消費者」の市場では競合相手に勝てないことを自覚しているか、そもそも「成熟した消費者」が何を求めているのかが分かってないか、だと思います。自社の商品の本当の理解者、すなわち自分がターゲットにしている人たちが何を求めているかが分からないから、何となく廉価版に飛びつく。
―― たとえば今、消費者の価格に対する目が厳しくて、しかも世の中でファストファッションが人気だから、うちのブランドもその路線でいくか、といったような発想ですね。
宇:深く自覚せずに価格帯が下の商品に手を出してしまうわけです。一方でエルメスのような企業は、本当に最先端のファッションリーダー層が何を欲しがっているかが分かっているし、だからこそ自社に強みがあると分かっているからそういうことはしません。この点を見失うと、もはや 「ブランド」ではない。単に、値札の高いものを売っているだけの企業です。
2009年は高級ブランド品の売り上げが米国をはじめ世界全体で落ち込んだそうです。でもエルメスは連結ベースで前年比で4.1%、売り上げを伸ばしている。しかも2009年第4四半期の売り上げは、前年同期比11%増です。
トヨタ自動車のような「何百万台」というような量の展開はできないけれど、十分採算が取れるビジネスをしているわけです。
―― 日本企業は今、大量生産が利くアジアなどの新興国における中間層を狙おうと意気込んでいる状態ですが、大量生産モデルの戦略としては、新興国に向かうのは間違いではないですよね。
宇:最後まで「マス」を対象として生きていこうとするならば、間違いではないでしょうね。ところで、これまで言ってきたことは、マスメディアについても言えます。
マスメディアは、国内で勝負し続けなければいけませんよね。今後、知識層をうならせるコンテンツ作りが出来るかどうか。情報市場における「最上の層」がどのような思考をするのか理解し、その目線での批判に耐えなければなりません。
iPad(アイパッド)やkindle(キンドル)などが出て来て、紙の「本離れ」は進んでいますが、「活字離れ」はしていないと思いますよ。本が売れなくなったといっても、売れなくなった本の中には「デートマニュアル」といった、ネットで代替できるような内容の薄いものも1冊としてカウントされてきたわけですから、それが減るのは当たり前です。「成熟した情報化社会」では、本当に質の高い本やメディアの意義がますます問われるようになると思います。
|
|
|
|
|
|
|
|
白石善章ゼミ 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
白石善章ゼミのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 広島東洋カープ
- 55345人
- 2位
- mixi バスケ部
- 37848人
- 3位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37151人