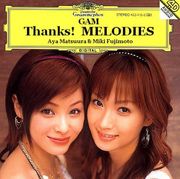「ギャグ100回」のアナリーゼを行います。
長くなるので、新しくトピ立てました。すみません。
「ギャグ100回分愛してください」は、シンプルさと遊び心、そして構成力において、近年のつんく氏の仕事の中でも注目に値するものです。
まず注目すべきは、チープなサウンドに満ちたイントロに続いて歌われる、「ソド ソド」という、人をくったような冒頭。
しかしこれは、例えばベートーヴェンが「運命」においてまさに当時としては人をくったように「運命のテーマ」を示したことに似ています。
そう、これは、この楽曲における、メインテーマの提示なのです。
しかしこの時点では、このテーマが一体何を示すのか、わかりません。
なお、この楽曲では他に「ソラシド」というのも出てきます。
これら2つの階名唱法は、この楽曲の調性である「イ長調」に適合させた、「移動ド」によるものです。
絶対音感が強く支配する僕にとっては、この移動ドでの提示はちょっと違和感があるのですが、このような手法については、ルチアーノ・ベリオの「シンフォニア」第3楽章が、先行例として有名です。(マーラーの2番に乗せて様々なクラシック名曲コラージュが炸裂する、あの有名な部分です。)あの曲も移動ドで階名唱法、というのが出てきます。(つんく氏は、さすがにこれを意識したわけではないでしょうけど。)
なお、本稿は、便宜上、イ長調の実音ではなく、この移動ドによる階名によって全て表記します。
そして本稿の主要な命題は、この「ソド ソド」と、「ソラシド」をめぐる考察です。とりわけ、「ソラシド」が意味するものを解き明かす道程です。
さて、「ソド ソド」に続く
「好きなんだ 好きなんだっけ? 好きか聞かせて」については、
大胆にも、「ドミソ」のみによる旋律構成が行われています。
「ソミド ド ソミド ド ド ソミド ド ド シ ド」
「聞かせて」以外は「ドミソ」ばかりなのです。オクターヴ跳躍を含むこの、跳躍音形で統一された旋律。
この旋律は、その構成音の大胆さもさることながら、リズムの構造も注目に価します。
「好き」という言葉をとりまく、乙女心の変化を、それぞれに異なる拍を当てはめることによって、絶妙に描き出しています。
3回の「好き」の変化は、
1)好き|なんだ(「好き」がアウフタクト、「なんだ」が1拍目)
2)好きなん|だっけ?(「好き」が3拍目、「だっけ?」が1拍目)
3)好きか|聞かせて(「好き」が3拍目、「聞かせて」が1拍目、
しかも、これまでは八分音符のリズムでドミソのみだったのが、
四分音符のリズムでドドシド、となる。)
・・・となっていますが、この、シンコペーションを用いた心情変化の描出は、後で「好き」を連呼するときに応用されます。
そして、続いて入る合いの手「Do you love me?」は、本来のイントネーションを無視した下行する「ソソソド」で受けています。
つまり、上行する「ソド ソド」で始められ、下行する「ソソソド」で締める、という方法で、この冒頭のメロディをまとめ、そしてこのメロディが、ドミソの跳躍音形のみで構成されていることを強調しているわけです。
なお、この部分全体は、いわゆるAメロといわれる部分に相当しますが、サビに匹敵する強いインパクトを持ち、極めて個性的な部分になっているため、この楽曲全体の最後にも配置されております。
さて、このAメロは、もう1度繰り返されます。
「言わないんだ・・・」の部分です。これは全く上記と同様ですが、問題は、最後の「ソラシド」という受けです。
なぜこれが、その前の「Do you love me?」と同様の「ソソソド」ではなく、「ソラシド」であるべきなのか、ということを、後で考察したいと思います。
Aメロの第2部分については後述することにして、ここではまず、「ソド」の構成を解明します。
Bメロ(「すんごい話題です」以後)では、これまで細かいリズムが主体だった中、やや引き伸ばされつつも細かい動きを含む順次進行のメロディーが主体になります。
そして他愛もない表現「すんごい話題です このケーキ屋さん」の中の「この」の部分において、「ソド」という音程が示唆されます。
ここではまだ、他愛もない部分に用いられているだけですが、続いて「ずっとあなたかな? かも」という、心情吐露の部分につながり、その「かも」という言葉は、上記の「この」の部分に相当する、つまり本来なら「ソド」という音程が当てはまるはずなわけですが、しかしながら、ここでは、わざと音程をはぐらかしているわけです。
(なお、このように、歌う旋律の中に、リズムは確定して語るようなニュアンスを指示する手法は、シェーンベルクが「月に憑かれたピエロ」において導入した「シュプレヒシュティンメ」といわれる手法であります。)
2回目の「かも」は、今度は音程が明確に歌われます。しかし、「ソド」ではなく、「シド」という音程が当てられています。
そして、サビに入ります。サビの構造は後述しますが、ここで注目すべきなのは、「モリモリ食べて」における、「ドドレミラ〜ミレ」という、4度跳躍によって、この楽曲の最高音(嗣永・夏焼・菅谷のいずれもが頭声・ファルセットによって歌唱しています)に到達します。
なぜわざわざファルセットを用いてまで4度の跳躍をするのでしょうか。
(もちろん、彼女たちの声の魅力を引き出す、ということでもありますが、)それは、この4度跳躍こそが、テーマである「ソド」と同じ音程であるからです。
そして続く「かっこよく愛してね」の「てね」において、まずは明確に「ソド」が当てはめられます。
そして、「世界で一番好き」の「好き」で、再度「ソド」が当てはめられ、ここにきて遂に、「好き」と「ソド」が結びつきます。
そしてそのことを強調すべく、リフレインされます。
最後には、「好き 好き」の連呼。
そしてこれは、冒頭の「ソド ソド」と完全に一致します。
そう、「ソド」は、「好き」のテーマだったわけです。
・・・つまり、楽曲冒頭の「ソド ソド」には、まだ自分の「好き」という気持ちをはっきり認識していない少女が、そのことの照れ隠しとして階名唱法によって歌う、という暗喩があるわけです。
この楽曲の流れは、その「ソド」という音程が、徐々に明確に「好き」という気持ちに結びついていく過程なのです。
とりわけ、「かも」の音程をわざとはぐらかすあたりは、一見、つんく氏のいつもの遊びと映りますが、そうとだけ受け取ってはいけません。
ここで「ソド」を明示しないことによって、サビの最後にようやく「好き」と自覚するに至る構成を実現しているのですから。
(2回目の「かも」も、「ソド」ではなく「シド」にして、わざと音程を変更している。)
・・・さて、ここまでの分析は、ともすれば言わずもがな、気付かれている方も多かろうと思います。
しかしここで我々は、「ソラシド」の謎に立ち向かわなければなりません。
話は、Aメロの途中に戻ります。
なぜ、「ソラシド」が「Do you love me?」と同様の「ソソソド」ではなく、「ソラシド」であるべきなのか。
・・・それは、後続する部分が、今度は全て順次進行によって構成されているからではないか、と思うのです。
まずそのことを確認します。
「ことばづかい」「なんとかして」「なおさないと」「いけません」
「ドドドシラソ」「ソソソファミ」「レレレドレミ」「ソソラシ」
・・・Aメロ冒頭がドミソばかりで構成されているのに対し、今度は見事に、全てが順次進行になっています。
なお、「いけません」から次につながるところに、「ソソラシド」という流れも存在しています。
好きかどうか言ってくれない彼に、無邪気にドミソの音程で気持ちを問う。
しかし、ここで反省の自問自答を始めます。
そのきっかけが「ソラシド」という順次進行であり、それによって気持ちを鎮めて、順次進行によって、きちんと内省する心情を描いているわけです。
つまり、Aメロの2つの部分は、ドミソの跳躍音形による「好き」という気持ちの確認と、順次進行の音形による「自問自答」によって構築されており、そのことを分節する鍵として、「ソド」と「ソラシド」が階名で表現されている、ということになります。
「ソド」が「好き」に結びつく構成は明白ですが、「ソラシド」がそういう役割を演じていることは、「好き」のように明示されてはいません。
しかし、ここに見てきたように、楽曲の音程構成と結び付けられていることは明白なのです。
そして、Bメロからサビへの展開は、それら2つの要素、即ち「跳躍進行」と「順次進行」が絶妙に配されながら、最後の「好き」の連呼に向かって収斂していく過程なのです。
まずはBメロ。これは、前述のように、順次進行のラインに「ソド」が介入する構成になっています。
「好き」という気持ちの高揚と、他愛もない日常。そのはざまで揺れ動く心情の中に、サビに向かって「かも」と、気持ちの自覚に向かいます。(でもここではまだ音程が明示されません。)
そしてサビ。これは、実はAメロにおける順次進行部分を、3度高めたものによって始められます。
「ド ド ドシラソ」→「ミ ミ ミレドシ」
そして、その後は跳躍進行と順次進行をうまく配置しながら進みますが、前述のように、ファルセットへの4度跳躍なども経て、最後の「好き」につなげます。
このように見れば、跳躍進行と順次進行の分節と融合の絶妙な配列によって、心情の変化と密接につながっていき、最後の「ソド=好き」に到達する、という構成が、「ソド」と「ソラシド」という、階名唱法によって暗示されていることがお判り頂けることと思います。
しかも、ここでは、作曲家の遊びとしての「暗示」なのではなく、少女の気恥ずかしさ、照れ隠しの心情として階名唱法を用いるという、表現意図をも実現したリアリゼーションとなっているわけです。
なお、音程はぐらかしは、「のにゅ」においては、2度ともに適用されています。「かも」では「好き」のはぐらかしだったのに対し、ここでは、ジレンマと、いたたまれなさの表現として、「好き」を敢えて異化するわけです。
ちなみに、言うまでもないことですが、このような、語尾を拾う手法
「克服だわ(だわだわ)」「駆けつけるわ(るわるわ)」
「ずっと居たいのに(のにゅ。のにゅ。)」
・・・については、「乙女パスタ」以来のつんく氏のお家芸ですが、ここでは、そのエスカレートぶり(のに→のにゅ。ってwww)が興味深いです。
つまりこれは、上記のような心情変化、及び音程はぐらかしの構造と、密接に結びついた「エスカレート」なのです。
また、ケーキ屋のマロングラッセと、受験生にラッセララッセラ、というのは、いかにもこじつけめいた押韻ですが、このような強引さも、「Loveマシーン」の「夫婦」以来のつんく氏のお家芸です。
「ギャグ100回分愛してください」という、ぶっとんだ命名が方向付けるように、この楽曲の珍妙なアレンジともあいまって、全編に笑いの要素をちりばめています。
しかしこれは、この主人公の、恋愛に対峙する微妙な心情を象徴しています。
これが、この楽曲の原型とも言える「ちょこっとLove」であれば、恋愛よりも家族を大切にしてしまう、という年齢設定であったわけですが、ここでは、もう少し大人、でもまだ子供、という、今のベリーの平均的年齢を前提にしているわけです。
最後に、桃子が「この瞬間が」で止まる部分。
このような、突如ブレイクを挿入する手法も、つんく氏のお家芸ですが、この感動的な「間」は何でしょう。
思えば、このような「間」の効果は、クラシック名曲の様々な場面で確認できることです。それこそ、「運命」の第1楽章にも、予想を裏切る間が仕組まれている場所がありますが、この楽曲のテーマ「ソド」の構成法といい、この「間」の手法といい、ひょっとすると、「題名のない音楽会」で「運命」を振った経験が、活かされているのかも、というのは、うがった見方でしょうか。
そして「ソド」の振り付け。
この、手をカクっと動かす振りは、以前、24時間テレビでモーニング娘。が「Loveマシーン」を手話で踊ったときのことを思い出します。
しかし、当コミュをご覧の皆さんであれば、更に、コダーイが実践した、ハンドサインによる音程教授メソッドを想起することでしょう。
「ソド」のハンドサインが、実は「好き」を示しているとしたら。。。
そんな、メタファーも含まれているのかもしれません。
長くなるので、新しくトピ立てました。すみません。
「ギャグ100回分愛してください」は、シンプルさと遊び心、そして構成力において、近年のつんく氏の仕事の中でも注目に値するものです。
まず注目すべきは、チープなサウンドに満ちたイントロに続いて歌われる、「ソド ソド」という、人をくったような冒頭。
しかしこれは、例えばベートーヴェンが「運命」においてまさに当時としては人をくったように「運命のテーマ」を示したことに似ています。
そう、これは、この楽曲における、メインテーマの提示なのです。
しかしこの時点では、このテーマが一体何を示すのか、わかりません。
なお、この楽曲では他に「ソラシド」というのも出てきます。
これら2つの階名唱法は、この楽曲の調性である「イ長調」に適合させた、「移動ド」によるものです。
絶対音感が強く支配する僕にとっては、この移動ドでの提示はちょっと違和感があるのですが、このような手法については、ルチアーノ・ベリオの「シンフォニア」第3楽章が、先行例として有名です。(マーラーの2番に乗せて様々なクラシック名曲コラージュが炸裂する、あの有名な部分です。)あの曲も移動ドで階名唱法、というのが出てきます。(つんく氏は、さすがにこれを意識したわけではないでしょうけど。)
なお、本稿は、便宜上、イ長調の実音ではなく、この移動ドによる階名によって全て表記します。
そして本稿の主要な命題は、この「ソド ソド」と、「ソラシド」をめぐる考察です。とりわけ、「ソラシド」が意味するものを解き明かす道程です。
さて、「ソド ソド」に続く
「好きなんだ 好きなんだっけ? 好きか聞かせて」については、
大胆にも、「ドミソ」のみによる旋律構成が行われています。
「ソミド ド ソミド ド ド ソミド ド ド シ ド」
「聞かせて」以外は「ドミソ」ばかりなのです。オクターヴ跳躍を含むこの、跳躍音形で統一された旋律。
この旋律は、その構成音の大胆さもさることながら、リズムの構造も注目に価します。
「好き」という言葉をとりまく、乙女心の変化を、それぞれに異なる拍を当てはめることによって、絶妙に描き出しています。
3回の「好き」の変化は、
1)好き|なんだ(「好き」がアウフタクト、「なんだ」が1拍目)
2)好きなん|だっけ?(「好き」が3拍目、「だっけ?」が1拍目)
3)好きか|聞かせて(「好き」が3拍目、「聞かせて」が1拍目、
しかも、これまでは八分音符のリズムでドミソのみだったのが、
四分音符のリズムでドドシド、となる。)
・・・となっていますが、この、シンコペーションを用いた心情変化の描出は、後で「好き」を連呼するときに応用されます。
そして、続いて入る合いの手「Do you love me?」は、本来のイントネーションを無視した下行する「ソソソド」で受けています。
つまり、上行する「ソド ソド」で始められ、下行する「ソソソド」で締める、という方法で、この冒頭のメロディをまとめ、そしてこのメロディが、ドミソの跳躍音形のみで構成されていることを強調しているわけです。
なお、この部分全体は、いわゆるAメロといわれる部分に相当しますが、サビに匹敵する強いインパクトを持ち、極めて個性的な部分になっているため、この楽曲全体の最後にも配置されております。
さて、このAメロは、もう1度繰り返されます。
「言わないんだ・・・」の部分です。これは全く上記と同様ですが、問題は、最後の「ソラシド」という受けです。
なぜこれが、その前の「Do you love me?」と同様の「ソソソド」ではなく、「ソラシド」であるべきなのか、ということを、後で考察したいと思います。
Aメロの第2部分については後述することにして、ここではまず、「ソド」の構成を解明します。
Bメロ(「すんごい話題です」以後)では、これまで細かいリズムが主体だった中、やや引き伸ばされつつも細かい動きを含む順次進行のメロディーが主体になります。
そして他愛もない表現「すんごい話題です このケーキ屋さん」の中の「この」の部分において、「ソド」という音程が示唆されます。
ここではまだ、他愛もない部分に用いられているだけですが、続いて「ずっとあなたかな? かも」という、心情吐露の部分につながり、その「かも」という言葉は、上記の「この」の部分に相当する、つまり本来なら「ソド」という音程が当てはまるはずなわけですが、しかしながら、ここでは、わざと音程をはぐらかしているわけです。
(なお、このように、歌う旋律の中に、リズムは確定して語るようなニュアンスを指示する手法は、シェーンベルクが「月に憑かれたピエロ」において導入した「シュプレヒシュティンメ」といわれる手法であります。)
2回目の「かも」は、今度は音程が明確に歌われます。しかし、「ソド」ではなく、「シド」という音程が当てられています。
そして、サビに入ります。サビの構造は後述しますが、ここで注目すべきなのは、「モリモリ食べて」における、「ドドレミラ〜ミレ」という、4度跳躍によって、この楽曲の最高音(嗣永・夏焼・菅谷のいずれもが頭声・ファルセットによって歌唱しています)に到達します。
なぜわざわざファルセットを用いてまで4度の跳躍をするのでしょうか。
(もちろん、彼女たちの声の魅力を引き出す、ということでもありますが、)それは、この4度跳躍こそが、テーマである「ソド」と同じ音程であるからです。
そして続く「かっこよく愛してね」の「てね」において、まずは明確に「ソド」が当てはめられます。
そして、「世界で一番好き」の「好き」で、再度「ソド」が当てはめられ、ここにきて遂に、「好き」と「ソド」が結びつきます。
そしてそのことを強調すべく、リフレインされます。
最後には、「好き 好き」の連呼。
そしてこれは、冒頭の「ソド ソド」と完全に一致します。
そう、「ソド」は、「好き」のテーマだったわけです。
・・・つまり、楽曲冒頭の「ソド ソド」には、まだ自分の「好き」という気持ちをはっきり認識していない少女が、そのことの照れ隠しとして階名唱法によって歌う、という暗喩があるわけです。
この楽曲の流れは、その「ソド」という音程が、徐々に明確に「好き」という気持ちに結びついていく過程なのです。
とりわけ、「かも」の音程をわざとはぐらかすあたりは、一見、つんく氏のいつもの遊びと映りますが、そうとだけ受け取ってはいけません。
ここで「ソド」を明示しないことによって、サビの最後にようやく「好き」と自覚するに至る構成を実現しているのですから。
(2回目の「かも」も、「ソド」ではなく「シド」にして、わざと音程を変更している。)
・・・さて、ここまでの分析は、ともすれば言わずもがな、気付かれている方も多かろうと思います。
しかしここで我々は、「ソラシド」の謎に立ち向かわなければなりません。
話は、Aメロの途中に戻ります。
なぜ、「ソラシド」が「Do you love me?」と同様の「ソソソド」ではなく、「ソラシド」であるべきなのか。
・・・それは、後続する部分が、今度は全て順次進行によって構成されているからではないか、と思うのです。
まずそのことを確認します。
「ことばづかい」「なんとかして」「なおさないと」「いけません」
「ドドドシラソ」「ソソソファミ」「レレレドレミ」「ソソラシ」
・・・Aメロ冒頭がドミソばかりで構成されているのに対し、今度は見事に、全てが順次進行になっています。
なお、「いけません」から次につながるところに、「ソソラシド」という流れも存在しています。
好きかどうか言ってくれない彼に、無邪気にドミソの音程で気持ちを問う。
しかし、ここで反省の自問自答を始めます。
そのきっかけが「ソラシド」という順次進行であり、それによって気持ちを鎮めて、順次進行によって、きちんと内省する心情を描いているわけです。
つまり、Aメロの2つの部分は、ドミソの跳躍音形による「好き」という気持ちの確認と、順次進行の音形による「自問自答」によって構築されており、そのことを分節する鍵として、「ソド」と「ソラシド」が階名で表現されている、ということになります。
「ソド」が「好き」に結びつく構成は明白ですが、「ソラシド」がそういう役割を演じていることは、「好き」のように明示されてはいません。
しかし、ここに見てきたように、楽曲の音程構成と結び付けられていることは明白なのです。
そして、Bメロからサビへの展開は、それら2つの要素、即ち「跳躍進行」と「順次進行」が絶妙に配されながら、最後の「好き」の連呼に向かって収斂していく過程なのです。
まずはBメロ。これは、前述のように、順次進行のラインに「ソド」が介入する構成になっています。
「好き」という気持ちの高揚と、他愛もない日常。そのはざまで揺れ動く心情の中に、サビに向かって「かも」と、気持ちの自覚に向かいます。(でもここではまだ音程が明示されません。)
そしてサビ。これは、実はAメロにおける順次進行部分を、3度高めたものによって始められます。
「ド ド ドシラソ」→「ミ ミ ミレドシ」
そして、その後は跳躍進行と順次進行をうまく配置しながら進みますが、前述のように、ファルセットへの4度跳躍なども経て、最後の「好き」につなげます。
このように見れば、跳躍進行と順次進行の分節と融合の絶妙な配列によって、心情の変化と密接につながっていき、最後の「ソド=好き」に到達する、という構成が、「ソド」と「ソラシド」という、階名唱法によって暗示されていることがお判り頂けることと思います。
しかも、ここでは、作曲家の遊びとしての「暗示」なのではなく、少女の気恥ずかしさ、照れ隠しの心情として階名唱法を用いるという、表現意図をも実現したリアリゼーションとなっているわけです。
なお、音程はぐらかしは、「のにゅ」においては、2度ともに適用されています。「かも」では「好き」のはぐらかしだったのに対し、ここでは、ジレンマと、いたたまれなさの表現として、「好き」を敢えて異化するわけです。
ちなみに、言うまでもないことですが、このような、語尾を拾う手法
「克服だわ(だわだわ)」「駆けつけるわ(るわるわ)」
「ずっと居たいのに(のにゅ。のにゅ。)」
・・・については、「乙女パスタ」以来のつんく氏のお家芸ですが、ここでは、そのエスカレートぶり(のに→のにゅ。ってwww)が興味深いです。
つまりこれは、上記のような心情変化、及び音程はぐらかしの構造と、密接に結びついた「エスカレート」なのです。
また、ケーキ屋のマロングラッセと、受験生にラッセララッセラ、というのは、いかにもこじつけめいた押韻ですが、このような強引さも、「Loveマシーン」の「夫婦」以来のつんく氏のお家芸です。
「ギャグ100回分愛してください」という、ぶっとんだ命名が方向付けるように、この楽曲の珍妙なアレンジともあいまって、全編に笑いの要素をちりばめています。
しかしこれは、この主人公の、恋愛に対峙する微妙な心情を象徴しています。
これが、この楽曲の原型とも言える「ちょこっとLove」であれば、恋愛よりも家族を大切にしてしまう、という年齢設定であったわけですが、ここでは、もう少し大人、でもまだ子供、という、今のベリーの平均的年齢を前提にしているわけです。
最後に、桃子が「この瞬間が」で止まる部分。
このような、突如ブレイクを挿入する手法も、つんく氏のお家芸ですが、この感動的な「間」は何でしょう。
思えば、このような「間」の効果は、クラシック名曲の様々な場面で確認できることです。それこそ、「運命」の第1楽章にも、予想を裏切る間が仕組まれている場所がありますが、この楽曲のテーマ「ソド」の構成法といい、この「間」の手法といい、ひょっとすると、「題名のない音楽会」で「運命」を振った経験が、活かされているのかも、というのは、うがった見方でしょうか。
そして「ソド」の振り付け。
この、手をカクっと動かす振りは、以前、24時間テレビでモーニング娘。が「Loveマシーン」を手話で踊ったときのことを思い出します。
しかし、当コミュをご覧の皆さんであれば、更に、コダーイが実践した、ハンドサインによる音程教授メソッドを想起することでしょう。
「ソド」のハンドサインが、実は「好き」を示しているとしたら。。。
そんな、メタファーも含まれているのかもしれません。
|
|
|
|
コメント(8)
長くなりましたが、更に補足です。
(いくら書いても書き足りないぐらいです。)
まず、コダーイのハンドサイン、ということについてですが、
「好き」という場合には前方に手を広げる、「ソド」のときには右上方でカクッとする、という振り。
その振り付け自体が、上記論考の証左と言えます。
照れ隠しの「階名唱法」と、「好き」と表明するときの振りが、横に振るのと前に向けられるのと、対応しているわけです。
更に、「ソラシド」も、PVでは、同様のハンドサイン式振り付けになっていますが、上記の「跳躍進行」と「順次進行」の構造を、視覚的にも表現していると言えます。
つんく氏が、振り付けについても、主要なアイデア部分で
口出しすることはよく知られております。
この楽曲の核となる構造を、振りでも暗喩していると思われます。
なお、つんく氏がコダーイのハンドサインまでを認知しているかどうかはわかりませんが、しかし、このコダーイのハンドサインは、皆さんもよくご存知の、知名度の高いソースでも知らしめられています。
そう、それは、映画「未知との遭遇」です。
「レ ミ ド ド ソ」という、あの、皆が心に浮かべる旋律、そしてハンドサイン。
つんく氏が、あの映画を見ていることは確実でしょうから、コダーイの直接引用ではないとしても、あの映画を下敷きにしている可能性は高いと思います。
もう一点。
「ソド」による跳躍進行と「ソラシド」による順次進行、
という対比は既に述べましたが、他にももうひとつ、合いの手のパターンがあります。
それは、「おっとどっこい」です。
これは「ソ ソラ ソ」という、2度の上下行によるものです。
もちろんこれも一種の順次進行ですが、続く
「すんごい話題です」以後が、2度の上下行で構成されていることを考えると、これも、合いの手によって導かれた旋律構成(逆に言えば、後続旋律を余示する合いの手)なのかもしれません。
「す〜んごい話題です」「このケーキ屋さん」「マロングラッセラッセ」
「ラララシラソ♯ラシ」「ソドソ ララソ」「ソソソファ♯ソファ♯ソ」
前述した、「この」の音程に「ソド」が適用されている以外は、全て2度の上下行です。
従って、この楽曲全体を、次のように分析できます。
<Aメロ1>「ソド ソド」に続く、ドミソの跳躍音程
(好きなんだ〜言ってほしいな)
<Aメロ2>「ソラシド」に続く、順次進行(音階)
(言葉使い〜克服だわ)
<Aメロ1>「だわだわ」に続く、Aメロ1のリフレイン
(好きなんだ〜好きか聞かせて)
<Bメロ>「おっとどっこい」に続く、2度上下行(+ソド)
(すんごい話題です〜あなたかな?)
<サビ>「かもっ。かもっ。」に続く、跳躍と順次の融合
(一日なら〜世界で一番)
・・・そして、「好き=ソド」の連呼。
こう見ると、「かもっ。」の1回目が「ソド」の変形、2回目が「シド」となっていることも、続く部分の構成原理を示していると言えます。
・・・なんという、完成されたフォルムでしょう。
このように、跳躍音形(アルペジョ)と順次進行による構成原理、というと、やはり思い出すのは、ベートーヴェンの時代の構成原理です。
古典派初期のソナタは、必ずと言っていいほど、第1主題の中に跳躍(アルペジョ)と順次進行を織り交ぜ、それらを組み合わせた構築によって主題を完結させる、という手法が採られています。
「ギャグ100回」の、あまりにも完成された構成原理を見るにつけ、ともすればつんく氏は、この、古典派の構成原理についての知見を得たのではないか、とすら勘ぐってしまいます。彼のことですから、「運命」を振るにあたって、多少なりともベートーヴェンについて勉強したかもしれません。
ついでに申し上げますと、「Do you love me?」は、本来のイントネーションと逆である、ということは既に触れましたが、この「ソソソド」という音形とリズム、何かを思い出しませんか?
・・・そう、まさに「運命」の動機ではありませんか!
「運命」の動機は、「ソソソミ♭」で始められますが、これは後で、低音部分では「ソソソド」という形でしばしば用いられていますし、第2主題導入部分は、平行調ですから「シ♭シ♭シ♭ミ♭」となりますが、これは移動ドで表記するなら「ソソソド」になるわけです。
実は、「運命」の動機が忍ばされていたとは。。。
そもそも、「ソド」という動きは、「運命」第1楽章の終結部分で繰り返されるわけですが、この反復と、「好き」の連呼を結びつけるのは、あながち間違いではないかもしれません。
詳述は避けますが、「運命」の完成された構成原理を思い返すと、「ギャグ100回」と、共通する要素が多いのです。
(例えば、第4楽章の主題は、「ドミソ」で始まり、「ファミレドレド」という順次進行につながりますよね。)
もちろん、「ギャグ100回」はソナタ形式ではありません。しかし、「運命」をはじめとするベートーヴェンの完璧な構成原理を、J Pop の中で再解釈したとすると、「ギャグ100回」のような構成方法になる、ということかもしれません。
完成されたフォルム、という意味では、ベートーヴェンに匹敵する仕事だと、断定できます。
この作品、旋律そのものは、聞き慣れたものですし、一見、シンプルな音楽に映じますが、畏るべき構築、しかも、J Pop としては全く新しい観点での構成原理による、極めて高い完成度を示す楽曲と言えるわけです。
(いくら書いても書き足りないぐらいです。)
まず、コダーイのハンドサイン、ということについてですが、
「好き」という場合には前方に手を広げる、「ソド」のときには右上方でカクッとする、という振り。
その振り付け自体が、上記論考の証左と言えます。
照れ隠しの「階名唱法」と、「好き」と表明するときの振りが、横に振るのと前に向けられるのと、対応しているわけです。
更に、「ソラシド」も、PVでは、同様のハンドサイン式振り付けになっていますが、上記の「跳躍進行」と「順次進行」の構造を、視覚的にも表現していると言えます。
つんく氏が、振り付けについても、主要なアイデア部分で
口出しすることはよく知られております。
この楽曲の核となる構造を、振りでも暗喩していると思われます。
なお、つんく氏がコダーイのハンドサインまでを認知しているかどうかはわかりませんが、しかし、このコダーイのハンドサインは、皆さんもよくご存知の、知名度の高いソースでも知らしめられています。
そう、それは、映画「未知との遭遇」です。
「レ ミ ド ド ソ」という、あの、皆が心に浮かべる旋律、そしてハンドサイン。
つんく氏が、あの映画を見ていることは確実でしょうから、コダーイの直接引用ではないとしても、あの映画を下敷きにしている可能性は高いと思います。
もう一点。
「ソド」による跳躍進行と「ソラシド」による順次進行、
という対比は既に述べましたが、他にももうひとつ、合いの手のパターンがあります。
それは、「おっとどっこい」です。
これは「ソ ソラ ソ」という、2度の上下行によるものです。
もちろんこれも一種の順次進行ですが、続く
「すんごい話題です」以後が、2度の上下行で構成されていることを考えると、これも、合いの手によって導かれた旋律構成(逆に言えば、後続旋律を余示する合いの手)なのかもしれません。
「す〜んごい話題です」「このケーキ屋さん」「マロングラッセラッセ」
「ラララシラソ♯ラシ」「ソドソ ララソ」「ソソソファ♯ソファ♯ソ」
前述した、「この」の音程に「ソド」が適用されている以外は、全て2度の上下行です。
従って、この楽曲全体を、次のように分析できます。
<Aメロ1>「ソド ソド」に続く、ドミソの跳躍音程
(好きなんだ〜言ってほしいな)
<Aメロ2>「ソラシド」に続く、順次進行(音階)
(言葉使い〜克服だわ)
<Aメロ1>「だわだわ」に続く、Aメロ1のリフレイン
(好きなんだ〜好きか聞かせて)
<Bメロ>「おっとどっこい」に続く、2度上下行(+ソド)
(すんごい話題です〜あなたかな?)
<サビ>「かもっ。かもっ。」に続く、跳躍と順次の融合
(一日なら〜世界で一番)
・・・そして、「好き=ソド」の連呼。
こう見ると、「かもっ。」の1回目が「ソド」の変形、2回目が「シド」となっていることも、続く部分の構成原理を示していると言えます。
・・・なんという、完成されたフォルムでしょう。
このように、跳躍音形(アルペジョ)と順次進行による構成原理、というと、やはり思い出すのは、ベートーヴェンの時代の構成原理です。
古典派初期のソナタは、必ずと言っていいほど、第1主題の中に跳躍(アルペジョ)と順次進行を織り交ぜ、それらを組み合わせた構築によって主題を完結させる、という手法が採られています。
「ギャグ100回」の、あまりにも完成された構成原理を見るにつけ、ともすればつんく氏は、この、古典派の構成原理についての知見を得たのではないか、とすら勘ぐってしまいます。彼のことですから、「運命」を振るにあたって、多少なりともベートーヴェンについて勉強したかもしれません。
ついでに申し上げますと、「Do you love me?」は、本来のイントネーションと逆である、ということは既に触れましたが、この「ソソソド」という音形とリズム、何かを思い出しませんか?
・・・そう、まさに「運命」の動機ではありませんか!
「運命」の動機は、「ソソソミ♭」で始められますが、これは後で、低音部分では「ソソソド」という形でしばしば用いられていますし、第2主題導入部分は、平行調ですから「シ♭シ♭シ♭ミ♭」となりますが、これは移動ドで表記するなら「ソソソド」になるわけです。
実は、「運命」の動機が忍ばされていたとは。。。
そもそも、「ソド」という動きは、「運命」第1楽章の終結部分で繰り返されるわけですが、この反復と、「好き」の連呼を結びつけるのは、あながち間違いではないかもしれません。
詳述は避けますが、「運命」の完成された構成原理を思い返すと、「ギャグ100回」と、共通する要素が多いのです。
(例えば、第4楽章の主題は、「ドミソ」で始まり、「ファミレドレド」という順次進行につながりますよね。)
もちろん、「ギャグ100回」はソナタ形式ではありません。しかし、「運命」をはじめとするベートーヴェンの完璧な構成原理を、J Pop の中で再解釈したとすると、「ギャグ100回」のような構成方法になる、ということかもしれません。
完成されたフォルム、という意味では、ベートーヴェンに匹敵する仕事だと、断定できます。
この作品、旋律そのものは、聞き慣れたものですし、一見、シンプルな音楽に映じますが、畏るべき構築、しかも、J Pop としては全く新しい観点での構成原理による、極めて高い完成度を示す楽曲と言えるわけです。
つんく氏が、僕が書いたようなことを全面的に自覚しているかどうかは定かではありません。事実、彼の公式ページを確認しても、上記のような構造についてはもちろん一言も言及していませんし、むしろ肩すかしをくらうようなことしか書かれていません。ひょっとすると、雑誌媒体など細かくチェックすると、それに類する発言が出てくるのかもしれませんが、そこまで詳細にはチェックしていませんので・・・。でも恐らく、100%までは、自覚的ではないことも確実でしょう。(こちらが指摘したら、「いや、自覚してた。」・・・と、調子いいこと言ってしまう、そういう人物でもありますね、彼は。)
しかし、分析とは、そういうものなのです。
本人が自覚しているかどうか、ではなく、テクストとしてどう読めるのか、ということなのです。
むしろ、本人の意図を超える内容を有するときにこそ、名曲は生まれるのです。
天才の仕事とは、そういうものなのです。
例えば、ベートーヴェンの楽曲を、後世の人々は、様々に分析しています。しかも、それは同一の内容ではなく、異なる見解も多いわけです。(本当に、様々な意見が今なお取り交わされております。)異なる見解がある、ということは、少なくともそのいずれかが、本人の自覚していない見解であることは間違いありません。
しかし、読めば読むほどに味わいが増す、聴けば聴くほどに新しい発見がある・・・優れたテクストとは、そういうものなのです。
演奏家が、これほどに名演があるにも関わらず、それでもなお、ベートーヴェンに挑むのは、そして我々がそれを聴くことに喜びを見出せるのは、テクストが優れているからであり、新たな解釈の可能性を無尽蔵に有しているからです。
20世紀、ベンヤミンの言う「複製芸術の時代」(音楽で言えば、録音による作品の流通が前提となる時代)において、音楽作品のテクストとしての再演性は低くなりました。ポピュラー音楽は、作曲家よりもアーティストと結びつき、認識されます。リメイクは、むしろ特殊なことですね。
でも、記録物が残ることによって、そのときその時点での表現としての完成形が記録され、時代を超えて、聴き手が再解釈可能なわけです。
「ギャグ100回」が、今のベリーにしか表現できないことは事実です。しかし、我々は、こうやって、商品として定着された楽曲を噛み締めることで、その良さを再認識、再発見し続けることができるわけです。
しかし一方、考えてみたら、つんくワークスは、彼自身によるものも含めて、再演機会の多いものです。それはハロコンなどで別ユニットによって演奏される、という機会も多いから、という、ある種特殊な事情によって形成されています。このような体制自体が、楽曲の再演性をある程度見越した作りを意識する→→結果的に、楽曲そのものの構成としての完成度も意識することになる・・・ということなのではないでしょうか。
つまり、作曲行為そのものが、19世紀の音楽事情(クラシックの作曲家)に近い環境なのです。
小室氏くらいから、J Popにおいても「作曲家=プロデューサー」の位置が前面に置かれることが多くなりましたが、つんく氏の場合、ハロプロというオーケストラの、座付き作曲家(レジデントコンポーザー)であり、かつ、音楽監督(兼首席指揮者)でもある、という、比喩が、このコミュ的にはもっともしっくりいくのではないでしょうか。ハロー全体を見渡すその度量、構成員全員の持てる魅力と知られざる魅力、今の実力と未来の可能性を理解し、最大限にそれを引き出す創作と総指揮。
座付き作曲家でありかつ音楽監督でもある、というのは、クラシックの場でもなかなか実現できる業ではありません。
・・・やはり彼は、偉大です。
しかし、ベリーは小学生を含みますので、活動に制限があるのがイタいですね。
そして、ソフトが売れない現象が、ここまで複製技術の発達した今、小学生とその親にまで波及しているはずですから、かつての娘。「ラブマ」〜プッチモニ。「ちょこっとLove」〜娘。「ダンスサイト」の流れに見られたような大流行にまでは至らないでしょうけど、
「ギャグ100回」は、本来、「ちょこっとLove」や「じゃんけんぴょん」に匹敵するヒットにつながってもいい作品です。
あの頃の露出頻度が実現していれば、「のにゅ。」は、矢口が「セクシービーム」で社会現象的にブレイクしたように、千奈美のブレイクを生んだでしょう。
でも、今の活動ペースは、アップフロントの愛を感じます。
ひと昔前なら、小学生だろうと寝る間もなく働かされていたことでしょうから。
彼女たちの屈託のない笑顔を守るには、露出控えめも、致し方ないでしょう。
しかし、J Pop は、残念ながら、現在、ヒットしていないと、なかなか後世に残ることはありません。メディアの力が楽曲の力を大きく上回っているからです。
だからこそ、よいと思っている人々が、永く、楽曲とその表現のすばらしさを受容し、語り継いでいく必要があるのです。
メンデルスゾーンが「マタイ受難曲」を復刻したのが、「演奏」による再解釈という文化が定着した頃だったことを考えると、ネットを含めた受容側の文化がここまで大きくなった今、現在のヒット率イコール後世に残る率、ということではない時代がくるかもしれません。
しかし、分析とは、そういうものなのです。
本人が自覚しているかどうか、ではなく、テクストとしてどう読めるのか、ということなのです。
むしろ、本人の意図を超える内容を有するときにこそ、名曲は生まれるのです。
天才の仕事とは、そういうものなのです。
例えば、ベートーヴェンの楽曲を、後世の人々は、様々に分析しています。しかも、それは同一の内容ではなく、異なる見解も多いわけです。(本当に、様々な意見が今なお取り交わされております。)異なる見解がある、ということは、少なくともそのいずれかが、本人の自覚していない見解であることは間違いありません。
しかし、読めば読むほどに味わいが増す、聴けば聴くほどに新しい発見がある・・・優れたテクストとは、そういうものなのです。
演奏家が、これほどに名演があるにも関わらず、それでもなお、ベートーヴェンに挑むのは、そして我々がそれを聴くことに喜びを見出せるのは、テクストが優れているからであり、新たな解釈の可能性を無尽蔵に有しているからです。
20世紀、ベンヤミンの言う「複製芸術の時代」(音楽で言えば、録音による作品の流通が前提となる時代)において、音楽作品のテクストとしての再演性は低くなりました。ポピュラー音楽は、作曲家よりもアーティストと結びつき、認識されます。リメイクは、むしろ特殊なことですね。
でも、記録物が残ることによって、そのときその時点での表現としての完成形が記録され、時代を超えて、聴き手が再解釈可能なわけです。
「ギャグ100回」が、今のベリーにしか表現できないことは事実です。しかし、我々は、こうやって、商品として定着された楽曲を噛み締めることで、その良さを再認識、再発見し続けることができるわけです。
しかし一方、考えてみたら、つんくワークスは、彼自身によるものも含めて、再演機会の多いものです。それはハロコンなどで別ユニットによって演奏される、という機会も多いから、という、ある種特殊な事情によって形成されています。このような体制自体が、楽曲の再演性をある程度見越した作りを意識する→→結果的に、楽曲そのものの構成としての完成度も意識することになる・・・ということなのではないでしょうか。
つまり、作曲行為そのものが、19世紀の音楽事情(クラシックの作曲家)に近い環境なのです。
小室氏くらいから、J Popにおいても「作曲家=プロデューサー」の位置が前面に置かれることが多くなりましたが、つんく氏の場合、ハロプロというオーケストラの、座付き作曲家(レジデントコンポーザー)であり、かつ、音楽監督(兼首席指揮者)でもある、という、比喩が、このコミュ的にはもっともしっくりいくのではないでしょうか。ハロー全体を見渡すその度量、構成員全員の持てる魅力と知られざる魅力、今の実力と未来の可能性を理解し、最大限にそれを引き出す創作と総指揮。
座付き作曲家でありかつ音楽監督でもある、というのは、クラシックの場でもなかなか実現できる業ではありません。
・・・やはり彼は、偉大です。
しかし、ベリーは小学生を含みますので、活動に制限があるのがイタいですね。
そして、ソフトが売れない現象が、ここまで複製技術の発達した今、小学生とその親にまで波及しているはずですから、かつての娘。「ラブマ」〜プッチモニ。「ちょこっとLove」〜娘。「ダンスサイト」の流れに見られたような大流行にまでは至らないでしょうけど、
「ギャグ100回」は、本来、「ちょこっとLove」や「じゃんけんぴょん」に匹敵するヒットにつながってもいい作品です。
あの頃の露出頻度が実現していれば、「のにゅ。」は、矢口が「セクシービーム」で社会現象的にブレイクしたように、千奈美のブレイクを生んだでしょう。
でも、今の活動ペースは、アップフロントの愛を感じます。
ひと昔前なら、小学生だろうと寝る間もなく働かされていたことでしょうから。
彼女たちの屈託のない笑顔を守るには、露出控えめも、致し方ないでしょう。
しかし、J Pop は、残念ながら、現在、ヒットしていないと、なかなか後世に残ることはありません。メディアの力が楽曲の力を大きく上回っているからです。
だからこそ、よいと思っている人々が、永く、楽曲とその表現のすばらしさを受容し、語り継いでいく必要があるのです。
メンデルスゾーンが「マタイ受難曲」を復刻したのが、「演奏」による再解釈という文化が定着した頃だったことを考えると、ネットを含めた受容側の文化がここまで大きくなった今、現在のヒット率イコール後世に残る率、ということではない時代がくるかもしれません。
初めてこのコミュに参加させて頂きます。よろしくお願いします。
さて、ベートーベンの楽曲との対比で始まるこの分析、興味深く読ませて頂きました。
一つあるのは「ドミソ」で構成されるフレーズは大変に力強く感じられると言うこと。
例えば映画音楽を見てみても、「スターウォーズ」とか「アラビアのロレンス」など、枚挙に暇がありません。
ギャグ100回は最初にこれを使い、その後は女の子らしい可愛いフレーズを持ってきてショックを和らげています。まさに分析されている通りです。
ギャグ100回は、一見奇抜な曲であるように見えて実は非常にオーソドックス且つクラシカルな要素で構成されているんですね。勉強になりました。
さて、ベートーベンの楽曲との対比で始まるこの分析、興味深く読ませて頂きました。
一つあるのは「ドミソ」で構成されるフレーズは大変に力強く感じられると言うこと。
例えば映画音楽を見てみても、「スターウォーズ」とか「アラビアのロレンス」など、枚挙に暇がありません。
ギャグ100回は最初にこれを使い、その後は女の子らしい可愛いフレーズを持ってきてショックを和らげています。まさに分析されている通りです。
ギャグ100回は、一見奇抜な曲であるように見えて実は非常にオーソドックス且つクラシカルな要素で構成されているんですね。勉強になりました。
さて、別トピ「松浦亜弥シングル楽曲における使用音域」でひろっぴぃ〜さんが、使用音域を視覚化する方法を考案なさったのを受けて、「ギャグ100回」についてもそれを適用してみたいと思います。
f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d'' e''f'' g''
09 ××××●◆●◆●●●●●●◆●●◆●●●○○○○▲××
なお、表記の凡例は下記の通りです。
×=音域外 ●=胸声使用音 ◆=胸声音域内未使用音
○=胸声音域と頭声音域の中間、頭声使用音の間 ▲=頭声使用音
(ポルタメントやずり上げによって経過する場合のみの音は未使用音とした)
各部の詳細としては、こうなります。
Aメロ=a−a' Bメロ=d♯'−a' サビ=e−c♯''(頭声はf♯''に到達)
低めのAメロ、中間音域のBメロ、高めのサビ、という構成になっています。
ここで全体の音域を、松浦亜弥の初期楽曲と比較すると、興味深いことがわかります。
f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d'' e''f'' g''
09 ××××●◆●◆●●●●●●◆●●◆●●●○○○○▲××
========松浦「ドキラブ〜桃片」=========
01 ×××××●●◆●◆●●●●●●●●●◆●◆●○○▲○▲
02 ×××××●●●●◆●●●●◆●●●●●●×××××××
03 ××××●◆◆●●●●●●●●●●●●●●×××××××
04 ××××●◆●●◆●◆●●◆●●●◆●●○▲○▲××××
05 ××××××××●●●●●●●●●●○○▲○○○▲▲××
・・・いかがでしょうか。
技巧派松浦の初期楽曲群にも引けをとらない、幅広い音域を要求していることがわかります。
とりわけ、サビにおいて、頭声のf♯''をきっちり歌わせている点は、かなり高度な要求だと言えます。
(初期松浦の頭声使用は、間奏部分に限定されており、サビメロディできっちりとらせているという点では、長13度に及ぶこの広い音域を、完全な楽曲の歌唱音域として設定しているわけで、その意味では松浦への要求を超えています。)
このサビ部分を歌っているのは、嗣永、菅谷、夏焼の3名ですが、そのうち最低音域を含む旋律(Aメロ)でソロをとっているのは、嗣永、菅谷の2名です。(夏焼も、ユニゾン部分では最低音のaを歌っていますが。)
少なくとも、これら2名については、初期松浦に匹敵する(いや、それ以上の)歌唱を要求されていると言って過言ではないでしょう。
ユニセックスな(どちらかというとボーイソプラノのような)しっかりしたヴォーカルを確立した菅谷、
少女のチャーミングさ、女性アイドル歌唱の王道のような萌え系ヴォーカルを確立した嗣永、
そして年齢不相応な色気を湛えつつも、いまだ子供としての側面も仄かに感じさせる夏焼。
要求の高い楽曲だけに、サビのソロ配分はこれら3人に(更に言えば嗣永に)偏っていますが、その他の部分も含めて、彼女たち3名の声の魅力とテクニックを、絶妙に配置した楽曲に仕上がっていると言えるでしょう。(3人以外推しのヲタには物足りないでしょうが。)
松浦楽曲で検証した音域変遷について、いずれBerryz工房についても作業してみたいと思いますが、今回の「ギャグ100回」については、声や表現の完成度、上述のような楽曲の完成度、ともに、Berryzにとっても、ハロプロ全体にとっても、記念碑的な作品であると考えています。
(例えば、「あなたなしでは生きていけない」については、少女らしからぬ低音を駆使しますが、つんく♂が声をかぶせまくって誤魔化しているわけです。「ギャグ100回」では、彼自身の声は登場しません。それは、彼女たちのヴォーカルを全面的に信頼し、安心して任せているのではないでしょうか。)
また、上記松浦との比較を見てもお判りのように、つんく♂がBerryz工房の歌唱に期待し、創作意欲とインスピレーションを触発されていることは明白です。
まだまだこれから表現の幅を広げていくであろう、Berryz工房の今後に、ますます期待です。
f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d'' e''f'' g''
09 ××××●◆●◆●●●●●●◆●●◆●●●○○○○▲××
なお、表記の凡例は下記の通りです。
×=音域外 ●=胸声使用音 ◆=胸声音域内未使用音
○=胸声音域と頭声音域の中間、頭声使用音の間 ▲=頭声使用音
(ポルタメントやずり上げによって経過する場合のみの音は未使用音とした)
各部の詳細としては、こうなります。
Aメロ=a−a' Bメロ=d♯'−a' サビ=e−c♯''(頭声はf♯''に到達)
低めのAメロ、中間音域のBメロ、高めのサビ、という構成になっています。
ここで全体の音域を、松浦亜弥の初期楽曲と比較すると、興味深いことがわかります。
f g a b c' d' e' f' g' a' b' c'' d'' e''f'' g''
09 ××××●◆●◆●●●●●●◆●●◆●●●○○○○▲××
========松浦「ドキラブ〜桃片」=========
01 ×××××●●◆●◆●●●●●●●●●◆●◆●○○▲○▲
02 ×××××●●●●◆●●●●◆●●●●●●×××××××
03 ××××●◆◆●●●●●●●●●●●●●●×××××××
04 ××××●◆●●◆●◆●●◆●●●◆●●○▲○▲××××
05 ××××××××●●●●●●●●●●○○▲○○○▲▲××
・・・いかがでしょうか。
技巧派松浦の初期楽曲群にも引けをとらない、幅広い音域を要求していることがわかります。
とりわけ、サビにおいて、頭声のf♯''をきっちり歌わせている点は、かなり高度な要求だと言えます。
(初期松浦の頭声使用は、間奏部分に限定されており、サビメロディできっちりとらせているという点では、長13度に及ぶこの広い音域を、完全な楽曲の歌唱音域として設定しているわけで、その意味では松浦への要求を超えています。)
このサビ部分を歌っているのは、嗣永、菅谷、夏焼の3名ですが、そのうち最低音域を含む旋律(Aメロ)でソロをとっているのは、嗣永、菅谷の2名です。(夏焼も、ユニゾン部分では最低音のaを歌っていますが。)
少なくとも、これら2名については、初期松浦に匹敵する(いや、それ以上の)歌唱を要求されていると言って過言ではないでしょう。
ユニセックスな(どちらかというとボーイソプラノのような)しっかりしたヴォーカルを確立した菅谷、
少女のチャーミングさ、女性アイドル歌唱の王道のような萌え系ヴォーカルを確立した嗣永、
そして年齢不相応な色気を湛えつつも、いまだ子供としての側面も仄かに感じさせる夏焼。
要求の高い楽曲だけに、サビのソロ配分はこれら3人に(更に言えば嗣永に)偏っていますが、その他の部分も含めて、彼女たち3名の声の魅力とテクニックを、絶妙に配置した楽曲に仕上がっていると言えるでしょう。(3人以外推しのヲタには物足りないでしょうが。)
松浦楽曲で検証した音域変遷について、いずれBerryz工房についても作業してみたいと思いますが、今回の「ギャグ100回」については、声や表現の完成度、上述のような楽曲の完成度、ともに、Berryzにとっても、ハロプロ全体にとっても、記念碑的な作品であると考えています。
(例えば、「あなたなしでは生きていけない」については、少女らしからぬ低音を駆使しますが、つんく♂が声をかぶせまくって誤魔化しているわけです。「ギャグ100回」では、彼自身の声は登場しません。それは、彼女たちのヴォーカルを全面的に信頼し、安心して任せているのではないでしょうか。)
また、上記松浦との比較を見てもお判りのように、つんく♂がBerryz工房の歌唱に期待し、創作意欲とインスピレーションを触発されていることは明白です。
まだまだこれから表現の幅を広げていくであろう、Berryz工房の今後に、ますます期待です。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
アイドルもクラシック音楽も好き 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
アイドルもクラシック音楽も好きのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 一行で笑わせろ!
- 82539人
- 2位
- 酒好き
- 170702人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90062人