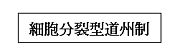最近の注目情報詳細(2010年7月)
1.科学・技術政策にも道州制の視点を(日本経済新聞 編集委員 永田好生)
日本の新しいあり方を議論する1テーマに「道州制」がある。行政区画の大幅な変更に課題や異論があり、実現の道筋は依然はっきりしない。しかし科学・技術の政策からみると、道州制との相性は割と良く、効果的な施策を推進できそうだ。
イノベーション(革新)に関するある講演を聞いていたら、日本の未来を切り開く有力な手法に道州制の導入を取り上げていた。
講師は、一橋大学イノベーション研究センター長の米倉誠一郎教授。日本よりも面積が広い米カリフォルニア州とシュワルツェネッガー知事の顔写真をスクリーンに映し出しながら「カリフォルニア州には州知事が1人。それに対し日本では……」と語るくだりは、思考実験を始めるよいきっかけになる。
「道州制を導入し各連合体に大胆に権限を委譲するだけで、国内に新しいフロンティアが出現する」という米倉教授の主張には説得力があった。同時に、現在の地域経済の活性化を目的にした科学・技術政策にも道州制が適しているのではないかと感じた。
地域振興に科学・技術を絡める試みは、1980年代の「テクノポリス法」以来、結構長く続いている。産業構造の変化に合わせて研究開発拠点の集積を促す頭脳立地法へと引き継がれ、多くの自治体が「リサーチパーク」の整備に力を入れた。
一連の施策は、その時々の社会・経済情勢に応じて役割を果たしたといえるだろう。浜松市や福島県郡山市を中心とする地域では、テクノポリス法で築いた仕組みを現在でも活用している。
ただ、土地の整備や建物を建設する“箱モノ行政”に陥る傾向は強く、新しい科学・技術の種を生み出したのか、国際的に競争力のある産業の基盤となったのか、といった検証はあまりなされていないようだ。
経済産業省が2001年度から始めた「産業クラスター計画」と文部科学省が02年度から始めた「知的クラスター創成事業」は、産学官の連携を重視したもので、施設偏重は多少改まった印象はある。それでも09年度の補正予算のように、各都道府県に産学連携の拠点を整備しようとする発想は根強い。文科省のこの案は、昨秋の事業仕分けで大幅に予算が削減された。知的クラスター創成事業も制度の重複が指摘され、廃止の方針が決まった。
もともと科学や技術は、地域の境界に縛られない性質を備える。大学の研究者や研究助成機関、実用化する企業など「これでやろう」と合意できる人や組織が、所在地にとらわれず機動的に結び付く方がより実践的だ。国による科学・技術政策の支援が都道府県単位では、あまりにも狭すぎる。特に、科学を基盤にした産業の形成を考えるときは、道州制の方が都合がよい。
そう唱えるのは、職業能力開発総合大学校の古川勇二校長だ。隆盛著しいアジア勢と競合できるものづくりの力を備えるためには、付加価値の高い製品開発が不可欠といい、そのための労働人口や企業集積を考えた科学・技術政策を展開すべきだと説く。
例えば、人口40万人の都市で労働人口の比率が6割、そのうちの20%(4万8000人)が製造業に就業する標準的なモデルの場合、部品数で約3000点を扱う製造業を維持するのが限界だと指摘する。部品3000点とは二輪車に相当する。
液晶テレビだと部品数は約1万点、自動車で1万5000点、航空機で20万点……。現実の産業集積はこうした条件をそなえた地域の連合体に移っている。産業への貢献を想定する科学・技術の振興策ならば、こうした動向を踏まえた計画でなければいけないと、古川校長は強調。道州制への移行を強く勧める。
経産・文科両省の事業からは、北海道と関西の定期的な交流会のように、クラスター間で連携しようとする活動が生まれている。昨春には「全国イノベーション推進機関ネットワーク」が立ち上がり、自律的な地域間の協力を支える動きも出てきた。道州単位で地域の特性を伸ばそうとする取り組みが実を結べば、研究が社会に還元されていないという議論にも一石を投じるだろう。
2.沖縄単独州の実現を 小川政務官、沖大で講演(2010年6月13日 琉球新報)
沖縄大学土曜教養講座が12日、那覇市の同大学で開かれ、「沖縄の自立と振興に向けて」と題して総務省の小川淳也総務政務官が講演した。小川氏は「近い将来、絶対に道州制を日本に導入するべきだ。沖縄と北海道は先行して導入に取り組み、他府県を先導する役割を果たしてもらいたい」と持論を展開。沖縄は他府県より先行して道州制を導入し、単独州を実現するよう訴えた。
単独州実現には「県庁と沖縄総合事務局関係の議論は避けて通れない」と指摘。予算総額6千億円で約2万人の職員を抱える県と、職員数千人の総合事務局、4千億円近い沖縄振興開発予算を持つ内閣府の統合を提案。単独州を実現できれば「職員数2万人強で、1兆円の財政規模を持つ、思い切った地域の振興を自らの知恵と努力、責任において実行できる沖縄になる」と主張した。
ヨーロッパの一部自治州には、国法で留保されている規則以外はすべて立法できる「一次立法権」、所得税など一定の範囲内で税率を設定できる「経済立法権」が付与されていると説明。「沖縄が自治州を志すなら、自治立法権なり、財政立法権、自主財政権の付与ぐらいは視野に入れるべきだ」とした。
最後に「そういう全国に先駆けたチャレンジを沖縄には期待したい。その環境づくりを政府として進めなければならない」と述べた。
3.橋下知事が連邦制で質問攻め ドイツ・ヘッセン州首相に(2010年6月18日 47news)
大阪府の橋下徹知事は16日、訪問先のドイツ・ヘッセン州のコッホ首相と同国の連邦制度をめぐり会談、「短所は何ですか?」といった“直球”を交え、首相を質問攻めにした。
橋下氏は、今回の欧州視察の主目的に連邦制研究を挙げていた。出発前、道州制のモデルとする考えを強調し「(長所短所を)肌で感じたい」と意気込みを語っていた。
首相が短所について「教育などで(連邦の)州ごとに格差が生まれる」と回答すると、橋下氏はすかさず「米国なら別だが、ドイツや日本くらいの(人口や国土の)規模で国民は格差を納得すると思うか」「連邦制をやめようという声は?」などと重ねて聞いた。
首相は、国が州ごとの財政調整を行っているとした上で「税収が多い州では、見合った住民サービスがなされず不満も出る」と課題を指摘した。
会談後、橋下氏は「各地域が責任を持つことが国の発展には不可欠と確信した。格差が生じたとしても、連邦制に近い形の分権を進めたい」と述べ、道州制や持論の「大阪都構想」推進への思いを強くした様子だった。
4.横浜の大都市制度に反論、知事「道州制こそ必要」/神奈川(2010年6月18日 神奈川新聞)
松沢成文知事は17日、横浜市などが国に提案するため検討している「大都市制度」について、県(広域自治体)からの独立を目指すという前提や政令市間の実績の差などの課題を挙げて反論し、「道州制の導入こそ、今必要なもの」との持論を展開した。
同日開かれた本会議で、平本敏氏(民主、瀬谷区)の質問に答えた。
横浜市が発表した大都市制度創設の在り方についての基本的な方向性では、「国の成長拠点となる大都市をつくる」が基本姿勢。県から独立した「特別な市」として、大都市は地方の事務をすべて担い、基礎自治体と広域自治体の性格を併せ持つと同時に、圏域の中核都市として広域的な役割を果たすとしている。
知事は、県から完全に分離・独立し、大都市が市域内の地方税を独占する考え方について「県が広域的な行政サービスを提供するための税源を確保できず、広域自治体としての地方自治が根本から成り立たなくなる」と反論。また横浜などのように政令市として長年の実績を持つ自治体と、相模原のようにまだ日が浅い自治体とでは「“都市力”に大きな格差がある」と指摘し、すべてが特別自治市を目指すとする同制度の提案に「無理がある」と反論した。
最後に知事は「今必要なのは、地方自治の在り方を根本的に見直し、新しい国の形を目指す『道州制』の導入の検討を進めるべき」と、自ら長年主張する道州制をアピールした。
5.「一括交付金」国が関与、地方の自由度縮小か(2010年6月20日 読売新聞)
国と地方との関係を見直す地域主権改革の具体策を盛り込んだ政府の「地域主権戦略大綱」最終案の全容が19日、判明した。
目玉政策である地方が自由に使える「一括交付金」をめぐり、中央省庁が交付の計画段階から関与できる内容となっており、原案より地方の自由度が縮小した。政府は21日の地域主権戦略会議(議長・菅首相)に最終案を示し、22日にも大綱を閣議決定したい考えだが、改革は「骨抜き」ともいえ、地方からの反発は必至だ。
一括交付金は、各省庁が使途を決める「ひも付き補助金」に代わる新制度。最終案は、公共事業関係の補助金をまず来年度から一括交付金にし、3〜5年をかけて完全導入を目指すとした。実施にあたっては、「PDCAサイクルを通じて制度の評価・改善を図る」と明記。PDCAは「計画・執行・点検・反映」のことで、計画段階から国が関与できることを意味する。
6.政令市初、大阪市が関西広域連合へ参加 橋下“都構想”に対抗(2010年7月7日 産経新聞)
府県の枠を超えて広域行政を行う関西広域連合(仮称)に、大阪市が設立当初から正式参加する意向を固めたことが6日、分かった。平松邦夫市長が近く表明する。関西広域連合にはこれまで2府5県が参加を表明しているが、政令市では初めて。
関係者によると、これまで大阪府の橋下徹知事が府と市を再編する大阪都構想を提唱していることに、平松市長は強く反発。都市の将来像として、大阪都ではなく、広域の関西州を目指す姿勢を明確に打ち出す狙いがあるという。
平松市長はこれまで「都をつくれば(問題が)解決するわけではない。経済や物流は府県レベルを大きく超えており、関西という広いエリアで考える必要がある」などと言及。市幹部は「広域連合は関西州への移行も想定される。加入が当然だろうと考えた」と述べた。
広域連合に参加表明しているのは京都、大阪、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の2府5県。議会調整などで足並みがそろわなかったため、当初の想定よりも設立スケジュールは遅れているという。現在は今秋の各府県議会に規約案を提案するための調整が進められている。
1.科学・技術政策にも道州制の視点を(日本経済新聞 編集委員 永田好生)
日本の新しいあり方を議論する1テーマに「道州制」がある。行政区画の大幅な変更に課題や異論があり、実現の道筋は依然はっきりしない。しかし科学・技術の政策からみると、道州制との相性は割と良く、効果的な施策を推進できそうだ。
イノベーション(革新)に関するある講演を聞いていたら、日本の未来を切り開く有力な手法に道州制の導入を取り上げていた。
講師は、一橋大学イノベーション研究センター長の米倉誠一郎教授。日本よりも面積が広い米カリフォルニア州とシュワルツェネッガー知事の顔写真をスクリーンに映し出しながら「カリフォルニア州には州知事が1人。それに対し日本では……」と語るくだりは、思考実験を始めるよいきっかけになる。
「道州制を導入し各連合体に大胆に権限を委譲するだけで、国内に新しいフロンティアが出現する」という米倉教授の主張には説得力があった。同時に、現在の地域経済の活性化を目的にした科学・技術政策にも道州制が適しているのではないかと感じた。
地域振興に科学・技術を絡める試みは、1980年代の「テクノポリス法」以来、結構長く続いている。産業構造の変化に合わせて研究開発拠点の集積を促す頭脳立地法へと引き継がれ、多くの自治体が「リサーチパーク」の整備に力を入れた。
一連の施策は、その時々の社会・経済情勢に応じて役割を果たしたといえるだろう。浜松市や福島県郡山市を中心とする地域では、テクノポリス法で築いた仕組みを現在でも活用している。
ただ、土地の整備や建物を建設する“箱モノ行政”に陥る傾向は強く、新しい科学・技術の種を生み出したのか、国際的に競争力のある産業の基盤となったのか、といった検証はあまりなされていないようだ。
経済産業省が2001年度から始めた「産業クラスター計画」と文部科学省が02年度から始めた「知的クラスター創成事業」は、産学官の連携を重視したもので、施設偏重は多少改まった印象はある。それでも09年度の補正予算のように、各都道府県に産学連携の拠点を整備しようとする発想は根強い。文科省のこの案は、昨秋の事業仕分けで大幅に予算が削減された。知的クラスター創成事業も制度の重複が指摘され、廃止の方針が決まった。
もともと科学や技術は、地域の境界に縛られない性質を備える。大学の研究者や研究助成機関、実用化する企業など「これでやろう」と合意できる人や組織が、所在地にとらわれず機動的に結び付く方がより実践的だ。国による科学・技術政策の支援が都道府県単位では、あまりにも狭すぎる。特に、科学を基盤にした産業の形成を考えるときは、道州制の方が都合がよい。
そう唱えるのは、職業能力開発総合大学校の古川勇二校長だ。隆盛著しいアジア勢と競合できるものづくりの力を備えるためには、付加価値の高い製品開発が不可欠といい、そのための労働人口や企業集積を考えた科学・技術政策を展開すべきだと説く。
例えば、人口40万人の都市で労働人口の比率が6割、そのうちの20%(4万8000人)が製造業に就業する標準的なモデルの場合、部品数で約3000点を扱う製造業を維持するのが限界だと指摘する。部品3000点とは二輪車に相当する。
液晶テレビだと部品数は約1万点、自動車で1万5000点、航空機で20万点……。現実の産業集積はこうした条件をそなえた地域の連合体に移っている。産業への貢献を想定する科学・技術の振興策ならば、こうした動向を踏まえた計画でなければいけないと、古川校長は強調。道州制への移行を強く勧める。
経産・文科両省の事業からは、北海道と関西の定期的な交流会のように、クラスター間で連携しようとする活動が生まれている。昨春には「全国イノベーション推進機関ネットワーク」が立ち上がり、自律的な地域間の協力を支える動きも出てきた。道州単位で地域の特性を伸ばそうとする取り組みが実を結べば、研究が社会に還元されていないという議論にも一石を投じるだろう。
2.沖縄単独州の実現を 小川政務官、沖大で講演(2010年6月13日 琉球新報)
沖縄大学土曜教養講座が12日、那覇市の同大学で開かれ、「沖縄の自立と振興に向けて」と題して総務省の小川淳也総務政務官が講演した。小川氏は「近い将来、絶対に道州制を日本に導入するべきだ。沖縄と北海道は先行して導入に取り組み、他府県を先導する役割を果たしてもらいたい」と持論を展開。沖縄は他府県より先行して道州制を導入し、単独州を実現するよう訴えた。
単独州実現には「県庁と沖縄総合事務局関係の議論は避けて通れない」と指摘。予算総額6千億円で約2万人の職員を抱える県と、職員数千人の総合事務局、4千億円近い沖縄振興開発予算を持つ内閣府の統合を提案。単独州を実現できれば「職員数2万人強で、1兆円の財政規模を持つ、思い切った地域の振興を自らの知恵と努力、責任において実行できる沖縄になる」と主張した。
ヨーロッパの一部自治州には、国法で留保されている規則以外はすべて立法できる「一次立法権」、所得税など一定の範囲内で税率を設定できる「経済立法権」が付与されていると説明。「沖縄が自治州を志すなら、自治立法権なり、財政立法権、自主財政権の付与ぐらいは視野に入れるべきだ」とした。
最後に「そういう全国に先駆けたチャレンジを沖縄には期待したい。その環境づくりを政府として進めなければならない」と述べた。
3.橋下知事が連邦制で質問攻め ドイツ・ヘッセン州首相に(2010年6月18日 47news)
大阪府の橋下徹知事は16日、訪問先のドイツ・ヘッセン州のコッホ首相と同国の連邦制度をめぐり会談、「短所は何ですか?」といった“直球”を交え、首相を質問攻めにした。
橋下氏は、今回の欧州視察の主目的に連邦制研究を挙げていた。出発前、道州制のモデルとする考えを強調し「(長所短所を)肌で感じたい」と意気込みを語っていた。
首相が短所について「教育などで(連邦の)州ごとに格差が生まれる」と回答すると、橋下氏はすかさず「米国なら別だが、ドイツや日本くらいの(人口や国土の)規模で国民は格差を納得すると思うか」「連邦制をやめようという声は?」などと重ねて聞いた。
首相は、国が州ごとの財政調整を行っているとした上で「税収が多い州では、見合った住民サービスがなされず不満も出る」と課題を指摘した。
会談後、橋下氏は「各地域が責任を持つことが国の発展には不可欠と確信した。格差が生じたとしても、連邦制に近い形の分権を進めたい」と述べ、道州制や持論の「大阪都構想」推進への思いを強くした様子だった。
4.横浜の大都市制度に反論、知事「道州制こそ必要」/神奈川(2010年6月18日 神奈川新聞)
松沢成文知事は17日、横浜市などが国に提案するため検討している「大都市制度」について、県(広域自治体)からの独立を目指すという前提や政令市間の実績の差などの課題を挙げて反論し、「道州制の導入こそ、今必要なもの」との持論を展開した。
同日開かれた本会議で、平本敏氏(民主、瀬谷区)の質問に答えた。
横浜市が発表した大都市制度創設の在り方についての基本的な方向性では、「国の成長拠点となる大都市をつくる」が基本姿勢。県から独立した「特別な市」として、大都市は地方の事務をすべて担い、基礎自治体と広域自治体の性格を併せ持つと同時に、圏域の中核都市として広域的な役割を果たすとしている。
知事は、県から完全に分離・独立し、大都市が市域内の地方税を独占する考え方について「県が広域的な行政サービスを提供するための税源を確保できず、広域自治体としての地方自治が根本から成り立たなくなる」と反論。また横浜などのように政令市として長年の実績を持つ自治体と、相模原のようにまだ日が浅い自治体とでは「“都市力”に大きな格差がある」と指摘し、すべてが特別自治市を目指すとする同制度の提案に「無理がある」と反論した。
最後に知事は「今必要なのは、地方自治の在り方を根本的に見直し、新しい国の形を目指す『道州制』の導入の検討を進めるべき」と、自ら長年主張する道州制をアピールした。
5.「一括交付金」国が関与、地方の自由度縮小か(2010年6月20日 読売新聞)
国と地方との関係を見直す地域主権改革の具体策を盛り込んだ政府の「地域主権戦略大綱」最終案の全容が19日、判明した。
目玉政策である地方が自由に使える「一括交付金」をめぐり、中央省庁が交付の計画段階から関与できる内容となっており、原案より地方の自由度が縮小した。政府は21日の地域主権戦略会議(議長・菅首相)に最終案を示し、22日にも大綱を閣議決定したい考えだが、改革は「骨抜き」ともいえ、地方からの反発は必至だ。
一括交付金は、各省庁が使途を決める「ひも付き補助金」に代わる新制度。最終案は、公共事業関係の補助金をまず来年度から一括交付金にし、3〜5年をかけて完全導入を目指すとした。実施にあたっては、「PDCAサイクルを通じて制度の評価・改善を図る」と明記。PDCAは「計画・執行・点検・反映」のことで、計画段階から国が関与できることを意味する。
6.政令市初、大阪市が関西広域連合へ参加 橋下“都構想”に対抗(2010年7月7日 産経新聞)
府県の枠を超えて広域行政を行う関西広域連合(仮称)に、大阪市が設立当初から正式参加する意向を固めたことが6日、分かった。平松邦夫市長が近く表明する。関西広域連合にはこれまで2府5県が参加を表明しているが、政令市では初めて。
関係者によると、これまで大阪府の橋下徹知事が府と市を再編する大阪都構想を提唱していることに、平松市長は強く反発。都市の将来像として、大阪都ではなく、広域の関西州を目指す姿勢を明確に打ち出す狙いがあるという。
平松市長はこれまで「都をつくれば(問題が)解決するわけではない。経済や物流は府県レベルを大きく超えており、関西という広いエリアで考える必要がある」などと言及。市幹部は「広域連合は関西州への移行も想定される。加入が当然だろうと考えた」と述べた。
広域連合に参加表明しているのは京都、大阪、滋賀、兵庫、和歌山、鳥取、徳島の2府5県。議会調整などで足並みがそろわなかったため、当初の想定よりも設立スケジュールは遅れているという。現在は今秋の各府県議会に規約案を提案するための調整が進められている。
|
|
|
|
|
|
|
|
道州制をひろめよう!! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
道州制をひろめよう!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 酒好き
- 170675人
- 2位
- 千葉 ロッテマリーンズ
- 37149人
- 3位
- お洒落な女の子が好き
- 90051人