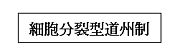こんにちはわいわいです。
勘違いしておりまして、今更6月分をアップします。
よろしくお願いします。
最近の注目情報詳細(2010年6月)
1.「九州府」検討委を市長会設置 委員長に幸山氏(2010年5月13日 熊本日日新聞)
九州市長会は12日、佐賀県嬉野市で会合を開き、道州制導入による「九州府」実現への課題などについて研究する機関として、九州・沖縄8県の26市長で構成する「九州府推進機構準備検討委員会」を設置した。
委員長には幸山政史熊本市長が就任。今後は九州地方知事会や町村会、経済界などとも意見交換しながら、基礎的自治体への権限移譲や税制の在り方、財源などに関して調査・研究を進める。
同日の第1回会合には、メンバーのうち20市長が出席し「道州制による住民のメリットを早めに検討する方が(議論の)スピードは速まる」などの意見が出された。次回は10月に鹿児島市で開催する予定。
九州市長会は2005年から道州制の議論に着手し、06年に「九州府構想報告書」を作成。昨年10月には、制度移行プロセスや課題解決の仕組みなどを提言した「九州府実現計画報告書」を取りまとめている。
2.横浜市が新たな大都市制度の創設に意欲、背景に地方制度の抜本改革へ向けた動向
(2010年5月17日 カナコロ)
1956年に指定都市(政令市)制度が暫定的に創設されて半世紀以上がたち、新たな制度の提起が地方から活発化しつつある。最大の政令市である横浜市が今月中にも県から独立した「大都市制度」の創設を国に要望するほか、指定都市市長会議では府県と同等の「特別自治市」が打ち出された。背景には、90年代に始まった地方分権改革が「未完」に終わったものの、政権交代後、急ピッチで進む地方制度の抜本改革へ向けた動向がある。
「分割ではなく、横浜は大都市でやっていく。一都市として自立していきたい」。横浜市の林文子市長は4月下旬の定例会見で、市と市会が検討を進めていた新たな大都市制度の創設をめぐり、その実現に意欲を示した。企業経営出身の林市長は、「国の成長拠点」としての横浜市の再構築に意欲があるとみられる。
政令市は広域自治体(府県)とほぼ同等の権限を持つが、あくまで政令による「特例」。まちづくり、教育、子育て、福祉、医療など市民生活とかかわりが深いさまざまな分野で重複行政が続いている。こうした状況を踏まえ、横浜市はいち早く、「暫定措置」として適用された政令市制度に一石を投じる行動に出た。「地域主権」を掲げる民主党政権の誕生の前から、市会に特別委員会を設け政令市制度に代わる新たな「大都市制度」の調査研究に着手。
今月6日に市会特別委に報告されたその基本的方向性では、「広域自治体(県)から独立した総合性と自立性の高い自治体」を目指す考えを鮮明に打ち出した。「スピード感を持って取り組んでいきたい」。基本的方向性を受け、林市長は現場に指示。11日に開かれた政令市長会議でも、大都市制度の実現へ積極的な発言が目立った。
横浜市が国に“先手”を打つ形で、新たな地方制度の在り方を提起する背景には、地方自治をめぐる国の新たな動向がある。政権交代後、政府は今夏をフェーズ1、2013年をフェーズ2として地方主権戦略の具体化を進めている。
同市が着目するのは、その集大成となる「地方政府基本法」の制定。国と地方の権限と財源の在り方について抜本的な制度改正が想定されるが、「自治体の規模の在り方については今後の議論になる」(横浜市大都市制度・地方分権推進課)。
本格議論の開始に先立って、新たな大都市像を示すという横浜市をはじめとした政令市からの発信は、道州制も含め地方制度をめぐる議論が多様化する中で、現行の人口規模を維持しながら「生き残り」を目指すという側面も持つ。二重行政を解決して行政を効率化し、国の成長拠点を形成する―。大都市制度の創設は、国の在り方の表裏ともいえる。
3.次期通常国会に道州制推進基本法 総務相(2010年5月19日 産経新聞)
行政区分を現在の都道府県制ではなく、道や州で大きく分ける道州制の議論が深まってきた。原口一博総務相は19日、次期通常国会に推進基本法案を提出する考えを表明。経済同友会も同日、道州制を導入する場合は東京23区を「東京特別州」として切り離し、国の特別会計を地方に移管し、それ以外の既存債務は「債務返済機構」を創設して返済すべきだという提言を発表した。いずれも政府が6月にまとめる地域主権戦略大綱をにらんだ動きだ。
原口総務相は同日午前、日本経団連の御手洗冨士夫会長との会談で、「地域主権戦略大綱に経済界の議論の成果を盛り込み、来年の法案につなげたい」と述べた。道州制では日本経団連が今年4月にまとめた成長戦略で基本法制定の必要性を明記しているが、民主党は昨年の衆院選時のマニュフェストで「将来的な導入も検討」「地域の自主的判断を尊重する」との表現にとどめていた。総務相発言はこれより踏み込んだものになる。
原口総務相は「経済成長を経験したことのない人が社会に出る時代だ。これまでのしがらみを捨てなければならず、道州制などが大きな課題になる」と指摘。会談後、記者団に法案の具体的な内容について「これからの議論だ。(道州制を希望する地域が)手を挙げる方式でやりたい」と述べた。基本法制定に向けては地方への権限移譲の進め方や、移譲の受け皿になる地方組織のあり方などが議論される見通しだ。
一方、経済同友会は道州制導入にあたり、総人口の1割が居住し、国の税収全体の4割を納めている東京は「他の地域と切り離して考える必要がある」(池田弘一副代表幹事・アサヒビール相談役)として、23区内を「東京特別州」に改変することを提言。また、国から地方に税源が移譲されることから国の長期債務返済に支障を期さないよう、債務返済機構を創設すべきだとしている。
4.『東京特別州』23区再編提言 同友会(2010年5月20日 東京新聞)
地域主権型の道州制導入について研究している経済同友会の地方行財政改革委員会(委員長・池田弘一アサヒビール相談役)は十九日、現在の東京二十三区を改編し、「東京特別州」を創設するよう求める政策提言を発表した。総務省や財務省に提出する。
提言では、二十三区を特別州に移行するとともに、現在の区は「行政事務の役割に応じて適正規模に再編する」とした。二十三区以外の市町村は「他の道州に組み入れる」として特別州からは除外する方向を提案した。
道州制論議の中で、巨額な税収入を誇る東京二十三区の扱いは大きな焦点の一つ。経済界では東京商工会議所が二〇〇八年秋、新たに東京二十三区一体で「東京市」を発足させる提言をまとめ、都議会などに波紋を広げた経緯がある。
5.地域主権戦略 骨子では「自立と創造」も権限移譲は難航か(2010年5月24日 毎日新聞)
政府は24日、首相官邸で地域主権戦略会議(議長、鳩山由紀夫首相)を開き、6月末に策定する「地域主権戦略大綱(仮称)」の骨子をまとめた。地域主権改革を、国民が自らの地域を自らの責任で作っていく「責任の改革」と位置づけ、「自立と創造」への転換をうたった。しかし、出先機関の原則廃止に向けた同日の公開ヒアリングでも、府省側は権限移譲に消極的で、高まいな理念の具体化は難航している。
骨子は地域主権改革の理念として、(1)国と地方は対等なパートナーシップへ転換(2)住民に身近な基礎自治体を重視−−などを提起。改革に伴い、自治体間で行政サービスの競争が始まることから、「首長と議会を選ぶ住民の判断と責任は重大」と指摘し、地方自治への有権者の責任も盛り込んだ。
国が使途を特定する「ひも付き補助金」の一括交付金化では、首相が会議で「省庁の枠組みを越える一括交付金をつくり上げ、個所付けを廃止したい」と述べ、使途の自由度を高める考えを示した。ただ、一括交付金化や出先機関改革の具体論は先送りされている。
一方、同会議では都道府県から市町村への権限移譲の状況についても報告された。「見直しを実施する」との回答が、事務権限384条項中207条項(54%)にほぼ倍増。しかし、前回ゼロ回答だった農林水産省は、12条項のうち農地の権利移動の許可の1条項(8%)のみ。同じくゼロだった環境省も57条項中16条項(28%)の見直しにとどまった。
戦略会議に先立ち、政府は出先機関の事務・権限仕分けに向けた各府省や地方6団体の代表らによる公開ヒアリングを開催。経済産業省は「経済産業局は必要不可欠」、厚生労働省は「ハローワークの地方移管は国際条約に違反する」など事実上のゼロ回答で、出先機関の廃止に各府省の抵抗が目立った。【笈田直樹】
6.地制調の廃止検討(2010年5月26日 朝日新聞)
平野文博官房長官は25日の衆院本会議で、学者や自治体の首長、国会議員らでつくる政府の地方制度調査会について「昨年7月以降、委員が任命されていない。廃止を含めて見直しを検討する」と述べた。
地制調は1952年に発足、道州制や市町村合併のあり方について政府に答申してきた。鳩山政権は、原口一博総務相が議長を務める「地方行財政検討会議」で地方自治法の抜本改正を検討しており、地制調は役割を終えたと判断した。自民党の石田真敏議員の質問に答えた。
勘違いしておりまして、今更6月分をアップします。
よろしくお願いします。
最近の注目情報詳細(2010年6月)
1.「九州府」検討委を市長会設置 委員長に幸山氏(2010年5月13日 熊本日日新聞)
九州市長会は12日、佐賀県嬉野市で会合を開き、道州制導入による「九州府」実現への課題などについて研究する機関として、九州・沖縄8県の26市長で構成する「九州府推進機構準備検討委員会」を設置した。
委員長には幸山政史熊本市長が就任。今後は九州地方知事会や町村会、経済界などとも意見交換しながら、基礎的自治体への権限移譲や税制の在り方、財源などに関して調査・研究を進める。
同日の第1回会合には、メンバーのうち20市長が出席し「道州制による住民のメリットを早めに検討する方が(議論の)スピードは速まる」などの意見が出された。次回は10月に鹿児島市で開催する予定。
九州市長会は2005年から道州制の議論に着手し、06年に「九州府構想報告書」を作成。昨年10月には、制度移行プロセスや課題解決の仕組みなどを提言した「九州府実現計画報告書」を取りまとめている。
2.横浜市が新たな大都市制度の創設に意欲、背景に地方制度の抜本改革へ向けた動向
(2010年5月17日 カナコロ)
1956年に指定都市(政令市)制度が暫定的に創設されて半世紀以上がたち、新たな制度の提起が地方から活発化しつつある。最大の政令市である横浜市が今月中にも県から独立した「大都市制度」の創設を国に要望するほか、指定都市市長会議では府県と同等の「特別自治市」が打ち出された。背景には、90年代に始まった地方分権改革が「未完」に終わったものの、政権交代後、急ピッチで進む地方制度の抜本改革へ向けた動向がある。
「分割ではなく、横浜は大都市でやっていく。一都市として自立していきたい」。横浜市の林文子市長は4月下旬の定例会見で、市と市会が検討を進めていた新たな大都市制度の創設をめぐり、その実現に意欲を示した。企業経営出身の林市長は、「国の成長拠点」としての横浜市の再構築に意欲があるとみられる。
政令市は広域自治体(府県)とほぼ同等の権限を持つが、あくまで政令による「特例」。まちづくり、教育、子育て、福祉、医療など市民生活とかかわりが深いさまざまな分野で重複行政が続いている。こうした状況を踏まえ、横浜市はいち早く、「暫定措置」として適用された政令市制度に一石を投じる行動に出た。「地域主権」を掲げる民主党政権の誕生の前から、市会に特別委員会を設け政令市制度に代わる新たな「大都市制度」の調査研究に着手。
今月6日に市会特別委に報告されたその基本的方向性では、「広域自治体(県)から独立した総合性と自立性の高い自治体」を目指す考えを鮮明に打ち出した。「スピード感を持って取り組んでいきたい」。基本的方向性を受け、林市長は現場に指示。11日に開かれた政令市長会議でも、大都市制度の実現へ積極的な発言が目立った。
横浜市が国に“先手”を打つ形で、新たな地方制度の在り方を提起する背景には、地方自治をめぐる国の新たな動向がある。政権交代後、政府は今夏をフェーズ1、2013年をフェーズ2として地方主権戦略の具体化を進めている。
同市が着目するのは、その集大成となる「地方政府基本法」の制定。国と地方の権限と財源の在り方について抜本的な制度改正が想定されるが、「自治体の規模の在り方については今後の議論になる」(横浜市大都市制度・地方分権推進課)。
本格議論の開始に先立って、新たな大都市像を示すという横浜市をはじめとした政令市からの発信は、道州制も含め地方制度をめぐる議論が多様化する中で、現行の人口規模を維持しながら「生き残り」を目指すという側面も持つ。二重行政を解決して行政を効率化し、国の成長拠点を形成する―。大都市制度の創設は、国の在り方の表裏ともいえる。
3.次期通常国会に道州制推進基本法 総務相(2010年5月19日 産経新聞)
行政区分を現在の都道府県制ではなく、道や州で大きく分ける道州制の議論が深まってきた。原口一博総務相は19日、次期通常国会に推進基本法案を提出する考えを表明。経済同友会も同日、道州制を導入する場合は東京23区を「東京特別州」として切り離し、国の特別会計を地方に移管し、それ以外の既存債務は「債務返済機構」を創設して返済すべきだという提言を発表した。いずれも政府が6月にまとめる地域主権戦略大綱をにらんだ動きだ。
原口総務相は同日午前、日本経団連の御手洗冨士夫会長との会談で、「地域主権戦略大綱に経済界の議論の成果を盛り込み、来年の法案につなげたい」と述べた。道州制では日本経団連が今年4月にまとめた成長戦略で基本法制定の必要性を明記しているが、民主党は昨年の衆院選時のマニュフェストで「将来的な導入も検討」「地域の自主的判断を尊重する」との表現にとどめていた。総務相発言はこれより踏み込んだものになる。
原口総務相は「経済成長を経験したことのない人が社会に出る時代だ。これまでのしがらみを捨てなければならず、道州制などが大きな課題になる」と指摘。会談後、記者団に法案の具体的な内容について「これからの議論だ。(道州制を希望する地域が)手を挙げる方式でやりたい」と述べた。基本法制定に向けては地方への権限移譲の進め方や、移譲の受け皿になる地方組織のあり方などが議論される見通しだ。
一方、経済同友会は道州制導入にあたり、総人口の1割が居住し、国の税収全体の4割を納めている東京は「他の地域と切り離して考える必要がある」(池田弘一副代表幹事・アサヒビール相談役)として、23区内を「東京特別州」に改変することを提言。また、国から地方に税源が移譲されることから国の長期債務返済に支障を期さないよう、債務返済機構を創設すべきだとしている。
4.『東京特別州』23区再編提言 同友会(2010年5月20日 東京新聞)
地域主権型の道州制導入について研究している経済同友会の地方行財政改革委員会(委員長・池田弘一アサヒビール相談役)は十九日、現在の東京二十三区を改編し、「東京特別州」を創設するよう求める政策提言を発表した。総務省や財務省に提出する。
提言では、二十三区を特別州に移行するとともに、現在の区は「行政事務の役割に応じて適正規模に再編する」とした。二十三区以外の市町村は「他の道州に組み入れる」として特別州からは除外する方向を提案した。
道州制論議の中で、巨額な税収入を誇る東京二十三区の扱いは大きな焦点の一つ。経済界では東京商工会議所が二〇〇八年秋、新たに東京二十三区一体で「東京市」を発足させる提言をまとめ、都議会などに波紋を広げた経緯がある。
5.地域主権戦略 骨子では「自立と創造」も権限移譲は難航か(2010年5月24日 毎日新聞)
政府は24日、首相官邸で地域主権戦略会議(議長、鳩山由紀夫首相)を開き、6月末に策定する「地域主権戦略大綱(仮称)」の骨子をまとめた。地域主権改革を、国民が自らの地域を自らの責任で作っていく「責任の改革」と位置づけ、「自立と創造」への転換をうたった。しかし、出先機関の原則廃止に向けた同日の公開ヒアリングでも、府省側は権限移譲に消極的で、高まいな理念の具体化は難航している。
骨子は地域主権改革の理念として、(1)国と地方は対等なパートナーシップへ転換(2)住民に身近な基礎自治体を重視−−などを提起。改革に伴い、自治体間で行政サービスの競争が始まることから、「首長と議会を選ぶ住民の判断と責任は重大」と指摘し、地方自治への有権者の責任も盛り込んだ。
国が使途を特定する「ひも付き補助金」の一括交付金化では、首相が会議で「省庁の枠組みを越える一括交付金をつくり上げ、個所付けを廃止したい」と述べ、使途の自由度を高める考えを示した。ただ、一括交付金化や出先機関改革の具体論は先送りされている。
一方、同会議では都道府県から市町村への権限移譲の状況についても報告された。「見直しを実施する」との回答が、事務権限384条項中207条項(54%)にほぼ倍増。しかし、前回ゼロ回答だった農林水産省は、12条項のうち農地の権利移動の許可の1条項(8%)のみ。同じくゼロだった環境省も57条項中16条項(28%)の見直しにとどまった。
戦略会議に先立ち、政府は出先機関の事務・権限仕分けに向けた各府省や地方6団体の代表らによる公開ヒアリングを開催。経済産業省は「経済産業局は必要不可欠」、厚生労働省は「ハローワークの地方移管は国際条約に違反する」など事実上のゼロ回答で、出先機関の廃止に各府省の抵抗が目立った。【笈田直樹】
6.地制調の廃止検討(2010年5月26日 朝日新聞)
平野文博官房長官は25日の衆院本会議で、学者や自治体の首長、国会議員らでつくる政府の地方制度調査会について「昨年7月以降、委員が任命されていない。廃止を含めて見直しを検討する」と述べた。
地制調は1952年に発足、道州制や市町村合併のあり方について政府に答申してきた。鳩山政権は、原口一博総務相が議長を務める「地方行財政検討会議」で地方自治法の抜本改正を検討しており、地制調は役割を終えたと判断した。自民党の石田真敏議員の質問に答えた。
|
|
|
|
|
|
|
|
道州制をひろめよう!! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
道州制をひろめよう!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 大人のmixi【おとミク】
- 6471人
- 2位
- 食べ物写真をつい撮ってしまう人
- 19249人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208305人