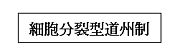最近の注目情報詳細(2010年2月)
1.地方に課税・立法権 橋下知事、地方政府基本法私案を提示
(2010年1月14日 産経新聞)
大阪府が国と地方のあり方を抜本的に見直すために提唱を検討していた「地方政府基本法」をめぐり、橋下徹知事は14日、政府の地域主権戦略会議の準備会合に出席し、基本法制定に向けた独自案を提示した。地方側に課税権や立法権を地方に与える改革案で、橋下知事は「国と地方の形を根本から作り直す法にすべきだ」と訴えた。
会合は非公開で、橋下知事のほか、原口一博総務相、上田清司埼玉県知事らが出席して意見交換。橋下知事は私案をまとめた50ページ近くの文書を「検討中資料」として提示し、「総務省顧問に就任したときから考えていた。今後の議論の参考にしてほしい」と述べた。
私案では政令指定都市の解消などを提言。地方自治体を都道府県を拡大した広域地方政府と、市町村レベルの基礎地方政府に再編することなどを記している。 中央政府が外交や防衛といった国家戦略に特化するのに対し、広域地方政府は道州制を見据えて産業育成やインフラ整備、雇用政策などを実施。基礎地方政府は、地域雇用の確保をはじめ、保育所整備や介護など市民生活に近い行政サービスを行う構想となっている。
また、地方の財政基盤を強化するため、法改正を進め、税財政自主権と自主立法権を確立。税源移譲を進め、地方が自由に税率を決めたり、条例で法令変更をできるようにするという。
さらに、予算編成に議員が参画する議会内閣制の導入や、教育委員会制度改革、公会計制度改革にも踏み込んでおり、地方自治法や地方公務員法の抜本的改正を求めている。
2.関西2府5県広域連合誕生へ 「道州制」モデルケースに発展か
(2010年1月19日 J-CASTニュース)
都道府県の枠を超え、自治体同士が連携する初の広域行政組織「関西広域連合」(仮称)が2010年内にも誕生することになった。大阪、京都、兵庫、滋賀、和歌山、徳島、鳥取の2府5県が同連合を設立することで、このほど合意した。
鳩山内閣は「地域主権」を掲げ、首相を議長とする「地域主権戦略会議」を内閣府に設置し、自治体への権限移譲や国の出先機関の統廃合などの基本方針を「地域主権戦略大綱」として、今夏にまとめることになっている。全国初の関西広域連合が地方分権の受け皿となるのは間違いない。将来的には「道州制」の是非を論議するモデルケースに発展する可能性もある。
ドクターへリの運用がメリット第一号
関西広域連合が想定する広域行政として、最も具体的なメリットが期待されるのは、ドクターヘリコプター(ドクターへり)の運用だ。遠隔地で自動車事故や急病人が発生した場合、医師が乗り込んだヘリコプターが現地に駆け付け、患者の応急処置を進めながら病院に搬送するシステムだが、単独の府県単位では維持費がかかるため、実用化は困難だった。 しかし、近隣同士で分担しながら運営すれば、実現は可能というわけだ。
このように関西広域連合を構成予定の7府県は、府県境を越えて防災や観光、医療など7分野の事務でスタートする方針で一致した。防災では地震や水害など災害発生時に府県間で応援救助体制を強化するほか、観光では各府県の観光資源を生かした集客などで連携するという。
自治体の広域連合は地方自治法で認められた制度で、市町村レベルでは消防や病院、港湾などを複数の市町村が共同で管理・運営する「一部事務組合」が全国各地に存在する。複数の都道府県で構成する初の広域連合は、この一部事務組合の都道府県バージョンとなる。
奈良県は「現段階ではメリットが分からない」
一部事務組合には予算などをチェックする議会が必要で、関西広域連合も7府県が広域連合について話し合う「連合議会」を構成することになる。トップの連合長は知事の互選となり、任期は2年。連合議会は府県議20人で構成し、人口に応じて大阪5▽兵庫4▽京都3▽残る4県が各2――に振り分けることも決まった。
実際の関西広域連合の運営や予算は、この議会が決定することになるため、自治体によっては広域連合の参加に温度差があるのは事実だ。た7府県のうち、徳島、鳥取両県は一部の事務のみ参加を表明。三重、福井両県はオブザーバーとして加わることになった。奈良県は「現段階ではメリットが分からない」として参加を見送った。
大阪府の橋下徹知事は会見で「関西広域連合が『関西州』になることはありえないが、関西州の入り口、片鱗をお見せできる実験モデルと位置付けて考えている」と述べている。年内にも発足する全国初の都道府県連合が、どんな具体的な成果を発揮するのか――。広域連合は関西が試金石となり、首都圏など全国に発展する可能性が高いだけに注目される。
※「関西広域連合」ホームページ
http://
<関連記事>
イ、首都圏に勝てる「大関西圏構想」を 目指せ「坂の上の雲」(2010年1月16日 産経新聞)
「もう四国、中国の枠組みにこだわっている時代じゃない」−。8日、関西周辺の知事らが大阪市で開いた「関西広域連合」の設立準備部会の閉会後、広域連合への参加を表明した徳島県の飯泉嘉門知事は、報道陣にこう語った。
関西といえば、一般的に大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県の2府4県を指す場合が多い。しかし、四国地方の徳島県と中国地方の鳥取県が名乗りを上げたことに全国の関心が集まっている。
「中・四国でも広域行政が盛り上がる突破口になればと思ったのが、加わった理由」と説明する飯泉知事。当初は、飯泉知事の“スタンドプレー”に四国知事会でも衝撃が走ったが、最近は「前向きにとらえられるようになった」という。
準備部会では、大阪、兵庫、京都、滋賀、和歌山、鳥取、徳島の2府5県が関西広域連合の設立に合意した。複数の都道府県で構成する全国初の広域連合は、国からの権限委譲の受け皿となる地方分権の担い手と位置づけられている。
なぜ、関西は地方分権にこだわるのか。関西は、首都圏とは一線を画した独自の経済圏を形作ってきたが、近年は企業の東京移転や工場の海外流出で、著しい地盤沈下に見舞われている。事実、日本の国内総生産(GDP)に占める関西の比率は2割を切り、4割弱を占める首都圏とは大きく水をあけられている。
このため、広域連合を「東京一極集中」に対抗するための起爆剤と期待する声は大きい。飯泉知事は「2府4県では、首都圏に勝てない。だから、中・四国地方も(関西広域連合に)入っていいんじゃないか」と主張する。「大関西」をつくるべきだとの考え方だ。
ただ、各府県知事は広域連合の設立には合意したものの、設立のタイムスケジュールには温度差がある。政府の地域戦略会議が今夏にも「地域主権戦略大綱」を策定することから、大阪府の橋下徹知事は「夏までに広域連合を発足し、国に分権を迫ることが大事」と主張。これに対し、滋賀県の嘉田由紀子知事らは「議会の理解を得るためには時間が必要」と慎重姿勢を見せた。
だが、関西の動きに触発されたのか、首都圏でも広域連合に向けた動きが盛り上がってきた。広域連合の発足で首都圏に後れを取れば、関西のまとまりの悪さを露呈することになり、もはや首都圏への対抗手段がなくなってしまうかもしれない。
閉会後の記者会見で、橋下知事は「(設立が遅れれば)地域主権の大きな流れに乗りきれない」と焦燥感をあらわにした。
広域連合の設立に尽力してきた関西広域機構の秋山喜久会長は、昨年末にテレビドラマ化された司馬遼太郎氏の小説「坂の上の雲」を引き合いに出し、「雲がない時代になり、自分たちで地域主権という大きな雲をつくった。経済界としても、国の閉塞(へいそく)感を打破するきっかにしてほしい」とエールを送った。
ロ、関西広域連合 北海道・東北も関心を(2010年1月27日 北海道新聞 社説)
鳩山由紀夫政権が掲げる「地域主権」を見据え、一足早く動きだしたとみるべきだろう。
大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀、徳島、鳥取の2府5県が、府県を超えた広域行政を担う「関西広域連合」(仮称)の設立で基本合意した。
都道府県レベルでの広域連合は、実現すれば全国初のケースとなる。国から地方への権限移譲の受け皿づくりを視野に、国の出先機関の統廃合などにも対応できる態勢整備が期待される。
明治維新以前の「国・藩」や府県の歴史を考えれば、お互いの垣根を取り除く難しさはあろう。しかし成功すれば、地方の発想に根ざした分権実現のけん引役になりうる。
分権の受け皿について、北海道ではこれまで、単独の道州制移行論議が主流となってきた。
だからといって、他県との広域連合を最初から排除する必要はない。
対岸の青森県や岩手県、秋田県などと、広域連合のメリット、デメリットについて十分に協議を重ね、自治の選択肢を広げておきたい。
関西連合は今秋にも発足する見通しだ。当初は医療連携、防災、観光・文化振興、産業振興、環境保全、資格試験・免許、職員研修の計7分野で広域事務を実施する。
国道や河川の一体管理も視野に入れている。事務効率化に加え、将来は関西国際、伊丹、神戸の3空港の並立など、複数府県にまたがる問題の調整に道を開く可能性もある。
徳島、鳥取両県は部分参加の見通しだ。道州制と違って、こうした柔軟な対応ができるのも広域連合の特徴といえる。
道州制の課題とされる道都、州都をめぐる綱引きも避けられる。
初の試みだけに、実際に動きだせば想定外の問題点が浮かび上がってくるかもしれない。
それでも、国の意思決定に従うだけの「待ち」の姿勢とは違った、7府県の意欲は評価できる。
北海道と東北の間にも、道と東北6県、新潟県で構成する知事会議や、道と北東北3県との知事サミットがある。
知事サミットの4道県は、縄文遺跡群の世界遺産登録推進などの実績も残してきた。ここでさらに一歩、踏み込んで考えてはどうか。
国の出先機関の見直し方針で、開発局の将来は不透明だ。ならば広域連合をてこに、出先機関見直しに先んじて、道県側から望ましい権限移譲を進める発想があってもいい。
協力できる分野は少なくない。東北各県に比べて人口、面積とも飛び抜けている北海道のリーダーシップに期待したい。
3.地方行財政検討会議が初会合 財源移譲議論
(2010年1月20日 産経新聞)
総務省は20日、地域主権(地方分権)改革の具体策を議論する「地方行財政検討会議」(議長・原口一博総務相)の初会合を開いた。国から地方への財源・権限の移譲に関する論点を整理する。11月までにまとめた論点について、来年3月に国会提出予定の地方自治法改正案に反映させる方針だ。
同会議には、原口総務相ら政務三役(4人)、達増拓也岩手県知事ら地方自治体関係者(8人)、石原俊彦関西学院大教授ら有識者(6人)ら計18人が参加。11月までに計7回会議を開き、主に(1)自治体の基本構造のあり方(2)住民参加のあり方(3)財務会計制度・財政運営の見直し(4)自治体の自由度の拡大(規制緩和)−をテーマに論点整理する。また、神奈川県の松沢成文知事、大阪府の橋下徹知事からそれぞれ提案があった改革私案も議論のたたき台とする考え。
同会議で議長役をつとめる原口総務相は、初会合の冒頭で「地域主権改革は鳩山政権の『一丁目一番地』だ。ここでご提案いただいたもので、できるものから即実行に移したい」とあいさつした。
4.地域主権型道州制へ本格論議
4月めどに政策立案 党推進本部が初会合 チーム3000の力を結集
(2010年1月22日 公明新聞)
公明党地方分権・地域主権推進本部(本部長=井上義久幹事長)は21日、東京都新宿区の公明会館で初会合を開き、公明党がめざす「地域主権型道州制」の導入に向けた本格的議論をスタートした。井上幹事長、斉藤鉄夫政務調査会長をはじめ、多数の国会議員、地方議員が出席した。
席上、井上幹事長は、日本の今後の課題として、貧困や格差の問題に対応するための所得再配分機能の再構築や、日本全体の成長戦略の推進と、それに伴う日本の統治機構改革の必要性を指摘。
その上で、昨年(2009年)12月に発表した党の新ビジョン(山口ビジョン)に基づき、現在の中央集権型から「地域主権型道州制」への移行をめざす考えを示した。
これに関して、井上幹事長は「(具体的に)どう推進していくかが課題だ」と述べる一方、「公明党らしさを発揮できる分野だ」とし、“チーム3000”の力を結集して取り組む考えを強調した。
同推進本部では、今後、学識経験者や各種団体との意見交換を行うほか、党の地方議員の意見を集約した上で、4月をめどに具体的な政策の取りまとめを行うことを決めた。
都市部と地方の格差、官僚機構の弊害、各地域における住民のニーズ(要望)の多様化などで、中央集権型の行政の限界が指摘される中、地方への税財源や権限の移譲、国の出先機関の統廃合など統治機構の改革が課題になっている。
公明党は、昨年の衆院選マニフェスト(政策綱領)で、新しい国のかたちとして「国―道州―基礎自治体」の3層構造による地域主権型道州制の実現を提唱。国がすべてを決める統治機構から、各地域が主体的に政策遂行できる体制への脱却をめざすとしている。
5.東北州へ地方議員結束 超党派「政治家連盟」4月発足
(2010年1月25日 河北新聞)
地域主権型道州制を実現しようと、東北6県の超党派の地方議員が「東北州政治家連盟」を4月に発足させる。東北州の行財政体系や政策を検討し、地域経営のビジネスモデルを確立する本格的な推進グループを目指す。全国の地方議員にも取り組みが波及するとみられる。
東北6県の県議、市町村議、町長ら30人が昨年12月、準備会を設立した。3月中旬までに各県30人以上の参加を目標とし、地方議員や市町村長、政治家志望者らに入会を呼び掛けている。
政治家連盟は、民間人などでつくる地域主権型道州制国民協議会(会長・江口克彦PHP総合研究所社長)の構成組織として結成。4月上旬に予定している設立総会には江口会長を招き、シンポジウムを開催する。
発足後は教育、産業などテーマごとに部会を設ける。大学教授や経済人、地域住民を交え、東北州政府に必要な組織、行財政制度、知事や議員の選挙方法、各地域の振興策などを話し合う。
各部会の検討状況はホームページや新聞広告で公表する。最終的には、政治家連盟として東北州の具体像を住民に示す。
国民協議会によると、地域主権型道州制を推進する地方政治家集団の発足は全国で初めて。村橋孝嶺理事長は「国の形を地域主権型に変えるのは国会議員には無理。党派を超え、地方議員が一つの旗の下に集まった意義は大きい」と歓迎する。
夏の参院選や2011年4月の統一地方選で、立候補者に道州制の賛否を問うアンケートを実施し、結果を有権者に公表することも検討する。
準備会世話人代表の菊地文博宮城県議(民主党)は「道州制導入が決まったらすぐ移行できるよう、東北州の仕組みや政策をきめ細かく考えておきたい。平成維新は東北が発信源になる」と話している。
[地域主権型道州制] 単なる都道府県の合併と違い、国の役割を外交や安全保障などに限定し、住民生活にかかわる内政は道州や市町村が担う仕組み。中央集権システムは廃止され、地方は自ら住民から税金を集めて使い道も決める。
6.論戦:道州制 改革か、逆行か
(2010年2月3日 毎日新聞)
2日の衆院代表質問では道州制などでも論戦が繰り広げられた。 「みんなの党はみんなで坂本龍馬をやっています」と切り出したみんなの党の渡辺喜美代表。明治維新の廃藩置県を引き合いに、道州制導入への意欲を鳩山由紀夫首相にただした。
渡辺氏「今必要なのは廃県置州、すなわち地域主権型道州制に変えることだ」
首相「地域主権は道州制にとどまらない。基礎自治体(市町村)が自分たちのことは自分たちでやる方法に変える」
渡辺氏はさらに菅直人副総理兼財務相のまとめた新成長戦略の基本方針を批判するなど鳩山政権の「改革」の手ぬるさを指摘した。たまらず菅氏が答弁の最後に渡辺氏に語りかけた。
菅氏「まだまだ試行錯誤があることはその通り。しかし、ぜひとも渡辺代表には、歴史の流れを逆行させる勢力に取り込まれることがないよう期待します」
7.道州制に期待と不安、中国5県住民調査
(2010年2月4日 山陰中央新報)
山陰両県を含む中国5県内にある6つのシンクタンクが3日、共同で行った地方分権や道州制に関する住民意識調査の報告会を広島市内で開いた。市町村合併に対する評価が割れると同時に、道州制にも期待と不安が交錯するなど、地方分権に対する多様な考え方が浮き彫りになった。
共同調査は、6つのシンクタンクが昨年7〜9月に、各県内の住民グループの代表や企業の経営者ら計約110人対し、聞き取りで行った。
このうち、市町村合併について、山陰経済経営研究所(松江市)の泉洋一主任調査役は、ごみ処理や育児などで、サービスは高水準、料金は低水準に統一され、プラス効果があった半面、「細かな行政サービスが減り、行政が身近な存在でなくなった」と指摘。役場の統合や職員削減によるマイナス面を感じる住民が少なくないとした。
さらに、道州制をめぐっても、積極論と慎重論が入り交じった。広島県内のシンクタンクは「道州制に備え、市町村の規模をさらに拡大すべき」との意見を紹介した。
一方、とっとり地域連携・総合研究センター(鳥取市)の田渕康修研究員は「人口の少ない鳥取県は周辺部となり、衰退すると憂慮されている」と報告。山陰経済経営研究所の泉氏も「地域でさらに議論を深め、意見を集約すべき」といった声が多かったと述べた。
1.地方に課税・立法権 橋下知事、地方政府基本法私案を提示
(2010年1月14日 産経新聞)
大阪府が国と地方のあり方を抜本的に見直すために提唱を検討していた「地方政府基本法」をめぐり、橋下徹知事は14日、政府の地域主権戦略会議の準備会合に出席し、基本法制定に向けた独自案を提示した。地方側に課税権や立法権を地方に与える改革案で、橋下知事は「国と地方の形を根本から作り直す法にすべきだ」と訴えた。
会合は非公開で、橋下知事のほか、原口一博総務相、上田清司埼玉県知事らが出席して意見交換。橋下知事は私案をまとめた50ページ近くの文書を「検討中資料」として提示し、「総務省顧問に就任したときから考えていた。今後の議論の参考にしてほしい」と述べた。
私案では政令指定都市の解消などを提言。地方自治体を都道府県を拡大した広域地方政府と、市町村レベルの基礎地方政府に再編することなどを記している。 中央政府が外交や防衛といった国家戦略に特化するのに対し、広域地方政府は道州制を見据えて産業育成やインフラ整備、雇用政策などを実施。基礎地方政府は、地域雇用の確保をはじめ、保育所整備や介護など市民生活に近い行政サービスを行う構想となっている。
また、地方の財政基盤を強化するため、法改正を進め、税財政自主権と自主立法権を確立。税源移譲を進め、地方が自由に税率を決めたり、条例で法令変更をできるようにするという。
さらに、予算編成に議員が参画する議会内閣制の導入や、教育委員会制度改革、公会計制度改革にも踏み込んでおり、地方自治法や地方公務員法の抜本的改正を求めている。
2.関西2府5県広域連合誕生へ 「道州制」モデルケースに発展か
(2010年1月19日 J-CASTニュース)
都道府県の枠を超え、自治体同士が連携する初の広域行政組織「関西広域連合」(仮称)が2010年内にも誕生することになった。大阪、京都、兵庫、滋賀、和歌山、徳島、鳥取の2府5県が同連合を設立することで、このほど合意した。
鳩山内閣は「地域主権」を掲げ、首相を議長とする「地域主権戦略会議」を内閣府に設置し、自治体への権限移譲や国の出先機関の統廃合などの基本方針を「地域主権戦略大綱」として、今夏にまとめることになっている。全国初の関西広域連合が地方分権の受け皿となるのは間違いない。将来的には「道州制」の是非を論議するモデルケースに発展する可能性もある。
ドクターへリの運用がメリット第一号
関西広域連合が想定する広域行政として、最も具体的なメリットが期待されるのは、ドクターヘリコプター(ドクターへり)の運用だ。遠隔地で自動車事故や急病人が発生した場合、医師が乗り込んだヘリコプターが現地に駆け付け、患者の応急処置を進めながら病院に搬送するシステムだが、単独の府県単位では維持費がかかるため、実用化は困難だった。 しかし、近隣同士で分担しながら運営すれば、実現は可能というわけだ。
このように関西広域連合を構成予定の7府県は、府県境を越えて防災や観光、医療など7分野の事務でスタートする方針で一致した。防災では地震や水害など災害発生時に府県間で応援救助体制を強化するほか、観光では各府県の観光資源を生かした集客などで連携するという。
自治体の広域連合は地方自治法で認められた制度で、市町村レベルでは消防や病院、港湾などを複数の市町村が共同で管理・運営する「一部事務組合」が全国各地に存在する。複数の都道府県で構成する初の広域連合は、この一部事務組合の都道府県バージョンとなる。
奈良県は「現段階ではメリットが分からない」
一部事務組合には予算などをチェックする議会が必要で、関西広域連合も7府県が広域連合について話し合う「連合議会」を構成することになる。トップの連合長は知事の互選となり、任期は2年。連合議会は府県議20人で構成し、人口に応じて大阪5▽兵庫4▽京都3▽残る4県が各2――に振り分けることも決まった。
実際の関西広域連合の運営や予算は、この議会が決定することになるため、自治体によっては広域連合の参加に温度差があるのは事実だ。た7府県のうち、徳島、鳥取両県は一部の事務のみ参加を表明。三重、福井両県はオブザーバーとして加わることになった。奈良県は「現段階ではメリットが分からない」として参加を見送った。
大阪府の橋下徹知事は会見で「関西広域連合が『関西州』になることはありえないが、関西州の入り口、片鱗をお見せできる実験モデルと位置付けて考えている」と述べている。年内にも発足する全国初の都道府県連合が、どんな具体的な成果を発揮するのか――。広域連合は関西が試金石となり、首都圏など全国に発展する可能性が高いだけに注目される。
※「関西広域連合」ホームページ
http://
<関連記事>
イ、首都圏に勝てる「大関西圏構想」を 目指せ「坂の上の雲」(2010年1月16日 産経新聞)
「もう四国、中国の枠組みにこだわっている時代じゃない」−。8日、関西周辺の知事らが大阪市で開いた「関西広域連合」の設立準備部会の閉会後、広域連合への参加を表明した徳島県の飯泉嘉門知事は、報道陣にこう語った。
関西といえば、一般的に大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県の2府4県を指す場合が多い。しかし、四国地方の徳島県と中国地方の鳥取県が名乗りを上げたことに全国の関心が集まっている。
「中・四国でも広域行政が盛り上がる突破口になればと思ったのが、加わった理由」と説明する飯泉知事。当初は、飯泉知事の“スタンドプレー”に四国知事会でも衝撃が走ったが、最近は「前向きにとらえられるようになった」という。
準備部会では、大阪、兵庫、京都、滋賀、和歌山、鳥取、徳島の2府5県が関西広域連合の設立に合意した。複数の都道府県で構成する全国初の広域連合は、国からの権限委譲の受け皿となる地方分権の担い手と位置づけられている。
なぜ、関西は地方分権にこだわるのか。関西は、首都圏とは一線を画した独自の経済圏を形作ってきたが、近年は企業の東京移転や工場の海外流出で、著しい地盤沈下に見舞われている。事実、日本の国内総生産(GDP)に占める関西の比率は2割を切り、4割弱を占める首都圏とは大きく水をあけられている。
このため、広域連合を「東京一極集中」に対抗するための起爆剤と期待する声は大きい。飯泉知事は「2府4県では、首都圏に勝てない。だから、中・四国地方も(関西広域連合に)入っていいんじゃないか」と主張する。「大関西」をつくるべきだとの考え方だ。
ただ、各府県知事は広域連合の設立には合意したものの、設立のタイムスケジュールには温度差がある。政府の地域戦略会議が今夏にも「地域主権戦略大綱」を策定することから、大阪府の橋下徹知事は「夏までに広域連合を発足し、国に分権を迫ることが大事」と主張。これに対し、滋賀県の嘉田由紀子知事らは「議会の理解を得るためには時間が必要」と慎重姿勢を見せた。
だが、関西の動きに触発されたのか、首都圏でも広域連合に向けた動きが盛り上がってきた。広域連合の発足で首都圏に後れを取れば、関西のまとまりの悪さを露呈することになり、もはや首都圏への対抗手段がなくなってしまうかもしれない。
閉会後の記者会見で、橋下知事は「(設立が遅れれば)地域主権の大きな流れに乗りきれない」と焦燥感をあらわにした。
広域連合の設立に尽力してきた関西広域機構の秋山喜久会長は、昨年末にテレビドラマ化された司馬遼太郎氏の小説「坂の上の雲」を引き合いに出し、「雲がない時代になり、自分たちで地域主権という大きな雲をつくった。経済界としても、国の閉塞(へいそく)感を打破するきっかにしてほしい」とエールを送った。
ロ、関西広域連合 北海道・東北も関心を(2010年1月27日 北海道新聞 社説)
鳩山由紀夫政権が掲げる「地域主権」を見据え、一足早く動きだしたとみるべきだろう。
大阪、兵庫、京都、和歌山、滋賀、徳島、鳥取の2府5県が、府県を超えた広域行政を担う「関西広域連合」(仮称)の設立で基本合意した。
都道府県レベルでの広域連合は、実現すれば全国初のケースとなる。国から地方への権限移譲の受け皿づくりを視野に、国の出先機関の統廃合などにも対応できる態勢整備が期待される。
明治維新以前の「国・藩」や府県の歴史を考えれば、お互いの垣根を取り除く難しさはあろう。しかし成功すれば、地方の発想に根ざした分権実現のけん引役になりうる。
分権の受け皿について、北海道ではこれまで、単独の道州制移行論議が主流となってきた。
だからといって、他県との広域連合を最初から排除する必要はない。
対岸の青森県や岩手県、秋田県などと、広域連合のメリット、デメリットについて十分に協議を重ね、自治の選択肢を広げておきたい。
関西連合は今秋にも発足する見通しだ。当初は医療連携、防災、観光・文化振興、産業振興、環境保全、資格試験・免許、職員研修の計7分野で広域事務を実施する。
国道や河川の一体管理も視野に入れている。事務効率化に加え、将来は関西国際、伊丹、神戸の3空港の並立など、複数府県にまたがる問題の調整に道を開く可能性もある。
徳島、鳥取両県は部分参加の見通しだ。道州制と違って、こうした柔軟な対応ができるのも広域連合の特徴といえる。
道州制の課題とされる道都、州都をめぐる綱引きも避けられる。
初の試みだけに、実際に動きだせば想定外の問題点が浮かび上がってくるかもしれない。
それでも、国の意思決定に従うだけの「待ち」の姿勢とは違った、7府県の意欲は評価できる。
北海道と東北の間にも、道と東北6県、新潟県で構成する知事会議や、道と北東北3県との知事サミットがある。
知事サミットの4道県は、縄文遺跡群の世界遺産登録推進などの実績も残してきた。ここでさらに一歩、踏み込んで考えてはどうか。
国の出先機関の見直し方針で、開発局の将来は不透明だ。ならば広域連合をてこに、出先機関見直しに先んじて、道県側から望ましい権限移譲を進める発想があってもいい。
協力できる分野は少なくない。東北各県に比べて人口、面積とも飛び抜けている北海道のリーダーシップに期待したい。
3.地方行財政検討会議が初会合 財源移譲議論
(2010年1月20日 産経新聞)
総務省は20日、地域主権(地方分権)改革の具体策を議論する「地方行財政検討会議」(議長・原口一博総務相)の初会合を開いた。国から地方への財源・権限の移譲に関する論点を整理する。11月までにまとめた論点について、来年3月に国会提出予定の地方自治法改正案に反映させる方針だ。
同会議には、原口総務相ら政務三役(4人)、達増拓也岩手県知事ら地方自治体関係者(8人)、石原俊彦関西学院大教授ら有識者(6人)ら計18人が参加。11月までに計7回会議を開き、主に(1)自治体の基本構造のあり方(2)住民参加のあり方(3)財務会計制度・財政運営の見直し(4)自治体の自由度の拡大(規制緩和)−をテーマに論点整理する。また、神奈川県の松沢成文知事、大阪府の橋下徹知事からそれぞれ提案があった改革私案も議論のたたき台とする考え。
同会議で議長役をつとめる原口総務相は、初会合の冒頭で「地域主権改革は鳩山政権の『一丁目一番地』だ。ここでご提案いただいたもので、できるものから即実行に移したい」とあいさつした。
4.地域主権型道州制へ本格論議
4月めどに政策立案 党推進本部が初会合 チーム3000の力を結集
(2010年1月22日 公明新聞)
公明党地方分権・地域主権推進本部(本部長=井上義久幹事長)は21日、東京都新宿区の公明会館で初会合を開き、公明党がめざす「地域主権型道州制」の導入に向けた本格的議論をスタートした。井上幹事長、斉藤鉄夫政務調査会長をはじめ、多数の国会議員、地方議員が出席した。
席上、井上幹事長は、日本の今後の課題として、貧困や格差の問題に対応するための所得再配分機能の再構築や、日本全体の成長戦略の推進と、それに伴う日本の統治機構改革の必要性を指摘。
その上で、昨年(2009年)12月に発表した党の新ビジョン(山口ビジョン)に基づき、現在の中央集権型から「地域主権型道州制」への移行をめざす考えを示した。
これに関して、井上幹事長は「(具体的に)どう推進していくかが課題だ」と述べる一方、「公明党らしさを発揮できる分野だ」とし、“チーム3000”の力を結集して取り組む考えを強調した。
同推進本部では、今後、学識経験者や各種団体との意見交換を行うほか、党の地方議員の意見を集約した上で、4月をめどに具体的な政策の取りまとめを行うことを決めた。
都市部と地方の格差、官僚機構の弊害、各地域における住民のニーズ(要望)の多様化などで、中央集権型の行政の限界が指摘される中、地方への税財源や権限の移譲、国の出先機関の統廃合など統治機構の改革が課題になっている。
公明党は、昨年の衆院選マニフェスト(政策綱領)で、新しい国のかたちとして「国―道州―基礎自治体」の3層構造による地域主権型道州制の実現を提唱。国がすべてを決める統治機構から、各地域が主体的に政策遂行できる体制への脱却をめざすとしている。
5.東北州へ地方議員結束 超党派「政治家連盟」4月発足
(2010年1月25日 河北新聞)
地域主権型道州制を実現しようと、東北6県の超党派の地方議員が「東北州政治家連盟」を4月に発足させる。東北州の行財政体系や政策を検討し、地域経営のビジネスモデルを確立する本格的な推進グループを目指す。全国の地方議員にも取り組みが波及するとみられる。
東北6県の県議、市町村議、町長ら30人が昨年12月、準備会を設立した。3月中旬までに各県30人以上の参加を目標とし、地方議員や市町村長、政治家志望者らに入会を呼び掛けている。
政治家連盟は、民間人などでつくる地域主権型道州制国民協議会(会長・江口克彦PHP総合研究所社長)の構成組織として結成。4月上旬に予定している設立総会には江口会長を招き、シンポジウムを開催する。
発足後は教育、産業などテーマごとに部会を設ける。大学教授や経済人、地域住民を交え、東北州政府に必要な組織、行財政制度、知事や議員の選挙方法、各地域の振興策などを話し合う。
各部会の検討状況はホームページや新聞広告で公表する。最終的には、政治家連盟として東北州の具体像を住民に示す。
国民協議会によると、地域主権型道州制を推進する地方政治家集団の発足は全国で初めて。村橋孝嶺理事長は「国の形を地域主権型に変えるのは国会議員には無理。党派を超え、地方議員が一つの旗の下に集まった意義は大きい」と歓迎する。
夏の参院選や2011年4月の統一地方選で、立候補者に道州制の賛否を問うアンケートを実施し、結果を有権者に公表することも検討する。
準備会世話人代表の菊地文博宮城県議(民主党)は「道州制導入が決まったらすぐ移行できるよう、東北州の仕組みや政策をきめ細かく考えておきたい。平成維新は東北が発信源になる」と話している。
[地域主権型道州制] 単なる都道府県の合併と違い、国の役割を外交や安全保障などに限定し、住民生活にかかわる内政は道州や市町村が担う仕組み。中央集権システムは廃止され、地方は自ら住民から税金を集めて使い道も決める。
6.論戦:道州制 改革か、逆行か
(2010年2月3日 毎日新聞)
2日の衆院代表質問では道州制などでも論戦が繰り広げられた。 「みんなの党はみんなで坂本龍馬をやっています」と切り出したみんなの党の渡辺喜美代表。明治維新の廃藩置県を引き合いに、道州制導入への意欲を鳩山由紀夫首相にただした。
渡辺氏「今必要なのは廃県置州、すなわち地域主権型道州制に変えることだ」
首相「地域主権は道州制にとどまらない。基礎自治体(市町村)が自分たちのことは自分たちでやる方法に変える」
渡辺氏はさらに菅直人副総理兼財務相のまとめた新成長戦略の基本方針を批判するなど鳩山政権の「改革」の手ぬるさを指摘した。たまらず菅氏が答弁の最後に渡辺氏に語りかけた。
菅氏「まだまだ試行錯誤があることはその通り。しかし、ぜひとも渡辺代表には、歴史の流れを逆行させる勢力に取り込まれることがないよう期待します」
7.道州制に期待と不安、中国5県住民調査
(2010年2月4日 山陰中央新報)
山陰両県を含む中国5県内にある6つのシンクタンクが3日、共同で行った地方分権や道州制に関する住民意識調査の報告会を広島市内で開いた。市町村合併に対する評価が割れると同時に、道州制にも期待と不安が交錯するなど、地方分権に対する多様な考え方が浮き彫りになった。
共同調査は、6つのシンクタンクが昨年7〜9月に、各県内の住民グループの代表や企業の経営者ら計約110人対し、聞き取りで行った。
このうち、市町村合併について、山陰経済経営研究所(松江市)の泉洋一主任調査役は、ごみ処理や育児などで、サービスは高水準、料金は低水準に統一され、プラス効果があった半面、「細かな行政サービスが減り、行政が身近な存在でなくなった」と指摘。役場の統合や職員削減によるマイナス面を感じる住民が少なくないとした。
さらに、道州制をめぐっても、積極論と慎重論が入り交じった。広島県内のシンクタンクは「道州制に備え、市町村の規模をさらに拡大すべき」との意見を紹介した。
一方、とっとり地域連携・総合研究センター(鳥取市)の田渕康修研究員は「人口の少ない鳥取県は周辺部となり、衰退すると憂慮されている」と報告。山陰経済経営研究所の泉氏も「地域でさらに議論を深め、意見を集約すべき」といった声が多かったと述べた。
|
|
|
|
|
|
|
|
道州制をひろめよう!! 更新情報
-
最新のイベント
-
最新のアンケート
-
まだ何もありません
-
道州制をひろめよう!!のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- mixi バスケ部
- 37859人
- 2位
- お洒落な女の子が好き
- 90055人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208304人