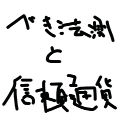・HPO:個人的な意見 ココログ版 力と力の作る構造 balance is all
http://
ひできさんのエントリ(上記)にコメントをしようと思って、ある言葉を捜していた時の出来事。欲しい言葉は見つからなかったのですが、セレンディピティ。個人的に引かれる言葉に遭遇。
あ、申し遅れました。「べき乗則とネット信頼通貨」についてちょっと勉強しようと思い、02/27に、このコミュニティに参加したit1127と申します。表題の「ネットワーク・エコノミクス」は、このコミュニティの基礎用語だと思い、関連するキーワードのURLをstudy用に関連リンクをメモしました。
えーと、いま暗中模索状態です。この辺の話題について、こんなURLがあるよとか、こんな本を読んだらいいんじゃないかとか、そんなことを教えていただけるとありがたいかな、と思っています。
・過剰転移 過剰慣性
http://
・ネットワーク・エコノミクス
http://
・ネットワーク効果
http://
「クリティカル・マス」って、「101匹目のサル」みたいな話しだな。
・ネットワーク外部性
http://
・ネットワーク外部性
http://
・ネットワークというどこにでもある不思議
http://
http://
ひできさんのエントリ(上記)にコメントをしようと思って、ある言葉を捜していた時の出来事。欲しい言葉は見つからなかったのですが、セレンディピティ。個人的に引かれる言葉に遭遇。
あ、申し遅れました。「べき乗則とネット信頼通貨」についてちょっと勉強しようと思い、02/27に、このコミュニティに参加したit1127と申します。表題の「ネットワーク・エコノミクス」は、このコミュニティの基礎用語だと思い、関連するキーワードのURLをstudy用に関連リンクをメモしました。
えーと、いま暗中模索状態です。この辺の話題について、こんなURLがあるよとか、こんな本を読んだらいいんじゃないかとか、そんなことを教えていただけるとありがたいかな、と思っています。
・過剰転移 過剰慣性
http://
・ネットワーク・エコノミクス
http://
・ネットワーク効果
http://
「クリティカル・マス」って、「101匹目のサル」みたいな話しだな。
・ネットワーク外部性
http://
・ネットワーク外部性
http://
・ネットワークというどこにでもある不思議
http://
|
|
|
|
コメント(19)
過剰慣性と旧い世代、新しい世代というのは、簡単に結びつくのですが、ネットワーク外部性とどう結びつくのかしら?ネットワーク外部性と過剰慣性、過剰転移どう関連するのかしら?
ちょっと考えて見ますね。自分で考えないとダメみたいですから、この件については答えは言わないでね(笑)
それから、これってメディア論、つーか道具論でもありますね。横道それちゃいますが、備忘録としてメモ。
ウォルター・オング『声の文化と文字の文化』
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0666.html
声の銀河系―メディア・女・エロティシズム
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4309241433/249-0466287-3283568
「声」の資本主義―電話・ラジオ・蓄音機の社会史 講談社選書メチエ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062580489/qid=1141365988/sr=1-32/ref=sr_1_2_32/249-0466287-3283568
鉄道旅行の歴史―十九世紀における空間と時間の工業化
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4588276417/qid=1141366303/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-0466287-3283568
これは、全然関係ないけど
・信頼通貨の基礎知識(viaある人)
http://www.picsy.org/02/index.html#02
ちょっと考えて見ますね。自分で考えないとダメみたいですから、この件については答えは言わないでね(笑)
それから、これってメディア論、つーか道具論でもありますね。横道それちゃいますが、備忘録としてメモ。
ウォルター・オング『声の文化と文字の文化』
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya0666.html
声の銀河系―メディア・女・エロティシズム
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4309241433/249-0466287-3283568
「声」の資本主義―電話・ラジオ・蓄音機の社会史 講談社選書メチエ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4062580489/qid=1141365988/sr=1-32/ref=sr_1_2_32/249-0466287-3283568
鉄道旅行の歴史―十九世紀における空間と時間の工業化
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4588276417/qid=1141366303/sr=1-1/ref=sr_1_2_1/249-0466287-3283568
これは、全然関係ないけど
・信頼通貨の基礎知識(viaある人)
http://www.picsy.org/02/index.html#02
>ラカン派
ああ、やっぱり。この欲望は、人間を語る上で重要なキーワードですよね!
私、この言葉、かなりツボです(笑)
数少ない、実感、噛み締めることのできる言葉です。
最初に知ったのは、これです。
「われわれがある女(または男)を情熱的に欲するのは、彼女(または彼)が第三者によって欲せられているときである。もちろん、三角関係として顕在化しない場合ですら、恋愛はそのような構造を持つ。しかし、相手を獲得したとたんに情熱はさめ、そのあとはなんとなく腹立たしく思う。ところが、相手の方はそれを心変わりだと思ってしまう。こういう齟齬はありふれているが、明瞭な三角関係においては、それはもっと劇的な形をとる。」(P207『批評とポスト・モダン』柄谷 行人 (著))
あと、夏目漱石の小説にも三角関係を扱ったもの、いまそれを思い出せないのですが、ありますね。
いろんな分野で援用されているんですね。ということは、強力な概念。
>ただし「集団」を何処まで広げて考えられるかはよくわかりません
ですね、定性的には分るのですが、定量的に理解するのは灘ありですね。その辺が、社会は合理だけでは解決できないということか。(笑)
ああ、やっぱり。この欲望は、人間を語る上で重要なキーワードですよね!
私、この言葉、かなりツボです(笑)
数少ない、実感、噛み締めることのできる言葉です。
最初に知ったのは、これです。
「われわれがある女(または男)を情熱的に欲するのは、彼女(または彼)が第三者によって欲せられているときである。もちろん、三角関係として顕在化しない場合ですら、恋愛はそのような構造を持つ。しかし、相手を獲得したとたんに情熱はさめ、そのあとはなんとなく腹立たしく思う。ところが、相手の方はそれを心変わりだと思ってしまう。こういう齟齬はありふれているが、明瞭な三角関係においては、それはもっと劇的な形をとる。」(P207『批評とポスト・モダン』柄谷 行人 (著))
あと、夏目漱石の小説にも三角関係を扱ったもの、いまそれを思い出せないのですが、ありますね。
いろんな分野で援用されているんですね。ということは、強力な概念。
>ただし「集団」を何処まで広げて考えられるかはよくわかりません
ですね、定性的には分るのですが、定量的に理解するのは灘ありですね。その辺が、社会は合理だけでは解決できないということか。(笑)
ケインズの美人投票も、ネットワーク外部性?
http://it1127.cocolog-nifty.com/it1127/2004/03/29.html#bijin
フェスティンガーの認知的不協和の心理
http://pag1u.net/network/ninchiteki.html
http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/deai/012ninchi.html
http://www.financialacademy.jp/yougo_247.html
http://www.e-kensyu.net/elearning/dictionary/na/ninchi.shtml
http://it1127.cocolog-nifty.com/it1127/2004/03/29.html#bijin
フェスティンガーの認知的不協和の心理
http://pag1u.net/network/ninchiteki.html
http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/deai/012ninchi.html
http://www.financialacademy.jp/yougo_247.html
http://www.e-kensyu.net/elearning/dictionary/na/ninchi.shtml
とりあえず、貨幣の複雑性は買おう。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1378863&comm_id=42072
http://hidekih.cocolog-nifty.com/hpo/2005/07/ecology_of_blog_0119.html
それから、記念に「ネットワーク・エコノミクス」、「ネットワーク経済の法則」も買ってしまおう。うん、かなりの出費。こりゃまじめにやって元取らないといけないな(笑)
>社会システム理論でも持ち込んで整理した方がよい
どなたか地図を書いてくだされ?(笑)
私、個人的に感慨にふけってるんですよね。当時は思いもよらなかったのですが、ここが約束の地なのかなぁー。
出発点は、「老子と現代物理学の対話」(長谷川晃)、その後ニューサイエンスを経て、ベルタランフィー「一般システム理論」、プリゴジン「混沌からの秩序」から、複雑系の科学と自然科学系の道を歩いていた過去(専門的にではなく、下手の横好き)があって、世の中に再度関心を持った今、辿り着いたのが、このコミュニティ。ま、そんなに大袈裟なもんでもないかぁー。(笑)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1378863&comm_id=42072
http://hidekih.cocolog-nifty.com/hpo/2005/07/ecology_of_blog_0119.html
それから、記念に「ネットワーク・エコノミクス」、「ネットワーク経済の法則」も買ってしまおう。うん、かなりの出費。こりゃまじめにやって元取らないといけないな(笑)
>社会システム理論でも持ち込んで整理した方がよい
どなたか地図を書いてくだされ?(笑)
私、個人的に感慨にふけってるんですよね。当時は思いもよらなかったのですが、ここが約束の地なのかなぁー。
出発点は、「老子と現代物理学の対話」(長谷川晃)、その後ニューサイエンスを経て、ベルタランフィー「一般システム理論」、プリゴジン「混沌からの秩序」から、複雑系の科学と自然科学系の道を歩いていた過去(専門的にではなく、下手の横好き)があって、世の中に再度関心を持った今、辿り着いたのが、このコミュニティ。ま、そんなに大袈裟なもんでもないかぁー。(笑)
ひできさん
私も、昨日知ったばかりなので、なんともいえないのですが、いま、ご紹介のURLを読んだり、調べた範囲でいいますと、似て非なるものかもしれないですね。頼母子講は歴史の変遷があるようで、最終的には、現代の金融に近いと思いました。
http://krd.roshy.human.nagoya-u.ac.jp/~rep2000/akiyama/akiyama1.html
鎌倉時代におこなわれた頼母子講は、講親救済のためのものであるから、勿論無利息であり無担保であった。しかし鎌倉時代の 末頃から頼母子金を受け取りつつもその後の掛金を怠る「取逃げ」をする者が出てきたので、担保として土地・衣類・道具をあて それを処分して弁済をすることとした。更には室町時代になると、担保だけでなく一定の割合で利息をとるという方法が発生して いる。このように時代が経つと共に人々の経済活動が活発になるにつれ、頼母子講の金融的意義はますます強調され、困窮者救済 という初期の宗教的意義はほとんど忘れられるに至った。明治以降にもなると近代的金融機関としての「銀行」の出現によって、 その衰微を余儀なくされたのである。
//
これに対して、五常講は、むしろエコマネーに近いのではと思います。ま、即席の理解ですが(笑)ちなみに、私の祖母が、二宮尊徳の弟の孫です。そんな関係もありまして、ちょっとふじすえ健三さんとこのエントリに目が留まったというわけです。ただ、報徳思想とかは名前は知っていましたが、中身について勉強もしたことなく、まったく知らないです。今回ちょうど良い機会だから、ちょっと調べてみようかななどと思っている、というわけです。
今日、「エンデの遺言」という本を読んでいて、シルビオ・ゲゼルの自由貨幣の根本原理だけを理解?したところです。
要するに、物理法則に従う商品(劣化がある)に物理法則に従わないお金(劣化が無い)を交換対象にしてしまったのがそもそもの間違いの始まり。だから、物理法則に従う、すなわち劣化があるお金(自由貨幣)を、モノやサービスの交換対象にすれば、もはや利子という余計なものを発生させなくても良いという考え。だけは、理解したつもり(笑)
ただ具体的な話しになると、ちょっと良く分らなくなってしまっている私です(笑)
それから、「タオ自然学」ですかー、懐かしいですー、私も読みました。ちなみに、調べたら、ちょうど本をたくさん読み始めた時期で、当時こんな本を読んでいました。
http://it1127.cocolog-nifty.com/it1127/2003/10/1988.html
私も、昨日知ったばかりなので、なんともいえないのですが、いま、ご紹介のURLを読んだり、調べた範囲でいいますと、似て非なるものかもしれないですね。頼母子講は歴史の変遷があるようで、最終的には、現代の金融に近いと思いました。
http://krd.roshy.human.nagoya-u.ac.jp/~rep2000/akiyama/akiyama1.html
鎌倉時代におこなわれた頼母子講は、講親救済のためのものであるから、勿論無利息であり無担保であった。しかし鎌倉時代の 末頃から頼母子金を受け取りつつもその後の掛金を怠る「取逃げ」をする者が出てきたので、担保として土地・衣類・道具をあて それを処分して弁済をすることとした。更には室町時代になると、担保だけでなく一定の割合で利息をとるという方法が発生して いる。このように時代が経つと共に人々の経済活動が活発になるにつれ、頼母子講の金融的意義はますます強調され、困窮者救済 という初期の宗教的意義はほとんど忘れられるに至った。明治以降にもなると近代的金融機関としての「銀行」の出現によって、 その衰微を余儀なくされたのである。
//
これに対して、五常講は、むしろエコマネーに近いのではと思います。ま、即席の理解ですが(笑)ちなみに、私の祖母が、二宮尊徳の弟の孫です。そんな関係もありまして、ちょっとふじすえ健三さんとこのエントリに目が留まったというわけです。ただ、報徳思想とかは名前は知っていましたが、中身について勉強もしたことなく、まったく知らないです。今回ちょうど良い機会だから、ちょっと調べてみようかななどと思っている、というわけです。
今日、「エンデの遺言」という本を読んでいて、シルビオ・ゲゼルの自由貨幣の根本原理だけを理解?したところです。
要するに、物理法則に従う商品(劣化がある)に物理法則に従わないお金(劣化が無い)を交換対象にしてしまったのがそもそもの間違いの始まり。だから、物理法則に従う、すなわち劣化があるお金(自由貨幣)を、モノやサービスの交換対象にすれば、もはや利子という余計なものを発生させなくても良いという考え。だけは、理解したつもり(笑)
ただ具体的な話しになると、ちょっと良く分らなくなってしまっている私です(笑)
それから、「タオ自然学」ですかー、懐かしいですー、私も読みました。ちなみに、調べたら、ちょうど本をたくさん読み始めた時期で、当時こんな本を読んでいました。
http://it1127.cocolog-nifty.com/it1127/2003/10/1988.html
「五常講」関連リンク
・破産と報徳思想
http://www.asanolaw.com/impression06a.html
1)日本の経済が回復しないのは、返せない借金を返そうとしているのが原因。借りた物は返すのが当然だが、不可能な事を頑張って続けても、全体として立ちゆかなくなる。大体、担保に入れた不動産の価値が1/10になったから、借金も1/10になると全て解決するはずだ。しかし、現実には、そうは行かない。これが、現在の日本経済がどうしようもなくなっている基本的原因。
4)二宮尊徳翁の報徳仕法は元々、小田原藩の武士の家計の逼迫を再建しようと考え出され、実践されたのが最初だ。当時の給与生活者である武士の家計は貨幣経済の発達により、支出は増えるが、収入が増えない状況にあった。これを無利子の講(五常講)を藩からの出資金で設立して、順番に貸し出して、借りた者は、高利の借金を一括返済し、五常講に分割で返済して解決した。その為、徹底的な倹約が強調実践された。
6)弁護士に頼んで、任意の分割返済、破産、給与所得者民事再生法の適用申請といろいろあるが、徳を施して貰った、困苦精励、倹約して余裕が出来たら、いつかそれを世に返す(報徳)するという事を忘れるべきではない。
8)法人の民事再生は雇用の確保が最大の目的。二宮尊徳翁の桜町領の再建は、現在の企業の再建と同じだ。法人の民事再生と同じだ。基本的に欠落しているのは、債権をカットされた債権者は徳を施したと考えるべきで、借金をカットして貰った債務者は、徳を施されたと考えるべきだ。借金の減った債務者は、倹約、困苦精励して、今度は、徳に報いる事を忘れない事が重要だ。これが報徳の意味だ。
・「報徳用語集」
http://www.nextftp.com/basukedaisuki/hotoku0032.html
徳という字は、人々へんに四方八方に心を配ることだそうです。気を使うんではなく、気を配ることなんですよ
論語にある『徳をもって徳に報いる』という生き方
・人間観の広がり -二宮尊徳と「新しい人間観」-
http://www.mskj.or.jp/getsurei/kamiyama0508.html
もっとも、人間の善性としての「徳」を尊徳が完全に所与として仕法に臨んでいたわけではない。口語訳された「語録」のなかにも、「人は富貴を求めて止まるところを知らない」とされたおり、分度の困難さのみならず、徳性が必ずしも全ての人間に顕在化しているとまでは考えていなかったことが読み取れる。銅像にある彼が『大学』を手にしており、仕法を進めるなかで書き記した五常講にて仁・義・礼・智・信を繰り返し唱えたことを念頭に置けば、本質的な徳性を信じつつ、目の前で生きる武家屋敷の奉公人や村人をはじめとする人間は、こうした規範論にて裏打ちされるべき人間でもあった。
・二宮金次郎ズ
http://blog.goo.ne.jp/scumscum/e/c28d01d4e8e4968f0805c3322f37b2ee
・破産と報徳思想
http://www.asanolaw.com/impression06a.html
1)日本の経済が回復しないのは、返せない借金を返そうとしているのが原因。借りた物は返すのが当然だが、不可能な事を頑張って続けても、全体として立ちゆかなくなる。大体、担保に入れた不動産の価値が1/10になったから、借金も1/10になると全て解決するはずだ。しかし、現実には、そうは行かない。これが、現在の日本経済がどうしようもなくなっている基本的原因。
4)二宮尊徳翁の報徳仕法は元々、小田原藩の武士の家計の逼迫を再建しようと考え出され、実践されたのが最初だ。当時の給与生活者である武士の家計は貨幣経済の発達により、支出は増えるが、収入が増えない状況にあった。これを無利子の講(五常講)を藩からの出資金で設立して、順番に貸し出して、借りた者は、高利の借金を一括返済し、五常講に分割で返済して解決した。その為、徹底的な倹約が強調実践された。
6)弁護士に頼んで、任意の分割返済、破産、給与所得者民事再生法の適用申請といろいろあるが、徳を施して貰った、困苦精励、倹約して余裕が出来たら、いつかそれを世に返す(報徳)するという事を忘れるべきではない。
8)法人の民事再生は雇用の確保が最大の目的。二宮尊徳翁の桜町領の再建は、現在の企業の再建と同じだ。法人の民事再生と同じだ。基本的に欠落しているのは、債権をカットされた債権者は徳を施したと考えるべきで、借金をカットして貰った債務者は、徳を施されたと考えるべきだ。借金の減った債務者は、倹約、困苦精励して、今度は、徳に報いる事を忘れない事が重要だ。これが報徳の意味だ。
・「報徳用語集」
http://www.nextftp.com/basukedaisuki/hotoku0032.html
徳という字は、人々へんに四方八方に心を配ることだそうです。気を使うんではなく、気を配ることなんですよ
論語にある『徳をもって徳に報いる』という生き方
・人間観の広がり -二宮尊徳と「新しい人間観」-
http://www.mskj.or.jp/getsurei/kamiyama0508.html
もっとも、人間の善性としての「徳」を尊徳が完全に所与として仕法に臨んでいたわけではない。口語訳された「語録」のなかにも、「人は富貴を求めて止まるところを知らない」とされたおり、分度の困難さのみならず、徳性が必ずしも全ての人間に顕在化しているとまでは考えていなかったことが読み取れる。銅像にある彼が『大学』を手にしており、仕法を進めるなかで書き記した五常講にて仁・義・礼・智・信を繰り返し唱えたことを念頭に置けば、本質的な徳性を信じつつ、目の前で生きる武家屋敷の奉公人や村人をはじめとする人間は、こうした規範論にて裏打ちされるべき人間でもあった。
・二宮金次郎ズ
http://blog.goo.ne.jp/scumscum/e/c28d01d4e8e4968f0805c3322f37b2ee
・ゼロ成長の富国論
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4163669507/249-0466287-3283568
・二宮尊徳スーパースター
http://homepage1.nifty.com/rekisi-iv/ninomiya/ninomiya-main.htm
もう一つの現実的な?人物像として面白そう!
?二宮尊徳は少年期の一時期を除き、ほとんど耕作をしていない。田は所有しているが、みな小作に出し、自ら鍬鋤を持つことは無かった。
?二宮尊徳は慈善家ではない。彼は、今で言うところの信用組合を日本で初めて作るなど、私的基金による金融業を事業として行い、その資金で各地の荒地を復興している。
?二宮尊徳はどちらかというと頑固な性格であった。時にそれが災いして、上司とそりが合わずに、現代で言うところの出社拒否症に陥ることもあった。また、晩年には胃潰瘍を患ったりもしており、ストレスに強かったとは必ずしも言えない。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4163669507/249-0466287-3283568
・二宮尊徳スーパースター
http://homepage1.nifty.com/rekisi-iv/ninomiya/ninomiya-main.htm
もう一つの現実的な?人物像として面白そう!
?二宮尊徳は少年期の一時期を除き、ほとんど耕作をしていない。田は所有しているが、みな小作に出し、自ら鍬鋤を持つことは無かった。
?二宮尊徳は慈善家ではない。彼は、今で言うところの信用組合を日本で初めて作るなど、私的基金による金融業を事業として行い、その資金で各地の荒地を復興している。
?二宮尊徳はどちらかというと頑固な性格であった。時にそれが災いして、上司とそりが合わずに、現代で言うところの出社拒否症に陥ることもあった。また、晩年には胃潰瘍を患ったりもしており、ストレスに強かったとは必ずしも言えない。
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
べき乗則とネット信頼通貨 更新情報
べき乗則とネット信頼通貨のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- お洒落な女の子が好き
- 90050人
- 2位
- 酒好き
- 170693人
- 3位
- 写真を撮るのが好き
- 208292人