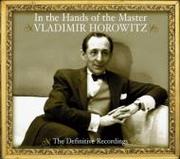ヴィルヘルム・バックハウス(1884〜1969年。ドイツ)
「鍵盤の獅子王」といわれる無類のテクニシャン。しかしバリバリ弾くのではなく、速いテンポで素っ気なく淡々と弾いています。とは言え、構成感のとれた表現、ダイナミックな盛り上げ方は紳士的な美しさで、質実剛健さには説得力があり、聴いたあとに深い味わいが残ります。ベートーヴェンのソナタ全集・協奏曲全集が有名ですが、決してドイツ的なスタンダードなものでなく、テンポはゆらすし、ペダルは指示に従わなかったりで、どちらかと言えば個性あふれるベートーヴェンだと思います。ドイツ音楽を中心にしたレパートリー(ブラームス・モーツァルト・バッハ・ハイドンなど)が彼の資質をよく物語っていると思います。
皆さんのお好きなバックハウスの名演をお教え下さい。
「鍵盤の獅子王」といわれる無類のテクニシャン。しかしバリバリ弾くのではなく、速いテンポで素っ気なく淡々と弾いています。とは言え、構成感のとれた表現、ダイナミックな盛り上げ方は紳士的な美しさで、質実剛健さには説得力があり、聴いたあとに深い味わいが残ります。ベートーヴェンのソナタ全集・協奏曲全集が有名ですが、決してドイツ的なスタンダードなものでなく、テンポはゆらすし、ペダルは指示に従わなかったりで、どちらかと言えば個性あふれるベートーヴェンだと思います。ドイツ音楽を中心にしたレパートリー(ブラームス・モーツァルト・バッハ・ハイドンなど)が彼の資質をよく物語っていると思います。
皆さんのお好きなバックハウスの名演をお教え下さい。
|
|
|
|
コメント(27)
ベートーヴェンのソナタ29番「ハンマークラヴィーア」は作品自体が巨大で、3楽章の瞑想的で静かな音楽は、ベートーヴェン後期を代表する孤高の境地のような存在ですね。
バックハウスは例のごとく淡々と弾いてるようで、心のこもった感動があります。楽譜に忠実な機械的な音楽とはまったく正反対の音楽ということでしょうか。4楽章の冒頭の幻想的なところは、他のピアニストに比してかなりハイスピードなんですよね(ポリーニの倍くらい?)。それでいて十分なくらい音楽的です。バックハウスはソナタ全集のステレオ再録音でこの曲を最後に録音するつもりが、その前に亡くなりました(ステレオの全集では、この29番だけモノラルの旧録音を擬似ステレオ化したもので代用)。返す返すも残念です。
バックハウスは例のごとく淡々と弾いてるようで、心のこもった感動があります。楽譜に忠実な機械的な音楽とはまったく正反対の音楽ということでしょうか。4楽章の冒頭の幻想的なところは、他のピアニストに比してかなりハイスピードなんですよね(ポリーニの倍くらい?)。それでいて十分なくらい音楽的です。バックハウスはソナタ全集のステレオ再録音でこの曲を最後に録音するつもりが、その前に亡くなりました(ステレオの全集では、この29番だけモノラルの旧録音を擬似ステレオ化したもので代用)。返す返すも残念です。
昔(中学生のころなので30年前くらい)、NHK−FMのクラシックアワーで作曲家の諸井誠氏の司会で面白い企画がありました。ベートーヴェンの悲愴ソナタ第1楽章冒頭はGrave(重々しく)の指示だけで速度指定はないからピアニストによって随分速さが違うということで、1小節目から2小節目までの速さを数十人のピアニストで聞きくらべしようというもの。細かい秒数は忘れましたが、一番速かったのがやはりバックハウス、一番遅かったバレンボイムの2倍もの速さでした(面白かったのはホロヴィッツとルービンシュタインがコンマ何秒まで全く同じだったこと)。まあ、速さでいい悪いのっていう話ではないんですけど、それぞれのピアニストのセンスがわかる企画でした。
ついでに、バックハウスのベートーヴェン以外では小品で印象的なものが多く、モーツァルトのロンド(イ短調)、メンデルスゾーンのロンドカプリチオーソ、シューベルトの楽興の時、ウィーンの夜会(リスト編曲。ライブのアンコール)などなど。あと珍しい室内楽でフルニエと組んだブラームスのチェロ・ソナタも同曲のベスト盤だと思います。
新星堂企画で1940〜50年代のEMI録音の復刻があり、目玉はブラームスのワルツとパガニーニ変奏曲(しかも2種)!。後者はピアノ最難曲の一つですが、速いテンポでサラリと弾き、しかもブラームスの感情をたたえていました。
長々とすいません。皆さんもどしどし書き込んで下さいね。
ついでに、バックハウスのベートーヴェン以外では小品で印象的なものが多く、モーツァルトのロンド(イ短調)、メンデルスゾーンのロンドカプリチオーソ、シューベルトの楽興の時、ウィーンの夜会(リスト編曲。ライブのアンコール)などなど。あと珍しい室内楽でフルニエと組んだブラームスのチェロ・ソナタも同曲のベスト盤だと思います。
新星堂企画で1940〜50年代のEMI録音の復刻があり、目玉はブラームスのワルツとパガニーニ変奏曲(しかも2種)!。後者はピアノ最難曲の一つですが、速いテンポでサラリと弾き、しかもブラームスの感情をたたえていました。
長々とすいません。皆さんもどしどし書き込んで下さいね。
実は正直に言うと、ベートーベンよりはモーツァルト、のタイプの人間なんで(笑)ベートーベンの名演奏家についてはあまり語る資格がないのですが、
それ故、他の小品について少しだけ。
バックハウスのモーツァルト ピアノ協奏曲第27番
とイ短調のロンドは、この曲の数ある演奏の中で、個人的には最高のものだと思ってます。
もう、感動した、とか、涙が出た、とかいう次元を超えて、天国の門の先にふと足を踏み入れたら、そこにはきっとこういう音が鳴っているのだろう、と思わせるような演奏。
昔買った、この2曲の入ったレコードは、本当に擦り切れるほど聴きました。今でも、心に残る演奏の5本の指に入る作品です。
それ故、他の小品について少しだけ。
バックハウスのモーツァルト ピアノ協奏曲第27番
とイ短調のロンドは、この曲の数ある演奏の中で、個人的には最高のものだと思ってます。
もう、感動した、とか、涙が出た、とかいう次元を超えて、天国の門の先にふと足を踏み入れたら、そこにはきっとこういう音が鳴っているのだろう、と思わせるような演奏。
昔買った、この2曲の入ったレコードは、本当に擦り切れるほど聴きました。今でも、心に残る演奏の5本の指に入る作品です。
しのさんがおっしゃってたモーツァルトのベスト3の私の書き込みとかぶって光栄です。ロンドはあの素っ気ない弾き方がたまらないですね。わがままを言えば、ギーゼキングも素っ気ないけど何か冷たい印象(ギーゼキングファンの方すいません。彼のモーツァルト演奏は高く評価しています)で、他たいていのピアニストは思い入れたっぷりに弾くのにも、ちょっと抵抗を感じてます。バックハウスならではの技有りです。ほとんど解釈の変わらないモノラル盤もあります。
協奏曲27番は、弾き方がモーツァルトらしくないとか、早すぎるんじゃないかって声も聞こえてきそうですけど、ベームVPOのバックは耽美的ですばらしく、さらっと弾いたピアノが余計に心に響く名演だと私は思います。
バックハウスのモーツァルトはCDにして3枚分くらいあります。初期のソナタとか10番〜12・14番とか幻想曲とか、どれも聴き応えありますね。
協奏曲27番は、弾き方がモーツァルトらしくないとか、早すぎるんじゃないかって声も聞こえてきそうですけど、ベームVPOのバックは耽美的ですばらしく、さらっと弾いたピアノが余計に心に響く名演だと私は思います。
バックハウスのモーツァルトはCDにして3枚分くらいあります。初期のソナタとか10番〜12・14番とか幻想曲とか、どれも聴き応えありますね。
>てっちゃんさん
イッセルシュテット指揮VPOの協奏曲はおっしゃるように素晴らしい名演ですね。3番の1楽章でバックハウスはライネッケ作の長くて珍しいカデンツァを弾いて、他のというか普通のカデンツァを聴くとなんだか物足りなく感じてしまいます。
ベームとの4番の映像は昔NHKのスペシャル(大木正純さんの司会の番組)で録画しました。晩年のバックハウスはこの曲とブラームスの2番ばかり弾いてらしたそうですが、職人技のような印象を受けました。CDで聴くよりもちょっとまろやかなベーゼンドルファーの響きも印象的です。
写真まで貼っていただき、たいへん盛り上がりました(?)
では、これからも宜しくお願いします。
イッセルシュテット指揮VPOの協奏曲はおっしゃるように素晴らしい名演ですね。3番の1楽章でバックハウスはライネッケ作の長くて珍しいカデンツァを弾いて、他のというか普通のカデンツァを聴くとなんだか物足りなく感じてしまいます。
ベームとの4番の映像は昔NHKのスペシャル(大木正純さんの司会の番組)で録画しました。晩年のバックハウスはこの曲とブラームスの2番ばかり弾いてらしたそうですが、職人技のような印象を受けました。CDで聴くよりもちょっとまろやかなベーゼンドルファーの響きも印象的です。
写真まで貼っていただき、たいへん盛り上がりました(?)
では、これからも宜しくお願いします。
バックハウスのライブ録音も素晴らしいです。
ORFEOレーベルから出ている、
ザルツブルグ音楽祭のライブ2種(66、68年)、
カーネギーホールライブ(54年)、
そして最後の演奏会(69年)、
いずれも終生舞台の人だったバックハウスの
偽らざる姿が刻印されています。
特にザルツブルクライブCDに記載されている
Gottfried Krausのバックハウス回想には
貴重な証言と所感が綴られていて
更に彼の人生を浮き彫りにしています。
最後の演奏会で、
モーツァルトK331ソナタを演奏する前に、
イ長調の和音を響き渡らせ、楽堂を満たします。
祈るような空気、包み込まれる聴衆。
ハッとする思いでした。
何もせずして全てを成し遂げる稀有の表現者、
「芸術家よ語るなかれ、創造せよ」
を座右の銘としたといいます。
私はただただ彼の紡ぎ出す音楽の豊かさ、巨きさに
感動してしまうのです。
ORFEOレーベルから出ている、
ザルツブルグ音楽祭のライブ2種(66、68年)、
カーネギーホールライブ(54年)、
そして最後の演奏会(69年)、
いずれも終生舞台の人だったバックハウスの
偽らざる姿が刻印されています。
特にザルツブルクライブCDに記載されている
Gottfried Krausのバックハウス回想には
貴重な証言と所感が綴られていて
更に彼の人生を浮き彫りにしています。
最後の演奏会で、
モーツァルトK331ソナタを演奏する前に、
イ長調の和音を響き渡らせ、楽堂を満たします。
祈るような空気、包み込まれる聴衆。
ハッとする思いでした。
何もせずして全てを成し遂げる稀有の表現者、
「芸術家よ語るなかれ、創造せよ」
を座右の銘としたといいます。
私はただただ彼の紡ぎ出す音楽の豊かさ、巨きさに
感動してしまうのです。
バックハウスは私にとっては師匠であり、聖職者であり、神ですらあります。
子供の頃からピアニストになりたくて先生についたのですが、運悪く、ピアノの専門家ではなくバイオリンの先生だったので、ベートーヴェンやショパンのピアノ曲は指導していただけず、オーケストラの曲の編曲ものばかり弾かされていたので、小学校3年生ぐらいから、中1で子育て休暇中のコンサートピアニストに教わるようになるまで、ピアノは独習でした。
その最も良き先生となったのが、バックハウスでした。ケンプもルビンシュタインも偉大な先達でしたが、バックハウスには特別なものがありました。
演奏はさっぱりしているのに、余韻がすばらしく、一度聴くと完全に虜(とりこ)になりました。
具体的な作品の演奏を少しあげます。
独奏曲:もし私にバックハウスを紹介するに最も適したディスクをあげよ、と質問すれば、「1954年カーネギーホール・リサイタル」を一押しします。これにはJoshさん(はじめまして。よろしく!)も言及されていますね。
ベートーベンのソナタ5曲(Nr. 8, 17, 26, 25, 32)とアンコール4曲を収めたものです。「悲愴」の冒頭のテンポの速さにはちょっと驚きますが(川さん、お世話になります。よろしく!)、25番ト長調(かっこう)など指ならし程度の曲だろうと思いますが、これがまた良いのです!森の中でカッコウが鳴くだけでなく、第一主題の後すぐ分散和音で上がって行くパッセージが本当に軽くて森の爽やかな空気を吸うようにリラックスさせてくれます。ほかの曲についても感動した話を書きたいのですが、長くなりすぎるので次に行きます。あ、その前にぜひアンコールの曲について書かせてください。
4曲(シューベルト、シューマン、シューベルト=リスト、ブラームス)ともリラックスして、もう演奏会で弾いているというより、鼻歌でも歌うように演奏しています。この中で特別注目に値するのが、シューベルト=リスト編曲、「ウィーンの夜会」です。1930年代にも一度スタジオ録音していますが、ライブのほうはもう本当に煌びやかでしかしコケットリーもある、たまらなく魅力的な演奏なのです。この一曲だけでも聴いて欲しい。
協奏曲:ベートーベンの4番(これはもう決定盤中の決定盤、ただし、同曲異演が6種類ほどあります。SP時代の録音の復刻盤、LPのステレオ盤とモノラール盤、さらにライブ盤で、1950年(ベームと)、1954年盤(クナッパーツブッシュと)(DVD盤とCD盤の両方が出ていますが第3楽章のカデンツァが絢爛豪華な自作ではないのが残念)、それから最近出たばかりのカンテッリとの1956年ニューヨークでの演奏、それに、てつやさん(よろしくお願いします)のお好きな1967年、バックハウスのザルツブルクの別荘をたずねてインタビューをした録画つきのスタジオ録音が今私の手元にあります。
どれを聴いても素晴らしい!バックハウスのこの曲への傾倒ぶりをうかがわせてくれます。ことに晩年83歳の頃のものは若い頃より心もちテンポが遅くなっているように感じますが、この曲への生涯にわたる愛着、いとおしみを感じさせます。インタビューで、
「私は、この曲をあらゆる指揮者とあらゆる町で弾いてきた」と言っており、よほど好きだったのでしょう。「いつかはこの曲も弾かなくなる...」という言葉がありますが、「弾けなくなる」ではないのですね。ひとつひとつの音にかける愛情が聴き取れる名演だと思います。
先ほど触れました、最近出たばかりのCDは日本で出ている「カーネギーホールリサイタル」(上述)の全曲に公には多分なっていなかった協奏曲の4番をバンドルした形で出ています。リサイタルのほうはリマスタリングに失敗したのか、音ゆれが激しく聴き辛いものですが、協奏曲のほうはよくとれているほうだと思います。
カンテッリとの共演も大変息のあったもので、このところずっと毎日一回は聴いています。カンデンツァを終了してオケが戻って来るあたりにも細心の注意が払われており、トリラーが短調から長調になる時の音色の変化、それからオケを迎え入れる時の少し控えめに
鳴らされた音など、数小説でも意味とバックハウスの演奏家としての配慮を感じます。
ほかの盤についても書きたいのですが、息切れしましたので、この辺で失礼いたします。
またブラームスの協奏曲、モーツアルトの27番協奏曲、ハイドンのソナタ集、ショパンのエチュード、室内楽についても書きます。
長いコメントにおつきあいいただき、有難うございました。
皆様、どうぞ今後ともよろしくご交誼のほどお願い申し上げます。
malte
PS:ひょっとするとこのコミュニティでは初書き込みかもしれません。これからもよろしくお願い致します。川さん、いつもお世話いただき、ありがとうございます。
子供の頃からピアニストになりたくて先生についたのですが、運悪く、ピアノの専門家ではなくバイオリンの先生だったので、ベートーヴェンやショパンのピアノ曲は指導していただけず、オーケストラの曲の編曲ものばかり弾かされていたので、小学校3年生ぐらいから、中1で子育て休暇中のコンサートピアニストに教わるようになるまで、ピアノは独習でした。
その最も良き先生となったのが、バックハウスでした。ケンプもルビンシュタインも偉大な先達でしたが、バックハウスには特別なものがありました。
演奏はさっぱりしているのに、余韻がすばらしく、一度聴くと完全に虜(とりこ)になりました。
具体的な作品の演奏を少しあげます。
独奏曲:もし私にバックハウスを紹介するに最も適したディスクをあげよ、と質問すれば、「1954年カーネギーホール・リサイタル」を一押しします。これにはJoshさん(はじめまして。よろしく!)も言及されていますね。
ベートーベンのソナタ5曲(Nr. 8, 17, 26, 25, 32)とアンコール4曲を収めたものです。「悲愴」の冒頭のテンポの速さにはちょっと驚きますが(川さん、お世話になります。よろしく!)、25番ト長調(かっこう)など指ならし程度の曲だろうと思いますが、これがまた良いのです!森の中でカッコウが鳴くだけでなく、第一主題の後すぐ分散和音で上がって行くパッセージが本当に軽くて森の爽やかな空気を吸うようにリラックスさせてくれます。ほかの曲についても感動した話を書きたいのですが、長くなりすぎるので次に行きます。あ、その前にぜひアンコールの曲について書かせてください。
4曲(シューベルト、シューマン、シューベルト=リスト、ブラームス)ともリラックスして、もう演奏会で弾いているというより、鼻歌でも歌うように演奏しています。この中で特別注目に値するのが、シューベルト=リスト編曲、「ウィーンの夜会」です。1930年代にも一度スタジオ録音していますが、ライブのほうはもう本当に煌びやかでしかしコケットリーもある、たまらなく魅力的な演奏なのです。この一曲だけでも聴いて欲しい。
協奏曲:ベートーベンの4番(これはもう決定盤中の決定盤、ただし、同曲異演が6種類ほどあります。SP時代の録音の復刻盤、LPのステレオ盤とモノラール盤、さらにライブ盤で、1950年(ベームと)、1954年盤(クナッパーツブッシュと)(DVD盤とCD盤の両方が出ていますが第3楽章のカデンツァが絢爛豪華な自作ではないのが残念)、それから最近出たばかりのカンテッリとの1956年ニューヨークでの演奏、それに、てつやさん(よろしくお願いします)のお好きな1967年、バックハウスのザルツブルクの別荘をたずねてインタビューをした録画つきのスタジオ録音が今私の手元にあります。
どれを聴いても素晴らしい!バックハウスのこの曲への傾倒ぶりをうかがわせてくれます。ことに晩年83歳の頃のものは若い頃より心もちテンポが遅くなっているように感じますが、この曲への生涯にわたる愛着、いとおしみを感じさせます。インタビューで、
「私は、この曲をあらゆる指揮者とあらゆる町で弾いてきた」と言っており、よほど好きだったのでしょう。「いつかはこの曲も弾かなくなる...」という言葉がありますが、「弾けなくなる」ではないのですね。ひとつひとつの音にかける愛情が聴き取れる名演だと思います。
先ほど触れました、最近出たばかりのCDは日本で出ている「カーネギーホールリサイタル」(上述)の全曲に公には多分なっていなかった協奏曲の4番をバンドルした形で出ています。リサイタルのほうはリマスタリングに失敗したのか、音ゆれが激しく聴き辛いものですが、協奏曲のほうはよくとれているほうだと思います。
カンテッリとの共演も大変息のあったもので、このところずっと毎日一回は聴いています。カンデンツァを終了してオケが戻って来るあたりにも細心の注意が払われており、トリラーが短調から長調になる時の音色の変化、それからオケを迎え入れる時の少し控えめに
鳴らされた音など、数小説でも意味とバックハウスの演奏家としての配慮を感じます。
ほかの盤についても書きたいのですが、息切れしましたので、この辺で失礼いたします。
またブラームスの協奏曲、モーツアルトの27番協奏曲、ハイドンのソナタ集、ショパンのエチュード、室内楽についても書きます。
長いコメントにおつきあいいただき、有難うございました。
皆様、どうぞ今後ともよろしくご交誼のほどお願い申し上げます。
malte
PS:ひょっとするとこのコミュニティでは初書き込みかもしれません。これからもよろしくお願い致します。川さん、いつもお世話いただき、ありがとうございます。
joshさん、malteさん
いろいろな情報ありがとうございます。
お二人の思い入れがよくわかります。デッカ録音以外の珍しいライブ盤などの情報が他にもありましたらお教え下さい。
るーしぇさん
バックハウスの戦後のショパン(デッカ盤)はけっこう好きですよ。ちっともショパンらしくなく堅固なイメージで、彼の人格がにじみ出るのか聴き入ってしまうようなショパンです。ワルツ2番なんかの終わりあたりで、テンポを落とすところなんかグランドマナー的で惚れ惚れしてしまいます。
あと「別れの曲」のゆったりとしたテンポ!中間部が普通以上に速くなっても主題が再現するとまたもとのゆっくりとしたテンポになるところはちょっと感動してしまいます。
いろいろな情報ありがとうございます。
お二人の思い入れがよくわかります。デッカ録音以外の珍しいライブ盤などの情報が他にもありましたらお教え下さい。
るーしぇさん
バックハウスの戦後のショパン(デッカ盤)はけっこう好きですよ。ちっともショパンらしくなく堅固なイメージで、彼の人格がにじみ出るのか聴き入ってしまうようなショパンです。ワルツ2番なんかの終わりあたりで、テンポを落とすところなんかグランドマナー的で惚れ惚れしてしまいます。
あと「別れの曲」のゆったりとしたテンポ!中間部が普通以上に速くなっても主題が再現するとまたもとのゆっくりとしたテンポになるところはちょっと感動してしまいます。
kankichi様
私も、かつて、ドイツエレクトローラ(EMIだったか?)から発売された2枚組LPのバックハウスのショパンの練習曲全曲は20年前に愛聴してました。
ブラームスのパガニーに変奏曲は、英国HMVの黒盤にラッパ吹き込みと電気吹き込みの2回の録音があるのですが、この曲を聞き比べても、確かにラッパ吹き込み時代のバックハウスは、バリバリ弾きまくってますけど、ベートーヴェンのソナタ全集を録音し始めた頃から、かなり内面的の表情が曲にあらわれてきたような気がします。ゆっくり雰囲気を味わうなら彼の人生の後半期の録音、凄さを実感したいときには、HMVへのラッパ録音のSP盤と、気分で聴きかえています。
晩年の深みは、人間って、年齢とともに心も移り変わる…という内面的な感情をおそわったような気がします。
私も、かつて、ドイツエレクトローラ(EMIだったか?)から発売された2枚組LPのバックハウスのショパンの練習曲全曲は20年前に愛聴してました。
ブラームスのパガニーに変奏曲は、英国HMVの黒盤にラッパ吹き込みと電気吹き込みの2回の録音があるのですが、この曲を聞き比べても、確かにラッパ吹き込み時代のバックハウスは、バリバリ弾きまくってますけど、ベートーヴェンのソナタ全集を録音し始めた頃から、かなり内面的の表情が曲にあらわれてきたような気がします。ゆっくり雰囲気を味わうなら彼の人生の後半期の録音、凄さを実感したいときには、HMVへのラッパ録音のSP盤と、気分で聴きかえています。
晩年の深みは、人間って、年齢とともに心も移り変わる…という内面的な感情をおそわったような気がします。
ピアニスト 内田光子さんを始め現役ピアニストのなかにも彼の演奏を絶賛する声が少なくない。
現役の女流ピアニスト マルタ・アルゲリッチは、
最近リリースされて第3協奏曲の録音に際し、
バックハウスのベートーヴェン演奏について
「これ以上何もできないと思うような演奏をしている」
と敬愛しているといいます。
音楽評論家 吉田秀和氏は、
「19世から20世紀に至るピアノの巨匠、大家、俊英たちのまっただなかにいて、泰然たる独自の面目を示していると同時に、他の人たちのベートーヴェン演奏の特徴を考えていく上でのひとつの指標として役立つような、そういう演奏の性格を持ち続けていたのである」
と語っています。
"真面目な仕事は真の喜びを与える"−セネカ
"人間の尊厳は君たちの手に委ねられている、それを守りたまえ"−シラー
"芸術家よ、創造したまえ、語るなかれ"−ゲーテ
ウィルヘルム・バックハウスの座右の銘です。
セネカ金言は、ライプツィヒゲヴァントハウスの正面に
彼自身の筆蹟で刻み込まれているそうです。
彼らしいですね。
現役の女流ピアニスト マルタ・アルゲリッチは、
最近リリースされて第3協奏曲の録音に際し、
バックハウスのベートーヴェン演奏について
「これ以上何もできないと思うような演奏をしている」
と敬愛しているといいます。
音楽評論家 吉田秀和氏は、
「19世から20世紀に至るピアノの巨匠、大家、俊英たちのまっただなかにいて、泰然たる独自の面目を示していると同時に、他の人たちのベートーヴェン演奏の特徴を考えていく上でのひとつの指標として役立つような、そういう演奏の性格を持ち続けていたのである」
と語っています。
"真面目な仕事は真の喜びを与える"−セネカ
"人間の尊厳は君たちの手に委ねられている、それを守りたまえ"−シラー
"芸術家よ、創造したまえ、語るなかれ"−ゲーテ
ウィルヘルム・バックハウスの座右の銘です。
セネカ金言は、ライプツィヒゲヴァントハウスの正面に
彼自身の筆蹟で刻み込まれているそうです。
彼らしいですね。
実家を新築する直前、伯母の部屋の棚の奥で偶然見つけた、父のLPコレクション(数枚ですが)の中にあった1枚がモーツァルトのピアノ協奏曲第27番&ピアノソナタK.331(バックハウス/ベーム/VPO)でした。
自分の父がこんな趣味の良いレコードを持っていたこと自体にまずびっくりでしたが、聴いてみて更にびっくり!
コンチェルトの、骨太だけど柔らかく豊かな表情、ソナタでは驚くほど繊細な音楽を奏でつつも決して緩むことなく、いずれも見事なモーツァルトでした。
高城鬼怒香さんも仰るとおり、バックハウスのモーツァルトは充分にアリだと思います。
ベートーヴェン、ブラームス、バッハ、ハイドンなどは言うまでもなく、っていうか語りだすと長くなるので・・・。
あ、でも「最後の演奏会(2枚組)」は感動的です。
自分の父がこんな趣味の良いレコードを持っていたこと自体にまずびっくりでしたが、聴いてみて更にびっくり!
コンチェルトの、骨太だけど柔らかく豊かな表情、ソナタでは驚くほど繊細な音楽を奏でつつも決して緩むことなく、いずれも見事なモーツァルトでした。
高城鬼怒香さんも仰るとおり、バックハウスのモーツァルトは充分にアリだと思います。
ベートーヴェン、ブラームス、バッハ、ハイドンなどは言うまでもなく、っていうか語りだすと長くなるので・・・。
あ、でも「最後の演奏会(2枚組)」は感動的です。
バックハウスのモーツアルト、とても好きです。イ短調のロンドがたまらなく好きで、しょっちゅう聴いています。モノラル録音のほうですが。
あと、圧巻は27番の協奏曲ですね。私は数十種類の演奏を聴きましたが、そして自分でも弾きましたが、バックハウスほどバランス感覚に優れた演奏家はいないと思います。けっこう大きな音ながら明るく、優しく、そして「走る悲しみ」もちゃんと味あわせてくれる最高の演奏だと思います。一楽章の展開部の緊張感は他の演奏ではなかなか得られない種類のものです。
高城鬼怒香さん、
>それと、晦渋で難解とされていたブラームスの小品は、バックハウ
>スがSPで熱心に録音しなかったら埋もれたままだったかも。
本当にそうですね!
ひとつモーツアルトとバックハウスで「何だかちょっと変だけどオッケーな演奏」をご紹介しますと、モーツアルトの戴冠式協奏曲(26番)です。大変古い録音なのですが、どう聴いてもモーツアルトの「皇帝」にきこえることです。
私は26番の協奏曲(「戴冠式})だけはあまり好きではないのですが、バックハウスで聴くとモーツアルトの譜面にない和音がドン、ドン、ドンと一楽章で入っていて、それはそれは戴冠式マーチにも「皇帝」にも聴こえておもしろいです。
最近次々とバックハウスのライブ録音が発売されて、子供の頃からのファンとしては嬉しい限りです。
malte
あと、圧巻は27番の協奏曲ですね。私は数十種類の演奏を聴きましたが、そして自分でも弾きましたが、バックハウスほどバランス感覚に優れた演奏家はいないと思います。けっこう大きな音ながら明るく、優しく、そして「走る悲しみ」もちゃんと味あわせてくれる最高の演奏だと思います。一楽章の展開部の緊張感は他の演奏ではなかなか得られない種類のものです。
高城鬼怒香さん、
>それと、晦渋で難解とされていたブラームスの小品は、バックハウ
>スがSPで熱心に録音しなかったら埋もれたままだったかも。
本当にそうですね!
ひとつモーツアルトとバックハウスで「何だかちょっと変だけどオッケーな演奏」をご紹介しますと、モーツアルトの戴冠式協奏曲(26番)です。大変古い録音なのですが、どう聴いてもモーツアルトの「皇帝」にきこえることです。
私は26番の協奏曲(「戴冠式})だけはあまり好きではないのですが、バックハウスで聴くとモーツアルトの譜面にない和音がドン、ドン、ドンと一楽章で入っていて、それはそれは戴冠式マーチにも「皇帝」にも聴こえておもしろいです。
最近次々とバックハウスのライブ録音が発売されて、子供の頃からのファンとしては嬉しい限りです。
malte
お久しぶりです。
バックハウスのライブ録音(1956年ニューヨーク)、そろそろ日本でも発売されると思いますが、私は待ちきれなくてすでに発売されていたドイツのショップから購入して何度か聴きました。これは大変なお値打ちものです!何せ今まで出ていなかった「ハンマークラヴィアソナタ」のライブが入っているんです!
1956年、バックハウス72歳の時のカーネギーホール・リサイタル。同じニューヨーク公演の別の日の録音もすでに発売されていて見事な出来栄えでした。
最初の曲はいわゆる「月光の曲」。この曲は遠い昔、まだ子供だった私が聴いてひどく感動したもの。ライブ盤はスタジオ録音盤よりもさらに即興性というか(Spontanität, spontaniety)音楽の流れの自然さがあって楽しめました。「月光」は第三楽章がきっちり弾けて始めて「できる」と言えます!大変迫力のある第三楽章でした。子供の頃、バックハウスのこの演奏でシンコペーションの弾き方を覚えたことを思い出します。(懐かしい)
「ハンマークラヴィアのための大ソナタ」Op.106、バックハウスはこの曲の録音をモノラールのスタジオ録音ひとつしか残していませんでしたが、今回は初のライブもの。
いや〜、バックハウスが「鍵盤の獅子王」と呼ばれた理由がよくわかります。ステレオの録音で聴けるのは晩年の録音ばかりなので衰えの見られる演奏もありますが、72歳の頃は絶好調という感じです。
雄大な第一楽章を聴いただけで圧倒されました。この人の音楽は常にぐいぐい前進するんですね。押して押して押しまくる。そこから生じるのはものすごく推進力のある力強い演奏なんです。そこがこの人の魅力だと思います。終楽章は私にはいまだに理解しきれない、解釈できない音楽なのですが、バックハウスの演奏では有無を言わさず納得させられました。もちろんこれまた前進する第2楽章とまさに深遠という言葉がふさわしい第3楽章も聴きがいがありました。
付属の解説に、ブラームスが10歳の頃のバックハウス少年に "Zu fröhlichem Anfang"(喜ばしい始まりに)とサインし、ピアノ協奏曲第2番第4楽章の冒頭部を引用している写真が載っていましたが、考えてみるとバックハウスはリストの孫弟子であり、ブラームスを実際に聴いているのですね。
現代の演奏家は完璧な技術で傷のない演奏はできるものの、なかなか感動させてくれないことが多いのですが、昔の「巨匠」と言われる人はとにかく凄い。
ベートーヴェンの音楽を満喫させてもらいました。
アンコールの4曲はたぶん当日のアンコールではないと思います。
malte
バックハウスのライブ録音(1956年ニューヨーク)、そろそろ日本でも発売されると思いますが、私は待ちきれなくてすでに発売されていたドイツのショップから購入して何度か聴きました。これは大変なお値打ちものです!何せ今まで出ていなかった「ハンマークラヴィアソナタ」のライブが入っているんです!
1956年、バックハウス72歳の時のカーネギーホール・リサイタル。同じニューヨーク公演の別の日の録音もすでに発売されていて見事な出来栄えでした。
最初の曲はいわゆる「月光の曲」。この曲は遠い昔、まだ子供だった私が聴いてひどく感動したもの。ライブ盤はスタジオ録音盤よりもさらに即興性というか(Spontanität, spontaniety)音楽の流れの自然さがあって楽しめました。「月光」は第三楽章がきっちり弾けて始めて「できる」と言えます!大変迫力のある第三楽章でした。子供の頃、バックハウスのこの演奏でシンコペーションの弾き方を覚えたことを思い出します。(懐かしい)
「ハンマークラヴィアのための大ソナタ」Op.106、バックハウスはこの曲の録音をモノラールのスタジオ録音ひとつしか残していませんでしたが、今回は初のライブもの。
いや〜、バックハウスが「鍵盤の獅子王」と呼ばれた理由がよくわかります。ステレオの録音で聴けるのは晩年の録音ばかりなので衰えの見られる演奏もありますが、72歳の頃は絶好調という感じです。
雄大な第一楽章を聴いただけで圧倒されました。この人の音楽は常にぐいぐい前進するんですね。押して押して押しまくる。そこから生じるのはものすごく推進力のある力強い演奏なんです。そこがこの人の魅力だと思います。終楽章は私にはいまだに理解しきれない、解釈できない音楽なのですが、バックハウスの演奏では有無を言わさず納得させられました。もちろんこれまた前進する第2楽章とまさに深遠という言葉がふさわしい第3楽章も聴きがいがありました。
付属の解説に、ブラームスが10歳の頃のバックハウス少年に "Zu fröhlichem Anfang"(喜ばしい始まりに)とサインし、ピアノ協奏曲第2番第4楽章の冒頭部を引用している写真が載っていましたが、考えてみるとバックハウスはリストの孫弟子であり、ブラームスを実際に聴いているのですね。
現代の演奏家は完璧な技術で傷のない演奏はできるものの、なかなか感動させてくれないことが多いのですが、昔の「巨匠」と言われる人はとにかく凄い。
ベートーヴェンの音楽を満喫させてもらいました。
アンコールの4曲はたぶん当日のアンコールではないと思います。
malte
- mixiユーザー
- ログインしてコメントしよう!
|
|
|
|
巨匠ピアニスト讃 更新情報
-
最新のイベント
-
まだ何もありません
-
-
最新のアンケート
巨匠ピアニスト讃のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています
人気コミュニティランキング
- 1位
- 十二国記
- 23166人
- 2位
- 楽天イーグルス
- 31952人
- 3位
- 北海道日本ハムファイターズ
- 28124人